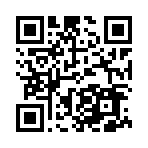2012年07月30日
河原で流しそうめん
昨日は子ども会の「流しそうめん&BBQ」。

まずは竹を割って、流しそうめんの準備。
ノミやサンドペーパーの作業は子どもたちは大好き。

三脚作り。

毎日のように鋸と金槌を使ってるんで、慣れたもの。

完成。

大勢なので、最初は中々下の方までそうめんが流れない。

にこちゃんは最後のザルの所で取る。
子どもたちはみんな、何の作業でも「やらせてー!」の連発。
ノミや鋸だけでなく、竹を運んだりとかも。
大人の役割は何でもやらせる事。
それには、子どもたちに合わせてこっちの補助が必要。
それをめんどくさがっては出来ない。
出来なくても、遅くても構わない。
こういう現場に学校教育型の「比較、競争」を持ち込んではならない。
脱比較、脱競争だ。
大人の出来る事は「信じて待つ」。
待てないのが美しく教育を受けた、僕ら大人。
自然農と自由な教育はリンクする。
「いついつまでにこれだけ出来ないといけない。」
という不自然な枠を勝手に作ったりするから、大変な悪循環が始まる。
子どもにそんなことを課すのは最悪。
大人だって、そんなしょうもない次元から解放されたい。
もちろん、半夏(はんげ、7月の始めごろ)までには稲を植え終わらないといけない。
こういう、「ねばならない」と、人為的に勝手に作った「ねばならない」とは根本が違う。
自然のサイクルに人間が合わせる。
これが当たり前の姿。
そのサイクルにそぐわない不自然な「ねばならない」を辞める。
それが自由とか解放と呼ばれる類のもの。
それでもって、自然のサイクルに合わせられる事を可能にする時間配分が各々に求められてる。
「自然に沿った生活がしたい。」
「地に足をつけた生活がしたい。」
でも、、、。
「年収は〇百万円ないといかない。」
「今の活動で成功を修めないといけない。」
という矛盾の中では、時間配分は難しい。
時間って決まってるんやから、今までやってきた不自然な何かを辞めない限り、余裕を持って草取り出来る時間は持てない。
考えりゃ当たり前。
それを可能にするのは、成功よりも草取りを重要だと思える価値観。
これがまた現代人には難しい?
まずは竹を割って、流しそうめんの準備。
ノミやサンドペーパーの作業は子どもたちは大好き。
三脚作り。
毎日のように鋸と金槌を使ってるんで、慣れたもの。
完成。
大勢なので、最初は中々下の方までそうめんが流れない。
にこちゃんは最後のザルの所で取る。
子どもたちはみんな、何の作業でも「やらせてー!」の連発。
ノミや鋸だけでなく、竹を運んだりとかも。
大人の役割は何でもやらせる事。
それには、子どもたちに合わせてこっちの補助が必要。
それをめんどくさがっては出来ない。
出来なくても、遅くても構わない。
こういう現場に学校教育型の「比較、競争」を持ち込んではならない。
脱比較、脱競争だ。
大人の出来る事は「信じて待つ」。
待てないのが美しく教育を受けた、僕ら大人。
自然農と自由な教育はリンクする。
「いついつまでにこれだけ出来ないといけない。」
という不自然な枠を勝手に作ったりするから、大変な悪循環が始まる。
子どもにそんなことを課すのは最悪。
大人だって、そんなしょうもない次元から解放されたい。
もちろん、半夏(はんげ、7月の始めごろ)までには稲を植え終わらないといけない。
こういう、「ねばならない」と、人為的に勝手に作った「ねばならない」とは根本が違う。
自然のサイクルに人間が合わせる。
これが当たり前の姿。
そのサイクルにそぐわない不自然な「ねばならない」を辞める。
それが自由とか解放と呼ばれる類のもの。
それでもって、自然のサイクルに合わせられる事を可能にする時間配分が各々に求められてる。
「自然に沿った生活がしたい。」
「地に足をつけた生活がしたい。」
でも、、、。
「年収は〇百万円ないといかない。」
「今の活動で成功を修めないといけない。」
という矛盾の中では、時間配分は難しい。
時間って決まってるんやから、今までやってきた不自然な何かを辞めない限り、余裕を持って草取り出来る時間は持てない。
考えりゃ当たり前。
それを可能にするのは、成功よりも草取りを重要だと思える価値観。
これがまた現代人には難しい?
タグ :流しそうめん
2012年07月29日
廃材バスケ
タッキーは旅立った。
29日の脱原発国会包囲網に東京まで行った後、成田からインドに飛ぶという予定。
彼女は大学の2回生で後2年インドに居る。
「是非来て下さいよ~!」とラブコールを受けてるけど、子どもたちは「犬怖くないん?」と心配げ。
大学の後はアーユルベーダも学びたいと。
でも、最終的には日本に帰ってきて、ウチのような手作り生活を送りたいそうな。
そのためのパートナーも募集中。
こういう生活を目指す若者には似たような価値観のパートナーが必須。
もちろん、そういう発信をし始めれば必ずやいい出会いが訪れる。
従兄のイッサが遊びに来てた。
バスケがやりたいからゴールを作ってくれと。

コンパネとオイル缶が見つかった。
材料探しから完成まで10分ぐらいのもん。
廃材ソーラーの乗ってる軒の下につけた。
ちょっと低いかと思ったけど、今のちびっ子たちのサイズには丁度よかった。
野遊とイッサ、土歩も入って、超盛り上がった。
でも、その盛り上がりは瞬時にして切り替わる。
次の瞬間、家の中でDSとか。
子どもたちの遊びってそういうもん。
コロコロ気分が変わる。
廃材バスケ自体また次にする時も来るやろうけど、もう誰も見向きもしないかもしれない。
そんなもんやし、それでいい。
それの為の労力には、今回ぐらいで丁度いい。
小さなコンパネ2枚を繋いで、オイル缶の底切って、ビス数本、チョイチョイっと留めるだけ。
既製品のゴール買うのは論外。
作るための材料を買うという発想もない。
その上、廃材手作りでも出来る限り最小限の労力にしたい。

さあ、アルミサッシも入った!
風呂用の新規薪置き場に薪を入れよう。
ちびっ子リレーで運ぶ。

丁度サッシの中央に仕切りを設けた。
左半分が焚きつけの細い薪。
右が太い薪。
これで、台風の時の土砂降りでも薪が濡れないようにもなった。

タッキーがノボリを玉ネギ染めにしてくれた液で、あっこちゃんが座布団カバーを染めた。
僕らがうどんを打ってる間じゅう何かしとるなーと思ってたら、この絞りを入れてた。

割と上手く出来てる。

中々手がこんでる。

これはキスを捌いてる所。
みんな真剣。

三枚に下ろして身は天ぷら、骨は唐揚げ。
国産の圧搾菜種油で揚げると黄色くて濃厚。
淡白なキスとこの油は相性がいい。
これは天草の松本さんの塩だけがいい。

鱧の梅肉餡。
これは瀬戸内の盛夏に必食の一品。

キュウリの豆乳サラダ。
天ぷらと対照的なアッサリ味がいい。
29日の脱原発国会包囲網に東京まで行った後、成田からインドに飛ぶという予定。
彼女は大学の2回生で後2年インドに居る。
「是非来て下さいよ~!」とラブコールを受けてるけど、子どもたちは「犬怖くないん?」と心配げ。
大学の後はアーユルベーダも学びたいと。
でも、最終的には日本に帰ってきて、ウチのような手作り生活を送りたいそうな。
そのためのパートナーも募集中。
こういう生活を目指す若者には似たような価値観のパートナーが必須。
もちろん、そういう発信をし始めれば必ずやいい出会いが訪れる。
従兄のイッサが遊びに来てた。
バスケがやりたいからゴールを作ってくれと。
コンパネとオイル缶が見つかった。
材料探しから完成まで10分ぐらいのもん。
廃材ソーラーの乗ってる軒の下につけた。
ちょっと低いかと思ったけど、今のちびっ子たちのサイズには丁度よかった。
野遊とイッサ、土歩も入って、超盛り上がった。
でも、その盛り上がりは瞬時にして切り替わる。
次の瞬間、家の中でDSとか。
子どもたちの遊びってそういうもん。
コロコロ気分が変わる。
廃材バスケ自体また次にする時も来るやろうけど、もう誰も見向きもしないかもしれない。
そんなもんやし、それでいい。
それの為の労力には、今回ぐらいで丁度いい。
小さなコンパネ2枚を繋いで、オイル缶の底切って、ビス数本、チョイチョイっと留めるだけ。
既製品のゴール買うのは論外。
作るための材料を買うという発想もない。
その上、廃材手作りでも出来る限り最小限の労力にしたい。
さあ、アルミサッシも入った!
風呂用の新規薪置き場に薪を入れよう。
ちびっ子リレーで運ぶ。
丁度サッシの中央に仕切りを設けた。
左半分が焚きつけの細い薪。
右が太い薪。
これで、台風の時の土砂降りでも薪が濡れないようにもなった。
タッキーがノボリを玉ネギ染めにしてくれた液で、あっこちゃんが座布団カバーを染めた。
僕らがうどんを打ってる間じゅう何かしとるなーと思ってたら、この絞りを入れてた。
割と上手く出来てる。
中々手がこんでる。
これはキスを捌いてる所。
みんな真剣。
三枚に下ろして身は天ぷら、骨は唐揚げ。
国産の圧搾菜種油で揚げると黄色くて濃厚。
淡白なキスとこの油は相性がいい。
これは天草の松本さんの塩だけがいい。
鱧の梅肉餡。
これは瀬戸内の盛夏に必食の一品。
キュウリの豆乳サラダ。
天ぷらと対照的なアッサリ味がいい。
2012年07月28日
讃岐うどん店に行かない家族
久々の手打ちうどん作り。
しょっちゅう打ってる訳ではないけど、慣れてるんで気軽にできる。
国産小麦の乾麺のうどんを茹でることもある。
野遊の慣れてるレシピと、雅のレシピの2種類やってみる。
どちらも粉は香川県産「さぬきの夢2000」。
最初の水回しが大事。
グルテンの弱い地粉でモチモチのうどんを作るのはここが命。

野遊のレシピは水が多めの、踏まないやりかた。

雅のは一般的な踏むやり方でやってみる。
さぬきの夢2000の袋の裏に書いてあるやり方。

野遊は以前から全工程を一人で出来る。
最近の野遊のレシピなら土歩でも打ちやすい。

野遊は几帳面なので、キッチリと同じ幅に切りそろえる。

土歩のは極太麺。
これはこれでイイ。

自作簡易カマドは簡単に持ち運べる。
前日タッキーが玉ネギ染めに使って、これはキッチンのすぐ前に持って来て焚いてる。

卵があるんで、まずは釜玉。
ゴマ、醤油、シソ、大人はラー油入れたり色々アレンジする。

これは土歩の極太麺。
噛みごたえがあっていい。

これは雅の生地を僕が打った。
薄く伸ばして、切る幅も狭くした。
細くて固めの強烈なコシやった。
やっぱり、地粉独特のモチモチ感を楽しむには野遊のレシピがいい。
さぬきうどん=強烈なコシというイメージを払拭する。
コシって固けりゃいいんではない。
でもこのモチモチはすぐに食べないと持続しない。
てことは店では使いにくい。
現実、800店もあるさぬきうどん店の90%以上がオーストラリア産のASWという粉。
グルテンが強くて、大量に供給があって、安い。
ポストハーベストや漂白のお陰で品質も安定してるし。
繊細な水回しなんかを必要としないし、機械で打っても上手くできる。
「ビジネス」の「原料」としては最高のもの。
ほとんどの店が出汁に使うグルタミン酸ソーダだって、安い原価でやっていくには必需品。
「明水亭」や「石川うどん」などは例外やけど。
家で作るのとビジネスは別物。
同じうどんでありながら、全く異質なもの。
比べられない。
イリコ、昆布、鰹節をふんだんに使った出汁に、杉樽で2年寝かした本醸造の醤油に三河本味醂。
薬味もショウガ、ネギ、ゴマ、刻み海苔以外に、シソ、バジル、ロケット、ユズなんかをアレンジしたり。
ラー油、柚子コショウ、時にはカンズリや豆腐ヨウなんかも面白い。
今回はタッキーのアチャールもよかった。
「アレ入れたら?」というマニアックな思いつきをその場で、即実践できるのが最高!
こういう手作りは難しいことではない。
家族総出でワイワイやるから楽しいし、みんなで分担して楽に出来る。
もう子どもたちも一人前になりつつあるし。
にこちゃんの包丁のレベルも随分上がってきた。
毎日やってる当たり前の手作り生活の中に、うどんやたこ焼きがある。
「〇〇食べたいなー。」と誰かが言えば、「よっしゃ、作ろ!」と即決する。
材料も設備も一通り揃えて、大体のことは出来るようにしてる。
やればやる程どんどん慣れて、更にやる。
そういう相乗効果は極めて自然なこと。
勢いで、やったことなくても「本みてやろ!」となる。
「大変そう。」とか「めんどくさい。」という所から解放されるとほんとに楽チン。
家作りでも食べ物作りでも、何でも軽いノリで取り掛かれる。
そのノリで日々生きるだけ!
しょっちゅう打ってる訳ではないけど、慣れてるんで気軽にできる。
国産小麦の乾麺のうどんを茹でることもある。
野遊の慣れてるレシピと、雅のレシピの2種類やってみる。
どちらも粉は香川県産「さぬきの夢2000」。
最初の水回しが大事。
グルテンの弱い地粉でモチモチのうどんを作るのはここが命。
野遊のレシピは水が多めの、踏まないやりかた。
雅のは一般的な踏むやり方でやってみる。
さぬきの夢2000の袋の裏に書いてあるやり方。
野遊は以前から全工程を一人で出来る。
最近の野遊のレシピなら土歩でも打ちやすい。
野遊は几帳面なので、キッチリと同じ幅に切りそろえる。
土歩のは極太麺。
これはこれでイイ。
自作簡易カマドは簡単に持ち運べる。
前日タッキーが玉ネギ染めに使って、これはキッチンのすぐ前に持って来て焚いてる。
卵があるんで、まずは釜玉。
ゴマ、醤油、シソ、大人はラー油入れたり色々アレンジする。
これは土歩の極太麺。
噛みごたえがあっていい。
これは雅の生地を僕が打った。
薄く伸ばして、切る幅も狭くした。
細くて固めの強烈なコシやった。
やっぱり、地粉独特のモチモチ感を楽しむには野遊のレシピがいい。
さぬきうどん=強烈なコシというイメージを払拭する。
コシって固けりゃいいんではない。
でもこのモチモチはすぐに食べないと持続しない。
てことは店では使いにくい。
現実、800店もあるさぬきうどん店の90%以上がオーストラリア産のASWという粉。
グルテンが強くて、大量に供給があって、安い。
ポストハーベストや漂白のお陰で品質も安定してるし。
繊細な水回しなんかを必要としないし、機械で打っても上手くできる。
「ビジネス」の「原料」としては最高のもの。
ほとんどの店が出汁に使うグルタミン酸ソーダだって、安い原価でやっていくには必需品。
「明水亭」や「石川うどん」などは例外やけど。
家で作るのとビジネスは別物。
同じうどんでありながら、全く異質なもの。
比べられない。
イリコ、昆布、鰹節をふんだんに使った出汁に、杉樽で2年寝かした本醸造の醤油に三河本味醂。
薬味もショウガ、ネギ、ゴマ、刻み海苔以外に、シソ、バジル、ロケット、ユズなんかをアレンジしたり。
ラー油、柚子コショウ、時にはカンズリや豆腐ヨウなんかも面白い。
今回はタッキーのアチャールもよかった。
「アレ入れたら?」というマニアックな思いつきをその場で、即実践できるのが最高!
こういう手作りは難しいことではない。
家族総出でワイワイやるから楽しいし、みんなで分担して楽に出来る。
もう子どもたちも一人前になりつつあるし。
にこちゃんの包丁のレベルも随分上がってきた。
毎日やってる当たり前の手作り生活の中に、うどんやたこ焼きがある。
「〇〇食べたいなー。」と誰かが言えば、「よっしゃ、作ろ!」と即決する。
材料も設備も一通り揃えて、大体のことは出来るようにしてる。
やればやる程どんどん慣れて、更にやる。
そういう相乗効果は極めて自然なこと。
勢いで、やったことなくても「本みてやろ!」となる。
「大変そう。」とか「めんどくさい。」という所から解放されるとほんとに楽チン。
家作りでも食べ物作りでも、何でも軽いノリで取り掛かれる。
そのノリで日々生きるだけ!
タグ :うどん
2012年07月27日
玉ネギ染め
全部で3枚作ったノボリの残り2枚は未完成。

タッキーが染めてくれた。
グラグラ玉ネギの皮を数時間煮て、色を抽出する。

超大量の玉ネギの皮!
かなり濃い色になった。
このぐらいにしておかないといけないそう。

いよいよ布を入れる。
また数時間。

ミョウバンを溶かした液に浸けこんで、バイセンという工程をする。

完成。
雅がパッチワークしたのよりも濃くなった。

タッキーの友達のモモコちゃんが高知から訪ねて来てくれて、ビワエキスの瓶詰めをしてくれた。
この季節はビワエキスが必需品。
蚊、アブ、蜂、ムカデなどの虫刺され。
アトピーや皮膚炎。
火傷の特効薬として。

サッシ化計画も進んでる。
トイレの裏の方は隙間だらけで、塞がないといけない。

当時張ったカマボコ状の板はもうないので、大工さんのキレイな廃材でガタガタに張った。
今後この中は部屋の中扱いなので、隙間なく張る。

裏のサッシの上の部分も入れて、随分部屋っぽくなったきた。
盛夏の中、うちはクーラーなしなので大量の汗をかく。
この季節に大量に汗をかくのを制御してはいけない。
特に、赤ちゃんの時(0~2歳)に寒さや暑さの中で過ごす事が重要。
それで、身体が環境に適応させようとするホメオスタシスが整備される。
みんな一日3、4回は水浴びしてる。
朝、起きてから。
昼ごはんの後。
休憩中とか。
井戸水なので、冷たくて気持ちいい。
飲み物はレモングラスとシソを代わる代わる作って冷やしておく。
ミントもたまに織り混ぜる。
残ったの同士をブレンドしても美味しい。
どれも、そのまま煎じるのでいい。
当然乾燥させておくと日持ちする。
キッチンの前の菜園にあるものばかりなので、保存させる必要もないけどね。
タッキーが染めてくれた。
グラグラ玉ネギの皮を数時間煮て、色を抽出する。
超大量の玉ネギの皮!
かなり濃い色になった。
このぐらいにしておかないといけないそう。
いよいよ布を入れる。
また数時間。
ミョウバンを溶かした液に浸けこんで、バイセンという工程をする。
完成。
雅がパッチワークしたのよりも濃くなった。
タッキーの友達のモモコちゃんが高知から訪ねて来てくれて、ビワエキスの瓶詰めをしてくれた。
この季節はビワエキスが必需品。
蚊、アブ、蜂、ムカデなどの虫刺され。
アトピーや皮膚炎。
火傷の特効薬として。
サッシ化計画も進んでる。
トイレの裏の方は隙間だらけで、塞がないといけない。
当時張ったカマボコ状の板はもうないので、大工さんのキレイな廃材でガタガタに張った。
今後この中は部屋の中扱いなので、隙間なく張る。
裏のサッシの上の部分も入れて、随分部屋っぽくなったきた。
盛夏の中、うちはクーラーなしなので大量の汗をかく。
この季節に大量に汗をかくのを制御してはいけない。
特に、赤ちゃんの時(0~2歳)に寒さや暑さの中で過ごす事が重要。
それで、身体が環境に適応させようとするホメオスタシスが整備される。
みんな一日3、4回は水浴びしてる。
朝、起きてから。
昼ごはんの後。
休憩中とか。
井戸水なので、冷たくて気持ちいい。
飲み物はレモングラスとシソを代わる代わる作って冷やしておく。
ミントもたまに織り混ぜる。
残ったの同士をブレンドしても美味しい。
どれも、そのまま煎じるのでいい。
当然乾燥させておくと日持ちする。
キッチンの前の菜園にあるものばかりなので、保存させる必要もないけどね。
タグ :草木染め
2012年07月26日
「手づくりの家、薪のくらし、廃材天国」
あっこちゃんが、前々から廃材天国の「のぼり」を作ろうとしてた。
シーツを四角に縫って、玉ネギの皮で染めた。
それに、雅がパッチワークで字を入れてくれた。

やっぱり、材料は古着。
しかも雅の即興でラフなデザインがいい。
出店の時なんかに使う。
ここがウチの「選択」。
業者にノボリを発注しない。
金が云々よりも、プロに頼むことにワクワクしない。
自分でクリエイトする楽しさを選ぶ。
雅は大学の時、アパレルデザイン、タッキーは現役のテキスタイル(染織)の学生。
オルタナティブ(代替)生活、自給自足、を目指しながらもこういう「得意分野」はずっと使える。
僕の陶芸もほとんどやってないけど、完全に辞める訳ではない。
半農半Xという捉え方。
「X」の部分が一つじゃなくていい。
この「半農半X」というのは京都の綾部、塩見直紀さんの本「半農半Xという生き方」で世に広まった。
「農」の部分には、障子の張り替えやトイの修理などの家のメンテナンス、漬けものや味噌作りなども含まれる。
要するに生活全般。
僕らのおじいちゃん世代まではみんなが当たり前にやってた生活。
決して、懐古主義とか古き良き時代への憧れという捉え方ではない。
これからの時代に合った、最先端生活だ。
「X」の部分は仕事。
完全にどっぷり自給自足という事じゃなく、農的な暮らしの合間の時間で他の仕事は十分可能。
アルバイト的な行為じゃなく、自分の得意分野を活かした仕事が望ましい。
別に即お金になるかどうかは重要ではない。
自分の好きなこと、得意なことは必ず生活の役に立つ。
うちの場合は「X」の中に、陶芸、ピザの出店、あっこスイーツ、廃材建築もこっちに入ってきてる。

ロケットのお浸しと、インゲンの胡麻和え。

枝豆。

マテ貝の酒蒸し、イタリアンパセリ添え。
マテ貝の強いコクとイタリアンパセリが抜群の相性。

マテ貝の燻製&干物。
これは完成度高かった。

梅肉サラダ。
サラダ以外の材料は全て、同級生の畑料理人からの頂き物。
マテ貝を採りに行って、自分の畑のロケットやイタリアンパセリと一緒に持って来てくれるのが最高にありがたい。
毎日の生活こそが生き方の選択。
朝から晩までの生活
一週間の生活
一ヶ月の生活
一年の生活
一生の生活
その生活の結果、あっという間の人生。
どうせなら納得のいく選択をせなねー。
シーツを四角に縫って、玉ネギの皮で染めた。
それに、雅がパッチワークで字を入れてくれた。
やっぱり、材料は古着。
しかも雅の即興でラフなデザインがいい。
出店の時なんかに使う。
ここがウチの「選択」。
業者にノボリを発注しない。
金が云々よりも、プロに頼むことにワクワクしない。
自分でクリエイトする楽しさを選ぶ。
雅は大学の時、アパレルデザイン、タッキーは現役のテキスタイル(染織)の学生。
オルタナティブ(代替)生活、自給自足、を目指しながらもこういう「得意分野」はずっと使える。
僕の陶芸もほとんどやってないけど、完全に辞める訳ではない。
半農半Xという捉え方。
「X」の部分が一つじゃなくていい。
この「半農半X」というのは京都の綾部、塩見直紀さんの本「半農半Xという生き方」で世に広まった。
「農」の部分には、障子の張り替えやトイの修理などの家のメンテナンス、漬けものや味噌作りなども含まれる。
要するに生活全般。
僕らのおじいちゃん世代まではみんなが当たり前にやってた生活。
決して、懐古主義とか古き良き時代への憧れという捉え方ではない。
これからの時代に合った、最先端生活だ。
「X」の部分は仕事。
完全にどっぷり自給自足という事じゃなく、農的な暮らしの合間の時間で他の仕事は十分可能。
アルバイト的な行為じゃなく、自分の得意分野を活かした仕事が望ましい。
別に即お金になるかどうかは重要ではない。
自分の好きなこと、得意なことは必ず生活の役に立つ。
うちの場合は「X」の中に、陶芸、ピザの出店、あっこスイーツ、廃材建築もこっちに入ってきてる。
ロケットのお浸しと、インゲンの胡麻和え。
枝豆。
マテ貝の酒蒸し、イタリアンパセリ添え。
マテ貝の強いコクとイタリアンパセリが抜群の相性。
マテ貝の燻製&干物。
これは完成度高かった。
梅肉サラダ。
サラダ以外の材料は全て、同級生の畑料理人からの頂き物。
マテ貝を採りに行って、自分の畑のロケットやイタリアンパセリと一緒に持って来てくれるのが最高にありがたい。
毎日の生活こそが生き方の選択。
朝から晩までの生活
一週間の生活
一ヶ月の生活
一年の生活
一生の生活
その生活の結果、あっという間の人生。
どうせなら納得のいく選択をせなねー。
タグ :のぼり
2012年07月25日
このぐらいのカオスぶりがまたいいね
インドの大学に行ってるタッキーが帰ってきてる。
帰省の度にウチに寄ってくれてる。

ビワエキス作りのためのビワの葉を洗ってもらう。
この葉は近所のビワ畑から採らせてもらう。

僕はサッシの枠の周りの隙間を埋める作業。
出番の多い、畳屋でもらえるゴザ。
もらいに行って、「一束もらって行きますよ。」と顔なじみの職人さんに言うと、「一つと言わずに!」と2、3束軽トラの荷台に積み込んでくれる。

こういう斜めの複雑な形状の所が難しい。

柔軟性があるんで、ガンタッカーで強引に留めまくる。
冬に寒くないようにという目的もあるし、今は蚊が入らないためなので、小さな隙間も徹底的に埋める。

ガラスも入れて、外観はこんな感じ。
網戸はボロくなってるので、張り替えないといけない。

妹の雅も京都から帰って来てる。
「金時人参は7月中が蒔きどきやで!」と言われて、丁度今まで人参を植えてた場所に植えることにした。
不耕起と言っても耕運機で耕さないだけで、平鍬で表面を削って、備中鍬で軽く混ぜる。
雅は京都の糸川さんという師匠の元で畑をやってる。
「糸川式自給農法」と言う長年のノウハウを教えてもらいながらも、自分で実践して何年も経験を積んでるんで、「へー!」と僕も教わることが多い。
その畑の野菜を使って、手作りのフードを出店したり、ケータリングを受けたりするのを生業にしてる。
兄妹で似たような事やってる。
ま、弟の所も同類。

少し溝を作って、たっぷりと水をやって人参を蒔く場所を作る。
これは後で水を遣ったりしないようにするため。
それと溝は、大雨が降った時に流れてしまうの防ぐ。
人参って発芽させるのが難しい。
大根や葉物などは超簡単やけどね。
人参の種は軽くて小さい。
発芽のためには覆土も最小限にしておかないといけないし。
で、編み出されたのが糸川式のノウハウ。
凄い!
理にかなってる!

種に灰をまぶす。
人参やホウレン草などは酸性土壌を嫌うから。

種を蒔いた後はうっすらと覆土して、パンパン叩いてしっかり鎮圧する。
これも種が流れないため。
種を蒔いた溝の上には草を置いて、乾燥を防ぐ。
この草が湿る程度にサラッと水やりすると一週間で発芽するそうな。
ナータンとネオンくんも夕方来てて、手伝ってくれた。
というか、彼らも雅のノウハウを勉強したくて一生懸命。

ご飯もみんなで作る。
インド帰りのタッキーがスパイスを色々持って来てくれてて、カレーパーティー。
一番上のはウチの鶏さんの茹で卵を揚げたのが入ったカレー。
次がナスとキュウリのカレー。
サラダは定番の豆乳と梅酢のサッパリ系。
一番下のちっこいのはシソとミントのアチャール。
カレーにはチリは入れてなくて子どもでも十分に食べられる。
アチャール(インドの漬けもの)はかなりホットで、大人はそれをつけながら食べると丁度いい。

これは雅の焼いてきた重いパン。
薄くスライスしてカリカリに焼くとつけ合わせにいい。
上から、ナスペースト、豆腐のディップ、砂糖ナシの米飴マーマレード。

トミーも合流して、大勢でのディナーになった。
トミーは10月のテント劇「どくんご」と同時開催の「手作り市」の事で来てくれてた。
そろそろ出店者さん募集していかななー。
今年は10/20(土)、21(日)でっせー!
オリジナルで一から手作りのフードや雑貨の作家さんも来たり、マッサージやヒーリング系の人も!
みんなで宣伝して盛り上げて行こう!!

初対面と思いきや、クロマニョンズのライブの最前列で一緒だったそう。
「あー、あの時ぶつかってきた!」と。
どっちもロック好き石屋ということで、超盛り上がってた!
帰省の度にウチに寄ってくれてる。
ビワエキス作りのためのビワの葉を洗ってもらう。
この葉は近所のビワ畑から採らせてもらう。
僕はサッシの枠の周りの隙間を埋める作業。
出番の多い、畳屋でもらえるゴザ。
もらいに行って、「一束もらって行きますよ。」と顔なじみの職人さんに言うと、「一つと言わずに!」と2、3束軽トラの荷台に積み込んでくれる。
こういう斜めの複雑な形状の所が難しい。
柔軟性があるんで、ガンタッカーで強引に留めまくる。
冬に寒くないようにという目的もあるし、今は蚊が入らないためなので、小さな隙間も徹底的に埋める。
ガラスも入れて、外観はこんな感じ。
網戸はボロくなってるので、張り替えないといけない。
妹の雅も京都から帰って来てる。
「金時人参は7月中が蒔きどきやで!」と言われて、丁度今まで人参を植えてた場所に植えることにした。
不耕起と言っても耕運機で耕さないだけで、平鍬で表面を削って、備中鍬で軽く混ぜる。
雅は京都の糸川さんという師匠の元で畑をやってる。
「糸川式自給農法」と言う長年のノウハウを教えてもらいながらも、自分で実践して何年も経験を積んでるんで、「へー!」と僕も教わることが多い。
その畑の野菜を使って、手作りのフードを出店したり、ケータリングを受けたりするのを生業にしてる。
兄妹で似たような事やってる。
ま、弟の所も同類。
少し溝を作って、たっぷりと水をやって人参を蒔く場所を作る。
これは後で水を遣ったりしないようにするため。
それと溝は、大雨が降った時に流れてしまうの防ぐ。
人参って発芽させるのが難しい。
大根や葉物などは超簡単やけどね。
人参の種は軽くて小さい。
発芽のためには覆土も最小限にしておかないといけないし。
で、編み出されたのが糸川式のノウハウ。
凄い!
理にかなってる!
種に灰をまぶす。
人参やホウレン草などは酸性土壌を嫌うから。
種を蒔いた後はうっすらと覆土して、パンパン叩いてしっかり鎮圧する。
これも種が流れないため。
種を蒔いた溝の上には草を置いて、乾燥を防ぐ。
この草が湿る程度にサラッと水やりすると一週間で発芽するそうな。
ナータンとネオンくんも夕方来てて、手伝ってくれた。
というか、彼らも雅のノウハウを勉強したくて一生懸命。
ご飯もみんなで作る。
インド帰りのタッキーがスパイスを色々持って来てくれてて、カレーパーティー。
一番上のはウチの鶏さんの茹で卵を揚げたのが入ったカレー。
次がナスとキュウリのカレー。
サラダは定番の豆乳と梅酢のサッパリ系。
一番下のちっこいのはシソとミントのアチャール。
カレーにはチリは入れてなくて子どもでも十分に食べられる。
アチャール(インドの漬けもの)はかなりホットで、大人はそれをつけながら食べると丁度いい。
これは雅の焼いてきた重いパン。
薄くスライスしてカリカリに焼くとつけ合わせにいい。
上から、ナスペースト、豆腐のディップ、砂糖ナシの米飴マーマレード。
トミーも合流して、大勢でのディナーになった。
トミーは10月のテント劇「どくんご」と同時開催の「手作り市」の事で来てくれてた。
そろそろ出店者さん募集していかななー。
今年は10/20(土)、21(日)でっせー!
オリジナルで一から手作りのフードや雑貨の作家さんも来たり、マッサージやヒーリング系の人も!
みんなで宣伝して盛り上げて行こう!!
初対面と思いきや、クロマニョンズのライブの最前列で一緒だったそう。
「あー、あの時ぶつかってきた!」と。
どっちもロック好き石屋ということで、超盛り上がってた!
2012年07月24日
ままごとキッチン料理教室
あっこスイーツ教室盛況やったよ。
「ままごとキッチン」という屋号であっこちゃん主宰の教室は不定期で月に一回ぐらい開催。

「子どもと一緒に手作りの生活」というのが信条のあっこちゃん。
ということで、ほとんどの方がちびっ子連れ。
子どもたちが少ないと、お母さんと一緒に作る流れにもなる。
昨日はお母さんソッチのけで子どもたち同士で遊んでた。
それもまたいい。

アメリカンドッグ風の「にんじんのスティックドーナツ」作り。
数々の試作を経て、完成度も上がってる。

お昼前に、みんなでランチの用意。
オムスビ作ったり、生春巻き巻いたり。
生春巻きの材料は野遊が、畑から野菜を採ってきて切ってくれてた。
ナンプラーとチリソースの定番のタレじゃなく、ゴマダレにした。
これも野遊のアレンジで美味しかった。

「おこめのアイスクリーム」!
自家製、野イチゴのソース。
どちらも卵、砂糖、乳製品ナシのマクロビスイーツ。
スティックドーナツはまだ分かるけど、このアイスが乳製品ナシとは驚き!
甘みは自家製の甘酒。
それに、何とご飯が入ってたりもする。

ココア味。
濃厚で、ラム酒かブランデーが欲しくなる。
前回の日記で紹介した鈴木博之さんのCDには多くの問い合わせが来てる。
メールくれた方には博之さんからのメッセージをコピペして送ってる。
CDの中には「それはないやろ~!」とツッコミ入れる所満載!
でもその「違う意見を受け止める」のが重要だと、ここ2、3日感じてる。
「僕の予想とは大きく食い違った」というのは、そう簡単にはこの資本主義社会が終焉に近づかないということ。
脱原発=脱資本主義
それは、脱政府にも繋がる。
てことは脱社会、、、。
別に反社会的な思想でクーデターを起こそうかということで、この生活やってる訳ではない。
実は廃材の家には地下があって、爆弾作ってるということは、、、ない。
そもそも僕は理数科系苦手やし。
ここの所の廃材天国の日記の「稼がないし、使わない」というフレーズには正論過ぎて、「無人島にでも行っとけ論」に飛躍する。
理解に苦しむと思うけど、稼がなくても、そんなに使う事がないんで十分事足りてるということ。
家賃も借金もなく、光熱費も食費もほとんどかからない生活。
廃材の家、田んぼと畑と薪の生活。
実際に、こういう生活を確立してしまったんやからしかたがない。
でも、これはこの社会の中のスキマを利用して実現してる生活。
そもそも無人島で廃材もらえるか!
と、開き直ってる。
その恩恵にあやかりながらの「社会批判」にツッコミを入れる不勉強者はまだ多い。
「電気使いながら脱原発なんて言うな!」という原発利権の裏さえ知らない人間もまだまだいる。
今回の大飯再稼働で、関電は「電気の需給の問題と再稼働は関係ない。」と断言したじゃん。
電源三法交付金目当ての天下り知事に、総括原価方式で成り立つ「あり得ない」電力会社、、、。
でまた、そういう行政や会社に翻弄される消費生活。
そういう次元から「イチ抜ーけた!」と廃材焚いて生活してるだけ。
もちろん抜けられないし、抜けるつもりもない。
「イチ抜ーけた!」というセリフを書ける自分を確認してるのだ。
目的は「自分に違和感のある事をしない生活」。
手段が廃材イジリ生活。
とっくに、手段が目的化してるけど、、、。
どっちにせよ、政府も円経済も淡々と動いていく。
その活動の中にありながら、呪縛されない生き方は可能だよ。
とお手本を指し示すのがこの日記。
人生を確立した中高年の諸先輩方は応援してくれるだけでいい。
今から35年ローンを組んで「辞めるに辞められないスパイラル」に入る前の若者に叱咤激励してるのだ。
「人生なんて大したことない。」
呪縛からの解放だ!
なんて力まなくていいから、まず口に出して言ってみろ。
やってるうちに知らずと軽くなってくるもんやー。
「ままごとキッチン」という屋号であっこちゃん主宰の教室は不定期で月に一回ぐらい開催。
「子どもと一緒に手作りの生活」というのが信条のあっこちゃん。
ということで、ほとんどの方がちびっ子連れ。
子どもたちが少ないと、お母さんと一緒に作る流れにもなる。
昨日はお母さんソッチのけで子どもたち同士で遊んでた。
それもまたいい。
アメリカンドッグ風の「にんじんのスティックドーナツ」作り。
数々の試作を経て、完成度も上がってる。
お昼前に、みんなでランチの用意。
オムスビ作ったり、生春巻き巻いたり。
生春巻きの材料は野遊が、畑から野菜を採ってきて切ってくれてた。
ナンプラーとチリソースの定番のタレじゃなく、ゴマダレにした。
これも野遊のアレンジで美味しかった。
「おこめのアイスクリーム」!
自家製、野イチゴのソース。
どちらも卵、砂糖、乳製品ナシのマクロビスイーツ。
スティックドーナツはまだ分かるけど、このアイスが乳製品ナシとは驚き!
甘みは自家製の甘酒。
それに、何とご飯が入ってたりもする。
ココア味。
濃厚で、ラム酒かブランデーが欲しくなる。
前回の日記で紹介した鈴木博之さんのCDには多くの問い合わせが来てる。
メールくれた方には博之さんからのメッセージをコピペして送ってる。
CDの中には「それはないやろ~!」とツッコミ入れる所満載!
でもその「違う意見を受け止める」のが重要だと、ここ2、3日感じてる。
「僕の予想とは大きく食い違った」というのは、そう簡単にはこの資本主義社会が終焉に近づかないということ。
脱原発=脱資本主義
それは、脱政府にも繋がる。
てことは脱社会、、、。
別に反社会的な思想でクーデターを起こそうかということで、この生活やってる訳ではない。
実は廃材の家には地下があって、爆弾作ってるということは、、、ない。
そもそも僕は理数科系苦手やし。
ここの所の廃材天国の日記の「稼がないし、使わない」というフレーズには正論過ぎて、「無人島にでも行っとけ論」に飛躍する。
理解に苦しむと思うけど、稼がなくても、そんなに使う事がないんで十分事足りてるということ。
家賃も借金もなく、光熱費も食費もほとんどかからない生活。
廃材の家、田んぼと畑と薪の生活。
実際に、こういう生活を確立してしまったんやからしかたがない。
でも、これはこの社会の中のスキマを利用して実現してる生活。
そもそも無人島で廃材もらえるか!
と、開き直ってる。
その恩恵にあやかりながらの「社会批判」にツッコミを入れる不勉強者はまだ多い。
「電気使いながら脱原発なんて言うな!」という原発利権の裏さえ知らない人間もまだまだいる。
今回の大飯再稼働で、関電は「電気の需給の問題と再稼働は関係ない。」と断言したじゃん。
電源三法交付金目当ての天下り知事に、総括原価方式で成り立つ「あり得ない」電力会社、、、。
でまた、そういう行政や会社に翻弄される消費生活。
そういう次元から「イチ抜ーけた!」と廃材焚いて生活してるだけ。
もちろん抜けられないし、抜けるつもりもない。
「イチ抜ーけた!」というセリフを書ける自分を確認してるのだ。
目的は「自分に違和感のある事をしない生活」。
手段が廃材イジリ生活。
とっくに、手段が目的化してるけど、、、。
どっちにせよ、政府も円経済も淡々と動いていく。
その活動の中にありながら、呪縛されない生き方は可能だよ。
とお手本を指し示すのがこの日記。
人生を確立した中高年の諸先輩方は応援してくれるだけでいい。
今から35年ローンを組んで「辞めるに辞められないスパイラル」に入る前の若者に叱咤激励してるのだ。
「人生なんて大したことない。」
呪縛からの解放だ!
なんて力まなくていいから、まず口に出して言ってみろ。
やってるうちに知らずと軽くなってくるもんやー。
タグ :料理教室
2012年07月23日
5年、10年先の具体的な社会のイメージ
アルミサッシ化リフォーム進んでるよ。

サッシ以外の所の壁の地は出来た。

中から見た所。

今回使って、この焦げた廃材も、ほぼ使い切った。
材木置き場が火事になったのを消防車が消した廃材。
家にして20棟分だったとか。

風呂と母屋の間は3mある。
この仕切りのお陰で随分広い部屋を確保することになる。
こちらに向いてるサッシから薪の積み込みを出来るようにする。

この作業は手も鼻の穴も真っ黒になる。
「考えずに身体を動かす。」
とは言いながら、今回は随分と考えた。
出来た写真を見れば「ふーん。」てもんやけど、作業中に腕組みして考えることしばしば。
材料、サッシの位置、デザイン、、、。
悩む訳ではない。
いかに廃材天国内の材料で、クールに仕上げるか?
その前向きな思考がまた楽しい。
いいアイデアが出ないとモヤモヤするけど、そのプロセスを経て「ええ事思いついたーーー!!!」と閃きがやってくる。
それは確実に保証されてる。
要は取り掛かりもしないうちから「あーでもない、こーでもない」と考えるんじゃなく、動き始めてから考える。
すると、新たな閃きがドンドン湧いてくる。
「時間も廃材も山ほどある。」
とは言いながら、自分を飽きさせない程度にはチャッチャと片づけたい。
僕は「あっと言う間に出来る。」というスピード感も大切にしたい。
その中で「ここはコレでええわ。」とアッサリ切り捨てられる所はそうする。
一から全てを築く廃材建築では、作るのも使うのも自分自身。
どの廃材を使ってどういうデザインでいくか?
全て決めるのは自分。
使い勝手はいいようにしたいけど、不必要な程の細かい仕上げを必要としない。
また、都合が悪ければ後でいくらでも手直しがきく。
そういう意味でも、躊躇なく大胆にガンガン進める。
それもこれも、向き不向きがあるし、「これからの社会がどうなって行くのか?」というビジョンも関係する。
「自分の好き嫌い」×「社会情勢」
これがキーになる。
「好きなこと、したいことしかしない!」と断言する僕も、今の自画杜撰な稼がなくても左ウチワ生活を送ってるのには経緯がある。
夫婦揃って、自給自足なんかに関心を持ち始めて実践するようになったのはナゼか?
一言で言うと「環境問題に関心を持ってから。」。
大阪の梅田にある「ネットワーク地球村」の講演会を聞いたのがキッカケ。
もう、16年前になる。
それからまた世情は変化した。
当時はまだ、少数の環境意識層に圧倒的多数の無関心層という構図。
それが3、11の原発震災からかなり変わって来た。
ここの所のデモとか10万人とか凄い数になってきてるし。
原発事故から放射能や食の安全の事。
国家破産やハイパーインフレなどの経済問題。
政府と大手企業は全く信用出来ない事が分かった。
では、これから具体的にそういうシナリオをたどるのか?
もちろん未来のことは誰にも分からない。
分からないとは言え、自分なりの予想はしなければいけない。
100年先の事はちょっと難しい。
せめて、5年、10年先の事を具体的にイメージして今の生活を決めなければいけない。
これから次々と原発が事故を起こすのか?
放射能でバンバン癌が加速するのか?
いつハイパーインフレが来るのか?
石油や核の代替エネルギーは確立できるのか?
日本の政治は機能していくのか?
国内の仕事は今後どうなっていくのか?
食料問題はどうなるのか?
戦争は起きないのか?
そういう事が自分の身にふりかかる前に予想しないといけない。
もちろん、「将来は、、、。」という漠然とした感覚では僕も捉えてたし、考えてたつもりだった。
でも、、、。
最近ある情報を聞いて、ある意味愕然とした。
上に書いた問題と言われてる事って、悪くなればなる程みんなが気付くキッカケになっていいと思ってた。
環境問題も経済問題も深刻になればなるほど「これではいけない!」と気付くから。
年に一回は廃材天国でセミナーを開いてくれる鈴木博之さん。
博之さんは環境問題から経済問題、歴史問題とあらゆる角度から話をしてくれる。
その博之さんが「ある人物」にインタビューをされた(上記のような、政治や経済、エネルギー、などの5年、10年先の事)。
僕は博之さんとは付き合いも長いし信頼してるので、このインタビューの内容に惹かれた。
それを収録したCDが出来たので、有料だったけど早速取り寄せて聞いた。
それは僕の予想とはかなり食い違う内容だった。
それで愕然とした。
ショックを受けるのはいい事。
みんなが同じ考えになんかなりっこない。
違いがあることで、「そっか、自分はコッチがいい。」と進む方向を決められる。
と、何日か経って思えるようになってきた。
もちろん、廃材天国での最高生活は今後この方向でジャンジャン突き進む事に変わりはない!
そのCDの事に質問があれば、コメントじゃなく、メールしてね。
haizaitengoku@gmail.comまで。
本当に求めてない人は聞かない方がいいと思う内容やから、関心のない人は忘れよう!
サッシ以外の所の壁の地は出来た。
中から見た所。
今回使って、この焦げた廃材も、ほぼ使い切った。
材木置き場が火事になったのを消防車が消した廃材。
家にして20棟分だったとか。
風呂と母屋の間は3mある。
この仕切りのお陰で随分広い部屋を確保することになる。
こちらに向いてるサッシから薪の積み込みを出来るようにする。
この作業は手も鼻の穴も真っ黒になる。
「考えずに身体を動かす。」
とは言いながら、今回は随分と考えた。
出来た写真を見れば「ふーん。」てもんやけど、作業中に腕組みして考えることしばしば。
材料、サッシの位置、デザイン、、、。
悩む訳ではない。
いかに廃材天国内の材料で、クールに仕上げるか?
その前向きな思考がまた楽しい。
いいアイデアが出ないとモヤモヤするけど、そのプロセスを経て「ええ事思いついたーーー!!!」と閃きがやってくる。
それは確実に保証されてる。
要は取り掛かりもしないうちから「あーでもない、こーでもない」と考えるんじゃなく、動き始めてから考える。
すると、新たな閃きがドンドン湧いてくる。
「時間も廃材も山ほどある。」
とは言いながら、自分を飽きさせない程度にはチャッチャと片づけたい。
僕は「あっと言う間に出来る。」というスピード感も大切にしたい。
その中で「ここはコレでええわ。」とアッサリ切り捨てられる所はそうする。
一から全てを築く廃材建築では、作るのも使うのも自分自身。
どの廃材を使ってどういうデザインでいくか?
全て決めるのは自分。
使い勝手はいいようにしたいけど、不必要な程の細かい仕上げを必要としない。
また、都合が悪ければ後でいくらでも手直しがきく。
そういう意味でも、躊躇なく大胆にガンガン進める。
それもこれも、向き不向きがあるし、「これからの社会がどうなって行くのか?」というビジョンも関係する。
「自分の好き嫌い」×「社会情勢」
これがキーになる。
「好きなこと、したいことしかしない!」と断言する僕も、今の自画杜撰な稼がなくても左ウチワ生活を送ってるのには経緯がある。
夫婦揃って、自給自足なんかに関心を持ち始めて実践するようになったのはナゼか?
一言で言うと「環境問題に関心を持ってから。」。
大阪の梅田にある「ネットワーク地球村」の講演会を聞いたのがキッカケ。
もう、16年前になる。
それからまた世情は変化した。
当時はまだ、少数の環境意識層に圧倒的多数の無関心層という構図。
それが3、11の原発震災からかなり変わって来た。
ここの所のデモとか10万人とか凄い数になってきてるし。
原発事故から放射能や食の安全の事。
国家破産やハイパーインフレなどの経済問題。
政府と大手企業は全く信用出来ない事が分かった。
では、これから具体的にそういうシナリオをたどるのか?
もちろん未来のことは誰にも分からない。
分からないとは言え、自分なりの予想はしなければいけない。
100年先の事はちょっと難しい。
せめて、5年、10年先の事を具体的にイメージして今の生活を決めなければいけない。
これから次々と原発が事故を起こすのか?
放射能でバンバン癌が加速するのか?
いつハイパーインフレが来るのか?
石油や核の代替エネルギーは確立できるのか?
日本の政治は機能していくのか?
国内の仕事は今後どうなっていくのか?
食料問題はどうなるのか?
戦争は起きないのか?
そういう事が自分の身にふりかかる前に予想しないといけない。
もちろん、「将来は、、、。」という漠然とした感覚では僕も捉えてたし、考えてたつもりだった。
でも、、、。
最近ある情報を聞いて、ある意味愕然とした。
上に書いた問題と言われてる事って、悪くなればなる程みんなが気付くキッカケになっていいと思ってた。
環境問題も経済問題も深刻になればなるほど「これではいけない!」と気付くから。
年に一回は廃材天国でセミナーを開いてくれる鈴木博之さん。
博之さんは環境問題から経済問題、歴史問題とあらゆる角度から話をしてくれる。
その博之さんが「ある人物」にインタビューをされた(上記のような、政治や経済、エネルギー、などの5年、10年先の事)。
僕は博之さんとは付き合いも長いし信頼してるので、このインタビューの内容に惹かれた。
それを収録したCDが出来たので、有料だったけど早速取り寄せて聞いた。
それは僕の予想とはかなり食い違う内容だった。
それで愕然とした。
ショックを受けるのはいい事。
みんなが同じ考えになんかなりっこない。
違いがあることで、「そっか、自分はコッチがいい。」と進む方向を決められる。
と、何日か経って思えるようになってきた。
もちろん、廃材天国での最高生活は今後この方向でジャンジャン突き進む事に変わりはない!
そのCDの事に質問があれば、コメントじゃなく、メールしてね。
haizaitengoku@gmail.comまで。
本当に求めてない人は聞かない方がいいと思う内容やから、関心のない人は忘れよう!
タグ :情報
2012年07月22日
石窯BBQ
昨日は田植えのお疲れ様会として、実家の石窯の前で宴会。
源とこ家族に、手伝ってくれたゆかりちゃんの両親やお姉さん夫婦も招いてのホームパーティー。

廃材天国の移動式と違って、簡単に作れる石窯。
親父が鶏のモモに塩コショウ、ニンニクなどをすり込んで仕込んでた。
店のは超辛い味付けなので、手作りの方が美味しい。
香川県では「骨付きどり」と言って、店もたくさんある。
B級グルメという事で流行ってるらしい。
親父の話では一鶴という有名な店も昔は丸亀駅の裏の小さな店で、七輪の炭火で焼いてたとか。
当時は鶏肉の質も味付けもよかったと親父は言う。
今まで作った19基のピザ窯のうち18基はこういうスタイル。
ここは土台が石で窯は土。
先日の「ひなの村」は土台が瓦。
そこにある材料を利用して作る。
材料の粘土だけはウチから陶芸用のストックしてるのを持って行く。

蒸しナスの生姜醤油漬け。

ゴボウとシメジの生春巻き。
醤油ベースのタレ。

こっちはカラーピーマン、玉ネギ、揚げ。
ゴマダレ。

ただの生野菜。
親父の畑でもナス、キュウリ、トマトなどの夏野菜はよく採れてる。

大勢なのでオムスビも大量。

鶏の後で、瀬戸内海の海の幸の丸焼き。
「魚の大空」のアナゴ、鯛、アオリイカ。
窯の熾き火と、いい塩でじっくり焼くと感動的な美味しさ。
田植えもみんな総出でワイワイやって、打ち上げもみんなの手作りでワイワイ。
これこそが真の贅沢だ。
源とこ家族に、手伝ってくれたゆかりちゃんの両親やお姉さん夫婦も招いてのホームパーティー。
廃材天国の移動式と違って、簡単に作れる石窯。
親父が鶏のモモに塩コショウ、ニンニクなどをすり込んで仕込んでた。
店のは超辛い味付けなので、手作りの方が美味しい。
香川県では「骨付きどり」と言って、店もたくさんある。
B級グルメという事で流行ってるらしい。
親父の話では一鶴という有名な店も昔は丸亀駅の裏の小さな店で、七輪の炭火で焼いてたとか。
当時は鶏肉の質も味付けもよかったと親父は言う。
今まで作った19基のピザ窯のうち18基はこういうスタイル。
ここは土台が石で窯は土。
先日の「ひなの村」は土台が瓦。
そこにある材料を利用して作る。
材料の粘土だけはウチから陶芸用のストックしてるのを持って行く。
蒸しナスの生姜醤油漬け。
ゴボウとシメジの生春巻き。
醤油ベースのタレ。
こっちはカラーピーマン、玉ネギ、揚げ。
ゴマダレ。
ただの生野菜。
親父の畑でもナス、キュウリ、トマトなどの夏野菜はよく採れてる。
大勢なのでオムスビも大量。
鶏の後で、瀬戸内海の海の幸の丸焼き。
「魚の大空」のアナゴ、鯛、アオリイカ。
窯の熾き火と、いい塩でじっくり焼くと感動的な美味しさ。
田植えもみんな総出でワイワイやって、打ち上げもみんなの手作りでワイワイ。
これこそが真の贅沢だ。
タグ :骨付き鶏
2012年07月21日
廃材リフォーム進行中
網戸を入れようとしたのが、かなり大掛かりなリフォームに発展してきた。
(前回の日記のイラスト参照)

これはおとといの作業。
アルミサッシの枠の下にモルタルを詰める。
土歩もコテを上手く使う。

完成。

これは前回の日記のイラストの下側(南側)。
石を切ってサッシを入れこむようにする。

その隙間に入るように、サッシの要らない部分を切り取る。

キッチンの出窓の角に合わせる。
45℃に斜めになってる所に2×4の廃材で下地を作る。

これで、サッシが入った。

風呂の薪置き場の方にもサッシを入れる。

コッチは下が土なので、基礎に石を置く。
丸亀沖の広島という島から出る青木石という花崗岩の廃材。
以前、板葺きの屋根の重石として乗せてたやつ。

石を二つ置いて、角材を置けばすぐにサッシが入る。

間の空間は材木屋が火事になった時に大量にもらった、焦げた木で埋める。
風呂の方とデザインを統一させた。
本当に焦げた木は腐りにくい。
もう雨ざらしで5、6年になるけど腐ってない。

作業の合間、子どもたちに鶏の餌に混ぜる貝殻を砕いてもらった。
こういうのはみんなやりたがる。

にこちゃんは豆腐のハンバーグ作り。

自家製ソースバージョン。

こっちはモヤシを炒めたのを乗せた。

こどもたちの大好きなポテトサラダ。
ユズを効かせてサッパリとしていい。
最近、一人の作業が多い。
思いつきの直感&即興の廃材建築。
しかもこういうちょこっとしたリフォームの時は「次はどうしようかな?」と常に考えながら。
そもそも材料は何でいくか?
どういう構造にするか?
デザインはどうするのか?
しかも、何も買わずにオール廃材で。
居候がいなくて、かえって一人の作業のペースが丁度いい。
ノルマもないし、急ぐ必要がない。
12年前のやり始めた頃は、遅々として進まないようなもどかしさもあった。
工程を間違えて、丸っきりやり直しをする羽目にも何度も遭った。
でもその、「全部一人でやりきる作業」という経験のお陰で今がある。
一軒目の廃材ハウス、陶芸の工房、7mの穴窯と3点セットで14ヶ月かけた。
一軒目も今の廃材天国も、一切プロの業者には頼んでない上に、材木の一本すら買ってない。
この作業には時間をかける価値がる。
「何千万という借金をしない」
これは若い時も、これからも。
暑かろうと、寒かろうと、この毎日の作業がそれを実現させてくれる。
材料がタダやから、お金のかかりようがない。
それがまた楽しい。
というマゾ的な要素があるよねー。
あっこちゃんなんか、全てにおいて「買わないで出来るということに喜びを覚える」という変態やし。
夫婦の得意分野は違う。
でも、こういう二人してブッ飛んでるとホントに楽チン!
(前回の日記のイラスト参照)
これはおとといの作業。
アルミサッシの枠の下にモルタルを詰める。
土歩もコテを上手く使う。
完成。
これは前回の日記のイラストの下側(南側)。
石を切ってサッシを入れこむようにする。
その隙間に入るように、サッシの要らない部分を切り取る。
キッチンの出窓の角に合わせる。
45℃に斜めになってる所に2×4の廃材で下地を作る。
これで、サッシが入った。
風呂の薪置き場の方にもサッシを入れる。
コッチは下が土なので、基礎に石を置く。
丸亀沖の広島という島から出る青木石という花崗岩の廃材。
以前、板葺きの屋根の重石として乗せてたやつ。
石を二つ置いて、角材を置けばすぐにサッシが入る。
間の空間は材木屋が火事になった時に大量にもらった、焦げた木で埋める。
風呂の方とデザインを統一させた。
本当に焦げた木は腐りにくい。
もう雨ざらしで5、6年になるけど腐ってない。
作業の合間、子どもたちに鶏の餌に混ぜる貝殻を砕いてもらった。
こういうのはみんなやりたがる。
にこちゃんは豆腐のハンバーグ作り。
自家製ソースバージョン。
こっちはモヤシを炒めたのを乗せた。
こどもたちの大好きなポテトサラダ。
ユズを効かせてサッパリとしていい。
最近、一人の作業が多い。
思いつきの直感&即興の廃材建築。
しかもこういうちょこっとしたリフォームの時は「次はどうしようかな?」と常に考えながら。
そもそも材料は何でいくか?
どういう構造にするか?
デザインはどうするのか?
しかも、何も買わずにオール廃材で。
居候がいなくて、かえって一人の作業のペースが丁度いい。
ノルマもないし、急ぐ必要がない。
12年前のやり始めた頃は、遅々として進まないようなもどかしさもあった。
工程を間違えて、丸っきりやり直しをする羽目にも何度も遭った。
でもその、「全部一人でやりきる作業」という経験のお陰で今がある。
一軒目の廃材ハウス、陶芸の工房、7mの穴窯と3点セットで14ヶ月かけた。
一軒目も今の廃材天国も、一切プロの業者には頼んでない上に、材木の一本すら買ってない。
この作業には時間をかける価値がる。
「何千万という借金をしない」
これは若い時も、これからも。
暑かろうと、寒かろうと、この毎日の作業がそれを実現させてくれる。
材料がタダやから、お金のかかりようがない。
それがまた楽しい。
というマゾ的な要素があるよねー。
あっこちゃんなんか、全てにおいて「買わないで出来るということに喜びを覚える」という変態やし。
夫婦の得意分野は違う。
でも、こういう二人してブッ飛んでるとホントに楽チン!
タグ :リフォーム
2012年07月19日
アルミサッシから閃くインスピレーション
先日の大きな開口部に網戸を設けたお陰で、随分涼しくなった。

後、廃材の母屋で網戸のない戸はココだけになった。
右の引き戸を開けて、外に冷蔵庫、風呂、トイレがある。
出店やあっこスイーツの為に最近、棄てられようとしてた白い冷蔵庫をもらった。
一軒目の廃材ハウスもそうやったけど、こういう深い軒のスペースを廊下代わりにする。
折角つくる廃材の家は全部有効利用したい。
廃材でセルフビルドする家に廊下って要らんね。

おととい、このアルミサッシ用の廃材網戸を見つけた。
ちょい、背が高過ぎるんで、グラインダーでアルミをカットして寸を詰めたり。
戸車の部分が傷んでて、サッシ屋に持って行ったりしてた。
部品を取り寄せるのに一週間ぐらいかかるとの事。

昨日になり、新たなアイデアが閃いた!
この通路的なスペースの両方にサッシを設ければ、冷蔵庫、風呂、トイレが全てサッシの中に入ることになる。
五右衛門風呂の焚口も当然入る。
冷蔵庫への出し入れや風呂焚き、トイレと、この戸を開ける頻度は超高い。
この全てのサッシに網戸を入れれば、涼しくなると同時に蚊が家に入る問題も解消しそう!

赤い所が新たにサッシを入れる予定の所。
今日の一枚目の写真は下から上に向けて撮ってる。
夏にキッチンの入り口を閉めなくてよくなれば、涼しい+冷蔵庫に行く度の開け閉めがなくなる。
冬の洗濯や風呂焚きも寒くなくなる。
「何で早よ思いつかんかったんやー!」てなもんやけど、こういうもの。
住んで4年目にしてようやくこういうアイデアが閃いた。
毎日生活してる中で、「いかに楽に、効率的に、快適に?」と常に考えて、閃きを形に進化させる。
実践の伴わない思考ではこうはいかない。
作りながら考える。
住みながら考える。
その考えを形にする。
どんどん自分の生活に合わせてリフォームしつづける。
これがセルフビルドの魅力。
かつ、廃材はタダなので、気軽く、閃いた次の瞬間から工事に入れる。

サッシは各種ストックされてる。
丁度いいのがあった。
というより、あるモノに合わせて工事する。
去年の夏、解体される家のソーラーパネルを自分で解体して取りに行くのに、お隣の愛媛県の新居浜市まで行った。
その家のサッシの状態がよかったんで、あくる日も軽トラで行って、解体屋の連中が他の仕事してる間にサッシを剥がして来てた。
解体屋から出る材木や瓦などの廃材は今では電話一本で持って来てくれるまでになった。
とはいえ、このサッシは外すのに労力がかかるんで、自ら外しに行かないといけない。

サッシの枠は角材。
こういう廃材は常にストックされてる。
雨ざらしで上等。
腐ってきたら焚きものにする。
この写真の置き場のはいいのばかり。

廃材のビフォー、アフター。
まずは、バールで釘を抜いたり、ボルトを外したりして、磨く。
手間を惜しまなければ廃材もキレイになる。

まずはイラストの上の部分(北側)から。

両サイドに角材を打ちつける。

ほい、サクッとアルミの枠が入る。
これはシビアに水平と垂直を出す。
この枠の大きさに合わせて、先に入れた角材の太さを選んで、ピッタリになるようにしてた。

ほい、オマケに上に窓用サッシも入れる。
これで、二つとも網戸にしてたら涼しいし、明るさも維持できる。
やっぱ、アルミサッシ最高!
先日の大きな開口部だけは木製の建具やけど、後は全部アルミ。
伝統工法の数寄屋造りとかで、アルミサッシは違和感がある。
やっぱし、木製の建具がクール。
ウチの場合は廃材建築自体の自然素材の存在感に圧倒されて、アルミサッシでも違和感はない。
実はハセヤンのカナディアンファームもアルミサッシが多用されてたけど、全然違和感なかった。
多分こういう目で見てないと、アルミかどうかさえ気づかないんちゃうかな。
それに、何を置いても、手軽に入口や窓が作れるのがいい。
隙間風も吹き降りの雨も入らんし。
解体現場に行けばいくらでも盗ってこれるし!

デカデカきゅうりと揚げの煮もの。
トロトロに煮たきゅうりを冷やして食べるのがいい。

前の日の残りのキュウリの炒め物がブレンドされたマーボーナス豆腐。
トウチと山椒を効かせると本格的になる。
大人は後でラー油をかける。

コンニャクとエリンギのソテー。
濃厚で美味しい。
廃材ごっこで汗を流した後、ご飯+ビールでまた瀧のような汗!
一日に何回も水浴びする季節になった。
それが気持ちいい~~。
後、廃材の母屋で網戸のない戸はココだけになった。
右の引き戸を開けて、外に冷蔵庫、風呂、トイレがある。
出店やあっこスイーツの為に最近、棄てられようとしてた白い冷蔵庫をもらった。
一軒目の廃材ハウスもそうやったけど、こういう深い軒のスペースを廊下代わりにする。
折角つくる廃材の家は全部有効利用したい。
廃材でセルフビルドする家に廊下って要らんね。
おととい、このアルミサッシ用の廃材網戸を見つけた。
ちょい、背が高過ぎるんで、グラインダーでアルミをカットして寸を詰めたり。
戸車の部分が傷んでて、サッシ屋に持って行ったりしてた。
部品を取り寄せるのに一週間ぐらいかかるとの事。
昨日になり、新たなアイデアが閃いた!
この通路的なスペースの両方にサッシを設ければ、冷蔵庫、風呂、トイレが全てサッシの中に入ることになる。
五右衛門風呂の焚口も当然入る。
冷蔵庫への出し入れや風呂焚き、トイレと、この戸を開ける頻度は超高い。
この全てのサッシに網戸を入れれば、涼しくなると同時に蚊が家に入る問題も解消しそう!
赤い所が新たにサッシを入れる予定の所。
今日の一枚目の写真は下から上に向けて撮ってる。
夏にキッチンの入り口を閉めなくてよくなれば、涼しい+冷蔵庫に行く度の開け閉めがなくなる。
冬の洗濯や風呂焚きも寒くなくなる。
「何で早よ思いつかんかったんやー!」てなもんやけど、こういうもの。
住んで4年目にしてようやくこういうアイデアが閃いた。
毎日生活してる中で、「いかに楽に、効率的に、快適に?」と常に考えて、閃きを形に進化させる。
実践の伴わない思考ではこうはいかない。
作りながら考える。
住みながら考える。
その考えを形にする。
どんどん自分の生活に合わせてリフォームしつづける。
これがセルフビルドの魅力。
かつ、廃材はタダなので、気軽く、閃いた次の瞬間から工事に入れる。
サッシは各種ストックされてる。
丁度いいのがあった。
というより、あるモノに合わせて工事する。
去年の夏、解体される家のソーラーパネルを自分で解体して取りに行くのに、お隣の愛媛県の新居浜市まで行った。
その家のサッシの状態がよかったんで、あくる日も軽トラで行って、解体屋の連中が他の仕事してる間にサッシを剥がして来てた。
解体屋から出る材木や瓦などの廃材は今では電話一本で持って来てくれるまでになった。
とはいえ、このサッシは外すのに労力がかかるんで、自ら外しに行かないといけない。
サッシの枠は角材。
こういう廃材は常にストックされてる。
雨ざらしで上等。
腐ってきたら焚きものにする。
この写真の置き場のはいいのばかり。
廃材のビフォー、アフター。
まずは、バールで釘を抜いたり、ボルトを外したりして、磨く。
手間を惜しまなければ廃材もキレイになる。
まずはイラストの上の部分(北側)から。
両サイドに角材を打ちつける。
ほい、サクッとアルミの枠が入る。
これはシビアに水平と垂直を出す。
この枠の大きさに合わせて、先に入れた角材の太さを選んで、ピッタリになるようにしてた。
ほい、オマケに上に窓用サッシも入れる。
これで、二つとも網戸にしてたら涼しいし、明るさも維持できる。
やっぱ、アルミサッシ最高!
先日の大きな開口部だけは木製の建具やけど、後は全部アルミ。
伝統工法の数寄屋造りとかで、アルミサッシは違和感がある。
やっぱし、木製の建具がクール。
ウチの場合は廃材建築自体の自然素材の存在感に圧倒されて、アルミサッシでも違和感はない。
実はハセヤンのカナディアンファームもアルミサッシが多用されてたけど、全然違和感なかった。
多分こういう目で見てないと、アルミかどうかさえ気づかないんちゃうかな。
それに、何を置いても、手軽に入口や窓が作れるのがいい。
隙間風も吹き降りの雨も入らんし。
解体現場に行けばいくらでも盗ってこれるし!
デカデカきゅうりと揚げの煮もの。
トロトロに煮たきゅうりを冷やして食べるのがいい。
前の日の残りのキュウリの炒め物がブレンドされたマーボーナス豆腐。
トウチと山椒を効かせると本格的になる。
大人は後でラー油をかける。
コンニャクとエリンギのソテー。
濃厚で美味しい。
廃材ごっこで汗を流した後、ご飯+ビールでまた瀧のような汗!
一日に何回も水浴びする季節になった。
それが気持ちいい~~。
タグ :アルミサッシ
2012年07月17日
「あっこスイーツ教室」のテーマは夏のジャンクフード
いやーーー。
やっと夏本番というぐらいの暑さになってきた。
イイ感じに暑くて、夏野菜とビールが美味い!
このぐらいの暑さじゃないと、夏野菜の力もビールのウマさも本領発揮しない。
作業してると滝のような汗ってレベルになってきたもんね。
一軒目の廃材ハウスの高瀬町は海抜70mと、中山間地で涼しかった。
真夏でも、夜中には網戸を閉めて寝ないと涼し過ぎるぐらいだった。
今の丸亀市郊外の廃材の家は海抜一ケタ。
名物、瀬戸内の夕凪がバッチリ効く。
まだ、この時期には風が止むことはなくて涼しい範囲。
廃材天国の室内も30℃を超えて来た。
当然エアコンはない。
天井が高いのと、窓が多いので明けまくって風が入るとなんとかなる。
夜開ける窓のアルミサッシの部分には網戸がある。

でも、この木製の建具の部分には網戸がないので開けられない。
左の土壁のが母屋。
右の二階の角ログ造りの建物が陶芸の工房。
あっこちゃんの要望で網戸を作ることに。
網戸は木枠を作りつけてしまって網を張るのが簡単な方法。

一番左の自動ドアのステッカーのあるガラスは厚みが2㎝もある超重いもので、はめ込んである。
そのガラスの部分に3枚の木製の建具が収まって、大きな開口部になる。
かつて、ライブでここを入り口にすることもあったんで、はめ込み式の網戸を作ってしまうのはどうかと躊躇してた。
かと言って、網戸もスライド式にするのは困難。
で、思いついた!
それなら、枠をビスで脱着式にすればいい!

二階の工房に下にストックしてる細めの廃材から材料を選ぶ。
細い材は解体現場ではほぼ出ない。
重機で壊すから折れてしまう。
こういうのは自分で現場に行って、バラしてこないといけない。

丁度いい感じの細くて揃ったのがあった。

計って、カットしてサンダで磨く。

造り付けにするんじゃなく、枠を作ってビス留めして、いつでも取り外しが出来るようにする。

厚みの差の部分には板を張って、蚊が入らないようにする。
こういう板は大工さんから来る廃材。
あらゆる廃材がストックされてるからねー。

網をガンタッカーで留めて完成。
思いついて、廃材の物色や加工を入れても2時間ぐらいの作業。
何も材料を買わなくて出来るのが廃材天国の誇り。
廃材使いのスキルが上がって来ると、どんどん速くてキレイにかつ丁寧な仕事が出来るようになる。
今シーズンでは一番暑かったと思われるけど、網戸のお陰で涼しく熟睡できたしね。
こんなに涼しくなるならもっと早くから作っときゃよかった。
やってしまええば簡単なことも、やる前には「戸が開かなくなると困るしなー。」とか考え過ぎて、作業に取りかかれてなかった。
後で気づく、「なーんや、簡単やったやん!」て事は多い。
廃材生活12年の僕でさえそう。
まだまだ、「考え過ぎる」という癖が残ってる。
考えずに直感で動くことの実践だ!
その実践の積み重ねが快適な生活を約束させる。

ナスも僕ら家族が食べるぐらいはギリギリで採れてる。
いよいよ今シーズン初のグラタン。
ソテーしてトマトソースで軽く煮たナスと、玉ネギを炒めて豆乳ホワイトソースに絡めたマカロニを重ねる。

オーブンで焼いて、バジルをバサッと乗せて完成。

チマサンチュがそろそろトウ立ちしそう。
歯ごたえがワイルドやけど、何とか食べられる。
甘酒ドレッシングを強くしてカバーする。

もずくと椎茸の和えもの。
これはポン酢でサッパリとさせる。
えー。
久々に「あっこスイーツ教室」開催決定!
ちびっ子連れ参加歓迎。
うちがいつやってるように子どもと作る教室。
7/23(月)朝10時からお昼まで
大人2000円、小学生1000円、3歳から500円。
スイーツ作りの後は、簡単なあっこ料理でランチタイム。
今回は
「人参のスティックドーナツ」
大きなイベントなどで、アメリカンドッグを子どもたちが欲しがるので、畑の人参と手作りの生地とで作ってみた。
これが大好評!
「豆乳のアイスクリーム」
自家製の甘酒だけで甘みをつける、マクロビアイス。
食べた後の喉の渇きがない、サッパリ系。
乳製品も砂糖もナシやから当たり前なんやけど、ちゃんと美味しいアイスクリームになるよ。
特に、この季節はイベントやお祭りが多いもの。
そういう所で子どもに「アレ食べたいー!」とねだられる。
いつもいつも、「アレはね、、、。」と我慢させるばかりよりは、手作りで作ってしまおう。
申し込みは
haizaitengoku@gmail.comまで。
やっと夏本番というぐらいの暑さになってきた。
イイ感じに暑くて、夏野菜とビールが美味い!
このぐらいの暑さじゃないと、夏野菜の力もビールのウマさも本領発揮しない。
作業してると滝のような汗ってレベルになってきたもんね。
一軒目の廃材ハウスの高瀬町は海抜70mと、中山間地で涼しかった。
真夏でも、夜中には網戸を閉めて寝ないと涼し過ぎるぐらいだった。
今の丸亀市郊外の廃材の家は海抜一ケタ。
名物、瀬戸内の夕凪がバッチリ効く。
まだ、この時期には風が止むことはなくて涼しい範囲。
廃材天国の室内も30℃を超えて来た。
当然エアコンはない。
天井が高いのと、窓が多いので明けまくって風が入るとなんとかなる。
夜開ける窓のアルミサッシの部分には網戸がある。
でも、この木製の建具の部分には網戸がないので開けられない。
左の土壁のが母屋。
右の二階の角ログ造りの建物が陶芸の工房。
あっこちゃんの要望で網戸を作ることに。
網戸は木枠を作りつけてしまって網を張るのが簡単な方法。
一番左の自動ドアのステッカーのあるガラスは厚みが2㎝もある超重いもので、はめ込んである。
そのガラスの部分に3枚の木製の建具が収まって、大きな開口部になる。
かつて、ライブでここを入り口にすることもあったんで、はめ込み式の網戸を作ってしまうのはどうかと躊躇してた。
かと言って、網戸もスライド式にするのは困難。
で、思いついた!
それなら、枠をビスで脱着式にすればいい!
二階の工房に下にストックしてる細めの廃材から材料を選ぶ。
細い材は解体現場ではほぼ出ない。
重機で壊すから折れてしまう。
こういうのは自分で現場に行って、バラしてこないといけない。
丁度いい感じの細くて揃ったのがあった。
計って、カットしてサンダで磨く。
造り付けにするんじゃなく、枠を作ってビス留めして、いつでも取り外しが出来るようにする。
厚みの差の部分には板を張って、蚊が入らないようにする。
こういう板は大工さんから来る廃材。
あらゆる廃材がストックされてるからねー。
網をガンタッカーで留めて完成。
思いついて、廃材の物色や加工を入れても2時間ぐらいの作業。
何も材料を買わなくて出来るのが廃材天国の誇り。
廃材使いのスキルが上がって来ると、どんどん速くてキレイにかつ丁寧な仕事が出来るようになる。
今シーズンでは一番暑かったと思われるけど、網戸のお陰で涼しく熟睡できたしね。
こんなに涼しくなるならもっと早くから作っときゃよかった。
やってしまええば簡単なことも、やる前には「戸が開かなくなると困るしなー。」とか考え過ぎて、作業に取りかかれてなかった。
後で気づく、「なーんや、簡単やったやん!」て事は多い。
廃材生活12年の僕でさえそう。
まだまだ、「考え過ぎる」という癖が残ってる。
考えずに直感で動くことの実践だ!
その実践の積み重ねが快適な生活を約束させる。
ナスも僕ら家族が食べるぐらいはギリギリで採れてる。
いよいよ今シーズン初のグラタン。
ソテーしてトマトソースで軽く煮たナスと、玉ネギを炒めて豆乳ホワイトソースに絡めたマカロニを重ねる。
オーブンで焼いて、バジルをバサッと乗せて完成。
チマサンチュがそろそろトウ立ちしそう。
歯ごたえがワイルドやけど、何とか食べられる。
甘酒ドレッシングを強くしてカバーする。
もずくと椎茸の和えもの。
これはポン酢でサッパリとさせる。
えー。
久々に「あっこスイーツ教室」開催決定!
ちびっ子連れ参加歓迎。
うちがいつやってるように子どもと作る教室。
7/23(月)朝10時からお昼まで
大人2000円、小学生1000円、3歳から500円。
スイーツ作りの後は、簡単なあっこ料理でランチタイム。
今回は
「人参のスティックドーナツ」
大きなイベントなどで、アメリカンドッグを子どもたちが欲しがるので、畑の人参と手作りの生地とで作ってみた。
これが大好評!
「豆乳のアイスクリーム」
自家製の甘酒だけで甘みをつける、マクロビアイス。
食べた後の喉の渇きがない、サッパリ系。
乳製品も砂糖もナシやから当たり前なんやけど、ちゃんと美味しいアイスクリームになるよ。
特に、この季節はイベントやお祭りが多いもの。
そういう所で子どもに「アレ食べたいー!」とねだられる。
いつもいつも、「アレはね、、、。」と我慢させるばかりよりは、手作りで作ってしまおう。
申し込みは
haizaitengoku@gmail.comまで。
タグ :ジャンクフード
2012年07月16日
山口が熱い!
ツリーハウス風トリ小屋作り、後は入口のドアと柵の強化。

この壊れた建具が目についた。

こんなん。
蝶つがいは真鍮製。
金物屋が廃業した店舗が解体される時に盗って来た、蝶つがいが山ほどある。

柵もかなりしつこく入れて。早速鶏さんたちに入ってもらった。

アジアというかアフリカというか、かなり迫力のある小屋になった。

左から、五右衛門風呂、母屋、井戸(草屋根)、井戸の奥の軒に廃材ソーラーが乗ってる。

子どもたちは学校の友達と遊んで帰って来た後、「お店ごっこ」。
にこちゃんが予約の電話を入れてる。
野遊がメインで料理を作って、土歩も手伝う。
一応あっこちゃんの指導で。

昨日はメニューは決まってて、飲み物メニューだけ。

前菜は蒸しナスのユズ味噌豆乳ソース。

メインの料理はご飯とセットのプレート。
厚揚げのソテーと叩きキュウリの和えもの。
椎茸のソテーは醤油味。
今まで「居酒屋ごっこ」とか、色々やってきたけど、「美味しんぼ」読んだりして進化してる。
当然あっこちゃんの指導あっての完成度やけど、中々よかった。
こうしてキレイに盛り付けるだけで、満足度が全然違う。
たくさん作ってくれて、おかわりを用意してくれてるけど、十分満足して要らない。
量が少なくても満足するのには盛り付けって大事なんやー。
店に行かないのに、想像力を働かせて色々やるもの。
話は変わるけど、今山口の県知事選が熱い。
自然エネルギーに詳しい候補が出てて、脱原発知事が生まれるかどうかが争点になってる。
いわゆる官僚キャリアの組織固め的なやり方と、市民中心の勝手連的なやり方が見えて面白い。
http://www.dailymotion.com/video/xs0bvm_20120706-yyyyyy-yyy-yyyy-yy_news?start=3
コレはあるニュース番組での候補者の紹介。
坂本龍一氏のメッセージ
http://www.youtube.com/watch?v=MNKG-57Tb3Q&list=PL9B7DF9FB4AE7F8B2&index=1&feature=plpp_video
一昨年の夏、香川でも県知事選があった。
現職が辞めて、元キャリア官僚対現職女性県議の渡辺さと子さん。
車に「香川から初の女性県議を!」というポスター貼りまくって毎日走った。
残念ながら完敗。
それでも、16万票対11万票と惜しかった。
40%を切る投票率。
香川の有権者が80万人やから30万人ぐらいしか投票に行ってない。
てことは後の50万人の内の5万人が投票してたら勝てた。
それはいわゆる無関心層。
「選挙なんか行っても変わらない。」という空気が蔓延してる。
その空気を作ってるのこそが、今の茶番政治とそれを報じるマスコミ。
賃金引き下げ、ボーナスカットと対極的に消費をあおるテレビや広告、大型ショッピングモール。
ワーキングプアなのに、散々買わされ、忙しくて心に余裕がない。
ソコが権力者の思う壺。
そういう無関心層が増える程、自分たちに都合のいい方向に国を動かせる。
ソコから脱却するにはまず自分の解放だ。
解放され、自由になればなる程、あらゆる問題に関心が向く。
当然、こういう知事選を楽しむのには理屈じゃない。
しょうたくんは山口で全面的に選挙を手伝ってる。
そこへ若者が集まってる。
ライブも企画して、イイ感じに盛り上がってるそう。
大飯原発ゲート占拠、官邸前のデモという直接行動は他に手段がないから。
でも、この選挙への投票は合法的で最大の意思表示の手段。
「再稼働反対!」
「命が大事!」
「こどもたちが安心できる社会を!」
それには、意思表示するしかない。
「投票」と「買い物」。
この二つが大きな意思表示の手段。
投票は直接の意思表示。
買い物だって、お金を払う先の企業や団体を応援してる訳やからね。
嫌な企業のモノを買わない。
不売というのも立派な意思表示。
戦後民主主義のぬるい平和と言われて久しい。
でも、ここの所のデモでの意思表示は凄い!
それに続いてこういう地方の首長が変わる。
それこそが希望だし、それしかない。
ここまで何十年とかかって、政治も原発も構築されてきた。
急に明日から180℃変わるのは無理。
それでも、こういう希望の知事なり、政治家の卵の潜在数は凄いと思う。
一人、また一人と変わっていく。
それを支持するのが、3、11以降「今までの社会って、、、。」と気付いた一人一人。
「社会を変える。」んじゃない。
「社会が変わっていく。」のだ。
自然と。
緩やかに。
この壊れた建具が目についた。
こんなん。
蝶つがいは真鍮製。
金物屋が廃業した店舗が解体される時に盗って来た、蝶つがいが山ほどある。
柵もかなりしつこく入れて。早速鶏さんたちに入ってもらった。
アジアというかアフリカというか、かなり迫力のある小屋になった。
左から、五右衛門風呂、母屋、井戸(草屋根)、井戸の奥の軒に廃材ソーラーが乗ってる。
子どもたちは学校の友達と遊んで帰って来た後、「お店ごっこ」。
にこちゃんが予約の電話を入れてる。
野遊がメインで料理を作って、土歩も手伝う。
一応あっこちゃんの指導で。
昨日はメニューは決まってて、飲み物メニューだけ。
前菜は蒸しナスのユズ味噌豆乳ソース。
メインの料理はご飯とセットのプレート。
厚揚げのソテーと叩きキュウリの和えもの。
椎茸のソテーは醤油味。
今まで「居酒屋ごっこ」とか、色々やってきたけど、「美味しんぼ」読んだりして進化してる。
当然あっこちゃんの指導あっての完成度やけど、中々よかった。
こうしてキレイに盛り付けるだけで、満足度が全然違う。
たくさん作ってくれて、おかわりを用意してくれてるけど、十分満足して要らない。
量が少なくても満足するのには盛り付けって大事なんやー。
店に行かないのに、想像力を働かせて色々やるもの。
話は変わるけど、今山口の県知事選が熱い。
自然エネルギーに詳しい候補が出てて、脱原発知事が生まれるかどうかが争点になってる。
いわゆる官僚キャリアの組織固め的なやり方と、市民中心の勝手連的なやり方が見えて面白い。
http://www.dailymotion.com/video/xs0bvm_20120706-yyyyyy-yyy-yyyy-yy_news?start=3
コレはあるニュース番組での候補者の紹介。
坂本龍一氏のメッセージ
http://www.youtube.com/watch?v=MNKG-57Tb3Q&list=PL9B7DF9FB4AE7F8B2&index=1&feature=plpp_video
一昨年の夏、香川でも県知事選があった。
現職が辞めて、元キャリア官僚対現職女性県議の渡辺さと子さん。
車に「香川から初の女性県議を!」というポスター貼りまくって毎日走った。
残念ながら完敗。
それでも、16万票対11万票と惜しかった。
40%を切る投票率。
香川の有権者が80万人やから30万人ぐらいしか投票に行ってない。
てことは後の50万人の内の5万人が投票してたら勝てた。
それはいわゆる無関心層。
「選挙なんか行っても変わらない。」という空気が蔓延してる。
その空気を作ってるのこそが、今の茶番政治とそれを報じるマスコミ。
賃金引き下げ、ボーナスカットと対極的に消費をあおるテレビや広告、大型ショッピングモール。
ワーキングプアなのに、散々買わされ、忙しくて心に余裕がない。
ソコが権力者の思う壺。
そういう無関心層が増える程、自分たちに都合のいい方向に国を動かせる。
ソコから脱却するにはまず自分の解放だ。
解放され、自由になればなる程、あらゆる問題に関心が向く。
当然、こういう知事選を楽しむのには理屈じゃない。
しょうたくんは山口で全面的に選挙を手伝ってる。
そこへ若者が集まってる。
ライブも企画して、イイ感じに盛り上がってるそう。
大飯原発ゲート占拠、官邸前のデモという直接行動は他に手段がないから。
でも、この選挙への投票は合法的で最大の意思表示の手段。
「再稼働反対!」
「命が大事!」
「こどもたちが安心できる社会を!」
それには、意思表示するしかない。
「投票」と「買い物」。
この二つが大きな意思表示の手段。
投票は直接の意思表示。
買い物だって、お金を払う先の企業や団体を応援してる訳やからね。
嫌な企業のモノを買わない。
不売というのも立派な意思表示。
戦後民主主義のぬるい平和と言われて久しい。
でも、ここの所のデモでの意思表示は凄い!
それに続いてこういう地方の首長が変わる。
それこそが希望だし、それしかない。
ここまで何十年とかかって、政治も原発も構築されてきた。
急に明日から180℃変わるのは無理。
それでも、こういう希望の知事なり、政治家の卵の潜在数は凄いと思う。
一人、また一人と変わっていく。
それを支持するのが、3、11以降「今までの社会って、、、。」と気付いた一人一人。
「社会を変える。」んじゃない。
「社会が変わっていく。」のだ。
自然と。
緩やかに。
タグ :知事選
2012年07月15日
一家総出の作業になった
朝一番に子どもたちが、簡易トリ小屋に駆けつけると!

まだ温かい生みたて卵ーーー。
にこちゃんは取れなくて残念。

昨日は何と、あっこちゃんも参入。
あっこスイーツを高松に卸すのを辞めて余裕が出来たそう。
今は善通寺の自然食品店「ポパイくん」の受注生産と出店だけ。
毎週毎週、新たなお菓子の開発やら、徹夜仕事での生産(ラッピングやポップ作りも)に明け暮れてたからね。
重要はあるし、「他にないものやから、求めてる人にはできるだけ提供したい。」と言い続けてたけど、、、。
「やっぱり、畑作業や子どもたちと一緒に手作りする生活を優先したい。」と。
よかったねー。
いかに稼ぐか?よりも、いかに使わないか?を念頭に置いた生活。
月に10万もあったら余る。
家賃、借金、ローン、光熱費がない生活。
ハッキリ言って、月に5万でも貯えが減るということはない。
安定した収入は皆無なので、何か買う時に「ホンマにコレ要るんか?」とトコトン考える。
要らないモノは絶対に買わない。
廃材利用だったり、自作できるもの、解体現場で盗ってこれるもので十分事足りる。
今回のトリ小屋作りに関しても、材料は何一つ買ってない。
買ったものと言えばビスぐらい。
僕は鶏が卵を生む小さな小屋作り。
鶏は地面から高い所で、少し暗い箱があると自然とそこへ生む。

廃材の家作りと並行して、井戸を掘った。
その時に出た粘土。

枯れ草と水でグチャグチャに混ぜて。

棟の部分に塗り付けた。

その上にも屋根を設ける。
廃材天国内でいらない木を伐採したのが2、3本あった。
何となく屋根っぽくくっつける。

畳やの廃材+廃ビニールで完成。
ツリーハウス風トリ小屋!

内側はこんなん。

昨日は彼は午前中は気分が乗らずにやらなくて、午後は学校の友達の家に遊びに行ってた。
5時過ぎて帰ってきてから、超やる気でやりだした。
子どもは気まぐれ。
「一回やる言うたんやから、やり続けんといかん!」とは絶対に言わない。
僕はずっとやってる。
「やらせてー。」と来たら、「どうぞ。」と言うだけ。
やりたかったらやったらええし、辞めたくなったら無理しない方がいい。

土歩も一人で、丸太を押さえながら片手でインパクト持ってビスを打ちこむのは大変。
それでも前の日はやってたけどね。
昨日はあっこちゃんと二人一組、インパクト2台体制で楽に出来てた。

お陰で僕はどんどんディティールに凝る。
内部に雨が入らないように、着物の古いのの中に廃ビニールを張ってある。

この、鶏が卵を生むスペースと雨宿りする所は出来た。
後は外の柵を強化するのと、入口のドアぐらいかな。

晩ご飯はコレ!
これほど卵ご飯を喜ぶ子どもも少ないんちゃうかなー。
滅多に買わないんで、遠足の時のお弁当とか特別の時だけやったからね。

あっこちゃんと子どもたちは夕方手分けして、風呂焚きにステンレスカマドでの料理。
残り物を入れた、簡単餃子。
生地は手打ちうどんの時の残ったのを冷凍してたやつ。

テキトーに作っても何とか餃子っぽくはなる。

それと、何と言うても生のキュウリが美味い。
労働で汗びっしょりかいた後には最高!
この手作りの最高料理もエアコンの効いた店でかしこまって出て来たって、美味しさが半減すると言うもの。
一日の労働の後、菜園から収穫、薪で料理して、手作りの〇〇と!
これがセット。
この感動は実践しないと味わえないぞ。
もちろん、無理してするこたあない。
やりたい奴だけやればいい!
「やりたくても出来ない。」なんてことは世の中に存在しない。
「やりたくないからしない。」というのが的確な日本語。
モシクハ、「いつかやりたいんよねー、と言っていたいから言う。」とか。
自分の意思と、自分の選択で!
まだ温かい生みたて卵ーーー。
にこちゃんは取れなくて残念。
昨日は何と、あっこちゃんも参入。
あっこスイーツを高松に卸すのを辞めて余裕が出来たそう。
今は善通寺の自然食品店「ポパイくん」の受注生産と出店だけ。
毎週毎週、新たなお菓子の開発やら、徹夜仕事での生産(ラッピングやポップ作りも)に明け暮れてたからね。
重要はあるし、「他にないものやから、求めてる人にはできるだけ提供したい。」と言い続けてたけど、、、。
「やっぱり、畑作業や子どもたちと一緒に手作りする生活を優先したい。」と。
よかったねー。
いかに稼ぐか?よりも、いかに使わないか?を念頭に置いた生活。
月に10万もあったら余る。
家賃、借金、ローン、光熱費がない生活。
ハッキリ言って、月に5万でも貯えが減るということはない。
安定した収入は皆無なので、何か買う時に「ホンマにコレ要るんか?」とトコトン考える。
要らないモノは絶対に買わない。
廃材利用だったり、自作できるもの、解体現場で盗ってこれるもので十分事足りる。
今回のトリ小屋作りに関しても、材料は何一つ買ってない。
買ったものと言えばビスぐらい。
僕は鶏が卵を生む小さな小屋作り。
鶏は地面から高い所で、少し暗い箱があると自然とそこへ生む。
廃材の家作りと並行して、井戸を掘った。
その時に出た粘土。
枯れ草と水でグチャグチャに混ぜて。
棟の部分に塗り付けた。
その上にも屋根を設ける。
廃材天国内でいらない木を伐採したのが2、3本あった。
何となく屋根っぽくくっつける。
畳やの廃材+廃ビニールで完成。
ツリーハウス風トリ小屋!
内側はこんなん。
昨日は彼は午前中は気分が乗らずにやらなくて、午後は学校の友達の家に遊びに行ってた。
5時過ぎて帰ってきてから、超やる気でやりだした。
子どもは気まぐれ。
「一回やる言うたんやから、やり続けんといかん!」とは絶対に言わない。
僕はずっとやってる。
「やらせてー。」と来たら、「どうぞ。」と言うだけ。
やりたかったらやったらええし、辞めたくなったら無理しない方がいい。
土歩も一人で、丸太を押さえながら片手でインパクト持ってビスを打ちこむのは大変。
それでも前の日はやってたけどね。
昨日はあっこちゃんと二人一組、インパクト2台体制で楽に出来てた。
お陰で僕はどんどんディティールに凝る。
内部に雨が入らないように、着物の古いのの中に廃ビニールを張ってある。
この、鶏が卵を生むスペースと雨宿りする所は出来た。
後は外の柵を強化するのと、入口のドアぐらいかな。
晩ご飯はコレ!
これほど卵ご飯を喜ぶ子どもも少ないんちゃうかなー。
滅多に買わないんで、遠足の時のお弁当とか特別の時だけやったからね。
あっこちゃんと子どもたちは夕方手分けして、風呂焚きにステンレスカマドでの料理。
残り物を入れた、簡単餃子。
生地は手打ちうどんの時の残ったのを冷凍してたやつ。
テキトーに作っても何とか餃子っぽくはなる。
それと、何と言うても生のキュウリが美味い。
労働で汗びっしょりかいた後には最高!
この手作りの最高料理もエアコンの効いた店でかしこまって出て来たって、美味しさが半減すると言うもの。
一日の労働の後、菜園から収穫、薪で料理して、手作りの〇〇と!
これがセット。
この感動は実践しないと味わえないぞ。
もちろん、無理してするこたあない。
やりたい奴だけやればいい!
「やりたくても出来ない。」なんてことは世の中に存在しない。
「やりたくないからしない。」というのが的確な日本語。
モシクハ、「いつかやりたいんよねー、と言っていたいから言う。」とか。
自分の意思と、自分の選択で!
タグ :トリ小屋
2012年07月14日
トリ小屋完成を見ずに、もう鶏さん来た!
トリ小屋作り2日目。
朝起きてすぐ、野遊も土歩も「トリ小屋作ろー!」と大張りきり。
昨日の朝、「今日一日あれば出来るよな。」と思って、県内の自然養鶏の生産者の方に電話。
「2、3羽でいいんで、鶏を分けて欲しいんですけど。」
「明日は予定があって、ダメやけど今日の夕方ならいいよ。」と。
「じゃあ、今日お願いします!」と即決。
この方は「自然卵養鶏法」の中島正さんの理論に基づいて実践されてる。
「自然養鶏」=「中島正」
「自然農法」=「福岡正信」のような、創設者。
中島正さんの著書には「都市を滅ぼせ」という名著がある。
何十年も前から脱原発なり、脱バビロンシステムを唱えられてる。
「自然養鶏」の定義は概ね
「平飼い」(広々とした鶏舎の地面で飼う、一坪10羽未満)
「自家製飼料」(クズ米、米ぬか、魚粉、牡蠣ガラなどを使い、抗生物質や女性ホルモン入りの配合飼料は使わない)
ゲージでギュウ詰めにして、ストレスで病気になるから餌に抗生物質を入れるという、経済効率一辺倒の飼い方とは全く別。
今の養鶏場は鶏インフルエンザを生み、数十万羽の鶏を生き埋めにした「アサダ農産」とどこも似てる。
ウインドウレス(窓ナシ)、24時間点灯(鶏は寝ないで餌を食べ続ける)、エアコンで温度管理、餌やり、採卵はベルトコンベアのオートメーション。
7階建てのゲージで、40㎝ぐらいの仕切りに2羽入れられてる。
その理由は動けないから、食べる事と卵を産むことだけに特化させるため!?
どこも、数万~数十万という単位。
よくあれから鶏インフルエンザ出ないと思うけど、役所からは消毒、殺菌という指導が徹底されてるそう。
卵ってアトピーの的のようなイメージがあるけど、それは不自然卵の中の化学物質に反応してるんやと思う。
スーパーの卵で平飼いの自然卵は滅多とみかけない。
プレミアム卵で有名な「ヨード卵光」のようにゲージ飼い、配合飼料だけどヨードを入れてあるというのは全然違う。
DHA配合とか、名前だけの「大自然卵」とかばかり。
「ヨード卵光」は変にブランド化して高いので別として、それ以外は値段が目安。
10個で400円から500円。
このぐらいが平飼いで飼料にもこだわった卵の平均値。
産直や自然食品屋に行かないとね。
普段、ウチでは肉や卵を常食しないけど、いいものをたまに食べるのは問題ない。
その判別法は「飼い方」と「餌」。
不自然な環境で、薬漬けにされる動物虐待を支持するのも嫌やし。
虐待とは命の尊厳を無視する、経済システムに組み込むこと。

腰袋つけて、インパクトでビス打つ。
野遊は随分上手いけど、土歩もかなり慣れてきた。
荒く枠を作れば金網張ったらええかなと思ってたけど、ちびっ子の活躍ぶりにオール丸太で作ることにした。
前日に横に入れた丸太に縦の格子を入れていく。
途中からの雨で合羽来ての作業。
それから、瞬間的やったけど、凄い豪雨で家の周りを奔走。
雨に当たるといけない物をしまったり、樋や溝の点検。
川のように流れる溝さらえが楽しい。

小雨になったんで、作業再会。
電動工具は使えないぐらいには降ってたんで、針金で細い丸太を留める作戦に変更。
雨で思うように進まなかったのもあるけど、夕方までには間に合いそうにない。
当初はパパッと手軽に作ろうと取り掛かったトリ小屋作り。
ちびっ子たちのモチベーションの高さに触発されて、思わず僕もディティールに入り出したのもある。
やってるウチに面白くなって変更に次ぐ変更ってのはしょっちゅう。
そこれもこれも、設計図ナシ、計画性ナシ、ある廃材での「直感&即興」の廃材建築ならでは。

どっちにせよ、鶏は夕方引き取りに行く。
なので、本小屋が完成するまでの仮小屋を作る。
パレット持って来てビスで留める。

塩ビの廃材ナミ板置いて10分もかけずに完成!
こういう急展開にも、廃材建築はめっぽう強い。

夕方、満濃町の養鶏家の鶏舎を訪ねた。
定番の平飼いのスタイル。

別の場所ではヒヨコが育てられてた。

PHFコーン(ポストハーベストフリー)、米ぬか、煮干し、牡蠣ガラ、EMボカシという自家配合の飼料。
魚粉じゃなく、煮干しというのが凄い!
伊吹島まで行って、クズのいりこを分けてもらえるように交渉したんだとか。
こういう餌だと、ヒヨコは半年近くかけて大人になる。
大手の完全配合飼料だと、肉にする鶏だと2ヶ月で出荷。
一軒目の廃材ハウスではヒヨコから飼ってたから分かるけど、2カ月言うたらまだピヨピヨ言うてるからねー。

2、3羽の予定が、「5羽ぐらい持って帰ったら。」と。
う~ん、あっこちゃんがまた色々言うかな、、、。
どっちにせよ、鶏さん来たんやからこっちのもん。
卵産んでくれるし、殺したての最高の肉も食べられるし!!!
餌やりは最近の風呂焚き同様、当番表を作って、野遊と土歩が交代でやろうとミーティングが為されてるみたいやし。
子どもたちも、僕がやるのを見て捌き方なんかあっという間に覚えるやろしね。
朝起きてすぐ、野遊も土歩も「トリ小屋作ろー!」と大張りきり。
昨日の朝、「今日一日あれば出来るよな。」と思って、県内の自然養鶏の生産者の方に電話。
「2、3羽でいいんで、鶏を分けて欲しいんですけど。」
「明日は予定があって、ダメやけど今日の夕方ならいいよ。」と。
「じゃあ、今日お願いします!」と即決。
この方は「自然卵養鶏法」の中島正さんの理論に基づいて実践されてる。
「自然養鶏」=「中島正」
「自然農法」=「福岡正信」のような、創設者。
中島正さんの著書には「都市を滅ぼせ」という名著がある。
何十年も前から脱原発なり、脱バビロンシステムを唱えられてる。
「自然養鶏」の定義は概ね
「平飼い」(広々とした鶏舎の地面で飼う、一坪10羽未満)
「自家製飼料」(クズ米、米ぬか、魚粉、牡蠣ガラなどを使い、抗生物質や女性ホルモン入りの配合飼料は使わない)
ゲージでギュウ詰めにして、ストレスで病気になるから餌に抗生物質を入れるという、経済効率一辺倒の飼い方とは全く別。
今の養鶏場は鶏インフルエンザを生み、数十万羽の鶏を生き埋めにした「アサダ農産」とどこも似てる。
ウインドウレス(窓ナシ)、24時間点灯(鶏は寝ないで餌を食べ続ける)、エアコンで温度管理、餌やり、採卵はベルトコンベアのオートメーション。
7階建てのゲージで、40㎝ぐらいの仕切りに2羽入れられてる。
その理由は動けないから、食べる事と卵を産むことだけに特化させるため!?
どこも、数万~数十万という単位。
よくあれから鶏インフルエンザ出ないと思うけど、役所からは消毒、殺菌という指導が徹底されてるそう。
卵ってアトピーの的のようなイメージがあるけど、それは不自然卵の中の化学物質に反応してるんやと思う。
スーパーの卵で平飼いの自然卵は滅多とみかけない。
プレミアム卵で有名な「ヨード卵光」のようにゲージ飼い、配合飼料だけどヨードを入れてあるというのは全然違う。
DHA配合とか、名前だけの「大自然卵」とかばかり。
「ヨード卵光」は変にブランド化して高いので別として、それ以外は値段が目安。
10個で400円から500円。
このぐらいが平飼いで飼料にもこだわった卵の平均値。
産直や自然食品屋に行かないとね。
普段、ウチでは肉や卵を常食しないけど、いいものをたまに食べるのは問題ない。
その判別法は「飼い方」と「餌」。
不自然な環境で、薬漬けにされる動物虐待を支持するのも嫌やし。
虐待とは命の尊厳を無視する、経済システムに組み込むこと。
腰袋つけて、インパクトでビス打つ。
野遊は随分上手いけど、土歩もかなり慣れてきた。
荒く枠を作れば金網張ったらええかなと思ってたけど、ちびっ子の活躍ぶりにオール丸太で作ることにした。
前日に横に入れた丸太に縦の格子を入れていく。
途中からの雨で合羽来ての作業。
それから、瞬間的やったけど、凄い豪雨で家の周りを奔走。
雨に当たるといけない物をしまったり、樋や溝の点検。
川のように流れる溝さらえが楽しい。
小雨になったんで、作業再会。
電動工具は使えないぐらいには降ってたんで、針金で細い丸太を留める作戦に変更。
雨で思うように進まなかったのもあるけど、夕方までには間に合いそうにない。
当初はパパッと手軽に作ろうと取り掛かったトリ小屋作り。
ちびっ子たちのモチベーションの高さに触発されて、思わず僕もディティールに入り出したのもある。
やってるウチに面白くなって変更に次ぐ変更ってのはしょっちゅう。
そこれもこれも、設計図ナシ、計画性ナシ、ある廃材での「直感&即興」の廃材建築ならでは。
どっちにせよ、鶏は夕方引き取りに行く。
なので、本小屋が完成するまでの仮小屋を作る。
パレット持って来てビスで留める。
塩ビの廃材ナミ板置いて10分もかけずに完成!
こういう急展開にも、廃材建築はめっぽう強い。
夕方、満濃町の養鶏家の鶏舎を訪ねた。
定番の平飼いのスタイル。
別の場所ではヒヨコが育てられてた。
PHFコーン(ポストハーベストフリー)、米ぬか、煮干し、牡蠣ガラ、EMボカシという自家配合の飼料。
魚粉じゃなく、煮干しというのが凄い!
伊吹島まで行って、クズのいりこを分けてもらえるように交渉したんだとか。
こういう餌だと、ヒヨコは半年近くかけて大人になる。
大手の完全配合飼料だと、肉にする鶏だと2ヶ月で出荷。
一軒目の廃材ハウスではヒヨコから飼ってたから分かるけど、2カ月言うたらまだピヨピヨ言うてるからねー。
2、3羽の予定が、「5羽ぐらい持って帰ったら。」と。
う~ん、あっこちゃんがまた色々言うかな、、、。
どっちにせよ、鶏さん来たんやからこっちのもん。
卵産んでくれるし、殺したての最高の肉も食べられるし!!!
餌やりは最近の風呂焚き同様、当番表を作って、野遊と土歩が交代でやろうとミーティングが為されてるみたいやし。
子どもたちも、僕がやるのを見て捌き方なんかあっという間に覚えるやろしね。
タグ :自然卵
2012年07月13日
トリ小屋作ろっと
急に思い立った。
トリ小屋作ろ!
飼ってた鶏が居なくなってもう3年ぐらい。
一軒目の廃材ハウスの時は最大20羽も飼ってた。
よく絞めて食べてた。
殺したての肝を生で食べるのが最高に美味い!
またいつかは飼おうと思いながら、「ちゃんと世話するの?」、「出かける時はどうするの?」とあっこちゃんに言われて、「そやなー。」と躊躇してた。
実際、卵って滅多と食べないし。
月に一回ぐらい10個で400円の平飼いの自然養鶏の生産者の卵を自然食品屋で買うぐらい。
無けりゃないで別にいいんやけどね。
まあ、子どもたちは欲しがるし、たまにと言うても400円という高価なものやし。
やっぱり自分ちで飼うのがいいという結論。
で、思いついた!
2、3羽だけ飼って、長期の旅とかで留守にする前に全部絞める。
帰ってきたらまた新たなヒヨコから飼う。
ンンーー!
いい思いつき!

コレが材料。
焚きものとして持って来てて、積み込みもしてくれる造園屋の廃材。
ソコソコ長いのがあるんで、十分使える。
前の鶏小屋は自転車置き場にしたんで、新たに作る。
「トリ小屋作りしたい人集合ー!」の号令で「ハイハイハイハーイ!」とやりたがる子どもたち。
今回の小屋は出来るだけ簡素な仕様。
屋根も最小限。
イメージとしてはツリーハウス型トリ小屋。
出来るだけ放し飼いに近いタイプ。
鶏が野生化してるイメージ。
屋久島の旅の途中に寄った、内子町の池田家の鶏なんか普通に生えてる木の枝にとまって寝てたし。

このクスの木の周りに作ることに決定。
大工さんの廃材で杭を作って打ちこむ。
子どもたちはバールで角材の釘を抜いてる。

柱を立てて、子どもたちが持ってくれてる間に杭にビス留めする。
長さも計らなければ、水平も垂直も見ないんで、一瞬で出来る。
超スーパー速い。

一人が持って、一人が打ちこむ。

土歩も大かた出来るようになってきた。

その杭に細い丸太をビス留めしていく。
野遊は普段から毎日のように、鋸や金槌使ってるし、インパクトドライバーにも慣れてる。
75㎜のビスなら下穴ナシで打ちこめる。
もう子どもたちが大活躍!
最近あっこちゃんと「居候がおらんで気楽よねー。」としょっちゅう言ってる。
ヘタな居候なんかよりも、ウチの子どもたちの方がよっぽど心得てるし。
ここの所「突然ですみません。」という居候は断ってる。
「ちょっと廃材の家を見学がてらに居候。」とかもブッブー。
メールで何度もやりとりする「面接」をクリアした者はOKにしてる。
その面接のハードルを更に上げてもいいと思ってる。
よっぽど、こういう生活に向けて勉強や経験を重ねてないとねー。
ここで一から「福岡さんの本読んだら。」とか、もう嫌やし。
ここは研修施設でもなければ、NPO法人でもない。
一つの家庭やからねー。
そこに上がり込んでこの素晴らしい生活を学びたいのなら並大抵の覚悟では来れない!

こんな感じ。
この枠に網を張る。
最終的には放し飼いのイメージなんで、出来るだけラフに作る。
素晴らしい仕事の後は素晴らしい晩ご飯。
汗も山ほどかいてビールも美味い!

豆腐を揚げて、野菜と混ぜた甘酢あん。
お昼に乾麺のうどんを食べた時に残った出汁や冷蔵庫に残ってる浸けダレなんかを利用する。
何種類かそういうタレが出来てくると甘酢あんになったり、カレーになったりする。

レタスもそろそろトウ立ちしそうなので毎日食べてる。
くぼさんの豆腐シリーズ「ごま豆腐」登場。
たっぷりの純正のゴマ油でカリカリに揚げたちりめんじゃこ乗せ。
最後に醤油を振りかける。
ゴマ豆腐と言っても、ゴマと本クズのネットリゴマ豆腐じゃない。
正確にはゴマ入り豆腐。
それでも濃厚で生野菜とよく合う。
トリ小屋作ろ!
飼ってた鶏が居なくなってもう3年ぐらい。
一軒目の廃材ハウスの時は最大20羽も飼ってた。
よく絞めて食べてた。
殺したての肝を生で食べるのが最高に美味い!
またいつかは飼おうと思いながら、「ちゃんと世話するの?」、「出かける時はどうするの?」とあっこちゃんに言われて、「そやなー。」と躊躇してた。
実際、卵って滅多と食べないし。
月に一回ぐらい10個で400円の平飼いの自然養鶏の生産者の卵を自然食品屋で買うぐらい。
無けりゃないで別にいいんやけどね。
まあ、子どもたちは欲しがるし、たまにと言うても400円という高価なものやし。
やっぱり自分ちで飼うのがいいという結論。
で、思いついた!
2、3羽だけ飼って、長期の旅とかで留守にする前に全部絞める。
帰ってきたらまた新たなヒヨコから飼う。
ンンーー!
いい思いつき!
コレが材料。
焚きものとして持って来てて、積み込みもしてくれる造園屋の廃材。
ソコソコ長いのがあるんで、十分使える。
前の鶏小屋は自転車置き場にしたんで、新たに作る。
「トリ小屋作りしたい人集合ー!」の号令で「ハイハイハイハーイ!」とやりたがる子どもたち。
今回の小屋は出来るだけ簡素な仕様。
屋根も最小限。
イメージとしてはツリーハウス型トリ小屋。
出来るだけ放し飼いに近いタイプ。
鶏が野生化してるイメージ。
屋久島の旅の途中に寄った、内子町の池田家の鶏なんか普通に生えてる木の枝にとまって寝てたし。
このクスの木の周りに作ることに決定。
大工さんの廃材で杭を作って打ちこむ。
子どもたちはバールで角材の釘を抜いてる。
柱を立てて、子どもたちが持ってくれてる間に杭にビス留めする。
長さも計らなければ、水平も垂直も見ないんで、一瞬で出来る。
超スーパー速い。
一人が持って、一人が打ちこむ。
土歩も大かた出来るようになってきた。
その杭に細い丸太をビス留めしていく。
野遊は普段から毎日のように、鋸や金槌使ってるし、インパクトドライバーにも慣れてる。
75㎜のビスなら下穴ナシで打ちこめる。
もう子どもたちが大活躍!
最近あっこちゃんと「居候がおらんで気楽よねー。」としょっちゅう言ってる。
ヘタな居候なんかよりも、ウチの子どもたちの方がよっぽど心得てるし。
ここの所「突然ですみません。」という居候は断ってる。
「ちょっと廃材の家を見学がてらに居候。」とかもブッブー。
メールで何度もやりとりする「面接」をクリアした者はOKにしてる。
その面接のハードルを更に上げてもいいと思ってる。
よっぽど、こういう生活に向けて勉強や経験を重ねてないとねー。
ここで一から「福岡さんの本読んだら。」とか、もう嫌やし。
ここは研修施設でもなければ、NPO法人でもない。
一つの家庭やからねー。
そこに上がり込んでこの素晴らしい生活を学びたいのなら並大抵の覚悟では来れない!
こんな感じ。
この枠に網を張る。
最終的には放し飼いのイメージなんで、出来るだけラフに作る。
素晴らしい仕事の後は素晴らしい晩ご飯。
汗も山ほどかいてビールも美味い!
豆腐を揚げて、野菜と混ぜた甘酢あん。
お昼に乾麺のうどんを食べた時に残った出汁や冷蔵庫に残ってる浸けダレなんかを利用する。
何種類かそういうタレが出来てくると甘酢あんになったり、カレーになったりする。
レタスもそろそろトウ立ちしそうなので毎日食べてる。
くぼさんの豆腐シリーズ「ごま豆腐」登場。
たっぷりの純正のゴマ油でカリカリに揚げたちりめんじゃこ乗せ。
最後に醤油を振りかける。
ゴマ豆腐と言っても、ゴマと本クズのネットリゴマ豆腐じゃない。
正確にはゴマ入り豆腐。
それでも濃厚で生野菜とよく合う。
タグ :トリ小屋
2012年07月12日
絶え間ない流れでイケイケの連続生活
朝一番、解体屋の社長から電話。
「以前にお聞きしていました廃瓦を持って行きます。」

とりあえず4t車に一杯。
廃材の家の大屋根(80坪)を葺き替えてる材料。
以前持って来てもらってるのでは足りないなー、と思ってたんで電話して頼んでた。
もうちょい要るかな。

葺き替え中の廃材の家。
左から、離れ(ウロコ)、五右衛門風呂、母屋(この奥が二階の工房へと続いてる)、手掘りの井戸(草屋根)。

今はこんな状態。
農業用ビニール(レタスのトンネルマルチ用)の廃材で防水して、トラックシートで養生。
その上に廃瓦をグチャグチャに置いてるだけ。

先日のアイドリングアップとオイル交換に続き、天ぷら油のフィルター交換に挑戦。
日産のキャラバン用のオイルフィルターが合う。

最初についてたのを外して。

これが天ぷら油を温めてサラサラにするための「熱交換器」。
単純な部品。
その下に取り付ける。
ここまでは簡単。

もちろん、フィルターには天ぷら油を満たしておくけど、少々はエアが入る。
ディーゼルにエア噛みは厳禁。
でも、WVOの天ぷらカーは軽油と天ぷら油の二系統。
噴射ポンプの中に燃料が残ってるうちに軽油と天ぷら油を切り替え切り替えやってるウチに透明のチューブの中のエアが抜けてくるのが目認できる。

あっこちゃんが菜園の自生してるつるむさきを間引いた。

大きいのだけを残してもこんなにある。
いつも自然に種を落ちたのが自生してるけど、今年は特に多い。

ここはルッコラとゴーヤが自生してるコーナー。
不耕起では文字通り耕さないので、自生する率が高い。

ゴーヤは廃材の支柱が常設されてるコーナーへと移植する。
子どもが食べないけど、大人は盛夏には欲しい一品。
滝のような汗をかく時期に、生で酢味噌和えが最高。

ハラさんが深谷ネギを大量に持って来てくれた。
一気に食べきれないので、土を被せて活けておく。
生芋コンニャク、キュウリも一緒に頂いた。
大量に頂いた野菜に「困る」という発想は禁物。
いかにその大量の野菜を使いこなすか?
そこがまた楽しい。

つるむささきはサッと茹でてゴマ和え。
子どもたちに大人気。

コンニャクは手でちぎって、ネギとお土産に頂いた鰹の生節とで炒める。
濃い目の醤油味が玄米ご飯にもビールにも合う。

また、くぼさんの豆腐の冷や奴やけど、前の日のナスのエスニック風の漬け液をかけた。
本醸造の純正醤油にショウガとネギだけも最高やけど、これもまた最高!
素材と調味料がいいので美味しくなるしかない。
ニンニク、ショウガ、ナンプラー、酢、練りゴマという、「夏が来たーーー!」という味。
畑作業→収穫→掃除→料理→前の日の残り物利用。
昨日はこれに頂き物も加わった。
夕方、料理に取り掛かるまでメニューなんか決めてなくても、この連続性によって自然に決まる。
「まず材料ありき」
このコンセプトは廃材建築も自給畑&手作り料理も全く一緒。
目の前の材料からの閃きで、「おっ、コレ使お!」という流れの連続。
イチイチ悩んだり、クヨクヨ考えたりのないスムーズでストレートな生活だ。
自分の中に抵抗勢力がないからイケイケでグングン進む。
やればやる程、経験も増して更に加速する。
バックボーンには「自分の芯からやりたい事」と「自然か不自然か」とか、ちょっとした目安を外さないことが大切。
宇宙はそういうメカニズムで動いてるみたいやでー!
「以前にお聞きしていました廃瓦を持って行きます。」
とりあえず4t車に一杯。
廃材の家の大屋根(80坪)を葺き替えてる材料。
以前持って来てもらってるのでは足りないなー、と思ってたんで電話して頼んでた。
もうちょい要るかな。
葺き替え中の廃材の家。
左から、離れ(ウロコ)、五右衛門風呂、母屋(この奥が二階の工房へと続いてる)、手掘りの井戸(草屋根)。
今はこんな状態。
農業用ビニール(レタスのトンネルマルチ用)の廃材で防水して、トラックシートで養生。
その上に廃瓦をグチャグチャに置いてるだけ。
先日のアイドリングアップとオイル交換に続き、天ぷら油のフィルター交換に挑戦。
日産のキャラバン用のオイルフィルターが合う。
最初についてたのを外して。
これが天ぷら油を温めてサラサラにするための「熱交換器」。
単純な部品。
その下に取り付ける。
ここまでは簡単。
もちろん、フィルターには天ぷら油を満たしておくけど、少々はエアが入る。
ディーゼルにエア噛みは厳禁。
でも、WVOの天ぷらカーは軽油と天ぷら油の二系統。
噴射ポンプの中に燃料が残ってるうちに軽油と天ぷら油を切り替え切り替えやってるウチに透明のチューブの中のエアが抜けてくるのが目認できる。
あっこちゃんが菜園の自生してるつるむさきを間引いた。
大きいのだけを残してもこんなにある。
いつも自然に種を落ちたのが自生してるけど、今年は特に多い。
ここはルッコラとゴーヤが自生してるコーナー。
不耕起では文字通り耕さないので、自生する率が高い。
ゴーヤは廃材の支柱が常設されてるコーナーへと移植する。
子どもが食べないけど、大人は盛夏には欲しい一品。
滝のような汗をかく時期に、生で酢味噌和えが最高。
ハラさんが深谷ネギを大量に持って来てくれた。
一気に食べきれないので、土を被せて活けておく。
生芋コンニャク、キュウリも一緒に頂いた。
大量に頂いた野菜に「困る」という発想は禁物。
いかにその大量の野菜を使いこなすか?
そこがまた楽しい。
つるむささきはサッと茹でてゴマ和え。
子どもたちに大人気。
コンニャクは手でちぎって、ネギとお土産に頂いた鰹の生節とで炒める。
濃い目の醤油味が玄米ご飯にもビールにも合う。
また、くぼさんの豆腐の冷や奴やけど、前の日のナスのエスニック風の漬け液をかけた。
本醸造の純正醤油にショウガとネギだけも最高やけど、これもまた最高!
素材と調味料がいいので美味しくなるしかない。
ニンニク、ショウガ、ナンプラー、酢、練りゴマという、「夏が来たーーー!」という味。
畑作業→収穫→掃除→料理→前の日の残り物利用。
昨日はこれに頂き物も加わった。
夕方、料理に取り掛かるまでメニューなんか決めてなくても、この連続性によって自然に決まる。
「まず材料ありき」
このコンセプトは廃材建築も自給畑&手作り料理も全く一緒。
目の前の材料からの閃きで、「おっ、コレ使お!」という流れの連続。
イチイチ悩んだり、クヨクヨ考えたりのないスムーズでストレートな生活だ。
自分の中に抵抗勢力がないからイケイケでグングン進む。
やればやる程、経験も増して更に加速する。
バックボーンには「自分の芯からやりたい事」と「自然か不自然か」とか、ちょっとした目安を外さないことが大切。
宇宙はそういうメカニズムで動いてるみたいやでー!
2012年07月11日
手巻き生春巻きパーティー
ウロコの柱2本とも完成。

二本目に入って慣れもあるし、益々カオス状態がエスカレートしてきた。

上に行くほど、濃く複雑になる。
別に決まりはないし、廃材はいくらでもあるし、ビニールが隠れたらいいだけ。
作業しても一本目の半分ぐらいの時間で出来る。
「ここはどうしよー?」とか考えたり迷ったりがなければ速い。
廃材建築においてスピードって大事。
いつまでもチマチマ時間がかかって自分が飽きるのは何としても避けたい。
タダの廃材を惜しみなく乱暴に使って、サクサクと小気味よく進める。
このワクワクする爽快さで、疲れたりしない。
疲れって、肉体的なものよりも、気苦労みたいな精神的なものの方が大きい。
ノルマ、人からどう思われるか?お金、時間が介在する仕事では常にそれが付きまとう。
もちろんウチも色々頼まれるけど、いい意味でそれを乗り越える楽しさもまたアリやとも思うけど。
要するに人から言われた通りの事をこなすルーティーンワークじゃなく、こっちの考えやアイデアを提案できるクリエイト性の高い仕事で、時間にも余裕があるという条件が必要。
無理に仕事を作るんじゃなく、ホントに必要とされてる仕事をする。
別にお金になるならないだけじゃなく、田植えも車のメンテも家の修理も立派な仕事。
働く=ハタ(周り)を楽にすること。
実質本位で生きることに必要な働きだ。
ソコを押さえてたら「生活できない。」なんて奇妙な日本語は生まれっこない。
金を稼いでそれで何でも買って生活するというのはロスが大きい。
5000億かけて原発作って電気を発電して遠い所まで送電線で送って、またお湯を沸かしたり、料理をしたりというロスと似てる。
そういうロスを省いてダイレクトに焚きものでお湯を沸かす。
その働きで生活はどんどんスムーズに流れる。
原発再稼働したし、鹿児島の脱原発知事も落選した。
もちろん残念やけど、クヨクヨして毎日PC眺めてたってしゃあない。
ここでは原発が動こうが、止まろうが、廃材で左ウチワの生活を続けていく。
それは誰にも止められない。

くぼさんの豆腐シリーズ「かたもめん」とニラの炒め物。
切干大根の煮物の残りを調味料代わりに混ぜたがよかった。

蒸しナスのバジル乗せ、エスニック風。
今年もバジルは調子よく出来てる。
ジェノベーゼも作って保存しよう。

生春巻きの材料。
下のレタスの横のは手作りハム。
四角の容器のはカレーの残りと切干大根の残り。
後は菜園のキュウリやシソ、トマトで彩りもバッチリ。
タレはナンプラー、甘酒、水。
大人用のは豆板醤を入れる。

デカデカに巻いて豪快に食べる!
残り物と菜園の野菜だけで簡単で美味い。
二本目に入って慣れもあるし、益々カオス状態がエスカレートしてきた。
上に行くほど、濃く複雑になる。
別に決まりはないし、廃材はいくらでもあるし、ビニールが隠れたらいいだけ。
作業しても一本目の半分ぐらいの時間で出来る。
「ここはどうしよー?」とか考えたり迷ったりがなければ速い。
廃材建築においてスピードって大事。
いつまでもチマチマ時間がかかって自分が飽きるのは何としても避けたい。
タダの廃材を惜しみなく乱暴に使って、サクサクと小気味よく進める。
このワクワクする爽快さで、疲れたりしない。
疲れって、肉体的なものよりも、気苦労みたいな精神的なものの方が大きい。
ノルマ、人からどう思われるか?お金、時間が介在する仕事では常にそれが付きまとう。
もちろんウチも色々頼まれるけど、いい意味でそれを乗り越える楽しさもまたアリやとも思うけど。
要するに人から言われた通りの事をこなすルーティーンワークじゃなく、こっちの考えやアイデアを提案できるクリエイト性の高い仕事で、時間にも余裕があるという条件が必要。
無理に仕事を作るんじゃなく、ホントに必要とされてる仕事をする。
別にお金になるならないだけじゃなく、田植えも車のメンテも家の修理も立派な仕事。
働く=ハタ(周り)を楽にすること。
実質本位で生きることに必要な働きだ。
ソコを押さえてたら「生活できない。」なんて奇妙な日本語は生まれっこない。
金を稼いでそれで何でも買って生活するというのはロスが大きい。
5000億かけて原発作って電気を発電して遠い所まで送電線で送って、またお湯を沸かしたり、料理をしたりというロスと似てる。
そういうロスを省いてダイレクトに焚きものでお湯を沸かす。
その働きで生活はどんどんスムーズに流れる。
原発再稼働したし、鹿児島の脱原発知事も落選した。
もちろん残念やけど、クヨクヨして毎日PC眺めてたってしゃあない。
ここでは原発が動こうが、止まろうが、廃材で左ウチワの生活を続けていく。
それは誰にも止められない。
くぼさんの豆腐シリーズ「かたもめん」とニラの炒め物。
切干大根の煮物の残りを調味料代わりに混ぜたがよかった。
蒸しナスのバジル乗せ、エスニック風。
今年もバジルは調子よく出来てる。
ジェノベーゼも作って保存しよう。
生春巻きの材料。
下のレタスの横のは手作りハム。
四角の容器のはカレーの残りと切干大根の残り。
後は菜園のキュウリやシソ、トマトで彩りもバッチリ。
タレはナンプラー、甘酒、水。
大人用のは豆板醤を入れる。
デカデカに巻いて豪快に食べる!
残り物と菜園の野菜だけで簡単で美味い。
タグ :生春巻き
2012年07月10日
ウロコの柱
前日の作業の続き。
廃材ソーラーの乗る、軒の柱がこれ以上腐らないように養生。

根元ののコンクリートの隙間はコーキングで塞いだので、柱全体を得意の農業用ビニールで覆う。
これで、吹き降りになっても柱には雨は当たらない。
もちろん、このままではビニールは風や日光で劣化する。
それを防ぐために何かで覆いをしないといけない。

ちょっと考えて、コレにした。
奥のパレットに積み込んだ廃材。
これはちょっと前に居候してたイッセイくんが小さく切ってくれて、キッチンの燃料用にしてる。
その中からイイ廃材を選ぶ。
後の腐りかけの廃材は子どもたちに割ってもらって、キッチンに運ぶ。

下から順に打ちつけて、ウロコ状のこんな感じになった。

結構板が厚かったのと覆う柱が細かったので、最初はやりづらいと思った。
そこはこの直感型即興作業がカバーする。
手に取った板を当ててみて、2、3回角度を変えてテキトーに打ちつける。
次の板もまた同じくテキトー。
その積み重ね。
段々と、こっちが材料と状況に慣れてくる。

しばらく作業して、離れて遠目で見るとランダムなテキトーさゆえのバラバラ感がデザインになってしまう。
デザインは別として、ビニール+廃材の板とこれで、柱に直接雨は当たらなくなった。
まあ、何年かしてこのウロコ板が腐ったらまた考える。
廃材建築の耐久性のスパンはせいぜい数年。
10年も持つようにはまず考えない。
そんな事考えると、新品のガルバリウム鋼板を買わないといけないし、なりよりこのようなクールな作業が出来ない。

雨も上がって、トマトがバッチリ採れた。
また同級生の畑料理人がズッキーニ、丸オクラ、手作りフォカッチャを持って来てくれた。
畑しながら、パスタソースの移動販売とか、田舎の民家で農家レストランとか色々アイデアを持ってる。
でも彼は、ちゃんとしたレストランの面接にも行ってる。
はてさて、どっちの路線に行くんやろねー。

ウチのトマトと、彼の野菜のコラボ。
後ろのドレシングはあっこちゃんの師匠、たま先生の塩麹ドレッシング。
先日の「オーガニックマルシェ」であっこちゃんが勉強のために買った。
このドレッシングと自家製の野菜はヤバ過ぎる美味さ!
トマトも塩や醤油でシンプルに食べてただけに、この変化にはドびっくり!!
もちろんズッキーニ、オクラとも非常に合う。
こんなに美味いものは自分で作らないとあやかれない。

キュウリもよく採れだした。
塩や味噌をつけてシンプルに食べるのから、徐々に変化させるのを楽しむ。
更にジャンジャン採れると炒め物や洋風の煮物にも使うけど、まだ早い。

これも、たま先生作の金山時味噌。
これがまた玄米と超ガッチリ合う。
青シソの上に乗せると尚最高。
ショウガやナスなどの夏野菜を入れて一年間寝かせたもの。
しかも塩分はそこまで高くないのに常温で一年保存できるとか。
発酵の成せる業か!?
でも、そこまで酸味が強い訳もないし。
作り方を聞かなければーーー。
こういう保存食も夏の終わりの散々キュウリやナスに飽きた頃に作るといい。
最初の塩だけで感動する、採れ始めの「走り」を経て、いよいよジャンジャン採れる「旬」に入った。
その旬の中でもまだ4、5本キュウリやナスが採れればそれだけで晩ご飯作りが楽しみな段階。
一通りの料理法を楽しむまではね。
今年の夏野菜は調子いいし、イタリアン、中華、エスニックと楽しみな季節やからねー。
ナスはグラタン、ラタトゥイユ、酸っぱ辛いナンプラー漬け、マーボーナスとかも。
キュウリは即席の叩きキムチ、じゃことシソ入りのキュウリ揉み、クミンとオリーブオイルでの炒め物もいい。
さあ、今日も自画杜撰生活を楽しもう!
廃材ソーラーの乗る、軒の柱がこれ以上腐らないように養生。
根元ののコンクリートの隙間はコーキングで塞いだので、柱全体を得意の農業用ビニールで覆う。
これで、吹き降りになっても柱には雨は当たらない。
もちろん、このままではビニールは風や日光で劣化する。
それを防ぐために何かで覆いをしないといけない。
ちょっと考えて、コレにした。
奥のパレットに積み込んだ廃材。
これはちょっと前に居候してたイッセイくんが小さく切ってくれて、キッチンの燃料用にしてる。
その中からイイ廃材を選ぶ。
後の腐りかけの廃材は子どもたちに割ってもらって、キッチンに運ぶ。
下から順に打ちつけて、ウロコ状のこんな感じになった。
結構板が厚かったのと覆う柱が細かったので、最初はやりづらいと思った。
そこはこの直感型即興作業がカバーする。
手に取った板を当ててみて、2、3回角度を変えてテキトーに打ちつける。
次の板もまた同じくテキトー。
その積み重ね。
段々と、こっちが材料と状況に慣れてくる。
しばらく作業して、離れて遠目で見るとランダムなテキトーさゆえのバラバラ感がデザインになってしまう。
デザインは別として、ビニール+廃材の板とこれで、柱に直接雨は当たらなくなった。
まあ、何年かしてこのウロコ板が腐ったらまた考える。
廃材建築の耐久性のスパンはせいぜい数年。
10年も持つようにはまず考えない。
そんな事考えると、新品のガルバリウム鋼板を買わないといけないし、なりよりこのようなクールな作業が出来ない。
雨も上がって、トマトがバッチリ採れた。
また同級生の畑料理人がズッキーニ、丸オクラ、手作りフォカッチャを持って来てくれた。
畑しながら、パスタソースの移動販売とか、田舎の民家で農家レストランとか色々アイデアを持ってる。
でも彼は、ちゃんとしたレストランの面接にも行ってる。
はてさて、どっちの路線に行くんやろねー。
ウチのトマトと、彼の野菜のコラボ。
後ろのドレシングはあっこちゃんの師匠、たま先生の塩麹ドレッシング。
先日の「オーガニックマルシェ」であっこちゃんが勉強のために買った。
このドレッシングと自家製の野菜はヤバ過ぎる美味さ!
トマトも塩や醤油でシンプルに食べてただけに、この変化にはドびっくり!!
もちろんズッキーニ、オクラとも非常に合う。
こんなに美味いものは自分で作らないとあやかれない。
キュウリもよく採れだした。
塩や味噌をつけてシンプルに食べるのから、徐々に変化させるのを楽しむ。
更にジャンジャン採れると炒め物や洋風の煮物にも使うけど、まだ早い。
これも、たま先生作の金山時味噌。
これがまた玄米と超ガッチリ合う。
青シソの上に乗せると尚最高。
ショウガやナスなどの夏野菜を入れて一年間寝かせたもの。
しかも塩分はそこまで高くないのに常温で一年保存できるとか。
発酵の成せる業か!?
でも、そこまで酸味が強い訳もないし。
作り方を聞かなければーーー。
こういう保存食も夏の終わりの散々キュウリやナスに飽きた頃に作るといい。
最初の塩だけで感動する、採れ始めの「走り」を経て、いよいよジャンジャン採れる「旬」に入った。
その旬の中でもまだ4、5本キュウリやナスが採れればそれだけで晩ご飯作りが楽しみな段階。
一通りの料理法を楽しむまではね。
今年の夏野菜は調子いいし、イタリアン、中華、エスニックと楽しみな季節やからねー。
ナスはグラタン、ラタトゥイユ、酸っぱ辛いナンプラー漬け、マーボーナスとかも。
キュウリは即席の叩きキムチ、じゃことシソ入りのキュウリ揉み、クミンとオリーブオイルでの炒め物もいい。
さあ、今日も自画杜撰生活を楽しもう!
タグ :廃材
2012年07月09日
お神楽
久しぶりのイイ天気だったんで、家の周りをチェックしてた。

廃材の母屋の前の大きな軒の柱。
この二本だけが電柱じゃなくて普通の梁なので松。
ちょっと腐って来つつある。

こんな感じで痩せた所に雨が入って、金槌で叩くとコンコンというまだ大丈夫な所と、ポコポコと不安な音の所がある。

廃材ソーラーの乗ってる軒。
まだ柱ごと取り換える程でもないけど、このまま放っておくとマズイ。
トタンで覆うのが手っ取り早いけど、オシャレじゃないし。
柱に漆喰を塗るのは廃材天国には上品過ぎるかな?
とか色々考える。
販売禁止になってるの劇薬の防腐剤クレオーソートも持ってはいるけど、子どもたちが頻繁に通るし菜園もある場所には使いたくない。

で、とりあえず、コーキング!
水が入るとマズイ所には、何はともあれシリコンコーク。
廃材建築とは切っても切れない素晴らしい素材。

遠目には全然気にならない。
というか気にしない。
まず全体が廃材でグチャッとした雰囲気なのと、こんなに細かい所だけを普段マジマジと見たりしない。
もちろん、この柱二本そのものが常に横降りの雨に晒されないように何かで覆いをする必要はある。
それなりにアイデアは思いつきつつある。

夕方出店から帰ってきたあっこちゃんの残り物で晩ご飯。
左から、車麩の揚げ煮、漬けものサラダ、玄米キッシュ、たま先生のキーマカレー、それに玄米ご飯を盛っただけ。
今回から、この車麩のようにお惣菜を単品で販売するようにしたみたい。
スイーツばっかしでは自分が飽きるし、マクロビスイーツでさえ頻繁な味見は作る本人の負担になるからだと。

ピーナッツクリームと穀物珈琲の珈琲ゼリー。

タルト系も余って子どもたちは大喜び。
余ったものを家族が食べても体に負担にならない。
これがウチの出店のコンセプト。
砂糖や添加物がないのは当然として、市販の味に追いつこうとする「やりすぎ感」はご法度。
かと言って、味もそっ気もない訳ではない。
その辺りがあっこスイーツの研究の成果。
もちろん、パティシエの美しくて甘いスイーツとは似て非なる全くの別物という前提。

夜は地域の氏神様の神社のお神楽。
ウチの実家が頭屋(祭りの世話役)が当たって、庭には神社のノボリが立ってる。
親父は紋付き袴で、朝から神社に出向いた。
丸亀市金倉町にある「八十主(やそすか)神社」の祭りは春、夏、秋と年に3回。
獅子組や神輿の出る秋の祭りが派手だけど、春や夏の祭りは地味にとり行われる。

段々夜も更けてくる。
宮司さん率いる神主さんたちが祝詞を奏上して、氏子の健康と繁栄を祈願する。

巫が天照大神が御隠れになって、ウズメノミコトが裸になって、、、という神話の一連のストーリーを漫才形式で喋ってくれる。

猩々の舞い。
この後客席に降りてきてお酒を振る舞う。
にこちゃんは怖がってた、、、。

最後にまた神主さんたちの舞いと祈祷。
アメノウズメノミコトが裸になって踊り狂ったのが祭りの原点とされてる。
今の再稼働反対でみんな湧いてるのもなんか似てる。
やっぱり祭りが必要なんやねー。
そんなに大勢ではないけど、地域の人たちが来てる。
エンターテイメントのない昔はこういう年に何度かの祭りが楽しみやったんやと思う。
その中で神話にふれたり、地域のみんなとの付き合いがごく普通にできてた。
ここ金倉町はイオンにゆめタウン、新興住宅と様変わりしつつある。
でもまだ、こういう神社の行事や地域のしきたりが残ってる。
この神社を中心として、農に関わる生活。
祭りの段取りのために集まったり、田んぼの水利の事で集まったり、同じメンバーで営々と生活していく訳。
こういう小さな文化圏の中で経済圏が成り立ってたんやろし、またそうなっていきたいもの。
大手優遇、経済優先からのシフト。
それは遠いどこかに理想郷を求めてエコビレッジを建設するんじゃない。
大都会以外の農村は日本中大体こういう感じ。
そこに人が戻り、生活が戻れば大丈夫。
絶望してるヒマはないぞ!
廃材の母屋の前の大きな軒の柱。
この二本だけが電柱じゃなくて普通の梁なので松。
ちょっと腐って来つつある。
こんな感じで痩せた所に雨が入って、金槌で叩くとコンコンというまだ大丈夫な所と、ポコポコと不安な音の所がある。
廃材ソーラーの乗ってる軒。
まだ柱ごと取り換える程でもないけど、このまま放っておくとマズイ。
トタンで覆うのが手っ取り早いけど、オシャレじゃないし。
柱に漆喰を塗るのは廃材天国には上品過ぎるかな?
とか色々考える。
販売禁止になってるの劇薬の防腐剤クレオーソートも持ってはいるけど、子どもたちが頻繁に通るし菜園もある場所には使いたくない。
で、とりあえず、コーキング!
水が入るとマズイ所には、何はともあれシリコンコーク。
廃材建築とは切っても切れない素晴らしい素材。
遠目には全然気にならない。
というか気にしない。
まず全体が廃材でグチャッとした雰囲気なのと、こんなに細かい所だけを普段マジマジと見たりしない。
もちろん、この柱二本そのものが常に横降りの雨に晒されないように何かで覆いをする必要はある。
それなりにアイデアは思いつきつつある。
夕方出店から帰ってきたあっこちゃんの残り物で晩ご飯。
左から、車麩の揚げ煮、漬けものサラダ、玄米キッシュ、たま先生のキーマカレー、それに玄米ご飯を盛っただけ。
今回から、この車麩のようにお惣菜を単品で販売するようにしたみたい。
スイーツばっかしでは自分が飽きるし、マクロビスイーツでさえ頻繁な味見は作る本人の負担になるからだと。
ピーナッツクリームと穀物珈琲の珈琲ゼリー。
タルト系も余って子どもたちは大喜び。
余ったものを家族が食べても体に負担にならない。
これがウチの出店のコンセプト。
砂糖や添加物がないのは当然として、市販の味に追いつこうとする「やりすぎ感」はご法度。
かと言って、味もそっ気もない訳ではない。
その辺りがあっこスイーツの研究の成果。
もちろん、パティシエの美しくて甘いスイーツとは似て非なる全くの別物という前提。
夜は地域の氏神様の神社のお神楽。
ウチの実家が頭屋(祭りの世話役)が当たって、庭には神社のノボリが立ってる。
親父は紋付き袴で、朝から神社に出向いた。
丸亀市金倉町にある「八十主(やそすか)神社」の祭りは春、夏、秋と年に3回。
獅子組や神輿の出る秋の祭りが派手だけど、春や夏の祭りは地味にとり行われる。
段々夜も更けてくる。
宮司さん率いる神主さんたちが祝詞を奏上して、氏子の健康と繁栄を祈願する。
巫が天照大神が御隠れになって、ウズメノミコトが裸になって、、、という神話の一連のストーリーを漫才形式で喋ってくれる。
猩々の舞い。
この後客席に降りてきてお酒を振る舞う。
にこちゃんは怖がってた、、、。
最後にまた神主さんたちの舞いと祈祷。
アメノウズメノミコトが裸になって踊り狂ったのが祭りの原点とされてる。
今の再稼働反対でみんな湧いてるのもなんか似てる。
やっぱり祭りが必要なんやねー。
そんなに大勢ではないけど、地域の人たちが来てる。
エンターテイメントのない昔はこういう年に何度かの祭りが楽しみやったんやと思う。
その中で神話にふれたり、地域のみんなとの付き合いがごく普通にできてた。
ここ金倉町はイオンにゆめタウン、新興住宅と様変わりしつつある。
でもまだ、こういう神社の行事や地域のしきたりが残ってる。
この神社を中心として、農に関わる生活。
祭りの段取りのために集まったり、田んぼの水利の事で集まったり、同じメンバーで営々と生活していく訳。
こういう小さな文化圏の中で経済圏が成り立ってたんやろし、またそうなっていきたいもの。
大手優遇、経済優先からのシフト。
それは遠いどこかに理想郷を求めてエコビレッジを建設するんじゃない。
大都会以外の農村は日本中大体こういう感じ。
そこに人が戻り、生活が戻れば大丈夫。
絶望してるヒマはないぞ!
タグ :神社
2012年07月08日
今日は「さぬきオーガニックマルシェ」
やっと仕込みの一仕事終わった!
今日、7/8(日)は宇多津は「公楽」の「さぬきオーガニックマルシェ」の日。
あっこちゃんだけで出発したよ。
11時から3時までやってるよー。
子どもたちもがよく働いてくれるので、超助かるー。
野遊や土歩はもちろん、にこちゃんまで既に人員に入ってる。
文字通り、家内制手工業って感じの産業革命以前のスタイル。
これから大手が回らなくなって、給料がでなくなればこういう路線にシフトしていけばいいだけ。

不耕起、無肥料の自然農の畑はソコソコよく出来てる。
これは何の畝でしょう?
自然農=ほったらかしと思う人も多いみたいやけど、全然違う。
ここももうちょっと草取りした方がいいしね。
当たり前やけど、作物よりも草が大きくなって、日光が阻害されると成長しない。

コレね。

上の小さなのは丸ごと蒸し煮にして、出店用のアメリカンドッグの芯にした。
先日の子どもたち用のは試作だったよう。

大きなのはカレーに入れた。
冷凍の百花、吊るしてある玉ネギ、じゃがいも。
カレールーを使わなくても美味しくするポイントはニンニクと玉ネギを油で炒める時に塩をシッカリ入れてガンガンに炒めること。
クミン、コリアンダー、カルダモンなども油でしっかり炒める。
子ども用はそれだけ、大人用は後でチリパウダーやガラムマサラを入れる。
後は味噌汁の残りやあらゆる調味料の残りなんかを入れる。
三杯酢やマリネ、タレなんか。
更におととしの真っ黒になった3年味噌。
コクが足りなければ練りゴマ。
結局、味見して何が足りないのかを見極める事が大事。
まあ、カレールーも肉も魚も使わないので中々難しい。
それで、何やかんや入れまくる。
煮物の残りや煮汁、漬けダレと和風や中華系でもいい。
塩分は最初の炒める時にシッカリ目に入れてても、後で味噌やそういう煮汁などのコクで美味くなる。
香りはニンニク、ショウガ、スパイス系。
子どもたちはスパイス類が苦手なので、そこまで入れない。
まして、トウガラシ系は大人用のだけ。
野遊はそろそろ大人用のと子ども用のを自分でブレンドし始めた。
こういうのも本人の判断でやってみるのがいい。

これはくぼさんの豆腐の中でも、冷や奴に向く「やわらかもめん」と違い「しっかりもめん」。
こういうステーキや麻婆豆腐に向く。
これはソテーしてバルサミコ酢と醤油を絡めて煮詰めたもの。
添えてるのはルッコラ。
昨日は名古屋でイタリアンのシェフしてた同級生が帰ってきて、ピザの窯を見たいという事でウチに来てた。
ルッコラは彼が育てたもの。
ピザの窯を見に来るのが目的やったけど、「これからどうしようか?」という話になる。
大借金しての独立開業も雇われシェフもどっちも大変。
だったら、借金せずにコツコツと手作りしながら自分のスタイルを模索すればいい。
働く=お金を生む
生活=お金を使う
この方程式以外の道があるということをウチが実現して証明していってる。
難しいと思い込まされてるのは、6、3、3、4の教育、テレビ、新聞、この社会ぐるみの洗脳だ。
やってみると実は簡単。
資格もいらないし、誰とも競う必要がない。
むしろ、今までの比較、競争という古めかしい努力を辞めるということ。
そりゃあ、長年かけて身についた「こうあらねばならない」という価値観を変えていくのには時間はかかる。
ウチだって、12年間の廃材生活で現在進行形の途上段階。
ボチボチ行こうぜ!
今日、7/8(日)は宇多津は「公楽」の「さぬきオーガニックマルシェ」の日。
あっこちゃんだけで出発したよ。
11時から3時までやってるよー。
子どもたちもがよく働いてくれるので、超助かるー。
野遊や土歩はもちろん、にこちゃんまで既に人員に入ってる。
文字通り、家内制手工業って感じの産業革命以前のスタイル。
これから大手が回らなくなって、給料がでなくなればこういう路線にシフトしていけばいいだけ。
不耕起、無肥料の自然農の畑はソコソコよく出来てる。
これは何の畝でしょう?
自然農=ほったらかしと思う人も多いみたいやけど、全然違う。
ここももうちょっと草取りした方がいいしね。
当たり前やけど、作物よりも草が大きくなって、日光が阻害されると成長しない。
コレね。
上の小さなのは丸ごと蒸し煮にして、出店用のアメリカンドッグの芯にした。
先日の子どもたち用のは試作だったよう。
大きなのはカレーに入れた。
冷凍の百花、吊るしてある玉ネギ、じゃがいも。
カレールーを使わなくても美味しくするポイントはニンニクと玉ネギを油で炒める時に塩をシッカリ入れてガンガンに炒めること。
クミン、コリアンダー、カルダモンなども油でしっかり炒める。
子ども用はそれだけ、大人用は後でチリパウダーやガラムマサラを入れる。
後は味噌汁の残りやあらゆる調味料の残りなんかを入れる。
三杯酢やマリネ、タレなんか。
更におととしの真っ黒になった3年味噌。
コクが足りなければ練りゴマ。
結局、味見して何が足りないのかを見極める事が大事。
まあ、カレールーも肉も魚も使わないので中々難しい。
それで、何やかんや入れまくる。
煮物の残りや煮汁、漬けダレと和風や中華系でもいい。
塩分は最初の炒める時にシッカリ目に入れてても、後で味噌やそういう煮汁などのコクで美味くなる。
香りはニンニク、ショウガ、スパイス系。
子どもたちはスパイス類が苦手なので、そこまで入れない。
まして、トウガラシ系は大人用のだけ。
野遊はそろそろ大人用のと子ども用のを自分でブレンドし始めた。
こういうのも本人の判断でやってみるのがいい。
これはくぼさんの豆腐の中でも、冷や奴に向く「やわらかもめん」と違い「しっかりもめん」。
こういうステーキや麻婆豆腐に向く。
これはソテーしてバルサミコ酢と醤油を絡めて煮詰めたもの。
添えてるのはルッコラ。
昨日は名古屋でイタリアンのシェフしてた同級生が帰ってきて、ピザの窯を見たいという事でウチに来てた。
ルッコラは彼が育てたもの。
ピザの窯を見に来るのが目的やったけど、「これからどうしようか?」という話になる。
大借金しての独立開業も雇われシェフもどっちも大変。
だったら、借金せずにコツコツと手作りしながら自分のスタイルを模索すればいい。
働く=お金を生む
生活=お金を使う
この方程式以外の道があるということをウチが実現して証明していってる。
難しいと思い込まされてるのは、6、3、3、4の教育、テレビ、新聞、この社会ぐるみの洗脳だ。
やってみると実は簡単。
資格もいらないし、誰とも競う必要がない。
むしろ、今までの比較、競争という古めかしい努力を辞めるということ。
そりゃあ、長年かけて身についた「こうあらねばならない」という価値観を変えていくのには時間はかかる。
ウチだって、12年間の廃材生活で現在進行形の途上段階。
ボチボチ行こうぜ!
タグ :マルシェ
2012年07月07日
天ぷらカーのメンテナンス
天ぷらカーは4月半ばに導入して、以来活躍してくれてる。
始動時と止まる前にしか軽油を使わないんで、まだ最初に入れた軽油が半分ぐらいに減っただけで、給油はしていない。
ほぼ天ぷら油で走ってる。
屋久島に福井の大飯原発と遠征もこなしてくれた。
そろそろエンジンオイルを交換しないといけない。

軽トラは車高が高いし、車が小さいのでドレンボルト緩めたり、エンジンオイルを抜き取る量も少ないから簡単やけど、、天ぷらカーは乗用車なので、全てがやりづらい。
オイルの缶で受け取るのも一つでは一杯になるんで、途中で差し替える。
手が真っ黒いオイルまみれになるのはいたしかたない。

新しいオイルは助手席の下から入れる。
これは簡単。
取り扱い説明書にオイルの量とか書いてあるし。
それと、アイドリングの回転数を上げたかったんで、マツダのディーラーまで行って、やり方を聞きに行った。
天ぷら油と軽油では圧縮や爆発のタイミングが違うそうで、天ぷら油ではアイドリングの安定が悪いから。
別にマツダで買った訳でもないけど、天ぷらカーはマツダ社製のボンゴフレンディーという車なので、親切丁寧に教えてくれた。

こっちの運転席の下にある、噴射ポンプにある、アイドルスイッチというのを回して調整するんだと。

これが噴射ポンプ。
下の透明のチューブが天ぷら油の供給ホース。

整備士用の資料までコピーしてくれた。
700~780回転とあるのを900回転ぐらいまで高めた。
と、書けば簡単そうやけど、実際はコレを見てやってみても中々うまくいかず、近所の同級生の車屋の友達に聞きに行って解決した。
ここには書かれてない、スイッチの配線のカプラーを外して回すという工程が必要やった、、、。
このちょっとの事を知らないから素人ではねー。
でも!
分からなければプロに聞く。
聞いてやってみる。
やってみても分からなければまた聞く。
建築、土木、板金、鉄工、自動車、、、あらゆるプロの職人は素人の果敢な取り組みに親切に教えてくれる。
本気で自分でやろうとする姿勢ならば。

マツダのディーラーからちょっと足を延ばせば宇多津町のくぼさんの豆腐の店がある。
久しぶりの「やわらかもめん」の冷や奴。
久保さんイチオシのこの定番の豆腐は、どこのスーパーでも見かける男前豆腐なんかとは対照的。
どちらも国産大豆、消泡材などの添加物ナシ。
男前は大量生産できるように機械化してる。
濃い豆乳に自動的にニガリを入れて、そのままパックする充填豆腐。
一方久保さんのはできるだけ薄い豆乳にギリギリまで抑えた少ないニガリを打つ。
これは久保さん自身が職人としての技術で日々実践されてる。
それが出来なくなるほどの機械化や大量生産はできないとおっしゃる。
ココが違い。
要するに濃い豆乳になら少々多めにラフにニガリを打っても大丈夫ということ。
実際に久保さんも若い時に今の男前豆腐のような濃いのを作った事があるんだとか。
最初は「これは美味い!」と感動したんだそう。
でも何回か食べてると、「ん、くどいな。」と飽きて、すぐに辞めてしまったんだと。
そういう経験も経て、今のギリギリ豆腐の形を成す「やわらかもめん」には職人のスキルの凄さが見える。
現に控え目な中にしっかりした味があって、ウチの子らも久保さんの豆腐大絶賛。
あっこスイーツのクリーム系もこの久保さんのじゃないとうまくいかないそう。
結局ここの所、久保さんの豆腐以外は買わなくなった。
ナカセンナリという豆が最高で、ウチの一年分仕込む味噌にも使わせてもらってる。
「やわらかもめん」はエンレイとい豆。
「ナカセンナリ」という豆腐での冷や奴もまた違った味で最高!

冬の自家製キムチがまだ冷蔵庫にあった。
乳酸菌で真っ白けになって、超酸っぱい。
ゴマ油で炒めると酸味がとんで食べられるようになる。

ゴボウやキャベツ、春雨なんかと煮込んでも美味しい。
これで、酸っぱいキムチが片付いた。
手作りで出来過ぎても食べきれずに棄てる羽目になることなんてない。
あの手この手を駆使して食べきる。
酸っぱくなるのもいい意味での発酵の変化。
その変化を楽しむのが工夫。
それこそが毎日飽きないどころか、毎日がワクワクの生活だ!!!
始動時と止まる前にしか軽油を使わないんで、まだ最初に入れた軽油が半分ぐらいに減っただけで、給油はしていない。
ほぼ天ぷら油で走ってる。
屋久島に福井の大飯原発と遠征もこなしてくれた。
そろそろエンジンオイルを交換しないといけない。
軽トラは車高が高いし、車が小さいのでドレンボルト緩めたり、エンジンオイルを抜き取る量も少ないから簡単やけど、、天ぷらカーは乗用車なので、全てがやりづらい。
オイルの缶で受け取るのも一つでは一杯になるんで、途中で差し替える。
手が真っ黒いオイルまみれになるのはいたしかたない。
新しいオイルは助手席の下から入れる。
これは簡単。
取り扱い説明書にオイルの量とか書いてあるし。
それと、アイドリングの回転数を上げたかったんで、マツダのディーラーまで行って、やり方を聞きに行った。
天ぷら油と軽油では圧縮や爆発のタイミングが違うそうで、天ぷら油ではアイドリングの安定が悪いから。
別にマツダで買った訳でもないけど、天ぷらカーはマツダ社製のボンゴフレンディーという車なので、親切丁寧に教えてくれた。
こっちの運転席の下にある、噴射ポンプにある、アイドルスイッチというのを回して調整するんだと。
これが噴射ポンプ。
下の透明のチューブが天ぷら油の供給ホース。
整備士用の資料までコピーしてくれた。
700~780回転とあるのを900回転ぐらいまで高めた。
と、書けば簡単そうやけど、実際はコレを見てやってみても中々うまくいかず、近所の同級生の車屋の友達に聞きに行って解決した。
ここには書かれてない、スイッチの配線のカプラーを外して回すという工程が必要やった、、、。
このちょっとの事を知らないから素人ではねー。
でも!
分からなければプロに聞く。
聞いてやってみる。
やってみても分からなければまた聞く。
建築、土木、板金、鉄工、自動車、、、あらゆるプロの職人は素人の果敢な取り組みに親切に教えてくれる。
本気で自分でやろうとする姿勢ならば。
マツダのディーラーからちょっと足を延ばせば宇多津町のくぼさんの豆腐の店がある。
久しぶりの「やわらかもめん」の冷や奴。
久保さんイチオシのこの定番の豆腐は、どこのスーパーでも見かける男前豆腐なんかとは対照的。
どちらも国産大豆、消泡材などの添加物ナシ。
男前は大量生産できるように機械化してる。
濃い豆乳に自動的にニガリを入れて、そのままパックする充填豆腐。
一方久保さんのはできるだけ薄い豆乳にギリギリまで抑えた少ないニガリを打つ。
これは久保さん自身が職人としての技術で日々実践されてる。
それが出来なくなるほどの機械化や大量生産はできないとおっしゃる。
ココが違い。
要するに濃い豆乳になら少々多めにラフにニガリを打っても大丈夫ということ。
実際に久保さんも若い時に今の男前豆腐のような濃いのを作った事があるんだとか。
最初は「これは美味い!」と感動したんだそう。
でも何回か食べてると、「ん、くどいな。」と飽きて、すぐに辞めてしまったんだと。
そういう経験も経て、今のギリギリ豆腐の形を成す「やわらかもめん」には職人のスキルの凄さが見える。
現に控え目な中にしっかりした味があって、ウチの子らも久保さんの豆腐大絶賛。
あっこスイーツのクリーム系もこの久保さんのじゃないとうまくいかないそう。
結局ここの所、久保さんの豆腐以外は買わなくなった。
ナカセンナリという豆が最高で、ウチの一年分仕込む味噌にも使わせてもらってる。
「やわらかもめん」はエンレイとい豆。
「ナカセンナリ」という豆腐での冷や奴もまた違った味で最高!
冬の自家製キムチがまだ冷蔵庫にあった。
乳酸菌で真っ白けになって、超酸っぱい。
ゴマ油で炒めると酸味がとんで食べられるようになる。
ゴボウやキャベツ、春雨なんかと煮込んでも美味しい。
これで、酸っぱいキムチが片付いた。
手作りで出来過ぎても食べきれずに棄てる羽目になることなんてない。
あの手この手を駆使して食べきる。
酸っぱくなるのもいい意味での発酵の変化。
その変化を楽しむのが工夫。
それこそが毎日飽きないどころか、毎日がワクワクの生活だ!!!
タグ :バイオディーゼル
2012年07月06日
雨の降る日は家の中で手作り作業
雨がよく降るんで、外の作業はできない。
こういう時には家の中での手作りの作業。

あっこちゃんはキュウリの漬物作り。
キュウリは塩漬け。
麹はすり潰す。

練り辛子も混ぜて完成。

これは天然酵母。
減ったら「さぬきの夢2000」の粉と水を足して延々と培養し続けてる。

その酵母で作ったのはアメリカンドッグ。
何から何まで全てを手作りする訳にはいかないので、中のウインナーは自然食品店の無添加のもの。

超大喜びなちびっ子たち。

僕は包丁を研ぐ。
月に2回ぐらいのペース。
頻度を上げる程すぐに研げるんで、おっくうにならない。

砥石は必ず「荒砥」から。
荒砥、中砥、仕上げと3種類当てる。
中砥、仕上げの2種類を使うなら、荒砥、中砥の2種類を使う方がベター。

太い板の間に細い板をはさんだだけの自作包丁差し。
洗ったらすぐにここへ差し込めるので、超便利。
ウチは基本全てが見える収納。
キッチンを使いやすくするのは手作りを加速させるコツ。

そういう様子を取材して、野遊が時々「ほんま新聞」というのを作ってる。
時間は山ほどあるんで、何やかんやと色々するよね。

午後から雨が上がって、みんなで草取り。
僕が草刈り機で刈ったのを子どもたちがクマ手で集めてくれる。
あっこちゃんは赤シソの収穫。

赤シソは塩揉みして漬かった梅の中へ入れる。
梅干し作りは簡単やからねー。

その後は風呂用の薪運び。
最近は野遊と土歩が二人で相談して、表を作って代わる代わる焚いてくれてる。
最初に火を点けた人じゃない方が追い焚きするとか決まってて、大人は風呂の管理をすることが一切なくなってる。

雨でもトマトがよく採れてる。
夕ご飯に早速、麹をまぶしたサラダにした。

イナリ寿司。
いつもは梅酢でやるけど、昨日はラッキョウを漬けた酢でやってみた。
甘みがあって美味しい寿司になった。
市販のラッキョウ酢なんか使ってなくても、塩、酢、水だけで十分甘くなる。
卵みたいな黄色いソボロはゴマ油で豆腐を炒めて、ターメリックと醤油で味付けした雷豆腐。
自家製紅ショウガと青シソも加われば最高の味。
やっぱし、薬味って大事やねー。

夜ご飯の後も面白かった。
再稼働反対サンバで「イーリャダスタルタルーガス」のサンバやドラムを聞きまくったんで、野遊が真似をしてドラムセットを作った。
僕もジャンべにディジュリドゥーでセッション。
いやーーー。
最近は居候がいなくて気楽でいい。
子どもたちも、サッカーなど僕が一緒にやってくれない事でもやってくれる居候じゃないと、来ない方がいいと言いだしたし。
手作りの食べ物だけでなく、エンターテイメントも自給するのが楽しいね。
テレビなくてもこれで十分。
ていうか、テレビがないからこんなこと思いつくのかも?
昨日も一日楽しかった。
今日もまた、違った楽しい日になる。
生きていくために必要な作業を日々こなす。
草が伸びれば草刈りして、時期がくれば種を蒔く。
野菜が採れれば保存食作り。
毎日毎日、家での作業と手作りの生活やけど、結構バリエーション豊か。
アレコレやってるんで、飽きるってことがない。
さあ。
今日は何をしよっかな~♪
こういう時には家の中での手作りの作業。
あっこちゃんはキュウリの漬物作り。
キュウリは塩漬け。
麹はすり潰す。
練り辛子も混ぜて完成。
これは天然酵母。
減ったら「さぬきの夢2000」の粉と水を足して延々と培養し続けてる。
その酵母で作ったのはアメリカンドッグ。
何から何まで全てを手作りする訳にはいかないので、中のウインナーは自然食品店の無添加のもの。
超大喜びなちびっ子たち。
僕は包丁を研ぐ。
月に2回ぐらいのペース。
頻度を上げる程すぐに研げるんで、おっくうにならない。
砥石は必ず「荒砥」から。
荒砥、中砥、仕上げと3種類当てる。
中砥、仕上げの2種類を使うなら、荒砥、中砥の2種類を使う方がベター。
太い板の間に細い板をはさんだだけの自作包丁差し。
洗ったらすぐにここへ差し込めるので、超便利。
ウチは基本全てが見える収納。
キッチンを使いやすくするのは手作りを加速させるコツ。
そういう様子を取材して、野遊が時々「ほんま新聞」というのを作ってる。
時間は山ほどあるんで、何やかんやと色々するよね。
午後から雨が上がって、みんなで草取り。
僕が草刈り機で刈ったのを子どもたちがクマ手で集めてくれる。
あっこちゃんは赤シソの収穫。
赤シソは塩揉みして漬かった梅の中へ入れる。
梅干し作りは簡単やからねー。
その後は風呂用の薪運び。
最近は野遊と土歩が二人で相談して、表を作って代わる代わる焚いてくれてる。
最初に火を点けた人じゃない方が追い焚きするとか決まってて、大人は風呂の管理をすることが一切なくなってる。
雨でもトマトがよく採れてる。
夕ご飯に早速、麹をまぶしたサラダにした。
イナリ寿司。
いつもは梅酢でやるけど、昨日はラッキョウを漬けた酢でやってみた。
甘みがあって美味しい寿司になった。
市販のラッキョウ酢なんか使ってなくても、塩、酢、水だけで十分甘くなる。
卵みたいな黄色いソボロはゴマ油で豆腐を炒めて、ターメリックと醤油で味付けした雷豆腐。
自家製紅ショウガと青シソも加われば最高の味。
やっぱし、薬味って大事やねー。
夜ご飯の後も面白かった。
再稼働反対サンバで「イーリャダスタルタルーガス」のサンバやドラムを聞きまくったんで、野遊が真似をしてドラムセットを作った。
僕もジャンべにディジュリドゥーでセッション。
いやーーー。
最近は居候がいなくて気楽でいい。
子どもたちも、サッカーなど僕が一緒にやってくれない事でもやってくれる居候じゃないと、来ない方がいいと言いだしたし。
手作りの食べ物だけでなく、エンターテイメントも自給するのが楽しいね。
テレビなくてもこれで十分。
ていうか、テレビがないからこんなこと思いつくのかも?
昨日も一日楽しかった。
今日もまた、違った楽しい日になる。
生きていくために必要な作業を日々こなす。
草が伸びれば草刈りして、時期がくれば種を蒔く。
野菜が採れれば保存食作り。
毎日毎日、家での作業と手作りの生活やけど、結構バリエーション豊か。
アレコレやってるんで、飽きるってことがない。
さあ。
今日は何をしよっかな~♪
タグ :漬けもの
2012年07月05日
久しぶりにテレビに出るよ
田植えがあらかた終わったんで、「よし、行こう!」と、大飯原発再稼働反対の直接行動に行った。
まだ苗代のこの小さな田んぼだけはまだ植えてなかった。

昨日、弟の源とあっこちゃんと僕の3人で植えた。
小さな田んぼなので2時間ぐらいで植えられる。
こんなに小さい面積でも、一俵(60㌔)以上は採れる。
お米の効率はほんとに凄い!

行く前に植えてた3反(約1000坪)の田んぼの方は苗が活着してる。
一本植えのこの苗が30~50本のシッカリとした株に成長する。
ちなみに5、6本植える機械植えでは20本ぐらいにしか分ケツしない。

これなーんだ?

このジャンボタニシの卵。
棄ててる苗を食べてる最中。
このタニシくんのお陰でウチは除草作業要らず。
無農薬、無肥料、除草剤ナシを目指すのに一番大変なのが夏の除草作業。
このタニシくんの繁殖力はとんでもないペース。
稲の苗も小さいと食べてしまう。
ウチの苗は30㎝前後のシッカリとした苗なので、食べられない。
これから生えてくるヒエやコナギなどの雑草は彼等が全て食べてしまう。

コンニャクのタン塩風。
叩いて延ばしたコンニャクをフライパンで徹底的に焼くのがポイント。

切干し大根の煮物。
人参や切干しを蒸し煮して甘さを引き出すのがポイント。
素材の甘さで砂糖はもちろん、味醂もいらない。

ナスの田楽。
自家製味噌に自家製甘酒を混ぜると、超美味い。
ショウガ、ネギ、シソなどの薬味を効かせると最高。
昨日は東京から某テレビ局のディレクターが取材の打ち合わせに来た。
電話やメールでの問い合わせはしょっちゅうある。
全国放送の場合は下見として来ても、実際に出演とまでは中々決まらない。
今回は来る前から出るという事が決まってるんだそう。
特番なので、まだ番組の名前も決まってないとか。
やっぱり、自給自足系のドキュメンタリー番組。
夏から秋ぐらいまで何度か取材に来て、暮れか年明けぐらいの放送なんだと。
早速、小さいカメラで田植えや薪の料理、子どもたちの仕事ぶりや遊びぶりを撮ってくれた。
雑誌やテレビの取材とか、講演や本の出版など、色々とオファーがある。
この廃材の自画杜撰生活から何を伝えるのか?
廃材でセルフビルドの家 (住)
田んぼや畑 (農)
手作りの保存食や料理 (食)
自力出産、ホームスクーリング、自然療法 (教育、医療)
薪の生活、天ぷらカー、廃材ソーラーパネル (エネルギー)
何でこんな生活してるのか?
したいから
楽だから
自由に生きたいから
色々と理由はあるけど、お金や原発、巨大企業、政治、、、権力と金にモノを言わせて無茶苦茶やって成り立つのがこのバビロンシステム。
ソコに風穴を開ける!
社会を変えるというより、日々のこういう自立した暮らしが広まれば権力と金に媚びずにやっていける。
その結果、自然と変わっていく。
反対活動でもないし、啓蒙運動でもない。
革命生活なのだ!!!
まだ苗代のこの小さな田んぼだけはまだ植えてなかった。
昨日、弟の源とあっこちゃんと僕の3人で植えた。
小さな田んぼなので2時間ぐらいで植えられる。
こんなに小さい面積でも、一俵(60㌔)以上は採れる。
お米の効率はほんとに凄い!
行く前に植えてた3反(約1000坪)の田んぼの方は苗が活着してる。
一本植えのこの苗が30~50本のシッカリとした株に成長する。
ちなみに5、6本植える機械植えでは20本ぐらいにしか分ケツしない。
これなーんだ?
このジャンボタニシの卵。
棄ててる苗を食べてる最中。
このタニシくんのお陰でウチは除草作業要らず。
無農薬、無肥料、除草剤ナシを目指すのに一番大変なのが夏の除草作業。
このタニシくんの繁殖力はとんでもないペース。
稲の苗も小さいと食べてしまう。
ウチの苗は30㎝前後のシッカリとした苗なので、食べられない。
これから生えてくるヒエやコナギなどの雑草は彼等が全て食べてしまう。
コンニャクのタン塩風。
叩いて延ばしたコンニャクをフライパンで徹底的に焼くのがポイント。
切干し大根の煮物。
人参や切干しを蒸し煮して甘さを引き出すのがポイント。
素材の甘さで砂糖はもちろん、味醂もいらない。
ナスの田楽。
自家製味噌に自家製甘酒を混ぜると、超美味い。
ショウガ、ネギ、シソなどの薬味を効かせると最高。
昨日は東京から某テレビ局のディレクターが取材の打ち合わせに来た。
電話やメールでの問い合わせはしょっちゅうある。
全国放送の場合は下見として来ても、実際に出演とまでは中々決まらない。
今回は来る前から出るという事が決まってるんだそう。
特番なので、まだ番組の名前も決まってないとか。
やっぱり、自給自足系のドキュメンタリー番組。
夏から秋ぐらいまで何度か取材に来て、暮れか年明けぐらいの放送なんだと。
早速、小さいカメラで田植えや薪の料理、子どもたちの仕事ぶりや遊びぶりを撮ってくれた。
雑誌やテレビの取材とか、講演や本の出版など、色々とオファーがある。
この廃材の自画杜撰生活から何を伝えるのか?
廃材でセルフビルドの家 (住)
田んぼや畑 (農)
手作りの保存食や料理 (食)
自力出産、ホームスクーリング、自然療法 (教育、医療)
薪の生活、天ぷらカー、廃材ソーラーパネル (エネルギー)
何でこんな生活してるのか?
したいから
楽だから
自由に生きたいから
色々と理由はあるけど、お金や原発、巨大企業、政治、、、権力と金にモノを言わせて無茶苦茶やって成り立つのがこのバビロンシステム。
ソコに風穴を開ける!
社会を変えるというより、日々のこういう自立した暮らしが広まれば権力と金に媚びずにやっていける。
その結果、自然と変わっていく。
反対活動でもないし、啓蒙運動でもない。
革命生活なのだ!!!
タグ :取材
2012年07月04日
原発にはナスで勝てるね
3日いなかっただけでも畑の様子は全然違う。
ナス、キュウリ、トマト、夏野菜は成長がはやい!

今年のナスは特に調子がいい。
不耕起、無肥料でも抜群!

紫玉ネギとモズクは塩に絡めておく。
別にナスを浅漬けにしておく。
結局塩だけで最高の料理になる。

ニンニクを炒めてナスも炒めた後、イリコ出汁で煮ものにした。
まずは初物なんで、こういう薄味でほっこり楽しむ。
しみじみ美味しい感動が湧き起る。

プチトマトはパラパラ採れ始めてたけど、大玉の完熟は初物。
しばし醤油に絡めてヅケにする。
今回は浅目。
漬け具合を深くして、握りにすると大味なマグロより遥かに美味い。
自家栽培のトマトは完全にスーパーのと別物。
トマトや人参の差って凄くよく分かる。
ナスを始め、夏野菜は中華、イタリアンとバリエーションが豊富に楽しめるからこれからが楽しみ。
大飯原発に踊りに行ってて、3日間家での生活から遠のいただけで、朝の味噌汁の感動ぶりにも、畑の収穫の喜びも、薪のキッチンに立っての作業も全てが新鮮。
改めて「この手作りの生活をやっててよかったーーー!」と身体の芯から歓喜する。
それはこの命が真に求めてるからだ。
再稼働しただと?
そんなのクソ喰らえ!
実は大飯の直接行動であんだけ頑張ったのに、アッサリ再稼働された事に対する落胆はない。
せいぜい原発稼働させるのも今のうちだけ。
自分の芯から自発的に金にならずとも出来る誇りある仕事ではない。
そんなダサい仕事が永続できるか?
出来る訳がないぞ。
この自画杜撰な廃材全開生活を差し置いて、勝てる訳ないじゃん。
と、自作ナス料理を一口食べて確信したね。
この感動に勝るものはないぞ!
絶対の金で買えない感動だ。
これを味わえば分かる。
本やネットでこの感動は伝わらん。
羨ましかったら、自分で実践せよ!
その実践というプロセスこそが命を解放し、真に歓喜する人生なのだ。
これは人間のDNAに書かれとる。
魂に組み込まれとる。
宇宙と大自然がそうしたんやから誰も反論できん。
金くれるから言われた通りの事をする。
そのウツロな仕事を辞めろ!!!
自分の意思で生きろ!!!
金にならんで上等。
いかに金を使わずとも生活を成り立たせるかを熟考せよ!
ウチは12年前の一軒目の廃材ハウスを建てる時からそれを最重要として生活を構築してきた。
今の立派な廃材天国だって、100%産廃。
一軒目なんかトタンにスレートという廃材バラック状態。
それで何も困らんかったし、死ぬまで困らん。
事実そうして生活してるんで、自信と確信に満ち溢れてる。
自分を信用するんだ!
生きてる以上、生きる力はみんなにあるぞ。
空虚で上品な踊らされた消費生活を辞めて、魂から湧き起るモリモリでバリバリの毎日を生きろ!
それこそが脱原発生活だ!
ナス、キュウリ、トマト、夏野菜は成長がはやい!
今年のナスは特に調子がいい。
不耕起、無肥料でも抜群!
紫玉ネギとモズクは塩に絡めておく。
別にナスを浅漬けにしておく。
結局塩だけで最高の料理になる。
ニンニクを炒めてナスも炒めた後、イリコ出汁で煮ものにした。
まずは初物なんで、こういう薄味でほっこり楽しむ。
しみじみ美味しい感動が湧き起る。
プチトマトはパラパラ採れ始めてたけど、大玉の完熟は初物。
しばし醤油に絡めてヅケにする。
今回は浅目。
漬け具合を深くして、握りにすると大味なマグロより遥かに美味い。
自家栽培のトマトは完全にスーパーのと別物。
トマトや人参の差って凄くよく分かる。
ナスを始め、夏野菜は中華、イタリアンとバリエーションが豊富に楽しめるからこれからが楽しみ。
大飯原発に踊りに行ってて、3日間家での生活から遠のいただけで、朝の味噌汁の感動ぶりにも、畑の収穫の喜びも、薪のキッチンに立っての作業も全てが新鮮。
改めて「この手作りの生活をやっててよかったーーー!」と身体の芯から歓喜する。
それはこの命が真に求めてるからだ。
再稼働しただと?
そんなのクソ喰らえ!
実は大飯の直接行動であんだけ頑張ったのに、アッサリ再稼働された事に対する落胆はない。
せいぜい原発稼働させるのも今のうちだけ。
自分の芯から自発的に金にならずとも出来る誇りある仕事ではない。
そんなダサい仕事が永続できるか?
出来る訳がないぞ。
この自画杜撰な廃材全開生活を差し置いて、勝てる訳ないじゃん。
と、自作ナス料理を一口食べて確信したね。
この感動に勝るものはないぞ!
絶対の金で買えない感動だ。
これを味わえば分かる。
本やネットでこの感動は伝わらん。
羨ましかったら、自分で実践せよ!
その実践というプロセスこそが命を解放し、真に歓喜する人生なのだ。
これは人間のDNAに書かれとる。
魂に組み込まれとる。
宇宙と大自然がそうしたんやから誰も反論できん。
金くれるから言われた通りの事をする。
そのウツロな仕事を辞めろ!!!
自分の意思で生きろ!!!
金にならんで上等。
いかに金を使わずとも生活を成り立たせるかを熟考せよ!
ウチは12年前の一軒目の廃材ハウスを建てる時からそれを最重要として生活を構築してきた。
今の立派な廃材天国だって、100%産廃。
一軒目なんかトタンにスレートという廃材バラック状態。
それで何も困らんかったし、死ぬまで困らん。
事実そうして生活してるんで、自信と確信に満ち溢れてる。
自分を信用するんだ!
生きてる以上、生きる力はみんなにあるぞ。
空虚で上品な踊らされた消費生活を辞めて、魂から湧き起るモリモリでバリバリの毎日を生きろ!
それこそが脱原発生活だ!
タグ :ナス
2012年07月03日
再稼働反対サンバ!!!
「オキュパイ大飯!」
大飯原発再稼働反対の直接行動に家族で行ってきた。
天ぷらーに廃油積み込んで、カセットコンロに観時、玄米、塩、梅干し、味噌を持参して。
結局、2泊3日のちょっとした旅になった。
原発から少し離れた公園の芝生にテント村が出来て、中心のカンタくんは住み込んでオキュパイ行動を呼びかけてた。

公園は和やかなもの。

「ザ・ファミリー」、「はるや」、「廃材天国」という、自給自足、玄米菜食、ホームスクーリングというキーワードが並ぶ3家族。
こういう時に久々の再会。

先日一緒に作業した山陰のアキくんと子どもたちは2年ぶりの再会。
何せ、7/1の夜、原子炉の制御棒が抜かれて、再稼働が始まるとの予定だった。
それで、6/30の午後から原発に通じるゲートを直接行動で封鎖しての座り込み(実は踊り込み!?)。

公園から原発ゲート前へ向かう。

活動家系のおっちゃんが発煙筒で警備員を引きつけてる間に、何台かの車をサッとゲートの前後に横付け。
何人かは手際よく鎖でゲートと自分を繋いで南京錠でロック。
すぐに機動隊のバスが2台到着。
「道路を占拠するのは違法です。」
「ただちに撤去して下さい。」とお決まりの呼びかけ。
占拠してるみんなからは口々に、
「再稼働は国民が納得していない、それこそが違法なんだから、話し合いをさせてくれ!」
「こっちもやりたくて占拠してるんじゃない、強引に再稼働しようとするからこういう手段しかないんだ!」
「署名集めもしたし、官邸や知事に電話やメールもしたけど、相手にされない。」
「これが国民の意思表示なんだ!」
それの答えは「そういう個別の案件についてはお答え出来ません。」
「ただちに違法行為を止めて下さい。」
としか言わない。
バカバカしくもなってくるけど、警察とはそういうもの。
僕も何度もその機動隊の管理職的な人に、たじろがずに目の前で叫んだ。
「それは出来ない!!!」
「あなたが答えられないなら話が出来る人を呼んできてくれ!」
と頼んだ。
「それも出来ません。」
「ただちに撤去を!」
としか言わない。
機動隊なり警察にそういう権限はない。
それに総理や大臣が政治的に決定した再稼働を撤回するのは、少々の声では届かない。
原発に通じる道路は公道やし、それを封鎖するのは当然違法行為。
でも、多数の人が座り込んで非暴力で訴えるのを権力で強制排除することも出来ない。

人間の鎖でゲートの占拠を排除されないように守る。
睨みあいは夜まで続く。

「再稼働反対!」
「子どもを守ろう!」
「原発バイバイ!」
「命が大事!」
とシュプレヒコールを上げながら、ジャンべにドラム、あらゆる楽器が止まることなく響く。
当然みんな踊りながらのコールは朝まで続く。

翌朝になると、官邸前のデモ隊が合流!

ウチの子らもゲートの中に入り、廃材ベニヤ板の自作プラカードでアピール。

奥に見えるトンネルの向こうが原発。
2日目にはゲートの占拠の向こうに、装備を固めた機動隊がお目見えした。
原発側と進入路の両方から機動隊の列と参加者の列で挟み打ち。
僕らはゲートを中心として機動隊と並行して列をなして対抗。
その中では「再稼働反対サンバ」を踊る。

自転車発電でアンプを動かして「再稼働反対ソング」を歌う人。

土砂降りの中、イイ感じに盛り上がってる。
前の日から夜通しやし、2日目も延々と踊る。
各自疲れきって車で仮眠しては、また差し入れのオムスビを食べて踊る。

夕方になって、機動隊が動いた。
「盾を上げろ!」という号令を横へ横へと伝言。
「押せ!」の合図でこっちの列へ押して来る。
ある程度こっちも押し返したりして揉み合いになってくると、「盾を下ろせ!」「現状維持!」の号令。
機動隊は非暴力の大勢の列をなしくずし的に排除はしない。
ただ、一度騒然となり始めると、参加者にも熱くなる者もいる。
ちょっとでも、揉め始めるとお互い掴み合いになる。
僕も揉み合いで押し倒されたり、着てたTシャツをビリビリに裂かれたりした。
60年安保に成田闘争、、、常に怒った国民と命令で鎮圧する機動隊という構図。
権力の中枢は国民の声になんか耳を貸さない。
いよいよになれば違法行為を排除するという理由で手を上げなくてもパクれる訳やし。

ゲートを中心として両方に機動隊。
その中ではとにかく「再稼働反対サンバ」!!!
この太鼓、ビート、リズムがないと2晩も続けられないよね。

僕も、踊るし、叫ぶし、ジャンべにドラムに猛打しまくった!
ただ、祭りやレイブのそれと違うのはジワジワと押してくる機動隊と拮抗しながらの切迫した訴え。
人数に余裕がないし、疲れようが腹が減ろうがギリギリまでは全力で動く。

2日目の深夜、山本太郎さんから現場に電話が入った。
「みなさんお疲れ様です。」
「みなさんの訴えはネットを通して世界中が注目しています。」
「しかし、先ほど再稼働されてしましました。」
「みなさんは休むことが必要です。」
「これからのやり方をまた共に考えていきましょう!」
祭りは終わり、ゲートを封鎖してた車や人も撤収した。
幸いにも、ケガ人も逮捕者も出ずにこのイベントは幕を引いた。
翌日の新聞で大臣は船で原発に入ったらしいし、ゲートを塞ごうとも、政府と電力会社にかなう筈はない。
そんな事はみんな分かってる。
分かってても、ここへ来ずにはいられかったから来た。
声を挙げる。
意思を示す。
何もユーストリームにアップされるのを目的にしてる訳ではない。
みんな自分で自分の人生を確かめるために来てるんだ。
今までは言われた事、決められた事をソツなくやってたら、順風満帆に生活できてた。
今でもソッチを選択しようと思えば、まだ出来なくもない。
「今からはそういう時代じゃない。」と自分で思い、考え、行動を起こす人間だから現地まで来るんだ。
しかし!
「現地に行けなくてもどかしい!」という人も多いけど、現地が全てじゃないぞ。
この転換期の直接行動には意義があるし、そう思って僕も家族で来た。
それでも、この運動なり活動に全生活を投げ打って、伊方に泊に飛び回ろうとは思わない。
ツイッターとフェイスブックで官邸前に15万とか20万の人がデモに集まる時代。
ここ大飯の様子も岩上さんのユーストでのIWJの映像でリアルタイムで見られた。
僕なんかドイツのテレビ局にインタビューされたし。
実際大飯に集まったのは4、500人とかかなー。
その10倍ぐらい来てたら、、、とか言っててもしゃあない。
そういう、「原発反対活動」だけで、少々人が集まろうとも大手メディアはまともに報道しない。
http://touch.dailymotion.com/video/xrwf80_20120702-yyyyyyyyyy-yyy_news
それでも一応テレビにも取り上げられてる。
一番必要なのは何か?
原発やお金に頼らない生活の実現!!!
個々の生活スタイルの転換。
都会で金を稼いで消費活動する人間が減らない以上は原発も経済もボロボロになりながら動き続ける。
僕は人里離れて自給自足の生活がしたい訳ではない。
丸亀市郊外の新興住宅の開発地帯にドッシリあぐらをかいてる廃材の家。
井戸を掘って、毎日薪で生活する。
衣食住、エネルギー、医療、教育、、、生きていくのに必要な項目を人任せにしない。
ましてや政府なんかアテにもしない。
そういう生活の様子をこの日記で発信する。
ここでの生活そのものがすでに革命なのだ。
日々の暮らし方。
どんな家に住み、何を買い、何を食べるのか?
「何をやって稼いで、何に金を使うのか?」
そこが全てだ!
ウチが目指すのは「稼がない、使わない」。
日々自分たち家族が生きるのに必要な労働に、大半の時間と労力を費やす。
多少は頼まれた出店や作業の収入で、必要な経費には十分。
「自分で生きていく覚悟をしない曖昧な生活」=「不安が拭えない生活」
「街での消費生活」=「稼がないと生活できないという呪縛」
その不安や呪縛から解放されようとしない奴隷がこのバビロンなり、原発を支えてる。
自分を解放せよ!
自分の頭と感覚で判断せよ!
何で稼ぎ、何に使うのか?
どういう働きをし、毎日の時間を何に費やすのか?
金と時間の使い道で、どんな人生かが決まる
金さえもらえれば、言われたことをする。
その人生の集合体が原発大国日本を支えて来た。
いい悪いじゃない。
事実だ。
オカシイと思ったら声を上げろ!
違和感がある仕事はすぐに辞めろ!
脱原発に一番必要なもの。
それは「日々の生活と仕事の転換」しかない。
シュプレヒコールを上げながら大手メーカーの命を育むことのない食べ物を食べてるのでは根本的には変わらない。
毎日の生活の改革だ!
自律した自立生活を目指すのだ!!!
それは今日から、今から、どこからでも出来る。
生活を変えられないという思い込みこそが、呪縛された奴隷に他ならないのだから。
大飯原発再稼働反対の直接行動に家族で行ってきた。
天ぷらーに廃油積み込んで、カセットコンロに観時、玄米、塩、梅干し、味噌を持参して。
結局、2泊3日のちょっとした旅になった。
原発から少し離れた公園の芝生にテント村が出来て、中心のカンタくんは住み込んでオキュパイ行動を呼びかけてた。
公園は和やかなもの。
「ザ・ファミリー」、「はるや」、「廃材天国」という、自給自足、玄米菜食、ホームスクーリングというキーワードが並ぶ3家族。
こういう時に久々の再会。
先日一緒に作業した山陰のアキくんと子どもたちは2年ぶりの再会。
何せ、7/1の夜、原子炉の制御棒が抜かれて、再稼働が始まるとの予定だった。
それで、6/30の午後から原発に通じるゲートを直接行動で封鎖しての座り込み(実は踊り込み!?)。
公園から原発ゲート前へ向かう。
活動家系のおっちゃんが発煙筒で警備員を引きつけてる間に、何台かの車をサッとゲートの前後に横付け。
何人かは手際よく鎖でゲートと自分を繋いで南京錠でロック。
すぐに機動隊のバスが2台到着。
「道路を占拠するのは違法です。」
「ただちに撤去して下さい。」とお決まりの呼びかけ。
占拠してるみんなからは口々に、
「再稼働は国民が納得していない、それこそが違法なんだから、話し合いをさせてくれ!」
「こっちもやりたくて占拠してるんじゃない、強引に再稼働しようとするからこういう手段しかないんだ!」
「署名集めもしたし、官邸や知事に電話やメールもしたけど、相手にされない。」
「これが国民の意思表示なんだ!」
それの答えは「そういう個別の案件についてはお答え出来ません。」
「ただちに違法行為を止めて下さい。」
としか言わない。
バカバカしくもなってくるけど、警察とはそういうもの。
僕も何度もその機動隊の管理職的な人に、たじろがずに目の前で叫んだ。
「それは出来ない!!!」
「あなたが答えられないなら話が出来る人を呼んできてくれ!」
と頼んだ。
「それも出来ません。」
「ただちに撤去を!」
としか言わない。
機動隊なり警察にそういう権限はない。
それに総理や大臣が政治的に決定した再稼働を撤回するのは、少々の声では届かない。
原発に通じる道路は公道やし、それを封鎖するのは当然違法行為。
でも、多数の人が座り込んで非暴力で訴えるのを権力で強制排除することも出来ない。
人間の鎖でゲートの占拠を排除されないように守る。
睨みあいは夜まで続く。
「再稼働反対!」
「子どもを守ろう!」
「原発バイバイ!」
「命が大事!」
とシュプレヒコールを上げながら、ジャンべにドラム、あらゆる楽器が止まることなく響く。
当然みんな踊りながらのコールは朝まで続く。
翌朝になると、官邸前のデモ隊が合流!
ウチの子らもゲートの中に入り、廃材ベニヤ板の自作プラカードでアピール。
奥に見えるトンネルの向こうが原発。
2日目にはゲートの占拠の向こうに、装備を固めた機動隊がお目見えした。
原発側と進入路の両方から機動隊の列と参加者の列で挟み打ち。
僕らはゲートを中心として機動隊と並行して列をなして対抗。
その中では「再稼働反対サンバ」を踊る。
自転車発電でアンプを動かして「再稼働反対ソング」を歌う人。
土砂降りの中、イイ感じに盛り上がってる。
前の日から夜通しやし、2日目も延々と踊る。
各自疲れきって車で仮眠しては、また差し入れのオムスビを食べて踊る。
夕方になって、機動隊が動いた。
「盾を上げろ!」という号令を横へ横へと伝言。
「押せ!」の合図でこっちの列へ押して来る。
ある程度こっちも押し返したりして揉み合いになってくると、「盾を下ろせ!」「現状維持!」の号令。
機動隊は非暴力の大勢の列をなしくずし的に排除はしない。
ただ、一度騒然となり始めると、参加者にも熱くなる者もいる。
ちょっとでも、揉め始めるとお互い掴み合いになる。
僕も揉み合いで押し倒されたり、着てたTシャツをビリビリに裂かれたりした。
60年安保に成田闘争、、、常に怒った国民と命令で鎮圧する機動隊という構図。
権力の中枢は国民の声になんか耳を貸さない。
いよいよになれば違法行為を排除するという理由で手を上げなくてもパクれる訳やし。
ゲートを中心として両方に機動隊。
その中ではとにかく「再稼働反対サンバ」!!!
この太鼓、ビート、リズムがないと2晩も続けられないよね。
僕も、踊るし、叫ぶし、ジャンべにドラムに猛打しまくった!
ただ、祭りやレイブのそれと違うのはジワジワと押してくる機動隊と拮抗しながらの切迫した訴え。
人数に余裕がないし、疲れようが腹が減ろうがギリギリまでは全力で動く。
2日目の深夜、山本太郎さんから現場に電話が入った。
「みなさんお疲れ様です。」
「みなさんの訴えはネットを通して世界中が注目しています。」
「しかし、先ほど再稼働されてしましました。」
「みなさんは休むことが必要です。」
「これからのやり方をまた共に考えていきましょう!」
祭りは終わり、ゲートを封鎖してた車や人も撤収した。
幸いにも、ケガ人も逮捕者も出ずにこのイベントは幕を引いた。
翌日の新聞で大臣は船で原発に入ったらしいし、ゲートを塞ごうとも、政府と電力会社にかなう筈はない。
そんな事はみんな分かってる。
分かってても、ここへ来ずにはいられかったから来た。
声を挙げる。
意思を示す。
何もユーストリームにアップされるのを目的にしてる訳ではない。
みんな自分で自分の人生を確かめるために来てるんだ。
今までは言われた事、決められた事をソツなくやってたら、順風満帆に生活できてた。
今でもソッチを選択しようと思えば、まだ出来なくもない。
「今からはそういう時代じゃない。」と自分で思い、考え、行動を起こす人間だから現地まで来るんだ。
しかし!
「現地に行けなくてもどかしい!」という人も多いけど、現地が全てじゃないぞ。
この転換期の直接行動には意義があるし、そう思って僕も家族で来た。
それでも、この運動なり活動に全生活を投げ打って、伊方に泊に飛び回ろうとは思わない。
ツイッターとフェイスブックで官邸前に15万とか20万の人がデモに集まる時代。
ここ大飯の様子も岩上さんのユーストでのIWJの映像でリアルタイムで見られた。
僕なんかドイツのテレビ局にインタビューされたし。
実際大飯に集まったのは4、500人とかかなー。
その10倍ぐらい来てたら、、、とか言っててもしゃあない。
そういう、「原発反対活動」だけで、少々人が集まろうとも大手メディアはまともに報道しない。
http://touch.dailymotion.com/video/xrwf80_20120702-yyyyyyyyyy-yyy_news
それでも一応テレビにも取り上げられてる。
一番必要なのは何か?
原発やお金に頼らない生活の実現!!!
個々の生活スタイルの転換。
都会で金を稼いで消費活動する人間が減らない以上は原発も経済もボロボロになりながら動き続ける。
僕は人里離れて自給自足の生活がしたい訳ではない。
丸亀市郊外の新興住宅の開発地帯にドッシリあぐらをかいてる廃材の家。
井戸を掘って、毎日薪で生活する。
衣食住、エネルギー、医療、教育、、、生きていくのに必要な項目を人任せにしない。
ましてや政府なんかアテにもしない。
そういう生活の様子をこの日記で発信する。
ここでの生活そのものがすでに革命なのだ。
日々の暮らし方。
どんな家に住み、何を買い、何を食べるのか?
「何をやって稼いで、何に金を使うのか?」
そこが全てだ!
ウチが目指すのは「稼がない、使わない」。
日々自分たち家族が生きるのに必要な労働に、大半の時間と労力を費やす。
多少は頼まれた出店や作業の収入で、必要な経費には十分。
「自分で生きていく覚悟をしない曖昧な生活」=「不安が拭えない生活」
「街での消費生活」=「稼がないと生活できないという呪縛」
その不安や呪縛から解放されようとしない奴隷がこのバビロンなり、原発を支えてる。
自分を解放せよ!
自分の頭と感覚で判断せよ!
何で稼ぎ、何に使うのか?
どういう働きをし、毎日の時間を何に費やすのか?
金と時間の使い道で、どんな人生かが決まる
金さえもらえれば、言われたことをする。
その人生の集合体が原発大国日本を支えて来た。
いい悪いじゃない。
事実だ。
オカシイと思ったら声を上げろ!
違和感がある仕事はすぐに辞めろ!
脱原発に一番必要なもの。
それは「日々の生活と仕事の転換」しかない。
シュプレヒコールを上げながら大手メーカーの命を育むことのない食べ物を食べてるのでは根本的には変わらない。
毎日の生活の改革だ!
自律した自立生活を目指すのだ!!!
それは今日から、今から、どこからでも出来る。
生活を変えられないという思い込みこそが、呪縛された奴隷に他ならないのだから。
タグ :再稼働反対