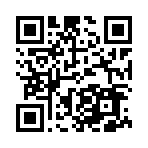2013年02月28日
子ども料理
そろそろ、宇多津の塩釜も終わりが見えてきた。
夕方宇多津から帰り、暗くなってからあくる日の段取り。
今日はまた「かぐや姫プレイパーク」の現場に向かう。
おととい立てた柱に桁を乗せる作業。
そのための105㎜×180㎜の2間モノを3本みつくろう。
積み込んである材木の中から引っ張り出すのが夜の一仕事。

何とか作業を終えて家の中に入るとご飯が出来てた。
またあっこちゃんも留守で、子どもたち3人だけで五右衛門風呂焚いて、薪ストーブの上で料理してくれてた。

がんもどき、大根、菜花の煮物。
大根や菜花は畑から採ってくる所からやし。
味付けもイリこ出汁に塩、醤油、甘酒でバッチリ美味い。

こちらはサツマイモと大根の炒め物。
ゴマ油と醤油、黒ゴマがふんだんに入ってリッチな味。
これに、メノリの佃煮やたくあん漬けなどの常備菜で十分。
酒飲みにはコノワタの塩辛もあるし。
いやー、僕ら大人が居る時でも色々よく手伝うけど、子どもたちだけでの方が本領発揮するんかいな。
言われた事をソツなくこなすのと、自分でどうやるかから考えて作業をするのとでは別世界。
「自分発」
これが大事。
自分で何を使って何を作る所から考える。
畑に行き、収穫しながらメニューを考えて、同時に2品作るのはかなり高等なレベル。
しかも薪調理!
野遊がリーダーで土歩やにこちゃんに指示しながら作業を進めるんやと思われる。
その土歩やにこちゃんでさえ、一人で一品作れるようになってきてるからね。
ほんと、この子らは後何年かするとどこへ行って何をやっても生きていける。
生きていく事にまつわる、医食住を自分でどうにかできる自信があれば困ることはまずない。
もちろん、10代後半になれば親から離れて、都会や外国での生活をしてみるのもいい。
「生きていく事は難しい」
「社会に出るのは大変な事」
「自分にはたいした事はできない」
僕ら親がこんな事微塵も思ってないし、子どもたちもこういう刷り込みナシに育ってゆく。
で、客観的に見れば、「何でもできてすごいよねー。」となる。
何にも凄くない。
これが当たり前、フツー、常識、なのだ。
人間、何でもはできない。
でも、医食住ぐらいは出来て当たり前。
その上で、専門的な分野の興味関心に趣いていけばいい。
生きることが余裕シャクシャクになる程、マニアックな嗜好性が目覚めやすいぞ。
夕方宇多津から帰り、暗くなってからあくる日の段取り。
今日はまた「かぐや姫プレイパーク」の現場に向かう。
おととい立てた柱に桁を乗せる作業。
そのための105㎜×180㎜の2間モノを3本みつくろう。
積み込んである材木の中から引っ張り出すのが夜の一仕事。
何とか作業を終えて家の中に入るとご飯が出来てた。
またあっこちゃんも留守で、子どもたち3人だけで五右衛門風呂焚いて、薪ストーブの上で料理してくれてた。
がんもどき、大根、菜花の煮物。
大根や菜花は畑から採ってくる所からやし。
味付けもイリこ出汁に塩、醤油、甘酒でバッチリ美味い。
こちらはサツマイモと大根の炒め物。
ゴマ油と醤油、黒ゴマがふんだんに入ってリッチな味。
これに、メノリの佃煮やたくあん漬けなどの常備菜で十分。
酒飲みにはコノワタの塩辛もあるし。
いやー、僕ら大人が居る時でも色々よく手伝うけど、子どもたちだけでの方が本領発揮するんかいな。
言われた事をソツなくこなすのと、自分でどうやるかから考えて作業をするのとでは別世界。
「自分発」
これが大事。
自分で何を使って何を作る所から考える。
畑に行き、収穫しながらメニューを考えて、同時に2品作るのはかなり高等なレベル。
しかも薪調理!
野遊がリーダーで土歩やにこちゃんに指示しながら作業を進めるんやと思われる。
その土歩やにこちゃんでさえ、一人で一品作れるようになってきてるからね。
ほんと、この子らは後何年かするとどこへ行って何をやっても生きていける。
生きていく事にまつわる、医食住を自分でどうにかできる自信があれば困ることはまずない。
もちろん、10代後半になれば親から離れて、都会や外国での生活をしてみるのもいい。
「生きていく事は難しい」
「社会に出るのは大変な事」
「自分にはたいした事はできない」
僕ら親がこんな事微塵も思ってないし、子どもたちもこういう刷り込みナシに育ってゆく。
で、客観的に見れば、「何でもできてすごいよねー。」となる。
何にも凄くない。
これが当たり前、フツー、常識、なのだ。
人間、何でもはできない。
でも、医食住ぐらいは出来て当たり前。
その上で、専門的な分野の興味関心に趣いていけばいい。
生きることが余裕シャクシャクになる程、マニアックな嗜好性が目覚めやすいぞ。
タグ :教育
2013年02月27日
新たな廃材建築着工
まんのう町、「かぐや姫プレイパーク」にピザ窯を作る。
いつものようにワークショップ形式で土日で作ることにしてる。
それは3/9(土)10(日)。
初日は土台作り。
ピザの窯って地面に作ると使いにくいので、80~90㎝ぐらいの土台が必要。
お次はみんなで長靴はいて粘土をふみふみして、ゴム手袋はいて生のレンガのようなサイコロを作る。
僕が竹で大きなカゴのような枠を作り、そこにくっつけていく。
4、5人居れば余裕を持って2日間で仕上がる。
耐火レンガをダイヤモンドカッターで切ったりするような難解な作業もないし、素人でできるのがいい。
それまでに窯の入る東屋を廃材建築で作っておく。
「庭にピザ窯って憧れる~!」という人は多い。
そのためには、まず窯を快適に使うためのロケーションが重要。
粘土で作る窯には屋根が要る。
窯本体の保護のための屋根だけでなく、窯の周りに広い屋根があると、ピザパーティー中の雨や夏の日差しにも安心できる。
焚きものをストックしたり、薪の搬入経路も考えておかないといけない。
そういうトータルでのイメージをしながら進める。

2間(3、6m)×3間(5、3m)の東屋を建てる。
3m×4m×5mの三角定規を作るとカネ(直角)が出る。

天ぷら油を回収する時に缶ごともらってくる店がある。
穴を掘って、その一斗缶を独立基礎にする。

グラインダーで一斗缶の底もフタも切りぬく。
穴の底にコンクリートを入れた上に缶を置く。
90℃方向に二本仮の筋かいを入れて、垂直を見ながら杭で固定。
その中に柱を入れて、コンクリートを突っつきながら入れていく。

写真では分かりづらいけど、コンクリートを盛り上げて水が溜まらないようにする。

どんどんコンクリートを練っては柱を固定していく。

しょうたくんと二人でやれば余裕を持って、一日で柱が完成。
片屋根でガルバリウムの波板が一番簡単にできる。
夕方、完成と同時に雨が降ってきた。
天気が持ってくれたのもラッキー。

大根を消費するため、ほとんどの大根鍋。
畑の春菊もまだ食べられる。
本葛の葛切りが最高に美味い。
自家製のポン酢とゴマダレの両方がいい。
薬味は柚子コショウを利かせる。

人参と人参葉のかき揚げ。
何と、所々に酒粕が入ってる。
味醂と醤油の天出汁もいいし、塩もいい。
これは酒のアテにも、ご飯のお供にも最高。
いつものようにワークショップ形式で土日で作ることにしてる。
それは3/9(土)10(日)。
初日は土台作り。
ピザの窯って地面に作ると使いにくいので、80~90㎝ぐらいの土台が必要。
お次はみんなで長靴はいて粘土をふみふみして、ゴム手袋はいて生のレンガのようなサイコロを作る。
僕が竹で大きなカゴのような枠を作り、そこにくっつけていく。
4、5人居れば余裕を持って2日間で仕上がる。
耐火レンガをダイヤモンドカッターで切ったりするような難解な作業もないし、素人でできるのがいい。
それまでに窯の入る東屋を廃材建築で作っておく。
「庭にピザ窯って憧れる~!」という人は多い。
そのためには、まず窯を快適に使うためのロケーションが重要。
粘土で作る窯には屋根が要る。
窯本体の保護のための屋根だけでなく、窯の周りに広い屋根があると、ピザパーティー中の雨や夏の日差しにも安心できる。
焚きものをストックしたり、薪の搬入経路も考えておかないといけない。
そういうトータルでのイメージをしながら進める。
2間(3、6m)×3間(5、3m)の東屋を建てる。
3m×4m×5mの三角定規を作るとカネ(直角)が出る。
天ぷら油を回収する時に缶ごともらってくる店がある。
穴を掘って、その一斗缶を独立基礎にする。
グラインダーで一斗缶の底もフタも切りぬく。
穴の底にコンクリートを入れた上に缶を置く。
90℃方向に二本仮の筋かいを入れて、垂直を見ながら杭で固定。
その中に柱を入れて、コンクリートを突っつきながら入れていく。
写真では分かりづらいけど、コンクリートを盛り上げて水が溜まらないようにする。
どんどんコンクリートを練っては柱を固定していく。
しょうたくんと二人でやれば余裕を持って、一日で柱が完成。
片屋根でガルバリウムの波板が一番簡単にできる。
夕方、完成と同時に雨が降ってきた。
天気が持ってくれたのもラッキー。
大根を消費するため、ほとんどの大根鍋。
畑の春菊もまだ食べられる。
本葛の葛切りが最高に美味い。
自家製のポン酢とゴマダレの両方がいい。
薬味は柚子コショウを利かせる。
人参と人参葉のかき揚げ。
何と、所々に酒粕が入ってる。
味醂と醤油の天出汁もいいし、塩もいい。
これは酒のアテにも、ご飯のお供にも最高。
タグ :ピザ窯
2013年02月26日
春の野草はやさしい味
塩釜作りはいよいよ左官職人登場。

僕としょうたくんの耐火レンガの仕上げも進んで、古いレンガの部分に左官さんが壁の下地をつけていく作業。

美しいコテさばきでサクサクと塗ってゆく。

バラス!(砕石の事)
午後からは次の現場の段取り。
随分と前に書いた、まんのう町「かぐや姫プレイパーク」のピザ窯作りの準備。
まずは2間(3、6m)×3間(5、4m)の東屋作りから。
これは基礎のコンクリートを練るための材料。

メインの材木は廃材天国にストックしてある廃材。
廃材代は取らないので安く作れる。
しょうたくんに簡単なイラストを見せて、廃材置き場からみつくろってもらう。
僕がまんのう町の現場に打ち合わせに行ってる間にテキパキとやってくれてた。
こういう段取りから完全に任せられるので、頼もしいもの。
自分の生活のための廃材建築を超えて、ヨソの現場のかけもちという予想しない展開になってきた。
う~ん、これは喜ぶべき事ではないような気もするけど、、、。
勉強になったり、楽しい面もあるから喜んでやってる。

カラシ菜の「おこめーず和え」。
ほろ苦さとドブロクの酒粕の酸味がベストマッチ。

カラスノエンドウのゴマ和え。
エグミもなく料理しやすい野草。
ウチに庭にわんさと生えてる。

土筆、メノリ、豆腐の卵とじ。
ツクシの味は春の味~。
寒くても庭の鶏は、ちゃんと毎日子どもたちが世話するので、卵を産んでくれてる。

カクテギ(大根のキムチ)。
ヤンニョムを作り置きしておくと、サッと作れる即席キムチ。

子どもたちに人気の豆乳シチュー。

美しいフキノトウも廃材の家から歩いて行ける休耕田にある。
僕としょうたくんの耐火レンガの仕上げも進んで、古いレンガの部分に左官さんが壁の下地をつけていく作業。
美しいコテさばきでサクサクと塗ってゆく。
バラス!(砕石の事)
午後からは次の現場の段取り。
随分と前に書いた、まんのう町「かぐや姫プレイパーク」のピザ窯作りの準備。
まずは2間(3、6m)×3間(5、4m)の東屋作りから。
これは基礎のコンクリートを練るための材料。
メインの材木は廃材天国にストックしてある廃材。
廃材代は取らないので安く作れる。
しょうたくんに簡単なイラストを見せて、廃材置き場からみつくろってもらう。
僕がまんのう町の現場に打ち合わせに行ってる間にテキパキとやってくれてた。
こういう段取りから完全に任せられるので、頼もしいもの。
自分の生活のための廃材建築を超えて、ヨソの現場のかけもちという予想しない展開になってきた。
う~ん、これは喜ぶべき事ではないような気もするけど、、、。
勉強になったり、楽しい面もあるから喜んでやってる。
カラシ菜の「おこめーず和え」。
ほろ苦さとドブロクの酒粕の酸味がベストマッチ。
カラスノエンドウのゴマ和え。
エグミもなく料理しやすい野草。
ウチに庭にわんさと生えてる。
土筆、メノリ、豆腐の卵とじ。
ツクシの味は春の味~。
寒くても庭の鶏は、ちゃんと毎日子どもたちが世話するので、卵を産んでくれてる。
カクテギ(大根のキムチ)。
ヤンニョムを作り置きしておくと、サッと作れる即席キムチ。
子どもたちに人気の豆乳シチュー。
美しいフキノトウも廃材の家から歩いて行ける休耕田にある。
タグ :野草
2013年02月25日
冷やすといけない
塩釜の試験燃焼も上手くいき、後は仕上げを残すのみ。

地面の裾と上の縁の仕上げの耐火レンガを築く。
その間は土壁の仕上げになる。

帰ると、久し振りに猪肉が解凍されてた。

薪ストーブの上で焼きながらみんな立ち食い。
大根おろしと醤油、自家製豆板醤も合う。

切干大根のゴマ油炒め。
味付けは醤油と味噌、隠し味にニンニク。

猪の脂で一緒に葉っぱを炒めると美味しい。
ここの所、朝昼晩と海草三昧だった。
瀬戸内の旬のワカメにメノリは最高。
でも、陰陽バランス的には海草は陰性。
やっぱり、まだまだ寒い時期にそればっかりというのは身体を冷やす。
昨日の猪肉のような超陽性のものこそ冬に向いてるとも言える。
もっとも、陰性だ陽性だとかの屁理屈よりも自分の体調との相談。
今の状態を自分で把握できないと話にならない。
で、傾向と対策が分る。
今の季節は冷えたビールより燗酒や湯割りが美味い。
夏の大汗の労働後の強制冷却が必要な時の夏野菜にビールという状態とは身体の内部ははえらい違い。
体にいいもの、悪いものという絶対的なモノは存在しない。
自分自身で大局的なバランスを計れ!
あ、冷えは確実に悪いよ♪
地面の裾と上の縁の仕上げの耐火レンガを築く。
その間は土壁の仕上げになる。
帰ると、久し振りに猪肉が解凍されてた。
薪ストーブの上で焼きながらみんな立ち食い。
大根おろしと醤油、自家製豆板醤も合う。
切干大根のゴマ油炒め。
味付けは醤油と味噌、隠し味にニンニク。
猪の脂で一緒に葉っぱを炒めると美味しい。
ここの所、朝昼晩と海草三昧だった。
瀬戸内の旬のワカメにメノリは最高。
でも、陰陽バランス的には海草は陰性。
やっぱり、まだまだ寒い時期にそればっかりというのは身体を冷やす。
昨日の猪肉のような超陽性のものこそ冬に向いてるとも言える。
もっとも、陰性だ陽性だとかの屁理屈よりも自分の体調との相談。
今の状態を自分で把握できないと話にならない。
で、傾向と対策が分る。
今の季節は冷えたビールより燗酒や湯割りが美味い。
夏の大汗の労働後の強制冷却が必要な時の夏野菜にビールという状態とは身体の内部ははえらい違い。
体にいいもの、悪いものという絶対的なモノは存在しない。
自分自身で大局的なバランスを計れ!
あ、冷えは確実に悪いよ♪
タグ :猪肉
2013年02月24日
コアラの仕事
宇多津の復元塩田の塩釜の修復工事。
コアラがいい仕事をした。

トロリーというチェーンブロックを掛ける道具。
耐火レンガの窯部分は出来てたものの、ステンレス製の釜の仕上がりを待ってた。

いよいよ完成して搬入。
入口を通らないため、斜めにして差し込む。
600㌔超という大物なので、ユニックで入口まで持っていって、中では移動式チェーンブロックで受ける。

何とか入った!

2、5m×1、8mの釜なので、かなりデカイ。

トロリーに掛けたチェーンブロックでガリガリ引き上げる。
ここからはコアラの本領発揮。
600㌔を超える釜を顔色一つかえずに持ち上げる。

無事、設置完了!

同時に新しいバーナーを取り付ける。

本番用のかん水(海水の濃度を濃くした、塩分18%のもの)ではないものの、海水を入れて試験燃焼をする準備。

バーナーの設置も完了して、満水になったんで初点火!

塩作りの職人さんたちに見てもらいながら、今までの釜の沸き具合との違いを確かめてもらう。

窯内部の構造を大幅に変えたにもかかわらず、うまく沸いたので一安心。
これで沸く時間がおお幅に延びるようなら、もう一度コアラで釜を持ち上げて、窯にもぐりこんで内部の構造を変更する所まで想定してた。
それも杞憂に終わり、感無量。
暗くなって家路につくと、あっこちゃんも留守にしてたみたいで、子どもたち3人だけだった。
何と、風呂を焚いて、洗濯物をたたみ、3人で料理もしてたよう。
煮物と蒸した玄米ご飯を3人仲良く食べてた。
何でもこなすようになったと普段から感心してたけど、全く大人が居なくてここまでやってるのを目の当たりにすると、僕でもビックリした。
野遊は最近では毎日学校に行き、宿題もこなしてるものの、改めてホームスクーリングの力を思い知らされた。
学校に行く、行かない、会社に行く、行かない、それだけじゃない。
自由で開放されると、こういう事になるんやなー、と感慨深い。
コアラがいい仕事をした。
トロリーというチェーンブロックを掛ける道具。
耐火レンガの窯部分は出来てたものの、ステンレス製の釜の仕上がりを待ってた。
いよいよ完成して搬入。
入口を通らないため、斜めにして差し込む。
600㌔超という大物なので、ユニックで入口まで持っていって、中では移動式チェーンブロックで受ける。
何とか入った!
2、5m×1、8mの釜なので、かなりデカイ。
トロリーに掛けたチェーンブロックでガリガリ引き上げる。
ここからはコアラの本領発揮。
600㌔を超える釜を顔色一つかえずに持ち上げる。
無事、設置完了!
同時に新しいバーナーを取り付ける。
本番用のかん水(海水の濃度を濃くした、塩分18%のもの)ではないものの、海水を入れて試験燃焼をする準備。
バーナーの設置も完了して、満水になったんで初点火!
塩作りの職人さんたちに見てもらいながら、今までの釜の沸き具合との違いを確かめてもらう。
窯内部の構造を大幅に変えたにもかかわらず、うまく沸いたので一安心。
これで沸く時間がおお幅に延びるようなら、もう一度コアラで釜を持ち上げて、窯にもぐりこんで内部の構造を変更する所まで想定してた。
それも杞憂に終わり、感無量。
暗くなって家路につくと、あっこちゃんも留守にしてたみたいで、子どもたち3人だけだった。
何と、風呂を焚いて、洗濯物をたたみ、3人で料理もしてたよう。
煮物と蒸した玄米ご飯を3人仲良く食べてた。
何でもこなすようになったと普段から感心してたけど、全く大人が居なくてここまでやってるのを目の当たりにすると、僕でもビックリした。
野遊は最近では毎日学校に行き、宿題もこなしてるものの、改めてホームスクーリングの力を思い知らされた。
学校に行く、行かない、会社に行く、行かない、それだけじゃない。
自由で開放されると、こういう事になるんやなー、と感慨深い。
タグ :窯
2013年02月23日
ワカメパーティー
採りにいったワカメが小さかったけど、旬を味わいたい。

ということで、宇多津産直の「魚の大空」でメカブ、茎ワカメ、ワカメを仕入れた。

薪ストーブの上で茹でる。
サッと一瞬で美しいグリーンになる。
メノリも底値になり、またまた大量に仕入れてしまったので、佃煮にする。
今年はメノリをよく炊いた。

茎ワカメは茹でた後、細く切る。
メカブは茎と切り離す。

メカブの酢醤油漬け。
米酢とユズ酢と本醸造醤油に漬けこむ。

茎ワカメも酢醤油につける。
ちょっと雰囲気を変えるために、針ショウガを加える。

後の半分は味醂と醤油で甘辛く煮た後、和辛子で和える。
茎ワカメは少々のエグミもあって、濃いので濃い目の味付けが合う。

ワカメと大根のサラダ。
まだ大根が生で食べられる。
軽く塩もみした大根とワカメの相性は抜群。

ワカメネギ焼き。
限りなく少なめの粉で薄く焼くのがポイント。
鰹節とポン酢で最高のアテになる。

寒さも極まって、ホウレン草が超甘くなってきた。
化学肥料を使ったシュウ酸たっぷりのと違って、灰汁も少なくて美味しい。
ホウレン草って他の葉物と違って、特別感がある。
お浸し、ゴマ和えも美味しいし、洋風料理にも合う。
豆乳でホワイトソースのシチューやグラタン、カレーにもいい。
一年中、目まぐるしく気候の変わる日本。
今のこの瀬戸内の旬は何と言っても、海草!
そろそろ野草も食べられるし、筍も待ち遠しい。
手作りにちょっと時間をあてるだけで、何という豊かな食生活がおくれるのか。
特別に素晴らしい土地や場所があるのではない。
どこでも素晴らしい。
それは自分の在り方なのだ。
「自分次第」が一番しっくり来るのが「食」。
自分の住んでる所の利を最大限享受する。
旬の地域の伝統食を味わう。
たまにマクロビオティックのレストランに行ってもダメダメ。
自分の生活に取り入れてこそ「食生活」と呼べるのだ。
「生活食」の方がしっくり来るかも。
ということで、宇多津産直の「魚の大空」でメカブ、茎ワカメ、ワカメを仕入れた。
薪ストーブの上で茹でる。
サッと一瞬で美しいグリーンになる。
メノリも底値になり、またまた大量に仕入れてしまったので、佃煮にする。
今年はメノリをよく炊いた。
茎ワカメは茹でた後、細く切る。
メカブは茎と切り離す。
メカブの酢醤油漬け。
米酢とユズ酢と本醸造醤油に漬けこむ。
茎ワカメも酢醤油につける。
ちょっと雰囲気を変えるために、針ショウガを加える。
後の半分は味醂と醤油で甘辛く煮た後、和辛子で和える。
茎ワカメは少々のエグミもあって、濃いので濃い目の味付けが合う。
ワカメと大根のサラダ。
まだ大根が生で食べられる。
軽く塩もみした大根とワカメの相性は抜群。
ワカメネギ焼き。
限りなく少なめの粉で薄く焼くのがポイント。
鰹節とポン酢で最高のアテになる。
寒さも極まって、ホウレン草が超甘くなってきた。
化学肥料を使ったシュウ酸たっぷりのと違って、灰汁も少なくて美味しい。
ホウレン草って他の葉物と違って、特別感がある。
お浸し、ゴマ和えも美味しいし、洋風料理にも合う。
豆乳でホワイトソースのシチューやグラタン、カレーにもいい。
一年中、目まぐるしく気候の変わる日本。
今のこの瀬戸内の旬は何と言っても、海草!
そろそろ野草も食べられるし、筍も待ち遠しい。
手作りにちょっと時間をあてるだけで、何という豊かな食生活がおくれるのか。
特別に素晴らしい土地や場所があるのではない。
どこでも素晴らしい。
それは自分の在り方なのだ。
「自分次第」が一番しっくり来るのが「食」。
自分の住んでる所の利を最大限享受する。
旬の地域の伝統食を味わう。
たまにマクロビオティックのレストランに行ってもダメダメ。
自分の生活に取り入れてこそ「食生活」と呼べるのだ。
「生活食」の方がしっくり来るかも。
タグ :ワカメ
2013年02月21日
野遊の誕生日
野遊11歳の誕生日。
好奇心旺盛で、ウチ生活コンテンツはなんでもこなす長男。
これからどんなんなるんか楽しみ。
どうなっても彼自身が納得する人生を選択してくれるのが僕ら夫婦の最大の望み。
大きなったら、外国に旅をしたり、都会の生活も体験すればいい。
「自分で選ぶ」という自由な環境を約束するのが親の仕事だ。

従兄のイッサも来て誕生日パーティー。
野遊のリクエストはステーキ!
いつもの豆腐ステーキや大根ステーキと違って、本物の牛肉のステーキ。
放し飼いで、草しか食べさせてない牛さんの肉。
折角たまに食べるなら品質を選びたい。
大人は豚しゃぶ。
今回は間に合わなかったけど、江迎町の「ハッピーポーク」という素晴らしい生産者をしょうたくんが教えてくれた。
http://ajisaishizenmura.com/
「味菜自然村」という生産者のサイト
完全に放し飼いの豚さん。
YOU TUBEで竹藪を走りまくる様子や母豚のおっぱいを吸う赤ちゃん豚の様子がある
ここでは自然分娩で母豚が子育てをしてる。
抗鬱剤の投与もなければ、配合飼料のようなわけの分らないものはここの豚さんには無縁。
「家畜福祉」という言葉がヨーロッパでは当たり前のよう。
鶏のケージ飼いが禁止されてたりと日本では考えられない。
http://www.youtube.com/watch?v=yyHHFijwO_o
畜産の現場はこの「ミートリックス」(マトリックスのパロディーアニメ)が面白い。

あっこバースデーケーキでお祝い。

ゆかりちゃんのレモンケーキ、土歩のみたらし団子も登場して盛りだくさん。

砂糖、卵、乳製品ナシ、自家製甘酒だけで甘味をつけたマクロビケーキ。

土歩が作ったみたらし団子。
黒練ゴマもみたらし餡も自家製米飴で甘味をつけてる。

大人も群がってお相伴にあやかった。
好奇心旺盛で、ウチ生活コンテンツはなんでもこなす長男。
これからどんなんなるんか楽しみ。
どうなっても彼自身が納得する人生を選択してくれるのが僕ら夫婦の最大の望み。
大きなったら、外国に旅をしたり、都会の生活も体験すればいい。
「自分で選ぶ」という自由な環境を約束するのが親の仕事だ。
従兄のイッサも来て誕生日パーティー。
野遊のリクエストはステーキ!
いつもの豆腐ステーキや大根ステーキと違って、本物の牛肉のステーキ。
放し飼いで、草しか食べさせてない牛さんの肉。
折角たまに食べるなら品質を選びたい。
大人は豚しゃぶ。
今回は間に合わなかったけど、江迎町の「ハッピーポーク」という素晴らしい生産者をしょうたくんが教えてくれた。
http://ajisaishizenmura.com/
「味菜自然村」という生産者のサイト
完全に放し飼いの豚さん。
YOU TUBEで竹藪を走りまくる様子や母豚のおっぱいを吸う赤ちゃん豚の様子がある
ここでは自然分娩で母豚が子育てをしてる。
抗鬱剤の投与もなければ、配合飼料のようなわけの分らないものはここの豚さんには無縁。
「家畜福祉」という言葉がヨーロッパでは当たり前のよう。
鶏のケージ飼いが禁止されてたりと日本では考えられない。
http://www.youtube.com/watch?v=yyHHFijwO_o
畜産の現場はこの「ミートリックス」(マトリックスのパロディーアニメ)が面白い。
あっこバースデーケーキでお祝い。
ゆかりちゃんのレモンケーキ、土歩のみたらし団子も登場して盛りだくさん。
砂糖、卵、乳製品ナシ、自家製甘酒だけで甘味をつけたマクロビケーキ。
土歩が作ったみたらし団子。
黒練ゴマもみたらし餡も自家製米飴で甘味をつけてる。
大人も群がってお相伴にあやかった。
タグ :誕生日
2013年02月20日
干し大根葉
さぶいけど、もう春になろうとしてる。

畑の大根もたくさんあるのに、食べきれない。
たくあん漬けも3回に分けて十分作ったし。

葉をはねて本体だけにする。
こうすることでトウ立ちするのを遅らせられる。
ちょっとでも、スカスカになるのが先延ばしになり、長く食べられる。
大根葉が大量に出た。
外の黄色くなりつつある部分は鶏小屋に放り込み、いい部分だけを茹でる。
大根葉のお好み焼きもいい加減食べたし。

干すことにした。

まだフニャッとしてるけど、ある程度干せた。

これは今朝の味噌汁。
味噌は各自食べる直前に入れる方式。
子どもたちは薄味、僕のような労働者は濃い味なので、好みの味付けにできるのがいい。
更にいいのは鍋で高温になって味噌の酵素が失われることがない所。
益々いいのは残った味噌汁って味噌の風味がなくなって不味くなるけど、それもない。
お昼はショウガのすりおろしとナンプラーでエスニック風スープにしてもいい。
話がそれたけど、干し大根葉は予想を上回る美味しさ。
昨日は鍋に入れたけど、生だと人気の低い大根葉が甘味があって濃くって美味しい。
切り干し大根が甘くて美味しくなるんやから、当然かもしれんけど、以外な程美味しい。
何より大根葉を無駄にすることなく、利用できたのが嬉しい。
それも、もったいないから何とか食べてしまおうという無理やり感じゃなく、美味しいのがよかった。
相当あるんで、これの素晴らしいレシピ開発が望まれる。
畑の大根もたくさんあるのに、食べきれない。
たくあん漬けも3回に分けて十分作ったし。
葉をはねて本体だけにする。
こうすることでトウ立ちするのを遅らせられる。
ちょっとでも、スカスカになるのが先延ばしになり、長く食べられる。
大根葉が大量に出た。
外の黄色くなりつつある部分は鶏小屋に放り込み、いい部分だけを茹でる。
大根葉のお好み焼きもいい加減食べたし。
干すことにした。
まだフニャッとしてるけど、ある程度干せた。
これは今朝の味噌汁。
味噌は各自食べる直前に入れる方式。
子どもたちは薄味、僕のような労働者は濃い味なので、好みの味付けにできるのがいい。
更にいいのは鍋で高温になって味噌の酵素が失われることがない所。
益々いいのは残った味噌汁って味噌の風味がなくなって不味くなるけど、それもない。
お昼はショウガのすりおろしとナンプラーでエスニック風スープにしてもいい。
話がそれたけど、干し大根葉は予想を上回る美味しさ。
昨日は鍋に入れたけど、生だと人気の低い大根葉が甘味があって濃くって美味しい。
切り干し大根が甘くて美味しくなるんやから、当然かもしれんけど、以外な程美味しい。
何より大根葉を無駄にすることなく、利用できたのが嬉しい。
それも、もったいないから何とか食べてしまおうという無理やり感じゃなく、美味しいのがよかった。
相当あるんで、これの素晴らしいレシピ開発が望まれる。
タグ :大根葉
2013年02月19日
今年も姫さんの野草教室やるよ
野草の季節になってきた。
3/16(土)、17(日)は岡山の姫さんを招いての「野草教室」。
16日の会場は廃材の家。
17の会場は粟島という2日連続。
まず、姫さんを散策して、野草の採集。
それらの処理&料理+野草パーティーという豪華版。
http://kadoya.ashita-sanuki.jp/e529516.html
これが去年の3月の様子。
3/16(土) 9:30~14:00(昼から野草料理でランチ+あっこスイーツ)
(廃材天国) 16:00~20:30(夜は野草料理宴会)
参加費 昼の部 3000円
夜の部 3000円(お酒飲みたい人は純米酒持参)
両方 5000円
17(日) 13:00~19:00
(粟島) 詳細は未定(岩佐さんの海遊荘に宿泊も可)
野草+海辺の散策もあるかも!(姫さんは海洋生物学のフィールドワークにも長けてるのだ)
いやいやいや!
今年はデラックスですなーーー。
凄いでーーー。
その辺りを散歩して食べられるもんが山ほどあるんやで。
しかも、市街地郊外の開発地帯の丸亀でさえ!
姫さんを招いての野草教室&パーティーは年に一回。
彼女の姿勢はほんまに凄いよー!
申し込みは haizaitengoku@gmail.com まで
3/16(土)、17(日)は岡山の姫さんを招いての「野草教室」。
16日の会場は廃材の家。
17の会場は粟島という2日連続。
まず、姫さんを散策して、野草の採集。
それらの処理&料理+野草パーティーという豪華版。
http://kadoya.ashita-sanuki.jp/e529516.html
これが去年の3月の様子。
3/16(土) 9:30~14:00(昼から野草料理でランチ+あっこスイーツ)
(廃材天国) 16:00~20:30(夜は野草料理宴会)
参加費 昼の部 3000円
夜の部 3000円(お酒飲みたい人は純米酒持参)
両方 5000円
17(日) 13:00~19:00
(粟島) 詳細は未定(岩佐さんの海遊荘に宿泊も可)
野草+海辺の散策もあるかも!(姫さんは海洋生物学のフィールドワークにも長けてるのだ)
いやいやいや!
今年はデラックスですなーーー。
凄いでーーー。
その辺りを散歩して食べられるもんが山ほどあるんやで。
しかも、市街地郊外の開発地帯の丸亀でさえ!
姫さんを招いての野草教室&パーティーは年に一回。
彼女の姿勢はほんまに凄いよー!
申し込みは haizaitengoku@gmail.com まで
タグ :野草
2013年02月18日
海鼠腸
「魚の大空」からナマコを仕入れた。

超巨大サイズ。
オマケにコノワタももらった。

このナマコのコノワタもギッシリ。

腸の中に詰まった泥を掃除する。

こんな感じ。

ヒラヒラの部分は掃除が簡単。

宇多津の復元塩田の塩でコノワタの塩辛を作る。

掃除したコノワタに15%ぐらいの強塩を混ぜる。
それで完成。

イイダコも仕入れた。

天ぷらが最高!

ナマコはやはり大根おろしとポン酢。

大量に採ったカメノテをワカメとサラダ風にした。
キャンプの時に採ったカメノテはここまで手間かけて料理しないから人気がなかった。
ここまでやるとちゃんとした食材として成り立つ。
一つ一つカメノテの殻から身を出す手仕事のスロー作業がまたいい。

まだカボチャがある。
カメノテやナマコよりも子どもたちにはこういう料理の方が人気。
スローライフとは手をとめずに延々とコツコツと作業して、出来る仕事のペースがスローという事。
作業もせずにお茶飲みながらお喋りするのはスローライフとは対極。
ポイントはノルマでもないし、他人に言われれする仕事でもないし、お金のためでもない。
当たり前の日常の作業をこなすこと。
こういう日々で完結できるというのが要。
見果てぬ遠くに夢や目的があるんじゃあないぞ。
夢は実現してる。
こういう暇つぶしをやってる間に人生あっという間。
超巨大サイズ。
オマケにコノワタももらった。
このナマコのコノワタもギッシリ。
腸の中に詰まった泥を掃除する。
こんな感じ。
ヒラヒラの部分は掃除が簡単。
宇多津の復元塩田の塩でコノワタの塩辛を作る。
掃除したコノワタに15%ぐらいの強塩を混ぜる。
それで完成。
イイダコも仕入れた。
天ぷらが最高!
ナマコはやはり大根おろしとポン酢。
大量に採ったカメノテをワカメとサラダ風にした。
キャンプの時に採ったカメノテはここまで手間かけて料理しないから人気がなかった。
ここまでやるとちゃんとした食材として成り立つ。
一つ一つカメノテの殻から身を出す手仕事のスロー作業がまたいい。
まだカボチャがある。
カメノテやナマコよりも子どもたちにはこういう料理の方が人気。
スローライフとは手をとめずに延々とコツコツと作業して、出来る仕事のペースがスローという事。
作業もせずにお茶飲みながらお喋りするのはスローライフとは対極。
ポイントはノルマでもないし、他人に言われれする仕事でもないし、お金のためでもない。
当たり前の日常の作業をこなすこと。
こういう日々で完結できるというのが要。
見果てぬ遠くに夢や目的があるんじゃあないぞ。
夢は実現してる。
こういう暇つぶしをやってる間に人生あっという間。
タグ :海鼠
2013年02月17日
ワカメの採集
ワカメ採りに行ってきた。

瀬戸大橋のかかる沙弥島に。

今の時期は大潮でも午前中がよく引くんだとか。

あるにはあったけど、まだ小さい。

カメノテが豊富にいた。

ワカメ採り用のカマでコロニーごとゴソッと採る。

これは陣笠という貝。
たくさんいたんで、何十個も採った。

採集だけでなく、海にいくこと自体が楽しい。

奥にしょうたくんがいる。
かなり深い洞窟。

帰ってから、親父の陶芸の窯用の薪割り機を借りて薪割り。
直径40㎝で長さ60㎝までの丸太なら割らずに焚ける自作薪ストーブ。
それより大きいのは斧で割ったりしてる。
さすがに、このクラスになると人力では無理。
このエンジンの薪割り機は22tという油圧のパワーでメキメキと割ってくれる。

こういう超デッカイのをためてたのを一気に割ってしまう。

夕方、友達の家に遊びに行ってた子どもたちが帰ってきて、運んでくれる。

カメノテとワケギの酢味噌和え。
これは絶品!
ワカメはサッとボイルして大根おろしとポン酢で頂いた。
瀬戸内海最高!!!
瀬戸大橋のかかる沙弥島に。
今の時期は大潮でも午前中がよく引くんだとか。
あるにはあったけど、まだ小さい。
カメノテが豊富にいた。
ワカメ採り用のカマでコロニーごとゴソッと採る。
これは陣笠という貝。
たくさんいたんで、何十個も採った。
採集だけでなく、海にいくこと自体が楽しい。
奥にしょうたくんがいる。
かなり深い洞窟。
帰ってから、親父の陶芸の窯用の薪割り機を借りて薪割り。
直径40㎝で長さ60㎝までの丸太なら割らずに焚ける自作薪ストーブ。
それより大きいのは斧で割ったりしてる。
さすがに、このクラスになると人力では無理。
このエンジンの薪割り機は22tという油圧のパワーでメキメキと割ってくれる。
こういう超デッカイのをためてたのを一気に割ってしまう。
夕方、友達の家に遊びに行ってた子どもたちが帰ってきて、運んでくれる。
カメノテとワケギの酢味噌和え。
これは絶品!
ワカメはサッとボイルして大根おろしとポン酢で頂いた。
瀬戸内海最高!!!
タグ :ワカメ
2013年02月15日
キムチ作り教室
あっこ料理教室のお知らせ。
今回はキムチ。
本格的なコリアンレシピにはアミの塩辛とか、無添加で手に入りにくいものがあって難しい。
あっこレシピはベジキムチ。
ナンプラーも入れない。
ナンプラー好きの僕としては、「ベジにこだわるのもええかえど、本格派キムチとはまた別モノやろ。」と甘く見てた。
ところが!
ベジとアナドルなかれ。
最近のあっこキムチは本格派コリアンレシピのそれを凌駕する仕上がり。
あっこちゃんのキムチは松見歯科の「無何有庵」直伝レシピを自分のものにしてる。
毎年漬けてるけど、今年になって教えてほしいとリクエストが度々。
なんちゃって派の僕と違って、彼女は慎重派。
注文販売のあっこスイーツも試作を重ね、寝る間も惜しんでコツコツと作る。
その彼女が教室にキムチを出すということはなかなか自信があるよう。
まず、うちの家族は大絶賛。
来る客にも出すけど、やはり大絶賛。
彼女としては、みんなが喜んでくれるのが一番だそうな。
しかも、無添加だし入手困難な材料も使わない。
一回覚えれば毎年できるし、ヤンニョムは一度にたくさん作って冷凍しておけば、白菜を漬けるだけなのでで簡単にできる。
「こんな素晴らしいものは是非伝えないと!」という想い。
ナンプラーやアミエビなどの強烈な旨味がなくて、ナゼここまで美味いのか?
その秘密は松の実や干し柿にもあるけど、味の深みに一番影響するのは発酵の具合。
まず、白菜の塩漬けが重要。
この段階での発酵具合が仕上がりに多大な貢献をする。
もちろん本漬けのヤンニョム(キムチの素)も大事。
ヤンニョムの内容は来てのお楽しみ。

まず、白菜は4分の1に切って、半日干す。
干し過ぎはよくないけど、適度に干すことで味が濃くなる。

4日~1週間漬ける。

これが完成品。

野遊のリクエストで学校の弁当にも入れてる。
大根の煮物、大根葉のお好み焼き、たくあん漬けという大根づくし。
冬の野菜がトウ立ちを始め、菜花のゴマ和えが美しい。
2/17(日) 10:00~12:00
参加費 5000円
まず、白菜の塩漬け。
その後、ヤンニョム作り。
予め漬けておいた白菜の塩漬けにヤンニョムを塗って、持って帰って熟成。
一人あたり白菜半分なので、後先着2名という狭い門になってしまった。
お昼からは出来てるキムチと玄米ご飯でみんなでランチ。
今回もあっこ料理教室は子どもたちと一緒に作るので、子ども連れOK。
申込みはhaizaitengoku@gmail.comまで!
今回はキムチ。
本格的なコリアンレシピにはアミの塩辛とか、無添加で手に入りにくいものがあって難しい。
あっこレシピはベジキムチ。
ナンプラーも入れない。
ナンプラー好きの僕としては、「ベジにこだわるのもええかえど、本格派キムチとはまた別モノやろ。」と甘く見てた。
ところが!
ベジとアナドルなかれ。
最近のあっこキムチは本格派コリアンレシピのそれを凌駕する仕上がり。
あっこちゃんのキムチは松見歯科の「無何有庵」直伝レシピを自分のものにしてる。
毎年漬けてるけど、今年になって教えてほしいとリクエストが度々。
なんちゃって派の僕と違って、彼女は慎重派。
注文販売のあっこスイーツも試作を重ね、寝る間も惜しんでコツコツと作る。
その彼女が教室にキムチを出すということはなかなか自信があるよう。
まず、うちの家族は大絶賛。
来る客にも出すけど、やはり大絶賛。
彼女としては、みんなが喜んでくれるのが一番だそうな。
しかも、無添加だし入手困難な材料も使わない。
一回覚えれば毎年できるし、ヤンニョムは一度にたくさん作って冷凍しておけば、白菜を漬けるだけなのでで簡単にできる。
「こんな素晴らしいものは是非伝えないと!」という想い。
ナンプラーやアミエビなどの強烈な旨味がなくて、ナゼここまで美味いのか?
その秘密は松の実や干し柿にもあるけど、味の深みに一番影響するのは発酵の具合。
まず、白菜の塩漬けが重要。
この段階での発酵具合が仕上がりに多大な貢献をする。
もちろん本漬けのヤンニョム(キムチの素)も大事。
ヤンニョムの内容は来てのお楽しみ。
まず、白菜は4分の1に切って、半日干す。
干し過ぎはよくないけど、適度に干すことで味が濃くなる。
4日~1週間漬ける。
これが完成品。
野遊のリクエストで学校の弁当にも入れてる。
大根の煮物、大根葉のお好み焼き、たくあん漬けという大根づくし。
冬の野菜がトウ立ちを始め、菜花のゴマ和えが美しい。
2/17(日) 10:00~12:00
参加費 5000円
まず、白菜の塩漬け。
その後、ヤンニョム作り。
予め漬けておいた白菜の塩漬けにヤンニョムを塗って、持って帰って熟成。
一人あたり白菜半分なので、後先着2名という狭い門になってしまった。
お昼からは出来てるキムチと玄米ご飯でみんなでランチ。
今回もあっこ料理教室は子どもたちと一緒に作るので、子ども連れOK。
申込みはhaizaitengoku@gmail.comまで!
タグ :キムチ
2013年02月14日
キャスタブル
塩釜の窯がほとんど見えてきた。

耐火レンガ積みは終了。

ステンレスの釜が乗る窯部分の上はキャスタブル(耐火セメント)でレベルを出す。
これはそのための型枠。

ドローッと流しこむ。

練ったキャスタブルが余ったので、急いで家に帰って窯の正面のバーナーの口部分を作る。
しょうたくんに枠を作ってもらって、流しこむ。
バーナーの口部分にコンクリートのテストピースがピッタリ合ってラッキー。

更に余って、今度は五右衛門風呂の焚き口の修理を思いついた。
何か月も前から徐々に穴が広がりつつあったのを「そろそろ直さななー。」と思いながら毎日焚いてた。

錬るのと道具を洗うのを入れても30分もあれば終わる作業だけに、「いつでも出来るわ。」とやらずにいた。
こういうタイミングでやっつけで終わらせられるのが喜ばしい。

カブや大根の葉を豆乳クリーム仕立てにして、パイ生地を乗せたキッシュ。

しょうたくんの誕生日カレーの残りをオカユパンにつけて食べる。

バジルソースを練りこんだバージョン。
耐火レンガ積みは終了。
ステンレスの釜が乗る窯部分の上はキャスタブル(耐火セメント)でレベルを出す。
これはそのための型枠。
ドローッと流しこむ。
練ったキャスタブルが余ったので、急いで家に帰って窯の正面のバーナーの口部分を作る。
しょうたくんに枠を作ってもらって、流しこむ。
バーナーの口部分にコンクリートのテストピースがピッタリ合ってラッキー。
更に余って、今度は五右衛門風呂の焚き口の修理を思いついた。
何か月も前から徐々に穴が広がりつつあったのを「そろそろ直さななー。」と思いながら毎日焚いてた。
錬るのと道具を洗うのを入れても30分もあれば終わる作業だけに、「いつでも出来るわ。」とやらずにいた。
こういうタイミングでやっつけで終わらせられるのが喜ばしい。
カブや大根の葉を豆乳クリーム仕立てにして、パイ生地を乗せたキッシュ。
しょうたくんの誕生日カレーの残りをオカユパンにつけて食べる。
バジルソースを練りこんだバージョン。
タグ :窯
2013年02月13日
「自分の仕事をつくる」
2日休みの後の塩釜の窯作り現場は延々と耐火レンガ積み。
一つ一つがバラバラのレンガを積んで、形になっていくのは即興性の強い面白い作業。
廃材天国での自分たち家族の生活のための仕事と、こういうヨソの作業では自分の中に違いはあるか?
以前はあった。
無意識にも、「自分のための仕事」と「他人に頼まれた仕事」という区別があったように思う。
今は、これは自分の生活のために必要な労働だから楽しいけど、これはお金を稼ぐための割り切った仕事という区別はない。
自給自足での左ウチワ自画杜撰生活を実現してしまったからというのもある。
月々決まったペイがなく、生活費がほとんど要らないんやから、「いくら稼がないといけない。」という切迫感がない。
そんな金の話よりも大事な事は、その「仕事」が本当に「自分の仕事」かどうかだ。
ともすれば「自分の家を作ったり田んぼや畑などの手作り作業は楽しいけど、 自給自足では金にならないからたまにはバイトで現金収入を。」となってしまう。
そういう矛盾の事をダブルバインド(二重拘束)という。
例えば、さっきまで感動で涙を流した映画の帰りに親が前の車にイラついてクラクション長押しするような。
純粋な子どもはその矛盾についていけない。
過剰包装の健康「的」な食品や、広告に金かけまくる環境「的」な商品。
「癒し」とやらに金を払う社会。
それらは完全に本質を欠いている。
「自分の仕事」とは自分が満足しないと意味がない。
自己満足とは初歩のステップとして必要不可欠。
徹底的にそれを貫くと、周りも満足し始める。
結果的に生活が成り立ったり、金になる。
これが本質だ。

この西村さんの本おススメ。
いわゆる自給自足系や環境系じゃなく、デザインとかプロダクトの現場の第一人者たちにインタビューしてる。
でも、内容は極めて本質をついてる。
「自分の仕事をつくる。」とは生きるための当たり前の事。
全力を出し切り、自分を最大限に活す状態。
実は余裕を持って、力が抜けた状態。
西村さんの著書は多いんで、他のも読みたい!
一つ一つがバラバラのレンガを積んで、形になっていくのは即興性の強い面白い作業。
廃材天国での自分たち家族の生活のための仕事と、こういうヨソの作業では自分の中に違いはあるか?
以前はあった。
無意識にも、「自分のための仕事」と「他人に頼まれた仕事」という区別があったように思う。
今は、これは自分の生活のために必要な労働だから楽しいけど、これはお金を稼ぐための割り切った仕事という区別はない。
自給自足での左ウチワ自画杜撰生活を実現してしまったからというのもある。
月々決まったペイがなく、生活費がほとんど要らないんやから、「いくら稼がないといけない。」という切迫感がない。
そんな金の話よりも大事な事は、その「仕事」が本当に「自分の仕事」かどうかだ。
ともすれば「自分の家を作ったり田んぼや畑などの手作り作業は楽しいけど、 自給自足では金にならないからたまにはバイトで現金収入を。」となってしまう。
そういう矛盾の事をダブルバインド(二重拘束)という。
例えば、さっきまで感動で涙を流した映画の帰りに親が前の車にイラついてクラクション長押しするような。
純粋な子どもはその矛盾についていけない。
過剰包装の健康「的」な食品や、広告に金かけまくる環境「的」な商品。
「癒し」とやらに金を払う社会。
それらは完全に本質を欠いている。
「自分の仕事」とは自分が満足しないと意味がない。
自己満足とは初歩のステップとして必要不可欠。
徹底的にそれを貫くと、周りも満足し始める。
結果的に生活が成り立ったり、金になる。
これが本質だ。
この西村さんの本おススメ。
いわゆる自給自足系や環境系じゃなく、デザインとかプロダクトの現場の第一人者たちにインタビューしてる。
でも、内容は極めて本質をついてる。
「自分の仕事をつくる。」とは生きるための当たり前の事。
全力を出し切り、自分を最大限に活す状態。
実は余裕を持って、力が抜けた状態。
西村さんの著書は多いんで、他のも読みたい!
タグ :本
2013年02月12日
建国記念誕生日会
2月11日は「建国記念の日」の祝日だった。
何と、この日はしょうたくんの誕生日でもある。
塩釜の窯作り現場は週休二日にしてるので、昨日も休み。
薪生活での自給自足において、ヨソに仕事に行くならこのぐらいが丁度いい。
大工さんなどの職人の休みは日曜日だけ、祝日も関係ないというのが普通。
2日休みがあると色んな事ができる。
廃天ぷら油の回収&精製
薪ストーブの薪の積み込み
コンポストトイレのウンコの堆肥化
菜園の世話
手作りの保存食系の作業
セルフ散髪
手打ちうどん
タコパー
などなど、、、。
この二日間はしょうたくんは野遊と二人で工房で作陶してる。
手捻りでカップ作ったり、何と電動ロクロにも挑戦してる。
野遊の方が上手いみたいやけど。

しょうたくんの友達がインドからお土産にスパイスを買ってきてくれたそう。
これで、カレーパーティーという流れになった。
他にも、カルダモン、マスタードシード、コショウなど色々入ってるみたい。

タイで買ってきたスパイス潰しで、ニンニク、ショウガを潰す。

トマトソースの赤いカレーと、ホウレン草とカブの葉のグリーンカレー。

猪肉のカツも作った。
薪ストーブでの強火料理の世話をしてると暑くなりすぎるのが玉にキズ。
贅沢な悩みやけど、ほんとに気持ち悪くなってくるんで、真剣に改善策を考え中。

二種類のカレーと猪カツという最高の誕生日会になった。
マル秘のお米ドリンクもいい感じの仕上がりをみせた。
建国記念の日とは神武天皇が即位したとされる、神話から来てる。
ソモソモ、神武天皇はいたのか?とか、2/11に建国したという証拠はない、とかいう論議はナンセンス。
神話とは宮司さんの祝詞の設定なのだ。
その設定上にこの国の歴史がある。
ソレは否定しようのない事実。
間違いなく今の日本という国があるには、神道なり天皇は必要不可欠な要素。
それが国家神道とかいうことになると右翼扱いされる。
脱原発や反戦、環境運動、反体制、自由、、、こういう方向は左翼的とされる。
まあ、そんなのは一般的な見解。
愛国心のある反戦平和思想があってもいい。
いや、思想じゃない。
平和行動であり、平和生活なのだ!
何と、この日はしょうたくんの誕生日でもある。
塩釜の窯作り現場は週休二日にしてるので、昨日も休み。
薪生活での自給自足において、ヨソに仕事に行くならこのぐらいが丁度いい。
大工さんなどの職人の休みは日曜日だけ、祝日も関係ないというのが普通。
2日休みがあると色んな事ができる。
廃天ぷら油の回収&精製
薪ストーブの薪の積み込み
コンポストトイレのウンコの堆肥化
菜園の世話
手作りの保存食系の作業
セルフ散髪
手打ちうどん
タコパー
などなど、、、。
この二日間はしょうたくんは野遊と二人で工房で作陶してる。
手捻りでカップ作ったり、何と電動ロクロにも挑戦してる。
野遊の方が上手いみたいやけど。
しょうたくんの友達がインドからお土産にスパイスを買ってきてくれたそう。
これで、カレーパーティーという流れになった。
他にも、カルダモン、マスタードシード、コショウなど色々入ってるみたい。
タイで買ってきたスパイス潰しで、ニンニク、ショウガを潰す。
トマトソースの赤いカレーと、ホウレン草とカブの葉のグリーンカレー。
猪肉のカツも作った。
薪ストーブでの強火料理の世話をしてると暑くなりすぎるのが玉にキズ。
贅沢な悩みやけど、ほんとに気持ち悪くなってくるんで、真剣に改善策を考え中。
二種類のカレーと猪カツという最高の誕生日会になった。
マル秘のお米ドリンクもいい感じの仕上がりをみせた。
建国記念の日とは神武天皇が即位したとされる、神話から来てる。
ソモソモ、神武天皇はいたのか?とか、2/11に建国したという証拠はない、とかいう論議はナンセンス。
神話とは宮司さんの祝詞の設定なのだ。
その設定上にこの国の歴史がある。
ソレは否定しようのない事実。
間違いなく今の日本という国があるには、神道なり天皇は必要不可欠な要素。
それが国家神道とかいうことになると右翼扱いされる。
脱原発や反戦、環境運動、反体制、自由、、、こういう方向は左翼的とされる。
まあ、そんなのは一般的な見解。
愛国心のある反戦平和思想があってもいい。
いや、思想じゃない。
平和行動であり、平和生活なのだ!
タグ :カレー
2013年02月11日
お地蔵さまのひとりごと展
藤原仙人掌(さぼてん)という友達がいる。
「お地蔵さまのひとりごと」という墨絵と木彫を手掛ける作家。
筆文字のロゴ作成
表札、木彫看板作成
篆刻(石に彫るハンコの事)
兵庫の豊岡の山中でカマドのある古民家で薪生活の自給自足を営んでる。
ウチよりも子どもたちの小さい家族。
6、7年前一軒目の廃材ハウスに来廃してくれた。
その時は丸亀で個展を開いていた。

久し振りの今回は観音寺の「むすび」というお店で。
2/10(日)~3/3(日)
10:00~17:00
(定休日 2/15、18、22、23、25、3/1)
作家在廊日2/10、3/2、3
心からだに優しい店 むすび
観音寺市観音寺町甲1087-107
090-4500-3977
観音寺の駅から橋を渡って、郵便局の裏辺りの店。

狭い店ながら、作品がたくさん並んで見応えがある。

建具の古いので額を作り、古い着物を丁寧に裏張りしてる。

てんつくマンの弟子の「路上詩人」たちとはまた違った感じ。

元々は木彫からスタートしたそう。

広葉樹に彫りこんだ重厚な作品。

写真でかつての仕事を紹介してた。

やはり、菜園作っての自給自足が基本。

毎日古民家での薪生活の中での手作り生活。
麹を自作しての味噌作りや、何と味醂も手作りしてる。
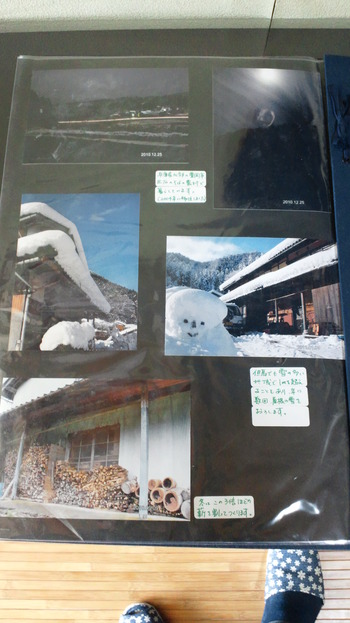
豊岡は寒いんやろなー。

五島列島の「手塩」という自然海塩で作った味噌。
「あ~す農場」の大森さんの息子さんたちや、Iターンで入植した菊池家もよく知ってるとか。
同じような事やってる者同士、超繋がってるねー。
今年は春になると、滋賀の「はるや」の家作りを手伝いに行こうと計画中なので、その帰りにでも寄れるとええな。
去年の屋久島への旅の時のように、旅すがらこういう同士の所を訪ねながらが楽しいからね。
妹の京都で田舎暮らししてる雅の所にも行きたいし。

一人で「オーガニックマルシェ」に出店してたあっこちゃんがお土産を持って帰ってきた。

切干しが干し上がった。

自家製切干し大根は滋味深い美味しさ。

しょうたくんと野遊と僕とで、菜園の収穫をした。
これはカブの間引き菜のお浸し。
まだ小さいのでカブの苦味がなく、甘くて美味しい。

ホウレン草もこの寒さで甘味が増して最高。
化学肥料の利いた深緑のはシュウ酸がキツいけど、自家菜園なら色が薄いぐらいで丁度いい。
「お地蔵さまのひとりごと」という墨絵と木彫を手掛ける作家。
筆文字のロゴ作成
表札、木彫看板作成
篆刻(石に彫るハンコの事)
兵庫の豊岡の山中でカマドのある古民家で薪生活の自給自足を営んでる。
ウチよりも子どもたちの小さい家族。
6、7年前一軒目の廃材ハウスに来廃してくれた。
その時は丸亀で個展を開いていた。
久し振りの今回は観音寺の「むすび」というお店で。
2/10(日)~3/3(日)
10:00~17:00
(定休日 2/15、18、22、23、25、3/1)
作家在廊日2/10、3/2、3
心からだに優しい店 むすび
観音寺市観音寺町甲1087-107
090-4500-3977
観音寺の駅から橋を渡って、郵便局の裏辺りの店。
狭い店ながら、作品がたくさん並んで見応えがある。
建具の古いので額を作り、古い着物を丁寧に裏張りしてる。
てんつくマンの弟子の「路上詩人」たちとはまた違った感じ。
元々は木彫からスタートしたそう。
広葉樹に彫りこんだ重厚な作品。
写真でかつての仕事を紹介してた。
やはり、菜園作っての自給自足が基本。
毎日古民家での薪生活の中での手作り生活。
麹を自作しての味噌作りや、何と味醂も手作りしてる。
豊岡は寒いんやろなー。
五島列島の「手塩」という自然海塩で作った味噌。
「あ~す農場」の大森さんの息子さんたちや、Iターンで入植した菊池家もよく知ってるとか。
同じような事やってる者同士、超繋がってるねー。
今年は春になると、滋賀の「はるや」の家作りを手伝いに行こうと計画中なので、その帰りにでも寄れるとええな。
去年の屋久島への旅の時のように、旅すがらこういう同士の所を訪ねながらが楽しいからね。
妹の京都で田舎暮らししてる雅の所にも行きたいし。
一人で「オーガニックマルシェ」に出店してたあっこちゃんがお土産を持って帰ってきた。
切干しが干し上がった。
自家製切干し大根は滋味深い美味しさ。
しょうたくんと野遊と僕とで、菜園の収穫をした。
これはカブの間引き菜のお浸し。
まだ小さいのでカブの苦味がなく、甘くて美味しい。
ホウレン草もこの寒さで甘味が増して最高。
化学肥料の利いた深緑のはシュウ酸がキツいけど、自家菜園なら色が薄いぐらいで丁度いい。
タグ :個展
2013年02月10日
初めての赤レンガ積み
窯の作業はいい感じにサクサク進んでる。

床は親父担当、壁面はしょうたくん担当。

床、後ろの部屋との仕切りまで完成。

僕はバーナーを据える部分の赤レンガを担当。
この作業は全く初めての作業だけに、慎重になった。
丁寧に時間をかけてやれば、素人でもそれなりにキレイにできるもの。
耐火レンガのメジの耐火モルタルはセメントのモルタルのように固まらないので、施工が簡単。
やり直しも効く。
でも、赤レンガのメジはセメントモルタルだけに、やり直しは効かない。
しかも、鉄筋も何もナシの一列積みだけで持たせないといけない。

レンガに水をしみ込ませたのを引き上げると、気化熱で表面が凍る寒さだった。

土歩が作った白菜と揚げの卵とじ。
10(日)は宇多津のオーガニックマルシェなので、前日のあっこちゃんは仕込みで大忙し。
僕も日中居ないんで、こういう時は子どもたちの出番。

こっちは野遊作の揚げだし里芋。
ほっこりした里芋と濃い目の餡はお酒にもご飯にも合う。
今朝早起きして、玄米オムスビと玄米ライスバーガー作りは僕の担当。
薪で玄米ご飯を炊く所からやからねー。
前日に作ったのではご飯が固くなって美味しくないし。
ピザの出店は自分の事として僕もそれなりに頑張る。
それ以外の出店に関してはあっこちゃんのマニアぶりにマトモには手伝わない。
本人は楽しくでしかたないから、寝なくても一心不乱に作りまくる。
僕はせいぜい子どもたちのご飯作ったり、援護ぐらい。
最近ではこうして、子どもたち自身でご飯や風呂焚きが出来るようになってきたから問題ないけどね。
こういうバランスが丁度いい。
夫婦して活動なり商売なりにのめりこむと、子どもたちはたまったものではない。
自画杜撰での左ウチワライフを実現した今となっては、「嫌なことはしない。」という事を貫くようになった。
いや、元々やりたい事しかしないからこそ、こういう生活を可能にさせ得るのだ。
もちろん、夫婦でお互いを尊重してコンセンサスをとってやってる。
コンセンサスには常に穏やかな話し合いばかりではうまくいかない。
掴み合いと罵り合いが必要な時もある。
何より、お互いに絶対に譲らないというぐらいで丁度いい。
その中で普段の働きぶりを見てたら協力せざるを得ない。
それで、結果的にリスペクトが生まれる。
本当のパートナーであればこそ、本気でぶつからないと道に反する。
こういうことが生きる中での礼儀というものだ。
床は親父担当、壁面はしょうたくん担当。
床、後ろの部屋との仕切りまで完成。
僕はバーナーを据える部分の赤レンガを担当。
この作業は全く初めての作業だけに、慎重になった。
丁寧に時間をかけてやれば、素人でもそれなりにキレイにできるもの。
耐火レンガのメジの耐火モルタルはセメントのモルタルのように固まらないので、施工が簡単。
やり直しも効く。
でも、赤レンガのメジはセメントモルタルだけに、やり直しは効かない。
しかも、鉄筋も何もナシの一列積みだけで持たせないといけない。
レンガに水をしみ込ませたのを引き上げると、気化熱で表面が凍る寒さだった。
土歩が作った白菜と揚げの卵とじ。
10(日)は宇多津のオーガニックマルシェなので、前日のあっこちゃんは仕込みで大忙し。
僕も日中居ないんで、こういう時は子どもたちの出番。
こっちは野遊作の揚げだし里芋。
ほっこりした里芋と濃い目の餡はお酒にもご飯にも合う。
今朝早起きして、玄米オムスビと玄米ライスバーガー作りは僕の担当。
薪で玄米ご飯を炊く所からやからねー。
前日に作ったのではご飯が固くなって美味しくないし。
ピザの出店は自分の事として僕もそれなりに頑張る。
それ以外の出店に関してはあっこちゃんのマニアぶりにマトモには手伝わない。
本人は楽しくでしかたないから、寝なくても一心不乱に作りまくる。
僕はせいぜい子どもたちのご飯作ったり、援護ぐらい。
最近ではこうして、子どもたち自身でご飯や風呂焚きが出来るようになってきたから問題ないけどね。
こういうバランスが丁度いい。
夫婦して活動なり商売なりにのめりこむと、子どもたちはたまったものではない。
自画杜撰での左ウチワライフを実現した今となっては、「嫌なことはしない。」という事を貫くようになった。
いや、元々やりたい事しかしないからこそ、こういう生活を可能にさせ得るのだ。
もちろん、夫婦でお互いを尊重してコンセンサスをとってやってる。
コンセンサスには常に穏やかな話し合いばかりではうまくいかない。
掴み合いと罵り合いが必要な時もある。
何より、お互いに絶対に譲らないというぐらいで丁度いい。
その中で普段の働きぶりを見てたら協力せざるを得ない。
それで、結果的にリスペクトが生まれる。
本当のパートナーであればこそ、本気でぶつからないと道に反する。
こういうことが生きる中での礼儀というものだ。
タグ :赤レンガ
2013年02月09日
春は海藻の季節
窯作り現場は寒かったーーー。
まだ戸を閉めてるからいいものの、さすがの瀬戸内でもかなり冷え込んだ。
しかし、こんなものはまだまだマシな方。
こんな季節の北陸や東北での労働はどんなんやろ?
家が潰されないように雪かきも日々の作業やろし。
こんなふざけた緩い傾斜の廃材の家なんか一発でアウトやろな。
窯の耐火レンガ作業は3人でジャンジャン進んだ。
夢中でやってて、写真がないけど、、、。

生春巻きの皮を使っての焼き餃子。
納豆やもやしに残り物を混ぜた中身もいい感じ。
これにはポン酢と和辛子。

この寒さでやられる前の、残り少ないサツマイモ。
練ゴマと味噌の和えもの。

浅漬けとキムチ、それぞれ3%の塩分で漬けたもの。
5%に比べると相当薄く感じる分、白菜の甘味が引き立つ。
白菜の質によっても塩分は変えないといけない。

「魚の大空」のメノリがいよいよ下がって、70円!?
前に仕入れたのは食べきったんで、また仕入れた。
今年は何十個仕入れたか分からない程。
スーパーでは未だに300円とかで売ってるんで、えらい差。
宇多津で作業してるんで、「宇多津産直」が近くて最高!
こんだけ冷えると、朝仕入れて夕方帰るまで外に置いておいてもクーラーも氷も要らんし。

よく洗って絞る。
これが甘いと、磯臭さが強くて子どもたちに不人気になる。

出始めの細くてヌメッとした状態から随分成長してるので、粗くカットした方がいい。
箸で取る時に繊維が長いと取りにくいし、食べてもこうしといた方がいい。

鍋に入れて三河本味醂と本醸造醤油で煮詰める。
よっぽど最終段階にならないと焦げつかないので、たまに混ぜるだけ。
薪ストーブの上でほっておくだけで出来て超お手軽。
ヨソで朝から夕方まで仕事してても、手作りライフは難しくない。
それが当然と組み込んでるから。
廃材生活も一軒目の廃材ハウスの時からすると、今年で13年目。
長年かけて培ってきた生活スキル。
予め準備段階や勉強や研修なんか必要ない。
生活とは常にぶっつけ本番なのだ!
どこまで本気で取り組むかが、自信のつき方に関わってくる。
廃材生活は自信満々の無敵生活。
自分の中から、「そんなん無理やわー。」とか「嫌やなー。」という抵抗勢力が無くすのは簡単。
いつも手加減や躊躇ナシの全開状態。
ブレーキもハンドルも放してしまえ。
アクセルだけは底につくまで踏みっぱなしだ!!!
で、どこまで行くんやろ???
まだ戸を閉めてるからいいものの、さすがの瀬戸内でもかなり冷え込んだ。
しかし、こんなものはまだまだマシな方。
こんな季節の北陸や東北での労働はどんなんやろ?
家が潰されないように雪かきも日々の作業やろし。
こんなふざけた緩い傾斜の廃材の家なんか一発でアウトやろな。
窯の耐火レンガ作業は3人でジャンジャン進んだ。
夢中でやってて、写真がないけど、、、。
生春巻きの皮を使っての焼き餃子。
納豆やもやしに残り物を混ぜた中身もいい感じ。
これにはポン酢と和辛子。
この寒さでやられる前の、残り少ないサツマイモ。
練ゴマと味噌の和えもの。
浅漬けとキムチ、それぞれ3%の塩分で漬けたもの。
5%に比べると相当薄く感じる分、白菜の甘味が引き立つ。
白菜の質によっても塩分は変えないといけない。
「魚の大空」のメノリがいよいよ下がって、70円!?
前に仕入れたのは食べきったんで、また仕入れた。
今年は何十個仕入れたか分からない程。
スーパーでは未だに300円とかで売ってるんで、えらい差。
宇多津で作業してるんで、「宇多津産直」が近くて最高!
こんだけ冷えると、朝仕入れて夕方帰るまで外に置いておいてもクーラーも氷も要らんし。
よく洗って絞る。
これが甘いと、磯臭さが強くて子どもたちに不人気になる。
出始めの細くてヌメッとした状態から随分成長してるので、粗くカットした方がいい。
箸で取る時に繊維が長いと取りにくいし、食べてもこうしといた方がいい。
鍋に入れて三河本味醂と本醸造醤油で煮詰める。
よっぽど最終段階にならないと焦げつかないので、たまに混ぜるだけ。
薪ストーブの上でほっておくだけで出来て超お手軽。
ヨソで朝から夕方まで仕事してても、手作りライフは難しくない。
それが当然と組み込んでるから。
廃材生活も一軒目の廃材ハウスの時からすると、今年で13年目。
長年かけて培ってきた生活スキル。
予め準備段階や勉強や研修なんか必要ない。
生活とは常にぶっつけ本番なのだ!
どこまで本気で取り組むかが、自信のつき方に関わってくる。
廃材生活は自信満々の無敵生活。
自分の中から、「そんなん無理やわー。」とか「嫌やなー。」という抵抗勢力が無くすのは簡単。
いつも手加減や躊躇ナシの全開状態。
ブレーキもハンドルも放してしまえ。
アクセルだけは底につくまで踏みっぱなしだ!!!
で、どこまで行くんやろ???
タグ :メノリ
2013年02月08日
茎ワカメ
塩釜の釜作り現場は風はあるものの、いい天気で気温は高かった。
最も釜屋は、締めきれば風の当たらない快適な環境。

ドンドン耐火レンガを積み上げていく。

親父担当の窯の床部分もいい感じに進む。

あっという間に窯の口部分完成。

こっちの裏部分はしょうたくん担当。

大豆ミートの海老チリ風。

アラメとレンコンの煮物。

コンニャクの煮物。

この皿は備前焼の弟子時代のもの。

大根のステーキが乗った。
あしらいは自生してるロケット。
まだまだ、大根が美味い。
トウ立ちには早いけど、そろそろ固くなり始めるので毎日食べまくってる。

晩ご飯の後、湯を沸かす。
たくさん沸かしたい時は少なめに入れた鍋の数を増やす。

「魚の大空」からコレを仕入れた。
まだ早いけどワカメの季節。
今回は茎だけ。
ワカメは大量に欲しいから、今度採りに行こうと考え中。

土歩がにこちゃんに指示しながらテキパキと茹でる。

薪ストーブの前での作業中にしょうたくんが中が空洞の軽い薪を発見。
こんなサイズでもにこちゃんが持てるぐらい。
この季節の薪生活では暖房と料理を兼ねてるんで、一日中焚きまくり。

斜めにカットして酢、醤油、針ショウガに漬け込む。
こうしておくと翌日から食べられる常備菜になる。
アイデアを捻り、どうやろうかと考える時と、方向性が決まって流れが出来た時。
どちらも楽しいけど、この耐火レンガ積みのようなドンドン進む爽快感はコツを掴んでうまくいく時のスポーツのようなもの。
サクサクと進む事が楽しい。
動線が出来、無駄を省き、ペースが上がってゆく。
夢中でやってると、「もうこんな時間か!?」と一瞬で時間が過ぎてる。
延々と先の見えない作業こそ、その瞬間にフォーカスする事が大事。
意識を集中しきった先の世界は、無我の境地。
自分を忘れて宇宙意識と合一してるという事。
お経や楽器や瞑想はトランス状態を促すけど、こういう単一労働の作業もそう。
これがワーキングメディテーションだ。
トランスすること、気持ちいいこと、楽しいこと、とは結果なのだ。
それが目的であってはならない。
むしろ僕は手段が目的化する事を推奨する。
その手段は何であってもいい。
オタクやマニアが市民権を得て久しい。
自分の嗜好性に特化すると当然そうならざるを得ない。
それが、永続性と自然の摂理に反しない限りにおいて。
最も釜屋は、締めきれば風の当たらない快適な環境。
ドンドン耐火レンガを積み上げていく。
親父担当の窯の床部分もいい感じに進む。
あっという間に窯の口部分完成。
こっちの裏部分はしょうたくん担当。
大豆ミートの海老チリ風。
アラメとレンコンの煮物。
コンニャクの煮物。
この皿は備前焼の弟子時代のもの。
大根のステーキが乗った。
あしらいは自生してるロケット。
まだまだ、大根が美味い。
トウ立ちには早いけど、そろそろ固くなり始めるので毎日食べまくってる。
晩ご飯の後、湯を沸かす。
たくさん沸かしたい時は少なめに入れた鍋の数を増やす。
「魚の大空」からコレを仕入れた。
まだ早いけどワカメの季節。
今回は茎だけ。
ワカメは大量に欲しいから、今度採りに行こうと考え中。
土歩がにこちゃんに指示しながらテキパキと茹でる。
薪ストーブの前での作業中にしょうたくんが中が空洞の軽い薪を発見。
こんなサイズでもにこちゃんが持てるぐらい。
この季節の薪生活では暖房と料理を兼ねてるんで、一日中焚きまくり。
斜めにカットして酢、醤油、針ショウガに漬け込む。
こうしておくと翌日から食べられる常備菜になる。
アイデアを捻り、どうやろうかと考える時と、方向性が決まって流れが出来た時。
どちらも楽しいけど、この耐火レンガ積みのようなドンドン進む爽快感はコツを掴んでうまくいく時のスポーツのようなもの。
サクサクと進む事が楽しい。
動線が出来、無駄を省き、ペースが上がってゆく。
夢中でやってると、「もうこんな時間か!?」と一瞬で時間が過ぎてる。
延々と先の見えない作業こそ、その瞬間にフォーカスする事が大事。
意識を集中しきった先の世界は、無我の境地。
自分を忘れて宇宙意識と合一してるという事。
お経や楽器や瞑想はトランス状態を促すけど、こういう単一労働の作業もそう。
これがワーキングメディテーションだ。
トランスすること、気持ちいいこと、楽しいこと、とは結果なのだ。
それが目的であってはならない。
むしろ僕は手段が目的化する事を推奨する。
その手段は何であってもいい。
オタクやマニアが市民権を得て久しい。
自分の嗜好性に特化すると当然そうならざるを得ない。
それが、永続性と自然の摂理に反しない限りにおいて。
タグ :ワカメ
2013年02月07日
繊細な耐火レンガ作業
親父も現場に復活して、しょうたくんと3人で窯作り作業。

ステンレスのアンカーが入ったので、側面の壁を耐火レンガで立ち上げ始める。

同時に窯の底面の耐火レンガも敷き詰める。

側面は頑丈な3列積み。
特に、こちらの面はコンクリートが塩害でなくなってるので強くする。

正面のバーナーの口の両側からも耐火レンガを積み始める。
耐火レンガを積むのはコツコツと耐火モルタルを塗っては合わせていく作業。
一個積むごとに水平機を当てて、レベルを取りながら。
大きさが合わない所はダイヤモンドカッターで削りながら合わせる。
一つの単位が小さいので、築きあげるのに時間がかかるけど、ある程度積み上がった時の達成感がいい。
水平、垂直も超厳密に見ながらの丁寧な作業。
何でも慌ててバタバタと終わらせるのが信条の廃材天国の作業とは違う楽しさ。
実は世の中の仕事って、そういう落ち着いてコツコツと進めていくものの方が多いのかも。
今の二極化でワーキングプアとかが発生するまでは。

ゴマ油でイリコをバラバラにしたものをよく炒めて、厚揚げ、ハヤト瓜、カボチャを炒め煮にした。

カラシ菜の辛子マヨネーズ。

車麩とダイコンのスープ。
塩麹ベースの濃い味で美味しい。
ステンレスのアンカーが入ったので、側面の壁を耐火レンガで立ち上げ始める。
同時に窯の底面の耐火レンガも敷き詰める。
側面は頑丈な3列積み。
特に、こちらの面はコンクリートが塩害でなくなってるので強くする。
正面のバーナーの口の両側からも耐火レンガを積み始める。
耐火レンガを積むのはコツコツと耐火モルタルを塗っては合わせていく作業。
一個積むごとに水平機を当てて、レベルを取りながら。
大きさが合わない所はダイヤモンドカッターで削りながら合わせる。
一つの単位が小さいので、築きあげるのに時間がかかるけど、ある程度積み上がった時の達成感がいい。
水平、垂直も超厳密に見ながらの丁寧な作業。
何でも慌ててバタバタと終わらせるのが信条の廃材天国の作業とは違う楽しさ。
実は世の中の仕事って、そういう落ち着いてコツコツと進めていくものの方が多いのかも。
今の二極化でワーキングプアとかが発生するまでは。
ゴマ油でイリコをバラバラにしたものをよく炒めて、厚揚げ、ハヤト瓜、カボチャを炒め煮にした。
カラシ菜の辛子マヨネーズ。
車麩とダイコンのスープ。
塩麹ベースの濃い味で美味しい。
タグ :窯
2013年02月06日
プロの仕事
久し振りの塩釜の窯作り現場。
どんどん気温の下がっていく寒い日になった。
と言うても瀬戸内海沿岸のココは氷点下にはまずならない。

窯の正面のバーナー取り付け口の枠を取り付けに来てくれた。
彼等は鉄工所のプロ集団。
慣れた動きでサクサクと仕事を進める。

コンクリートの躯体が塩害でなくなった部分は底の土間コンからアンカーを取る。
横に回してる細いアングルが釜の底のライン。
常にレーザーを当てながらの正確な作業。
バーナーの口もアンカーも75㎜のステンレスアングル。
こんなしっかりしたステンレスのアンカーは初めて見た。
ステンレス萌えな僕としては美しいビードの溶接面に引き込まれる。

大容量のエンジンウェルダーでクールな溶接作業。

鉄工職人が美しい仕事をしてくれてた。
その間にしょうたくんが奥の煙道の方の耐火レンガを積んだ。
親父は風邪でダウンして来てなかった。
いわゆるプロの職人の仕事はこういう窯のアンカーごときでも1㎜単位の仕事。
2㎜ずれてもやり直す。
ウチの担当する窯部分、その上のステンレスの釜部分、外側の左官仕事の仕上げ部分、あらゆる職人が同時に仕事をする。
お互いに段取りがあるので、他の職人の仕事も見計らいながら合わる必要がある。
考えてみれば当たり前やけど、今までやったことのない分野だけに超新鮮。
やはりプロの仕事は美しい。
使ってる道具もプロ仕様の堅牢で美しいもの。
バイスクランプでも見たことないカッコイイもの。
廃材建築や自分の使う陶芸の窯、ピザの窯などはセンチ単位。
2~3㎝ズレても何の問題もないどころか、その場その場で変更しながら合わせていく。
自分だけで仕事を進め、自分が把握して、完成してからも自分が使いながら修正していく。
こういう場合には全てアバウトな「現場合わせ」という即興作業でOK。
今回はこの新鮮なミリ単位の仕事を楽しんでる。
自分の所の仕事って、とかく「早よせなー!」的な慌てモードになってしまう。
むしろ、こういう頼まれた仕事の方が時間をかけても正確で美しい仕事が要求される。
そやし、自分の所のガツガツとした作業じゃないキチンキチンとしていくのが新しい。
プロというのはプロ仕様の道具を使いこなし、段取りを踏んで一つ一つの工程をこなしていく職人仕事。
それが長年培ったコツや数々の現場を踏んだ経験。
そういう経験ナシに建築も窯作りもやってきたけど、やってりゃできるもの。
経験を積まないとできないんじゃなく、やってるうちに経験がついてくる。
要は勉強や修行をしないとできないんじゃなく、イキナリ始めるのが勉強。
ぶっつけ本番が一番勉強になる。
勉強のための勉強みたいなのが一番ナンセンスだぞ!
どんどん気温の下がっていく寒い日になった。
と言うても瀬戸内海沿岸のココは氷点下にはまずならない。
窯の正面のバーナー取り付け口の枠を取り付けに来てくれた。
彼等は鉄工所のプロ集団。
慣れた動きでサクサクと仕事を進める。
コンクリートの躯体が塩害でなくなった部分は底の土間コンからアンカーを取る。
横に回してる細いアングルが釜の底のライン。
常にレーザーを当てながらの正確な作業。
バーナーの口もアンカーも75㎜のステンレスアングル。
こんなしっかりしたステンレスのアンカーは初めて見た。
ステンレス萌えな僕としては美しいビードの溶接面に引き込まれる。
大容量のエンジンウェルダーでクールな溶接作業。
鉄工職人が美しい仕事をしてくれてた。
その間にしょうたくんが奥の煙道の方の耐火レンガを積んだ。
親父は風邪でダウンして来てなかった。
いわゆるプロの職人の仕事はこういう窯のアンカーごときでも1㎜単位の仕事。
2㎜ずれてもやり直す。
ウチの担当する窯部分、その上のステンレスの釜部分、外側の左官仕事の仕上げ部分、あらゆる職人が同時に仕事をする。
お互いに段取りがあるので、他の職人の仕事も見計らいながら合わる必要がある。
考えてみれば当たり前やけど、今までやったことのない分野だけに超新鮮。
やはりプロの仕事は美しい。
使ってる道具もプロ仕様の堅牢で美しいもの。
バイスクランプでも見たことないカッコイイもの。
廃材建築や自分の使う陶芸の窯、ピザの窯などはセンチ単位。
2~3㎝ズレても何の問題もないどころか、その場その場で変更しながら合わせていく。
自分だけで仕事を進め、自分が把握して、完成してからも自分が使いながら修正していく。
こういう場合には全てアバウトな「現場合わせ」という即興作業でOK。
今回はこの新鮮なミリ単位の仕事を楽しんでる。
自分の所の仕事って、とかく「早よせなー!」的な慌てモードになってしまう。
むしろ、こういう頼まれた仕事の方が時間をかけても正確で美しい仕事が要求される。
そやし、自分の所のガツガツとした作業じゃないキチンキチンとしていくのが新しい。
プロというのはプロ仕様の道具を使いこなし、段取りを踏んで一つ一つの工程をこなしていく職人仕事。
それが長年培ったコツや数々の現場を踏んだ経験。
そういう経験ナシに建築も窯作りもやってきたけど、やってりゃできるもの。
経験を積まないとできないんじゃなく、やってるうちに経験がついてくる。
要は勉強や修行をしないとできないんじゃなく、イキナリ始めるのが勉強。
ぶっつけ本番が一番勉強になる。
勉強のための勉強みたいなのが一番ナンセンスだぞ!
タグ :プロ
2013年02月05日
カブトの幼虫
二日連続で家での作業。
週休二日だと、家の生活仕事がハカドルハカドル。
天ぷらカー用の廃油の回収に2軒の店を回り。
菜園では大根の収穫したり。

昨日は風呂用の焚き物の準備。
ほんの30分ぐらいのエクササイズで、1週間分以上の薪はできる。

しょうたくんが大きな丸太を割ると、カブトの幼虫が入ってた。

次々と発見されて、4匹も居た。
大き目の水槽型の虫カゴに、この木ごと入れて飼うことになった。
こんな市街化されつつある丸亀でも、カブトが居ることに感動。
クヌギやケヤキ、クスなどの雑木を植えたり、廃材天国内だけでも数年で自然の生態系ができつつある。
数本の雑木があると、虫が居て、鳥が来てと、土地は年々豊かになっていく。
環境破壊に警鐘が鳴らされて久しいけど、人間が破壊するのを止めた途端、自然の力はあっという間に回復するに違いない。
ちょっとした土があれば天文学的な量の微生物がいる。
その倍々論理で線虫やミミズがいて、更に土を肥やしてゆく。
落ち葉や枯れ木も土と化す。
石油製品や化学物質、放射能でさえ、微生物によって分解されることも分かってきてるし。

前回、浅干しで半分漬けたたくあんの残りが十分干せた。
今度は暖かくなるまで持つように塩分を10%にして、昆布も入れない。

よく干せてるので密着させやすい。

色づけにクチナシがなかったので、ホワイトリカーにターメリックを溶かして入れた。

廃材ストーンも大きめのでドカンと重石をかける。
ここからはそれこそ微生物の仕事。

収穫した大量の大根。

突いて切干しにする。
この突く道具はフランス製でめっちゃ能率いい。
キッチンツールマニアには堪えられない品。

こんだけ突くのに10分もかからない猛スピード。
後は、天日と風があれば乾燥する。
大根を生で食べるよりもカルシウムが増えたり、味も深く美味しくなる。

僕が切干し突いてる間に、みんなは餃子の皮作り。
大根の葉が大量に出たんで、餃子にしようという流れ。

特に強力粉じゃなく、さぬきの夢で十分できる。

茹でた大根葉、椎茸、エノキ、みじん切りの大根は塩で揉んで入れる。
厚揚げをよくほぐしたものも入れる。
ニンニク、ショウガ、練ゴマ、片栗粉、ゴマ油、塩、醤油で下味をつけておく。

大半は水餃子にした。
ポン酢、柚子コショウが合う。

最後にちょっとだけ焼き餃子に。
片栗粉を水で溶いて流し込み、パリパリに焼くのがポイント。
外に仕事に出かけてても週休2日だと、かなり色々できる。
もちろん窯作りの仕事も楽しいし、休みの日の生活のための労働や手作りも楽しい。
それこそ週休2日を利用すれば菜園や漬物、薪作り、ちょっとしたリフォームレベルのDIYぐらいなら簡単にできる。
別段バタバタと忙しい訳ではないけど、色々やることがあるのがスローライフ。
週休二日だと、家の生活仕事がハカドルハカドル。
天ぷらカー用の廃油の回収に2軒の店を回り。
菜園では大根の収穫したり。
昨日は風呂用の焚き物の準備。
ほんの30分ぐらいのエクササイズで、1週間分以上の薪はできる。
しょうたくんが大きな丸太を割ると、カブトの幼虫が入ってた。
次々と発見されて、4匹も居た。
大き目の水槽型の虫カゴに、この木ごと入れて飼うことになった。
こんな市街化されつつある丸亀でも、カブトが居ることに感動。
クヌギやケヤキ、クスなどの雑木を植えたり、廃材天国内だけでも数年で自然の生態系ができつつある。
数本の雑木があると、虫が居て、鳥が来てと、土地は年々豊かになっていく。
環境破壊に警鐘が鳴らされて久しいけど、人間が破壊するのを止めた途端、自然の力はあっという間に回復するに違いない。
ちょっとした土があれば天文学的な量の微生物がいる。
その倍々論理で線虫やミミズがいて、更に土を肥やしてゆく。
落ち葉や枯れ木も土と化す。
石油製品や化学物質、放射能でさえ、微生物によって分解されることも分かってきてるし。
前回、浅干しで半分漬けたたくあんの残りが十分干せた。
今度は暖かくなるまで持つように塩分を10%にして、昆布も入れない。
よく干せてるので密着させやすい。
色づけにクチナシがなかったので、ホワイトリカーにターメリックを溶かして入れた。
廃材ストーンも大きめのでドカンと重石をかける。
ここからはそれこそ微生物の仕事。
収穫した大量の大根。
突いて切干しにする。
この突く道具はフランス製でめっちゃ能率いい。
キッチンツールマニアには堪えられない品。
こんだけ突くのに10分もかからない猛スピード。
後は、天日と風があれば乾燥する。
大根を生で食べるよりもカルシウムが増えたり、味も深く美味しくなる。
僕が切干し突いてる間に、みんなは餃子の皮作り。
大根の葉が大量に出たんで、餃子にしようという流れ。
特に強力粉じゃなく、さぬきの夢で十分できる。
茹でた大根葉、椎茸、エノキ、みじん切りの大根は塩で揉んで入れる。
厚揚げをよくほぐしたものも入れる。
ニンニク、ショウガ、練ゴマ、片栗粉、ゴマ油、塩、醤油で下味をつけておく。
大半は水餃子にした。
ポン酢、柚子コショウが合う。
最後にちょっとだけ焼き餃子に。
片栗粉を水で溶いて流し込み、パリパリに焼くのがポイント。
外に仕事に出かけてても週休2日だと、かなり色々できる。
もちろん窯作りの仕事も楽しいし、休みの日の生活のための労働や手作りも楽しい。
それこそ週休2日を利用すれば菜園や漬物、薪作り、ちょっとしたリフォームレベルのDIYぐらいなら簡単にできる。
別段バタバタと忙しい訳ではないけど、色々やることがあるのがスローライフ。
タグ :たくあん
2013年02月04日
節分パーティー
昨日は現場は休みにして、日常の生活労働にした。
僕は天ぷらカーで観音寺の「入江麹製造所」に麹の引き取り。
そのタイミングでウチの米を預けておいて、次に欲しい時に電話して仕込んでもらうというローテーション。

しょうたくんと子どもたちとで薪ストーブの焚き物運び。
この道路沿いに積まれた薪を軽トラに満載すると、10日ぐらいは持つ。

あっこちゃん担当の節分の太巻き作り。
夜に実家に集まって、節分パーティー。
寿司飯・・・玄米ご飯、米酢、梅酢、ユズ酢、塩。
高野豆腐の含め煮・・・昆布出汁に塩と甘酒、醤油、味醂。
自家製卵の卵焼き・・・昆布出汁、固造り甘酒、塩。
人参のフライ・・・小麦粉だけの衣に塩を利かせるのがポイント。
レンコンの棒キンピラ・・・ゴマ油で炒めて、醤油だけ。
椎茸の旨煮・・・甘酒、醤油。
ほうれん草の胡麻和え・・・醤油、ゴマ。
ミョウガの梅酢漬け・・・ミョウガ、梅酢。

イワシは七輪で焼く。

大豆と黒豆はホウロクで炒る。

太巻き完成。
しょうたくんは丸ごと食べてたけど、他の人はみんなカットして食べた。
寿司飯は酸っぱくして、具に甘味をつけて炊くのがミソ。
甘い言うても、砂糖の入った巻き寿司からすれば、ほんのりと淡い甘さ。
身体の芯にしみ渡る滋味深い味。
ウチほど自給自足しなくとも、ちゃんとした材料(米、野菜、調味料)を揃えて手作りするのは難しいことじゃないよ。

子どもたちは各自、自分の分をマキスで巻いて切る。
自分で作るという所が面白い。

それぞれ、微妙に個性が出て面白い。

にこちゃんは切りながらフライングで食べてた。

野遊が即席で作った鬼の面で、しょうた鬼に豆をぶつける。

野遊が倒した。

後はせっせとみんなで豆を拾いながら食べる。
黒豆が特に美味い。
こういう年中行事を手作りでするのはほんとに楽しい。
巻き寿司なんかも滅多に作らないから、こういう時に気合いを入れて作るのが丁度いい。
豆まきとイワシは昔からの風習として、太巻きなんか昔はなかったぞーとか言わずに遊びでやればいい。
バレンタインやクリスマスだって何でやってるかサッパリ分らんけど、手作りを楽しむキッカケとして利用すればいい。
そういう遊びと、神道や仏教の年中行事に大した区別をつける必要もない。
ただ、「何でやってるのか?」がハッキリしてるバックボーンを持つ行事の方が深いに決まってる。
そこら辺りは日本人としての歴史的な認識からくるもの。
その認識をするかしないか?
ソコが自分は自分であるという主体性、アイデンティティーになるのだ。
自分は何者なのか?
自信満々で答えるのだ!!!
僕は天ぷらカーで観音寺の「入江麹製造所」に麹の引き取り。
そのタイミングでウチの米を預けておいて、次に欲しい時に電話して仕込んでもらうというローテーション。
しょうたくんと子どもたちとで薪ストーブの焚き物運び。
この道路沿いに積まれた薪を軽トラに満載すると、10日ぐらいは持つ。
あっこちゃん担当の節分の太巻き作り。
夜に実家に集まって、節分パーティー。
寿司飯・・・玄米ご飯、米酢、梅酢、ユズ酢、塩。
高野豆腐の含め煮・・・昆布出汁に塩と甘酒、醤油、味醂。
自家製卵の卵焼き・・・昆布出汁、固造り甘酒、塩。
人参のフライ・・・小麦粉だけの衣に塩を利かせるのがポイント。
レンコンの棒キンピラ・・・ゴマ油で炒めて、醤油だけ。
椎茸の旨煮・・・甘酒、醤油。
ほうれん草の胡麻和え・・・醤油、ゴマ。
ミョウガの梅酢漬け・・・ミョウガ、梅酢。
イワシは七輪で焼く。
大豆と黒豆はホウロクで炒る。
太巻き完成。
しょうたくんは丸ごと食べてたけど、他の人はみんなカットして食べた。
寿司飯は酸っぱくして、具に甘味をつけて炊くのがミソ。
甘い言うても、砂糖の入った巻き寿司からすれば、ほんのりと淡い甘さ。
身体の芯にしみ渡る滋味深い味。
ウチほど自給自足しなくとも、ちゃんとした材料(米、野菜、調味料)を揃えて手作りするのは難しいことじゃないよ。
子どもたちは各自、自分の分をマキスで巻いて切る。
自分で作るという所が面白い。
それぞれ、微妙に個性が出て面白い。
にこちゃんは切りながらフライングで食べてた。
野遊が即席で作った鬼の面で、しょうた鬼に豆をぶつける。
野遊が倒した。
後はせっせとみんなで豆を拾いながら食べる。
黒豆が特に美味い。
こういう年中行事を手作りでするのはほんとに楽しい。
巻き寿司なんかも滅多に作らないから、こういう時に気合いを入れて作るのが丁度いい。
豆まきとイワシは昔からの風習として、太巻きなんか昔はなかったぞーとか言わずに遊びでやればいい。
バレンタインやクリスマスだって何でやってるかサッパリ分らんけど、手作りを楽しむキッカケとして利用すればいい。
そういう遊びと、神道や仏教の年中行事に大した区別をつける必要もない。
ただ、「何でやってるのか?」がハッキリしてるバックボーンを持つ行事の方が深いに決まってる。
そこら辺りは日本人としての歴史的な認識からくるもの。
その認識をするかしないか?
ソコが自分は自分であるという主体性、アイデンティティーになるのだ。
自分は何者なのか?
自信満々で答えるのだ!!!
タグ :節分
2013年02月03日
3Kだからこそ楽しめる
ここの所、香川は暖かくて最高気温が15℃とか。
塩釜の窯作りの作業は超快適。

前日に打ったステコンの上に墨を出す。

しっかりした既存のコンクリートにも墨を出す。

残すコンクリートの境目をダイヤモンドカッターで切る。
180㎜の刃のグラインダーでギャンギャン切る。
道具がいいと作業が気持ちいい。

奥もキチンとカットする。

細かい所まで解体とハツリも終わり、墨も出したので、これからの作業が見えてきた。
解体や耐火レンガをカットするような作業はいわゆる「3K」と呼ばれる「危険、汚い、キツイ」作業。
廃材建築も3K。
その大変な労働をワクワクするエンターテイメントと捉え得るのはなんでか?
今までやったことのない、「どうやったやるんやろ?」、「出来るんかな?」という不安から、「おっ、こうすればいいんか!」という閃きや発見によって、開拓していくような所にワクワク感が起こる。
で、やってるうちにどんどん自分のスキルもアップして更にできるようになる。
この「出来るようになる」プロセスがとっても楽しい。
特に廃材建築の場合、測量、デザイン、土木、大工、左官、内装、設備、、、とあらゆる業種の工事を全部自分でやってしまう。
一つ一つの工事や作業が専門的にやろうとするととてつもなく深いのに、全部をプロ級に掘り下げるのは至難の技。
だからこそいいのだ。
やることが一杯あるってことは終わりがない。
だからいつまでも楽しめる。
分業化が進むのが面白くない根本だ。
餅は餅屋という意味では陶芸家は作品作りだけ。
窯は築炉職人に作ってもらう。
窯の建屋は大工さんに建ててもらう。
それでは自分の出番は作品作るだけになる。
それが飽きる根幹なのだ。
色々やってると、常に勉強やし、常に挑戦の連続。
この現在進行形のリアリティーが楽しいのだ。
昨日の180㎜のダイヤモンドカッターのような作業が超楽しい。
振動、轟音、粉塵にまみれてても、実は自分自身はクールな瞑想状態。
ハイなトランス状態になって楽しくない訳がないじゃん。

家では子どもたちがプチ廃材建築で基地を作ってたみたい。
塩釜の窯作りの作業は超快適。
前日に打ったステコンの上に墨を出す。
しっかりした既存のコンクリートにも墨を出す。
残すコンクリートの境目をダイヤモンドカッターで切る。
180㎜の刃のグラインダーでギャンギャン切る。
道具がいいと作業が気持ちいい。
奥もキチンとカットする。
細かい所まで解体とハツリも終わり、墨も出したので、これからの作業が見えてきた。
解体や耐火レンガをカットするような作業はいわゆる「3K」と呼ばれる「危険、汚い、キツイ」作業。
廃材建築も3K。
その大変な労働をワクワクするエンターテイメントと捉え得るのはなんでか?
今までやったことのない、「どうやったやるんやろ?」、「出来るんかな?」という不安から、「おっ、こうすればいいんか!」という閃きや発見によって、開拓していくような所にワクワク感が起こる。
で、やってるうちにどんどん自分のスキルもアップして更にできるようになる。
この「出来るようになる」プロセスがとっても楽しい。
特に廃材建築の場合、測量、デザイン、土木、大工、左官、内装、設備、、、とあらゆる業種の工事を全部自分でやってしまう。
一つ一つの工事や作業が専門的にやろうとするととてつもなく深いのに、全部をプロ級に掘り下げるのは至難の技。
だからこそいいのだ。
やることが一杯あるってことは終わりがない。
だからいつまでも楽しめる。
分業化が進むのが面白くない根本だ。
餅は餅屋という意味では陶芸家は作品作りだけ。
窯は築炉職人に作ってもらう。
窯の建屋は大工さんに建ててもらう。
それでは自分の出番は作品作るだけになる。
それが飽きる根幹なのだ。
色々やってると、常に勉強やし、常に挑戦の連続。
この現在進行形のリアリティーが楽しいのだ。
昨日の180㎜のダイヤモンドカッターのような作業が超楽しい。
振動、轟音、粉塵にまみれてても、実は自分自身はクールな瞑想状態。
ハイなトランス状態になって楽しくない訳がないじゃん。
家では子どもたちがプチ廃材建築で基地を作ってたみたい。
タグ :窯
2013年02月02日
レーザーレベラー
塩の釜のやりかえ工事の、窯部分の作業進行中。

コンクリート躯体の劣化部分を徹底的にハツッてキレイにする。

同時進行で、親父には煙道の方から新品の耐火レンガを築いていく。
これは一旦水に浸して、耐火モルタルの定着を促すための工程。

耐火モルタルを練って、メジで高さを合わせながら水平を出していく。
僕は杭を打って、窯部分の墨出しをするための準備をする。
杭と野地板をビスで固定して水糸を張って、水平やカネ(直角)を出す。
直角は3:4:5の直角三角形で出せる。

が、、、。
僕がマゴマゴしてると、釜部分をやってくれてる鉄工所の社長がレーザーレベラーを持って登場してくれた。
この機械は置いただけで水平やカネは一瞬で出る。
こういう機械があることは知ってたけど、実際に本物を目の前で使うのを見たのは初めて!
ホントに凄い、凄いと連発する感動。
これはめちゃ凄いけど、ウチでの工事には必要ないし、これからも要らないもの。
買ってもウチなんかに置いておくとすぐに壊しそうやし、、、。

さすがに陶芸の窯を4つも作ってきただけあって、耐火レンガの扱いには慣れてる親父。

土間の基礎が割れて、墨が打てない所にはステコンを打つ。
ステコンとはその名の通り、捨てるコンクリートという意味だそう。
この部分に墨を打つことでその上の耐火レンガの施工や、普通なら型枠を組んでコンクリートを打つ確実性を約束させる。
こういうのは、半年以上も建築会社で働いてたしょうたくんの方が僕よりも詳しい。
臨機応変って大事。
こういう現場では精密性が求められるので、レーザーとかの意味がある。
それを廃材の家に適応させる必要はない。
全てが現場合わせの廃材建築では水平や垂直が多少ズレてようとも構わない。
今回の場合はそれでは通用しない。
下の窯部分がズレると、鉄工所で制作してもらう上の釜部分にも関わってくるからね。
要するに、「何のための仕事か?」を熟慮しないといけない。
「〇〇のための必要があって、この作業をしないといけない。」という理由が要る。
本来、「こうしないといけない。」という決まりはない。
決まりとは自分で決めるもの。
他人に決められるもんじゃあない。

レンコンの団子の揚げたやつ。

同じものを蒸したもの。
どちらもポン酢が合う。

山東菜、春菊、のらぼう菜のミックスお浸し。

ほっこりする薄味の煮物。
コンクリート躯体の劣化部分を徹底的にハツッてキレイにする。
同時進行で、親父には煙道の方から新品の耐火レンガを築いていく。
これは一旦水に浸して、耐火モルタルの定着を促すための工程。
耐火モルタルを練って、メジで高さを合わせながら水平を出していく。
僕は杭を打って、窯部分の墨出しをするための準備をする。
杭と野地板をビスで固定して水糸を張って、水平やカネ(直角)を出す。
直角は3:4:5の直角三角形で出せる。
が、、、。
僕がマゴマゴしてると、釜部分をやってくれてる鉄工所の社長がレーザーレベラーを持って登場してくれた。
この機械は置いただけで水平やカネは一瞬で出る。
こういう機械があることは知ってたけど、実際に本物を目の前で使うのを見たのは初めて!
ホントに凄い、凄いと連発する感動。
これはめちゃ凄いけど、ウチでの工事には必要ないし、これからも要らないもの。
買ってもウチなんかに置いておくとすぐに壊しそうやし、、、。
さすがに陶芸の窯を4つも作ってきただけあって、耐火レンガの扱いには慣れてる親父。
土間の基礎が割れて、墨が打てない所にはステコンを打つ。
ステコンとはその名の通り、捨てるコンクリートという意味だそう。
この部分に墨を打つことでその上の耐火レンガの施工や、普通なら型枠を組んでコンクリートを打つ確実性を約束させる。
こういうのは、半年以上も建築会社で働いてたしょうたくんの方が僕よりも詳しい。
臨機応変って大事。
こういう現場では精密性が求められるので、レーザーとかの意味がある。
それを廃材の家に適応させる必要はない。
全てが現場合わせの廃材建築では水平や垂直が多少ズレてようとも構わない。
今回の場合はそれでは通用しない。
下の窯部分がズレると、鉄工所で制作してもらう上の釜部分にも関わってくるからね。
要するに、「何のための仕事か?」を熟慮しないといけない。
「〇〇のための必要があって、この作業をしないといけない。」という理由が要る。
本来、「こうしないといけない。」という決まりはない。
決まりとは自分で決めるもの。
他人に決められるもんじゃあない。
レンコンの団子の揚げたやつ。
同じものを蒸したもの。
どちらもポン酢が合う。
山東菜、春菊、のらぼう菜のミックスお浸し。
ほっこりする薄味の煮物。
タグ :窯
2013年02月01日
ド迫力のバーナー
既存の窯の解体と同時進行で、先日備前から買ってきた新品の耐火レンガを搬入する。
現場にフォークリフトもないし、今度はユニック車じゃない2tダンプをリースしたので、一つ一つ手作業での積み込み。
どのみち、茅葺きの塩の釜屋内への搬入は手作業にならざるを得ない。

ダンプを横づけした高さが、積み込みに丁度いい。
一輪車じゃなく、2輪の車が絶対に倒れないし、重量物を運ぶ時にいい。
これはホームセンターとかにはないけど、金物屋で注文すると取り寄せてくれる。
しょうたくんの仮置きのアイデアが秀逸だった。
縦に積んでおくと、こっちで取る人が凄く楽になる。
こういう現場での何気ない工夫の積み重ねで仕事が楽になる。
高校生の時、アルバイトしてた鮨割烹の店での壁に貼ってあった、「早く、キレイに、丁寧に!」という親方の標語があった。
当時、「キレイで丁寧にして早いなんてあり得ないじゃん!」と心の中で思いながら山と積まれた皿と格闘してた。
器も高級なので、割ったりするとめちゃくちゃ怒られた。
自分が成長して、あらゆる仕事を余裕を持ってこなせるようになって、理解できる。
同じ仕事が、早く、キレイに、丁寧に進められるようになると、何より自分自身が気持ちいい。
これは農作業、廃材建築、薪生活と全てに通じる。
自分が気持ちいいい作業や生活とは無理のない、理にかなったもの。
自然界に無理ってない。
理不尽もない。
地震も津波も起こってしかるべき。
でも、自然の流れに逆らう人間のやることには無理が起きるもの。

全部で3t分(約1000個)搬入した。

一度外したバーナーを再度取り付けて、点火してみた。
ステンレスの釜部分がない状態での燃焼具合を見たかったから。
何もないので、低音の轟音でゴーーーッと激しく燃える。
何とスイッチが壊れて、常に全開モードで焚いてたそう。
そのお蔭で窯部分や上の釜も傷んだのかも。
この外したバーナーの利用法が何かないかなー。
ウチの陶芸の窯は薪なので、こんな大型のバーナー要らんし。
天ぷら油で焚けると面白いけど、灯油を買ってまで焚きたい用途はないわな。
薪生活にこんな大型バーナーお呼びではない。

窯の解体もキリのいい所までやり終えた。

帰ると、にこちゃんが得意の煮物を作っててくれた。
しょうゆと黒練ゴマの味付けで美味しかった。

これは椎茸を裏返しにした上に里芋のマッシュ、塩とニンニク、オリーブオイル入りのパン粉をまぶしてオーブンで焼いたもの。
塩がよく利いてて酒にも合う料理になってた。
現場にフォークリフトもないし、今度はユニック車じゃない2tダンプをリースしたので、一つ一つ手作業での積み込み。
どのみち、茅葺きの塩の釜屋内への搬入は手作業にならざるを得ない。
ダンプを横づけした高さが、積み込みに丁度いい。
一輪車じゃなく、2輪の車が絶対に倒れないし、重量物を運ぶ時にいい。
これはホームセンターとかにはないけど、金物屋で注文すると取り寄せてくれる。
しょうたくんの仮置きのアイデアが秀逸だった。
縦に積んでおくと、こっちで取る人が凄く楽になる。
こういう現場での何気ない工夫の積み重ねで仕事が楽になる。
高校生の時、アルバイトしてた鮨割烹の店での壁に貼ってあった、「早く、キレイに、丁寧に!」という親方の標語があった。
当時、「キレイで丁寧にして早いなんてあり得ないじゃん!」と心の中で思いながら山と積まれた皿と格闘してた。
器も高級なので、割ったりするとめちゃくちゃ怒られた。
自分が成長して、あらゆる仕事を余裕を持ってこなせるようになって、理解できる。
同じ仕事が、早く、キレイに、丁寧に進められるようになると、何より自分自身が気持ちいい。
これは農作業、廃材建築、薪生活と全てに通じる。
自分が気持ちいいい作業や生活とは無理のない、理にかなったもの。
自然界に無理ってない。
理不尽もない。
地震も津波も起こってしかるべき。
でも、自然の流れに逆らう人間のやることには無理が起きるもの。
全部で3t分(約1000個)搬入した。
一度外したバーナーを再度取り付けて、点火してみた。
ステンレスの釜部分がない状態での燃焼具合を見たかったから。
何もないので、低音の轟音でゴーーーッと激しく燃える。
何とスイッチが壊れて、常に全開モードで焚いてたそう。
そのお蔭で窯部分や上の釜も傷んだのかも。
この外したバーナーの利用法が何かないかなー。
ウチの陶芸の窯は薪なので、こんな大型のバーナー要らんし。
天ぷら油で焚けると面白いけど、灯油を買ってまで焚きたい用途はないわな。
薪生活にこんな大型バーナーお呼びではない。
窯の解体もキリのいい所までやり終えた。
帰ると、にこちゃんが得意の煮物を作っててくれた。
しょうゆと黒練ゴマの味付けで美味しかった。
これは椎茸を裏返しにした上に里芋のマッシュ、塩とニンニク、オリーブオイル入りのパン粉をまぶしてオーブンで焼いたもの。
塩がよく利いてて酒にも合う料理になってた。
タグ :窯