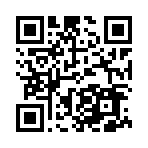2013年07月18日
レンガ職人
廃材建築じゃなく、レンガ職人としての仕事。
焼却炉を作って欲しいという依頼。
田舎の農家では必ず剪定クズなどのゴミを燃やす必要がある。
でも今の風潮は「野焼き禁止」。
塩化ビニールを低温で燃やした時に発生する猛毒のダイオキシンが有名。
もちろん、ダイオキシンが出ないものでも、石油製品は庭や畑で燃やさない方がいい。
そういうのと、落ち葉や剪定クズなどを区別せずに、全面的に禁止というのはナンセンス。

今までにあった炉が壊れて、しっかりしたのを作って欲しいという要望。

砂とセメントを水を入れずに混ぜた「空練り」を水平に敷く。

土台となる底面は目地ナシで耐火レンガを敷き詰める。

炉の壁面を積み上げる。

火を扱う炉の目地には耐火モルタルを使う。
屋根のある窯などなら耐火モルタル100%でいく。
でも、露天の焼却炉なので、普通のセメントも混ぜて耐水性を持たせる。

どんどん積み上げてゆく。

朝から夕方まで目一杯でここまでいった。
依頼された仕事は自分ちの廃材天国のようなテキトーさじゃなく、キチッとする。
どっちも真剣な仕事だけど、かける労力のベクトルが異なる。

廃材天国に帰って、鉄工所でちゃんと作ってもらったフタの裏にアンカーを溶接する。
これで、次の日の準備もバッチリ。
いやー。
暑かった。
西日までバッチリ浴びて、一切影のない現場だったので、汗の量もお茶の量も大量。
熱中症対策は水だけでなく、自家製の梅干しを持参する。
スポーツドリンクでは摂りたくない糖分が入り過ぎてるのでNG。
これだけ暑い中、バリバリ労働できるのは何を置いても「手作りの食」。
玄米と伝統純正調味料、ナス、キュウリ、トマトのばっかり食。
純正とは、醤油なら「大豆、小麦、塩」で作られたもの。
脱脂加工大豆やカラメル色素の入ったのは偽物。
エンジンオイルは純正じゃなくっても大丈夫。
調味料は絶対に純正だぞ!!!
焼却炉を作って欲しいという依頼。
田舎の農家では必ず剪定クズなどのゴミを燃やす必要がある。
でも今の風潮は「野焼き禁止」。
塩化ビニールを低温で燃やした時に発生する猛毒のダイオキシンが有名。
もちろん、ダイオキシンが出ないものでも、石油製品は庭や畑で燃やさない方がいい。
そういうのと、落ち葉や剪定クズなどを区別せずに、全面的に禁止というのはナンセンス。
今までにあった炉が壊れて、しっかりしたのを作って欲しいという要望。
砂とセメントを水を入れずに混ぜた「空練り」を水平に敷く。
土台となる底面は目地ナシで耐火レンガを敷き詰める。
炉の壁面を積み上げる。
火を扱う炉の目地には耐火モルタルを使う。
屋根のある窯などなら耐火モルタル100%でいく。
でも、露天の焼却炉なので、普通のセメントも混ぜて耐水性を持たせる。
どんどん積み上げてゆく。
朝から夕方まで目一杯でここまでいった。
依頼された仕事は自分ちの廃材天国のようなテキトーさじゃなく、キチッとする。
どっちも真剣な仕事だけど、かける労力のベクトルが異なる。
廃材天国に帰って、鉄工所でちゃんと作ってもらったフタの裏にアンカーを溶接する。
これで、次の日の準備もバッチリ。
いやー。
暑かった。
西日までバッチリ浴びて、一切影のない現場だったので、汗の量もお茶の量も大量。
熱中症対策は水だけでなく、自家製の梅干しを持参する。
スポーツドリンクでは摂りたくない糖分が入り過ぎてるのでNG。
これだけ暑い中、バリバリ労働できるのは何を置いても「手作りの食」。
玄米と伝統純正調味料、ナス、キュウリ、トマトのばっかり食。
純正とは、醤油なら「大豆、小麦、塩」で作られたもの。
脱脂加工大豆やカラメル色素の入ったのは偽物。
エンジンオイルは純正じゃなくっても大丈夫。
調味料は絶対に純正だぞ!!!
2013年07月13日
廃材天国HP仮オープン
いよいよ「廃材天国HP」がソコソコ形になってきた。
まだまだ改良したり、ボリュームを持たせていく。
とりあえずは仮のオープンということで。
このサイトを作った一番の目的は、「やりたい者は誰でも自主、自立の生活ができるんだ。」とキッカケにしてもらいたいから。
日々更新されるブログでは様々な情報が埋もれてゆくというのもある。
HPで、ウチでやってる事の一覧を網羅できるようにした。
今作ったコンテンツから更にリンクさせたり、掘り下げていこうと思う。
乞うご期待!!
それとサイト内で「自給自足合宿」という案内もしてる。
第一回目は9月に開催予定!
今までの弟子居候を日常に受け入れるのを辞めた代わりという訳ではない。
日常に漫然と来るのでなく、2泊3日のプログラム化した凝縮スケジュールにしたい。
詳細はサイトの方を見てちょうだい!!
http://haizaitengoku.com/
コチラ!

赤シソが出来るまで待って、塩揉みして梅の中に入れる。
梅はすぐに水が上がって使ってたけど、赤シソが大きくなるのを待って入れる。

今年は梅雨明けが異常に早かった。
気候的にはもう土用干ししてもいいぐらい。
土用前後の一ヶ月間ぐらいは猶予がある。

パイプハウスの屋根の作業をしてたら、野遊が学校から帰ってきて、地下足袋を履いて、「何か手伝うわー。」と。
土歩もやる気になったので、下から突き出たビスをグラインダーで切りとばしてもらう。
夥しい数のビスも二人同時にかかってジャンジャン切ればあっという間。

最近グラインダーデビューした土歩も、早くも慣れたもの。
ぶっつけ本番が当たり前の廃材建築においては、一回経験すれば次からは余裕でできる。

子どもたちが上でギャギャーッと切削してくれてる間にも、僕はひたすら下から丸材の隙間に板を打ちつける。

ほぼ打ち終えたね。
テキトーにジャンジャンやってると、かなりカオスで濃いデザインになる。
何も考えてない訳ではない。
単調にならないよう、揃わないよう、敢えてバラバラに打ちつけてる。

トマトがどんどん採れ始めた。

土歩専用の畑でも採れた。
こちらは畑にして新しく、まだ土地がやせてるのか、キュウリとナスは小さい。
でも、トマトはいい感じに大きくなってる。
夏は作業の後、菜園の水やりが日課。
ここの所、夕立ちの来る様子もないし。
天草の松本さんの薪で炊いた塩を小皿に入れて、ビールを片手に井戸水のホースを持つ。
その時に美味しそうなキュウリやトマトに塩をつけながら飲むビールは最高!
一通り水をやってると、野菜の成長具合もチェックできていい。
この汗の噴き出す季節は夏野菜に最高。
自分ちの菜園の採れたて野菜はスーパーのとは比べものにならない程美味しい。
これはやった者にしか得られない豊穣の境地なのだ!!!
まだまだ改良したり、ボリュームを持たせていく。
とりあえずは仮のオープンということで。
このサイトを作った一番の目的は、「やりたい者は誰でも自主、自立の生活ができるんだ。」とキッカケにしてもらいたいから。
日々更新されるブログでは様々な情報が埋もれてゆくというのもある。
HPで、ウチでやってる事の一覧を網羅できるようにした。
今作ったコンテンツから更にリンクさせたり、掘り下げていこうと思う。
乞うご期待!!
それとサイト内で「自給自足合宿」という案内もしてる。
第一回目は9月に開催予定!
今までの弟子居候を日常に受け入れるのを辞めた代わりという訳ではない。
日常に漫然と来るのでなく、2泊3日のプログラム化した凝縮スケジュールにしたい。
詳細はサイトの方を見てちょうだい!!
http://haizaitengoku.com/
コチラ!
赤シソが出来るまで待って、塩揉みして梅の中に入れる。
梅はすぐに水が上がって使ってたけど、赤シソが大きくなるのを待って入れる。
今年は梅雨明けが異常に早かった。
気候的にはもう土用干ししてもいいぐらい。
土用前後の一ヶ月間ぐらいは猶予がある。
パイプハウスの屋根の作業をしてたら、野遊が学校から帰ってきて、地下足袋を履いて、「何か手伝うわー。」と。
土歩もやる気になったので、下から突き出たビスをグラインダーで切りとばしてもらう。
夥しい数のビスも二人同時にかかってジャンジャン切ればあっという間。
最近グラインダーデビューした土歩も、早くも慣れたもの。
ぶっつけ本番が当たり前の廃材建築においては、一回経験すれば次からは余裕でできる。
子どもたちが上でギャギャーッと切削してくれてる間にも、僕はひたすら下から丸材の隙間に板を打ちつける。
ほぼ打ち終えたね。
テキトーにジャンジャンやってると、かなりカオスで濃いデザインになる。
何も考えてない訳ではない。
単調にならないよう、揃わないよう、敢えてバラバラに打ちつけてる。
トマトがどんどん採れ始めた。
土歩専用の畑でも採れた。
こちらは畑にして新しく、まだ土地がやせてるのか、キュウリとナスは小さい。
でも、トマトはいい感じに大きくなってる。
夏は作業の後、菜園の水やりが日課。
ここの所、夕立ちの来る様子もないし。
天草の松本さんの薪で炊いた塩を小皿に入れて、ビールを片手に井戸水のホースを持つ。
その時に美味しそうなキュウリやトマトに塩をつけながら飲むビールは最高!
一通り水をやってると、野菜の成長具合もチェックできていい。
この汗の噴き出す季節は夏野菜に最高。
自分ちの菜園の採れたて野菜はスーパーのとは比べものにならない程美味しい。
これはやった者にしか得られない豊穣の境地なのだ!!!
2013年06月08日
鶏カゴ完成
鶏カゴ完成。

こんな感じ。

鶏を入れてみた。
が、、、。
自由に出られるよう、、、。

細かく鉄材を溶接した。

これで大丈夫みたい。

クスの木の周りの細い丸太の柵は野遊と土歩と3人で作った。
丸太をインパクトでビス留めするのはほぼ子どもたちでやってのけた。
ツリーハウス風の小屋に卵を産むようにしてる。

しばらくは地面を蹴って虫を探したり草をついばんだりしてたけど、結局狭そうだったので、カゴから出した。
夕方暗くなると自主的に小屋に帰る。

土歩の要望で餃子作り。

エビ入りの水餃子にすることにした。
瀬戸内海産の芝エビの中でも大き目のを仕入れた。
東南アジア産のブラックタイガーは絶対に買わない。
「養殖」は国産でも買わないけど、インドネシアのプランテーション的な生産方法が嫌やから。
買う=支持。
自分の納得のいかないものは断じて支持できないのだ。

エビはよく叩いて潰す。
頭は餃子には使わないので、唐揚げにする。

みんなで皮を延ばしながら包んでいく。
この作業が楽しい。

子どもたちは焼き餃子よりも水餃子が好き。
大人は自家製ラー油を入れると最高。

最後に少し焼き餃子にした。
もちろんこっちも美味い。
こんな感じ。
鶏を入れてみた。
が、、、。
自由に出られるよう、、、。
細かく鉄材を溶接した。
これで大丈夫みたい。
クスの木の周りの細い丸太の柵は野遊と土歩と3人で作った。
丸太をインパクトでビス留めするのはほぼ子どもたちでやってのけた。
ツリーハウス風の小屋に卵を産むようにしてる。
しばらくは地面を蹴って虫を探したり草をついばんだりしてたけど、結局狭そうだったので、カゴから出した。
夕方暗くなると自主的に小屋に帰る。
土歩の要望で餃子作り。
エビ入りの水餃子にすることにした。
瀬戸内海産の芝エビの中でも大き目のを仕入れた。
東南アジア産のブラックタイガーは絶対に買わない。
「養殖」は国産でも買わないけど、インドネシアのプランテーション的な生産方法が嫌やから。
買う=支持。
自分の納得のいかないものは断じて支持できないのだ。
エビはよく叩いて潰す。
頭は餃子には使わないので、唐揚げにする。
みんなで皮を延ばしながら包んでいく。
この作業が楽しい。
子どもたちは焼き餃子よりも水餃子が好き。
大人は自家製ラー油を入れると最高。
最後に少し焼き餃子にした。
もちろんこっちも美味い。
2013年06月07日
鉄の鶏カゴ
季節は夏に近付いてきた。
鶏の食べる草が少なくなってきてる。
時々は鶏小屋から出して草をついばんだり、ミミズを掘ったりできるようにする。
「自然養鶏」とは言え、人間の与える餌だけではこういったものは食べられない。
中島正「自然養鶏」の定義とは?
平飼いと言って、ケージじゃなく、地面の上で飼う。
一坪に10羽未満。
自家飼料で育てる。
自分で手植えしてるお米のクズ米、米ぬか、牡蠣ガラ、いりこなどの出汁カス、生ゴミ、雑草。
これが自家養鶏の基本。
今の養鶏場はケージ飼いどころかウインドウレスという、窓がない。
冷暖房完備で24時間点灯。
常に餌を食べ続けさせ、効率よく卵を産ませるシステム。
その餌とは完全配合飼料という外国産のポストハーベスト入りで遺伝子組換えのトウモロコシ主体。
そこに成長を促進させる女性ホルモン、ケージでのストレスから病気にならないための抗生物質という贅沢な配合。
そんな卵食ってたらアトピーにもなるわな。
最近では自然食品の店だけじゃなく、コープなんかでも平飼いの卵を置き始めた。
一個40円以上するのが相場。
えー。
ウチの鶏の話に戻そう。
鶏は自分の小屋から出ても、暗くなったら帰る。
帰巣本能という。
なので、毎日小屋から出しててもちゃんと帰るので、野犬に襲われたりはしない。
でも、菜園の土をガサガサ掘りまくるのが迷惑。
そこで、ラオスに行った時の竹製の鶏カゴを思い出した。
カナディアンファームのハセヤンも作ってた。
そのカゴを毎日動かせば、新鮮な草やミミズを食べられる。
草や虫を食べた代わりに糞をするので、日々移動していけばまたその土地は豊かになる。

軽トラを繰り出し、鉄工所へGO!
ウチの近所には竹藪がないので、代わりにこの鉄の廃材で作ることにした。

何か作ってると必ず「何作んりょん?」と子どもたちが寄ってくる。
「もうちょい大きくなったら教えるきん。」と言われてワクワクしてる。
廃材なんちゃって溶接は超簡単。

テキトーに曲げて全体像を形作っていく。
手でクニクニ曲がるので成形しやすい。

こんな感じになってきた。

あっこ農園のジャガイモが初収穫。
子どもたちのリクエストで丸ごと揚げにした。
圧搾菜種油に、これまた圧搾のゴマ油を加えると香ばしくて美味しい。
自然海塩をまぶしてパーフェクト!
鶏の食べる草が少なくなってきてる。
時々は鶏小屋から出して草をついばんだり、ミミズを掘ったりできるようにする。
「自然養鶏」とは言え、人間の与える餌だけではこういったものは食べられない。
中島正「自然養鶏」の定義とは?
平飼いと言って、ケージじゃなく、地面の上で飼う。
一坪に10羽未満。
自家飼料で育てる。
自分で手植えしてるお米のクズ米、米ぬか、牡蠣ガラ、いりこなどの出汁カス、生ゴミ、雑草。
これが自家養鶏の基本。
今の養鶏場はケージ飼いどころかウインドウレスという、窓がない。
冷暖房完備で24時間点灯。
常に餌を食べ続けさせ、効率よく卵を産ませるシステム。
その餌とは完全配合飼料という外国産のポストハーベスト入りで遺伝子組換えのトウモロコシ主体。
そこに成長を促進させる女性ホルモン、ケージでのストレスから病気にならないための抗生物質という贅沢な配合。
そんな卵食ってたらアトピーにもなるわな。
最近では自然食品の店だけじゃなく、コープなんかでも平飼いの卵を置き始めた。
一個40円以上するのが相場。
えー。
ウチの鶏の話に戻そう。
鶏は自分の小屋から出ても、暗くなったら帰る。
帰巣本能という。
なので、毎日小屋から出しててもちゃんと帰るので、野犬に襲われたりはしない。
でも、菜園の土をガサガサ掘りまくるのが迷惑。
そこで、ラオスに行った時の竹製の鶏カゴを思い出した。
カナディアンファームのハセヤンも作ってた。
そのカゴを毎日動かせば、新鮮な草やミミズを食べられる。
草や虫を食べた代わりに糞をするので、日々移動していけばまたその土地は豊かになる。
軽トラを繰り出し、鉄工所へGO!
ウチの近所には竹藪がないので、代わりにこの鉄の廃材で作ることにした。
何か作ってると必ず「何作んりょん?」と子どもたちが寄ってくる。
「もうちょい大きくなったら教えるきん。」と言われてワクワクしてる。
廃材なんちゃって溶接は超簡単。
テキトーに曲げて全体像を形作っていく。
手でクニクニ曲がるので成形しやすい。
こんな感じになってきた。
あっこ農園のジャガイモが初収穫。
子どもたちのリクエストで丸ごと揚げにした。
圧搾菜種油に、これまた圧搾のゴマ油を加えると香ばしくて美味しい。
自然海塩をまぶしてパーフェクト!
2013年05月15日
廃材水道
しょうたくんと半日だけ作業した、外の水道(もちろん井戸水がポンプで汲み上げられてるだけの)が中途半端なまんま。
手掘りの井戸の水はツルベで汲んでる訳ではない。
解体現場から盗ってきた日立の浅井戸用ポンプ(電動)で汲み上げる。
そこからキッチン、風呂、洗たく場などへと塩ビパイプを配管してある。

この状態から進んでなかった。

解体で出た塩ビパイプのストックがある。

同じく蛇口も。
ピカピカでもなく、メッキがはがれかけてボロい。

こういう風にグラインダーで磨いてメッキを剝してしまえば逆にカッコいい。

既存の蛇口を一度切り離して、配管する。

外の配管は凍るといけないので化繊の古着で養生。
ここ瀬戸内沿岸ではまず凍る心配はないけど。

シルバーの素材はコレ。

これで廃材蛇口が立派に完成。
上は野菜を洗ったり包丁を研いだり、下は寸胴などの大物を洗う時や鶏の水用、ホースを繋いで菜園の水やりというように使い分ける。

、、、残念ながら、ポタポタ漏れる。

大抵は下に写ってるコマを換えれば直る。
でも、コマの劣化はない。
てことは。
外した蛇口の奥をのぞき込むと、やっぱり!
蛇口を閉めた時にコマが当たる部分の金属の方が劣化してた。
長い廃蛇口生活の中で2回目のケース。
滅多にこの金属部分(鋳物やし)が劣化してる事はない。
こういう時は蛇口そのものを交換するしかない。
毎日毎日壊されてる家、家、家、、、。
この巨大な廃材の家に利用してる言うたって微々たるもの。
木材だけでなく、こういう設備関係だって夥しい量になるやろう。
もっとも、最近は金属類を無駄に捨てたりせずに分別して売る。
アルミサッシや銅線、この蛇口の真鍮なんかは高く買ってくれる。
高いとは言え、製品としてのアルミサッシなり、蛇口からすれば100分の1にもならない。
蛇口だって買うと2000円とかするしねー。
木材狙いで解体現場に通い始めた頃、こういう事に気が付いた。
サッシ、蛇口にとどまらず、照明器具、コンセントやスイッチ類なども。
オマケ的に田舎の農家ではハンマーやバール、クワやツルハシなどの道具も出る。
そういう貴重なものも鉄クズになってしまえば二束三文。

長いタイプのがなく、こういうのがあった。

磨いて取りつけて完成!
捻る部分がやぼったいので、カットしてシャープにした。
朝、「えーっと、何やろか。」とお茶飲んでて、「そうそう、コレやろ。」と思いついて取り掛かる。
どこにも買い物に行かずに完成に至るのが廃材生活の真骨頂だ!
もちろん100%廃材で出来ないことだってある。
そういう時に一部買い足したってしれてる。
シールテープや塩ビボンドなんかは倉庫にストックされてるし。
基礎から構造、設備、内装と全工程を自分でやってるセルフビルドだから、後々のメンテナンスも思いのまま。
道具や材料も揃ってるし、自分の頭の中に全ての工程が入ってる。
配管や配線がどこを通ってるかも忘れようがない。
自分で自分の生活の根底を支える。
これを地に足のついた盤石のライフスタイルと呼ぶのだよ。
手掘りの井戸の水はツルベで汲んでる訳ではない。
解体現場から盗ってきた日立の浅井戸用ポンプ(電動)で汲み上げる。
そこからキッチン、風呂、洗たく場などへと塩ビパイプを配管してある。
この状態から進んでなかった。
解体で出た塩ビパイプのストックがある。
同じく蛇口も。
ピカピカでもなく、メッキがはがれかけてボロい。
こういう風にグラインダーで磨いてメッキを剝してしまえば逆にカッコいい。
既存の蛇口を一度切り離して、配管する。
外の配管は凍るといけないので化繊の古着で養生。
ここ瀬戸内沿岸ではまず凍る心配はないけど。
シルバーの素材はコレ。
これで廃材蛇口が立派に完成。
上は野菜を洗ったり包丁を研いだり、下は寸胴などの大物を洗う時や鶏の水用、ホースを繋いで菜園の水やりというように使い分ける。
、、、残念ながら、ポタポタ漏れる。
大抵は下に写ってるコマを換えれば直る。
でも、コマの劣化はない。
てことは。
外した蛇口の奥をのぞき込むと、やっぱり!
蛇口を閉めた時にコマが当たる部分の金属の方が劣化してた。
長い廃蛇口生活の中で2回目のケース。
滅多にこの金属部分(鋳物やし)が劣化してる事はない。
こういう時は蛇口そのものを交換するしかない。
毎日毎日壊されてる家、家、家、、、。
この巨大な廃材の家に利用してる言うたって微々たるもの。
木材だけでなく、こういう設備関係だって夥しい量になるやろう。
もっとも、最近は金属類を無駄に捨てたりせずに分別して売る。
アルミサッシや銅線、この蛇口の真鍮なんかは高く買ってくれる。
高いとは言え、製品としてのアルミサッシなり、蛇口からすれば100分の1にもならない。
蛇口だって買うと2000円とかするしねー。
木材狙いで解体現場に通い始めた頃、こういう事に気が付いた。
サッシ、蛇口にとどまらず、照明器具、コンセントやスイッチ類なども。
オマケ的に田舎の農家ではハンマーやバール、クワやツルハシなどの道具も出る。
そういう貴重なものも鉄クズになってしまえば二束三文。
長いタイプのがなく、こういうのがあった。
磨いて取りつけて完成!
捻る部分がやぼったいので、カットしてシャープにした。
朝、「えーっと、何やろか。」とお茶飲んでて、「そうそう、コレやろ。」と思いついて取り掛かる。
どこにも買い物に行かずに完成に至るのが廃材生活の真骨頂だ!
もちろん100%廃材で出来ないことだってある。
そういう時に一部買い足したってしれてる。
シールテープや塩ビボンドなんかは倉庫にストックされてるし。
基礎から構造、設備、内装と全工程を自分でやってるセルフビルドだから、後々のメンテナンスも思いのまま。
道具や材料も揃ってるし、自分の頭の中に全ての工程が入ってる。
配管や配線がどこを通ってるかも忘れようがない。
自分で自分の生活の根底を支える。
これを地に足のついた盤石のライフスタイルと呼ぶのだよ。
2013年03月15日
お墓スタンド
天ぷらカーであるボンゴのタイヤの減り具合を見て、ローテーションを思い立った。
車に付属してるパンタグラフ式のジャッキと4tの油圧ボトルジャッキがある。
でも、タイヤを2本同時に外すのは初めて。
廃材鉄工で「ジャッキスタンド」なるものを作る。
ジャッキで車を持ち上げて、下にいれる台のこと。

材料はストックしてある廃材があった。

ギャイーンと切って、パリパリッと溶接して出来た。
お墓みたいなデザインになった。
しかも、一つは材が寸足らずになって、ツギハギで作った。

デフの下にジャッキをかけて持ち上げる。
途中、ゴキッと重い音がしてドキッとするも問題なく上がった。
ある程度持ち上がったら自作ジャッキスタンドを差し込む。
で、難なくタイヤを外せた。
今までは軽ばかり乗って来たので、普通車のタイヤはデカイ。

前輪はパンタグラフジャッキで持ち上げて外す。
うまくローテーション出来た。
終わって見ると、お墓スタンドは2台しか要らないことに気づいた。
鉄クズを売りに行く時に一緒に混ぜよう。

タイヤを付け終わった後、空気圧をチェック。
この自転車用のポンプはゲージが付いてる上に、ママチャリ(英式バルブ)、ロードバイク(仏式バルブ)、車やオートバイ(米式バルブ)、と対応してる。
仏式バルブの自転車用に買ったけど、車にも使えて超便利。

やりたがりの子どもたちが「やらせてー!」と来た。
子どもの力だけでは重いので補助して一緒に入れる。
ほんと、天ぷらカーになってからと言うものメキメキとメンテナンスするようになった。
噴射ポンプのストレーナーの詰まりを直したり、燃料タンクを外して中を丸洗いしたり、必然に駆られての作業。
でも、やってるうちに出来るようになるもの。
よっぽど専門的な部分じゃない限りは、かなり出来るということが分かってきた。
いつもの手段が目的化するという順番。
目的は車を自分で直すという部分。
でも、ホームセンターやオートバックスの部品売り場の前で、「こんなん自作できるんちゃうん。」という所から展開が始まる。
「出来たものを買わない」=「自作する楽しみ」に繋がる。
それが、オカズ、家具、野菜、薬、家、エネルギーまでをも自給する醍醐味がある。
ストイックに自給を極めようとすると大変さがつきまとう。
「自給×廃材=楽勝生活」という公式なのだ。
結果的に金がかからないから、無理して儲ける必要もないし。
ココが究極!

春になってアサツキ(細ネギ)が出始めた。
冬は地上部分はなくなってたけど、春になるとジャンジャン出てくる。
草を取ってやると見る見る成長する。
毎朝の味噌汁やあらゆる料理の薬味に極めて上品。

近所の休耕田で土筆が採れる。
一気に頭が開いて胞子が飛ぶ。

野遊は最近は学校なので、こういう作業から遠ざかってる。
居残り組はコツコツとやってくれる。
車に付属してるパンタグラフ式のジャッキと4tの油圧ボトルジャッキがある。
でも、タイヤを2本同時に外すのは初めて。
廃材鉄工で「ジャッキスタンド」なるものを作る。
ジャッキで車を持ち上げて、下にいれる台のこと。
材料はストックしてある廃材があった。
ギャイーンと切って、パリパリッと溶接して出来た。
お墓みたいなデザインになった。
しかも、一つは材が寸足らずになって、ツギハギで作った。
デフの下にジャッキをかけて持ち上げる。
途中、ゴキッと重い音がしてドキッとするも問題なく上がった。
ある程度持ち上がったら自作ジャッキスタンドを差し込む。
で、難なくタイヤを外せた。
今までは軽ばかり乗って来たので、普通車のタイヤはデカイ。
前輪はパンタグラフジャッキで持ち上げて外す。
うまくローテーション出来た。
終わって見ると、お墓スタンドは2台しか要らないことに気づいた。
鉄クズを売りに行く時に一緒に混ぜよう。
タイヤを付け終わった後、空気圧をチェック。
この自転車用のポンプはゲージが付いてる上に、ママチャリ(英式バルブ)、ロードバイク(仏式バルブ)、車やオートバイ(米式バルブ)、と対応してる。
仏式バルブの自転車用に買ったけど、車にも使えて超便利。
やりたがりの子どもたちが「やらせてー!」と来た。
子どもの力だけでは重いので補助して一緒に入れる。
ほんと、天ぷらカーになってからと言うものメキメキとメンテナンスするようになった。
噴射ポンプのストレーナーの詰まりを直したり、燃料タンクを外して中を丸洗いしたり、必然に駆られての作業。
でも、やってるうちに出来るようになるもの。
よっぽど専門的な部分じゃない限りは、かなり出来るということが分かってきた。
いつもの手段が目的化するという順番。
目的は車を自分で直すという部分。
でも、ホームセンターやオートバックスの部品売り場の前で、「こんなん自作できるんちゃうん。」という所から展開が始まる。
「出来たものを買わない」=「自作する楽しみ」に繋がる。
それが、オカズ、家具、野菜、薬、家、エネルギーまでをも自給する醍醐味がある。
ストイックに自給を極めようとすると大変さがつきまとう。
「自給×廃材=楽勝生活」という公式なのだ。
結果的に金がかからないから、無理して儲ける必要もないし。
ココが究極!
春になってアサツキ(細ネギ)が出始めた。
冬は地上部分はなくなってたけど、春になるとジャンジャン出てくる。
草を取ってやると見る見る成長する。
毎朝の味噌汁やあらゆる料理の薬味に極めて上品。
近所の休耕田で土筆が採れる。
一気に頭が開いて胞子が飛ぶ。
野遊は最近は学校なので、こういう作業から遠ざかってる。
居残り組はコツコツとやってくれる。
タグ :鉄工
2013年03月07日
エレメント
一ヶ月間にわたる仕事を終え、しょうたくんが旅立った。
しょうたくんはかつての弟子居候で、4年前に半年間居てウチで廃材建築から自給自足と色々と学んだ。
ウチの後もアチコチで居候や仕事の経験を積み、今では山口県で土地を借りて自分の小屋を一人で建てた程。
最近では廃材建築などの仕事がある時に職人として呼ぶようになってる。
彼も好きなことで仕事になって、僕も一人では出来ないような大掛かりな現場には助かる。
えー、昨日は軽トラのエンジンオイルの交換。

廃材乗り上げ板。
天ぷらカーの燃料タンクを外して、中を洗った時に作ったもの。
エンジンオイルの交換にも最適。

たったの12㎝だけ地面から持ち上がるだけで、色んなメンテナンスが超やりやすい。
今回はオイルエレメントの交換にも挑戦。
今までも、オイル交換は自分でやってたけど、エレメントの交換はしたことがなかった。
でも、天ぷらカーのメンテナンスに取り組むようになって、天ぷら油のフィルターの交換をやってみて、「簡単じゃん。」と分かった。
天ぷら油のフィルターは日産用のオイルエレメントを使ってるので。
エレメントと一緒にそれ用のチャチな専用工具があればすぐに外せる。

これはテールランプと軽トラのオイルエレメント。
テールランプも切れてたので、ついでに換える。
これに、4ℓのエンジンオイルを入れても2400円で済む。
高い安いよりも、自分で自分の車のメンテナンスをするって事は凄く有意義。
楽しいという趣味的な要素もあるけど、「次はそろそろ〇〇の交換かな。」自分の車の状態を把握できる所。
トラブルが起きても、自分で対処できる。
日常に起きる生活上のトラブル。
もちろん全て自分で対処はできないから専門家の知恵を借りる必要がある。
でも、できる所まで自分やるという姿勢が大事。
車や農機具が調子悪くなって自分で直せるって、田舎のおっちゃんには普通に多い。
田舎暮らしの要はそういう非常事態に柔軟に対応できないとやっていけない。
「雨が漏った。」、「排水管が詰まった。」、「漏電してブレーカーが落ちた。」、というのも自分で工事して把握してるからすぐに直せる。
「喉が痛いな。」と思えばレンコンやショウガ、梅醤番茶という身体の事も同じ。
トラブルとか、非常事態という言葉が悪い。
昔の生活なら、そういうのも含めて当たり前の日常茶飯事。
何が起きても慌てない。
そういう先人たちの知恵を学ぶのだ。
しょうたくんはかつての弟子居候で、4年前に半年間居てウチで廃材建築から自給自足と色々と学んだ。
ウチの後もアチコチで居候や仕事の経験を積み、今では山口県で土地を借りて自分の小屋を一人で建てた程。
最近では廃材建築などの仕事がある時に職人として呼ぶようになってる。
彼も好きなことで仕事になって、僕も一人では出来ないような大掛かりな現場には助かる。
えー、昨日は軽トラのエンジンオイルの交換。
廃材乗り上げ板。
天ぷらカーの燃料タンクを外して、中を洗った時に作ったもの。
エンジンオイルの交換にも最適。
たったの12㎝だけ地面から持ち上がるだけで、色んなメンテナンスが超やりやすい。
今回はオイルエレメントの交換にも挑戦。
今までも、オイル交換は自分でやってたけど、エレメントの交換はしたことがなかった。
でも、天ぷらカーのメンテナンスに取り組むようになって、天ぷら油のフィルターの交換をやってみて、「簡単じゃん。」と分かった。
天ぷら油のフィルターは日産用のオイルエレメントを使ってるので。
エレメントと一緒にそれ用のチャチな専用工具があればすぐに外せる。
これはテールランプと軽トラのオイルエレメント。
テールランプも切れてたので、ついでに換える。
これに、4ℓのエンジンオイルを入れても2400円で済む。
高い安いよりも、自分で自分の車のメンテナンスをするって事は凄く有意義。
楽しいという趣味的な要素もあるけど、「次はそろそろ〇〇の交換かな。」自分の車の状態を把握できる所。
トラブルが起きても、自分で対処できる。
日常に起きる生活上のトラブル。
もちろん全て自分で対処はできないから専門家の知恵を借りる必要がある。
でも、できる所まで自分やるという姿勢が大事。
車や農機具が調子悪くなって自分で直せるって、田舎のおっちゃんには普通に多い。
田舎暮らしの要はそういう非常事態に柔軟に対応できないとやっていけない。
「雨が漏った。」、「排水管が詰まった。」、「漏電してブレーカーが落ちた。」、というのも自分で工事して把握してるからすぐに直せる。
「喉が痛いな。」と思えばレンコンやショウガ、梅醤番茶という身体の事も同じ。
トラブルとか、非常事態という言葉が悪い。
昔の生活なら、そういうのも含めて当たり前の日常茶飯事。
何が起きても慌てない。
そういう先人たちの知恵を学ぶのだ。
タグ :メンテナンス
2012年07月29日
廃材バスケ
タッキーは旅立った。
29日の脱原発国会包囲網に東京まで行った後、成田からインドに飛ぶという予定。
彼女は大学の2回生で後2年インドに居る。
「是非来て下さいよ~!」とラブコールを受けてるけど、子どもたちは「犬怖くないん?」と心配げ。
大学の後はアーユルベーダも学びたいと。
でも、最終的には日本に帰ってきて、ウチのような手作り生活を送りたいそうな。
そのためのパートナーも募集中。
こういう生活を目指す若者には似たような価値観のパートナーが必須。
もちろん、そういう発信をし始めれば必ずやいい出会いが訪れる。
従兄のイッサが遊びに来てた。
バスケがやりたいからゴールを作ってくれと。

コンパネとオイル缶が見つかった。
材料探しから完成まで10分ぐらいのもん。
廃材ソーラーの乗ってる軒の下につけた。
ちょっと低いかと思ったけど、今のちびっ子たちのサイズには丁度よかった。
野遊とイッサ、土歩も入って、超盛り上がった。
でも、その盛り上がりは瞬時にして切り替わる。
次の瞬間、家の中でDSとか。
子どもたちの遊びってそういうもん。
コロコロ気分が変わる。
廃材バスケ自体また次にする時も来るやろうけど、もう誰も見向きもしないかもしれない。
そんなもんやし、それでいい。
それの為の労力には、今回ぐらいで丁度いい。
小さなコンパネ2枚を繋いで、オイル缶の底切って、ビス数本、チョイチョイっと留めるだけ。
既製品のゴール買うのは論外。
作るための材料を買うという発想もない。
その上、廃材手作りでも出来る限り最小限の労力にしたい。

さあ、アルミサッシも入った!
風呂用の新規薪置き場に薪を入れよう。
ちびっ子リレーで運ぶ。

丁度サッシの中央に仕切りを設けた。
左半分が焚きつけの細い薪。
右が太い薪。
これで、台風の時の土砂降りでも薪が濡れないようにもなった。

タッキーがノボリを玉ネギ染めにしてくれた液で、あっこちゃんが座布団カバーを染めた。
僕らがうどんを打ってる間じゅう何かしとるなーと思ってたら、この絞りを入れてた。

割と上手く出来てる。

中々手がこんでる。

これはキスを捌いてる所。
みんな真剣。

三枚に下ろして身は天ぷら、骨は唐揚げ。
国産の圧搾菜種油で揚げると黄色くて濃厚。
淡白なキスとこの油は相性がいい。
これは天草の松本さんの塩だけがいい。

鱧の梅肉餡。
これは瀬戸内の盛夏に必食の一品。

キュウリの豆乳サラダ。
天ぷらと対照的なアッサリ味がいい。
29日の脱原発国会包囲網に東京まで行った後、成田からインドに飛ぶという予定。
彼女は大学の2回生で後2年インドに居る。
「是非来て下さいよ~!」とラブコールを受けてるけど、子どもたちは「犬怖くないん?」と心配げ。
大学の後はアーユルベーダも学びたいと。
でも、最終的には日本に帰ってきて、ウチのような手作り生活を送りたいそうな。
そのためのパートナーも募集中。
こういう生活を目指す若者には似たような価値観のパートナーが必須。
もちろん、そういう発信をし始めれば必ずやいい出会いが訪れる。
従兄のイッサが遊びに来てた。
バスケがやりたいからゴールを作ってくれと。
コンパネとオイル缶が見つかった。
材料探しから完成まで10分ぐらいのもん。
廃材ソーラーの乗ってる軒の下につけた。
ちょっと低いかと思ったけど、今のちびっ子たちのサイズには丁度よかった。
野遊とイッサ、土歩も入って、超盛り上がった。
でも、その盛り上がりは瞬時にして切り替わる。
次の瞬間、家の中でDSとか。
子どもたちの遊びってそういうもん。
コロコロ気分が変わる。
廃材バスケ自体また次にする時も来るやろうけど、もう誰も見向きもしないかもしれない。
そんなもんやし、それでいい。
それの為の労力には、今回ぐらいで丁度いい。
小さなコンパネ2枚を繋いで、オイル缶の底切って、ビス数本、チョイチョイっと留めるだけ。
既製品のゴール買うのは論外。
作るための材料を買うという発想もない。
その上、廃材手作りでも出来る限り最小限の労力にしたい。
さあ、アルミサッシも入った!
風呂用の新規薪置き場に薪を入れよう。
ちびっ子リレーで運ぶ。
丁度サッシの中央に仕切りを設けた。
左半分が焚きつけの細い薪。
右が太い薪。
これで、台風の時の土砂降りでも薪が濡れないようにもなった。
タッキーがノボリを玉ネギ染めにしてくれた液で、あっこちゃんが座布団カバーを染めた。
僕らがうどんを打ってる間じゅう何かしとるなーと思ってたら、この絞りを入れてた。
割と上手く出来てる。
中々手がこんでる。
これはキスを捌いてる所。
みんな真剣。
三枚に下ろして身は天ぷら、骨は唐揚げ。
国産の圧搾菜種油で揚げると黄色くて濃厚。
淡白なキスとこの油は相性がいい。
これは天草の松本さんの塩だけがいい。
鱧の梅肉餡。
これは瀬戸内の盛夏に必食の一品。
キュウリの豆乳サラダ。
天ぷらと対照的なアッサリ味がいい。
2012年07月15日
一家総出の作業になった
朝一番に子どもたちが、簡易トリ小屋に駆けつけると!

まだ温かい生みたて卵ーーー。
にこちゃんは取れなくて残念。

昨日は何と、あっこちゃんも参入。
あっこスイーツを高松に卸すのを辞めて余裕が出来たそう。
今は善通寺の自然食品店「ポパイくん」の受注生産と出店だけ。
毎週毎週、新たなお菓子の開発やら、徹夜仕事での生産(ラッピングやポップ作りも)に明け暮れてたからね。
重要はあるし、「他にないものやから、求めてる人にはできるだけ提供したい。」と言い続けてたけど、、、。
「やっぱり、畑作業や子どもたちと一緒に手作りする生活を優先したい。」と。
よかったねー。
いかに稼ぐか?よりも、いかに使わないか?を念頭に置いた生活。
月に10万もあったら余る。
家賃、借金、ローン、光熱費がない生活。
ハッキリ言って、月に5万でも貯えが減るということはない。
安定した収入は皆無なので、何か買う時に「ホンマにコレ要るんか?」とトコトン考える。
要らないモノは絶対に買わない。
廃材利用だったり、自作できるもの、解体現場で盗ってこれるもので十分事足りる。
今回のトリ小屋作りに関しても、材料は何一つ買ってない。
買ったものと言えばビスぐらい。
僕は鶏が卵を生む小さな小屋作り。
鶏は地面から高い所で、少し暗い箱があると自然とそこへ生む。

廃材の家作りと並行して、井戸を掘った。
その時に出た粘土。

枯れ草と水でグチャグチャに混ぜて。

棟の部分に塗り付けた。

その上にも屋根を設ける。
廃材天国内でいらない木を伐採したのが2、3本あった。
何となく屋根っぽくくっつける。

畳やの廃材+廃ビニールで完成。
ツリーハウス風トリ小屋!

内側はこんなん。

昨日は彼は午前中は気分が乗らずにやらなくて、午後は学校の友達の家に遊びに行ってた。
5時過ぎて帰ってきてから、超やる気でやりだした。
子どもは気まぐれ。
「一回やる言うたんやから、やり続けんといかん!」とは絶対に言わない。
僕はずっとやってる。
「やらせてー。」と来たら、「どうぞ。」と言うだけ。
やりたかったらやったらええし、辞めたくなったら無理しない方がいい。

土歩も一人で、丸太を押さえながら片手でインパクト持ってビスを打ちこむのは大変。
それでも前の日はやってたけどね。
昨日はあっこちゃんと二人一組、インパクト2台体制で楽に出来てた。

お陰で僕はどんどんディティールに凝る。
内部に雨が入らないように、着物の古いのの中に廃ビニールを張ってある。

この、鶏が卵を生むスペースと雨宿りする所は出来た。
後は外の柵を強化するのと、入口のドアぐらいかな。

晩ご飯はコレ!
これほど卵ご飯を喜ぶ子どもも少ないんちゃうかなー。
滅多に買わないんで、遠足の時のお弁当とか特別の時だけやったからね。

あっこちゃんと子どもたちは夕方手分けして、風呂焚きにステンレスカマドでの料理。
残り物を入れた、簡単餃子。
生地は手打ちうどんの時の残ったのを冷凍してたやつ。

テキトーに作っても何とか餃子っぽくはなる。

それと、何と言うても生のキュウリが美味い。
労働で汗びっしょりかいた後には最高!
この手作りの最高料理もエアコンの効いた店でかしこまって出て来たって、美味しさが半減すると言うもの。
一日の労働の後、菜園から収穫、薪で料理して、手作りの〇〇と!
これがセット。
この感動は実践しないと味わえないぞ。
もちろん、無理してするこたあない。
やりたい奴だけやればいい!
「やりたくても出来ない。」なんてことは世の中に存在しない。
「やりたくないからしない。」というのが的確な日本語。
モシクハ、「いつかやりたいんよねー、と言っていたいから言う。」とか。
自分の意思と、自分の選択で!
まだ温かい生みたて卵ーーー。
にこちゃんは取れなくて残念。
昨日は何と、あっこちゃんも参入。
あっこスイーツを高松に卸すのを辞めて余裕が出来たそう。
今は善通寺の自然食品店「ポパイくん」の受注生産と出店だけ。
毎週毎週、新たなお菓子の開発やら、徹夜仕事での生産(ラッピングやポップ作りも)に明け暮れてたからね。
重要はあるし、「他にないものやから、求めてる人にはできるだけ提供したい。」と言い続けてたけど、、、。
「やっぱり、畑作業や子どもたちと一緒に手作りする生活を優先したい。」と。
よかったねー。
いかに稼ぐか?よりも、いかに使わないか?を念頭に置いた生活。
月に10万もあったら余る。
家賃、借金、ローン、光熱費がない生活。
ハッキリ言って、月に5万でも貯えが減るということはない。
安定した収入は皆無なので、何か買う時に「ホンマにコレ要るんか?」とトコトン考える。
要らないモノは絶対に買わない。
廃材利用だったり、自作できるもの、解体現場で盗ってこれるもので十分事足りる。
今回のトリ小屋作りに関しても、材料は何一つ買ってない。
買ったものと言えばビスぐらい。
僕は鶏が卵を生む小さな小屋作り。
鶏は地面から高い所で、少し暗い箱があると自然とそこへ生む。
廃材の家作りと並行して、井戸を掘った。
その時に出た粘土。
枯れ草と水でグチャグチャに混ぜて。
棟の部分に塗り付けた。
その上にも屋根を設ける。
廃材天国内でいらない木を伐採したのが2、3本あった。
何となく屋根っぽくくっつける。
畳やの廃材+廃ビニールで完成。
ツリーハウス風トリ小屋!
内側はこんなん。
昨日は彼は午前中は気分が乗らずにやらなくて、午後は学校の友達の家に遊びに行ってた。
5時過ぎて帰ってきてから、超やる気でやりだした。
子どもは気まぐれ。
「一回やる言うたんやから、やり続けんといかん!」とは絶対に言わない。
僕はずっとやってる。
「やらせてー。」と来たら、「どうぞ。」と言うだけ。
やりたかったらやったらええし、辞めたくなったら無理しない方がいい。
土歩も一人で、丸太を押さえながら片手でインパクト持ってビスを打ちこむのは大変。
それでも前の日はやってたけどね。
昨日はあっこちゃんと二人一組、インパクト2台体制で楽に出来てた。
お陰で僕はどんどんディティールに凝る。
内部に雨が入らないように、着物の古いのの中に廃ビニールを張ってある。
この、鶏が卵を生むスペースと雨宿りする所は出来た。
後は外の柵を強化するのと、入口のドアぐらいかな。
晩ご飯はコレ!
これほど卵ご飯を喜ぶ子どもも少ないんちゃうかなー。
滅多に買わないんで、遠足の時のお弁当とか特別の時だけやったからね。
あっこちゃんと子どもたちは夕方手分けして、風呂焚きにステンレスカマドでの料理。
残り物を入れた、簡単餃子。
生地は手打ちうどんの時の残ったのを冷凍してたやつ。
テキトーに作っても何とか餃子っぽくはなる。
それと、何と言うても生のキュウリが美味い。
労働で汗びっしょりかいた後には最高!
この手作りの最高料理もエアコンの効いた店でかしこまって出て来たって、美味しさが半減すると言うもの。
一日の労働の後、菜園から収穫、薪で料理して、手作りの〇〇と!
これがセット。
この感動は実践しないと味わえないぞ。
もちろん、無理してするこたあない。
やりたい奴だけやればいい!
「やりたくても出来ない。」なんてことは世の中に存在しない。
「やりたくないからしない。」というのが的確な日本語。
モシクハ、「いつかやりたいんよねー、と言っていたいから言う。」とか。
自分の意思と、自分の選択で!
タグ :トリ小屋
2012年07月14日
トリ小屋完成を見ずに、もう鶏さん来た!
トリ小屋作り2日目。
朝起きてすぐ、野遊も土歩も「トリ小屋作ろー!」と大張りきり。
昨日の朝、「今日一日あれば出来るよな。」と思って、県内の自然養鶏の生産者の方に電話。
「2、3羽でいいんで、鶏を分けて欲しいんですけど。」
「明日は予定があって、ダメやけど今日の夕方ならいいよ。」と。
「じゃあ、今日お願いします!」と即決。
この方は「自然卵養鶏法」の中島正さんの理論に基づいて実践されてる。
「自然養鶏」=「中島正」
「自然農法」=「福岡正信」のような、創設者。
中島正さんの著書には「都市を滅ぼせ」という名著がある。
何十年も前から脱原発なり、脱バビロンシステムを唱えられてる。
「自然養鶏」の定義は概ね
「平飼い」(広々とした鶏舎の地面で飼う、一坪10羽未満)
「自家製飼料」(クズ米、米ぬか、魚粉、牡蠣ガラなどを使い、抗生物質や女性ホルモン入りの配合飼料は使わない)
ゲージでギュウ詰めにして、ストレスで病気になるから餌に抗生物質を入れるという、経済効率一辺倒の飼い方とは全く別。
今の養鶏場は鶏インフルエンザを生み、数十万羽の鶏を生き埋めにした「アサダ農産」とどこも似てる。
ウインドウレス(窓ナシ)、24時間点灯(鶏は寝ないで餌を食べ続ける)、エアコンで温度管理、餌やり、採卵はベルトコンベアのオートメーション。
7階建てのゲージで、40㎝ぐらいの仕切りに2羽入れられてる。
その理由は動けないから、食べる事と卵を産むことだけに特化させるため!?
どこも、数万~数十万という単位。
よくあれから鶏インフルエンザ出ないと思うけど、役所からは消毒、殺菌という指導が徹底されてるそう。
卵ってアトピーの的のようなイメージがあるけど、それは不自然卵の中の化学物質に反応してるんやと思う。
スーパーの卵で平飼いの自然卵は滅多とみかけない。
プレミアム卵で有名な「ヨード卵光」のようにゲージ飼い、配合飼料だけどヨードを入れてあるというのは全然違う。
DHA配合とか、名前だけの「大自然卵」とかばかり。
「ヨード卵光」は変にブランド化して高いので別として、それ以外は値段が目安。
10個で400円から500円。
このぐらいが平飼いで飼料にもこだわった卵の平均値。
産直や自然食品屋に行かないとね。
普段、ウチでは肉や卵を常食しないけど、いいものをたまに食べるのは問題ない。
その判別法は「飼い方」と「餌」。
不自然な環境で、薬漬けにされる動物虐待を支持するのも嫌やし。
虐待とは命の尊厳を無視する、経済システムに組み込むこと。

腰袋つけて、インパクトでビス打つ。
野遊は随分上手いけど、土歩もかなり慣れてきた。
荒く枠を作れば金網張ったらええかなと思ってたけど、ちびっ子の活躍ぶりにオール丸太で作ることにした。
前日に横に入れた丸太に縦の格子を入れていく。
途中からの雨で合羽来ての作業。
それから、瞬間的やったけど、凄い豪雨で家の周りを奔走。
雨に当たるといけない物をしまったり、樋や溝の点検。
川のように流れる溝さらえが楽しい。

小雨になったんで、作業再会。
電動工具は使えないぐらいには降ってたんで、針金で細い丸太を留める作戦に変更。
雨で思うように進まなかったのもあるけど、夕方までには間に合いそうにない。
当初はパパッと手軽に作ろうと取り掛かったトリ小屋作り。
ちびっ子たちのモチベーションの高さに触発されて、思わず僕もディティールに入り出したのもある。
やってるウチに面白くなって変更に次ぐ変更ってのはしょっちゅう。
そこれもこれも、設計図ナシ、計画性ナシ、ある廃材での「直感&即興」の廃材建築ならでは。

どっちにせよ、鶏は夕方引き取りに行く。
なので、本小屋が完成するまでの仮小屋を作る。
パレット持って来てビスで留める。

塩ビの廃材ナミ板置いて10分もかけずに完成!
こういう急展開にも、廃材建築はめっぽう強い。

夕方、満濃町の養鶏家の鶏舎を訪ねた。
定番の平飼いのスタイル。

別の場所ではヒヨコが育てられてた。

PHFコーン(ポストハーベストフリー)、米ぬか、煮干し、牡蠣ガラ、EMボカシという自家配合の飼料。
魚粉じゃなく、煮干しというのが凄い!
伊吹島まで行って、クズのいりこを分けてもらえるように交渉したんだとか。
こういう餌だと、ヒヨコは半年近くかけて大人になる。
大手の完全配合飼料だと、肉にする鶏だと2ヶ月で出荷。
一軒目の廃材ハウスではヒヨコから飼ってたから分かるけど、2カ月言うたらまだピヨピヨ言うてるからねー。

2、3羽の予定が、「5羽ぐらい持って帰ったら。」と。
う~ん、あっこちゃんがまた色々言うかな、、、。
どっちにせよ、鶏さん来たんやからこっちのもん。
卵産んでくれるし、殺したての最高の肉も食べられるし!!!
餌やりは最近の風呂焚き同様、当番表を作って、野遊と土歩が交代でやろうとミーティングが為されてるみたいやし。
子どもたちも、僕がやるのを見て捌き方なんかあっという間に覚えるやろしね。
朝起きてすぐ、野遊も土歩も「トリ小屋作ろー!」と大張りきり。
昨日の朝、「今日一日あれば出来るよな。」と思って、県内の自然養鶏の生産者の方に電話。
「2、3羽でいいんで、鶏を分けて欲しいんですけど。」
「明日は予定があって、ダメやけど今日の夕方ならいいよ。」と。
「じゃあ、今日お願いします!」と即決。
この方は「自然卵養鶏法」の中島正さんの理論に基づいて実践されてる。
「自然養鶏」=「中島正」
「自然農法」=「福岡正信」のような、創設者。
中島正さんの著書には「都市を滅ぼせ」という名著がある。
何十年も前から脱原発なり、脱バビロンシステムを唱えられてる。
「自然養鶏」の定義は概ね
「平飼い」(広々とした鶏舎の地面で飼う、一坪10羽未満)
「自家製飼料」(クズ米、米ぬか、魚粉、牡蠣ガラなどを使い、抗生物質や女性ホルモン入りの配合飼料は使わない)
ゲージでギュウ詰めにして、ストレスで病気になるから餌に抗生物質を入れるという、経済効率一辺倒の飼い方とは全く別。
今の養鶏場は鶏インフルエンザを生み、数十万羽の鶏を生き埋めにした「アサダ農産」とどこも似てる。
ウインドウレス(窓ナシ)、24時間点灯(鶏は寝ないで餌を食べ続ける)、エアコンで温度管理、餌やり、採卵はベルトコンベアのオートメーション。
7階建てのゲージで、40㎝ぐらいの仕切りに2羽入れられてる。
その理由は動けないから、食べる事と卵を産むことだけに特化させるため!?
どこも、数万~数十万という単位。
よくあれから鶏インフルエンザ出ないと思うけど、役所からは消毒、殺菌という指導が徹底されてるそう。
卵ってアトピーの的のようなイメージがあるけど、それは不自然卵の中の化学物質に反応してるんやと思う。
スーパーの卵で平飼いの自然卵は滅多とみかけない。
プレミアム卵で有名な「ヨード卵光」のようにゲージ飼い、配合飼料だけどヨードを入れてあるというのは全然違う。
DHA配合とか、名前だけの「大自然卵」とかばかり。
「ヨード卵光」は変にブランド化して高いので別として、それ以外は値段が目安。
10個で400円から500円。
このぐらいが平飼いで飼料にもこだわった卵の平均値。
産直や自然食品屋に行かないとね。
普段、ウチでは肉や卵を常食しないけど、いいものをたまに食べるのは問題ない。
その判別法は「飼い方」と「餌」。
不自然な環境で、薬漬けにされる動物虐待を支持するのも嫌やし。
虐待とは命の尊厳を無視する、経済システムに組み込むこと。
腰袋つけて、インパクトでビス打つ。
野遊は随分上手いけど、土歩もかなり慣れてきた。
荒く枠を作れば金網張ったらええかなと思ってたけど、ちびっ子の活躍ぶりにオール丸太で作ることにした。
前日に横に入れた丸太に縦の格子を入れていく。
途中からの雨で合羽来ての作業。
それから、瞬間的やったけど、凄い豪雨で家の周りを奔走。
雨に当たるといけない物をしまったり、樋や溝の点検。
川のように流れる溝さらえが楽しい。
小雨になったんで、作業再会。
電動工具は使えないぐらいには降ってたんで、針金で細い丸太を留める作戦に変更。
雨で思うように進まなかったのもあるけど、夕方までには間に合いそうにない。
当初はパパッと手軽に作ろうと取り掛かったトリ小屋作り。
ちびっ子たちのモチベーションの高さに触発されて、思わず僕もディティールに入り出したのもある。
やってるウチに面白くなって変更に次ぐ変更ってのはしょっちゅう。
そこれもこれも、設計図ナシ、計画性ナシ、ある廃材での「直感&即興」の廃材建築ならでは。
どっちにせよ、鶏は夕方引き取りに行く。
なので、本小屋が完成するまでの仮小屋を作る。
パレット持って来てビスで留める。
塩ビの廃材ナミ板置いて10分もかけずに完成!
こういう急展開にも、廃材建築はめっぽう強い。
夕方、満濃町の養鶏家の鶏舎を訪ねた。
定番の平飼いのスタイル。
別の場所ではヒヨコが育てられてた。
PHFコーン(ポストハーベストフリー)、米ぬか、煮干し、牡蠣ガラ、EMボカシという自家配合の飼料。
魚粉じゃなく、煮干しというのが凄い!
伊吹島まで行って、クズのいりこを分けてもらえるように交渉したんだとか。
こういう餌だと、ヒヨコは半年近くかけて大人になる。
大手の完全配合飼料だと、肉にする鶏だと2ヶ月で出荷。
一軒目の廃材ハウスではヒヨコから飼ってたから分かるけど、2カ月言うたらまだピヨピヨ言うてるからねー。
2、3羽の予定が、「5羽ぐらい持って帰ったら。」と。
う~ん、あっこちゃんがまた色々言うかな、、、。
どっちにせよ、鶏さん来たんやからこっちのもん。
卵産んでくれるし、殺したての最高の肉も食べられるし!!!
餌やりは最近の風呂焚き同様、当番表を作って、野遊と土歩が交代でやろうとミーティングが為されてるみたいやし。
子どもたちも、僕がやるのを見て捌き方なんかあっという間に覚えるやろしね。
タグ :自然卵
2012年02月11日
子どもが頼りの出店
けん引装置が塗装も終えて、無事復活。

取り付ける。

車のシャーシ自体に穴を開けてボルトで固定してある。
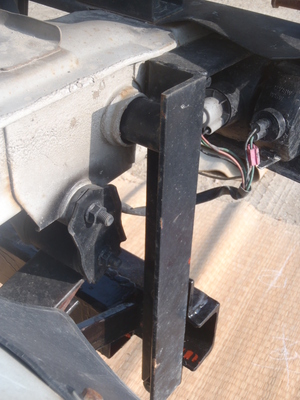
この開いてた穴に鉄管を突っ込んで、アングルを溶接してある。

パーフェクト!
いやー。
この12日にはアイレックスでイベントがあって、ピザ窯を持って行くんで間に合ってよかったー。
昨日からトマトソースなどの仕込み、あっこちゃんはせっせとスイーツ作りが始めてる。
実は、僕は12日の10時~のイベントで、あっこちゃんは11時から宇多津で「さぬきオーガニックマルシェ」。
別々に出店というのは初めて。
子どもたちは僕のピザの方に来ることになった。
お客とのお金のやりとりや皿やコップの洗いものなどは子どもたちに頼るしかない!
高知の「ぽっちり堂」のパスタマシンでの出店では毎年、「よく働くわー。」と感心されてるうちのちびっ子たち。
まあ、あんだけ忙しかったら手伝うしかないという状態で、2年前でも土歩は雨が降ってる時に半泣きで洗い物してた。
要するに、出番があると言えば聞こえがいいけど、「せなしゃあない。」という状態では誰でもスイッチが入るもの。
僕もあっこちゃんも常にやる事があって、何かと動いてる。
朝起きて、布団の片づけ、薪の搬入、土間の箒がけ、洗濯物を干したり、と一連の作務は毎日子どもの日課。
僕の作業中の「集合!」の一言で、何を置いても子どもたちは労働する体制に入る。
何が教育なのか?
何が子どもにとっていいのか?
そんなものに答えはない。
答えはいらん。
僕ら夫婦の子育ては簡単シンプル。
親が本気で生きる事。
いらん事したり、悩んだり、揺れたりしない事。
そんだけ。
自分たち大人がブレずに毎日やりきってたら、結果として子どもは勝手に育つ。
親が興味を持つことには当然のように興味を持つし。
face fookで友達がアップしてた映像があった。
京都市長選に脱原発の候補者が出てて、山本太郎さんが応援に駆け付けた演説で、それをyou tubeで見た時、野遊は「京都の市長選何とかせないかんやん!」と、どうやったらこの人は受かるのか?と真剣に聞いてきたもんね。
こういう事にも僕らは自分たちの言葉でしか答えられない。
そしてその言葉は毎日のライフスタイルからの産物でしかない。

豆腐、レンコン、人参などの揚げ団子。
キャベツの芯とか、とにかく固くて捨てるような部分を冷凍してためておいて、ミジン切りにして入れる。
そういう固いものを入れるのがコツ。
ニンニク、ショウガ、塩、味噌などで味もしっかりとさせる。
ソースはお好み焼きソースの残ったのに、トマトソースを混ぜた。

豆腐をしっかりフライパンで焼いて、醤油とバルサミコ酢で濃い味にした。
それを大根や人参に乗せて食べる。
豆腐マヨネーズをトッピングしても美味しかったよ。
どうかなー?というアイデアやったけど、結果オーライ。
昨日の2品はどちらも僕の料理。
あっこちゃんの料理とはまた違うスタンスやけど、団子のアイデアは彼女に色々聞きながら出来た。
どうも純米酒よりはワインの合う日になったね。
取り付ける。
車のシャーシ自体に穴を開けてボルトで固定してある。
この開いてた穴に鉄管を突っ込んで、アングルを溶接してある。
パーフェクト!
いやー。
この12日にはアイレックスでイベントがあって、ピザ窯を持って行くんで間に合ってよかったー。
昨日からトマトソースなどの仕込み、あっこちゃんはせっせとスイーツ作りが始めてる。
実は、僕は12日の10時~のイベントで、あっこちゃんは11時から宇多津で「さぬきオーガニックマルシェ」。
別々に出店というのは初めて。
子どもたちは僕のピザの方に来ることになった。
お客とのお金のやりとりや皿やコップの洗いものなどは子どもたちに頼るしかない!
高知の「ぽっちり堂」のパスタマシンでの出店では毎年、「よく働くわー。」と感心されてるうちのちびっ子たち。
まあ、あんだけ忙しかったら手伝うしかないという状態で、2年前でも土歩は雨が降ってる時に半泣きで洗い物してた。
要するに、出番があると言えば聞こえがいいけど、「せなしゃあない。」という状態では誰でもスイッチが入るもの。
僕もあっこちゃんも常にやる事があって、何かと動いてる。
朝起きて、布団の片づけ、薪の搬入、土間の箒がけ、洗濯物を干したり、と一連の作務は毎日子どもの日課。
僕の作業中の「集合!」の一言で、何を置いても子どもたちは労働する体制に入る。
何が教育なのか?
何が子どもにとっていいのか?
そんなものに答えはない。
答えはいらん。
僕ら夫婦の子育ては簡単シンプル。
親が本気で生きる事。
いらん事したり、悩んだり、揺れたりしない事。
そんだけ。
自分たち大人がブレずに毎日やりきってたら、結果として子どもは勝手に育つ。
親が興味を持つことには当然のように興味を持つし。
face fookで友達がアップしてた映像があった。
京都市長選に脱原発の候補者が出てて、山本太郎さんが応援に駆け付けた演説で、それをyou tubeで見た時、野遊は「京都の市長選何とかせないかんやん!」と、どうやったらこの人は受かるのか?と真剣に聞いてきたもんね。
こういう事にも僕らは自分たちの言葉でしか答えられない。
そしてその言葉は毎日のライフスタイルからの産物でしかない。
豆腐、レンコン、人参などの揚げ団子。
キャベツの芯とか、とにかく固くて捨てるような部分を冷凍してためておいて、ミジン切りにして入れる。
そういう固いものを入れるのがコツ。
ニンニク、ショウガ、塩、味噌などで味もしっかりとさせる。
ソースはお好み焼きソースの残ったのに、トマトソースを混ぜた。
豆腐をしっかりフライパンで焼いて、醤油とバルサミコ酢で濃い味にした。
それを大根や人参に乗せて食べる。
豆腐マヨネーズをトッピングしても美味しかったよ。
どうかなー?というアイデアやったけど、結果オーライ。
昨日の2品はどちらも僕の料理。
あっこちゃんの料理とはまた違うスタンスやけど、団子のアイデアは彼女に色々聞きながら出来た。
どうも純米酒よりはワインの合う日になったね。
タグ :ピザ
2012年02月09日
道具の差は大きいねー
完成したけん引装置の部品を磨く。
前の塗装を一回剥がした方がいい。
で、錆止めを塗る。
昨日は近所の電気工事士のおっちゃんに、この電気工事を依頼した。
太い電線を扱うこういう要の電気工事は自分では出来ない。
ほんの1時間ほどでチャチャッとしてくれた。
今までは普通の分電盤の中の20Aのブレーカーを30Aにして溶接機を使ってた。
去年、薪ストーブの大改造まではこの小型の溶接機を使ってた。
これは家庭用の200V、20Aでいけてた。
溶接棒も2、6㎜がギリギリだった。
これは最近中古で買った本格的なもの。
本格的言うたって、古いんで1万ちょっと。
これで溶接作業をやってるけど、30Aに容量を上げても時々落ちてた。
で、60Aにしてもらった。
単層の200Vでも太い電線にして大きなブレーカーをつけると、かなり大きな電力を使えるようになる。
今回の工事はソーラー発電システムが完成するまでの仮のもの。
それでも3、2㎜や4㎜の溶接棒がバリバリ焚けるようになったのが喜ばしい。
一応付いてはいるけど、、、。
こっちが容量を上げた後。
経験が上がって上手くなったとも言えるけど、道具の違いという面も大きい。
「弘法筆を選ばず」というのは達人の域の話やと思う。
素人であればある程、道具による差ってデカイ。
プロ仕様の道具を装備することで、かなり本格的な仕事が出来るようになる。
ネットオークションで、本格的な工具も古ければ安く買えるからねー。
ソーラーパネルの架台もバリバリ溶ける。
このCチャンの亜鉛メッキを食い破るのにパワーが必要。
容量が上がって容易になった。
これで最後。
まだ、アングルとCチャンがついてないけど、随分進んできた。
こうして、ジワジワと進むのが自作なりセルフビルド。
それでいい。
全部業者に頼んで数日で出来る代わりにとんでもない額面を用意することを思えばたやすいもん。
またちょっとだけ雪が積もった。
野遊が「このホワイトスライム肉を切って、焼くんだ!」と!?
朝、face bookで話題になってる「ピンクスライム肉」映像をyou tubeで見て、一同「げ~~~~!!!」とびっくりしたからねー。
先日見たばかりの「フード・インク」とも被って「やっぱりねー!」って感じ。
http://youpouch.com/2012/02/07/53351/
この映像凄いよ!
タグ :溶接
2012年02月07日
鉄のDIY
自作、移動式ピザ窯のけん引システム。
作って丸2年になる。
出動はせいぜい月に一回ぐらいのもん。
窯本体の方は年末に屋根を付けて雨にも対応できるようになった。
その時ぐらいから、軽トラ側の鉄骨に少し問題が発生してる。

コレ。
この写真では分かりにくい。

ココ。
チャンネルというこのコの字型の鉄骨が緩やかに歪んできた。
すぐにどうこうなる問題でもないので、「いつかは直さななー。」と思ってた。
雨でソーラーパネルの作業ができないんで、コッチにかかった。

ボルトナットで固定してるんで、すぐに外せる。

この上から大ハンマーで思いっきり叩く。
かなり力を入れないと曲がらないチャンネル。

何回も叩いはて睨んでの繰り返しで何とか直ってきた。

でも叩きすぎて、アングルの溶接箇所にヒビが入った、、、。

チャンネルを補強する鉄の廃材をもらいに近所の鉄工所へ。
色々適当にもらってきた。
ピザの窯本体の台車もこの鉄工所から廃材をもらってきて作った。
鉄の場合廃材とはいえ、鉄クズとして㌔20円とかで売れる。
それでも、色々付き合ってるウチに、「陣くんが作るぐらいしれてるんやから好きなだけもっていけ。」と言うてくれてる。

このシャコ万力という強力なクランプも貸してくれた。
これで締め付けてる間に溶接する。

もらってきた角パイプを繋いでチャンネルに沿わせて補強にした。
こんだけ頑丈になれば大丈夫やと思う。
何でもテキトーに即興で作るんで、問題が発生したらその時に対応する。
「問題が発生しないように作る。」事に頭を悩ませたりするのはナンセンス極まりない。
鉄の自作系のDIYは意外と簡単やし、木では無理な強度の構造物が出来るんで、廃材建築家としてはドンドンスキルを磨いていきたい分野。
建築関係のアルバイトすらしたことなくて家を2軒建てたのと同様、鉄工所で働いて技術を習得しなくとも、何とかやってる。
この「やってるうちに出来るようになる。」というのが共通項。
何でも、「正式に習わないといけない。」という幻想に捉われてることが多い。
資格がないと〇〇できないというのもおかしなもの。
こういうのも結局は好きか嫌いか、になってくる。
僕は「ゲリラ好き」なので、こういうスタイル。
正式や資格の好きな人はそういう路線でええし。
要するに、自分の作業そのものが楽しいのなら「ゲリラ」で十分。
客観的な評価を必要とするのなら「正式」の方がいい。
一つの分野をマニアックに研究したり、スキルを高めたいとかも「正式」の方がいいんかな?
どっちでもええんやけど、ほんとに「どっちがええやろ?」と純粋に選べる方がいい。
「これはこういうもん。」とハナから選択肢がないのは気持ち悪い。
そうして自由な選択の結果として、どっちになってもいい。
自分で決めないとスッキリしないからね。
作って丸2年になる。
出動はせいぜい月に一回ぐらいのもん。
窯本体の方は年末に屋根を付けて雨にも対応できるようになった。
その時ぐらいから、軽トラ側の鉄骨に少し問題が発生してる。
コレ。
この写真では分かりにくい。
ココ。
チャンネルというこのコの字型の鉄骨が緩やかに歪んできた。
すぐにどうこうなる問題でもないので、「いつかは直さななー。」と思ってた。
雨でソーラーパネルの作業ができないんで、コッチにかかった。
ボルトナットで固定してるんで、すぐに外せる。
この上から大ハンマーで思いっきり叩く。
かなり力を入れないと曲がらないチャンネル。
何回も叩いはて睨んでの繰り返しで何とか直ってきた。
でも叩きすぎて、アングルの溶接箇所にヒビが入った、、、。
チャンネルを補強する鉄の廃材をもらいに近所の鉄工所へ。
色々適当にもらってきた。
ピザの窯本体の台車もこの鉄工所から廃材をもらってきて作った。
鉄の場合廃材とはいえ、鉄クズとして㌔20円とかで売れる。
それでも、色々付き合ってるウチに、「陣くんが作るぐらいしれてるんやから好きなだけもっていけ。」と言うてくれてる。
このシャコ万力という強力なクランプも貸してくれた。
これで締め付けてる間に溶接する。
もらってきた角パイプを繋いでチャンネルに沿わせて補強にした。
こんだけ頑丈になれば大丈夫やと思う。
何でもテキトーに即興で作るんで、問題が発生したらその時に対応する。
「問題が発生しないように作る。」事に頭を悩ませたりするのはナンセンス極まりない。
鉄の自作系のDIYは意外と簡単やし、木では無理な強度の構造物が出来るんで、廃材建築家としてはドンドンスキルを磨いていきたい分野。
建築関係のアルバイトすらしたことなくて家を2軒建てたのと同様、鉄工所で働いて技術を習得しなくとも、何とかやってる。
この「やってるうちに出来るようになる。」というのが共通項。
何でも、「正式に習わないといけない。」という幻想に捉われてることが多い。
資格がないと〇〇できないというのもおかしなもの。
こういうのも結局は好きか嫌いか、になってくる。
僕は「ゲリラ好き」なので、こういうスタイル。
正式や資格の好きな人はそういう路線でええし。
要するに、自分の作業そのものが楽しいのなら「ゲリラ」で十分。
客観的な評価を必要とするのなら「正式」の方がいい。
一つの分野をマニアックに研究したり、スキルを高めたいとかも「正式」の方がいいんかな?
どっちでもええんやけど、ほんとに「どっちがええやろ?」と純粋に選べる方がいい。
「これはこういうもん。」とハナから選択肢がないのは気持ち悪い。
そうして自由な選択の結果として、どっちになってもいい。
自分で決めないとスッキリしないからね。
タグ :溶接
2011年12月11日
自作スタンド
ホームセンターに買い物に行った。
ついでにLEDの球が安くなってきたのでチェック。
とはいえ家中の球を全部替えるのには躊躇する。
まずは子どもたちが本やマンガを読むのに必要な電気スタンドを作ろうと思い立った。
最低限の部品を買って自作する。

大工さんの持ってくる廃材で本体を作る。
廃材を見ながら直観でデザインを考える。

4寸角の太い材木を台にしよう。

完成。
夕方1時間ぐらいのちょこっと作業。
廃材でも、磨けば美しい製品になる。
ソケットを取りつける首の部分を切ったり磨いたりしてスリムなデザインにした。
買ったのはLEDの球とガイシのソケットとスイッチ。
コードは電化製品の産廃から外してストックしてある。
ココがポイント。
電線やコンセントなどが以外とかかる所やからね。
家だけじゃなく、こういう日常使うちょっとしたものも作る。
ちょっとしたものを作る所から始めて、、、。
というのと反対。
僕は11年前、いきなり家を作った。
建築関係のアルバイト経験すらなく、日曜大工もほとんどしたことないままに。
7~8mの木の電柱を4t車で30本ぐらいもらってきた。
「さあ、これを切る本格的なチェーンソーってどこで買うんやろ?」という所から。
完成予想図も設計図もなしにやり始める。
やり始めさえすれば。
そして、止めなければ。
絶対に形になる。
当たり前すぎてアホらしいけど、、、。
それをやり続けるのに必要なのは「時間」。
一軒目の廃材ハウスの時から今に至るまで、自給いくらのアルバイトはしない。
何よりも大切なのは自分の時間。
それさえあれば何でも好きなことができる。
「モモ」に出てくる灰色の男に気をつけろ!
ついでにLEDの球が安くなってきたのでチェック。
とはいえ家中の球を全部替えるのには躊躇する。
まずは子どもたちが本やマンガを読むのに必要な電気スタンドを作ろうと思い立った。
最低限の部品を買って自作する。
大工さんの持ってくる廃材で本体を作る。
廃材を見ながら直観でデザインを考える。
4寸角の太い材木を台にしよう。
完成。
夕方1時間ぐらいのちょこっと作業。
廃材でも、磨けば美しい製品になる。
ソケットを取りつける首の部分を切ったり磨いたりしてスリムなデザインにした。
買ったのはLEDの球とガイシのソケットとスイッチ。
コードは電化製品の産廃から外してストックしてある。
ココがポイント。
電線やコンセントなどが以外とかかる所やからね。
家だけじゃなく、こういう日常使うちょっとしたものも作る。
ちょっとしたものを作る所から始めて、、、。
というのと反対。
僕は11年前、いきなり家を作った。
建築関係のアルバイト経験すらなく、日曜大工もほとんどしたことないままに。
7~8mの木の電柱を4t車で30本ぐらいもらってきた。
「さあ、これを切る本格的なチェーンソーってどこで買うんやろ?」という所から。
完成予想図も設計図もなしにやり始める。
やり始めさえすれば。
そして、止めなければ。
絶対に形になる。
当たり前すぎてアホらしいけど、、、。
それをやり続けるのに必要なのは「時間」。
一軒目の廃材ハウスの時から今に至るまで、自給いくらのアルバイトはしない。
何よりも大切なのは自分の時間。
それさえあれば何でも好きなことができる。
「モモ」に出てくる灰色の男に気をつけろ!
タグ :スタンド
2011年11月25日
ピザ窯のアウトラインが見えてきた
移動式ピザ窯に屋根をつける計画進行中。
何度も書いてるけど、廃材の家作りも薪ストーブやピザ窯のような廃材鉄工も、設計図や完成予想図はナシ。
たまたま目の前に山と積まれた廃材から「お、コレ使お!」と閃き、作業を始める。
素人ほどこの直感型じゃないと家ぐらいデカイものには対応できない。
一つの工程を進めるとで次の工程が見えてくる。
このピザ窯の屋根も、「窯が丸いからドーム状の屋根にしようかな。」と何となく始めた。
徐々に形になってくるごとに自分の中で具体的に次の展開が見えてくる。

こんなん。

このフレームに0、3㎜の平トタンの廃材を小さくして張っていくかな。
そんなのも張り始めてからまた細かい所を考える。
もう今シーズンはピザ屋の出店はないかなー、と思ってたら12/17(高松)、12/23(善通寺)があるし。
それまではまだ時間があるからじっくりいこう。
何度も書いてるけど、廃材の家作りも薪ストーブやピザ窯のような廃材鉄工も、設計図や完成予想図はナシ。
たまたま目の前に山と積まれた廃材から「お、コレ使お!」と閃き、作業を始める。
素人ほどこの直感型じゃないと家ぐらいデカイものには対応できない。
一つの工程を進めるとで次の工程が見えてくる。
このピザ窯の屋根も、「窯が丸いからドーム状の屋根にしようかな。」と何となく始めた。
徐々に形になってくるごとに自分の中で具体的に次の展開が見えてくる。
こんなん。
このフレームに0、3㎜の平トタンの廃材を小さくして張っていくかな。
そんなのも張り始めてからまた細かい所を考える。
もう今シーズンはピザ屋の出店はないかなー、と思ってたら12/17(高松)、12/23(善通寺)があるし。
それまではまだ時間があるからじっくりいこう。
タグ :ピザ窯
2011年11月22日
薪ストーブ調子ええよ
薪ストーブが完成したんで、煙突工事。

秋の台風の最中に、自称日本でも最大級の雨漏りの体験を経て、農業用ビニールで直した屋根。
まだ、そのビニールのまんま。
ほんとはこの上に何か廃材で屋根を葺かないといかんのやけど、いい廃材がなくて保留中。
まず、ビニールをカッターで切って穴を開けた。

こういうステンレスの煙突はある時には廃材としてもらってきて、ゴロゴロ邪魔になってるようなもの。
今はなくて、アチコチ電話しまくって探したけど、それでもなかった。
早くストーブを焚きたいし、そう高いものでもないんで新調した。

根元は厚い鉄管にして強化されたし、ストーブとしての機能はこれでバッチリ。
この煙突をストレートにするのが重要。
松をくべようが、少々湿っていようが、まず煤掃除フリーでずっと使える。
たまにゴンゴン叩くとストーブ内に煤が落ちてくる。

耐熱ガラス越しに見える美しい炎はなくて、こんだけ。
実質本位の廃材天国としてはこれでOK。

このドでかい薪が丸ごと入るのがポイント。
シルバー人材センターのおっちゃんが持ってきてくれるのを運んでくべるだけ。
真冬は一輪車に何台分も焚くけど、供給量の方が上回ってて消費しきれない。

移動式ピザ窯の屋根はこんな風になってきた。

計ったり計算したりしないし、もちろん設計図すらない。
何を作ってもそう。
直観と即興。
それが楽しい。
悩んだり苦労の末、超時間かけて完成するようなのは好みじゃない。
もちろんハタから見れば、廃材をこねくり回してロクなもんになってないと思われたってノープロブレム。
僕はこの無限に手に入る廃材を使って遊んでるだけ。
それでいい。
日々「夢中で遊んでるうちに気が付いたら暗くなってた。」みたいなもん。
そのうち「遊んでるうちに気が付いたら人生終わってた。」ということになるだけ。
別に偉大な人生になる必要性はないぞ。
客観的な世間の評価云々はもとより、権威と金に結びつくことをしなければ成功だ!
僕はね。
秋の台風の最中に、自称日本でも最大級の雨漏りの体験を経て、農業用ビニールで直した屋根。
まだ、そのビニールのまんま。
ほんとはこの上に何か廃材で屋根を葺かないといかんのやけど、いい廃材がなくて保留中。
まず、ビニールをカッターで切って穴を開けた。
こういうステンレスの煙突はある時には廃材としてもらってきて、ゴロゴロ邪魔になってるようなもの。
今はなくて、アチコチ電話しまくって探したけど、それでもなかった。
早くストーブを焚きたいし、そう高いものでもないんで新調した。
根元は厚い鉄管にして強化されたし、ストーブとしての機能はこれでバッチリ。
この煙突をストレートにするのが重要。
松をくべようが、少々湿っていようが、まず煤掃除フリーでずっと使える。
たまにゴンゴン叩くとストーブ内に煤が落ちてくる。
耐熱ガラス越しに見える美しい炎はなくて、こんだけ。
実質本位の廃材天国としてはこれでOK。
このドでかい薪が丸ごと入るのがポイント。
シルバー人材センターのおっちゃんが持ってきてくれるのを運んでくべるだけ。
真冬は一輪車に何台分も焚くけど、供給量の方が上回ってて消費しきれない。
移動式ピザ窯の屋根はこんな風になってきた。
計ったり計算したりしないし、もちろん設計図すらない。
何を作ってもそう。
直観と即興。
それが楽しい。
悩んだり苦労の末、超時間かけて完成するようなのは好みじゃない。
もちろんハタから見れば、廃材をこねくり回してロクなもんになってないと思われたってノープロブレム。
僕はこの無限に手に入る廃材を使って遊んでるだけ。
それでいい。
日々「夢中で遊んでるうちに気が付いたら暗くなってた。」みたいなもん。
そのうち「遊んでるうちに気が付いたら人生終わってた。」ということになるだけ。
別に偉大な人生になる必要性はないぞ。
客観的な世間の評価云々はもとより、権威と金に結びつくことをしなければ成功だ!
僕はね。
タグ :薪
2011年11月20日
薪ストーブ改造計画進行中
夜中は野遊が窯の番をしてくれてる。
今日の早朝からは従兄のイッサも加わり、みんなでやってくれてる。
お陰で僕は溶接作業に集中できる。
薪ストーブ改造計画も随分いい所まで進んだ。
下のオーブン室にも扉をつけた。
煙突の根元の部分の鉄管も4、5㎜厚なので、簡単には劣化しないと思う。
下の部屋からの煙が、上の部屋の右奥の四角い煙突から抜ける。
後はストーブの上に開けた3つの穴の加工を残すのみ。
使ってみんと分からんけど、これは随分快適になると思う。
作業も思ったほど大変じゃなかったし。
全てやりながら、考える。
素人は一つ進まないと次が見えてこない。
取りかかる前から完成を思い描くのが無理でも、こうして一つまた一つと進んでいくごとに閃きも加速して、完成に近づいていく。
これなら思考も実践もストップしない。
「出来る気がしない。」もしくは「自分に出来るかどうかすら考えたことがない。」というのが最初の壁。
完成を目指すな。
まず、最初のステップに取り掛かろう。
それが廃材集めだ。
作れるかどうかよりも、材料がないと始まらない。
廃材ありきで家もストーブもデザインが決まってくる。
しかも廃材なので、失敗しても惜し気がないし。
そうこうやってるウチに何かしらのアイデアが生まれてくる。
その繰り返し。
目の前に材料が山と積まれたら、それをどうにかしたくなる衝動が生まれるもの。
タグ :薪ストーブ
2011年11月11日
自作薪ストーブ改造計画
廃材天国では料理、暖房、風呂と毎日の熱源は全て薪。
家の材料も全て廃材なら、燃料も全て廃材。
住み始めた08年は鋳物の縦長の薪ストーブだった。
それでは能力が低くて、作ろうと思い立った。
思えばそれがぶっつけ本番の初めての溶接やった。
09年に作り、2シーズンを経た自作薪ストーブを改造することにした。
もちろん薪ストーブの鉄板も鉄工所の廃材。
思いつきでテキトーに作って、使ってみて直す。
コレが基本。
その割には2シーズンも使ったって事はまあまあ満足してた。
約30坪の仕切りナシ、高さ4、5mの部屋を22、3℃までは楽にもっていける能力。
よくある薪ストーブのカタログにあるカロリーで言うとめっちゃ強力やと思われる。

コレがそう。
廃材の鉄板を溶接しただけの箱。
直径20㎝、長さ60㎝ぐらいの薪が2、3本くべられてジャンジャン燃える。
松とかだと鉄板が赤くなる程。
主に薪は造園業のおっちゃんが50~60㎝に切って持ってきてくれる。
ラッシュ時には「迷惑にならんようにウチで積みこむから。」と道路沿いの薪置き場に積み込みまでしてくれてる。
ストックが大量にあって、切迫して欲しい状況じゃないと、「今あるしなー。」と廃材をもらい渋ることになる。
そうなればもらって欲しい相手としては、出来るだけ僕が頷く条件にする。
で、常に山程の薪があって、悠々と快適な左ウチワ薪生活が実現する。
薪ストーブ=鋳物というイメージがある。
バーモントキャスティングス、ダッチウエスト、ヨツールのような外国製のそれは小さくて3、40万、大きくなると6、70万とかする。
同じ鋳物でも最近ホームセンターでよく見る中国製だと10万もしない。
一軒目の廃材ハウスの薪ストーブはその中国製の5万ぐらいのやった。
リビングの天井の高さもふつうの家ぐらいで、12坪やったんでそれで十分やった。
では、能力的に満足してるのにナゼ改造するのか?
よくあるステンレスの直径12㎝の煙突に小さな穴が何か所も開いて、プラネタリウム状にキラキラし始めたから。
この間の屋根の工事の時に煙突を外した。
そのついでもあって、改造を思いついた。

左は最初の煙突用、右が09年に開けた穴。
今はビニールで防水されて光だけが入ってくる。
こういう風に屋根に穴を開けて、煙突をストレートに屋外に出すのが理想的。
一軒目の廃材ハウスの時は横に曲げて出してたから、1シーズンに2、3回は煤掃除が必要やった。
それも、早めにすればいいけど、「引きが悪くなってきななー。」と思いながら焚いてて、夜に急に詰まって部屋中煙だらけになって、窓を全部開けて急遽煙突を外したり、、、。
ま、そういう非常事態が楽しくてこういう生活をしてる節はあるけど、一回苦労した事をみすみす繰り返しはしない。
今の廃材天国では料理用のステンレスカマド、薪ストーブ、五右衛門風呂とどれも煙突はストレート。
これなら全くの煤掃除いらず。
で、煙突に穴が開く問題を解決するために、近所の鉄工所へ。
社長と、鉄の廃材置き場でしばらく喋ってると。
あった。
ありました。
丁度いいのが。
ただ、直径が14㎝でちょい太めの鉄管。
これに12㎝の普通のステンレスの煙突をつけるように工夫しないといけない。
そのアイデアは寝かせて温めよう。
それともう一つ。
折角、一旦薪ストーブを外すんやから、更に快適に使えるようにしたい。
今までは一枚目の写真の状態で焚いてた。
冬はステンレスカマドの出番がなくなり、料理は全てこのストーブの上に移動する。
一つは低くて腰が痛くなること。
もう一つは強火を得るにはガンガンに燃やさないといけなくて、料理してる本人が暑くてしんどくなること。

まずは足をつけた。
これで料理時の高さはバッチリ。
移動式ピザ窯を作った時の頑丈なアングルが残ってたんで、カットしてつけただけ。
後は暑さ対策。
色々アイデアはある。
この、「どうしよっかなー♪」というのが一番楽しくてやってるようなもの。
家の材料も全て廃材なら、燃料も全て廃材。
住み始めた08年は鋳物の縦長の薪ストーブだった。
それでは能力が低くて、作ろうと思い立った。
思えばそれがぶっつけ本番の初めての溶接やった。
09年に作り、2シーズンを経た自作薪ストーブを改造することにした。
もちろん薪ストーブの鉄板も鉄工所の廃材。
思いつきでテキトーに作って、使ってみて直す。
コレが基本。
その割には2シーズンも使ったって事はまあまあ満足してた。
約30坪の仕切りナシ、高さ4、5mの部屋を22、3℃までは楽にもっていける能力。
よくある薪ストーブのカタログにあるカロリーで言うとめっちゃ強力やと思われる。
コレがそう。
廃材の鉄板を溶接しただけの箱。
直径20㎝、長さ60㎝ぐらいの薪が2、3本くべられてジャンジャン燃える。
松とかだと鉄板が赤くなる程。
主に薪は造園業のおっちゃんが50~60㎝に切って持ってきてくれる。
ラッシュ時には「迷惑にならんようにウチで積みこむから。」と道路沿いの薪置き場に積み込みまでしてくれてる。
ストックが大量にあって、切迫して欲しい状況じゃないと、「今あるしなー。」と廃材をもらい渋ることになる。
そうなればもらって欲しい相手としては、出来るだけ僕が頷く条件にする。
で、常に山程の薪があって、悠々と快適な左ウチワ薪生活が実現する。
薪ストーブ=鋳物というイメージがある。
バーモントキャスティングス、ダッチウエスト、ヨツールのような外国製のそれは小さくて3、40万、大きくなると6、70万とかする。
同じ鋳物でも最近ホームセンターでよく見る中国製だと10万もしない。
一軒目の廃材ハウスの薪ストーブはその中国製の5万ぐらいのやった。
リビングの天井の高さもふつうの家ぐらいで、12坪やったんでそれで十分やった。
では、能力的に満足してるのにナゼ改造するのか?
よくあるステンレスの直径12㎝の煙突に小さな穴が何か所も開いて、プラネタリウム状にキラキラし始めたから。
この間の屋根の工事の時に煙突を外した。
そのついでもあって、改造を思いついた。
左は最初の煙突用、右が09年に開けた穴。
今はビニールで防水されて光だけが入ってくる。
こういう風に屋根に穴を開けて、煙突をストレートに屋外に出すのが理想的。
一軒目の廃材ハウスの時は横に曲げて出してたから、1シーズンに2、3回は煤掃除が必要やった。
それも、早めにすればいいけど、「引きが悪くなってきななー。」と思いながら焚いてて、夜に急に詰まって部屋中煙だらけになって、窓を全部開けて急遽煙突を外したり、、、。
ま、そういう非常事態が楽しくてこういう生活をしてる節はあるけど、一回苦労した事をみすみす繰り返しはしない。
今の廃材天国では料理用のステンレスカマド、薪ストーブ、五右衛門風呂とどれも煙突はストレート。
これなら全くの煤掃除いらず。
で、煙突に穴が開く問題を解決するために、近所の鉄工所へ。
社長と、鉄の廃材置き場でしばらく喋ってると。
あった。
ありました。
丁度いいのが。
ただ、直径が14㎝でちょい太めの鉄管。
これに12㎝の普通のステンレスの煙突をつけるように工夫しないといけない。
そのアイデアは寝かせて温めよう。
それともう一つ。
折角、一旦薪ストーブを外すんやから、更に快適に使えるようにしたい。
今までは一枚目の写真の状態で焚いてた。
冬はステンレスカマドの出番がなくなり、料理は全てこのストーブの上に移動する。
一つは低くて腰が痛くなること。
もう一つは強火を得るにはガンガンに燃やさないといけなくて、料理してる本人が暑くてしんどくなること。
まずは足をつけた。
これで料理時の高さはバッチリ。
移動式ピザ窯を作った時の頑丈なアングルが残ってたんで、カットしてつけただけ。
後は暑さ対策。
色々アイデアはある。
この、「どうしよっかなー♪」というのが一番楽しくてやってるようなもの。
タグ :薪ストーブ
2010年02月09日
けん引装置の取り付け
ケンシくんの塗装してくれた、軽トラに付ける方のけん引装置。
これをいよいよ車に装着。
塗装をはがさないように丁寧に作業する。
いよいよやねー。
黒に塗装されて中々かっこええな。
窯本体の方も毎日ケンシくんが叩いて締めていく作業を続けてる。
叩く時以外はボロの毛布をかけて、風が当たらないようにしてる。
これはまだまだ乾かない。
というか、ゆっくりと乾く程ヒビのリスクが下がる。
家の中のターザンのロープを延長して、竹に布を巻きつけて座る部分を作ってブランコのようになった。
これはケンシくんのアイデア。
野遊とかはメチャクチャ振って、ロープ大丈夫かなーって心配になるぐらい。
まあ、切れたってたいした事にはならんけど。
にこちゃんもターザンデビュー。





これをいよいよ車に装着。
塗装をはがさないように丁寧に作業する。
いよいよやねー。
黒に塗装されて中々かっこええな。
窯本体の方も毎日ケンシくんが叩いて締めていく作業を続けてる。
叩く時以外はボロの毛布をかけて、風が当たらないようにしてる。
これはまだまだ乾かない。
というか、ゆっくりと乾く程ヒビのリスクが下がる。
家の中のターザンのロープを延長して、竹に布を巻きつけて座る部分を作ってブランコのようになった。
これはケンシくんのアイデア。
野遊とかはメチャクチャ振って、ロープ大丈夫かなーって心配になるぐらい。
まあ、切れたってたいした事にはならんけど。
にこちゃんもターザンデビュー。
2010年01月29日
自作鉄鍋
おととい鉄の廃材をもらいに、いつもの鉄工所へ。
メッシュ状の廃材や、角パイプ、板、、、といろいろもらう。
中に丸い4、5㎜の板があった。
これにフチを付ければ鉄鍋になるやん。
玄米珈琲を薪ストーブの上で煎る際に、いつも使ってるのはフロリダのフリーマーケットで買ってきたロッジの鋳物のフライパン。
他の業務用の鉄のフライパンでは、微妙に底がカーブしてて、ストーブに真ん中だけが、密着してしまう。
ただ、ロッジのフライパンは底はフラットやけど、内径で24、5cm程と小さい。
日本でロッジ製品を買うとなると、デパートでの取り寄せになるんで、まんま定価の超高い。
前々から、何かないかなーと中古厨房機器のテンポスでチェックしてるけど、出ない。
というのも、ビオマーケットに東京の香川物産販売コーナーに出品の話が来た。
うちの出品できるもので、日持ちがするもの、、、。
お菓子類は無理やから、玄米珈琲やな。
2/25から4日間の販売で、人気のあったものはその後も売ってくれるそう。
廃材天国のコンセプトである、自給的な手づくりライフから生まれた品のおすそ分け。
手植えで植えた無農薬のお米を薪ストーブの上で何日もかけて、じっくり煎った玄米珈琲。
いつも、鉄工所の社長に「こうこう、こういう風にできるかな?」と相談すると、「そんなん、簡単やが!」と様々な大型の機械で、切断から曲げとチョチョイと加工してくれる。
今回はフチの3、2㎜の帯鉄をグルーッと曲げるのを専用の機械でやってもらった。
しかも、仕上げ用の流れにくいという溶接棒も頂いた。
後は帰って溶接してくっつけるだけ。
そこそこはうまく出来るようになったとはいえ、プロみたく一定でキレイな溶接にはまだまだ。
(写真の部分はうまくいってる所)
溶接した後をカスを叩いて落としては、何回も凹んだ部分を盛りなおしたり、盛りすぎた所はサンダーで削ったりを繰り返す。
最後に大きめの取っ手を作って溶接して、削って完成!
内径で、33cmの重たーい鉄鍋になった。
ケンシくんはみかんジャムの真空脱気の残りの作業。
それから、仕込んでた米アメが糖化してシャブシャブになったんで、絞り作業。
これも薪ストーブでドロッとするまで煮詰める。
土歩くんは学校の説明会に参加。
土歩くんも学校は楽しみにしてる!



メッシュ状の廃材や、角パイプ、板、、、といろいろもらう。
中に丸い4、5㎜の板があった。
これにフチを付ければ鉄鍋になるやん。
玄米珈琲を薪ストーブの上で煎る際に、いつも使ってるのはフロリダのフリーマーケットで買ってきたロッジの鋳物のフライパン。
他の業務用の鉄のフライパンでは、微妙に底がカーブしてて、ストーブに真ん中だけが、密着してしまう。
ただ、ロッジのフライパンは底はフラットやけど、内径で24、5cm程と小さい。
日本でロッジ製品を買うとなると、デパートでの取り寄せになるんで、まんま定価の超高い。
前々から、何かないかなーと中古厨房機器のテンポスでチェックしてるけど、出ない。
というのも、ビオマーケットに東京の香川物産販売コーナーに出品の話が来た。
うちの出品できるもので、日持ちがするもの、、、。
お菓子類は無理やから、玄米珈琲やな。
2/25から4日間の販売で、人気のあったものはその後も売ってくれるそう。
廃材天国のコンセプトである、自給的な手づくりライフから生まれた品のおすそ分け。
手植えで植えた無農薬のお米を薪ストーブの上で何日もかけて、じっくり煎った玄米珈琲。
いつも、鉄工所の社長に「こうこう、こういう風にできるかな?」と相談すると、「そんなん、簡単やが!」と様々な大型の機械で、切断から曲げとチョチョイと加工してくれる。
今回はフチの3、2㎜の帯鉄をグルーッと曲げるのを専用の機械でやってもらった。
しかも、仕上げ用の流れにくいという溶接棒も頂いた。
後は帰って溶接してくっつけるだけ。
そこそこはうまく出来るようになったとはいえ、プロみたく一定でキレイな溶接にはまだまだ。
(写真の部分はうまくいってる所)
溶接した後をカスを叩いて落としては、何回も凹んだ部分を盛りなおしたり、盛りすぎた所はサンダーで削ったりを繰り返す。
最後に大きめの取っ手を作って溶接して、削って完成!
内径で、33cmの重たーい鉄鍋になった。
ケンシくんはみかんジャムの真空脱気の残りの作業。
それから、仕込んでた米アメが糖化してシャブシャブになったんで、絞り作業。
これも薪ストーブでドロッとするまで煮詰める。
土歩くんは学校の説明会に参加。
土歩くんも学校は楽しみにしてる!