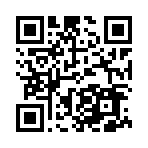2009年11月29日
すもも村、ピザ窯完成!
で、出来た、、、。
ふぅ~、、、。
三木町の今回窯うを作った場所は果樹のふんだんにある雑木林&畑。
その名も「すもも村」という所。
すももの木が一番多いから。
こんなにも、「これほんまに二日で出来るんかなー、、、。」という不安と、何が何でもやらなしゃあないというプレッシャーのかかった窯作りは後にも先にもないね。
昨日の瓦の土台が未完成やったのを今日は朝、8時半から再スタート。
野遊もスコップに鍬にどんどん仕事して「これは相当やっとるなー。」とおじさんたちの度肝を抜いてたね。
特にモルタル練る時の手つき、スコップや鍬を使う時の腰の入れ方、身体の捌き方に経験のある大人たちだからこそ驚嘆の連続。
昨日よりは人手があると言うてもみんな、僕の両親以上のお年の方ばかり、、、。
それをあんまし、「はい、次はコレ!」「オイ、それ取って!」とじゃんじゃん使う訳にもいかないんで、自分で積極的にフルパワーで動くしかない、、、。
思いっきり動きながらも、時間的な制限と、次々に展開する窯作りの段取り、高齢の参加者さんたちにも気を遣いながら、、、と身体も神経も最大限に稼動させたね。
ここの所、段取りさえキチンと踏んでたらスムーズに運ぶようになってきてただけあって、「!!!???」の脳味噌コンフューズ連続カオス状態、、、。
心底、疲労コンパイでありがとうございましたー!でした、、、。
自分でも凄いと思ったのは、結局、今日の午前中まで土台に費やしたのに、夕方暗くなる前には窯が完成した上に、片付けまでを終えられた事。
ほんま、今日の午後のスパートが凄かった。
窯、本体の粘土、ワラ、砂を混ぜての練り具合をかなり柔らかめにして、練りやすくした。
もちろん水分は少なければ少ない程いい。
水分を多く含む程、後の収縮が大きくなり、ヒビ割れの危険性が高まる。
でも、今回に限ってはそんな事を言うてられなかったね。
水分が少ないって事は長靴やスコップに粘土がへばりついて何倍もの労力になるからね。
とにかく、今日中に完成させる事にウエイトを置いた。
もちろん、そこまで無理せんでも月曜にもちこしても問題はないんやけど、みんなが土日に集って最後の夕方に美しく終えるという雰囲気を優先した。
ワークショップである以上はこの雰囲気って大事。
参加者みんなが楽しんでくれて、「二日でここまで出来るんやー!?」という感動の体験が出来る醍醐味。
きちんとやればやる程、堅牢になるし、デティールにも凝れる。
もちろん、やればやるほどキリがない。
クオリティー的にはこの間火事で焼失した廃材天国の窯がピンやったけどね。
そう考えたら今回は今回で、最大限僕の出来る事をやりきったね。
いやー、それにしても、この瓦の土台の窯はカッコええなーーー。
何枚使こたか分からんけど、この大量の瓦は美しい。
今日も女性陣は、薪でお釜の炊き込みご飯作ってくれたり、ワラ焼きのローストビーフ入りのサラダ、大根の味噌汁と最高のアウトドア料理のオンパレード。
昼前には土歩くん、にこちゃんも到着して、思う存分遊びまわってたね。
おやつには熾き火で焼き芋焼いたり。
窯作りはギリギリ感たっぷりで、僕にはスリリングすぎたけど、いざピザを焼くようになれば女性陣も本領発揮して楽しいに違いないね。
最後、煙突をつけて、耐火コーキングをした後に、立派なクヌギの枝が煙突の上にかぶさってたのを木に登って切ったりと最後のケアまでうまくいったね。
ある意味、かなりいい経験になった。
今後たくさんのピザ窯作りを控えてるだけにね。
こればっかしはケースバイケースで臨機応変に対応せなね。
間違いなく、いっつも結果オーライ!
このギリギリやけど、終わってみると大成功ってのがええんよねー。
最後の写真見ても分かると思うけど、ホント最高のロケーションやね。
こんな大木のある雑木林の脇の畑付きのピザ窯はありえないね。
しかも、高松の中心から車で30分未満の所。
東バイパスからほんのちょっと入ったところにあるんやからねー。
一月の終わりに初ピザパーティーするんやと。
トッピングは白菜、大根、春菊、ほうれん草の冬野菜ピザやねーーー。
白菜の塩もみに純正の圧搾ゴマ油たらしたのを生地に乗せたりね。





ふぅ~、、、。
三木町の今回窯うを作った場所は果樹のふんだんにある雑木林&畑。
その名も「すもも村」という所。
すももの木が一番多いから。
こんなにも、「これほんまに二日で出来るんかなー、、、。」という不安と、何が何でもやらなしゃあないというプレッシャーのかかった窯作りは後にも先にもないね。
昨日の瓦の土台が未完成やったのを今日は朝、8時半から再スタート。
野遊もスコップに鍬にどんどん仕事して「これは相当やっとるなー。」とおじさんたちの度肝を抜いてたね。
特にモルタル練る時の手つき、スコップや鍬を使う時の腰の入れ方、身体の捌き方に経験のある大人たちだからこそ驚嘆の連続。
昨日よりは人手があると言うてもみんな、僕の両親以上のお年の方ばかり、、、。
それをあんまし、「はい、次はコレ!」「オイ、それ取って!」とじゃんじゃん使う訳にもいかないんで、自分で積極的にフルパワーで動くしかない、、、。
思いっきり動きながらも、時間的な制限と、次々に展開する窯作りの段取り、高齢の参加者さんたちにも気を遣いながら、、、と身体も神経も最大限に稼動させたね。
ここの所、段取りさえキチンと踏んでたらスムーズに運ぶようになってきてただけあって、「!!!???」の脳味噌コンフューズ連続カオス状態、、、。
心底、疲労コンパイでありがとうございましたー!でした、、、。
自分でも凄いと思ったのは、結局、今日の午前中まで土台に費やしたのに、夕方暗くなる前には窯が完成した上に、片付けまでを終えられた事。
ほんま、今日の午後のスパートが凄かった。
窯、本体の粘土、ワラ、砂を混ぜての練り具合をかなり柔らかめにして、練りやすくした。
もちろん水分は少なければ少ない程いい。
水分を多く含む程、後の収縮が大きくなり、ヒビ割れの危険性が高まる。
でも、今回に限ってはそんな事を言うてられなかったね。
水分が少ないって事は長靴やスコップに粘土がへばりついて何倍もの労力になるからね。
とにかく、今日中に完成させる事にウエイトを置いた。
もちろん、そこまで無理せんでも月曜にもちこしても問題はないんやけど、みんなが土日に集って最後の夕方に美しく終えるという雰囲気を優先した。
ワークショップである以上はこの雰囲気って大事。
参加者みんなが楽しんでくれて、「二日でここまで出来るんやー!?」という感動の体験が出来る醍醐味。
きちんとやればやる程、堅牢になるし、デティールにも凝れる。
もちろん、やればやるほどキリがない。
クオリティー的にはこの間火事で焼失した廃材天国の窯がピンやったけどね。
そう考えたら今回は今回で、最大限僕の出来る事をやりきったね。
いやー、それにしても、この瓦の土台の窯はカッコええなーーー。
何枚使こたか分からんけど、この大量の瓦は美しい。
今日も女性陣は、薪でお釜の炊き込みご飯作ってくれたり、ワラ焼きのローストビーフ入りのサラダ、大根の味噌汁と最高のアウトドア料理のオンパレード。
昼前には土歩くん、にこちゃんも到着して、思う存分遊びまわってたね。
おやつには熾き火で焼き芋焼いたり。
窯作りはギリギリ感たっぷりで、僕にはスリリングすぎたけど、いざピザを焼くようになれば女性陣も本領発揮して楽しいに違いないね。
最後、煙突をつけて、耐火コーキングをした後に、立派なクヌギの枝が煙突の上にかぶさってたのを木に登って切ったりと最後のケアまでうまくいったね。
ある意味、かなりいい経験になった。
今後たくさんのピザ窯作りを控えてるだけにね。
こればっかしはケースバイケースで臨機応変に対応せなね。
間違いなく、いっつも結果オーライ!
このギリギリやけど、終わってみると大成功ってのがええんよねー。
最後の写真見ても分かると思うけど、ホント最高のロケーションやね。
こんな大木のある雑木林の脇の畑付きのピザ窯はありえないね。
しかも、高松の中心から車で30分未満の所。
東バイパスからほんのちょっと入ったところにあるんやからねー。
一月の終わりに初ピザパーティーするんやと。
トッピングは白菜、大根、春菊、ほうれん草の冬野菜ピザやねーーー。
白菜の塩もみに純正の圧搾ゴマ油たらしたのを生地に乗せたりね。
2009年11月29日
ピザ窯作りワークショップ
今、県外から4つも依頼が入ってる人気ワークショップになった、ピザ窯作り。
この土日は県内の三木町。
医大のすぐ近くの、小高い雑木林のある畑。
柑橘類がいろいろ、イチジク、スモモ、花梨、柿、などのいろんな種類の果物の樹。
その間には今の冬野菜が美しく育てられてる。
そんないい感じの畑が、主催者の自宅のすぐ隣にある。
やっぱ、畑って家のすぐ目の前じゃないとねー。
今の廃材天国の畑は花壇程度で、面積をたくさん作ってるのは親父がメインでやってる方の畑で、自転車で、3、4分とちょっと離れた所にある。
大根2、3本と葉物をいろいろとか、ちょっとした収穫を考えると軽トラで行くんで、毎日は行かないもん。
その雑木林の中に2坪ぐらいの小さなキットログの小屋がある。
その小屋から軒を大きく出して、そこへピザの窯を作るという計画。
軒は予め大工さんに頼んで、美しい新品の木でがっしりとしたのが出来上がってた。
粘土は車で一時間強の県内なので、僕の陶芸用の土を軽トラで搬入。
この粘土の質が一番大事やからね。
ほんと、現地に着いて「ええっ、まさか、この粘土で、、、。」と目が点になったケースもあった。
今は県外の場合、僕の持ってる粘土をサンプルとして送って、探してもらい、先方からも「こういうのが手に入りそう。」と僕に送ってもらって、最終チェックをしてゴーを出すようにした。
やっぱりオール粘土の窯やし、それなりに耐久性も考えると、粘土の粘性、耐火性などが重要。
厳密に言うと、収縮性とか細かい事になってくるけど、キリがないんで、とりあえず粘性だけはそれなりに強いもので、そこまで砂や砂利の率が高くないもの。
土台は大体現地にあるもので、というケースが多い。
ゴロゴロの大きな石がある時は石組み。
孟宗竹の竹薮があって、時期が大丈夫なら、四方を竹で組んで、中に砂利や土を入れて踏み固める。
何しろ、前にうちで採用してた、全部廃材の丸太を組み合わせるのは、火事の可能性があってNG(笑)。
今回は大量に瓦があった。
しかも、割れたりしてなくて状態がいい。
この瓦を四方に塀状に積み込んで、中に土と割れた瓦を混ぜて突き固める。
これは初めてやけど、堅牢やし、美しい~。
お昼には女性陣がマメに仕込みをしてくれての、打ち込みうどん、大根サラダ、オムスビ。
大鍋で作る打ち込みうどんは美味いねー。
里芋や白ネギに油揚げが入るとパーフェクトやね。
お約束の近所の何でも出来るおっちゃんなんかも居て、僕が持って行ってない道具なんかを取りに帰ってくれたりして、超助かった。
ただ、、、。
午前中、そのおっちゃんともう一人と、こつこつ作業してて、「えらい人数少ないなど、大丈夫かなー。」と不安に思い始めてて。
お昼どきのうどんパーティーの時にわーっと大勢来てくれたー、と思ったら、またお昼タイムが終わったらザーッと帰って、また2、3人に、、、。
結局土台は7割方までは持っていったけど、予定の完成までは行けんかった。
僕ともう一人とかの時間帯も結構あったからねー。
何回も「10人前後参加者集まれば土日で出来ますよ。」と主催者の方には言ったんやけど、、、。
こっちも引き受けた以上は完成させな責任あるしで、昨日は超ハイピッチでの作業に肩から背中、腰にかけての疲労が、、、。
今日はもう少しは人手が期待できるそうなんで、張り切って行こう!
昨日はちびっ子は「みたから市」にあっこちゃんと出店してたんで、今日は野遊も窯作りに行く気満々。
玄米も炊けたし、そろそろ行こかなー。



この土日は県内の三木町。
医大のすぐ近くの、小高い雑木林のある畑。
柑橘類がいろいろ、イチジク、スモモ、花梨、柿、などのいろんな種類の果物の樹。
その間には今の冬野菜が美しく育てられてる。
そんないい感じの畑が、主催者の自宅のすぐ隣にある。
やっぱ、畑って家のすぐ目の前じゃないとねー。
今の廃材天国の畑は花壇程度で、面積をたくさん作ってるのは親父がメインでやってる方の畑で、自転車で、3、4分とちょっと離れた所にある。
大根2、3本と葉物をいろいろとか、ちょっとした収穫を考えると軽トラで行くんで、毎日は行かないもん。
その雑木林の中に2坪ぐらいの小さなキットログの小屋がある。
その小屋から軒を大きく出して、そこへピザの窯を作るという計画。
軒は予め大工さんに頼んで、美しい新品の木でがっしりとしたのが出来上がってた。
粘土は車で一時間強の県内なので、僕の陶芸用の土を軽トラで搬入。
この粘土の質が一番大事やからね。
ほんと、現地に着いて「ええっ、まさか、この粘土で、、、。」と目が点になったケースもあった。
今は県外の場合、僕の持ってる粘土をサンプルとして送って、探してもらい、先方からも「こういうのが手に入りそう。」と僕に送ってもらって、最終チェックをしてゴーを出すようにした。
やっぱりオール粘土の窯やし、それなりに耐久性も考えると、粘土の粘性、耐火性などが重要。
厳密に言うと、収縮性とか細かい事になってくるけど、キリがないんで、とりあえず粘性だけはそれなりに強いもので、そこまで砂や砂利の率が高くないもの。
土台は大体現地にあるもので、というケースが多い。
ゴロゴロの大きな石がある時は石組み。
孟宗竹の竹薮があって、時期が大丈夫なら、四方を竹で組んで、中に砂利や土を入れて踏み固める。
何しろ、前にうちで採用してた、全部廃材の丸太を組み合わせるのは、火事の可能性があってNG(笑)。
今回は大量に瓦があった。
しかも、割れたりしてなくて状態がいい。
この瓦を四方に塀状に積み込んで、中に土と割れた瓦を混ぜて突き固める。
これは初めてやけど、堅牢やし、美しい~。
お昼には女性陣がマメに仕込みをしてくれての、打ち込みうどん、大根サラダ、オムスビ。
大鍋で作る打ち込みうどんは美味いねー。
里芋や白ネギに油揚げが入るとパーフェクトやね。
お約束の近所の何でも出来るおっちゃんなんかも居て、僕が持って行ってない道具なんかを取りに帰ってくれたりして、超助かった。
ただ、、、。
午前中、そのおっちゃんともう一人と、こつこつ作業してて、「えらい人数少ないなど、大丈夫かなー。」と不安に思い始めてて。
お昼どきのうどんパーティーの時にわーっと大勢来てくれたー、と思ったら、またお昼タイムが終わったらザーッと帰って、また2、3人に、、、。
結局土台は7割方までは持っていったけど、予定の完成までは行けんかった。
僕ともう一人とかの時間帯も結構あったからねー。
何回も「10人前後参加者集まれば土日で出来ますよ。」と主催者の方には言ったんやけど、、、。
こっちも引き受けた以上は完成させな責任あるしで、昨日は超ハイピッチでの作業に肩から背中、腰にかけての疲労が、、、。
今日はもう少しは人手が期待できるそうなんで、張り切って行こう!
昨日はちびっ子は「みたから市」にあっこちゃんと出店してたんで、今日は野遊も窯作りに行く気満々。
玄米も炊けたし、そろそろ行こかなー。
2009年11月28日
薪ストーブ本体、見事に完成
新作薪ストーブ。
本体は完成!
薪をくべる扉の部分は4方を40㎜のアングルで囲む。
ストーブ本体が50cm×50cmで奥行き67cm。
扉は45cm×45cm。
溶接用の分厚い蝶番と掛け金をつけて、うまくいった。
真ん中の鉄板の継ぎ目には4、5㎜の帯鉄を溶接して補強。
煙突を付ける部分には丸いワッカを作って溶接して、煙突をつけやすくした。
途中まで2mmの溶接棒で溶接してたんやけど、無くなったんで、2、6㎜のを買ってくると超やりやすくなった!
うちの溶接機では2、6㎜までやろうけど、2mmから比べると全然違うね!!!
是非とも大きな溶接機で3、2mmの溶接棒で溶接してみたいね。
しかし、こんなに大きな扉では、中の薪が燃えてる最中に新たに薪をくべようとして扉を開けると、随分と煙が室内に出てくる。
でも、廃材天国は広いのと天井が高いの、更に低気密性も手伝って、煙が充満して目が痛くなるまではいかない。
黒煎り玄米を練炭七輪で煎る時に締め切ってても、一酸化炭素中毒の心配は全くないぐらいやから。
実は大きな扉にしたのは考えがあっての事。
中にサナ(台)を設けてピザやパンを焼いたり、ロッジのダッチオーブンを放り込めるようにというイメージで大口にした。
別にピザの窯が火事で無くなったからと言う訳ではないよ。
ピザの窯はまたすぐに作るけど、わざわざアレを焚くのにやっぱり、2時間ぐらいはどんどん燃やしてからじゃないとオーブンとして使えない。
それに引き換え、ストーブは冬場は毎日焚く。
ストーブとして毎日焚いてるついでに、中で調理が出来るという構造にしたかった。
これはハセヤンのカナディアンファームからちょっと離れた「かえでの樹」というレストランに鎮座してるキッチンストーブを見て思った。
でかけりゃいいんやと。
もちろん、ハセヤンのそれはデカイだけじゃなく、創意工夫に溢れた多機能のキッチンストーブとして、毎日レストランで実働してるから凄い。
見た目のデザインもワイルドながらも美しく、ちゃんと耐火ガラスも入ってて、中の炎も見える。
そういう意味では今回、廃材天国の新作薪ストーブは焼却炉よろしく何の凝った意匠もない、ただの鉄の箱。
もっと、小さな鉄板をパッチワーク状に溶接しまくって、ハウルの動く城のように迫力のあるデザインにしたかったんやけど、たまたま大きな鉄板があったり、正面の扉は鉄工所の社長がわざわざ作ってくれたりしたしね。
今回は溶接でここまで大きなモノに挑むのが初めてというのと、出店やピザ窯作りの仕事の合間をぬって、2、3日でパパッと作りたかったから、という理由でこうなった。
大体うちは、何でもパパッと終わらせたいからデザイン的に凝るということはない。
でもそこは、新しい材料からは決して来ない、廃材たちから貰うインスピレーションでカバーしてる。
溶接に関しては、今回猛烈に自信を持ったんで、今後の「廃材天国鉄工部」が楽しみや。
鉄板の破片は近所の鉄工所の廃材をいくらでももらえるし。
一応、古いストーブと煙突は外した。
で、仮に新作ストーブを置いてみた。
周りには石や耐火煉瓦で囲いも作った。
後は新しい煙突の工事が残ってる。
この間のピザ窯の火事もあるし、今度は屋根にもっと大きく穴を開けて、鉄板を入れよう。
防水はネットで注文した「耐火コーキング」。
まだ使ってないけど、うまくいくとええけどね。
このあたりの「耐火+防水」が非常に難しい。
国内の薪ストーブやステンレスの煙突のシェアでは、トップの「ホンマ製作所」のHPなんか見てると、屋根に取り付ける防水で耐火の部材は一つが何万もする。
そんだけ、堅牢なつくりのステンレスの部材ということやろう。
需要も少ないやろし。
このあたりを見事になんちゃって手づくりでクリアする醍醐味が最高!
この間、ピザ窯の煙突で随分と学んだからねー。
今の所、僕の中では0、3㎜の平トタンに耐火コーキングという結論。
今まで使ってた、セメダイン社の「耐火パテ」では熱で鉄板が変形した際にはがれてしまう。
耐火コーキングは普通のシリコンコーキングと同じサイズで3000円もするからねー。
たぶん大丈夫なんちゃうの。
今日、明日は三木町(県内)でのピザ窯作りワークショップなので、煙突は月曜日に持ち越しやな。



本体は完成!
薪をくべる扉の部分は4方を40㎜のアングルで囲む。
ストーブ本体が50cm×50cmで奥行き67cm。
扉は45cm×45cm。
溶接用の分厚い蝶番と掛け金をつけて、うまくいった。
真ん中の鉄板の継ぎ目には4、5㎜の帯鉄を溶接して補強。
煙突を付ける部分には丸いワッカを作って溶接して、煙突をつけやすくした。
途中まで2mmの溶接棒で溶接してたんやけど、無くなったんで、2、6㎜のを買ってくると超やりやすくなった!
うちの溶接機では2、6㎜までやろうけど、2mmから比べると全然違うね!!!
是非とも大きな溶接機で3、2mmの溶接棒で溶接してみたいね。
しかし、こんなに大きな扉では、中の薪が燃えてる最中に新たに薪をくべようとして扉を開けると、随分と煙が室内に出てくる。
でも、廃材天国は広いのと天井が高いの、更に低気密性も手伝って、煙が充満して目が痛くなるまではいかない。
黒煎り玄米を練炭七輪で煎る時に締め切ってても、一酸化炭素中毒の心配は全くないぐらいやから。
実は大きな扉にしたのは考えがあっての事。
中にサナ(台)を設けてピザやパンを焼いたり、ロッジのダッチオーブンを放り込めるようにというイメージで大口にした。
別にピザの窯が火事で無くなったからと言う訳ではないよ。
ピザの窯はまたすぐに作るけど、わざわざアレを焚くのにやっぱり、2時間ぐらいはどんどん燃やしてからじゃないとオーブンとして使えない。
それに引き換え、ストーブは冬場は毎日焚く。
ストーブとして毎日焚いてるついでに、中で調理が出来るという構造にしたかった。
これはハセヤンのカナディアンファームからちょっと離れた「かえでの樹」というレストランに鎮座してるキッチンストーブを見て思った。
でかけりゃいいんやと。
もちろん、ハセヤンのそれはデカイだけじゃなく、創意工夫に溢れた多機能のキッチンストーブとして、毎日レストランで実働してるから凄い。
見た目のデザインもワイルドながらも美しく、ちゃんと耐火ガラスも入ってて、中の炎も見える。
そういう意味では今回、廃材天国の新作薪ストーブは焼却炉よろしく何の凝った意匠もない、ただの鉄の箱。
もっと、小さな鉄板をパッチワーク状に溶接しまくって、ハウルの動く城のように迫力のあるデザインにしたかったんやけど、たまたま大きな鉄板があったり、正面の扉は鉄工所の社長がわざわざ作ってくれたりしたしね。
今回は溶接でここまで大きなモノに挑むのが初めてというのと、出店やピザ窯作りの仕事の合間をぬって、2、3日でパパッと作りたかったから、という理由でこうなった。
大体うちは、何でもパパッと終わらせたいからデザイン的に凝るということはない。
でもそこは、新しい材料からは決して来ない、廃材たちから貰うインスピレーションでカバーしてる。
溶接に関しては、今回猛烈に自信を持ったんで、今後の「廃材天国鉄工部」が楽しみや。
鉄板の破片は近所の鉄工所の廃材をいくらでももらえるし。
一応、古いストーブと煙突は外した。
で、仮に新作ストーブを置いてみた。
周りには石や耐火煉瓦で囲いも作った。
後は新しい煙突の工事が残ってる。
この間のピザ窯の火事もあるし、今度は屋根にもっと大きく穴を開けて、鉄板を入れよう。
防水はネットで注文した「耐火コーキング」。
まだ使ってないけど、うまくいくとええけどね。
このあたりの「耐火+防水」が非常に難しい。
国内の薪ストーブやステンレスの煙突のシェアでは、トップの「ホンマ製作所」のHPなんか見てると、屋根に取り付ける防水で耐火の部材は一つが何万もする。
そんだけ、堅牢なつくりのステンレスの部材ということやろう。
需要も少ないやろし。
このあたりを見事になんちゃって手づくりでクリアする醍醐味が最高!
この間、ピザ窯の煙突で随分と学んだからねー。
今の所、僕の中では0、3㎜の平トタンに耐火コーキングという結論。
今まで使ってた、セメダイン社の「耐火パテ」では熱で鉄板が変形した際にはがれてしまう。
耐火コーキングは普通のシリコンコーキングと同じサイズで3000円もするからねー。
たぶん大丈夫なんちゃうの。
今日、明日は三木町(県内)でのピザ窯作りワークショップなので、煙突は月曜日に持ち越しやな。
2009年11月27日
講演会
そんなに頻繁にはないけど、久しぶりの講演。
県内のある建設会社の安全大会という会合。
その会社や協力会社、下請けなどで作る安全協力会というもんがあるそうな。
僕の前は国の○○協会の方、熊谷組の安全部の方。
更にはその間で自民党の代議士、大野よしのりの息子さんの挨拶、、、。
「民主党に交代していい所は我々も認める。」
「しかし、箱物=悪では経済はダメになってしまう!。」
「わが国の基幹産業である建設業を盛り返さないと!」
と言う流れに、一同超うなずく。
かなり場違いの所に呼ばれたんちゃう!?
その後で僕の「エコの楽しさ体験」という話。
もちろん、わざわざ「大きな建設会社自体、これから淘汰されて行くでしょうね。」と言う話をするような空気じゃあないし。
僕は、僕のやってきた2軒の廃材の家作りの話。
何でそんな事をやってるのか?
今の廃材天国の話。
安全大会なので、県の建築課の職員に指導を受けた話には一同大爆笑。
時間の都合で、一軒目のひっくり返った話や今回の火事の話まではしなかった。
まあ、ゆめタウンとイオンタウンの間のこの場所で、井戸掘って、毎日薪で料理や風呂焚いて生活してる事だけでもお笑いのネタレベル。
国の職員のパワーポイントでの話で居眠りしてた人も、ちゃんと起きて聞いてくれた。
近頃、店や家がじゃんじゃん出来てる丸亀市郊外での、廃材天国の存在はかなり凄いということを再認識したね。
新聞やテレビもやたらと取材に来るし、こういう講演の依頼もあったり。
ほんでも、一般的な世論からは冷やかしめいた「珍しいモン」扱いやろね。
それはもちろんOK。
こんな生活なり、価値観があっと言う間に浸透するぐらいなら、原発も添加物も世の中には存在できない。
そういう負の存在がなくならないのは、まだまだ資本主義経済が力を持ってるから。
自分や家族、目に見える近所の人たちとのコミュニティーで助け合いながら生活してた数十年前なら話は違う。
近所の人が買ってくれるのが分かってて農薬は使えない。
自分としての判断なら白いものを黒とは言えない。
でも、能率や効率、立場、組織、しがらみ、と自分の感覚以外の部分で判断したり、行動したりするのが常の現状では、反対にそっちが普通。
解決は簡単。
経済がもっともっと落ち込む方向へ行くだけ。
「成長の限界」の折れ線グラフ通り、これから経済は縮小していく。
21世紀にも尚、経済が右肩上がりに成長すると思う?
思うんならこの日記読むなよ!
「今までの常識」という考え方の延長線上で、エコやロハスとカッコつけても白々しいだけ。
大きな会社や行政の言ってるエコなぞ、体裁だけ。
もしくはエコと言いながら更に環境破壊して金儲けするだけ。
そもそも環境に配慮した金儲けは在り得ない。
金が儲かる事自体に問題がある事に関心を持てよ。
はっきり言うよ。
成長し続けないと継続できん経済活動なり、会社は今後必ず潰れていく。
でも、「今までの常識」を外して、これからほんとに必要とされる事をする会社なり活動なら存続できるよ。
もう、車も家も電化製品も十分にある。
そういう「不必要」なものを宣伝や営業して無理に売ろうとしてもダメ。
だって、ようけあるんやもん。
今からは、今失われつつあるものやほんとに生きて行く為に必要なものなら売れる。
それは希少な本醸造の醤油だったり、無農薬のお米だったりする。
しかも、家内制手工業よろしく、大規模な設備や投資を必要としないスタイル。
って、急に、大きな会社が方向転換できんやろねー。
でも今のうちならまだ間に合うかも。
まあ、そういう会社には、はよ潰れてもろた方が問題が少ないわな。
日航に国の税金使うなー。
飛行機や、そなんようけ要らんきん減らせっちゅう事やー。
温暖化対策言うて原発推進するなー。
あんなに大規模に金使って工事する事自体で温暖化じゃん。
それ以前に自分の心で仕事してない電力会社の職員を見てみー。
http://www.youtube.com/watch?v=LcTr27HfZM8&feature=player_embedded#
カヤック隊の活躍はほんとにかっこいい。
国も個人の生活も、大金使わな成りたたんというのはおかしいんやから。
うちみたく、たいして金儲けせんのに豊かに暮らせる努力をすれば生き残れるぞ。
金を儲ける努力と儲けない努力。
今までの常識では圧倒的に後者の方が難しいのかも。
県内のある建設会社の安全大会という会合。
その会社や協力会社、下請けなどで作る安全協力会というもんがあるそうな。
僕の前は国の○○協会の方、熊谷組の安全部の方。
更にはその間で自民党の代議士、大野よしのりの息子さんの挨拶、、、。
「民主党に交代していい所は我々も認める。」
「しかし、箱物=悪では経済はダメになってしまう!。」
「わが国の基幹産業である建設業を盛り返さないと!」
と言う流れに、一同超うなずく。
かなり場違いの所に呼ばれたんちゃう!?
その後で僕の「エコの楽しさ体験」という話。
もちろん、わざわざ「大きな建設会社自体、これから淘汰されて行くでしょうね。」と言う話をするような空気じゃあないし。
僕は、僕のやってきた2軒の廃材の家作りの話。
何でそんな事をやってるのか?
今の廃材天国の話。
安全大会なので、県の建築課の職員に指導を受けた話には一同大爆笑。
時間の都合で、一軒目のひっくり返った話や今回の火事の話まではしなかった。
まあ、ゆめタウンとイオンタウンの間のこの場所で、井戸掘って、毎日薪で料理や風呂焚いて生活してる事だけでもお笑いのネタレベル。
国の職員のパワーポイントでの話で居眠りしてた人も、ちゃんと起きて聞いてくれた。
近頃、店や家がじゃんじゃん出来てる丸亀市郊外での、廃材天国の存在はかなり凄いということを再認識したね。
新聞やテレビもやたらと取材に来るし、こういう講演の依頼もあったり。
ほんでも、一般的な世論からは冷やかしめいた「珍しいモン」扱いやろね。
それはもちろんOK。
こんな生活なり、価値観があっと言う間に浸透するぐらいなら、原発も添加物も世の中には存在できない。
そういう負の存在がなくならないのは、まだまだ資本主義経済が力を持ってるから。
自分や家族、目に見える近所の人たちとのコミュニティーで助け合いながら生活してた数十年前なら話は違う。
近所の人が買ってくれるのが分かってて農薬は使えない。
自分としての判断なら白いものを黒とは言えない。
でも、能率や効率、立場、組織、しがらみ、と自分の感覚以外の部分で判断したり、行動したりするのが常の現状では、反対にそっちが普通。
解決は簡単。
経済がもっともっと落ち込む方向へ行くだけ。
「成長の限界」の折れ線グラフ通り、これから経済は縮小していく。
21世紀にも尚、経済が右肩上がりに成長すると思う?
思うんならこの日記読むなよ!
「今までの常識」という考え方の延長線上で、エコやロハスとカッコつけても白々しいだけ。
大きな会社や行政の言ってるエコなぞ、体裁だけ。
もしくはエコと言いながら更に環境破壊して金儲けするだけ。
そもそも環境に配慮した金儲けは在り得ない。
金が儲かる事自体に問題がある事に関心を持てよ。
はっきり言うよ。
成長し続けないと継続できん経済活動なり、会社は今後必ず潰れていく。
でも、「今までの常識」を外して、これからほんとに必要とされる事をする会社なり活動なら存続できるよ。
もう、車も家も電化製品も十分にある。
そういう「不必要」なものを宣伝や営業して無理に売ろうとしてもダメ。
だって、ようけあるんやもん。
今からは、今失われつつあるものやほんとに生きて行く為に必要なものなら売れる。
それは希少な本醸造の醤油だったり、無農薬のお米だったりする。
しかも、家内制手工業よろしく、大規模な設備や投資を必要としないスタイル。
って、急に、大きな会社が方向転換できんやろねー。
でも今のうちならまだ間に合うかも。
まあ、そういう会社には、はよ潰れてもろた方が問題が少ないわな。
日航に国の税金使うなー。
飛行機や、そなんようけ要らんきん減らせっちゅう事やー。
温暖化対策言うて原発推進するなー。
あんなに大規模に金使って工事する事自体で温暖化じゃん。
それ以前に自分の心で仕事してない電力会社の職員を見てみー。
http://www.youtube.com/watch?v=LcTr27HfZM8&feature=player_embedded#
カヤック隊の活躍はほんとにかっこいい。
国も個人の生活も、大金使わな成りたたんというのはおかしいんやから。
うちみたく、たいして金儲けせんのに豊かに暮らせる努力をすれば生き残れるぞ。
金を儲ける努力と儲けない努力。
今までの常識では圧倒的に後者の方が難しいのかも。
2009年11月26日
もう完成のメドはついたね
オリジナル薪ストーブ作り、続編。
朝8時に鉄工所へ駆け込むと、機械は稼動してて、職人さんは仕事を始めてた。
薪ストーブを作りたいんだという構想を説明して、切れ端の鉄クズが溜められてる大きなボックスの中を物色。
「こないだ出したとこやきん、あんましないぞー。」と社長。
問題は破片の幅。
35cm~40cmもあればそれをツギハギして奥行きを60~70にして長い薪の入るようにしようというアイデア。
そのパッチワークのデザインがまた楽しいんちゃうかなとも思ってた。
鉄板の厚みは4、5㎜とか6㎜とかが理想なのかもしれんけど、あんまし厚いとストーブ本体が重くなりすぎるし。
結構大きめの鉄板が目に付いた。
厚みは3㎜。
長い辺が50cm。
たくさんある。
どうせなら容積が大きい程よく燃えるんで、一辺が50cmで奥行きが65cmの直方体の箱型にすることにした。
ちょっと、このサイズになると、3㎜では薄いと思うけどね。
まあ、材料はタダなんで、練習ってことで、、、。
今シーズンは使えるやろ。
今度は行きつけの金物屋の倉庫へ。
倉庫番のおっちゃんに煙突や平トタンの相談をする。
煙突はここで以前大量にもらったブリキに塗装してある奴がある。
でも、風呂の煙突に使って、一年ぐらいで元口に穴が開いた。
ブリキも薄いしねー。
廃材天国は天井が高いんで、全部ステンレスのを新調すると2万まではいかないけど、かなり高くつく。
なので、火力の強い元口の一本だけステンレスのを買う。
直径12cmの90cmで2000円。
昨日書いたヨーロッパ製の50万とかのストーブには二重煙突が勧められてて、90cmのが一本2万とかする。
煙突全部でストーブ本体と同じぐらいかかるのが常識なんだそう、、、。
アホらし、、、、、。
後、職人さんは使えない傷物の平トタンがうまくあったんで、それはもらった。
これは煙突と屋根の接触部分の部材にする。
早速、帰って、作業に入る。
溶接機を出して、コンテナにコンパネのボロを乗せて作業台にする。
溶接機は家庭用の小さな奴ながらも100Vと単層の200Vとを選択できるようになってて、たまたま解体現場から外してきた、今使ってる分電盤に「エアコン200V」と、ブレーカーの一つが200Vに設定されてた。
そこから(I-)こんな大型のコンセントを付けて配線してある。
それに、溶接棒、面、皮手、こんだけあれば溶接が出来る。
今まで、五右衛門風呂やキッチンストーブの灰をかき出す道具やこないだの軽のバンにつけたアングルで作ったルーフキャリアなど、そんなに長いラインを溶接した経験はなく、途切れつつ、四苦八苦してた。
そこへ、アララトさんが新しく出たコピーフリーの「STOP!上関原発」のDVDを持って来てくれた。
アララトさんは溶接の経験があって、基本的な事をいろいろ実演を交えながら教えてもらった。
祝島や上関の現状もいろいろ聞けた。
先日、電力側が工事延期を発表したけど、現場では着々と準備が進められてて、今も数人が交代で張り付いてる状況なんだと。
以前、山口の「百姓庵」から来て、手伝ってくれたマサも通ってるそう。
結局、「賛成、反対」の二元論で反対派が勝ってもワダカマリは消えない。
そういう地元のドロドロした対立じゃなく、世論的に原発に頼らんでもエネルギーを賄えるようになって、原発なくてもええやん、とならないといけない。
実際にヨーロッパの各国は原発止めていってるんやから。
子どもたちとも一緒に観たけど、このDVDすっごくいいよ。
ほんとにリアリティーを持って生きてる祝島のおばあちゃん、Uターンで帰ってきた若者。
コピーフリーなんで、DVDを焼ける人はどんどん焼いて、みんなに配ろう。
この前はドタキャンになってしまったけど、現場は長期戦の様相やし、みんな手弁当のボランティアでやってるんで、僕も応援に駆けつけたい。
熊本の仕事の後に家族で行こうという話になってきてる。
子どもにもその「今の日本」のリアルな現場の空気を味わわせたいという想いもあるし。
僕はチェーンソーにインパクト持参で現場の小屋や設備を直したりしてあげられるし。
アララトさんから水がないからね、と、井戸が掘れないかという話もあった、、、。
アララトさんが帰ってからは溶接の工程も今までよりはスムーズに進み始めた。
そうしてると近所のおっちゃんが来て「わしも溶接の経験あるんぞ!」と更に指導してもらった。
なんだかんだで、朝もらってきた材料を使って、そこそこの格好にはなってきた。
後は薪をくべる正面だけ。
もう鉄板もないんで、夕方再度鉄工所を訪ねる。
もちろん出来つつある本体を軽トラに乗せて。
「社長、ここまで出来たんやけどー。」と見せると、「ほほう、もうそこまで作ったんか。」と後の材料を段取りしてくれた。
ここからは廃材で丁度いい破片は無かったんで、大きな鉄板を機械にかけて切断してくれたり、長いアングルを切ってくれたり、とキップよくテキパキ加工してくれた。
反対にこんだけしてもろて、材料代すらとらないんで、僕としても次々と頼みに行くのに気を遣う。
今日もまだ少し加工が残ってて、行かないといけないんで、お酒を持って行こうっと。
デジカメ直ったんで写真アップできるようになったよ。
去年まで使ってた縦型の鋳物の薪ストーブと新作の状況。



朝8時に鉄工所へ駆け込むと、機械は稼動してて、職人さんは仕事を始めてた。
薪ストーブを作りたいんだという構想を説明して、切れ端の鉄クズが溜められてる大きなボックスの中を物色。
「こないだ出したとこやきん、あんましないぞー。」と社長。
問題は破片の幅。
35cm~40cmもあればそれをツギハギして奥行きを60~70にして長い薪の入るようにしようというアイデア。
そのパッチワークのデザインがまた楽しいんちゃうかなとも思ってた。
鉄板の厚みは4、5㎜とか6㎜とかが理想なのかもしれんけど、あんまし厚いとストーブ本体が重くなりすぎるし。
結構大きめの鉄板が目に付いた。
厚みは3㎜。
長い辺が50cm。
たくさんある。
どうせなら容積が大きい程よく燃えるんで、一辺が50cmで奥行きが65cmの直方体の箱型にすることにした。
ちょっと、このサイズになると、3㎜では薄いと思うけどね。
まあ、材料はタダなんで、練習ってことで、、、。
今シーズンは使えるやろ。
今度は行きつけの金物屋の倉庫へ。
倉庫番のおっちゃんに煙突や平トタンの相談をする。
煙突はここで以前大量にもらったブリキに塗装してある奴がある。
でも、風呂の煙突に使って、一年ぐらいで元口に穴が開いた。
ブリキも薄いしねー。
廃材天国は天井が高いんで、全部ステンレスのを新調すると2万まではいかないけど、かなり高くつく。
なので、火力の強い元口の一本だけステンレスのを買う。
直径12cmの90cmで2000円。
昨日書いたヨーロッパ製の50万とかのストーブには二重煙突が勧められてて、90cmのが一本2万とかする。
煙突全部でストーブ本体と同じぐらいかかるのが常識なんだそう、、、。
アホらし、、、、、。
後、職人さんは使えない傷物の平トタンがうまくあったんで、それはもらった。
これは煙突と屋根の接触部分の部材にする。
早速、帰って、作業に入る。
溶接機を出して、コンテナにコンパネのボロを乗せて作業台にする。
溶接機は家庭用の小さな奴ながらも100Vと単層の200Vとを選択できるようになってて、たまたま解体現場から外してきた、今使ってる分電盤に「エアコン200V」と、ブレーカーの一つが200Vに設定されてた。
そこから(I-)こんな大型のコンセントを付けて配線してある。
それに、溶接棒、面、皮手、こんだけあれば溶接が出来る。
今まで、五右衛門風呂やキッチンストーブの灰をかき出す道具やこないだの軽のバンにつけたアングルで作ったルーフキャリアなど、そんなに長いラインを溶接した経験はなく、途切れつつ、四苦八苦してた。
そこへ、アララトさんが新しく出たコピーフリーの「STOP!上関原発」のDVDを持って来てくれた。
アララトさんは溶接の経験があって、基本的な事をいろいろ実演を交えながら教えてもらった。
祝島や上関の現状もいろいろ聞けた。
先日、電力側が工事延期を発表したけど、現場では着々と準備が進められてて、今も数人が交代で張り付いてる状況なんだと。
以前、山口の「百姓庵」から来て、手伝ってくれたマサも通ってるそう。
結局、「賛成、反対」の二元論で反対派が勝ってもワダカマリは消えない。
そういう地元のドロドロした対立じゃなく、世論的に原発に頼らんでもエネルギーを賄えるようになって、原発なくてもええやん、とならないといけない。
実際にヨーロッパの各国は原発止めていってるんやから。
子どもたちとも一緒に観たけど、このDVDすっごくいいよ。
ほんとにリアリティーを持って生きてる祝島のおばあちゃん、Uターンで帰ってきた若者。
コピーフリーなんで、DVDを焼ける人はどんどん焼いて、みんなに配ろう。
この前はドタキャンになってしまったけど、現場は長期戦の様相やし、みんな手弁当のボランティアでやってるんで、僕も応援に駆けつけたい。
熊本の仕事の後に家族で行こうという話になってきてる。
子どもにもその「今の日本」のリアルな現場の空気を味わわせたいという想いもあるし。
僕はチェーンソーにインパクト持参で現場の小屋や設備を直したりしてあげられるし。
アララトさんから水がないからね、と、井戸が掘れないかという話もあった、、、。
アララトさんが帰ってからは溶接の工程も今までよりはスムーズに進み始めた。
そうしてると近所のおっちゃんが来て「わしも溶接の経験あるんぞ!」と更に指導してもらった。
なんだかんだで、朝もらってきた材料を使って、そこそこの格好にはなってきた。
後は薪をくべる正面だけ。
もう鉄板もないんで、夕方再度鉄工所を訪ねる。
もちろん出来つつある本体を軽トラに乗せて。
「社長、ここまで出来たんやけどー。」と見せると、「ほほう、もうそこまで作ったんか。」と後の材料を段取りしてくれた。
ここからは廃材で丁度いい破片は無かったんで、大きな鉄板を機械にかけて切断してくれたり、長いアングルを切ってくれたり、とキップよくテキパキ加工してくれた。
反対にこんだけしてもろて、材料代すらとらないんで、僕としても次々と頼みに行くのに気を遣う。
今日もまだ少し加工が残ってて、行かないといけないんで、お酒を持って行こうっと。
デジカメ直ったんで写真アップできるようになったよ。
去年まで使ってた縦型の鋳物の薪ストーブと新作の状況。
2009年11月25日
薪ストーブ、新作か!?
廃材天国の縦型の鋳物の薪ストーブ。
これはコークス(石炭)用。
なので、くべる口がめっちゃ小さい。
幸い上の天井部分が楕円形に大きく開口するんで、その蓋をペンチで持ち上げては大きな薪をくべて使ってた(一軒目の廃材ハウスの時は工房用やった)。
でも、去年一冬使ってみて、やっぱり、効率が悪い、、、。
縦長なんで、長い薪を差し込むようにくべても燃えが悪く、どうしても薪を短めにしないといけない。
この、薪をチェーンソーで切る労力が一番めんどくさい。
生ならいざしらず、乾いた雑木の堅いのなんか、ソーチェーンの傷みが超早いし。
今、廃材天国の道路沿いに積み込んである雑木はほぼ、50~60㎝にカットされてる。
これは造園屋さんやシルバー人材センターが持って来てくれてる。
主に陶芸の窯焚き用なんで、このぐらいの長さをリクエストしてる。
まあ、でも、陶芸の窯なんか、年に一回ぐらいやし、明らかに僕が使う量よりも供給量の方が多い。
で、やっぱり、これを薪ストーブ用の燃料に、と考えると、そのまんまこの50~60㎝の薪を横から差し込むようにくべる形態が最も望ましい。
廃材天国の広さ(約30坪)と高さ(4、5m)を考えた時に、市販の薪ストーブは選択肢には入らない。
何十万もするアメリカやヨーロッパのストーブは燃焼効率や耐久性、デザインには優れるけど、廃材天国にはお呼びじゃない。
大体、あんなん、似合わんやん。
廃材で出来た家に新品のものが似合わんというのは当たり前やけど、そんなものを買うという選択肢が最初からないのが嬉しいねー。
とにかく、薪ストーブというとオシャレなイメージを持つけど、廃材天国では焼却場よろしく、なんでもええから囲いがあって、じゃんじゃんデッカイ薪を燃やしまくれたらいい。
耐火煉瓦で、、、というのも考えたけど、耐火煉瓦が蓄熱してしまえば、さぞかし暖かいやろけど、朝起きてすぐに暖かくしたい時(大体すぐに暖かくしたいわな)なんかには不利。
という事で、思い切って廃材で新作することを決意!
近所の鉄工所のクズ鉄で。
耐火煉瓦との折衷でもええしー。
と布団の中でアイデアが膨らんで、目が覚めた。
はよ8時来んかなーーー。
鉄工所行って、廃材見たらまたアイデアが来るに違いない!
ここの所、出店や、ピザ体験、月末はピザ窯作り、12月は熊本に遠征となにかと忙しいし、今年は去年と同じでええかなー、という事で保留にしてきたけど、そろそろ四国でも寒くなってきて切実な問題として考え始めたらこういう結果になった。
もちろん、まだ10℃は切らんけどね。
て言うか、去年家の中が10℃切ったんて、何回あったやろう?
という、暖地での立地が嬉しい廃材天国ならではの悠長な考えかも、、、。
とにかく料理も風呂も暖房も薪の生活の廃材天国では、薪作りの労力は最小限に抑えたい気持ちが一番!
料理の薪は大工さんの木っ端で事足りてる。
風呂の薪は3寸5分の柱の廃材なので、4、50cmにチェーンソーでカットするだけ(これは非常に楽ちん)。
ストーブの薪作りも楽にしたいから、という欲求が一番強いかな?
これはコークス(石炭)用。
なので、くべる口がめっちゃ小さい。
幸い上の天井部分が楕円形に大きく開口するんで、その蓋をペンチで持ち上げては大きな薪をくべて使ってた(一軒目の廃材ハウスの時は工房用やった)。
でも、去年一冬使ってみて、やっぱり、効率が悪い、、、。
縦長なんで、長い薪を差し込むようにくべても燃えが悪く、どうしても薪を短めにしないといけない。
この、薪をチェーンソーで切る労力が一番めんどくさい。
生ならいざしらず、乾いた雑木の堅いのなんか、ソーチェーンの傷みが超早いし。
今、廃材天国の道路沿いに積み込んである雑木はほぼ、50~60㎝にカットされてる。
これは造園屋さんやシルバー人材センターが持って来てくれてる。
主に陶芸の窯焚き用なんで、このぐらいの長さをリクエストしてる。
まあ、でも、陶芸の窯なんか、年に一回ぐらいやし、明らかに僕が使う量よりも供給量の方が多い。
で、やっぱり、これを薪ストーブ用の燃料に、と考えると、そのまんまこの50~60㎝の薪を横から差し込むようにくべる形態が最も望ましい。
廃材天国の広さ(約30坪)と高さ(4、5m)を考えた時に、市販の薪ストーブは選択肢には入らない。
何十万もするアメリカやヨーロッパのストーブは燃焼効率や耐久性、デザインには優れるけど、廃材天国にはお呼びじゃない。
大体、あんなん、似合わんやん。
廃材で出来た家に新品のものが似合わんというのは当たり前やけど、そんなものを買うという選択肢が最初からないのが嬉しいねー。
とにかく、薪ストーブというとオシャレなイメージを持つけど、廃材天国では焼却場よろしく、なんでもええから囲いがあって、じゃんじゃんデッカイ薪を燃やしまくれたらいい。
耐火煉瓦で、、、というのも考えたけど、耐火煉瓦が蓄熱してしまえば、さぞかし暖かいやろけど、朝起きてすぐに暖かくしたい時(大体すぐに暖かくしたいわな)なんかには不利。
という事で、思い切って廃材で新作することを決意!
近所の鉄工所のクズ鉄で。
耐火煉瓦との折衷でもええしー。
と布団の中でアイデアが膨らんで、目が覚めた。
はよ8時来んかなーーー。
鉄工所行って、廃材見たらまたアイデアが来るに違いない!
ここの所、出店や、ピザ体験、月末はピザ窯作り、12月は熊本に遠征となにかと忙しいし、今年は去年と同じでええかなー、という事で保留にしてきたけど、そろそろ四国でも寒くなってきて切実な問題として考え始めたらこういう結果になった。
もちろん、まだ10℃は切らんけどね。
て言うか、去年家の中が10℃切ったんて、何回あったやろう?
という、暖地での立地が嬉しい廃材天国ならではの悠長な考えかも、、、。
とにかく料理も風呂も暖房も薪の生活の廃材天国では、薪作りの労力は最小限に抑えたい気持ちが一番!
料理の薪は大工さんの木っ端で事足りてる。
風呂の薪は3寸5分の柱の廃材なので、4、50cmにチェーンソーでカットするだけ(これは非常に楽ちん)。
ストーブの薪作りも楽にしたいから、という欲求が一番強いかな?
2009年11月24日
愛媛、内子手づくり市へ
松山を大きく越えて内子町への出店。
こんだけ離れた距離で連日というのも初めてやし、ぽっちり堂では予想を超えての完売だったんで、新しく仕込み直さないとー。
と、夕方帰ってから平和の圧力鍋で玄米炊いて、、、。
内子町は前にも書いたけど、超過疎でIターンを奨励してる町。
年間10組以上の若い夫婦などが移住してるそう。
その受け入れの中心が自然農の中谷さんや、今回の手づくり市の会場の「菜月自然農園」の和田さん。
この内子の手づくり市は規模が凄い!
うちみたいな出店者が50店。
お客さんは1000人を超えるとか、、、!
しかも規定が厳しくて、まず店舗を持ってる人はダメ、仕入れたモノを売るのもダメ、もちろん白い砂糖や味の素などの添加物入りはダメ、自分で一から作ったものだけの猛者揃い。
もちろんそういう噂は聞いてたので、ぽっちり堂から帰って全力で準備してきた。
出すものはもちろんやけど、出店の形態をバージョンアップ。
コンテナにコンパネスタイルからテーブルスタイルへ。
一つはジョイのビオマーケットで使ってる自作コンパネテーブル。
パスタマシンを回したり、ガスも、となってくるとテーブルがもっと要る。
で、夜中に低い折りたたみの事務机の脚を延長させるアイデアを思いつく。
2時頃やったかな、、、。
丸鋸を一瞬だけ回して木をカット。
針金での固定も考えたけど、パスタマシンを回すのに耐えられないといけない。
で、鉄板ビスで机の鉄の脚に直接木を縫い付ける。
インパクトは廃材天国内で、、、。
8本のビスだけやったからねー。
結局いろいろ準備してると外が明るく、、、。
元々、朝の6時には出発したいなーと思ってたんで、貫徹で荷物を積み込み高速で内子へゴー!
今のうちらの自由なライフスタイルでよもや徹夜とはねー。
これが仕事となれば絶対にやりたくない。
思いっきり遊んでるレベルやからやれる。
文化祭の準備みたいなもん。
とにかく、午後からの雨にも関わらず凄いお客さんやったねー。
この日もほぼ完売状態。
いろいろ物々交換も出来たしー。
同年代の「山そだち」の大崎さん、「まんがら農園」の野満さんも出店。
あまらさんとすおうも来てた。
上関帰りのハギさんとも初対面から意気投合した。
あまりにも濃い出店者で、残念ながら全員とは喋れないけど、、、。
お客さんも分かってる人たちが多く、マイバックはもちろん、マイ皿、マイ箸、マイカップ、と店側としては超助かるよねー。
もちろん使い捨ての容器でパスタや玄米珈琲出したくないんでステンレスの皿やうちの陶器で出してたんやけど、洗い物の手間もバカにならんからね。
うちの皿で食べても洗ってくれたりとかねー。
隣のジャム屋のお姉さんも凄かったー。
数十種類のジャム、ジャム、ジャム。
カボチャの皮ばっかしのジャム、自分で育てたショウガのジャム(完全に大人の味)など超マニアックながらもお客さん釘付け。
その隣のお姉さんはチベット餃子「モモ」を木製の四角いセイロで蒸す。
その場で皮伸ばして包んでるしー。
これがとんでもないクオリティーの美味しさやった。
菜月自然農園の自家製全粒粉のクッキーもやばかった。
自分で作った小麦で作ったクッキーやで!
高知、愛媛、、、。
す、凄い、盛り上がりじゃん、、、。
まだ、行ってない高知市のオーガニックマーケットも凄いっちゅう噂やし。
そりゃあ、京都の手づくり市や代々木公園のアースデイマーケットは知らんけど、四国も熱いっす!
香川はどないやねん、香川はー。
高松のビオマーケットは閑古鳥やしーーー。
て言うか、うちらがもっと頑張らんとーー。
みんなに共通してるのは、自分で農を楽しみ、出来た野菜や果物を加工する。
しかも毎年やって、自然に改良を重ねて完成度が高い。
こんだけ、手づくりやってるウチも脱帽の品々ばかりやもん。
ほんとにこういうグレードの高い手づくり品に比べたらコスト計算しながら大きい設備据えて大量に作ってる食べモンがいかに貧相なことか、、、。
はっきり言ってここのはどれも今の日本の常識では「合わない」ものばかり。
でもねー、人間一日にそんなに食べられんからねー。
しかも手づくりに慣れてくるとちょっとの手間でいろいろ保存食とか出来て、普段の食生活が超豊かになるからね。
こんなにも自然の豊かな瑞穂の国で日清食品やヤマザキのパン食ってる場合じゃないよ。
ほんとに食から生活を見直すと、何が大切で何が必要じゃないかがはっきりしてくる。
自家製のミソはお金に換えられないし、自分の時間もお金には換算出来んハズ。
瀬戸内海の豊かな海に原発が出来るのも数億ごときもらっても、そんな価値はないぞ!
ほんとうに大切なものを当たり前に大切にしてる人たちが作る手作り市。
しかもその会場は不耕起自然農の畑。
それはアメージングな世界。
こんだけ離れた距離で連日というのも初めてやし、ぽっちり堂では予想を超えての完売だったんで、新しく仕込み直さないとー。
と、夕方帰ってから平和の圧力鍋で玄米炊いて、、、。
内子町は前にも書いたけど、超過疎でIターンを奨励してる町。
年間10組以上の若い夫婦などが移住してるそう。
その受け入れの中心が自然農の中谷さんや、今回の手づくり市の会場の「菜月自然農園」の和田さん。
この内子の手づくり市は規模が凄い!
うちみたいな出店者が50店。
お客さんは1000人を超えるとか、、、!
しかも規定が厳しくて、まず店舗を持ってる人はダメ、仕入れたモノを売るのもダメ、もちろん白い砂糖や味の素などの添加物入りはダメ、自分で一から作ったものだけの猛者揃い。
もちろんそういう噂は聞いてたので、ぽっちり堂から帰って全力で準備してきた。
出すものはもちろんやけど、出店の形態をバージョンアップ。
コンテナにコンパネスタイルからテーブルスタイルへ。
一つはジョイのビオマーケットで使ってる自作コンパネテーブル。
パスタマシンを回したり、ガスも、となってくるとテーブルがもっと要る。
で、夜中に低い折りたたみの事務机の脚を延長させるアイデアを思いつく。
2時頃やったかな、、、。
丸鋸を一瞬だけ回して木をカット。
針金での固定も考えたけど、パスタマシンを回すのに耐えられないといけない。
で、鉄板ビスで机の鉄の脚に直接木を縫い付ける。
インパクトは廃材天国内で、、、。
8本のビスだけやったからねー。
結局いろいろ準備してると外が明るく、、、。
元々、朝の6時には出発したいなーと思ってたんで、貫徹で荷物を積み込み高速で内子へゴー!
今のうちらの自由なライフスタイルでよもや徹夜とはねー。
これが仕事となれば絶対にやりたくない。
思いっきり遊んでるレベルやからやれる。
文化祭の準備みたいなもん。
とにかく、午後からの雨にも関わらず凄いお客さんやったねー。
この日もほぼ完売状態。
いろいろ物々交換も出来たしー。
同年代の「山そだち」の大崎さん、「まんがら農園」の野満さんも出店。
あまらさんとすおうも来てた。
上関帰りのハギさんとも初対面から意気投合した。
あまりにも濃い出店者で、残念ながら全員とは喋れないけど、、、。
お客さんも分かってる人たちが多く、マイバックはもちろん、マイ皿、マイ箸、マイカップ、と店側としては超助かるよねー。
もちろん使い捨ての容器でパスタや玄米珈琲出したくないんでステンレスの皿やうちの陶器で出してたんやけど、洗い物の手間もバカにならんからね。
うちの皿で食べても洗ってくれたりとかねー。
隣のジャム屋のお姉さんも凄かったー。
数十種類のジャム、ジャム、ジャム。
カボチャの皮ばっかしのジャム、自分で育てたショウガのジャム(完全に大人の味)など超マニアックながらもお客さん釘付け。
その隣のお姉さんはチベット餃子「モモ」を木製の四角いセイロで蒸す。
その場で皮伸ばして包んでるしー。
これがとんでもないクオリティーの美味しさやった。
菜月自然農園の自家製全粒粉のクッキーもやばかった。
自分で作った小麦で作ったクッキーやで!
高知、愛媛、、、。
す、凄い、盛り上がりじゃん、、、。
まだ、行ってない高知市のオーガニックマーケットも凄いっちゅう噂やし。
そりゃあ、京都の手づくり市や代々木公園のアースデイマーケットは知らんけど、四国も熱いっす!
香川はどないやねん、香川はー。
高松のビオマーケットは閑古鳥やしーーー。
て言うか、うちらがもっと頑張らんとーー。
みんなに共通してるのは、自分で農を楽しみ、出来た野菜や果物を加工する。
しかも毎年やって、自然に改良を重ねて完成度が高い。
こんだけ、手づくりやってるウチも脱帽の品々ばかりやもん。
ほんとにこういうグレードの高い手づくり品に比べたらコスト計算しながら大きい設備据えて大量に作ってる食べモンがいかに貧相なことか、、、。
はっきり言ってここのはどれも今の日本の常識では「合わない」ものばかり。
でもねー、人間一日にそんなに食べられんからねー。
しかも手づくりに慣れてくるとちょっとの手間でいろいろ保存食とか出来て、普段の食生活が超豊かになるからね。
こんなにも自然の豊かな瑞穂の国で日清食品やヤマザキのパン食ってる場合じゃないよ。
ほんとに食から生活を見直すと、何が大切で何が必要じゃないかがはっきりしてくる。
自家製のミソはお金に換えられないし、自分の時間もお金には換算出来んハズ。
瀬戸内海の豊かな海に原発が出来るのも数億ごときもらっても、そんな価値はないぞ!
ほんとうに大切なものを当たり前に大切にしてる人たちが作る手作り市。
しかもその会場は不耕起自然農の畑。
それはアメージングな世界。
2009年11月24日
高知のぽっちり堂へ
怒涛の仕込み&出店!
19、20は丸々仕込み。
最近よくやってる「手打ちパスタ」。
もちろんマクロビスイーツも。
美しい玄米弁当もぽっちり堂の敬子ちゃんの要望で作ったよ。
陶芸の作品も同時展示!
21日は高知、早目浦ダムの手前の土佐町。
「ぽっちり堂」というお菓子屋をやってる友達のイベント。
ふる~い民家を改造して地元のオーガニック素材でお菓子を作って、ネット販売中心で商売をしてる。
その民家に併設して新しくカフェを構えて来年の一月にオープンさせる。
丸みのある土壁と板張りのミックスしたカワイイデザイン。
これはプロの職人さんの仕事。
かなりいい感じやね。
それで居ながら、すぐ裏の山には草がいい感じに生えながらも管理された美しい菜園があった。
更に、岩ゴロゴロの沢には野遊や土歩くんがワクワクでクライミングできる。
夏は沢ガニいっぱい獲れるやろなー。
とにかく、廃材天国からすれば自然の宝庫!
今回は噂の高知のオーガニックマーケットに出店してるようなポッチリ堂の仲間が中心。
かまどGOGOの青木さんのライブも!
主人のコウジくんの宣伝がよかったのかたくさんのお客さんやったね。
まだまだ、お客さんに並ばれたことのない廃材天国はテーブルなんかの設備面で苦戦した。
マクロビスイーツだけでなく、パスタとなると、水、火と設備も一気に倍増するし。
ソースは大量に仕込んで、シャトルシェフで保温。
普段は薪で料理してる廃材天国もこういう時には5㌔のガスボンベを持って行く。
それでも新たに投入したパスタマシンのカッターは目を見張る活躍やった!
これには見てるお客さんも「写真撮っていいですか!」を連発。
おそらくたくさんの人がブログにアップしてくれてそう。
残念ながらうちのデジカメは壊れてて写真ないけど、、、。
おかげさんで早々と玄米弁当から完売。
次はスイーツ。
パスタも大好評!
定番のトマトソースを二回、次はキノコのぺペロンチーニ、で、今回は根菜の醤油ソース。
やっぱり、自分が飽きるのは嫌やからねー。
気がつくと、完売御礼!!
高知のオーガニックマーケットの関係者が来られてて、1月から場所を移転してやるんで、そのオープニングの時に来てくれないかというお誘いを頂いた。
今までは高知かーーーと腰を上げかねてた所があったけど、土佐町まで来れば高知市もそんなに変わらんしーと思い始めたね。
ぽっちり堂も1/9にいよいよグランドオープン!
三線の「月と蛙」というミュージシャンも呼んでのオープニングパーティーをするんだそう。
その月と蛙さんが、他に四国で、、、といつもの流れで1/7に廃材天国で新春ライブという運びになった。
you tubeで月と蛙、観たけど、かなりオリジナリティ溢れるいい感じの世界。
新年会はこれで決まりっと。
4時頃に、翌日の仕込みの為に土佐町を後にした。
天気も良くて最高やったねーーー。
19、20は丸々仕込み。
最近よくやってる「手打ちパスタ」。
もちろんマクロビスイーツも。
美しい玄米弁当もぽっちり堂の敬子ちゃんの要望で作ったよ。
陶芸の作品も同時展示!
21日は高知、早目浦ダムの手前の土佐町。
「ぽっちり堂」というお菓子屋をやってる友達のイベント。
ふる~い民家を改造して地元のオーガニック素材でお菓子を作って、ネット販売中心で商売をしてる。
その民家に併設して新しくカフェを構えて来年の一月にオープンさせる。
丸みのある土壁と板張りのミックスしたカワイイデザイン。
これはプロの職人さんの仕事。
かなりいい感じやね。
それで居ながら、すぐ裏の山には草がいい感じに生えながらも管理された美しい菜園があった。
更に、岩ゴロゴロの沢には野遊や土歩くんがワクワクでクライミングできる。
夏は沢ガニいっぱい獲れるやろなー。
とにかく、廃材天国からすれば自然の宝庫!
今回は噂の高知のオーガニックマーケットに出店してるようなポッチリ堂の仲間が中心。
かまどGOGOの青木さんのライブも!
主人のコウジくんの宣伝がよかったのかたくさんのお客さんやったね。
まだまだ、お客さんに並ばれたことのない廃材天国はテーブルなんかの設備面で苦戦した。
マクロビスイーツだけでなく、パスタとなると、水、火と設備も一気に倍増するし。
ソースは大量に仕込んで、シャトルシェフで保温。
普段は薪で料理してる廃材天国もこういう時には5㌔のガスボンベを持って行く。
それでも新たに投入したパスタマシンのカッターは目を見張る活躍やった!
これには見てるお客さんも「写真撮っていいですか!」を連発。
おそらくたくさんの人がブログにアップしてくれてそう。
残念ながらうちのデジカメは壊れてて写真ないけど、、、。
おかげさんで早々と玄米弁当から完売。
次はスイーツ。
パスタも大好評!
定番のトマトソースを二回、次はキノコのぺペロンチーニ、で、今回は根菜の醤油ソース。
やっぱり、自分が飽きるのは嫌やからねー。
気がつくと、完売御礼!!
高知のオーガニックマーケットの関係者が来られてて、1月から場所を移転してやるんで、そのオープニングの時に来てくれないかというお誘いを頂いた。
今までは高知かーーーと腰を上げかねてた所があったけど、土佐町まで来れば高知市もそんなに変わらんしーと思い始めたね。
ぽっちり堂も1/9にいよいよグランドオープン!
三線の「月と蛙」というミュージシャンも呼んでのオープニングパーティーをするんだそう。
その月と蛙さんが、他に四国で、、、といつもの流れで1/7に廃材天国で新春ライブという運びになった。
you tubeで月と蛙、観たけど、かなりオリジナリティ溢れるいい感じの世界。
新年会はこれで決まりっと。
4時頃に、翌日の仕込みの為に土佐町を後にした。
天気も良くて最高やったねーーー。
2009年11月19日
オイル交換
軽トラ、軽バン共にそろそろオイル交換の時期。
もちろん自分でやる。
まず、ホームセンターの4ℓで998円ℓのオイルを二つ買う。
廃オイルを受けるのに、空のオイル缶を横にして、金切りバサミで大きく穴を開けて、オイル入れを作る。
これは毎回使い捨て。
廃材天国内でやると、地べたに寝っころがってやらんといけないんで、農道の隅に車を止めて、一段低い田んぼから作業をする。
これならドレンボルト緩めたり、廃オイルを出すのに寝そべらんでもできる。
オイル交換って簡単やけど、ここが、ポイントなんよねー。
軽トラは座席の下から、バンは後ろのバンパーを外して、新しいオイルを入れる。
大体2、5ℓちょい計って入れて、後はオイルゲージを差し込んで、ゲージを見ながら微調整する。
どっちの車も頂き物で、人のお下がりやけど、快調に走ってくれよるからね。
オイル交換とかは得にマメにやらんとね。
こういうメカっぽい作業はそこまで得意じゃないけど、このぐらいなら僕にも出来るし。
田舎の自給自足生活にこそ、軽トラなんかは大事やからねー。



もちろん自分でやる。
まず、ホームセンターの4ℓで998円ℓのオイルを二つ買う。
廃オイルを受けるのに、空のオイル缶を横にして、金切りバサミで大きく穴を開けて、オイル入れを作る。
これは毎回使い捨て。
廃材天国内でやると、地べたに寝っころがってやらんといけないんで、農道の隅に車を止めて、一段低い田んぼから作業をする。
これならドレンボルト緩めたり、廃オイルを出すのに寝そべらんでもできる。
オイル交換って簡単やけど、ここが、ポイントなんよねー。
軽トラは座席の下から、バンは後ろのバンパーを外して、新しいオイルを入れる。
大体2、5ℓちょい計って入れて、後はオイルゲージを差し込んで、ゲージを見ながら微調整する。
どっちの車も頂き物で、人のお下がりやけど、快調に走ってくれよるからね。
オイル交換とかは得にマメにやらんとね。
こういうメカっぽい作業はそこまで得意じゃないけど、このぐらいなら僕にも出来るし。
田舎の自給自足生活にこそ、軽トラなんかは大事やからねー。
2009年11月17日
ストップ!上関原発!明るいニュース
火事で近所の人も遠方の人も心配して来てくれたり、電話をくれたりしてる。
みんなありがとう!
ほんとに不幸中の幸いって感じで、絶妙のタイミングで消防の人が消してくれた。
ほんとにありがたい。
廃材天国の存在自体がみんなから貰ったゴミで出来てるのもありがたい。
実は、一週間程前から15日のピザ体験が終わった夜に出発しようと旅の段取りをしてた。
目的地は山口県にある「上関原発予定地」の田ノ浦という所。
以前、僕の日記で、「ぶんぶん通信」という映画の上映会の事を書いたよね。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1226051928&owner_id=2989823
祝島(上関原発の向かいの島)の30年近く反対運動してるおじいちゃんから若者。
その芯からかっこいい生き方と全然自分の言葉じゃない説明を繰り返す電力の職員のダッサイ生き方。
今、この問題が現実に進んでる。
その最前線で阻止行動をしてる現場に行って、炊き出しをしようと、まんがら農園の野菜とうちの米を持って馳せ参じるつもりやった。
もちろんちびっ子もみんな連れてね。
ここの所、原発の予定地を埋め立てる為のブイを設置する電力側と阻止行動をする住民側や全国から駆けつけたカヤック隊。
その攻防の様子を常にネットでチェックしてた。
ストップ!上関原発!
http://stop-kaminoseki.net/
いわゆる「反対運動」で、問題解決はしないとよく言われる。
ゴミ処理場建設反対と言いながらゴミを出す生活をしてたり、原発反対と言いながら電気を浪費してたんではいけない。
そこの反対運動は成功しても結局また別の場所に建設されてしまうハメになる。
なので、僕もかつて環境運動をいろいろやってきた結果、今の廃材天国という形になってる。
今の僕のスタイルは活動や運動でなく、毎日の自分の生活である、買い物、食事、エネルギー、投票、お金、ということへの選択でより「自分の気持ちのいい方」にしてる。
それでも、実際に「反対」というエネルギーはよくないからとか言った所で、反対でも賛成でもないという無関心な層によって、一部の利権にあやかる少数の人が推進してるんよ。
今回でも事実、カヤック隊や祝島の漁船が中国電力の作業台船を阻止するという直接行動によって工事がスムーズに進む事を防いでる。
明るいニュースとして、正式に中国電力は「上関原発の建設延期」という声明を発表して、現場の作業台船も引っ込めたそう。
でも、これは「延期」であって、「撤回」ではない。
民主党政権になって、いい意味でのダムの白紙撤回や脱官僚などの革命的とも言える、具体的な改革が行われようとしてる。
でも、、、。
原子力政策に関してはブッブーーーー。
今までどおり「推進」なんよねー。
ていうか、25%も炭酸ガスを減らすと言うたって事は益々原子力発電に力を入れるとか。
僕はこういう所で賛成、反対の議論をしたいんじゃない。
自分の生き方として、事実を知った上で、自分の納得のいく選択をする。
だから上関にも祝島にも行きたかった。
もちろん、いかなくても実際に行ってカメラを回してる鎌仲監督の映画からでも十分伝わってくる。
何しろ、このカヤック隊や祝島の住民の運動はまず、全国ニュースにはならないそう。
マスコミは自分たちのスポンサーの不利になる情報は流さないのは常識。
だからこそ、僕が自分のスタイルでこの問題を伝えていきたい。
僕の毎日の選択ってこうやで、ってな。
今、うちの電気代は3000円台。
そんなに細かく節電、節電と心がけてる訳やない。
電化製品が極端に少ない!
電気炊飯器、電気ポット、コタツ、電気カーペット、電子レンジ、エアコン、ドライヤー、テレビ、、、、と代表的なものがない。
冷蔵庫、洗濯機、PC、なんかはある。
とにかく電気で「熱」を発生させて、長時間運転するもの。
エアコンや冷蔵庫、コタツみたいな。
これが電気をたくさん消費するんよね。
繰り返すけど、節電の為にそれらを排除してるんじゃない。
ぼくらには用がないから、いらない。
使わんもんはいらんし、要るものはどっかから回ってくる。
これが廃材天国だ。
とにかくヨーロッパを始め、先進国は原発を辞めていく方向。
危険やから。
そのリスクに見合う発電じゃないんよねー。
危険じゃない発電はいくらである。
石油がなくて、原発もないデンマークも日本と同じレベルのエネルギー自給率から、今や風力発電やバイオガスなんかでエネルギー自給率100%を達成してる。
みんなが廃材天国や自給自足を目指す必要なない。
日本の立地条件や経済、テクノロジー、と条件的には必ずエネルギーの自給は出来るんやって。
マスコミの情報操作でなく、事実という情報を知ればね。
12/19(土)「どうなるんなあ?うちらの食べもんとくらし」
というタイトルの講演会が高松のサンポートホール5階であるよ。
14時から16時、参加費は500円、小中高生100円、託児600円。
講師は京都大学の小出さん。
それこそ、映画「六ヶ所村ラプソティー」に登場されてる先生。
あっこちゃんはかつて岡山で小出さんの講演を聴いたことがあるそう。
めっちゃ分かりやすいらしいよー。
一緒に行こうぜ!
楽でワクワクする生き方をしたいなら。
今までどおりが好きなんなら無理にとは言わんけどね。
上関の現場は、今回はいい方向に向かって、予定を変更した。
でもまた、上関なり、祝島の方の状況次第で駆けつけようと思う。
イェイ、イェ~イ!
みんなありがとう!
ほんとに不幸中の幸いって感じで、絶妙のタイミングで消防の人が消してくれた。
ほんとにありがたい。
廃材天国の存在自体がみんなから貰ったゴミで出来てるのもありがたい。
実は、一週間程前から15日のピザ体験が終わった夜に出発しようと旅の段取りをしてた。
目的地は山口県にある「上関原発予定地」の田ノ浦という所。
以前、僕の日記で、「ぶんぶん通信」という映画の上映会の事を書いたよね。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1226051928&owner_id=2989823
祝島(上関原発の向かいの島)の30年近く反対運動してるおじいちゃんから若者。
その芯からかっこいい生き方と全然自分の言葉じゃない説明を繰り返す電力の職員のダッサイ生き方。
今、この問題が現実に進んでる。
その最前線で阻止行動をしてる現場に行って、炊き出しをしようと、まんがら農園の野菜とうちの米を持って馳せ参じるつもりやった。
もちろんちびっ子もみんな連れてね。
ここの所、原発の予定地を埋め立てる為のブイを設置する電力側と阻止行動をする住民側や全国から駆けつけたカヤック隊。
その攻防の様子を常にネットでチェックしてた。
ストップ!上関原発!
http://stop-kaminoseki.net/
いわゆる「反対運動」で、問題解決はしないとよく言われる。
ゴミ処理場建設反対と言いながらゴミを出す生活をしてたり、原発反対と言いながら電気を浪費してたんではいけない。
そこの反対運動は成功しても結局また別の場所に建設されてしまうハメになる。
なので、僕もかつて環境運動をいろいろやってきた結果、今の廃材天国という形になってる。
今の僕のスタイルは活動や運動でなく、毎日の自分の生活である、買い物、食事、エネルギー、投票、お金、ということへの選択でより「自分の気持ちのいい方」にしてる。
それでも、実際に「反対」というエネルギーはよくないからとか言った所で、反対でも賛成でもないという無関心な層によって、一部の利権にあやかる少数の人が推進してるんよ。
今回でも事実、カヤック隊や祝島の漁船が中国電力の作業台船を阻止するという直接行動によって工事がスムーズに進む事を防いでる。
明るいニュースとして、正式に中国電力は「上関原発の建設延期」という声明を発表して、現場の作業台船も引っ込めたそう。
でも、これは「延期」であって、「撤回」ではない。
民主党政権になって、いい意味でのダムの白紙撤回や脱官僚などの革命的とも言える、具体的な改革が行われようとしてる。
でも、、、。
原子力政策に関してはブッブーーーー。
今までどおり「推進」なんよねー。
ていうか、25%も炭酸ガスを減らすと言うたって事は益々原子力発電に力を入れるとか。
僕はこういう所で賛成、反対の議論をしたいんじゃない。
自分の生き方として、事実を知った上で、自分の納得のいく選択をする。
だから上関にも祝島にも行きたかった。
もちろん、いかなくても実際に行ってカメラを回してる鎌仲監督の映画からでも十分伝わってくる。
何しろ、このカヤック隊や祝島の住民の運動はまず、全国ニュースにはならないそう。
マスコミは自分たちのスポンサーの不利になる情報は流さないのは常識。
だからこそ、僕が自分のスタイルでこの問題を伝えていきたい。
僕の毎日の選択ってこうやで、ってな。
今、うちの電気代は3000円台。
そんなに細かく節電、節電と心がけてる訳やない。
電化製品が極端に少ない!
電気炊飯器、電気ポット、コタツ、電気カーペット、電子レンジ、エアコン、ドライヤー、テレビ、、、、と代表的なものがない。
冷蔵庫、洗濯機、PC、なんかはある。
とにかく電気で「熱」を発生させて、長時間運転するもの。
エアコンや冷蔵庫、コタツみたいな。
これが電気をたくさん消費するんよね。
繰り返すけど、節電の為にそれらを排除してるんじゃない。
ぼくらには用がないから、いらない。
使わんもんはいらんし、要るものはどっかから回ってくる。
これが廃材天国だ。
とにかくヨーロッパを始め、先進国は原発を辞めていく方向。
危険やから。
そのリスクに見合う発電じゃないんよねー。
危険じゃない発電はいくらである。
石油がなくて、原発もないデンマークも日本と同じレベルのエネルギー自給率から、今や風力発電やバイオガスなんかでエネルギー自給率100%を達成してる。
みんなが廃材天国や自給自足を目指す必要なない。
日本の立地条件や経済、テクノロジー、と条件的には必ずエネルギーの自給は出来るんやって。
マスコミの情報操作でなく、事実という情報を知ればね。
12/19(土)「どうなるんなあ?うちらの食べもんとくらし」
というタイトルの講演会が高松のサンポートホール5階であるよ。
14時から16時、参加費は500円、小中高生100円、託児600円。
講師は京都大学の小出さん。
それこそ、映画「六ヶ所村ラプソティー」に登場されてる先生。
あっこちゃんはかつて岡山で小出さんの講演を聴いたことがあるそう。
めっちゃ分かりやすいらしいよー。
一緒に行こうぜ!
楽でワクワクする生き方をしたいなら。
今までどおりが好きなんなら無理にとは言わんけどね。
上関の現場は、今回はいい方向に向かって、予定を変更した。
でもまた、上関なり、祝島の方の状況次第で駆けつけようと思う。
イェイ、イェ~イ!
2009年11月16日
即、行動
早速火事の後片付け。
瓦礫の山と化した窯を材料ごとに分別。
まず、窯本体。
もちろん粘土、砂、ワラでできたこの瓦礫は再生可能。
窯の内側なんかは何回も焚いてて、素焼き状態ぐらいになってる。
今度作る窯のサイズを大きくして生の粘土も混ぜれば十分窯の素材としてOK。
生の粘土100%よりも、こういう焼けた粘土が少し混ざる事は耐火性アップ、収縮の縮小にもつながって、ひび割れを防いだり、いい意味にもなる。
一軒目の家に作った7mもある陶芸用の窯なんかには6tの粘土に対して、シャモットと呼ばれる耐火煉瓦を砕いた砂利状の素材を2t混ぜた。
なので、窯のすぐ横に一山に盛り上げとくことにした。
次は一部に使用してた耐火煉瓦。
上の部屋と下の部屋の間に敷いてた長い煉瓦やその煉瓦の土台にしてた普通の耐火煉瓦。
これらはもちろんそのまま使えるので、一まとめにしておく。
後は土台の丸太。
これは当然焚き物になる。
めちゃくちゃ太いのはチェーンソーで切るのもおっくうなんで、よそへ運ぶ。
そこそこ太さのはぶつ切りにして、いまから薪ストーブの燃料になる。
窯の下に敷いてた砂利や砂、焦げた木の消し炭のようなものを粘土とは別にして一まとめにして、雑木林の方の低い場所に敷く。
こうして廃材天国の中にある材料で出来た窯は、壊れても再生だったり、燃料になったり、地面に敷いたりと、どっかへ産廃として捨てにいく事はない。
そういえば、廃材天国内にある材料って、よそで産廃として捨てられよるものを持って来てもろたり、もろてきたモンやからねー。
それと、こんな小さな窯ごとき、作るのもあっという間やけど、片付けるのなんか半日で十分。
作るのはやりたいけど、片付けはやりたくないというのはおかしいし、何でも自分の身体を使って作業してるとスイッチが入る。
これは肉体労働と限定はせんけど、自分の発想に対して自分で取り掛かって行動する、その部分にワクワクするんやと思うね。
スイッチが入ったから動くんじゃない。
やってるうちに楽しくなってきて、それがどんどん加速していく感じ。
これが廃材天国のコンセプトである「思いつきを即実践する」という事。
実際にやろうとして、必要な材料や道具が分からん時に頼りになるのはタウンページ。
ネットよりも具体的で早いのがいい。
やっぱりネットって必要なものにヒットするまでに膨大な時間を要するしね。
それぞれの専門化に直接電話で話を聞いてるといいアイデアや情報がどんどん入ってくる。
もちろんその上でネットと組み合わせるのがベストかな。
今回のトラブルで一軒目の廃材ハウスの時の「家がひっくり返った事件」を思い出した。
一斗缶にコンクリ練って、アンカー出して、土台の角材を固定して、そこから柱立てて、スレートで屋根葺いて、アルミサッシ入れた。
いろいろ教えてくれてた田村さんに「筋交い」というものを教えてもらった。
ほいで借りに筋交いを入れてて、建物の強度を持たせてたんやけど、サッシを入れる時に「邪魔やなー。」と思っていくつか外したんよねー。
で、グラグラになったんで「ヤバイ!」と思って、急いでインパクトを取って小さく筋交いを入れようとした途端、グラッと来た!
一瞬は支えようと柱を掴んだけど、すぐに命の危険を感じ、飛びのいた瞬間ドーンと物凄い轟音と共に倒れたからねー。
さすがに10分ぐらいは呆然と立ち尽くしたね。
それこそ、レッカーか何かでグーッと引っ張り上げてもろて直らんかなー、とか、、、。
頭の中は現実を受け入れたくないモード。
でも、それまでも全部一人でやって建ててきた訳やし、また自分がコツコツとバラシて直ししかないなー、という事を理解した。
その日のうちにスレートを留めてる大きな傘釘をボルトクリッパーで切って、スレートを外しにかかったね。
そこまで行くのに何ヶ月もかかったものが一瞬でキャンセルされたとショックやったけど、実際に再建するのは2週間ぐらいやった。
ここポイントよね。
要するに壊れたかに見えた家は柱や何かは全部また使える訳やし、なにより、そこまでやって身につけたノウハウは僕の中のものになっとった。
この経験は凄い学びになった。
まあ、今なら筋交いを外してひっくり返ったりはせんけどね。
とにかく、何が起こっても落ち込んだり、やる気がなくなったりはせん自信は満々やね。
いや、くれぐれも次は全焼からの再建を心待ちにしてる訳ではないよ、、、。

瓦礫の山と化した窯を材料ごとに分別。
まず、窯本体。
もちろん粘土、砂、ワラでできたこの瓦礫は再生可能。
窯の内側なんかは何回も焚いてて、素焼き状態ぐらいになってる。
今度作る窯のサイズを大きくして生の粘土も混ぜれば十分窯の素材としてOK。
生の粘土100%よりも、こういう焼けた粘土が少し混ざる事は耐火性アップ、収縮の縮小にもつながって、ひび割れを防いだり、いい意味にもなる。
一軒目の家に作った7mもある陶芸用の窯なんかには6tの粘土に対して、シャモットと呼ばれる耐火煉瓦を砕いた砂利状の素材を2t混ぜた。
なので、窯のすぐ横に一山に盛り上げとくことにした。
次は一部に使用してた耐火煉瓦。
上の部屋と下の部屋の間に敷いてた長い煉瓦やその煉瓦の土台にしてた普通の耐火煉瓦。
これらはもちろんそのまま使えるので、一まとめにしておく。
後は土台の丸太。
これは当然焚き物になる。
めちゃくちゃ太いのはチェーンソーで切るのもおっくうなんで、よそへ運ぶ。
そこそこ太さのはぶつ切りにして、いまから薪ストーブの燃料になる。
窯の下に敷いてた砂利や砂、焦げた木の消し炭のようなものを粘土とは別にして一まとめにして、雑木林の方の低い場所に敷く。
こうして廃材天国の中にある材料で出来た窯は、壊れても再生だったり、燃料になったり、地面に敷いたりと、どっかへ産廃として捨てにいく事はない。
そういえば、廃材天国内にある材料って、よそで産廃として捨てられよるものを持って来てもろたり、もろてきたモンやからねー。
それと、こんな小さな窯ごとき、作るのもあっという間やけど、片付けるのなんか半日で十分。
作るのはやりたいけど、片付けはやりたくないというのはおかしいし、何でも自分の身体を使って作業してるとスイッチが入る。
これは肉体労働と限定はせんけど、自分の発想に対して自分で取り掛かって行動する、その部分にワクワクするんやと思うね。
スイッチが入ったから動くんじゃない。
やってるうちに楽しくなってきて、それがどんどん加速していく感じ。
これが廃材天国のコンセプトである「思いつきを即実践する」という事。
実際にやろうとして、必要な材料や道具が分からん時に頼りになるのはタウンページ。
ネットよりも具体的で早いのがいい。
やっぱりネットって必要なものにヒットするまでに膨大な時間を要するしね。
それぞれの専門化に直接電話で話を聞いてるといいアイデアや情報がどんどん入ってくる。
もちろんその上でネットと組み合わせるのがベストかな。
今回のトラブルで一軒目の廃材ハウスの時の「家がひっくり返った事件」を思い出した。
一斗缶にコンクリ練って、アンカー出して、土台の角材を固定して、そこから柱立てて、スレートで屋根葺いて、アルミサッシ入れた。
いろいろ教えてくれてた田村さんに「筋交い」というものを教えてもらった。
ほいで借りに筋交いを入れてて、建物の強度を持たせてたんやけど、サッシを入れる時に「邪魔やなー。」と思っていくつか外したんよねー。
で、グラグラになったんで「ヤバイ!」と思って、急いでインパクトを取って小さく筋交いを入れようとした途端、グラッと来た!
一瞬は支えようと柱を掴んだけど、すぐに命の危険を感じ、飛びのいた瞬間ドーンと物凄い轟音と共に倒れたからねー。
さすがに10分ぐらいは呆然と立ち尽くしたね。
それこそ、レッカーか何かでグーッと引っ張り上げてもろて直らんかなー、とか、、、。
頭の中は現実を受け入れたくないモード。
でも、それまでも全部一人でやって建ててきた訳やし、また自分がコツコツとバラシて直ししかないなー、という事を理解した。
その日のうちにスレートを留めてる大きな傘釘をボルトクリッパーで切って、スレートを外しにかかったね。
そこまで行くのに何ヶ月もかかったものが一瞬でキャンセルされたとショックやったけど、実際に再建するのは2週間ぐらいやった。
ここポイントよね。
要するに壊れたかに見えた家は柱や何かは全部また使える訳やし、なにより、そこまでやって身につけたノウハウは僕の中のものになっとった。
この経験は凄い学びになった。
まあ、今なら筋交いを外してひっくり返ったりはせんけどね。
とにかく、何が起こっても落ち込んだり、やる気がなくなったりはせん自信は満々やね。
いや、くれぐれも次は全焼からの再建を心待ちにしてる訳ではないよ、、、。
2009年11月15日
まさかと思ったけど、遂に、、、
夜中、消防車のサイレンで目が覚めた!
近くで止まったぞ。
まさかーーーーーーーーーーーー!!!
飛び起きてピザの窯の方へすっ飛んでいくと、轟々と真っ赤に燃えてる!
新聞配達の人が119番通報してくれたそう。
僕が窯の近くへ行った時には消防の人が準備を整えてくれてて、放水開始!
4時台やったね。
発火場所は窯の底と丸太の土台の際みたい。
なので、とんでもない水圧で放水するも煙が立ち昇る。
「ご主人、窯を壊して丸太に放水する必要がありますけどいいですか?」と消防の人。
もちろんこうなったのは窯の構造に問題があるんで、今後使えないし、どうせ作り変えんといかんので、「よろしくお願いします!」と僕。
ハンマーやバールなんかでドンドン叩いて壊して、下の丸太にも放水。
これでやっと完全に消えた。
いろいろ消防の人は現場を測ったり、うちの家族の生年月日を聞いたり書類に書き込んでた。
警察の人も来た。
ある程度消えた所で地域の消防団にバトンタッチ。
近所のよく知ってるおっちゃんたち。
7時過ぎに消防の人が再度チェックに来るまで、分団の人たちが確認のために残ってくれた。
急いで大学芋を作って、熱いお茶と一緒に食べてもらった。
いやーーー。
ほんと、ピザ窯だけでよかったーーー。
僕が起きた時には窯の上の軒の部分近くまで炎が上がって、そこらじゅうが明るくなるぐらい燃えてたからねー。
もう少し遅かったら窯の屋根も燃えてたやろね。
何しろ廃材天国は燃えやすい事ここの上ないからねー。
まだこれがウチでよかった。
今まで15基も窯を作って来たし、今月の終わりには三木町、12月は熊本、来年3月、4月には京都、滋賀、群馬と窯作りの依頼が殺到してるからね。
今後は土台は石やブロック、レンガみたいな素材でないとね。
それにしても日本の警察は世界一と言うけど、この消防にしたってほんとに凄いね。
ほんとに徹底的に任務を遂行してくれる。
これは近所の分団という仕組みが特に凄いね。
僕は今の自給自足生活のスタイルや仕事の関係上分団員になる事は出来んけど、ほんまにありがたかった。
消防が帰った後も一時間半ぐらいは現場に残って再発しないように見張る。
まあ、僕が居るんやし、もう煙も昇ってないんやから帰ってもよさそうなんやけど、そういう決まりだそう。
もちろん、この仕事で念を入れ過ぎる事はないやろし、かつて大きい現場なんかでは再発したこともあったそう。
うちはギリギリとか何とかってのが多いけど、念には念を入れてとか余裕をもってという発想を取り入れていかなねー。
早速、薪ストーブとキッチンストーブの煙突と屋根の接触部分なんかをチェーンソーでドバッと大きく開けて鉄板入れてやりなおそう!
瓦礫の山と化したピザの窯の片付けもせなな。
折角作り変えるんなら今度はまた違う構造の窯にしよっと。
どんなんにするか楽しみー。
ハセヤンのカナディアンファームの大きな窯みたいにしよかなー。
まあ、来年の話になるやろけどな。



さすがに燃えよる最中や消防の人が忙しくしよる間は写真取れんかったね。
近くで止まったぞ。
まさかーーーーーーーーーーーー!!!
飛び起きてピザの窯の方へすっ飛んでいくと、轟々と真っ赤に燃えてる!
新聞配達の人が119番通報してくれたそう。
僕が窯の近くへ行った時には消防の人が準備を整えてくれてて、放水開始!
4時台やったね。
発火場所は窯の底と丸太の土台の際みたい。
なので、とんでもない水圧で放水するも煙が立ち昇る。
「ご主人、窯を壊して丸太に放水する必要がありますけどいいですか?」と消防の人。
もちろんこうなったのは窯の構造に問題があるんで、今後使えないし、どうせ作り変えんといかんので、「よろしくお願いします!」と僕。
ハンマーやバールなんかでドンドン叩いて壊して、下の丸太にも放水。
これでやっと完全に消えた。
いろいろ消防の人は現場を測ったり、うちの家族の生年月日を聞いたり書類に書き込んでた。
警察の人も来た。
ある程度消えた所で地域の消防団にバトンタッチ。
近所のよく知ってるおっちゃんたち。
7時過ぎに消防の人が再度チェックに来るまで、分団の人たちが確認のために残ってくれた。
急いで大学芋を作って、熱いお茶と一緒に食べてもらった。
いやーーー。
ほんと、ピザ窯だけでよかったーーー。
僕が起きた時には窯の上の軒の部分近くまで炎が上がって、そこらじゅうが明るくなるぐらい燃えてたからねー。
もう少し遅かったら窯の屋根も燃えてたやろね。
何しろ廃材天国は燃えやすい事ここの上ないからねー。
まだこれがウチでよかった。
今まで15基も窯を作って来たし、今月の終わりには三木町、12月は熊本、来年3月、4月には京都、滋賀、群馬と窯作りの依頼が殺到してるからね。
今後は土台は石やブロック、レンガみたいな素材でないとね。
それにしても日本の警察は世界一と言うけど、この消防にしたってほんとに凄いね。
ほんとに徹底的に任務を遂行してくれる。
これは近所の分団という仕組みが特に凄いね。
僕は今の自給自足生活のスタイルや仕事の関係上分団員になる事は出来んけど、ほんまにありがたかった。
消防が帰った後も一時間半ぐらいは現場に残って再発しないように見張る。
まあ、僕が居るんやし、もう煙も昇ってないんやから帰ってもよさそうなんやけど、そういう決まりだそう。
もちろん、この仕事で念を入れ過ぎる事はないやろし、かつて大きい現場なんかでは再発したこともあったそう。
うちはギリギリとか何とかってのが多いけど、念には念を入れてとか余裕をもってという発想を取り入れていかなねー。
早速、薪ストーブとキッチンストーブの煙突と屋根の接触部分なんかをチェーンソーでドバッと大きく開けて鉄板入れてやりなおそう!
瓦礫の山と化したピザの窯の片付けもせなな。
折角作り変えるんなら今度はまた違う構造の窯にしよっと。
どんなんにするか楽しみー。
ハセヤンのカナディアンファームの大きな窯みたいにしよかなー。
まあ、来年の話になるやろけどな。
さすがに燃えよる最中や消防の人が忙しくしよる間は写真取れんかったね。
タグ :火事
2009年11月15日
薪のピザ体験
丸亀の「NPOさぬきっずコムシアター」。
元「子ども劇場」。
ここの代表の高橋さんとは7、8年前からの知り合い。
一軒目の廃材ハウスの裏の竹藪で「竹山で基地作り」を毎年企画したりしてた。
今回、学校関係にも何千枚とチラシを入れての一大イベント。
参加者、スタッフ、うちらも入れると30人以上。
キャンセル待ちで断った人もいたとか。
生地はさぬきの夢2000ベース。
実はコープの国産強力粉が売り切れてなかったんで、、、。
前日からうちのドブロク酵母で練って風呂で醗酵させてた。
まず、みんな9時過ぎに集合。
簡単な説明の後、すぐに窯に点火。
その後、生地の説明と配合、練る作業。
そこで練った生地は各自持ち帰ってもらって、家で焼いてもらう。
高橋さんの要望でどうしても生地を練る所からさせたいと。
でも、朝来てから練ったんでは天然酵母はそんなに簡単に醗酵しない。
で、あっこちゃんのアイデアで「これが醗酵させておいた生地です。」と前もって醗酵済みの生地を渡すようにした。
後は予め蒸してあったカボチャ、シメジ、ピーマン、玉ねぎなどのトッピングのカットもみんなで。
トマトソースはこれも前もって作っておいた。
うちのオリジナルトマトソースは完全に完成形でレシピ化できてるからね。
生地やソースのレシピもみんな教えたよ。
いよいよ11時前ぐらいからピザを焼き始める。
何せ、一人一枚。
生地延ばして、野菜トッピングしてチーズ乗せてと言う所までを子どもが各自でやる。
そこからは僕がじゃんじゃん窯に入れて焼いていく。
何しろ30枚以上なんで、窯の温度のキープに気を配る。
何しろこの薪の窯には温度計がないだけでなく、常に上火と下火のバランスが崩れていく傾向がある。
それを上手に薪をくべる量だけでなく、燃やす位置やなんかにも気を配らないといけない。
まあ、無事に昼過ぎには全部のピザが焼きあがり、みんなお腹も一杯になって満足してくれたよ。
実際、ピザ作り教室のようなもんなんで、ポイントを指導しながらみんなで作業していくんで、その辺りはあっこちゃん、僕は窯で焼くの担当。
30人のお客が座ってて、生地延ばしたりトッピングしたり、窯も焼いたりとかとは断然楽に作業が進むね。
うちも余った生地を醗酵させておいて夜にパンにして焼いたよ。
最後に真っ暗な中、窯の前で焼酎呑んで満足間に浸ってた、、、。
この後にまさかの展開が待っようとはねー。
、、、分かったー?
次の日記に続く






元「子ども劇場」。
ここの代表の高橋さんとは7、8年前からの知り合い。
一軒目の廃材ハウスの裏の竹藪で「竹山で基地作り」を毎年企画したりしてた。
今回、学校関係にも何千枚とチラシを入れての一大イベント。
参加者、スタッフ、うちらも入れると30人以上。
キャンセル待ちで断った人もいたとか。
生地はさぬきの夢2000ベース。
実はコープの国産強力粉が売り切れてなかったんで、、、。
前日からうちのドブロク酵母で練って風呂で醗酵させてた。
まず、みんな9時過ぎに集合。
簡単な説明の後、すぐに窯に点火。
その後、生地の説明と配合、練る作業。
そこで練った生地は各自持ち帰ってもらって、家で焼いてもらう。
高橋さんの要望でどうしても生地を練る所からさせたいと。
でも、朝来てから練ったんでは天然酵母はそんなに簡単に醗酵しない。
で、あっこちゃんのアイデアで「これが醗酵させておいた生地です。」と前もって醗酵済みの生地を渡すようにした。
後は予め蒸してあったカボチャ、シメジ、ピーマン、玉ねぎなどのトッピングのカットもみんなで。
トマトソースはこれも前もって作っておいた。
うちのオリジナルトマトソースは完全に完成形でレシピ化できてるからね。
生地やソースのレシピもみんな教えたよ。
いよいよ11時前ぐらいからピザを焼き始める。
何せ、一人一枚。
生地延ばして、野菜トッピングしてチーズ乗せてと言う所までを子どもが各自でやる。
そこからは僕がじゃんじゃん窯に入れて焼いていく。
何しろ30枚以上なんで、窯の温度のキープに気を配る。
何しろこの薪の窯には温度計がないだけでなく、常に上火と下火のバランスが崩れていく傾向がある。
それを上手に薪をくべる量だけでなく、燃やす位置やなんかにも気を配らないといけない。
まあ、無事に昼過ぎには全部のピザが焼きあがり、みんなお腹も一杯になって満足してくれたよ。
実際、ピザ作り教室のようなもんなんで、ポイントを指導しながらみんなで作業していくんで、その辺りはあっこちゃん、僕は窯で焼くの担当。
30人のお客が座ってて、生地延ばしたりトッピングしたり、窯も焼いたりとかとは断然楽に作業が進むね。
うちも余った生地を醗酵させておいて夜にパンにして焼いたよ。
最後に真っ暗な中、窯の前で焼酎呑んで満足間に浸ってた、、、。
この後にまさかの展開が待っようとはねー。
、、、分かったー?
次の日記に続く
2009年11月13日
小さな屋根なら半日やでー!
先日の脱穀作業でバラした稲の乾燥用の木。
ここらでは「ハゼ」という。
この木を回収して、雨に当てない為の屋根を作ることにした。
前は本宅に持って帰ってたけど、今は親父が有機無農薬の菜園を始めてて、堆肥場にしてる畑の方が近くて便利やから。
この作業は僕、親父、松永くん(親父の所に勤める障害者)の3人で。
昨日の昼から夕方までで完成。
屋根のサイズは3m×4m。
基礎や水平や垂直もいい加減で、雨除けの屋根だけなんで、このぐらいでノープロブレム。
午前中はリビング高松という新聞が取材に来てて、その後、必要な廃材だけを軽トラに積み込んでた。
一番大事なのは段取り。
材料、道具。
どういう材料を使って、どういう風に建てるか?
大体、屋根の大きさをイメージしながら廃材天国の庭を歩いて、材料を物色。
常に大量に丸太や角材のストック(山積みになってるけど、、、)されてる廃材天国では直接材料との交渉。
必要な長さや太さ、材質、腐り度(これ大事)なんかでどれを使うかピックアップしていく。
今回のようないい加減な屋根なんかは多少悪い材を優先させる。
いい材料は家用に取っておく。
あまり大事に取っといてもどうせ雨ざらしなんで、早く使わな腐っていくんやけどね。
この、アイデアを巡らせながら「おっ、これ使お!」と閃く瞬間が楽しい。
もう、僕ぐらいのレベルになるといちいち迷ったり悩んだりはしない。
柱は、コレ。
桁がコレで。
えー、上に乗せる4mの角材はコレや。
波板はこの前、解体現場でもろてきた奴で。
細い筋交い用のも要るな。
と、あっと言う間に決定して軽トラに積み込む。
この工法は車庫や倉庫など小さな建物全てに応用できる、究極の手抜きお手軽版。
・まず、ガソリンスタンドで貰ってきたエンジンオイルの缶を少し埋める。
・そこへ柱を突っ込む。
・杭を3方へ打ち込み、杭と柱をビス留め。
・メジャーと水平機を使って、好きな高さで柱をチェーンソーで切断。
・勾配に桁を固定、90㎜のコースビスを斜め打ちで。
・傾斜の付いた桁の上に4mの角材を4本固定、これもビス。
・あちこちに細い角材で筋交いをビス留め。
・波板を打つ
・オイル缶にモルタルを練って流し込む
最後は僕が波板を打ってる間に親父がモルタルを練って流し込む。
なかり暗くなったけど、5時台に全部の作業終了。
塩ビの波板がグニャグニャに曲がってたんで、上から近所の大工さんに貰ってたボロいブリキの波板を被せて2重の屋根にした。
パッチワークのトタンがいい感じ。
まー、そこそこしっかりさせから少々の台風ぐらいは大丈夫。
耐久性も10年ぐらいは持つんちゃう?
波板が腐ったらまた廃材の波板を張り替えたらええだけやし。
廃材天国ではトタンや波板の簡単な屋根はないけど、この波板ってええよー。
一軒目の廃材ハウスはほとんど、コレ。
鶏舎の解体現場で超大量に貰ったりしてね。
ビスや傘釘、砂なんかはストックがあったんで、買ったのは生セメント一袋、298円。
さすがに廃材天国と言った所やねー。
もうちょっと大きくすればガレージぐらいにはなるよね。
まー、美しい新車のガレージにはキツイけど、、、。
いや、そういう時にはちょと手間かければいい。
廃材に電機カンナあてて、キレイに出来るし、屋根は新品のポリカ波板にすれば美しいし。
アルミの屋根だけのガレージが20万とか、、、!?
DIYしよー。
安くて、楽しいし。
ホームセンターで全部材料買ってもしれてるで。
おまけに軽トラは無料で貸してくれるし、ドリルやインパクトや丸鋸なんかも一日からでもレンタルで貸してくれる。
ホームセンターの品揃えは充実してるし、廃材もタダでもらえる。
ほんまにええ時代やのーーー。




ここらでは「ハゼ」という。
この木を回収して、雨に当てない為の屋根を作ることにした。
前は本宅に持って帰ってたけど、今は親父が有機無農薬の菜園を始めてて、堆肥場にしてる畑の方が近くて便利やから。
この作業は僕、親父、松永くん(親父の所に勤める障害者)の3人で。
昨日の昼から夕方までで完成。
屋根のサイズは3m×4m。
基礎や水平や垂直もいい加減で、雨除けの屋根だけなんで、このぐらいでノープロブレム。
午前中はリビング高松という新聞が取材に来てて、その後、必要な廃材だけを軽トラに積み込んでた。
一番大事なのは段取り。
材料、道具。
どういう材料を使って、どういう風に建てるか?
大体、屋根の大きさをイメージしながら廃材天国の庭を歩いて、材料を物色。
常に大量に丸太や角材のストック(山積みになってるけど、、、)されてる廃材天国では直接材料との交渉。
必要な長さや太さ、材質、腐り度(これ大事)なんかでどれを使うかピックアップしていく。
今回のようないい加減な屋根なんかは多少悪い材を優先させる。
いい材料は家用に取っておく。
あまり大事に取っといてもどうせ雨ざらしなんで、早く使わな腐っていくんやけどね。
この、アイデアを巡らせながら「おっ、これ使お!」と閃く瞬間が楽しい。
もう、僕ぐらいのレベルになるといちいち迷ったり悩んだりはしない。
柱は、コレ。
桁がコレで。
えー、上に乗せる4mの角材はコレや。
波板はこの前、解体現場でもろてきた奴で。
細い筋交い用のも要るな。
と、あっと言う間に決定して軽トラに積み込む。
この工法は車庫や倉庫など小さな建物全てに応用できる、究極の手抜きお手軽版。
・まず、ガソリンスタンドで貰ってきたエンジンオイルの缶を少し埋める。
・そこへ柱を突っ込む。
・杭を3方へ打ち込み、杭と柱をビス留め。
・メジャーと水平機を使って、好きな高さで柱をチェーンソーで切断。
・勾配に桁を固定、90㎜のコースビスを斜め打ちで。
・傾斜の付いた桁の上に4mの角材を4本固定、これもビス。
・あちこちに細い角材で筋交いをビス留め。
・波板を打つ
・オイル缶にモルタルを練って流し込む
最後は僕が波板を打ってる間に親父がモルタルを練って流し込む。
なかり暗くなったけど、5時台に全部の作業終了。
塩ビの波板がグニャグニャに曲がってたんで、上から近所の大工さんに貰ってたボロいブリキの波板を被せて2重の屋根にした。
パッチワークのトタンがいい感じ。
まー、そこそこしっかりさせから少々の台風ぐらいは大丈夫。
耐久性も10年ぐらいは持つんちゃう?
波板が腐ったらまた廃材の波板を張り替えたらええだけやし。
廃材天国ではトタンや波板の簡単な屋根はないけど、この波板ってええよー。
一軒目の廃材ハウスはほとんど、コレ。
鶏舎の解体現場で超大量に貰ったりしてね。
ビスや傘釘、砂なんかはストックがあったんで、買ったのは生セメント一袋、298円。
さすがに廃材天国と言った所やねー。
もうちょっと大きくすればガレージぐらいにはなるよね。
まー、美しい新車のガレージにはキツイけど、、、。
いや、そういう時にはちょと手間かければいい。
廃材に電機カンナあてて、キレイに出来るし、屋根は新品のポリカ波板にすれば美しいし。
アルミの屋根だけのガレージが20万とか、、、!?
DIYしよー。
安くて、楽しいし。
ホームセンターで全部材料買ってもしれてるで。
おまけに軽トラは無料で貸してくれるし、ドリルやインパクトや丸鋸なんかも一日からでもレンタルで貸してくれる。
ホームセンターの品揃えは充実してるし、廃材もタダでもらえる。
ほんまにええ時代やのーーー。
2009年11月12日
ピザ窯前、造成
いやー、よく降ったねー。
廃材天国にはコンクリートもアスファルトもないんで長雨だとビチョビチョのドロドロ。
一応建物の建ってる場所は花崗土で盛り上げてるんでそうでもないけどね。
何せ、元々水田の場所でロクに造成なんかしてないんやから。
今ごろの新築ってやたらとコンクリートで高く囲って花崗土めちゃくちゃ入れるけどね。
水害の時なんかの事を考えての事やろけど。
廃材天国の場合「何かあったら、、、。」と先々の不安な材料を素に余分な工事はしない。
というか、全部自分でやる訳なんで、そんなプロ並の仕事は出来ないし目指さない。
ほんと、セルフビルドでもプロ並のを雑誌とかで見るけど凄いよねー。
感心はスゴクするんやけど、マネしようとは思わない。
「臨機応変」とも「その場しのぎ」とも取れるこういうスタンスは超楽やでー。
来たことある人は分かると思うけど、二階の下なり、母屋の周りは一段高くなってるけど、ピザ窯のために作った大きな軒。
あの軒下部分は田んぼの時のまんまの地面。
当然雨が降ると水が溜まる。
こないだの手づくり市の時なんかは長く雨が降ってなかったんでどうもなかった。
今度14日にNPO法人「さぬきっずコムシアター」という丸亀の元子ども劇場がピザ作り体験をさせて欲しいと言う事で頼まれてる。
ので、さすがにこの水溜まりじゃーなー、と土を入れる事にした。
先にしとけよ、と自分でも思うけど、「今」というタイミングでしか出来ないんよねー。
まず水の入ってくる部分に先に土を入れてせき止めてから水を汲み出す。
これをしとかないといくら花崗土でもドロドロの沼のようになってしまう。
花崗土は最近2tダンプ一車もらったばかりで丁度いいタイミング。
雨は降ってたって合羽着てすればええ。
基本、土木工事は雨で出来ないって事はない。
こういう作業を雨やから、、、と先延ばしにしてはいけない。
この花崗土でないといかんのか?
という問題は僕の中で答えは持ってる。
急いで固い地面にしたいかどうか。
家を建てる為の造成でも時間をかけられるんなら何の土でもええ。
残土と呼ばれる土なら持って来てくれてタダ。
土建屋と仲良くなれば「ガラ交じりのしっかりした奴を。」とかいろいろ要望に応えてくれる。
彼らはキチンと処分すれはお金がかかるんやから、徹底的に応えてくれるよ。
実際、「どくんご」のテント劇の為に造成した広場は花崗土じゃなく、残土。
でも、今はもう固くなってて車が煮え込む(ハマる)こともない。
この煮え込むことだけでも一軒目の廃材建築の時からのストーリーは超豊富(苦笑)。
要は長い時間をかけて置いとくと土は固くなるんである。
何しろこの造成だけでプロに頼むと何百万もかかるからね。
プロの土建屋は自分らが造成した後、すぐに建築屋が来て建てんといかんから花崗土じゃないとこまるだけ。
後、水が溜まらんように溝を作って水はけはある程度考えた方がええね。
後々水が溜まらんようにさえしとけば残土で十分。
あ、雨のさなか、頻繁に車が出入りするようなポイントはやっぱ花崗土やね。
どっちにせよ今回はたまたま花崗土があったからそれにしただけ。
実際にひいたのは5、6cmぐらいかなー。
10cmもひくとめっちゃ土が要るからね。
何とかこれで雨の中のピザ作り体験にも対応できるようになった。
ピザの窯の軒は二階の下と繋がってるんで、30人ぐらいならゆったりとピザ作りできるかな。
まあ、生地延ばしたり、トッピングしたり、食べたりといろいろ考えると20人ぐらいがええ規模かもね。
子どもたちも土木作業は大好き。
もう正味で助かってるもんねー。
それにしてもほんと土木作業って楽しいよ。
一日で凄い進んだ感があるんよね。
肉体労働して結果も早いから達成感が大きいんかな?



廃材天国にはコンクリートもアスファルトもないんで長雨だとビチョビチョのドロドロ。
一応建物の建ってる場所は花崗土で盛り上げてるんでそうでもないけどね。
何せ、元々水田の場所でロクに造成なんかしてないんやから。
今ごろの新築ってやたらとコンクリートで高く囲って花崗土めちゃくちゃ入れるけどね。
水害の時なんかの事を考えての事やろけど。
廃材天国の場合「何かあったら、、、。」と先々の不安な材料を素に余分な工事はしない。
というか、全部自分でやる訳なんで、そんなプロ並の仕事は出来ないし目指さない。
ほんと、セルフビルドでもプロ並のを雑誌とかで見るけど凄いよねー。
感心はスゴクするんやけど、マネしようとは思わない。
「臨機応変」とも「その場しのぎ」とも取れるこういうスタンスは超楽やでー。
来たことある人は分かると思うけど、二階の下なり、母屋の周りは一段高くなってるけど、ピザ窯のために作った大きな軒。
あの軒下部分は田んぼの時のまんまの地面。
当然雨が降ると水が溜まる。
こないだの手づくり市の時なんかは長く雨が降ってなかったんでどうもなかった。
今度14日にNPO法人「さぬきっずコムシアター」という丸亀の元子ども劇場がピザ作り体験をさせて欲しいと言う事で頼まれてる。
ので、さすがにこの水溜まりじゃーなー、と土を入れる事にした。
先にしとけよ、と自分でも思うけど、「今」というタイミングでしか出来ないんよねー。
まず水の入ってくる部分に先に土を入れてせき止めてから水を汲み出す。
これをしとかないといくら花崗土でもドロドロの沼のようになってしまう。
花崗土は最近2tダンプ一車もらったばかりで丁度いいタイミング。
雨は降ってたって合羽着てすればええ。
基本、土木工事は雨で出来ないって事はない。
こういう作業を雨やから、、、と先延ばしにしてはいけない。
この花崗土でないといかんのか?
という問題は僕の中で答えは持ってる。
急いで固い地面にしたいかどうか。
家を建てる為の造成でも時間をかけられるんなら何の土でもええ。
残土と呼ばれる土なら持って来てくれてタダ。
土建屋と仲良くなれば「ガラ交じりのしっかりした奴を。」とかいろいろ要望に応えてくれる。
彼らはキチンと処分すれはお金がかかるんやから、徹底的に応えてくれるよ。
実際、「どくんご」のテント劇の為に造成した広場は花崗土じゃなく、残土。
でも、今はもう固くなってて車が煮え込む(ハマる)こともない。
この煮え込むことだけでも一軒目の廃材建築の時からのストーリーは超豊富(苦笑)。
要は長い時間をかけて置いとくと土は固くなるんである。
何しろこの造成だけでプロに頼むと何百万もかかるからね。
プロの土建屋は自分らが造成した後、すぐに建築屋が来て建てんといかんから花崗土じゃないとこまるだけ。
後、水が溜まらんように溝を作って水はけはある程度考えた方がええね。
後々水が溜まらんようにさえしとけば残土で十分。
あ、雨のさなか、頻繁に車が出入りするようなポイントはやっぱ花崗土やね。
どっちにせよ今回はたまたま花崗土があったからそれにしただけ。
実際にひいたのは5、6cmぐらいかなー。
10cmもひくとめっちゃ土が要るからね。
何とかこれで雨の中のピザ作り体験にも対応できるようになった。
ピザの窯の軒は二階の下と繋がってるんで、30人ぐらいならゆったりとピザ作りできるかな。
まあ、生地延ばしたり、トッピングしたり、食べたりといろいろ考えると20人ぐらいがええ規模かもね。
子どもたちも土木作業は大好き。
もう正味で助かってるもんねー。
それにしてもほんと土木作業って楽しいよ。
一日で凄い進んだ感があるんよね。
肉体労働して結果も早いから達成感が大きいんかな?
2009年11月10日
黄金の絨毯
昨日で田んぼにワラを広げる作業を終えた。
「そこに育ったものはそこへ還す」
これは自然農の福岡さんや川口さんはじめ、有機農を実践してる人にとっては常識とも言える。
でも、去年は牛を飼ってる人が買ってくれるからと親父が近所のおっちゃんからの話で、束にして売ってしまった。
もちろん僕や源も最終的には納得して束ねる作業も手伝った。
3反分のワラが6万になったそう。
でも、刈り取られた稲のカブだけが露出した裸の田んぼは痛々しかった。
今年は早くからワラを土に還す事の話題を僕がしきりに持ち出したし、源も同様だったんで、作業の流れはちゃんと土に還す方向へ。
親父もなんとなく納得。
親父はオルタナティブ系の本読まんからねー。
ネットもせんしー。
結構近所のおっちゃん連中の話を真に受けて聞いてるもん。
中々家族に言われてもスッキリと納得できないもの。
自分だってそう。
この問題は過去の記憶の「あの時こう言うた、、、。」みたいな部分も含んでるんで非常にややこしい。
ほんと、そういうのに固執するとトラウマのように問題化するんやろうけど、その時その時で起こってる現象を受け止めるしかない。
ありがたく、、、。
少なくとも自分の思うようにならなくても、自分の発信は普通にしよう。
発信した結果が逆の方向でもこれはこれでしょうがないし。
普通に自分の想いを出す。
それの継続。
まあ、今は僕を親父はかなり対等な関係でいい感じ。
源はよくぶつかってるけど、、、。
ま、想いが強すぎてぶつかるってのが常やからねー。
わざと強調したような言い方や姿勢は対立の素やね。
僕はこう想うからこうする。
てのがスッキリするよね。
いやー、一日中田んぼに居ると気持ちええねー。
バインダーで束ねたワラの麻ヒモを鎌で切ってバラバラにしていく。
延々と続くかのようなこういう地味な作業が農においては常識。
僕なんかは常にもっと能率的に、、、とか考えてしまう。
先人はそういうのを考えまくって機械化していったんやろね。
誰でも、機械の開発される前は機械化を望んだやろね。
でも、こうして機械が常識の現代では手作業の意味を掘り返して脱機械化という考え方も出てきて当然。
まー、福岡正信さんなんか60年以上も前から「そんなん意味ないぞー。」って言うてきた訳やからゴツイよね。
「ワラ一本の革命」読んでない人はちゃんと読もうね。
現代人は何にも考えずに淡々としたこの手作業は出来ない。
もっと早く、もっと能率的に、と言う洗脳を受けてるから。
もちろん僕も。
福岡さんの「人智無為」(人間の考える事は全て意味が無い)という思想にしたって超考えまくって出てきた発想やろし。
てことは、超頑張って非能率的な手作業を味わうのだ。
いや、ほんま、機械に使われてる時の作業と、静かに手作業でやってる時の違いって凄いよ。
何しろ、もっと早く!とさえ考えんかったらね。
でも全部の農機具を買う計算すれば、実は全部手作業でした方が絶対的に楽。
経済的に。
かつて一反を完全に不耕起でやって成功した事があるけど、2、3人も居れば田植えや稲刈りは4日前後って感じ。
てことは食べる人数総出でかかれば全く機械がなくても、家族が食べるだけの2、3反の田んぼは十分に可能。
おっと、自分の人件費は0で計算するように。
別に田植えや稲刈りに一週間かかったってかまんやん。
一番大事な穀物お米のため。
うちでは毎日玄米をモリモリ食べる以外にも、、、。
自家製の麹を仕込んでの
甘酒
ドブロク
味噌
これは完成してる。
後、玄米粉のスイーツも。
それこそスイーツの甘味の米飴も。
後は黒煎り玄米コーヒーも。
凄いよねー。
主食、調味料、酒、甘味とお米からできる加工品ってほんまパーフェクト!
自分の田んぼから産み出すマクロビオティックやねー。
夕方、ワラの広がる田んぼに立ってると、どこから来るでもない満足感に浸れる。
ほんまに気持ちええよ。
これが真の贅沢だーーー!


「そこに育ったものはそこへ還す」
これは自然農の福岡さんや川口さんはじめ、有機農を実践してる人にとっては常識とも言える。
でも、去年は牛を飼ってる人が買ってくれるからと親父が近所のおっちゃんからの話で、束にして売ってしまった。
もちろん僕や源も最終的には納得して束ねる作業も手伝った。
3反分のワラが6万になったそう。
でも、刈り取られた稲のカブだけが露出した裸の田んぼは痛々しかった。
今年は早くからワラを土に還す事の話題を僕がしきりに持ち出したし、源も同様だったんで、作業の流れはちゃんと土に還す方向へ。
親父もなんとなく納得。
親父はオルタナティブ系の本読まんからねー。
ネットもせんしー。
結構近所のおっちゃん連中の話を真に受けて聞いてるもん。
中々家族に言われてもスッキリと納得できないもの。
自分だってそう。
この問題は過去の記憶の「あの時こう言うた、、、。」みたいな部分も含んでるんで非常にややこしい。
ほんと、そういうのに固執するとトラウマのように問題化するんやろうけど、その時その時で起こってる現象を受け止めるしかない。
ありがたく、、、。
少なくとも自分の思うようにならなくても、自分の発信は普通にしよう。
発信した結果が逆の方向でもこれはこれでしょうがないし。
普通に自分の想いを出す。
それの継続。
まあ、今は僕を親父はかなり対等な関係でいい感じ。
源はよくぶつかってるけど、、、。
ま、想いが強すぎてぶつかるってのが常やからねー。
わざと強調したような言い方や姿勢は対立の素やね。
僕はこう想うからこうする。
てのがスッキリするよね。
いやー、一日中田んぼに居ると気持ちええねー。
バインダーで束ねたワラの麻ヒモを鎌で切ってバラバラにしていく。
延々と続くかのようなこういう地味な作業が農においては常識。
僕なんかは常にもっと能率的に、、、とか考えてしまう。
先人はそういうのを考えまくって機械化していったんやろね。
誰でも、機械の開発される前は機械化を望んだやろね。
でも、こうして機械が常識の現代では手作業の意味を掘り返して脱機械化という考え方も出てきて当然。
まー、福岡正信さんなんか60年以上も前から「そんなん意味ないぞー。」って言うてきた訳やからゴツイよね。
「ワラ一本の革命」読んでない人はちゃんと読もうね。
現代人は何にも考えずに淡々としたこの手作業は出来ない。
もっと早く、もっと能率的に、と言う洗脳を受けてるから。
もちろん僕も。
福岡さんの「人智無為」(人間の考える事は全て意味が無い)という思想にしたって超考えまくって出てきた発想やろし。
てことは、超頑張って非能率的な手作業を味わうのだ。
いや、ほんま、機械に使われてる時の作業と、静かに手作業でやってる時の違いって凄いよ。
何しろ、もっと早く!とさえ考えんかったらね。
でも全部の農機具を買う計算すれば、実は全部手作業でした方が絶対的に楽。
経済的に。
かつて一反を完全に不耕起でやって成功した事があるけど、2、3人も居れば田植えや稲刈りは4日前後って感じ。
てことは食べる人数総出でかかれば全く機械がなくても、家族が食べるだけの2、3反の田んぼは十分に可能。
おっと、自分の人件費は0で計算するように。
別に田植えや稲刈りに一週間かかったってかまんやん。
一番大事な穀物お米のため。
うちでは毎日玄米をモリモリ食べる以外にも、、、。
自家製の麹を仕込んでの
甘酒
ドブロク
味噌
これは完成してる。
後、玄米粉のスイーツも。
それこそスイーツの甘味の米飴も。
後は黒煎り玄米コーヒーも。
凄いよねー。
主食、調味料、酒、甘味とお米からできる加工品ってほんまパーフェクト!
自分の田んぼから産み出すマクロビオティックやねー。
夕方、ワラの広がる田んぼに立ってると、どこから来るでもない満足感に浸れる。
ほんまに気持ちええよ。
これが真の贅沢だーーー!
2009年11月09日
88祭りファイナル
8日は徳島は美馬町、「四国三郎の郷」。
四国三郎とは四国を代表する吉野川の事。
書道詩人てらきちの言い出した3年連続で四国を一周歩く。
でもって、毎年四国四県で「88祭り」をやって四国のおもろいもの、美味しいものを繋げて楽しもうと。
今年は2年目。
去年も今年も廃材天国として高松の中央公園での祭りに出店させてもろた。
しかし、てんつくマンの開発した「路上詩人、あなたを見てインスピレーションで言葉を書きます」というパフォーマンスは超流行ってる。
このてらきちもてんつくマンの弟子。
まあ、全国に居る路上詩人がどう言おうが路上詩人は全員てんつくマンの弟子にあたる。
やっぱり、自分発という新たな分野を開拓した男は凄いね。
このてらきちもその中でもかなりのレベル。
完全に成功してる。
パフォーマンスや講演だけでも引く手アマタ。
その上この3年連続の88祭り。
おそらく来年の最後の年には凄い事になりそうやね。
イベント自体はこないだの「たいこの祭り」や「山水人」のようなコアなものじゃなく、あくまで、明るいお日様の元子ども連れで参加できる入り口の広い祭り。
僕も個人的にはいわゆる「祭り系」のコアなイベントも大好きやけど、こういう明るい祭りも楽しいね。
いや、コアな祭り系にこそ、子どもと一緒に行って、こどものうちからああいう空気でいい意味の教育を施した方がええよ。
むしろ、88祭りなどは今の社会や生活に何の疑問も、危機感もないゴクフツーの人でも入りやすい入門編。
でも入門編やからというでバカに出来んで。
ほんとにこのてらきちは天然のアホ丸出しで熱い男。
この男の役割としてこれをやってくれよる事はかなり意味が深いね。
カマドGOGOの青木ーズや神山の楽音のみんなも来てる事がそれを伺わせる。
今回はマクロビスイーツや玄米オムスビはもちろん、ここの所勢いに乗ってる手打ちパスタも出店。
前回がトマトソースだったんで、今回はピリ辛キノコぺペロンチーニ。
醤油ベースの和風仕上げ。
もちろん自画自賛のハイクオリティーの仕上がりになったね。
茹で立ての手打ちパスタにキノコソースを絡ませて、生のルッコラを刻んだのを混ぜて最後に刻み海苔をふりかける。
見た目にも味的にも最高やね。
その辺の安物のイタメシ屋でここまでのクオリティーのパスタを500円で出してくれるだろうか、いや在り得ないね。
思わず二重否定入るぐらいの出来栄えやったね。
最後に楽音の阿波+アフリカンのアワリカンドラムとトラディショナルな「きらく連」とのセッションでみんなで総踊り!
いやー、踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃソンソン♪
僕の解釈では「同じ」やないぞ。
見るだけの一歩引いた立場での参加で祭りが楽しい訳ないし、人生だってそうだろ。
キャーステキー、と芸能人やスポーツ選手を崇める前に自分を崇めろ。
自分が凄い。
誰よりも。
自分にとっては。
むしろ、芸能人なりスポーツ選手はそこを言わんが為にスターとして自分の行き方を見せてくれとる訳やぞ。
繰り返すぞ。
踊る阿呆と見る阿呆は同じやない。
踊ってこその阿呆やし、冷ややかな観客としての生き方からマジにアホになる熱い生き方をしようぜ。
アホの神様てんつくマンのお陰で、香川が誇るこれまたドアホのてらきちがある。
で、僕ら四国のアホな仲間が終結する。
アホ最高!
踊る阿呆はところん踊る。
踊ることに躊躇しよる間に人生終わるぞ。
ウカウカするな。
踊れー!
踊れよーーー!!!



四国三郎とは四国を代表する吉野川の事。
書道詩人てらきちの言い出した3年連続で四国を一周歩く。
でもって、毎年四国四県で「88祭り」をやって四国のおもろいもの、美味しいものを繋げて楽しもうと。
今年は2年目。
去年も今年も廃材天国として高松の中央公園での祭りに出店させてもろた。
しかし、てんつくマンの開発した「路上詩人、あなたを見てインスピレーションで言葉を書きます」というパフォーマンスは超流行ってる。
このてらきちもてんつくマンの弟子。
まあ、全国に居る路上詩人がどう言おうが路上詩人は全員てんつくマンの弟子にあたる。
やっぱり、自分発という新たな分野を開拓した男は凄いね。
このてらきちもその中でもかなりのレベル。
完全に成功してる。
パフォーマンスや講演だけでも引く手アマタ。
その上この3年連続の88祭り。
おそらく来年の最後の年には凄い事になりそうやね。
イベント自体はこないだの「たいこの祭り」や「山水人」のようなコアなものじゃなく、あくまで、明るいお日様の元子ども連れで参加できる入り口の広い祭り。
僕も個人的にはいわゆる「祭り系」のコアなイベントも大好きやけど、こういう明るい祭りも楽しいね。
いや、コアな祭り系にこそ、子どもと一緒に行って、こどものうちからああいう空気でいい意味の教育を施した方がええよ。
むしろ、88祭りなどは今の社会や生活に何の疑問も、危機感もないゴクフツーの人でも入りやすい入門編。
でも入門編やからというでバカに出来んで。
ほんとにこのてらきちは天然のアホ丸出しで熱い男。
この男の役割としてこれをやってくれよる事はかなり意味が深いね。
カマドGOGOの青木ーズや神山の楽音のみんなも来てる事がそれを伺わせる。
今回はマクロビスイーツや玄米オムスビはもちろん、ここの所勢いに乗ってる手打ちパスタも出店。
前回がトマトソースだったんで、今回はピリ辛キノコぺペロンチーニ。
醤油ベースの和風仕上げ。
もちろん自画自賛のハイクオリティーの仕上がりになったね。
茹で立ての手打ちパスタにキノコソースを絡ませて、生のルッコラを刻んだのを混ぜて最後に刻み海苔をふりかける。
見た目にも味的にも最高やね。
その辺の安物のイタメシ屋でここまでのクオリティーのパスタを500円で出してくれるだろうか、いや在り得ないね。
思わず二重否定入るぐらいの出来栄えやったね。
最後に楽音の阿波+アフリカンのアワリカンドラムとトラディショナルな「きらく連」とのセッションでみんなで総踊り!
いやー、踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃソンソン♪
僕の解釈では「同じ」やないぞ。
見るだけの一歩引いた立場での参加で祭りが楽しい訳ないし、人生だってそうだろ。
キャーステキー、と芸能人やスポーツ選手を崇める前に自分を崇めろ。
自分が凄い。
誰よりも。
自分にとっては。
むしろ、芸能人なりスポーツ選手はそこを言わんが為にスターとして自分の行き方を見せてくれとる訳やぞ。
繰り返すぞ。
踊る阿呆と見る阿呆は同じやない。
踊ってこその阿呆やし、冷ややかな観客としての生き方からマジにアホになる熱い生き方をしようぜ。
アホの神様てんつくマンのお陰で、香川が誇るこれまたドアホのてらきちがある。
で、僕ら四国のアホな仲間が終結する。
アホ最高!
踊る阿呆はところん踊る。
踊ることに躊躇しよる間に人生終わるぞ。
ウカウカするな。
踊れー!
踊れよーーー!!!
2009年11月09日
廃材カントリー
農業用語での「カントリー」とは農協が大きな設備を構える籾の乾燥、籾摺り、更には玄米の冷蔵貯蔵まで年間を通して管理してくれる施設「カントリーエレベータ」の事。
もちろん秋山家の米、誰それの米とイチイチ分けて管理は出来ないんで、品種ごとに分けて全部一緒になってしまう。
で、「保有米」として農協に管理してもらってる米は一月に何体、二月に何体、、、と申し込みをしておくと近所の農協の支所の職員が配達までしてくれる。
一方、コンバインで刈り取った後、乾燥機、籾摺り機、30㌔に袋詰めするパッカー、玄米を貯蔵する大型冷蔵庫、と自前で揃えるとその設備代だけでも凄い事になる。
お金の事だけで言うといわゆる「米なんか買うた方が早い」のである。
ここの所、ヒノヒカリの30㌔の原価は6000円前後。
一升で300円やからねー。
今の時代、一日何合食べる?
家族で3合とか5合とかやろ。
5合やったら150円。
30㌔単位で買うとこんなにも安い。
精米も10㌔単位でそこらじゅうにコイン精米機があるし。
ちなみに今年はカメムシが大発生して、玄米の中に黒い米の混じる率が高く、ひどい米は一合の中に何粒も入るほど。
これは白米に精米しても「色選機」という特殊な機械を設備しない限り黒く残る。
そのひどい状態の玄米30㌔は3500円、、、。
これが現代日本の流通の常識。
井戸端会議では曲がったキュウリでもいいじゃんとなるけど、現実お店では曲がったキュウリも黒い粒がたまに混じる米も商品価値はサッパリない。
いっその事、黒米を少し混ぜて最初から黒米入りの米としてプレミアムを付けて逆に高く売るとかしたらええんちゃうの。
そういう話も高瀬の一軒目の廃材ハウスの土地のオーナー河野さんの「廃材カントリー」で聞いた。
何しろ、河野さんの籾摺り場自体が僕の廃材建築の原点。
木の電柱で出来てる。
もちろん、「廃材王国」のハセヤンの本で「できるかも?」と思い立ったのがスタートやけどその実行する現場が河野さんの土地というのがよかった。
その河野さんの廃材カントリーの電柱の作業場には超古い乾燥機が所狭しと並ばされ、河野さんのアイデアによってスパイラルのパイプや籾を上げるタワー、ベルトコンベアーなどでほんとに効率よく設備されてる。
パイプの隙間なんかにはガムテープが随所に使われてて、いい感じ。
玄米をパレットに積んだのを移動するフォークリフトなんかも中古で5万とか。
もちろんちゃんと動いてるで。
更にオモロイのはそのフォークのバッテリーは土建屋のお下がりでユンボのバッテリーが弱って交換した時のをもらったりしてる。
今回でもウチの籾摺りをしながら籾摺り機を叩いたり、籾が漏れる箇所に張ってあるガムテープを張り替えたりと河野さんは忙しい。
その河野さん「ウチの機械は何回動かんようになったって直されるきんいつまで経っても引退させてくれへんでー。」とガハハ笑いをしながら軽く語ってくれたよ。
実質本位。
ほんとうに必要なのはお金じゃなくてお米。
景気が悪くなろうが、金融崩壊しようが、食料輸入がストップしようが、原子力発電所が事故を起こそうが、毎日食べるものは要る。
要るやろが!
と言うた所で、何でもお金さえ出せば買えるという今では何も説得力もないけどね、、、。
自分にとってほんとうに実質本位のモノや事を選択せないかんよ。
今のモヤモヤした不安は一体ドコから来るのか?
それは細胞の中にあるDNAや魂に記憶されてる宇宙の情報に反する今の歪んだ社会の常識から。
その自分の中の不安を脱却するのは自分にしか出来ない。
八ヶ岳のハセヤンとこもそやし、この河野さんの廃材カントリーもそう。
そういう自力で何とかしてしまってる型の所に行けば超リアリティーのある説得力がある。
全部新品で揃えれば何千万もかかる設備をホントに最低限で実現してる河野さんはこの4ヶ月程で一年間の収入を得る。
そして「アートで田んぼ」などの自分のやりたい事に全力投球されてる。
地域社会の真ん中で生き方そのものがアートな河野さんはほんとに地に足をつけて活動してる。
ほんとにラピュタのドーントレス号のような廃材カントリーで、23俵のお米を籾摺りしてもらってほんとに豊かな気分。
30㌔の袋一体の籾摺り代は200円。
農協のカントリーなら年間契約で超高額の管理費取られた上に自分の作ったお米が食べられないという百姓としては在り得ないことやからねー。
自分のやってる事がしっくりくるアットホームな農のスタイルがええね。
一年間の稲の作業が終了して感無量!





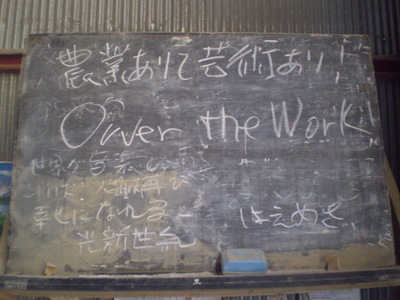
もちろん秋山家の米、誰それの米とイチイチ分けて管理は出来ないんで、品種ごとに分けて全部一緒になってしまう。
で、「保有米」として農協に管理してもらってる米は一月に何体、二月に何体、、、と申し込みをしておくと近所の農協の支所の職員が配達までしてくれる。
一方、コンバインで刈り取った後、乾燥機、籾摺り機、30㌔に袋詰めするパッカー、玄米を貯蔵する大型冷蔵庫、と自前で揃えるとその設備代だけでも凄い事になる。
お金の事だけで言うといわゆる「米なんか買うた方が早い」のである。
ここの所、ヒノヒカリの30㌔の原価は6000円前後。
一升で300円やからねー。
今の時代、一日何合食べる?
家族で3合とか5合とかやろ。
5合やったら150円。
30㌔単位で買うとこんなにも安い。
精米も10㌔単位でそこらじゅうにコイン精米機があるし。
ちなみに今年はカメムシが大発生して、玄米の中に黒い米の混じる率が高く、ひどい米は一合の中に何粒も入るほど。
これは白米に精米しても「色選機」という特殊な機械を設備しない限り黒く残る。
そのひどい状態の玄米30㌔は3500円、、、。
これが現代日本の流通の常識。
井戸端会議では曲がったキュウリでもいいじゃんとなるけど、現実お店では曲がったキュウリも黒い粒がたまに混じる米も商品価値はサッパリない。
いっその事、黒米を少し混ぜて最初から黒米入りの米としてプレミアムを付けて逆に高く売るとかしたらええんちゃうの。
そういう話も高瀬の一軒目の廃材ハウスの土地のオーナー河野さんの「廃材カントリー」で聞いた。
何しろ、河野さんの籾摺り場自体が僕の廃材建築の原点。
木の電柱で出来てる。
もちろん、「廃材王国」のハセヤンの本で「できるかも?」と思い立ったのがスタートやけどその実行する現場が河野さんの土地というのがよかった。
その河野さんの廃材カントリーの電柱の作業場には超古い乾燥機が所狭しと並ばされ、河野さんのアイデアによってスパイラルのパイプや籾を上げるタワー、ベルトコンベアーなどでほんとに効率よく設備されてる。
パイプの隙間なんかにはガムテープが随所に使われてて、いい感じ。
玄米をパレットに積んだのを移動するフォークリフトなんかも中古で5万とか。
もちろんちゃんと動いてるで。
更にオモロイのはそのフォークのバッテリーは土建屋のお下がりでユンボのバッテリーが弱って交換した時のをもらったりしてる。
今回でもウチの籾摺りをしながら籾摺り機を叩いたり、籾が漏れる箇所に張ってあるガムテープを張り替えたりと河野さんは忙しい。
その河野さん「ウチの機械は何回動かんようになったって直されるきんいつまで経っても引退させてくれへんでー。」とガハハ笑いをしながら軽く語ってくれたよ。
実質本位。
ほんとうに必要なのはお金じゃなくてお米。
景気が悪くなろうが、金融崩壊しようが、食料輸入がストップしようが、原子力発電所が事故を起こそうが、毎日食べるものは要る。
要るやろが!
と言うた所で、何でもお金さえ出せば買えるという今では何も説得力もないけどね、、、。
自分にとってほんとうに実質本位のモノや事を選択せないかんよ。
今のモヤモヤした不安は一体ドコから来るのか?
それは細胞の中にあるDNAや魂に記憶されてる宇宙の情報に反する今の歪んだ社会の常識から。
その自分の中の不安を脱却するのは自分にしか出来ない。
八ヶ岳のハセヤンとこもそやし、この河野さんの廃材カントリーもそう。
そういう自力で何とかしてしまってる型の所に行けば超リアリティーのある説得力がある。
全部新品で揃えれば何千万もかかる設備をホントに最低限で実現してる河野さんはこの4ヶ月程で一年間の収入を得る。
そして「アートで田んぼ」などの自分のやりたい事に全力投球されてる。
地域社会の真ん中で生き方そのものがアートな河野さんはほんとに地に足をつけて活動してる。
ほんとにラピュタのドーントレス号のような廃材カントリーで、23俵のお米を籾摺りしてもらってほんとに豊かな気分。
30㌔の袋一体の籾摺り代は200円。
農協のカントリーなら年間契約で超高額の管理費取られた上に自分の作ったお米が食べられないという百姓としては在り得ないことやからねー。
自分のやってる事がしっくりくるアットホームな農のスタイルがええね。
一年間の稲の作業が終了して感無量!
2009年11月07日
からくも脱穀終了
5、6日とハゼ(稲の乾燥用の木)に吊り下げて乾かしてて稲の脱穀。
ここ3年、バインダーで刈ってバーベスタで脱穀という30年前のスタンダードスタイルでやってる。
近所のおっちゃんに貰ったバインダーとハーベスタが今年はどちらも限界にきてて、かなり作業は難航した。
って言うても稲刈りに4日、脱穀に2日やからええんちゃう?
ちなみに普通サイズのコンバインなら全部で一日で終わる作業。
まーでも、コンバインで刈ると乾燥機のボイラーで乾燥させんといかんしね。
自然農の川口さんから聞いた「刈って干してる間にも稲は生きてて、茎の養分を籾に蓄えてるんだ。」という話にえらく納得したのを思い出したね。
3反あるんで、オール農機具フリーは大変なんで今のこのスタイルでしばらくやろかね。
徹底的に力んでコダワルよりもまずは自分たちが楽なスタンスでね。
実は90になる僕のばあちゃんが「長いことかかってフが悪いきん私がお金出してやるきん来年からコンバインで刈ってもらえ。」と言い出した局面があった。
コンバインの刈り賃は一反で2万4000円という相場。
そりゃ、普通サイズで300万、賃刈りを請け負うような大型のだと700万とかやもん、、、。
この「フが悪い」というのは「風ていが悪い」の讃岐弁で、年寄り連中はみんなが連発する愛用語になってる。
そもそも今の秋山家の稲作りは「農業」じゃなく「農的遊びの延長」なんで、お金が高い安いとか、ましてや早い遅いなどという尺度はお呼びでない。
でもね、お金に換算すれば、うちの農薬、化学肥料、除草剤フリーのオーガニック米の相場は30㌔1万5千円。
一反に7俵ぐらいは採れるから3反で20俵ぐらい。
てことは40体できるんで60万。
年間、集中的な作業はほんの何日かでこんだけの価値やからねー。
(ちなみに普通のお米の相場は30㌔で6000円切ってる、、、)。
もちろん水の管理や苗代作りや何やかんやあるけど、うちで消費する無農薬米が60万とは驚きやね。
という、屁理屈はばあちゃんには通用せんけどね。
でも理解は無理でもちゃんと、繰り返し伝える事が大切。
もちろん口だけでは何にも伝わらん。
楽しい労働を日々実践し続ける事やぞ。
実はばあちゃんの心配の根拠は「お父さんが疲れとるが、身体壊してしまうが。」というのがあった。
確かに親父はやたらと最近しんどそうにする。
それで作業が長引いて大変そうとの気遣いからという事やった。
年のせいというよりは、事実しんどいような身体の使い方をしてる。
古武術や気の勉強したらええんちゃうの、と思ってしまう。
それに同居の無職のユルユル系の源に、ロクに陶芸で儲けてもない長男と、ばあちゃんの心配は「私や長生きしても何ちゃええ事ないわ、早よ死にたい、、、。」という一同シーンとなるキメ台詞でシメる。
そこで源が「見てみー、ばあちゃんこの空気、みんなが嫌な雰囲気になるやろー。そんだけ心配できるんやきん元気なもんや!まだまだ死なへんぞ!」と明るく突っ込む。
この言われっぱなしでない「明るいニート」は最近益々成長してる(いい意味で)。
ほんとにばあちゃんは90にして尚気丈でボケるヒマもなく、みんなの事を考えてくれてる。
そういう意味ではありがたいよねー。
親父に楽に取り組めるようになって欲しいし、僕や源がもっと積極的に日常の田の管理なんかもやったほうがええんやろな。
でも船頭は親父やからあんまし、僕が仕切るのもね。
とにかく、今日のキーワード「楽しい労働」に徹するしかないよね。
まー、機械も僕より長生きしてるような骨董品やからね。
バインダーはタイヤがイカレて、ハーベスタはベルトが3本も切れかけやった、、、。
そういうのは近所の農機具屋のプロに頼んで直してもらった。
一軒目の廃材建築の時、オーナーの河野さんに口を酸っぱくして言うわれた「サラの機械は少々無理しても壊れんけど、ボロ程丁寧に使わないかん。」と言われてたのを思い出したね。
始めの頃は一時間ユンボに乗って、後の時間は外したキャタピラを入れるのに四苦八苦して一日が終わるというのがしょっちゅうやったからね、、、。
今回も一日目はほとんど作業にならんかったけど、機械の調子を伺いながら2日目で全部脱穀できたんやからええんちゃうの。
こういう時に農機具屋は「今のハーベスタなら40万もあればバリバリですよ!」とセールスする。
だからー、バリバリでなくってええんやって!
このボロを上手く直しながら使うプロの河野さんや田村さんという師匠に一軒目の時に徹底的に世話になってるので、僕もそういう美学めいた価値観がある。
お金云々よりもオモロないんよ、新車や新品って、ワクワクしないんよ、全っ然。
あの「天空の城ラピュタ」に出てくるママの海賊船のような河野さんの籾摺り場へ今日籾摺りに行く。
それはそれはワクワクやでー。
天才やー!
映画にワクワクするヒマがあったら自分が主人公の人生という映画をワクワクさせよーぜ。
次の日記に譲るけど、それこそ自力で電柱で建てた籾摺り場、30年40年前の乾燥機は30台を超え、5万で買ったフォークリフトも現役で働いてる。
籾摺り場には籾摺りに来る人の差し入れが絶えることなく仲間で宴会。
まさしく近未来型の農村の姿。
ほんと、一軒目の廃材ハウスを河野さんの土地を借りて出来たことは本当にありがたい。
その精神が今の廃材天国に根付いてるんやからねー。
作業に必死で写真はない、、、。
ここ3年、バインダーで刈ってバーベスタで脱穀という30年前のスタンダードスタイルでやってる。
近所のおっちゃんに貰ったバインダーとハーベスタが今年はどちらも限界にきてて、かなり作業は難航した。
って言うても稲刈りに4日、脱穀に2日やからええんちゃう?
ちなみに普通サイズのコンバインなら全部で一日で終わる作業。
まーでも、コンバインで刈ると乾燥機のボイラーで乾燥させんといかんしね。
自然農の川口さんから聞いた「刈って干してる間にも稲は生きてて、茎の養分を籾に蓄えてるんだ。」という話にえらく納得したのを思い出したね。
3反あるんで、オール農機具フリーは大変なんで今のこのスタイルでしばらくやろかね。
徹底的に力んでコダワルよりもまずは自分たちが楽なスタンスでね。
実は90になる僕のばあちゃんが「長いことかかってフが悪いきん私がお金出してやるきん来年からコンバインで刈ってもらえ。」と言い出した局面があった。
コンバインの刈り賃は一反で2万4000円という相場。
そりゃ、普通サイズで300万、賃刈りを請け負うような大型のだと700万とかやもん、、、。
この「フが悪い」というのは「風ていが悪い」の讃岐弁で、年寄り連中はみんなが連発する愛用語になってる。
そもそも今の秋山家の稲作りは「農業」じゃなく「農的遊びの延長」なんで、お金が高い安いとか、ましてや早い遅いなどという尺度はお呼びでない。
でもね、お金に換算すれば、うちの農薬、化学肥料、除草剤フリーのオーガニック米の相場は30㌔1万5千円。
一反に7俵ぐらいは採れるから3反で20俵ぐらい。
てことは40体できるんで60万。
年間、集中的な作業はほんの何日かでこんだけの価値やからねー。
(ちなみに普通のお米の相場は30㌔で6000円切ってる、、、)。
もちろん水の管理や苗代作りや何やかんやあるけど、うちで消費する無農薬米が60万とは驚きやね。
という、屁理屈はばあちゃんには通用せんけどね。
でも理解は無理でもちゃんと、繰り返し伝える事が大切。
もちろん口だけでは何にも伝わらん。
楽しい労働を日々実践し続ける事やぞ。
実はばあちゃんの心配の根拠は「お父さんが疲れとるが、身体壊してしまうが。」というのがあった。
確かに親父はやたらと最近しんどそうにする。
それで作業が長引いて大変そうとの気遣いからという事やった。
年のせいというよりは、事実しんどいような身体の使い方をしてる。
古武術や気の勉強したらええんちゃうの、と思ってしまう。
それに同居の無職のユルユル系の源に、ロクに陶芸で儲けてもない長男と、ばあちゃんの心配は「私や長生きしても何ちゃええ事ないわ、早よ死にたい、、、。」という一同シーンとなるキメ台詞でシメる。
そこで源が「見てみー、ばあちゃんこの空気、みんなが嫌な雰囲気になるやろー。そんだけ心配できるんやきん元気なもんや!まだまだ死なへんぞ!」と明るく突っ込む。
この言われっぱなしでない「明るいニート」は最近益々成長してる(いい意味で)。
ほんとにばあちゃんは90にして尚気丈でボケるヒマもなく、みんなの事を考えてくれてる。
そういう意味ではありがたいよねー。
親父に楽に取り組めるようになって欲しいし、僕や源がもっと積極的に日常の田の管理なんかもやったほうがええんやろな。
でも船頭は親父やからあんまし、僕が仕切るのもね。
とにかく、今日のキーワード「楽しい労働」に徹するしかないよね。
まー、機械も僕より長生きしてるような骨董品やからね。
バインダーはタイヤがイカレて、ハーベスタはベルトが3本も切れかけやった、、、。
そういうのは近所の農機具屋のプロに頼んで直してもらった。
一軒目の廃材建築の時、オーナーの河野さんに口を酸っぱくして言うわれた「サラの機械は少々無理しても壊れんけど、ボロ程丁寧に使わないかん。」と言われてたのを思い出したね。
始めの頃は一時間ユンボに乗って、後の時間は外したキャタピラを入れるのに四苦八苦して一日が終わるというのがしょっちゅうやったからね、、、。
今回も一日目はほとんど作業にならんかったけど、機械の調子を伺いながら2日目で全部脱穀できたんやからええんちゃうの。
こういう時に農機具屋は「今のハーベスタなら40万もあればバリバリですよ!」とセールスする。
だからー、バリバリでなくってええんやって!
このボロを上手く直しながら使うプロの河野さんや田村さんという師匠に一軒目の時に徹底的に世話になってるので、僕もそういう美学めいた価値観がある。
お金云々よりもオモロないんよ、新車や新品って、ワクワクしないんよ、全っ然。
あの「天空の城ラピュタ」に出てくるママの海賊船のような河野さんの籾摺り場へ今日籾摺りに行く。
それはそれはワクワクやでー。
天才やー!
映画にワクワクするヒマがあったら自分が主人公の人生という映画をワクワクさせよーぜ。
次の日記に譲るけど、それこそ自力で電柱で建てた籾摺り場、30年40年前の乾燥機は30台を超え、5万で買ったフォークリフトも現役で働いてる。
籾摺り場には籾摺りに来る人の差し入れが絶えることなく仲間で宴会。
まさしく近未来型の農村の姿。
ほんと、一軒目の廃材ハウスを河野さんの土地を借りて出来たことは本当にありがたい。
その精神が今の廃材天国に根付いてるんやからねー。
作業に必死で写真はない、、、。
2009年11月04日
第二回、たいこのまつり
高知は安芸。
タイガースのキャンプで有名な球場の手前。
55線からガタガタ道を海に下りた砂利浜(砂でなくて砂利)。
車を止めた場所からザクザクと歩いて行くとパラパラとテントが並んでる。
この祭の主催者はくずめさんというジャンベを作る専門家。
もちろんアフリカ(マリ共和国)に行かれてジャンベの作り方を習得されて、日本で製作されてる。
お話を伺うと、アフリカで太鼓を作る事は日常に使う臼やイス、ボウルを作る延長なんだと。
その家を継ぐ家長が鍛冶になり、チョウナのような道具を作る。
弟やおじさんのような取り巻きが丸太削りの職人になるんだと。
太鼓作りの職人でなく、丸太削り。
丸太を削る人はイスやボウルという日常の道具を産み出し、太鼓も作る。
もちろん、チェーンソーも電動工具もなしで。
と、いうアフリカントラディショナルなスタイルで、くずめさんも実際にイスや太鼓を削ってる。
で、その日本でも唯一と言うてもええぐらいの本格的な手づくりのジャンベ職人のくずめさんの太鼓を愛用する、これまた日本のトップクラスのマスタードラマーの競演っ!!!
僕もハタチぐらいの時、岡山でママディ・ケイタの演奏を生で観て涙が溢れた。
アフリカとは縁もゆかりもないような現代人の日本の僕でさえ、魂レベルで芯から揺さぶられる。
今回、こんなに贅沢な演奏の連続でええんかーーーという超凄い面々。
サヨコオトナラの奈良さん、岡山のわっしーの師匠のニシヤマン、一月程前に廃材天国に寄ってくれた三好トウヨウ、神戸のまことくん、他にもたくさんの太鼓マニア大集結。
やっぱり天才的な奏者はほんとに芯から太鼓が好きでやりまくってたら上手くなったという事やと思ったね。
誰も苦労して努力を重ねた人はここにはいない。
出発のくずめさんがそう。
日本を代表する宮大工の今は亡き西岡棟梁の話を用いて、当時の職人は木と対話出来たと。
法隆寺のように600年も持つ建築物を建てるような技術はテクノロジーとかいう言葉で表現できるような世界ではないぞ。
おそらく、このジャンベという太鼓もそう。
丸太を前にして経験と直感で彫る。
いかに木と付き合うか。
その真髄にほんのすこしだけ触れて鳥肌が立った。
とにかく自分で音楽の演奏とかはしない僕も、ジャンベを目の前にしてアホみたいに踊り狂うのが大好き。
そういう意味でも普段在り得ない、太平洋の水平線をバックに焚き火を囲むハイグレードなジャンベ奏者たちには痺れるーー。
うちは手打ちパスタ、マクロビスイーツ、玄米オムスビなんかを出店しながら心ゆくまで楽しんだ。
出店に関しては連続で大変な面と連続することで次々回していけるメリットがある。
宇多津の収穫祭で残ったトマトソースをここへ持ってきたし、スイーツなんかもそう。
麺に関しては現地でパスタマシン廻した。
ほんと、遊びに行って合間で商売できるんやから最高!
僕もあっこちゃんも自分ら的には山水人よりも他の祭よりも最高のロケーションとすばらしい条件での出店が出来て絶対に来年も来たいねーと言いながら帰路についた。
うちらもそやし、くずめさんやトウヨウやニシヤマンを観てて思うけど、ほんとに好きな事をしてみんなに喜んでもらえる事しか続かないね。
そういう生き方の根幹に熱く訴える為の祭であったとも思うね。
横に並ぶ出店者のじゃじゃロクさん、アララトさん、青キーズ、楽音家族、アイタルカレーのデバちゃん、、、とみんな同士。
僕の言う同士とはほんとに大切なものに全精力をかける、当たり前のライフスタイルを選択した人たち。
ほんとに僕には最高で至高の祭やった。
この為に産まれてきて、今生きてるんやーってね。
なっちゃんが「上関原発いらん」という旗を持ってきて踊ったのも象徴的やった。
クマさんやアララトさん、ナダ長老が山口の田名埠頭に行ってた話も深く聞いた。
僕も行かないかん。
この楽しくないかのようなの原発反対も、美味しいもんつくって太鼓を楽しむ最高の宴も実は同じ。
同じエネルギーだぞ。
ほんとに好きなことをして生きていくための責任がぼくらにはある。
その責任を果たさない限り、ほんとの自由は手にはいらないんよ。
分かるか!
ほんとに分かりたい奴だけが前に出ろ!
その覚悟をせんかぎりほんとに楽しい人生は決して訪れない。
決してね。
歯を食いしばらずに、口を開けて両手両足ブラブラで。
ブラブラで居て自立と自律を兼ね備えた自由がキーワードやきんねー。
大手の商社にも外食産業にも電力会社にも世話にならんでも自分らの世話は自分らの仲間でしようぞ。
いやー、一日カフェ、宇多津の祭、たいこのまつりと連日の出店がいい意味でリンクと加速を呼んで超能率がよくて、いい仕事ができた4日間になったねー。
そういう意味では連日で大変という部分と連日やからいろんな準備が兼ねられるメリットとかあるね。
どっちにせよ、僕らの目的は痺れる太鼓に自分ら家族が楽しい遊びに兼ねて出店してるだけなんで、あんまし細かい事は考えてない。
ほんとに焚き火と太鼓と夕日にここまで感動できたら、ある意味怖いもんなしのフルパワー状態。
ほんとにくずめさんの彫った太鼓を愛用するとんでも無くレベルの高い奏者が繋がってることも希望やね。
かれらからは太鼓以外の人生の指針も含めてエッセンスとして受け取るイベントやったと思う。
そのぐらいゴツかった!
ほんとに人間は「今」に満足してたら、過剰に溜め込んだり不安にさいなまれたりせずにハッピーに生きていけるね。
集まったみんながその「今を楽しむ」ことに全エネルギーをかけてるんやからそうなるしかないって。
海最高!
月最高!
夕日最高!
太鼓最高!
踊り最高!
アナゴ最高!
お酒最高!
植物最高!
みんな最高!

僕とくずめ氏の語らい



ファイヤーダンスも凄かったーーー!
タイガースのキャンプで有名な球場の手前。
55線からガタガタ道を海に下りた砂利浜(砂でなくて砂利)。
車を止めた場所からザクザクと歩いて行くとパラパラとテントが並んでる。
この祭の主催者はくずめさんというジャンベを作る専門家。
もちろんアフリカ(マリ共和国)に行かれてジャンベの作り方を習得されて、日本で製作されてる。
お話を伺うと、アフリカで太鼓を作る事は日常に使う臼やイス、ボウルを作る延長なんだと。
その家を継ぐ家長が鍛冶になり、チョウナのような道具を作る。
弟やおじさんのような取り巻きが丸太削りの職人になるんだと。
太鼓作りの職人でなく、丸太削り。
丸太を削る人はイスやボウルという日常の道具を産み出し、太鼓も作る。
もちろん、チェーンソーも電動工具もなしで。
と、いうアフリカントラディショナルなスタイルで、くずめさんも実際にイスや太鼓を削ってる。
で、その日本でも唯一と言うてもええぐらいの本格的な手づくりのジャンベ職人のくずめさんの太鼓を愛用する、これまた日本のトップクラスのマスタードラマーの競演っ!!!
僕もハタチぐらいの時、岡山でママディ・ケイタの演奏を生で観て涙が溢れた。
アフリカとは縁もゆかりもないような現代人の日本の僕でさえ、魂レベルで芯から揺さぶられる。
今回、こんなに贅沢な演奏の連続でええんかーーーという超凄い面々。
サヨコオトナラの奈良さん、岡山のわっしーの師匠のニシヤマン、一月程前に廃材天国に寄ってくれた三好トウヨウ、神戸のまことくん、他にもたくさんの太鼓マニア大集結。
やっぱり天才的な奏者はほんとに芯から太鼓が好きでやりまくってたら上手くなったという事やと思ったね。
誰も苦労して努力を重ねた人はここにはいない。
出発のくずめさんがそう。
日本を代表する宮大工の今は亡き西岡棟梁の話を用いて、当時の職人は木と対話出来たと。
法隆寺のように600年も持つ建築物を建てるような技術はテクノロジーとかいう言葉で表現できるような世界ではないぞ。
おそらく、このジャンベという太鼓もそう。
丸太を前にして経験と直感で彫る。
いかに木と付き合うか。
その真髄にほんのすこしだけ触れて鳥肌が立った。
とにかく自分で音楽の演奏とかはしない僕も、ジャンベを目の前にしてアホみたいに踊り狂うのが大好き。
そういう意味でも普段在り得ない、太平洋の水平線をバックに焚き火を囲むハイグレードなジャンベ奏者たちには痺れるーー。
うちは手打ちパスタ、マクロビスイーツ、玄米オムスビなんかを出店しながら心ゆくまで楽しんだ。
出店に関しては連続で大変な面と連続することで次々回していけるメリットがある。
宇多津の収穫祭で残ったトマトソースをここへ持ってきたし、スイーツなんかもそう。
麺に関しては現地でパスタマシン廻した。
ほんと、遊びに行って合間で商売できるんやから最高!
僕もあっこちゃんも自分ら的には山水人よりも他の祭よりも最高のロケーションとすばらしい条件での出店が出来て絶対に来年も来たいねーと言いながら帰路についた。
うちらもそやし、くずめさんやトウヨウやニシヤマンを観てて思うけど、ほんとに好きな事をしてみんなに喜んでもらえる事しか続かないね。
そういう生き方の根幹に熱く訴える為の祭であったとも思うね。
横に並ぶ出店者のじゃじゃロクさん、アララトさん、青キーズ、楽音家族、アイタルカレーのデバちゃん、、、とみんな同士。
僕の言う同士とはほんとに大切なものに全精力をかける、当たり前のライフスタイルを選択した人たち。
ほんとに僕には最高で至高の祭やった。
この為に産まれてきて、今生きてるんやーってね。
なっちゃんが「上関原発いらん」という旗を持ってきて踊ったのも象徴的やった。
クマさんやアララトさん、ナダ長老が山口の田名埠頭に行ってた話も深く聞いた。
僕も行かないかん。
この楽しくないかのようなの原発反対も、美味しいもんつくって太鼓を楽しむ最高の宴も実は同じ。
同じエネルギーだぞ。
ほんとに好きなことをして生きていくための責任がぼくらにはある。
その責任を果たさない限り、ほんとの自由は手にはいらないんよ。
分かるか!
ほんとに分かりたい奴だけが前に出ろ!
その覚悟をせんかぎりほんとに楽しい人生は決して訪れない。
決してね。
歯を食いしばらずに、口を開けて両手両足ブラブラで。
ブラブラで居て自立と自律を兼ね備えた自由がキーワードやきんねー。
大手の商社にも外食産業にも電力会社にも世話にならんでも自分らの世話は自分らの仲間でしようぞ。
いやー、一日カフェ、宇多津の祭、たいこのまつりと連日の出店がいい意味でリンクと加速を呼んで超能率がよくて、いい仕事ができた4日間になったねー。
そういう意味では連日で大変という部分と連日やからいろんな準備が兼ねられるメリットとかあるね。
どっちにせよ、僕らの目的は痺れる太鼓に自分ら家族が楽しい遊びに兼ねて出店してるだけなんで、あんまし細かい事は考えてない。
ほんとに焚き火と太鼓と夕日にここまで感動できたら、ある意味怖いもんなしのフルパワー状態。
ほんとにくずめさんの彫った太鼓を愛用するとんでも無くレベルの高い奏者が繋がってることも希望やね。
かれらからは太鼓以外の人生の指針も含めてエッセンスとして受け取るイベントやったと思う。
そのぐらいゴツかった!
ほんとに人間は「今」に満足してたら、過剰に溜め込んだり不安にさいなまれたりせずにハッピーに生きていけるね。
集まったみんながその「今を楽しむ」ことに全エネルギーをかけてるんやからそうなるしかないって。
海最高!
月最高!
夕日最高!
太鼓最高!
踊り最高!
アナゴ最高!
お酒最高!
植物最高!
みんな最高!
僕とくずめ氏の語らい
ファイヤーダンスも凄かったーーー!
2009年11月01日
宇多津、収穫祭
宇多津の町をあげてのイベント。
その名も収穫祭。
まあ、なんぼ店あるねん!?ていう出店者。
じゃこてん、うどん、焼き鳥、鮮魚、マグロの解体(マジに本マグロ)、乾物、宇治茶、婦人会、農協、ライオンズ、ラーメン、おはぎのおばちゃん、りんご飴、たこ焼き、アイスクリン、高知の物産、土佐刃物、フランクフルト、お寿司、、、、、、。
連想ゲームかーーーー!?
というぐらいの店、店、店!!!
と混沌とした本気激安の店の中に「さぬきビオマーケット」の仲間とい堂々の出店!
リーダーのよしむら農園もカフェ部門のオーガニックコーヒーとケーキも出店。
廃材天国は手打ちパスタと玄米オムスビ、玄米タルト、マクロビスイーツ。
ココペリはいつものパンに加え、揚げたて讃岐牛カツサンド。
ACISは薬膳カレー、玄米甘酒。
はっきり言って、ビオマーケットのクオリティーの高さもびっくりの採算度外視の獲れたて鮮魚を始めとするマジに魅力的で安い品々が満載。
ここで、営業丸出しのプロの店はさぞかし大苦戦を強いられたことと思うね。
さすがに、ビオマーケットの仲間たちもクオリティーの高さが、あまりの店の多さに押されててしまった感はあったけど、お客さんの絶対数もあって、ココペリなんかは早くから完売御礼。
これが代々木公園のアースデイマーケットや京都のはるやの出店する知恩院の手づくり市のような場所やったらなーと無いものねだりしてしまうねー。
いかんせん、人口のしれてるここ香川でオーガニックなり、マクロビを打ち出していこうと言うんやからね。
これがどこどこやったら、、、。
と、情けない「たら」「れば」はお呼びでない!
むしろ、ここやから、ここでやる意義を見出すことの大切さや。
いかに、自分がこのやりたい仕事に満足感を見出すか。
100円で売れようが500円の価値を認めてくれようが、出発は自分。
自分が納得せんことには全てが在り得ないぞ。
昨日の続きになるけど、その自分は自分でさえ認める最高の自分。
自分の汚い部分もせこい所も知った自分が認める自分ぐらい偉大な存在はない。
これこそ在り得ないぞ。
在り得ない事で成り立ってるこの現実の社会であり、僕ら人間の存在。
即色是空、空即是色。
かまへん、かまへん、何でもありの何でも来いコイ。
何があろうと、自分がここにおる以上のリアリティーはあり得んぞ。
そのリアリティーありきで、後は銘々の好きな自分を自己実現するプロセス。
あくまで、飽くまでも、、、いつまで経っても、死ぬ間際まで、そのプロセスの連続でしかない。
誰も分からんし、いかなる存在ですら決定できない、このカオスな宇宙に浮かぶこの星に居させてもらってる。
ここまで掘り下げてくると「いつもいつもありがとうございます!」
としか言えないねよねー。
しつこいようやけど、いくら儲かったから成功という価値観ではない所でいこうぜ。
素の自分の納得度よ。
エクスタシーとでも言おうか!



その名も収穫祭。
まあ、なんぼ店あるねん!?ていう出店者。
じゃこてん、うどん、焼き鳥、鮮魚、マグロの解体(マジに本マグロ)、乾物、宇治茶、婦人会、農協、ライオンズ、ラーメン、おはぎのおばちゃん、りんご飴、たこ焼き、アイスクリン、高知の物産、土佐刃物、フランクフルト、お寿司、、、、、、。
連想ゲームかーーーー!?
というぐらいの店、店、店!!!
と混沌とした本気激安の店の中に「さぬきビオマーケット」の仲間とい堂々の出店!
リーダーのよしむら農園もカフェ部門のオーガニックコーヒーとケーキも出店。
廃材天国は手打ちパスタと玄米オムスビ、玄米タルト、マクロビスイーツ。
ココペリはいつものパンに加え、揚げたて讃岐牛カツサンド。
ACISは薬膳カレー、玄米甘酒。
はっきり言って、ビオマーケットのクオリティーの高さもびっくりの採算度外視の獲れたて鮮魚を始めとするマジに魅力的で安い品々が満載。
ここで、営業丸出しのプロの店はさぞかし大苦戦を強いられたことと思うね。
さすがに、ビオマーケットの仲間たちもクオリティーの高さが、あまりの店の多さに押されててしまった感はあったけど、お客さんの絶対数もあって、ココペリなんかは早くから完売御礼。
これが代々木公園のアースデイマーケットや京都のはるやの出店する知恩院の手づくり市のような場所やったらなーと無いものねだりしてしまうねー。
いかんせん、人口のしれてるここ香川でオーガニックなり、マクロビを打ち出していこうと言うんやからね。
これがどこどこやったら、、、。
と、情けない「たら」「れば」はお呼びでない!
むしろ、ここやから、ここでやる意義を見出すことの大切さや。
いかに、自分がこのやりたい仕事に満足感を見出すか。
100円で売れようが500円の価値を認めてくれようが、出発は自分。
自分が納得せんことには全てが在り得ないぞ。
昨日の続きになるけど、その自分は自分でさえ認める最高の自分。
自分の汚い部分もせこい所も知った自分が認める自分ぐらい偉大な存在はない。
これこそ在り得ないぞ。
在り得ない事で成り立ってるこの現実の社会であり、僕ら人間の存在。
即色是空、空即是色。
かまへん、かまへん、何でもありの何でも来いコイ。
何があろうと、自分がここにおる以上のリアリティーはあり得んぞ。
そのリアリティーありきで、後は銘々の好きな自分を自己実現するプロセス。
あくまで、飽くまでも、、、いつまで経っても、死ぬ間際まで、そのプロセスの連続でしかない。
誰も分からんし、いかなる存在ですら決定できない、このカオスな宇宙に浮かぶこの星に居させてもらってる。
ここまで掘り下げてくると「いつもいつもありがとうございます!」
としか言えないねよねー。
しつこいようやけど、いくら儲かったから成功という価値観ではない所でいこうぜ。
素の自分の納得度よ。
エクスタシーとでも言おうか!