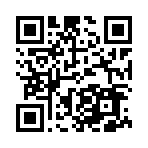2013年07月04日
苗代の田植え
田植えは苗代の小さな田んぼを植えずに終了してた。
苗が足りなくなって。
植え終わった後、近所の人に、「ここは植えんのな?」と聞かれた。
「それが、苗がないんやがな。」と答えると、「ウチの余っとるきん植えな。」という流れで、頂いた。

田植え機用の苗だが、ウチの直前に植え終わり、そこまで徒長してなくてイイ感じの苗。
品種もヒノヒカリなので一緒。

しかもこの苗箱は「ミノル式」の田植え機用のもの。
一本一本が太いので手植えにも向いてる。
今までにも、苗代が失敗したりして箱苗を頂いて植えたことが何度もある。
苗が徒長してようが、黄色くなりかかってて悪かろうが、植えればお米になる。
これが結論。

苗代の田んぼは小さい。
4、50坪ぐらいのもの。
先日の田植え中に親父がトラクターで代掻きはしてた。

定規は使わずにフリー植え。

こんな感じで歪むけど問題ない。
定規を使う最大の理由は田車(除草用)を押すのに困るから。
アレは縦横十文字に押すから列が歪んでると困る。
ウチの場合、ジャンボタニシ除草なので関係ない。
ただ、大きな田んぼは複数で植えるので、何かしらの指針がないと植えづらい。
定規の役割はそれぐらいのもの。

植え終わって水を入れる。
親父と僕、ちびっ子二人の作業。
ならすのに30分、植えるのに2時間といった所。
にこちゃんは一瞬で飽きて止めるけど、土歩はコツコツとやり続けた。
丸一日はまだ無理やけど、このぐらいならいけるみたい。
実は、朝の鶏の世話が終わってなかったので、「先に田んぼ行っとくでー。」とにこちゃんと出かけた。
土歩も「鶏の世話したらすぐに行くわー。」と。
で、親父とにこちゃんと作業してても中々来ない。
後で聞くと、「焼き物作りがしたくなってロクロ引いてた。」と。
最初は、「ええーっ(何でやねん)。」と思ったけど、あっこちゃんに聞くと、「どうしてロクロがしたくなったけど、構んの?」と聞いたよう。
で、一緒にやってたんだと、、、。
「最初はすぐに行く言うたやないか。」
と怒りたくもなるけど、ここで怒鳴ったりすると、彼の心は閉ざしてしまう。
そしてそういう事が繰り返されると、「自分のやりたい事を主張しても無駄だ。」と思わざるを得なくなる。
それを考えると、大人の都合を押し付けたり、こっちの論理に無理やり従わせる訳にはいかない。
よっぽどの状況じゃないと本人の意思を尊重したい。
と思う。
ようにしてる。
しょっちゅう怒鳴って怒るけど、、、。
彼女曰く、「そんなにやりたいんならやった方がええと思って。」と。
たしかに、しばらくして田んぼに来たし、来たら最後までコツコツと作業するし、感心なもの。
夕方も、野遊が帰ってきてから、土歩と僕と3人で晩ご飯作りもした。
田んぼ、畑、薪作り、家の建設、、、。
手伝ってくれて助かるというのは事実。
鶏の世話と風呂焚きは大人は全くタッチしない。
二人で相談して交代でやってるみたい。
でも、一番大事なのは大人の補助になる事ではない。
大人の言うことをよく聞くことでもない。
彼等にとって、ワクワクしてやりたい事が日々実現するということだ!!!
苗が足りなくなって。
植え終わった後、近所の人に、「ここは植えんのな?」と聞かれた。
「それが、苗がないんやがな。」と答えると、「ウチの余っとるきん植えな。」という流れで、頂いた。
田植え機用の苗だが、ウチの直前に植え終わり、そこまで徒長してなくてイイ感じの苗。
品種もヒノヒカリなので一緒。
しかもこの苗箱は「ミノル式」の田植え機用のもの。
一本一本が太いので手植えにも向いてる。
今までにも、苗代が失敗したりして箱苗を頂いて植えたことが何度もある。
苗が徒長してようが、黄色くなりかかってて悪かろうが、植えればお米になる。
これが結論。
苗代の田んぼは小さい。
4、50坪ぐらいのもの。
先日の田植え中に親父がトラクターで代掻きはしてた。
定規は使わずにフリー植え。
こんな感じで歪むけど問題ない。
定規を使う最大の理由は田車(除草用)を押すのに困るから。
アレは縦横十文字に押すから列が歪んでると困る。
ウチの場合、ジャンボタニシ除草なので関係ない。
ただ、大きな田んぼは複数で植えるので、何かしらの指針がないと植えづらい。
定規の役割はそれぐらいのもの。
植え終わって水を入れる。
親父と僕、ちびっ子二人の作業。
ならすのに30分、植えるのに2時間といった所。
にこちゃんは一瞬で飽きて止めるけど、土歩はコツコツとやり続けた。
丸一日はまだ無理やけど、このぐらいならいけるみたい。
実は、朝の鶏の世話が終わってなかったので、「先に田んぼ行っとくでー。」とにこちゃんと出かけた。
土歩も「鶏の世話したらすぐに行くわー。」と。
で、親父とにこちゃんと作業してても中々来ない。
後で聞くと、「焼き物作りがしたくなってロクロ引いてた。」と。
最初は、「ええーっ(何でやねん)。」と思ったけど、あっこちゃんに聞くと、「どうしてロクロがしたくなったけど、構んの?」と聞いたよう。
で、一緒にやってたんだと、、、。
「最初はすぐに行く言うたやないか。」
と怒りたくもなるけど、ここで怒鳴ったりすると、彼の心は閉ざしてしまう。
そしてそういう事が繰り返されると、「自分のやりたい事を主張しても無駄だ。」と思わざるを得なくなる。
それを考えると、大人の都合を押し付けたり、こっちの論理に無理やり従わせる訳にはいかない。
よっぽどの状況じゃないと本人の意思を尊重したい。
と思う。
ようにしてる。
しょっちゅう怒鳴って怒るけど、、、。
彼女曰く、「そんなにやりたいんならやった方がええと思って。」と。
たしかに、しばらくして田んぼに来たし、来たら最後までコツコツと作業するし、感心なもの。
夕方も、野遊が帰ってきてから、土歩と僕と3人で晩ご飯作りもした。
田んぼ、畑、薪作り、家の建設、、、。
手伝ってくれて助かるというのは事実。
鶏の世話と風呂焚きは大人は全くタッチしない。
二人で相談して交代でやってるみたい。
でも、一番大事なのは大人の補助になる事ではない。
大人の言うことをよく聞くことでもない。
彼等にとって、ワクワクしてやりたい事が日々実現するということだ!!!
2013年07月01日
新たな田植えスタイル
田植え3日目。

1歳児も田んぼに慣れてきた。

ええ顔になった。

子どもたちは苗取り作業に大活躍してくれた。
ビワ食べて休憩中。

お昼ごはんは毎日親父のピザ窯の前。
3日目にして、新たな田植えスタイルを開発した。

これは従来のスタイル。
回転式定規を返す労力から解放されたとはいえ、中腰で結構キツイ。

田んぼが固くてそんなにめり込まないので、膝をついてやってるうちに四つん這いになった。
苗の選別も両手でできる。

植えるのも両手で植えられる。
しかも、腰への負担が少なくていい。
こういうのも、その時の状況で柔軟な思いつきで閃く。
そしてそれを実行する。
やってみてまたどんどん改良が加わって発展する。
自分で考えて自分がいいようにする。
これが自由なスタイル。
「〇〇でなくてはならない。」なんてことはないのだ。

夕方早目に一番大きな3枚目の田んぼも終わった。
終わるやいなや夕立ちのような雨が降った。
今年も無事に植えられた。
植えたという事は必ずお米はできる。
水、空気、太陽があれば。
衆院選、アベノミクス、TPP、消費税、原発再稼働、、、。
そんな情勢がどうなろうとも、お米はできるのだ。
そして、お米さえあれば生きていけるという盤石の自信に繋がる。
お米だけじゃない。
自分で医食住、エネルギーを何とかできる。
この自主、自立のライフスタイルを確立すると、政治や経済の情勢にビクつくことはない。
しかし、社会に無関心で自分さえよければいい訳でもない。
こういう生き方こそがこれから必要なのだという発信。
この細々とした動きこそが必要なのだ。
そして、こういう動きが全国各地で同時多発してる。
これが革命だ!!!
とか、能天気にほざいて悦に浸ってるんやから手の施しようがない。
これが敵の存在しない、無敵状態なのだ。
1歳児も田んぼに慣れてきた。
ええ顔になった。
子どもたちは苗取り作業に大活躍してくれた。
ビワ食べて休憩中。
お昼ごはんは毎日親父のピザ窯の前。
3日目にして、新たな田植えスタイルを開発した。
これは従来のスタイル。
回転式定規を返す労力から解放されたとはいえ、中腰で結構キツイ。
田んぼが固くてそんなにめり込まないので、膝をついてやってるうちに四つん這いになった。
苗の選別も両手でできる。
植えるのも両手で植えられる。
しかも、腰への負担が少なくていい。
こういうのも、その時の状況で柔軟な思いつきで閃く。
そしてそれを実行する。
やってみてまたどんどん改良が加わって発展する。
自分で考えて自分がいいようにする。
これが自由なスタイル。
「〇〇でなくてはならない。」なんてことはないのだ。
夕方早目に一番大きな3枚目の田んぼも終わった。
終わるやいなや夕立ちのような雨が降った。
今年も無事に植えられた。
植えたという事は必ずお米はできる。
水、空気、太陽があれば。
衆院選、アベノミクス、TPP、消費税、原発再稼働、、、。
そんな情勢がどうなろうとも、お米はできるのだ。
そして、お米さえあれば生きていけるという盤石の自信に繋がる。
お米だけじゃない。
自分で医食住、エネルギーを何とかできる。
この自主、自立のライフスタイルを確立すると、政治や経済の情勢にビクつくことはない。
しかし、社会に無関心で自分さえよければいい訳でもない。
こういう生き方こそがこれから必要なのだという発信。
この細々とした動きこそが必要なのだ。
そして、こういう動きが全国各地で同時多発してる。
これが革命だ!!!
とか、能天気にほざいて悦に浸ってるんやから手の施しようがない。
これが敵の存在しない、無敵状態なのだ。
2013年06月30日
田んぼマニア
田植え2日目。

朝一番はまず、苗取り。
この苗代の田にも田植えするので、苗を取ってしまわないといけない。
親父がトラクターで耕し始める。

いとこ同士仲良く遊ぶ。

ほどなく2枚目の田んぼが植え終わる。

3枚目の大きな田んぼ。
最も大きな田んぼだった、2反の所に廃材の家を建てたので、この1反4畝のが最大になった。
野遊が活躍する。
一日目に植えられなかったのもあってか、随分大人と一緒に植えた。
にこちゃんは一列ぐらいは植えるけど、すぐ飽きる。
土歩でさえしばらくはやるけど、やっぱり長続きしない。
こういうのは年齢に応じて続くようになってくる。

先に水の溜まってる所に植えて、水を入れながら植える。
ハッキリとマーキングされてる所は水を入れた方が植え易い。
かつて不耕起で植えてたのを思い出すと、いくら乾いても植え易いには違いない。

6時半でもこのぐらい日が高い。
この夕方の静けさの中、延々とやり続けるのがクール。
一日目に来てくれてた妹の雅友達が帰り、2日目はゆかりちゃんのお父さんが来てくれた。
去年も来てくれたけど、「50年ぶりの田植えやー!」と喜んでやってくれる。
超助かる上に、たまに来る客人なので夜の宴会も盛り上がるし。
午前中源がギックリ腰になったり、トラクターが溝にハマったり、というトラブルもあった。
ギックリ腰は安静にするのが一番やし、トラクターは廃材の家のタイヤショベルでひっぱし出した。
こういうトラブルは想定内。
何かあり得ない事が起きて田植えが続行出来ないなんてことはない。
少々のトラブルが起ころうとも、やり続けると終わる。
それが手作業だ。
そういう意味ではトラクターが壊れたら出来ないという事もない。
そうなればいよいよ不耕起だ。
以前不耕起で一反植えた時には3~4人で4日間かかった。
一人でやった時には10日ぐらいかかったこともあった。
それで何か問題があったか?
何もない。
少々時間がかかろうとも、その作業で一年分のお米が自給できるのだ。
その重要性からすれば3日の田植えが10日や2週間になろうとも問題ではない。
何より、これを最優先できる生活や仕事の環境をバッチリ整えてるし。
この時間の余裕。
これが自給自足なり、廃材生活における魅力であり、大前提なのだ。
時間は万人に等しく与えられてる。
それを各人の選択と判断によって使ってるのだ。
この社会でみんながみんな自給自足だ、自由な生活だとうつつを抜かすのが無理なのも理解できる。
ただ、その時間の使い道が自分の納得のいくものであればOK。
嫌々やってる
させられてる
しゃあなしになってる
これらはブッブー(ドクロマーク)。
そうせざるを得ないなんてことは断じてないぞ。
必ず自分の意思でやってるのだ。
ごまかすな。
先延ばしにするな。
その意思をハッキリせよ!
朝一番はまず、苗取り。
この苗代の田にも田植えするので、苗を取ってしまわないといけない。
親父がトラクターで耕し始める。
いとこ同士仲良く遊ぶ。
ほどなく2枚目の田んぼが植え終わる。
3枚目の大きな田んぼ。
最も大きな田んぼだった、2反の所に廃材の家を建てたので、この1反4畝のが最大になった。
野遊が活躍する。
一日目に植えられなかったのもあってか、随分大人と一緒に植えた。
にこちゃんは一列ぐらいは植えるけど、すぐ飽きる。
土歩でさえしばらくはやるけど、やっぱり長続きしない。
こういうのは年齢に応じて続くようになってくる。
先に水の溜まってる所に植えて、水を入れながら植える。
ハッキリとマーキングされてる所は水を入れた方が植え易い。
かつて不耕起で植えてたのを思い出すと、いくら乾いても植え易いには違いない。
6時半でもこのぐらい日が高い。
この夕方の静けさの中、延々とやり続けるのがクール。
一日目に来てくれてた妹の雅友達が帰り、2日目はゆかりちゃんのお父さんが来てくれた。
去年も来てくれたけど、「50年ぶりの田植えやー!」と喜んでやってくれる。
超助かる上に、たまに来る客人なので夜の宴会も盛り上がるし。
午前中源がギックリ腰になったり、トラクターが溝にハマったり、というトラブルもあった。
ギックリ腰は安静にするのが一番やし、トラクターは廃材の家のタイヤショベルでひっぱし出した。
こういうトラブルは想定内。
何かあり得ない事が起きて田植えが続行出来ないなんてことはない。
少々のトラブルが起ころうとも、やり続けると終わる。
それが手作業だ。
そういう意味ではトラクターが壊れたら出来ないという事もない。
そうなればいよいよ不耕起だ。
以前不耕起で一反植えた時には3~4人で4日間かかった。
一人でやった時には10日ぐらいかかったこともあった。
それで何か問題があったか?
何もない。
少々時間がかかろうとも、その作業で一年分のお米が自給できるのだ。
その重要性からすれば3日の田植えが10日や2週間になろうとも問題ではない。
何より、これを最優先できる生活や仕事の環境をバッチリ整えてるし。
この時間の余裕。
これが自給自足なり、廃材生活における魅力であり、大前提なのだ。
時間は万人に等しく与えられてる。
それを各人の選択と判断によって使ってるのだ。
この社会でみんながみんな自給自足だ、自由な生活だとうつつを抜かすのが無理なのも理解できる。
ただ、その時間の使い道が自分の納得のいくものであればOK。
嫌々やってる
させられてる
しゃあなしになってる
これらはブッブー(ドクロマーク)。
そうせざるを得ないなんてことは断じてないぞ。
必ず自分の意思でやってるのだ。
ごまかすな。
先延ばしにするな。
その意思をハッキリせよ!
2013年06月29日
自分労働
28日から植え始める。

六角定規で碁盤の目にマーキングが出来てるので、各自自分のペースで植えられる。

子どもたちも張り切って植える。

こんな風にペースが違っても、回転式の定規のように待たなくていいのがいい。

一枚植え終わって水を入れる。
苗が大きくてしっかりしてる。

二枚目の田んぼもメイメイ好きなところから植えられる。
僕は昨日も一日中六角定規を回してた。
ずっとやってると結構きつい。
それでも、一日半で3反全てにマーキングできたので、後は植えるだけ。

こういう超ガッシリした苗。
籾蒔きも田植えも去年とほぼ一緒なのに苗の生育が全然違った。
こういうのは気候の問題やろね。
去年までの回転式定規でワイワイ言いながらも楽しいけど、今年の「自分のペースで出来る」というのはほんとにいい。
泥の中を歩いて苗を一本ずつ取り、植えていく。
延々とこの繰り返し。
回りの時間が止まったかのような自分だけの時間。
自分の中は平穏な空気で満たされる。
陶芸のロクロ作業、菜園の草取り作業、井戸掘り、ハツリ作業、薪割り、、、。
全ての作業に共通するのは「自分のペース」。
「一日でよりたくさんの労働をこなそう。」というのが折角の美しい労働を台無しにする。
量より質なのだ。
しかし!
ゆっくり、のんびり、ダラダラ、とやってても楽しくならない。
自分がノッてくる、ワクワクするペースというものがある。
アドレナリンかベータエンドルフィンか分らんけど、やってるうちにハイになる。
これが「自分のペース」なのだ。
気がついて顔を上げると、「おおーー、こんなに植えたんか!」と感慨深い。
上質の労働。
それは自分自身にしか分からない。
「はよせな!」
「こんなんじゃダメだ!」
「もっと、もっと!」
という、させられる労働から、自分主体の労働。
一人で静かに黙々と続けるそれは極めて心地の良いもの。
自分の内面に入るちょっとした旅でもある。
そこで起こるあらゆる事象に対する自分の気持ちの変化で、自分の状態が丸分かりになるとも言える。
「失敗したー!」
とかで、イラついてるうちはまだまだ。
そのうち何が起こっても、クヨクヨ考えたり、イライラしたりしなくなる。
これがシャンティーでクールな「自分労働」なのだ。
六角定規で碁盤の目にマーキングが出来てるので、各自自分のペースで植えられる。
子どもたちも張り切って植える。
こんな風にペースが違っても、回転式の定規のように待たなくていいのがいい。
一枚植え終わって水を入れる。
苗が大きくてしっかりしてる。
二枚目の田んぼもメイメイ好きなところから植えられる。
僕は昨日も一日中六角定規を回してた。
ずっとやってると結構きつい。
それでも、一日半で3反全てにマーキングできたので、後は植えるだけ。
こういう超ガッシリした苗。
籾蒔きも田植えも去年とほぼ一緒なのに苗の生育が全然違った。
こういうのは気候の問題やろね。
去年までの回転式定規でワイワイ言いながらも楽しいけど、今年の「自分のペースで出来る」というのはほんとにいい。
泥の中を歩いて苗を一本ずつ取り、植えていく。
延々とこの繰り返し。
回りの時間が止まったかのような自分だけの時間。
自分の中は平穏な空気で満たされる。
陶芸のロクロ作業、菜園の草取り作業、井戸掘り、ハツリ作業、薪割り、、、。
全ての作業に共通するのは「自分のペース」。
「一日でよりたくさんの労働をこなそう。」というのが折角の美しい労働を台無しにする。
量より質なのだ。
しかし!
ゆっくり、のんびり、ダラダラ、とやってても楽しくならない。
自分がノッてくる、ワクワクするペースというものがある。
アドレナリンかベータエンドルフィンか分らんけど、やってるうちにハイになる。
これが「自分のペース」なのだ。
気がついて顔を上げると、「おおーー、こんなに植えたんか!」と感慨深い。
上質の労働。
それは自分自身にしか分からない。
「はよせな!」
「こんなんじゃダメだ!」
「もっと、もっと!」
という、させられる労働から、自分主体の労働。
一人で静かに黙々と続けるそれは極めて心地の良いもの。
自分の内面に入るちょっとした旅でもある。
そこで起こるあらゆる事象に対する自分の気持ちの変化で、自分の状態が丸分かりになるとも言える。
「失敗したー!」
とかで、イラついてるうちはまだまだ。
そのうち何が起こっても、クヨクヨ考えたり、イライラしたりしなくなる。
これがシャンティーでクールな「自分労働」なのだ。
2013年06月28日
六角定規始動
さあ、いよいよ田植えだ。

弟の源や妹の雅が参加するのは28日からなので、27日に六角定規を始動させてみた。

こんだけマーキングできれば十分に分かる。

とりあえず田んぼ一枚やってみた。

これが去年までの定規。
この辺りでは昔からこのスタイル。
今までの定規の「くるっと回転させる動作」と「横の人に合わせる」というこの二つから解放される。
しかも、植える動きが「バックから前進に変わる」。
この3点はかなり大きな変化。
毎年手植えで田植えをしてる者としては、革新的に楽になると確信する。
六角定規での印の付き具合も使ってみて上手くいくことが分かったし。

苗取り作業も並行して始める。
今年の苗は全部と言っていいぐらい分ケツが進み、巨大サイズになった。
このメリットはジャンボタニシに食害されないという所。
ウチの田んぼには10年近く前からジャンボタニシが繁殖するようになり、みんな苗の食害に悩まされている。
機械植えの苗は小さい。
それで水が深いと水面がらいくらも出ない。
その部分を食われる。
このような立派な苗だと食べられようがない。
こういう安心があると、ジャンボタニシは除草作業の有力選手として最高なのだ。
実際に、ウチの田には除草作業ナシでヒエ一本生えない。
無農薬と化学肥料ナシは割と簡単。
止めればいいだけ。
でも、草だけは稲よりほこると大変。
除草剤不使用が簡単に実現するのは非常に助かる。

親父とお袋、にこちゃんが担当。
今日から植え始める。
2、3日やってるので県内の人でやってみたい人は来てね。
弟の源や妹の雅が参加するのは28日からなので、27日に六角定規を始動させてみた。
こんだけマーキングできれば十分に分かる。
とりあえず田んぼ一枚やってみた。
これが去年までの定規。
この辺りでは昔からこのスタイル。
今までの定規の「くるっと回転させる動作」と「横の人に合わせる」というこの二つから解放される。
しかも、植える動きが「バックから前進に変わる」。
この3点はかなり大きな変化。
毎年手植えで田植えをしてる者としては、革新的に楽になると確信する。
六角定規での印の付き具合も使ってみて上手くいくことが分かったし。
苗取り作業も並行して始める。
今年の苗は全部と言っていいぐらい分ケツが進み、巨大サイズになった。
このメリットはジャンボタニシに食害されないという所。
ウチの田んぼには10年近く前からジャンボタニシが繁殖するようになり、みんな苗の食害に悩まされている。
機械植えの苗は小さい。
それで水が深いと水面がらいくらも出ない。
その部分を食われる。
このような立派な苗だと食べられようがない。
こういう安心があると、ジャンボタニシは除草作業の有力選手として最高なのだ。
実際に、ウチの田には除草作業ナシでヒエ一本生えない。
無農薬と化学肥料ナシは割と簡単。
止めればいいだけ。
でも、草だけは稲よりほこると大変。
除草剤不使用が簡単に実現するのは非常に助かる。
親父とお袋、にこちゃんが担当。
今日から植え始める。
2、3日やってるので県内の人でやってみたい人は来てね。
2013年06月25日
ワクワクの田んぼが始まる
田植えが近付いてきた。
6/28(金)から植え始める。
参加者が多くなると、2日で終わる。
家族だけでやっても3日ぐらいのもの。
おじいちゃんが元気な頃は6反ぐらい作って出荷してた。
今は家族が食べるだけなので、水の管理のしやすい条件のいい田んぼ3反(約1000坪)だけに減らしてる。
このぐらいなら手植えでしても途方もない作業という感じじゃなく、手軽に取り組める。
食べる人数が総員で作業するなら、お米の自給ぐらい効率のいいものはない。
数人で植えれば1反を一日で植えるのは何でもない労働。
というか年に一度のレジャーみたいなもん。
実際に田植えって、一大イベントやし。

親父がトラクターで代掻きした後、高い部分をならす作業。
田んぼに入るだけで楽しいのは大人も子どもも一緒。

どうしてもこういう隅っこの部分が高くなる。

水が入ってるので、簡単に寄せられる。
特に今年は新調した自作六角定規の使い方が未知数。
やはり、フラットな田んぼに浅水というのが理想やと思う。
高い所や深い所があると、うまく定規の印がつかないといけないので、丁寧にならした。

苗代の苗もバッチリ成長した。

田植え機用の箱苗とは完全に別モノ。
大きい所は30㎝にも及ぶ立派な苗。
既に分ケツが始まってる。
初心者が手伝うと、たまに稲と草の区別がつかずに間違える事がある。
上の写真の部分は稲ばかりやから分りやすい。
野遊なんか、金曜日は学校があるから、「うわー、残念やー!」と言うてるぐらい。
「土日があるやないか。」と言うと、「よっしゃーーー!」と張り切ってる。
行ってない土歩とにこちゃんは昨日の作業だけでもかなりテンション上ってた。
僕もやっぱり楽しみ。
これはねー。
瑞穂の国の農耕民のDNAに入ってるとしか言えない。
このお米を毎食食べるのはもちろん。
麹に加工して、発酵させて味噌、お酒にする。
あっこスイーツの素、甘酒は昔は夏の飲み物だったそう。
お米が発酵したエキスでもある甘酒は、「飲む点滴」というぐらい夏の厳しさにもってこい。
お米=日本人
折角なら、食べるだけじゃなく、労働も込みで味わうのが醍醐味というもの。
「労働が大変」というのも一種の洗脳なんちゃうの?
そこにはテレビ、新聞、学校、会社と社会ぐるみでの情報操作がある。
「させられる労働」は確かに大変。
それと混同してはいけない。
「手軽で簡単労力要らず」
「ボタン一つでほっとくだけ」
「買ったほうが安い」
これらは完全に洗脳プログラムの一環だぞ。
自分の食べるお米を作る。
自分の使う薪を作る。
自分の住む家を建てる。
家族の食べる料理を作る。
こういう事にまつわる労働は本来ワクワクする作業なのだ。
実は自由な時間があればみんなやりたい事。
だからウチがテレビに出されたり、ダッシュ村が流行ったりする。
ここの順番が大事。
「自由な時間が出来てから出来る。」のではないぞ。
「田んぼして、家作って、手作り生活を実践する。」から自由になれるのだ!
ここキーポイントね!!
6/28(金)から植え始める。
参加者が多くなると、2日で終わる。
家族だけでやっても3日ぐらいのもの。
おじいちゃんが元気な頃は6反ぐらい作って出荷してた。
今は家族が食べるだけなので、水の管理のしやすい条件のいい田んぼ3反(約1000坪)だけに減らしてる。
このぐらいなら手植えでしても途方もない作業という感じじゃなく、手軽に取り組める。
食べる人数が総員で作業するなら、お米の自給ぐらい効率のいいものはない。
数人で植えれば1反を一日で植えるのは何でもない労働。
というか年に一度のレジャーみたいなもん。
実際に田植えって、一大イベントやし。
親父がトラクターで代掻きした後、高い部分をならす作業。
田んぼに入るだけで楽しいのは大人も子どもも一緒。
どうしてもこういう隅っこの部分が高くなる。
水が入ってるので、簡単に寄せられる。
特に今年は新調した自作六角定規の使い方が未知数。
やはり、フラットな田んぼに浅水というのが理想やと思う。
高い所や深い所があると、うまく定規の印がつかないといけないので、丁寧にならした。
苗代の苗もバッチリ成長した。
田植え機用の箱苗とは完全に別モノ。
大きい所は30㎝にも及ぶ立派な苗。
既に分ケツが始まってる。
初心者が手伝うと、たまに稲と草の区別がつかずに間違える事がある。
上の写真の部分は稲ばかりやから分りやすい。
野遊なんか、金曜日は学校があるから、「うわー、残念やー!」と言うてるぐらい。
「土日があるやないか。」と言うと、「よっしゃーーー!」と張り切ってる。
行ってない土歩とにこちゃんは昨日の作業だけでもかなりテンション上ってた。
僕もやっぱり楽しみ。
これはねー。
瑞穂の国の農耕民のDNAに入ってるとしか言えない。
このお米を毎食食べるのはもちろん。
麹に加工して、発酵させて味噌、お酒にする。
あっこスイーツの素、甘酒は昔は夏の飲み物だったそう。
お米が発酵したエキスでもある甘酒は、「飲む点滴」というぐらい夏の厳しさにもってこい。
お米=日本人
折角なら、食べるだけじゃなく、労働も込みで味わうのが醍醐味というもの。
「労働が大変」というのも一種の洗脳なんちゃうの?
そこにはテレビ、新聞、学校、会社と社会ぐるみでの情報操作がある。
「させられる労働」は確かに大変。
それと混同してはいけない。
「手軽で簡単労力要らず」
「ボタン一つでほっとくだけ」
「買ったほうが安い」
これらは完全に洗脳プログラムの一環だぞ。
自分の食べるお米を作る。
自分の使う薪を作る。
自分の住む家を建てる。
家族の食べる料理を作る。
こういう事にまつわる労働は本来ワクワクする作業なのだ。
実は自由な時間があればみんなやりたい事。
だからウチがテレビに出されたり、ダッシュ村が流行ったりする。
ここの順番が大事。
「自由な時間が出来てから出来る。」のではないぞ。
「田んぼして、家作って、手作り生活を実践する。」から自由になれるのだ!
ここキーポイントね!!
2013年06月14日
六角定規
京都の北の方で自給生活を送る妹の雅からの情報。
「六角形の田植え定規があるんやて。」

ウチでは、この辺りの伝統的な定規を使って植えてる。

こんな感じで、定規の部分を植え終わると、くるっと手前に回転させる。
で、バックして植えてゆく。
これを延々と続けてると、定規の奥に手を伸ばしてて、手前に持ってくるのがおっくうになってくる。
特に小さな女性などは大変。
この労のないのが六角定規だそうな。
田んぼを浅水にしておいて、先にゴロゴロと定規を回してマーキングしておく。
そして、それぞれが前進で植えてゆく。
横の定規の人とのタイミングを計るというのも実は大変なことの一つ。
速く植える人は隣を待たないといけないし、遅い人は焦るハメになる。
これも解消されるんなら言うことない。
「六角 田植え定規」で調べると色々出てきた。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%85%AD%E8%A7%92%E3%80%80%E7%94%B0%E6%A4%8D%E3%81%88%E5%AE%9A%E8%A6%8F&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gUy6UfytHIWokQW4yoH4DQ&sqi=2&ved=0CDgQsAQ&biw=1120&bih=611#imgrc=_
是非、今年の田植えまでに作ろう!
でも、細い木を組み合わせるのはめんどくさそう。

で、廃材鉄工で作ることにした。
ネタはストックしてるのがあった。
まずは細い部材にバラす。

予め、図面や作り方を熟慮するのがキライなので、いきなり作りはじめる。
正三角形を繋げていけば正六角形になるやろ。
ということで、今までの定規の印の間を計ると、9寸(約27㎝)だったので、27㎝の部品をたくさん作る。

案の定六角形になった。
これを3つ作った。

起こして、六角柱にする。

間のラインを入れて、更に奥へと延ばす。

全てのラインを入れ終えた。
まだ、写真で見たのよりも短い。
後、一コマづつ両サイドに広げよう。

あっこちゃんは梅の作業。
大きさや熟れ具合によって分類する。

黄色くなってるものを先に塩漬けにする。

ラッキョウの皮をむく作業も延々と根気のいる仕事。
梅干しの漬け方も毎年経験値が上がり、微妙なところまで気を使えるようになってくる。
梅干しにしろ、田植えにしろ、年に一回の作業。
その作業の中のあらゆる事に対応する。
それは繰り返しの実践しかない。
自分の中では進化してるようでも、ベテランの古老からすれば、「まだそんなことも分かっとらんのか!」と叱咤されそう、、、。
要らんものを開発する「進歩、発展」とこういう農や手作りのスキルは同じ土俵では比べられない。
季節は巡り、命も巡る。
その大いなる循環の中の一コマが、ちっぽけな我人生。
我々はどこへ向かうのだ?
少なくとも、いくら科学が発達しようとも、「自然のメカニズムが解明出来ないという事が分かってきた。」というレベル。
籾の中の遺伝子いじって、食糧危機が救えるかよ!
ママゴトとしては面白いと思うけど、、、。
田んぼをする。
梅干しを漬ける。
これらは生きる上での最重要項目に位置づけられる。
自分の時間の中でこういう実践が増えてくることを「ダイレクトに生きる」と言うのだよ。
「六角形の田植え定規があるんやて。」
ウチでは、この辺りの伝統的な定規を使って植えてる。
こんな感じで、定規の部分を植え終わると、くるっと手前に回転させる。
で、バックして植えてゆく。
これを延々と続けてると、定規の奥に手を伸ばしてて、手前に持ってくるのがおっくうになってくる。
特に小さな女性などは大変。
この労のないのが六角定規だそうな。
田んぼを浅水にしておいて、先にゴロゴロと定規を回してマーキングしておく。
そして、それぞれが前進で植えてゆく。
横の定規の人とのタイミングを計るというのも実は大変なことの一つ。
速く植える人は隣を待たないといけないし、遅い人は焦るハメになる。
これも解消されるんなら言うことない。
「六角 田植え定規」で調べると色々出てきた。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%85%AD%E8%A7%92%E3%80%80%E7%94%B0%E6%A4%8D%E3%81%88%E5%AE%9A%E8%A6%8F&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gUy6UfytHIWokQW4yoH4DQ&sqi=2&ved=0CDgQsAQ&biw=1120&bih=611#imgrc=_
是非、今年の田植えまでに作ろう!
でも、細い木を組み合わせるのはめんどくさそう。
で、廃材鉄工で作ることにした。
ネタはストックしてるのがあった。
まずは細い部材にバラす。
予め、図面や作り方を熟慮するのがキライなので、いきなり作りはじめる。
正三角形を繋げていけば正六角形になるやろ。
ということで、今までの定規の印の間を計ると、9寸(約27㎝)だったので、27㎝の部品をたくさん作る。
案の定六角形になった。
これを3つ作った。
起こして、六角柱にする。
間のラインを入れて、更に奥へと延ばす。
全てのラインを入れ終えた。
まだ、写真で見たのよりも短い。
後、一コマづつ両サイドに広げよう。
あっこちゃんは梅の作業。
大きさや熟れ具合によって分類する。
黄色くなってるものを先に塩漬けにする。
ラッキョウの皮をむく作業も延々と根気のいる仕事。
梅干しの漬け方も毎年経験値が上がり、微妙なところまで気を使えるようになってくる。
梅干しにしろ、田植えにしろ、年に一回の作業。
その作業の中のあらゆる事に対応する。
それは繰り返しの実践しかない。
自分の中では進化してるようでも、ベテランの古老からすれば、「まだそんなことも分かっとらんのか!」と叱咤されそう、、、。
要らんものを開発する「進歩、発展」とこういう農や手作りのスキルは同じ土俵では比べられない。
季節は巡り、命も巡る。
その大いなる循環の中の一コマが、ちっぽけな我人生。
我々はどこへ向かうのだ?
少なくとも、いくら科学が発達しようとも、「自然のメカニズムが解明出来ないという事が分かってきた。」というレベル。
籾の中の遺伝子いじって、食糧危機が救えるかよ!
ママゴトとしては面白いと思うけど、、、。
田んぼをする。
梅干しを漬ける。
これらは生きる上での最重要項目に位置づけられる。
自分の時間の中でこういう実践が増えてくることを「ダイレクトに生きる」と言うのだよ。
2013年06月10日
苗成育中
空梅雨で田んぼの水が心配。
何せ、日本一雨が少なく、ため池の多い香川。
もっとも、ここ丸亀は徳島から引いてる香川用水に頼らなくとも地下水もある。

苗も順調に育って来てる。

このぐらいあれば3反分は十分。
自分たち家族が食べる分を作るのは簡単。
農業じゃなく、家庭菜園みたいなもの。
「〇〇業」にしてしまうと、効率化のために機械に投資してみたり、収支計算して、やれ合う合わないとイチイチうるさくってしかたない。
これは農だけに限った話じゃなく、仕事全般について当てはまる。
一見、効率や採算を度外視してても、経営と生活が成り立っていけば問題ない。
ウチの生活がその最たるものだ。
何年かかろうが、オール廃材で家を作り、何でも廃材利用で生活できるスキルを身につけた。

未だに絞れてないダイダイがあったので、子どもたちに絞ってもらった。
「早よしとかなー。」という作業で出来てない事って結構ある。
何を優先させるか?
この優先順位が自分の生活の価値観。
価値観の細分化と言われて久しい。
何を大事にするのか?
ちゃんと自分自身に向き合え。
あいまいに流されるな。

ギリギリセーフというか、少し水分が減ってきてたけど、何とかダイダイ酢が採れた。
冷蔵保存して、ポン酢にする。
次のスダチが出来るまで持ってくれるか?
数種類の柑橘酢、米酢、梅酢、柿酢、バルサミコ酢とあわゆる酢があることで料理のバリエーションが増える。
昨日は月に一度のオーガニックマルシェ。
あっこちゃんと子どもたちが出店してた。
帰りに弟の源とゆかりちゃんが寄ってくれた。

これは琵琶仁豆腐。
杏仁豆腐ならぬ、琵琶の種と琵琶の実で作ってる。
ゆかりちゃんのマニアックさは深く、コンセプトや見た目が先行しがち。
でも、これはちゃんと美味しかったので、更に凄い!

甘酒餡の蒸しパン。
酒粕のカレー餡もあって、どっちも美味しかった。

スコーンはキウイ、バナナ、いちご。
それぞれ、粉と果物と塩、油、アルミフリーのベーキングパウダーというシンプルな材料。
あっこちゃんのマニアぶりとはまた違うけど、ゆかりちゃんも凄い。
出店の残りものと、ウチの家の残り物でプチパーティーとなった。
お互いに食べながら、作り方や味の意見交換は実に意義深い。
手作りマニアに行き着くゴールはない。
その季節に採れる材料、もらったものがあれば、いくらでも作り、研究を続ける。
自分の嗜好性を知れば迷わずに進める。
「あるもんで」から直観的に閃く、即興建築と、直観料理は非常に通じる部分がある。
何せ、日本一雨が少なく、ため池の多い香川。
もっとも、ここ丸亀は徳島から引いてる香川用水に頼らなくとも地下水もある。
苗も順調に育って来てる。
このぐらいあれば3反分は十分。
自分たち家族が食べる分を作るのは簡単。
農業じゃなく、家庭菜園みたいなもの。
「〇〇業」にしてしまうと、効率化のために機械に投資してみたり、収支計算して、やれ合う合わないとイチイチうるさくってしかたない。
これは農だけに限った話じゃなく、仕事全般について当てはまる。
一見、効率や採算を度外視してても、経営と生活が成り立っていけば問題ない。
ウチの生活がその最たるものだ。
何年かかろうが、オール廃材で家を作り、何でも廃材利用で生活できるスキルを身につけた。
未だに絞れてないダイダイがあったので、子どもたちに絞ってもらった。
「早よしとかなー。」という作業で出来てない事って結構ある。
何を優先させるか?
この優先順位が自分の生活の価値観。
価値観の細分化と言われて久しい。
何を大事にするのか?
ちゃんと自分自身に向き合え。
あいまいに流されるな。
ギリギリセーフというか、少し水分が減ってきてたけど、何とかダイダイ酢が採れた。
冷蔵保存して、ポン酢にする。
次のスダチが出来るまで持ってくれるか?
数種類の柑橘酢、米酢、梅酢、柿酢、バルサミコ酢とあわゆる酢があることで料理のバリエーションが増える。
昨日は月に一度のオーガニックマルシェ。
あっこちゃんと子どもたちが出店してた。
帰りに弟の源とゆかりちゃんが寄ってくれた。
これは琵琶仁豆腐。
杏仁豆腐ならぬ、琵琶の種と琵琶の実で作ってる。
ゆかりちゃんのマニアックさは深く、コンセプトや見た目が先行しがち。
でも、これはちゃんと美味しかったので、更に凄い!
甘酒餡の蒸しパン。
酒粕のカレー餡もあって、どっちも美味しかった。
スコーンはキウイ、バナナ、いちご。
それぞれ、粉と果物と塩、油、アルミフリーのベーキングパウダーというシンプルな材料。
あっこちゃんのマニアぶりとはまた違うけど、ゆかりちゃんも凄い。
出店の残りものと、ウチの家の残り物でプチパーティーとなった。
お互いに食べながら、作り方や味の意見交換は実に意義深い。
手作りマニアに行き着くゴールはない。
その季節に採れる材料、もらったものがあれば、いくらでも作り、研究を続ける。
自分の嗜好性を知れば迷わずに進める。
「あるもんで」から直観的に閃く、即興建築と、直観料理は非常に通じる部分がある。
2013年05月18日
苗代
田んぼの季節が来た!

苗代の準備。
トラクターで耕し、苗床を作る。

大体水平になったら、先にスズメ除けの網を張るための枠を作る。
細い廃材をインパクトでビス留めして簡単に作る。

籾は去年の脱穀作業の時に取ってある。
1週間近く浸水して芽出ししておく。

籾はテキトーに苗代に振りまいていく。
田植え機用の箱苗からすれば驚くほど粗く蒔く。
粗い程苗が良く育つ、でも粗すぎて草がはびこっても苗取り作業が大変になる。

籾を蒔いた後、網を張る。
これで3反分(約900坪)の苗代。

早朝の田んぼは気持ちがいい。
数日間は薄く水を張って、しっかり芽が出たら水を畝間だけにする。
このやり方は6年前から。
3反の田んぼを無農薬、無肥料、除草剤なしでやり始めてから。
それまではこの3反はおじいちゃんが仕切ってた。
いわゆる化学肥料、農薬、除草剤の慣行農法で。
それはそれで手伝いながら、別に5畝(約150坪)の田んぼで不耕起でやってた。
化学肥料や農薬の害を知ったばかりの頃はおじいちゃんとぶつかったりもした。
でも、経験のない若者が知識や理論だけで、何十年と実践してきた人間と対等にぶつかれる訳もない。
おじいちゃんの田んぼを手伝いながら、小さな田んぼで不耕起を実験的に始めてからも、大事な抑えどころはほとんどおじいちゃんが教えてくれた。
化学肥料や農薬の有無よりもココを抑えないと稲は育たないというレッキとした幹がある。
ソコを抜きにした農薬云々の議論は不毛だ。
実践なき議論そのものがグロテスクだぞ。
今はトラクターで代かきして、30㎝ぐらいになったしっかりした苗を手植えする。
トラクターは親父の担当、壊れたら3反全部を不耕起にしようと思ってる。
一人で不耕起なら1反ぐらいなら余裕を持ってできる。
3反になると、大勢でかかった方がいい。
ウチは親父、お袋、僕ら夫婦、弟夫婦、それに子どもたち。
例年やらせて欲しいという飛び入りの参加者が加わり、大勢になる。
飛び入り者は労働力をしてアテにしてはいない。
基本は大家族で十分できる。
「田んぼの作業が手伝いたいです~。」という手伝う代わりに居候させて欲しいという奴が現れる時期。
ここで書いておくとハッキリする。
中途半端な居候は受け付けない!
田植えだけ通って参加したいとかはok。
苗代の準備。
トラクターで耕し、苗床を作る。
大体水平になったら、先にスズメ除けの網を張るための枠を作る。
細い廃材をインパクトでビス留めして簡単に作る。
籾は去年の脱穀作業の時に取ってある。
1週間近く浸水して芽出ししておく。
籾はテキトーに苗代に振りまいていく。
田植え機用の箱苗からすれば驚くほど粗く蒔く。
粗い程苗が良く育つ、でも粗すぎて草がはびこっても苗取り作業が大変になる。
籾を蒔いた後、網を張る。
これで3反分(約900坪)の苗代。
早朝の田んぼは気持ちがいい。
数日間は薄く水を張って、しっかり芽が出たら水を畝間だけにする。
このやり方は6年前から。
3反の田んぼを無農薬、無肥料、除草剤なしでやり始めてから。
それまではこの3反はおじいちゃんが仕切ってた。
いわゆる化学肥料、農薬、除草剤の慣行農法で。
それはそれで手伝いながら、別に5畝(約150坪)の田んぼで不耕起でやってた。
化学肥料や農薬の害を知ったばかりの頃はおじいちゃんとぶつかったりもした。
でも、経験のない若者が知識や理論だけで、何十年と実践してきた人間と対等にぶつかれる訳もない。
おじいちゃんの田んぼを手伝いながら、小さな田んぼで不耕起を実験的に始めてからも、大事な抑えどころはほとんどおじいちゃんが教えてくれた。
化学肥料や農薬の有無よりもココを抑えないと稲は育たないというレッキとした幹がある。
ソコを抜きにした農薬云々の議論は不毛だ。
実践なき議論そのものがグロテスクだぞ。
今はトラクターで代かきして、30㎝ぐらいになったしっかりした苗を手植えする。
トラクターは親父の担当、壊れたら3反全部を不耕起にしようと思ってる。
一人で不耕起なら1反ぐらいなら余裕を持ってできる。
3反になると、大勢でかかった方がいい。
ウチは親父、お袋、僕ら夫婦、弟夫婦、それに子どもたち。
例年やらせて欲しいという飛び入りの参加者が加わり、大勢になる。
飛び入り者は労働力をしてアテにしてはいない。
基本は大家族で十分できる。
「田んぼの作業が手伝いたいです~。」という手伝う代わりに居候させて欲しいという奴が現れる時期。
ここで書いておくとハッキリする。
中途半端な居候は受け付けない!
田植えだけ通って参加したいとかはok。
2013年03月19日
果樹の苗
畑ではほとんどの野菜がトウ立ちを始めた。
アブラナ科系の葉物は全部菜花としてジャンジャン採っては食べてる。

金時人参も固くなりつつあるんで、一気に収穫。
土歩が丁寧に洗ってくれる。

何クールも干しまくってる切干し大根は完成したらふくろに詰めて保存。
これも土歩がやってくれた。
ほんとに助かる。
今のウチに食べるのはいいけど、梅雨前には冷蔵庫に入れないと黒くなって不味くなる。
冷蔵庫が占有されるのはいけないので、それまでに食べるのが一番。

果樹の苗を買ってきた。
苗屋の果樹のコーナー見てるだけで、「アレもいいし、コレも植えようか。」と幸せな時間を過ごせる。

レモン。
一度植えてたけど、アゲハの幼虫に食い荒らされて枯れたので再度植えた。

マスカット。

巨峰。
ブドウは前々から植えたいと思ってた。
この2本はキッチンのすぐ前の井戸の脇に植えた。
で、キッチンの前にポリカの屋根を作って雨除け栽培する計画。

ライム。
夏にボンベイサファイヤでジンライムを飲めるのが楽しみ。

木頭ゆず。
本当はレモンとブドウを買う計画だった。
ライムとゆずは半額セールだったんで、つい買ってしまった。
柑橘系はそれぞれ香りが違うので、何種類あっても悪くない。

果樹の苗を植えようと、鉄のゴミの片付けを始めたらすぐに軽トラ一車分できた。
苗を植えるよりも、ゴミの片付けにスイッチが入ってしばらくやってた。
廃材生活においては、ちょこちょこっと片付けるとこうなる。
鉄のゴミはスクラップ屋に売りに行けるのが魅力。
コンクリートガラやプラスチックなども、何をどこに持っていけばいいかを把握しとかないと、イチイチ処分代がカサム。

同級生がコールラビとワサビ菜を持ってきてくれた。
キャベツの仲間で芯を食べるための野菜。
土筆の甘酢漬けの酢にオリーブオイルを混ぜてドレッシングにしたそうな。
アブラナ科系の葉物は全部菜花としてジャンジャン採っては食べてる。
金時人参も固くなりつつあるんで、一気に収穫。
土歩が丁寧に洗ってくれる。
何クールも干しまくってる切干し大根は完成したらふくろに詰めて保存。
これも土歩がやってくれた。
ほんとに助かる。
今のウチに食べるのはいいけど、梅雨前には冷蔵庫に入れないと黒くなって不味くなる。
冷蔵庫が占有されるのはいけないので、それまでに食べるのが一番。
果樹の苗を買ってきた。
苗屋の果樹のコーナー見てるだけで、「アレもいいし、コレも植えようか。」と幸せな時間を過ごせる。
レモン。
一度植えてたけど、アゲハの幼虫に食い荒らされて枯れたので再度植えた。
マスカット。
巨峰。
ブドウは前々から植えたいと思ってた。
この2本はキッチンのすぐ前の井戸の脇に植えた。
で、キッチンの前にポリカの屋根を作って雨除け栽培する計画。
ライム。
夏にボンベイサファイヤでジンライムを飲めるのが楽しみ。
木頭ゆず。
本当はレモンとブドウを買う計画だった。
ライムとゆずは半額セールだったんで、つい買ってしまった。
柑橘系はそれぞれ香りが違うので、何種類あっても悪くない。
果樹の苗を植えようと、鉄のゴミの片付けを始めたらすぐに軽トラ一車分できた。
苗を植えるよりも、ゴミの片付けにスイッチが入ってしばらくやってた。
廃材生活においては、ちょこちょこっと片付けるとこうなる。
鉄のゴミはスクラップ屋に売りに行けるのが魅力。
コンクリートガラやプラスチックなども、何をどこに持っていけばいいかを把握しとかないと、イチイチ処分代がカサム。
同級生がコールラビとワサビ菜を持ってきてくれた。
キャベツの仲間で芯を食べるための野菜。
土筆の甘酢漬けの酢にオリーブオイルを混ぜてドレッシングにしたそうな。
タグ :果樹
2013年02月20日
干し大根葉
さぶいけど、もう春になろうとしてる。

畑の大根もたくさんあるのに、食べきれない。
たくあん漬けも3回に分けて十分作ったし。

葉をはねて本体だけにする。
こうすることでトウ立ちするのを遅らせられる。
ちょっとでも、スカスカになるのが先延ばしになり、長く食べられる。
大根葉が大量に出た。
外の黄色くなりつつある部分は鶏小屋に放り込み、いい部分だけを茹でる。
大根葉のお好み焼きもいい加減食べたし。

干すことにした。

まだフニャッとしてるけど、ある程度干せた。

これは今朝の味噌汁。
味噌は各自食べる直前に入れる方式。
子どもたちは薄味、僕のような労働者は濃い味なので、好みの味付けにできるのがいい。
更にいいのは鍋で高温になって味噌の酵素が失われることがない所。
益々いいのは残った味噌汁って味噌の風味がなくなって不味くなるけど、それもない。
お昼はショウガのすりおろしとナンプラーでエスニック風スープにしてもいい。
話がそれたけど、干し大根葉は予想を上回る美味しさ。
昨日は鍋に入れたけど、生だと人気の低い大根葉が甘味があって濃くって美味しい。
切り干し大根が甘くて美味しくなるんやから、当然かもしれんけど、以外な程美味しい。
何より大根葉を無駄にすることなく、利用できたのが嬉しい。
それも、もったいないから何とか食べてしまおうという無理やり感じゃなく、美味しいのがよかった。
相当あるんで、これの素晴らしいレシピ開発が望まれる。
畑の大根もたくさんあるのに、食べきれない。
たくあん漬けも3回に分けて十分作ったし。
葉をはねて本体だけにする。
こうすることでトウ立ちするのを遅らせられる。
ちょっとでも、スカスカになるのが先延ばしになり、長く食べられる。
大根葉が大量に出た。
外の黄色くなりつつある部分は鶏小屋に放り込み、いい部分だけを茹でる。
大根葉のお好み焼きもいい加減食べたし。
干すことにした。
まだフニャッとしてるけど、ある程度干せた。
これは今朝の味噌汁。
味噌は各自食べる直前に入れる方式。
子どもたちは薄味、僕のような労働者は濃い味なので、好みの味付けにできるのがいい。
更にいいのは鍋で高温になって味噌の酵素が失われることがない所。
益々いいのは残った味噌汁って味噌の風味がなくなって不味くなるけど、それもない。
お昼はショウガのすりおろしとナンプラーでエスニック風スープにしてもいい。
話がそれたけど、干し大根葉は予想を上回る美味しさ。
昨日は鍋に入れたけど、生だと人気の低い大根葉が甘味があって濃くって美味しい。
切り干し大根が甘くて美味しくなるんやから、当然かもしれんけど、以外な程美味しい。
何より大根葉を無駄にすることなく、利用できたのが嬉しい。
それも、もったいないから何とか食べてしまおうという無理やり感じゃなく、美味しいのがよかった。
相当あるんで、これの素晴らしいレシピ開発が望まれる。
タグ :大根葉
2013年01月12日
ミニダップ
ミニダップ!
それは超小型籾すり機。

コレがそれ。
自給農において、お米作りのネックは農器具。
もうひとつの、水の事で水利組合とか自治会との折り合いという超ネックはおいといて。
コンバイン、トラクター、田植え機、これが高い順から3つ。
コンバインが嫌ならバインダーとハーベスタ(脱穀機)で自然乾燥。
後は籾すり機。
もちろん自給用にコンバインなんか要らないけど。
不耕起で一反(300坪)だけ作るのなら農器具はそんなに要らない。
籾蒔きして、苗を育て、手植え、草取り、水管理、手刈り、ハゼ掛けして乾燥。
ここまでは全部手作業でやった経験は5、6年あるけど、十分可能。
後は籾すり。
どうしても籾すり機は要る。
もちろん、ソコソコの量になると委託でやってもらえる。
他の作業よりは籾すりは安価でやってもらえる。
例えば、コンバインの作業を委託すると反当たり2万4千円(しかも、籾を乾燥機に入れないといけない)。
それに比べると籾すりだけなら一袋数百円なので、一反で8俵(16袋)採れても、自然乾燥しておけば数千円。
しかも、このミニダップは超小型でモーター動力なので、メンテナンスも楽。
新品で12万、中古を探せば安く手に入る可能性はある。
ウチは5万で買った。
何より、小型なので、黒米などの古代米を多品種作りたい時に便利。
籾すり場には少量で、しかも色のついた米は他に混じるので嫌がられる。
それと、籾貯蔵が出来るというメリットもある。
30㌔の袋に10数袋とか採れて、全部籾すりして玄米にすると、貯蔵に気を使う。
春までに食べてしまう量なら問題ない。
夏を越すのには土壁の納屋や蔵で、梅雨の湿気の影響も受けない場所が必須。
もしくは玄米貯蔵用の冷蔵庫。
これは高い。
それに比べて籾貯蔵なら低温貯蔵しなくとも傷まないし、虫もつかない。
しかし、食べる分づつ籾すりするのはおっくう。
それを解決するのがこのミニダップ。
この機械のセールスみたくなってきたけど、本当に手軽で高性能なミニ農機具。

これは何年も置いてあった黒米の籾。
一年だけみやびに籾をもらって作ってみた。
今回これを籾すりした。

籾が残ると再度通せばいい。
今回、妹のみやびが京都から帰ってきたのはこの機械を持って帰るため。
親父が中心でやってるこっちの田んぼは3反以上あり、ヒノヒカリ単一。
今後も古代米とか作る予定はない。
籾すりは一軒目の廃材ハウスの土地を借りてた河野さんにやってもらう。
みやびは京北町で一反ぐらい、色んな品種を作ってる。
いつも、コレと同じミニダップを知り合いに借りて籾すりしてたとか。
それで、ウチで出番の少ないなら持って帰りたいという流れになった。
僕自身も親父も色々多品種のお米を作りたいという願望はない。
一年分食べられる量が採れればいい。
僕は以前よりも「農」にウエイトを置かなくなってきた。
一年分の米の自給は楽々出来てるし、ちょっとした菜園だけで十分。
楽勝で自給できてるのに、これ以上に拡張したいとは思わない。
あっこちゃんの方がやる気なのでバトンタッチしつつある。
一軒目の廃材ハウスの時やそれ以前から「自然農」だ「自然養鶏」だとかなりのめり込んでた。
確かに福岡さんや川口さんにも会いに行ったし、今の自分に多大な影響を頂いた。
ここへ来て、廃材で自画杜撰の生活も極まってきた。
自分でチマチマ作るよりも、余ってるタダのものをガガーッと獲ってくる泥棒型が一番フィットする。
これは自分にしか分からない嗜好性。
しかも、その嗜好性はどんどん変化する。
アレもやりたい、コレもやりたいと、誰でも願望は多いもの。
その願望を妄想に終わらせないためにも、優先順位の低いものに労力を割かない。
ここポイント!
自分のやりたい事に集中せよ!
やりたいやりたいって、ホンマはどんだけ?
これを常に自分自身に問うのだ。

頂きもののカチンコチンの餅。

揚げ餅にした。
醤油をつけるのもいいし、塩をつけながらもいい。

またメノリの佃煮。
宇多津産直市「魚の大空」で更に安く(1㌔100円)出てたんで、大量に仕入れた。
最近四国の瀬戸内沿岸は超温かく、昼に料理のために薪ストーブを焚き過ぎると暑過ぎる。
で、外の簡易カマドで煮詰める。

強火にして、ガンガン混ぜるとあっという間に出来る。
本醸造醤油と三河本味醂だけ。
メノリはよく洗うのがポイント。
洗いが少ないと海臭くなって子どもに不人気。
何だかんだ一日中手作りしてるけど何やっても楽しいもの。
アレもコレも「やりたい」が、アレもコレも「せな」に逆転しない範囲ではね♪
それは超小型籾すり機。
コレがそれ。
自給農において、お米作りのネックは農器具。
もうひとつの、水の事で水利組合とか自治会との折り合いという超ネックはおいといて。
コンバイン、トラクター、田植え機、これが高い順から3つ。
コンバインが嫌ならバインダーとハーベスタ(脱穀機)で自然乾燥。
後は籾すり機。
もちろん自給用にコンバインなんか要らないけど。
不耕起で一反(300坪)だけ作るのなら農器具はそんなに要らない。
籾蒔きして、苗を育て、手植え、草取り、水管理、手刈り、ハゼ掛けして乾燥。
ここまでは全部手作業でやった経験は5、6年あるけど、十分可能。
後は籾すり。
どうしても籾すり機は要る。
もちろん、ソコソコの量になると委託でやってもらえる。
他の作業よりは籾すりは安価でやってもらえる。
例えば、コンバインの作業を委託すると反当たり2万4千円(しかも、籾を乾燥機に入れないといけない)。
それに比べると籾すりだけなら一袋数百円なので、一反で8俵(16袋)採れても、自然乾燥しておけば数千円。
しかも、このミニダップは超小型でモーター動力なので、メンテナンスも楽。
新品で12万、中古を探せば安く手に入る可能性はある。
ウチは5万で買った。
何より、小型なので、黒米などの古代米を多品種作りたい時に便利。
籾すり場には少量で、しかも色のついた米は他に混じるので嫌がられる。
それと、籾貯蔵が出来るというメリットもある。
30㌔の袋に10数袋とか採れて、全部籾すりして玄米にすると、貯蔵に気を使う。
春までに食べてしまう量なら問題ない。
夏を越すのには土壁の納屋や蔵で、梅雨の湿気の影響も受けない場所が必須。
もしくは玄米貯蔵用の冷蔵庫。
これは高い。
それに比べて籾貯蔵なら低温貯蔵しなくとも傷まないし、虫もつかない。
しかし、食べる分づつ籾すりするのはおっくう。
それを解決するのがこのミニダップ。
この機械のセールスみたくなってきたけど、本当に手軽で高性能なミニ農機具。
これは何年も置いてあった黒米の籾。
一年だけみやびに籾をもらって作ってみた。
今回これを籾すりした。
籾が残ると再度通せばいい。
今回、妹のみやびが京都から帰ってきたのはこの機械を持って帰るため。
親父が中心でやってるこっちの田んぼは3反以上あり、ヒノヒカリ単一。
今後も古代米とか作る予定はない。
籾すりは一軒目の廃材ハウスの土地を借りてた河野さんにやってもらう。
みやびは京北町で一反ぐらい、色んな品種を作ってる。
いつも、コレと同じミニダップを知り合いに借りて籾すりしてたとか。
それで、ウチで出番の少ないなら持って帰りたいという流れになった。
僕自身も親父も色々多品種のお米を作りたいという願望はない。
一年分食べられる量が採れればいい。
僕は以前よりも「農」にウエイトを置かなくなってきた。
一年分の米の自給は楽々出来てるし、ちょっとした菜園だけで十分。
楽勝で自給できてるのに、これ以上に拡張したいとは思わない。
あっこちゃんの方がやる気なのでバトンタッチしつつある。
一軒目の廃材ハウスの時やそれ以前から「自然農」だ「自然養鶏」だとかなりのめり込んでた。
確かに福岡さんや川口さんにも会いに行ったし、今の自分に多大な影響を頂いた。
ここへ来て、廃材で自画杜撰の生活も極まってきた。
自分でチマチマ作るよりも、余ってるタダのものをガガーッと獲ってくる泥棒型が一番フィットする。
これは自分にしか分からない嗜好性。
しかも、その嗜好性はどんどん変化する。
アレもやりたい、コレもやりたいと、誰でも願望は多いもの。
その願望を妄想に終わらせないためにも、優先順位の低いものに労力を割かない。
ここポイント!
自分のやりたい事に集中せよ!
やりたいやりたいって、ホンマはどんだけ?
これを常に自分自身に問うのだ。
頂きもののカチンコチンの餅。
揚げ餅にした。
醤油をつけるのもいいし、塩をつけながらもいい。
またメノリの佃煮。
宇多津産直市「魚の大空」で更に安く(1㌔100円)出てたんで、大量に仕入れた。
最近四国の瀬戸内沿岸は超温かく、昼に料理のために薪ストーブを焚き過ぎると暑過ぎる。
で、外の簡易カマドで煮詰める。
強火にして、ガンガン混ぜるとあっという間に出来る。
本醸造醤油と三河本味醂だけ。
メノリはよく洗うのがポイント。
洗いが少ないと海臭くなって子どもに不人気。
何だかんだ一日中手作りしてるけど何やっても楽しいもの。
アレもコレも「やりたい」が、アレもコレも「せな」に逆転しない範囲ではね♪
タグ :自然農
2012年11月02日
廃材の籾すり場で籾すり
脱穀も終わり、今度は籾すり。
これは毎年、一軒目の廃材ハウスの土地を貸してくれてた河野さん所でやってもらう。

とんでもない量のもみ殻が積もる河野さんの籾すり場。
実はここも廃材セルフビルド。
昔の木の電柱を穴掘って埋め込んで使うという工法はここから学んだ。

とにかくサイズがデカイ。
右の上の段の白い乾燥機が2、5mはあるので、この建物の大きさが凄いことが分かる。
もちろんこのトタンも廃材。
河野さんの周りの田舎のおっちゃんたちは、どこで鶏舎が解体されるとかいう情報に鋭敏。
僕もこの地で廃材集めのノウハウを学んだ。

工場がセルフビルドってだけじゃなく、籾を乾燥させる乾燥機も農家の納屋から発掘してきてる。
30年、40年前の機械も河野さんがバラして直して使う。
こういう機械類に金をかけないから農家は安く籾すりさせてもらえる。
ここに来る農家は脱JA型の猛者が多い。
今のJAのシステムはカントリーエレベータと言って、コンバインで刈り取った籾を大きなプラントに集約して、乾燥から籾すり、冷蔵保管までしてくれる。
もちろん多大な金を払わされることは必至やし、何よりみんなが持ってきたお米はごちゃ混ぜになり、自分の作ったお米が個別に管理されたりしない。
百姓が自分の作ったお米を食べられないという事態になってきてる。

ウチの籾は自然乾燥されてきてるので、乾燥機に入れる必要はなく、直接このベルトコンベアーで籾すり機の上部の箱に投入する。

上の奥が籾すり機。
2年前、河野さんの主催する「アートで田んぼ」に呼んだ「渋さしらズ」のカオスオーケストラがここでライブした。

ハーベスタから袋に入れた籾は60袋以上だったので、軽トラ2台と天ぷらカーに分けて行ってた。
籾すり後は30㌔の袋に計量してキチッと入れて、50袋!
2袋で一俵なので、25俵採れた。
去年より5、6袋多い。
しかもイモチ病も紋枯病も来てなくて、キレイな玄米やった。
数々の農家のお米を見てる河野さんにも合格点を頂いた。
これを一年かけて実家、ウチ、弟家族の3家族で消費する。
この玄米は毎日薪で焚いて食べる以外に、麹に加工して甘酒にしたり、麦芽と合わせて米飴にしたり、豆と麹で一年分の味噌にしたり、黒煎り玄米珈琲にしたり、トコトン利用する。
クダケと言う籾すり時にでるクズ米は鶏の餌になる。
もみ殻はコンポストトイレに毎回投入したり、と全く無駄がない。
言わばお米ありきの生活。
お米が一年分自給できてるってホントにありがたい。
とりあえず玄米さえ炊いとけば食事の用意は7、8割出来たようなモン。
他にも一年分の味噌や梅干しがストックされてるので、超楽チン。
後はキッチンの前の菜園から何か採ってきて料理する。
毎日それの繰り返しで、バリエーション豊かな食生活が満喫できる。
ほんと、瑞穂の国日本に生まれてよかった!
戦後、お米ばかり食べてると脳の発達に支障をきたすという洗脳がアメリカから来て、給食からパン食と粉ミルクが導入された。
動物性たんぱく質が足りないとか、牛乳飲まないとカルシウムが不足するとか、まことしやかに医者や学者がのたまった。
僕らの両親ぐらいの団塊の世代がそれの最大の被害者。
そういう時代も過ぎ、マクロビオティックや玄米食が若い女性雑誌にも載るようになった。
と言っても、食の価値観も超多様化してる。
〇〇が体にいい、△△が悪いという枝葉末節に囚われるな!
ご飯を食べる。
粉ものを減らす。
ご飯で腹一杯にして、余計な加工品を食べない。
それには一年以上かけて熟成した味噌や醤油が必携。
もちろんその上で、和洋中エスニックと色々取り入れて飽きないように楽しむのだ。
これは毎年、一軒目の廃材ハウスの土地を貸してくれてた河野さん所でやってもらう。
とんでもない量のもみ殻が積もる河野さんの籾すり場。
実はここも廃材セルフビルド。
昔の木の電柱を穴掘って埋め込んで使うという工法はここから学んだ。
とにかくサイズがデカイ。
右の上の段の白い乾燥機が2、5mはあるので、この建物の大きさが凄いことが分かる。
もちろんこのトタンも廃材。
河野さんの周りの田舎のおっちゃんたちは、どこで鶏舎が解体されるとかいう情報に鋭敏。
僕もこの地で廃材集めのノウハウを学んだ。
工場がセルフビルドってだけじゃなく、籾を乾燥させる乾燥機も農家の納屋から発掘してきてる。
30年、40年前の機械も河野さんがバラして直して使う。
こういう機械類に金をかけないから農家は安く籾すりさせてもらえる。
ここに来る農家は脱JA型の猛者が多い。
今のJAのシステムはカントリーエレベータと言って、コンバインで刈り取った籾を大きなプラントに集約して、乾燥から籾すり、冷蔵保管までしてくれる。
もちろん多大な金を払わされることは必至やし、何よりみんなが持ってきたお米はごちゃ混ぜになり、自分の作ったお米が個別に管理されたりしない。
百姓が自分の作ったお米を食べられないという事態になってきてる。
ウチの籾は自然乾燥されてきてるので、乾燥機に入れる必要はなく、直接このベルトコンベアーで籾すり機の上部の箱に投入する。
上の奥が籾すり機。
2年前、河野さんの主催する「アートで田んぼ」に呼んだ「渋さしらズ」のカオスオーケストラがここでライブした。
ハーベスタから袋に入れた籾は60袋以上だったので、軽トラ2台と天ぷらカーに分けて行ってた。
籾すり後は30㌔の袋に計量してキチッと入れて、50袋!
2袋で一俵なので、25俵採れた。
去年より5、6袋多い。
しかもイモチ病も紋枯病も来てなくて、キレイな玄米やった。
数々の農家のお米を見てる河野さんにも合格点を頂いた。
これを一年かけて実家、ウチ、弟家族の3家族で消費する。
この玄米は毎日薪で焚いて食べる以外に、麹に加工して甘酒にしたり、麦芽と合わせて米飴にしたり、豆と麹で一年分の味噌にしたり、黒煎り玄米珈琲にしたり、トコトン利用する。
クダケと言う籾すり時にでるクズ米は鶏の餌になる。
もみ殻はコンポストトイレに毎回投入したり、と全く無駄がない。
言わばお米ありきの生活。
お米が一年分自給できてるってホントにありがたい。
とりあえず玄米さえ炊いとけば食事の用意は7、8割出来たようなモン。
他にも一年分の味噌や梅干しがストックされてるので、超楽チン。
後はキッチンの前の菜園から何か採ってきて料理する。
毎日それの繰り返しで、バリエーション豊かな食生活が満喫できる。
ほんと、瑞穂の国日本に生まれてよかった!
戦後、お米ばかり食べてると脳の発達に支障をきたすという洗脳がアメリカから来て、給食からパン食と粉ミルクが導入された。
動物性たんぱく質が足りないとか、牛乳飲まないとカルシウムが不足するとか、まことしやかに医者や学者がのたまった。
僕らの両親ぐらいの団塊の世代がそれの最大の被害者。
そういう時代も過ぎ、マクロビオティックや玄米食が若い女性雑誌にも載るようになった。
と言っても、食の価値観も超多様化してる。
〇〇が体にいい、△△が悪いという枝葉末節に囚われるな!
ご飯を食べる。
粉ものを減らす。
ご飯で腹一杯にして、余計な加工品を食べない。
それには一年以上かけて熟成した味噌や醤油が必携。
もちろんその上で、和洋中エスニックと色々取り入れて飽きないように楽しむのだ。
タグ :籾すり
2012年10月31日
籾が乾燥したので脱穀作業
さあ、いよいよ脱穀作業。
ハゼに掛けて自然乾燥してた籾がイイ感じに乾燥した。
水分率で15%切ると丁度いい。
13~14%まで乾いた。
口に入れて噛むとカキッと割れる固さ。

脱穀はハーベスタという脱穀機で行う。
この機械も40年前クラスのベテラン。
近所の農家の納屋に眠ってるのをもらって使ってる。
今じゃ、コンバインが普及してハーベスタの出番はない。
手植え、無農薬、無肥料で作ってる自家用米の最後のこだわりがこの自然乾燥。
不耕起で5畝(約150坪)の田んぼを作ってた時は手植え、手刈り、この脱穀は足踏み脱穀でやってた。
今は3反(約1000坪)に増やしたので、手植え、バインダーで刈り、ハーベスタで脱穀という工程。
こういう古い機械なら「欲しいんです!」とアチコチ声をかければ必ず出てくる。
折角、有機無農薬でもコンバインで刈り取ると乾燥機でボイラー乾燥になる。
コンバインが高いからわざわざ買いたくないという意味もあるけどと、刈り取ってから3週間も天日乾燥するという所に大きな違いがある。
籾は刈り取られてからも、茎からの養分を蓄えようとするそうな。
しかも、天日乾燥の籾は確実に来年発芽するのに比べ、ボイラー乾燥の籾はそうじゃない。
ここが決定的な違い。
発芽しないとは命がないということだ。
命のないお米を喰って自分の命が養えるか!
美味しいか美味しくないかは主観の問題なので置いておくとして、命のエネルギーを取りこんで生きているのは厳然とした事実なのだ。
しかし、天日乾燥までのクオリティーになってくるとネットで見ても、5㌔4500円とか10㌔7000円という少量でとんでもなく高い。
ちなみに有機無農薬米の相場は1㌔500円~。
一袋30㌔で15000円~になる。
除草剤と化学肥料入りの普通栽培の米なら1万円を切る。
それでもまだ、新米の単一米100%なら良心的な方。
田舎の生産者から玄米を30㌔単位で買うと間違いなく大丈夫。
近頃は100円で10㌔精米できるコイン精米も増えたし。
でも、スーパーの5㌔や10㌔に小分けされた精白米はほぼブレンド米。
中には古古古米を混ぜる猛者も居る。
今は放射能の問題もあるから混ぜて薄めて100ベクレル以下なんてのもザラ。
高い安い、安全性が、、、とか言う議論の前に自分で作るとこんなに簡単なのか!?とビックリする。
一家族が一年分自給する量を家族総出で作業すると年間に直すとほんの数日の作業でいける。
今は実家、廃材の家、弟家族と3家族分をみんなでやってるけど、非常に楽チン。
こんな貴重なお米を売る訳にはいかないが、黒煎り玄米珈琲、麹にして甘酒、米飴などに加工する。
それらがあっこちゃんのマクロビスイーツの材料になる。
玄米珈琲は最近人気でよく煎ってる。
しかも薪で煎るので、陽性が強くて冷え症の人にはもってこい。
イベント出店の時限定で、玄米オムスビやライスバーガーにも使う。
最近では長岡式酵素玄米のオムスビというプレミアムメニューも加わった。

子どもたちは脱穀後の稲ワラを田んぼ中に散らばらせるのが仕事。

ハゼの木を片づける時に上に乗って走るのが楽しい。
ハゼに掛けて自然乾燥してた籾がイイ感じに乾燥した。
水分率で15%切ると丁度いい。
13~14%まで乾いた。
口に入れて噛むとカキッと割れる固さ。
脱穀はハーベスタという脱穀機で行う。
この機械も40年前クラスのベテラン。
近所の農家の納屋に眠ってるのをもらって使ってる。
今じゃ、コンバインが普及してハーベスタの出番はない。
手植え、無農薬、無肥料で作ってる自家用米の最後のこだわりがこの自然乾燥。
不耕起で5畝(約150坪)の田んぼを作ってた時は手植え、手刈り、この脱穀は足踏み脱穀でやってた。
今は3反(約1000坪)に増やしたので、手植え、バインダーで刈り、ハーベスタで脱穀という工程。
こういう古い機械なら「欲しいんです!」とアチコチ声をかければ必ず出てくる。
折角、有機無農薬でもコンバインで刈り取ると乾燥機でボイラー乾燥になる。
コンバインが高いからわざわざ買いたくないという意味もあるけどと、刈り取ってから3週間も天日乾燥するという所に大きな違いがある。
籾は刈り取られてからも、茎からの養分を蓄えようとするそうな。
しかも、天日乾燥の籾は確実に来年発芽するのに比べ、ボイラー乾燥の籾はそうじゃない。
ここが決定的な違い。
発芽しないとは命がないということだ。
命のないお米を喰って自分の命が養えるか!
美味しいか美味しくないかは主観の問題なので置いておくとして、命のエネルギーを取りこんで生きているのは厳然とした事実なのだ。
しかし、天日乾燥までのクオリティーになってくるとネットで見ても、5㌔4500円とか10㌔7000円という少量でとんでもなく高い。
ちなみに有機無農薬米の相場は1㌔500円~。
一袋30㌔で15000円~になる。
除草剤と化学肥料入りの普通栽培の米なら1万円を切る。
それでもまだ、新米の単一米100%なら良心的な方。
田舎の生産者から玄米を30㌔単位で買うと間違いなく大丈夫。
近頃は100円で10㌔精米できるコイン精米も増えたし。
でも、スーパーの5㌔や10㌔に小分けされた精白米はほぼブレンド米。
中には古古古米を混ぜる猛者も居る。
今は放射能の問題もあるから混ぜて薄めて100ベクレル以下なんてのもザラ。
高い安い、安全性が、、、とか言う議論の前に自分で作るとこんなに簡単なのか!?とビックリする。
一家族が一年分自給する量を家族総出で作業すると年間に直すとほんの数日の作業でいける。
今は実家、廃材の家、弟家族と3家族分をみんなでやってるけど、非常に楽チン。
こんな貴重なお米を売る訳にはいかないが、黒煎り玄米珈琲、麹にして甘酒、米飴などに加工する。
それらがあっこちゃんのマクロビスイーツの材料になる。
玄米珈琲は最近人気でよく煎ってる。
しかも薪で煎るので、陽性が強くて冷え症の人にはもってこい。
イベント出店の時限定で、玄米オムスビやライスバーガーにも使う。
最近では長岡式酵素玄米のオムスビというプレミアムメニューも加わった。
子どもたちは脱穀後の稲ワラを田んぼ中に散らばらせるのが仕事。
ハゼの木を片づける時に上に乗って走るのが楽しい。
タグ :田んぼ
2012年10月11日
稲刈り3日目でほぼ終わりが見えた
稲刈り3日目。
近所のベテラン農家のおっちゃんが来て、「よう出来とるのう。ほんまにキレイな稲じゃ。」と言ってくれた。
何でも、今年は近所の稲の多くに紋枯病という病気が出たそう。
原因は機械植えで株と株の間が狭い上に、化学肥料で成長過多になり、風通しが悪くなって稲の生命力が弱るから。

手植えなら株の間が広いし、一本植えなのでしっかりした稲になる。
しかも無肥料というのが更にいい。
化学肥料、有機肥料、まして農薬という要らないもののオンパレードで悪循環に陥ってる。

一本植えで無肥料なら稲の株の分ケツが進んで多くなる。
しかも一本一本のワラが固い。
稲そのものが健康なので、病気や害虫が来ない。

昨日は源が居たし、午後からからハラさんも手伝ってくれたりして随分進んだ。
3枚目の田んぼまで、刈り取りとハゼ掛けが終わった。

苗代にしてるこの小さな田んぼを残すのみとなった。
作物も人間も一緒。
免疫力が高い健康な身体にする。
コレしかない!
健康な苗を一本ずつ植える。
これで、肥料と農薬は要らない。
肥料をやらないから、病気や虫の問題は起こらない。
玄米と純正調味料を食べて市販の加工品と砂糖を辞める。
これで、サプリメントも病院もいらない。
粉モノ辞めて白いご飯をしっかり食べるだけでもいい。
加工品と砂糖を減らすと身体は楽になる。
稲も人間も本来健康であるようにDNAに書き込まれてる。
それを病気にするには途方もないような努力を費やさないと出来ないのだ。
「現代の機械農業では無理やわー。」
「忙しい現代人には出来んわー。」
と、最初から狂ってる社会ありきで思考をストップさせるな!!
その当たり前の常識を覆せ!
ウチらは家族で自分たちの食べるお米を作って、一日3食玄米でモリモリ食べてる。
ウンコもスルスルで体調もバッチリ、頭脳も明晰!
生活と食は切り離せない。
自分の納得するウチのような手作り生活のをしたいのならまず食生活から。
こういう食生活が送れない仕事や日常のありかたに問題があるのだ。
それを改めようともせずに羨ましがってもしゃあないぞ。

京都の北部で農暮らししてる妹の雅から素敵なものが届いた。
自家栽培の舞茸。

オリーブオイルと塩だけでサッと炒めて、スダチを絞る!
割としっかりと塩を利かせる。
これは純米酒にピッタリ。

キンピラゴボウとさつま芋。
後で素揚げした芋を混ぜたのがよかった。

ゴーヤとニラの天ぷら。
ゴーヤは輪切りで厚切りの種ごとが美味しい。
ニラだけの天ぷらは掻き揚げ風でまた目新しい。
天ぷらにもやはりスダチが合う。

最近ウチで流行ってるオカラサラダ。

徳島の半田素麺でのナス素麺。
もちろんこれは前菜で玄米ご飯をしっかり食べる。
近所のベテラン農家のおっちゃんが来て、「よう出来とるのう。ほんまにキレイな稲じゃ。」と言ってくれた。
何でも、今年は近所の稲の多くに紋枯病という病気が出たそう。
原因は機械植えで株と株の間が狭い上に、化学肥料で成長過多になり、風通しが悪くなって稲の生命力が弱るから。
手植えなら株の間が広いし、一本植えなのでしっかりした稲になる。
しかも無肥料というのが更にいい。
化学肥料、有機肥料、まして農薬という要らないもののオンパレードで悪循環に陥ってる。
一本植えで無肥料なら稲の株の分ケツが進んで多くなる。
しかも一本一本のワラが固い。
稲そのものが健康なので、病気や害虫が来ない。
昨日は源が居たし、午後からからハラさんも手伝ってくれたりして随分進んだ。
3枚目の田んぼまで、刈り取りとハゼ掛けが終わった。
苗代にしてるこの小さな田んぼを残すのみとなった。
作物も人間も一緒。
免疫力が高い健康な身体にする。
コレしかない!
健康な苗を一本ずつ植える。
これで、肥料と農薬は要らない。
肥料をやらないから、病気や虫の問題は起こらない。
玄米と純正調味料を食べて市販の加工品と砂糖を辞める。
これで、サプリメントも病院もいらない。
粉モノ辞めて白いご飯をしっかり食べるだけでもいい。
加工品と砂糖を減らすと身体は楽になる。
稲も人間も本来健康であるようにDNAに書き込まれてる。
それを病気にするには途方もないような努力を費やさないと出来ないのだ。
「現代の機械農業では無理やわー。」
「忙しい現代人には出来んわー。」
と、最初から狂ってる社会ありきで思考をストップさせるな!!
その当たり前の常識を覆せ!
ウチらは家族で自分たちの食べるお米を作って、一日3食玄米でモリモリ食べてる。
ウンコもスルスルで体調もバッチリ、頭脳も明晰!
生活と食は切り離せない。
自分の納得するウチのような手作り生活のをしたいのならまず食生活から。
こういう食生活が送れない仕事や日常のありかたに問題があるのだ。
それを改めようともせずに羨ましがってもしゃあないぞ。
京都の北部で農暮らししてる妹の雅から素敵なものが届いた。
自家栽培の舞茸。
オリーブオイルと塩だけでサッと炒めて、スダチを絞る!
割としっかりと塩を利かせる。
これは純米酒にピッタリ。
キンピラゴボウとさつま芋。
後で素揚げした芋を混ぜたのがよかった。
ゴーヤとニラの天ぷら。
ゴーヤは輪切りで厚切りの種ごとが美味しい。
ニラだけの天ぷらは掻き揚げ風でまた目新しい。
天ぷらにもやはりスダチが合う。
最近ウチで流行ってるオカラサラダ。
徳島の半田素麺でのナス素麺。
もちろんこれは前菜で玄米ご飯をしっかり食べる。
タグ :稲刈り
2012年10月09日
稲刈りスタート
待ちに待った稲刈りスタート。

今年もよく実ってる。
レンゲを蒔くだけの全くの無肥料でもよく出来る。
畑は不耕起だけど、田んぼはトラクターで代掻きして手植えしてる。
トラクターが壊れたら、田んぼも不耕起にしようと思ってる。
年間数日間だけ集中的に作業すれば、年中美味しい玄米が供給されるんやからほんとに効率がいい。

親父、お袋、あっこちゃん、野遊、土歩、にこに加え、女性が2人来てくれた。
源とこの家族は来てない。
僕がバインダーで刈って、畔の周囲の刈り取りと結束をみんなでやる。
たまにバインダーが結束ミスをしたのも結束する。
この田んぼが1反3畝(約)400坪で、バインダーなら午前中で刈ってしまえる。
よっぽど細い棚田でもバインダーなら入れる。
何せ、刈り取りと結束を同時にしてくれるのが最高。

親父のピザ窯の前で玄米ご飯とうどんでランチ。
お昼ご飯の後、高知へIターンで自給自足生活に入ってるまーくんが来た。
いつもの1ナンバーのキャラバンから新型のハイエースにグレードアップしてて、これ見よがしに田んぼの横に停めて手伝ってくれた。
容量的にウチのボンゴの二倍以上あるんちゃうかと思われるデカさ!
田舎暮らしにハイエースは最高!!
車、ユンボ、チェーンソー、電動工具、、、「アレは値段の割に調子いい。」など、こういう情報交換は大切。

チヂミ5種。
スダチと醤油、豆板醤のタレが相性がいい。

晩ご飯が終わりかけた頃に、近所の人が釣りたての魚を持って来てくれた。
ママカリが中心で鰯、鯵が混じる超新鮮そのもの。

捌いてるといつもやりたがりのちびっ子が手伝う。
ウロコを落とすのだけやってたのが、「にこちゃん、ないぞうとりたいー。」と進歩した。
新鮮な魚は気持ち悪くないからね。

最初は小さいし下ろすのがめんどくさいけど、新鮮さの魅力で丸ごとガリガリと食べてた。
やっぱり下ろした方が美味しい。
同じ青魚が3種類あってもそれぞれ味わいが違っていい。
大型の回遊魚のような大味さがなく、繊細な違いに順番に食べてるといつまでも飽きない。
後は焼いて3杯酢に漬けこんだ。
今年もよく実ってる。
レンゲを蒔くだけの全くの無肥料でもよく出来る。
畑は不耕起だけど、田んぼはトラクターで代掻きして手植えしてる。
トラクターが壊れたら、田んぼも不耕起にしようと思ってる。
年間数日間だけ集中的に作業すれば、年中美味しい玄米が供給されるんやからほんとに効率がいい。
親父、お袋、あっこちゃん、野遊、土歩、にこに加え、女性が2人来てくれた。
源とこの家族は来てない。
僕がバインダーで刈って、畔の周囲の刈り取りと結束をみんなでやる。
たまにバインダーが結束ミスをしたのも結束する。
この田んぼが1反3畝(約)400坪で、バインダーなら午前中で刈ってしまえる。
よっぽど細い棚田でもバインダーなら入れる。
何せ、刈り取りと結束を同時にしてくれるのが最高。
親父のピザ窯の前で玄米ご飯とうどんでランチ。
お昼ご飯の後、高知へIターンで自給自足生活に入ってるまーくんが来た。
いつもの1ナンバーのキャラバンから新型のハイエースにグレードアップしてて、これ見よがしに田んぼの横に停めて手伝ってくれた。
容量的にウチのボンゴの二倍以上あるんちゃうかと思われるデカさ!
田舎暮らしにハイエースは最高!!
車、ユンボ、チェーンソー、電動工具、、、「アレは値段の割に調子いい。」など、こういう情報交換は大切。
チヂミ5種。
スダチと醤油、豆板醤のタレが相性がいい。
晩ご飯が終わりかけた頃に、近所の人が釣りたての魚を持って来てくれた。
ママカリが中心で鰯、鯵が混じる超新鮮そのもの。
捌いてるといつもやりたがりのちびっ子が手伝う。
ウロコを落とすのだけやってたのが、「にこちゃん、ないぞうとりたいー。」と進歩した。
新鮮な魚は気持ち悪くないからね。
最初は小さいし下ろすのがめんどくさいけど、新鮮さの魅力で丸ごとガリガリと食べてた。
やっぱり下ろした方が美味しい。
同じ青魚が3種類あってもそれぞれ味わいが違っていい。
大型の回遊魚のような大味さがなく、繊細な違いに順番に食べてるといつまでも飽きない。
後は焼いて3杯酢に漬けこんだ。
タグ :稲刈り
2012年10月05日
稲刈り迫る
また、テレビの話。
大阪の読売テレビの取材が入った。
最近重なるねー。

打ち合わせに来たディレクターが子ども達とサッカーをしてくれて、みんな大喜び。
テント劇「どくんご」公演に向けて、庭の草刈りもバッチリ整ったゴール前。

稲がイイ感じに熟れてきた。
草取りせずにこんだけ美しく実るのはジャンボタニシ様のお陰。
ここでは猪の害もないし、後は刈り取るだけ。

穂のついた茎の色が3分の1程枯れると刈り頃。
まだ若干早いぐらい。
出荷する米は青米の混じった未熟気味じゃないといけない。
なぜなら熟れすぎは等級が下がって、値段も下がるから。
それはコンバインで刈り取って、乾燥機のボイラーの熱で乾燥する時に胴割れを起こすから。
手刈りやバインダーで刈りとって、自然乾燥ならそういう心配は皆無。
籾は刈り取った後、乾燥木に吊るしてる間にも稲全体の養分を吸収する。
そういう意味でも自然乾燥がいいに決まってる。
ただ、労力を惜しんでコンバインで刈り取るようになってる。
機械化のためには小型でも200~300万もするコンバイン、トラクター、田植え機、最低でもこの3台は必要。
更に、乾燥機、籾すり機、パッカー、冷蔵貯蔵庫まで揃えると全部自分の所で玄米になる。
自前で揃えるのは大変というのならコンバインだけ外注するというのもある。
ただ、反当たり24000円という対価が必要。
当然その後の乾燥機も委託しないといけない。
そもそも、お米程効率のいい穀類はないのだ。
反当たり7俵しか採れなくても、30㌔の玄米が14袋。
4人家族ならそのぐらいで十分。
一年分に食べるお米を食べる人数で作るのなら、トラクターもコンバインもナシの完全手作業はたやすい。
一人か二人で5反も作るということになると、機械化が迫られる。
そして、5反ごときのお米の収入から高価な機械代はペイしない。
20町歩とかべらぼうに作る大規模営農の700万の大型コンバインだって、国の補助があってこそ成り立つ代物。
農や食に関する事を大規模化して起きる問題は山ほど。
自分でそこに関わらずに、喋ってるだけでの政治的な解決は望めないのだ。

昨日は田んぼにレンゲの種を蒔いた。
稲が生えてる間に蒔いておいて、稲刈り後に発芽する。
ウチは化学肥料だけじゃなく、有機肥料もナシ。
このレンゲが唯一の施肥的なもの。
有機肥料も植物性の完熟堆肥ならまだしも、動物性のものはかえって悪い場合が多い。
さあ。
稲刈りが迫ってきた。
この土日は神社の秋祭りがあるので、それが終わってから。
8日から10日か11日まで予定してる。
実家の親父やお袋、廃材天国の家族、源の家族、+αの手伝い人でワイワイやるよ。

種蒔き機。

こんな風に使う。

冬に向けて冷凍庫を減らしていく。
これはイカナゴ、玉ねぎ、さつま芋の掻き揚げ。
醤油と味醂で濃い目の天出汁を作って、大人はショウガやミョウガをたっぷりと利かせる。

玉井さんの「雲南百草」という葉物と揚げの白みそ和え。

もやしはオルター(自然食の宅配NPO)の国産豆のもの。
まだ若い自家製豆板醤入りのナムル風。
畑のピーマンがカワイイ。
大阪の読売テレビの取材が入った。
最近重なるねー。
打ち合わせに来たディレクターが子ども達とサッカーをしてくれて、みんな大喜び。
テント劇「どくんご」公演に向けて、庭の草刈りもバッチリ整ったゴール前。
稲がイイ感じに熟れてきた。
草取りせずにこんだけ美しく実るのはジャンボタニシ様のお陰。
ここでは猪の害もないし、後は刈り取るだけ。
穂のついた茎の色が3分の1程枯れると刈り頃。
まだ若干早いぐらい。
出荷する米は青米の混じった未熟気味じゃないといけない。
なぜなら熟れすぎは等級が下がって、値段も下がるから。
それはコンバインで刈り取って、乾燥機のボイラーの熱で乾燥する時に胴割れを起こすから。
手刈りやバインダーで刈りとって、自然乾燥ならそういう心配は皆無。
籾は刈り取った後、乾燥木に吊るしてる間にも稲全体の養分を吸収する。
そういう意味でも自然乾燥がいいに決まってる。
ただ、労力を惜しんでコンバインで刈り取るようになってる。
機械化のためには小型でも200~300万もするコンバイン、トラクター、田植え機、最低でもこの3台は必要。
更に、乾燥機、籾すり機、パッカー、冷蔵貯蔵庫まで揃えると全部自分の所で玄米になる。
自前で揃えるのは大変というのならコンバインだけ外注するというのもある。
ただ、反当たり24000円という対価が必要。
当然その後の乾燥機も委託しないといけない。
そもそも、お米程効率のいい穀類はないのだ。
反当たり7俵しか採れなくても、30㌔の玄米が14袋。
4人家族ならそのぐらいで十分。
一年分に食べるお米を食べる人数で作るのなら、トラクターもコンバインもナシの完全手作業はたやすい。
一人か二人で5反も作るということになると、機械化が迫られる。
そして、5反ごときのお米の収入から高価な機械代はペイしない。
20町歩とかべらぼうに作る大規模営農の700万の大型コンバインだって、国の補助があってこそ成り立つ代物。
農や食に関する事を大規模化して起きる問題は山ほど。
自分でそこに関わらずに、喋ってるだけでの政治的な解決は望めないのだ。
昨日は田んぼにレンゲの種を蒔いた。
稲が生えてる間に蒔いておいて、稲刈り後に発芽する。
ウチは化学肥料だけじゃなく、有機肥料もナシ。
このレンゲが唯一の施肥的なもの。
有機肥料も植物性の完熟堆肥ならまだしも、動物性のものはかえって悪い場合が多い。
さあ。
稲刈りが迫ってきた。
この土日は神社の秋祭りがあるので、それが終わってから。
8日から10日か11日まで予定してる。
実家の親父やお袋、廃材天国の家族、源の家族、+αの手伝い人でワイワイやるよ。
種蒔き機。
こんな風に使う。
冬に向けて冷凍庫を減らしていく。
これはイカナゴ、玉ねぎ、さつま芋の掻き揚げ。
醤油と味醂で濃い目の天出汁を作って、大人はショウガやミョウガをたっぷりと利かせる。
玉井さんの「雲南百草」という葉物と揚げの白みそ和え。
もやしはオルター(自然食の宅配NPO)の国産豆のもの。
まだ若い自家製豆板醤入りのナムル風。
畑のピーマンがカワイイ。
タグ :稲刈り
2012年09月19日
ほったらかしのをゴソッと収穫するのが楽しい
廃材の家の敷地とは別に秋山家の田畑はたくさんある。
その中の一つにおじいちゃんが植えた果樹が色々ある畑がある。

スダチが丁度いい頃になってる。

一年間の中でする世話は収穫だけ。
それでよく採れてる。

この月桂樹なんか6mぐらいある。
この葉っぱをパッケージして売って何とか金にならんかなー。
スーパーのスパイスコーナーのなんか数枚しか入ってないもんね。

これはダイダイ。
大きなのは去年の取り忘れでスカスカ。
小さい実が結実しえるけど、まだまだ大きくなる。
ダイダイはお正月のしめ飾りに使うぐらいなので、収穫は随分寒くなってから。

これは僕が植えたオリーブで2本ある。
まだ実はなったことないけど、いつ成るのか楽しみ。
他にも柿や温州みかんもあって青い実が成ってる。
廃材天国内にも色々植えてるけど、クルミは葉が虫に食べられてボロボロになってしまった。
ユズとレモンはアゲハの幼虫に丸裸にされて枯れたり。
菜園の野菜と違って、「木やからそんなに世話せんでも、、、。」とほったらかしにしてるとそうなる。
あっこちゃんのお父さんのように熱意を持って世話しないといけない。
僕は菜園や果樹の世話に熱心ではない結果やからしゃあない。
何でもかんでも同等の熱意を注ぐ訳にはいかない。
それでいい。
僕の中の設定はそんなもん。
ショックも受けないし、凹んだりしない秘訣。
またどっかで苗木を手に入れて植えよう。
一番自分の中でスイッチの入るワクワクとは?
解体現場の何をどうやってもいい火事場泥棒状態。
畑一枚丸ごと放棄されたキャベツをタダでもらうとかに超スイッチ入る。
そういうタダで取り放題というものをトラックにコンパネの煽りつけて目一杯積み込むのに生き甲斐を感じる。
日々、チマチマと自分で世話をして育てるよりも遥かにワクワクする。
そのために、「話が来たら何でも全部もらう!」という姿勢を貫いて来た。
そうすることで、「あいつに言えばありがたがって引き取ってくれる。」という空気が出来る。
こうして自分の嗜好性を発信するのも大事なこと。
何か欲しいものを思いつくと当たりをつけるためにアチコチ電話しておく。
花崗土が欲しいと思えば土建屋の友達に電話して残土として出るのがないか聞いたり。
そうしとけば、すぐにはなくてもいずれ出た時にもらえる。
屋根材の廃ビニールだってもらえるまでに、どんだけ電話したり走り回ったことか。
果樹の話から廃材の話にすり替わったけど、そのぐらい僕の廃材に対する思い入れと行動力は強いという事。
ビジネスとして成功したり、社会的に認められる事を目指さない。
社会のスキマで生活していこうと思うなら貪欲にならないとねー!!!
いや、真似しなくていいよ、、、。
その中の一つにおじいちゃんが植えた果樹が色々ある畑がある。
スダチが丁度いい頃になってる。
一年間の中でする世話は収穫だけ。
それでよく採れてる。
この月桂樹なんか6mぐらいある。
この葉っぱをパッケージして売って何とか金にならんかなー。
スーパーのスパイスコーナーのなんか数枚しか入ってないもんね。
これはダイダイ。
大きなのは去年の取り忘れでスカスカ。
小さい実が結実しえるけど、まだまだ大きくなる。
ダイダイはお正月のしめ飾りに使うぐらいなので、収穫は随分寒くなってから。
これは僕が植えたオリーブで2本ある。
まだ実はなったことないけど、いつ成るのか楽しみ。
他にも柿や温州みかんもあって青い実が成ってる。
廃材天国内にも色々植えてるけど、クルミは葉が虫に食べられてボロボロになってしまった。
ユズとレモンはアゲハの幼虫に丸裸にされて枯れたり。
菜園の野菜と違って、「木やからそんなに世話せんでも、、、。」とほったらかしにしてるとそうなる。
あっこちゃんのお父さんのように熱意を持って世話しないといけない。
僕は菜園や果樹の世話に熱心ではない結果やからしゃあない。
何でもかんでも同等の熱意を注ぐ訳にはいかない。
それでいい。
僕の中の設定はそんなもん。
ショックも受けないし、凹んだりしない秘訣。
またどっかで苗木を手に入れて植えよう。
一番自分の中でスイッチの入るワクワクとは?
解体現場の何をどうやってもいい火事場泥棒状態。
畑一枚丸ごと放棄されたキャベツをタダでもらうとかに超スイッチ入る。
そういうタダで取り放題というものをトラックにコンパネの煽りつけて目一杯積み込むのに生き甲斐を感じる。
日々、チマチマと自分で世話をして育てるよりも遥かにワクワクする。
そのために、「話が来たら何でも全部もらう!」という姿勢を貫いて来た。
そうすることで、「あいつに言えばありがたがって引き取ってくれる。」という空気が出来る。
こうして自分の嗜好性を発信するのも大事なこと。
何か欲しいものを思いつくと当たりをつけるためにアチコチ電話しておく。
花崗土が欲しいと思えば土建屋の友達に電話して残土として出るのがないか聞いたり。
そうしとけば、すぐにはなくてもいずれ出た時にもらえる。
屋根材の廃ビニールだってもらえるまでに、どんだけ電話したり走り回ったことか。
果樹の話から廃材の話にすり替わったけど、そのぐらい僕の廃材に対する思い入れと行動力は強いという事。
ビジネスとして成功したり、社会的に認められる事を目指さない。
社会のスキマで生活していこうと思うなら貪欲にならないとねー!!!
いや、真似しなくていいよ、、、。
タグ :スダチ
2012年09月13日
ニセコ自給自足研究所
久しぶりの居候タイチくんが来た。
大学を休学中で、北海道のニセコで自給自足体験をしてきたそう。
メールでのやりとりの末、見事来ることを許可された。
ニセコ自給自足研究所のサイト
http://toyako.net/index.html
いやー、ウチよりもカナディアンファームに近い山の中。
5000坪の土地というから羨ましい。
その土地の原木をチェーンソーで伐採してのセルフビルドには心底憧れるーーー!
ていうか、全国には似たようなことやってる所がようけあるもんやねー。
似てる言うてもキーワードが似てるだけで、環境も違えば、主人の嗜好性の違いで全く様相は異なってくる。
それが面白い。
意欲的な若者はアチコチ体験して自分に合ってる部分を取り入れたらええよね。
ウチに来る前は徳島の空音遊(くうねるあそぶ)に行ってきたそう。
こちらはマクロビオティックの古民家民宿。
空音遊のサイト
http://www.k-n-a.com/index.shtml
先日のうさと展の出店中に空音遊の話をお客さんから聞いたばっかりだったんで、ビックリ。
その方から、「そこで廃材天国の話題がよく出るんです。」と聞いた。
アチコチで噂されよるんやなー。

丁度玄米珈琲が少なくなってきたんで、煎ってもらうことにした。
イベント出店では煎じた玄米珈琲を焼き締めの器に入れて出してる。
その他、200ccをパック詰めして黒煎り玄米そのものも売ってる。
最近では10パック単位で注文する人やお店が出てきて、煎るペースが早まってる。

ここの所の雨でか涼しくなったからか、ナスが非常に調子いい。

長ナス、千両、ボテナスと3種類ある。

ゴーヤもドンドン成ってる。
ただ、子どもが食べんからなー。
タイチくんが居るうちに料理せな。
玄米珈琲作りの後は大工さんの木端の整理。
最近、特に持って来てくれるペースが使うペースを上回ってて嬉しい悲鳴。
同級生の工務店2軒が競うように新築しまくってるからね。
どちらも無垢材にこだわったり、外断熱工法と言ったこだわりの工務店なだけに、いわゆる不景気とは関係ないのか?
どっちにしろ、一軒新築すると木端が大量に出る。
大工さんの木端=キッチンの料理用ということになってる。

先日作った畝に、大根、カブ、山東菜を蒔いた。
野口種苗に頼んでた種が届いたから。
来春はちゃんと種取りせなー。

ハラさんに大量のニラをもらったんで、チヂミ。
タイチくんの持ってきたカボスと醤油、豆板醤で頂いた。
カボスは数回しか食べたことがないけど、またスダチやユズとも違っていい。
ウチではスダチとダイダイの木があるので、ダイダイのポン酢が一番しっくりくる。
柑橘類ってどれも違う個性で感動する。

ナスとカボチャの煮物がほっこりと合う季節になった。
ナスもカボチャも予め中華鍋でジャッと炒めてから煮るとコクが出て美味しい。
揚げるのも美味しいけど油っこくなりすぎるので、その時の気分でコントロールする。

まだキュウリやオクラも採れてる。
ゴマダレで頂いた。
大学を休学中で、北海道のニセコで自給自足体験をしてきたそう。
メールでのやりとりの末、見事来ることを許可された。
ニセコ自給自足研究所のサイト
http://toyako.net/index.html
いやー、ウチよりもカナディアンファームに近い山の中。
5000坪の土地というから羨ましい。
その土地の原木をチェーンソーで伐採してのセルフビルドには心底憧れるーーー!
ていうか、全国には似たようなことやってる所がようけあるもんやねー。
似てる言うてもキーワードが似てるだけで、環境も違えば、主人の嗜好性の違いで全く様相は異なってくる。
それが面白い。
意欲的な若者はアチコチ体験して自分に合ってる部分を取り入れたらええよね。
ウチに来る前は徳島の空音遊(くうねるあそぶ)に行ってきたそう。
こちらはマクロビオティックの古民家民宿。
空音遊のサイト
http://www.k-n-a.com/index.shtml
先日のうさと展の出店中に空音遊の話をお客さんから聞いたばっかりだったんで、ビックリ。
その方から、「そこで廃材天国の話題がよく出るんです。」と聞いた。
アチコチで噂されよるんやなー。
丁度玄米珈琲が少なくなってきたんで、煎ってもらうことにした。
イベント出店では煎じた玄米珈琲を焼き締めの器に入れて出してる。
その他、200ccをパック詰めして黒煎り玄米そのものも売ってる。
最近では10パック単位で注文する人やお店が出てきて、煎るペースが早まってる。
ここの所の雨でか涼しくなったからか、ナスが非常に調子いい。
長ナス、千両、ボテナスと3種類ある。
ゴーヤもドンドン成ってる。
ただ、子どもが食べんからなー。
タイチくんが居るうちに料理せな。
玄米珈琲作りの後は大工さんの木端の整理。
最近、特に持って来てくれるペースが使うペースを上回ってて嬉しい悲鳴。
同級生の工務店2軒が競うように新築しまくってるからね。
どちらも無垢材にこだわったり、外断熱工法と言ったこだわりの工務店なだけに、いわゆる不景気とは関係ないのか?
どっちにしろ、一軒新築すると木端が大量に出る。
大工さんの木端=キッチンの料理用ということになってる。
先日作った畝に、大根、カブ、山東菜を蒔いた。
野口種苗に頼んでた種が届いたから。
来春はちゃんと種取りせなー。
ハラさんに大量のニラをもらったんで、チヂミ。
タイチくんの持ってきたカボスと醤油、豆板醤で頂いた。
カボスは数回しか食べたことがないけど、またスダチやユズとも違っていい。
ウチではスダチとダイダイの木があるので、ダイダイのポン酢が一番しっくりくる。
柑橘類ってどれも違う個性で感動する。
ナスとカボチャの煮物がほっこりと合う季節になった。
ナスもカボチャも予め中華鍋でジャッと炒めてから煮るとコクが出て美味しい。
揚げるのも美味しいけど油っこくなりすぎるので、その時の気分でコントロールする。
まだキュウリやオクラも採れてる。
ゴマダレで頂いた。
タグ :自給自足
2012年09月04日
自由で軽い「自給農法」
暑い昼間を避けて、早朝と夕方に開墾作業。
早朝の野良仕事は気持ちがいい。

毎日のようにノコギリを使ってた野遊は右手が使えなくなり、土歩に指示して切ってもらう。
ギプス生活にも慣れてきて、それなりに工夫して遊んでる。

一日目で平らになった所から大きな草の根を取り除いて、畝を作る作業。
夕方に小雨があって涼しくて気持ちよかった。
小さいとはいえ雑木の根っこが強靭でてこずった。
根っこパワー凄いねー。
草でもかなり太くて強い根もある。
何年間も草生えっぱなしだとちょっと大変。
だからと言って。
「畑を放置しておくと、土地が荒れて野菜を作れなくなる。」という変な常識があるけど、完全な間違い。
草茫々で放置される程土地は豊かになる。
誰も耕しもしないし、肥料もやらないのにナゼ森の木々は育つのか?
自然の生態系が完全に回っていれば、草、虫、微生物、酵素、、、様々な要素で大木が育つ環境になる。
畑も一緒。
それが不耕起自然農の根幹。
ほったらかし程いいものはない。
何しろ人為的に肥料や農薬を蒔いて不自然な状況になっていないから。
今回のように畝立ての時に木や草の根を取り除く作業がちょい大変なだけで、土そのものは豊かになってる。
畝は1、4m幅、水路というか通路が60㎝。
これは妹の雅の実践してる「糸川式自給農法」のノウハウ。
この異常に広い通路に刈った草、生ゴミなどを敷き、土寄せの時のマルチ&肥料として使う。
広くて作業性の良さは一回やると、狭い通路では出来ないほどだとか。
で、試しにやってみることにした。
http://www.jikyunoho.org/index.htm
これが「自給農法」のサイト
自然農を応用して、自給用に特化してアドバンスした分かりやすい農法。
自分で食べるためと出荷するためでは全く別モノ。
そこが農業と農の違い。
家庭菜園で化学肥料や耕運機がないといけないというのは、絶対にオカシイ。
ところが、自然農の本読んで「耕してはいけないのか!」とまた初心者は変に縛られてしまう。
いけないのでなくって、基本的にその方がよく出来るから。
もちろん種を蒔く時に表面を削ったり、草を削ったり、土寄せしたり、芋を収穫する時に掘り起こしたり、鍬で土を起こす作業は当たり前。
そういう柔軟にやっていくためにも「自給農法」は分かりやすいよ。

あっこちゃんがナンを作った。

カレーの残り、キュウリ、じゃがいもの豆腐マヨネーズ和え。
カレーの残りがあったからこうなった。
じゃがいもの和えものも、玉ねぎとミョウガの酢漬けなどと残りものの合わせ技。
早朝の野良仕事は気持ちがいい。
毎日のようにノコギリを使ってた野遊は右手が使えなくなり、土歩に指示して切ってもらう。
ギプス生活にも慣れてきて、それなりに工夫して遊んでる。
一日目で平らになった所から大きな草の根を取り除いて、畝を作る作業。
夕方に小雨があって涼しくて気持ちよかった。
小さいとはいえ雑木の根っこが強靭でてこずった。
根っこパワー凄いねー。
草でもかなり太くて強い根もある。
何年間も草生えっぱなしだとちょっと大変。
だからと言って。
「畑を放置しておくと、土地が荒れて野菜を作れなくなる。」という変な常識があるけど、完全な間違い。
草茫々で放置される程土地は豊かになる。
誰も耕しもしないし、肥料もやらないのにナゼ森の木々は育つのか?
自然の生態系が完全に回っていれば、草、虫、微生物、酵素、、、様々な要素で大木が育つ環境になる。
畑も一緒。
それが不耕起自然農の根幹。
ほったらかし程いいものはない。
何しろ人為的に肥料や農薬を蒔いて不自然な状況になっていないから。
今回のように畝立ての時に木や草の根を取り除く作業がちょい大変なだけで、土そのものは豊かになってる。
畝は1、4m幅、水路というか通路が60㎝。
これは妹の雅の実践してる「糸川式自給農法」のノウハウ。
この異常に広い通路に刈った草、生ゴミなどを敷き、土寄せの時のマルチ&肥料として使う。
広くて作業性の良さは一回やると、狭い通路では出来ないほどだとか。
で、試しにやってみることにした。
http://www.jikyunoho.org/index.htm
これが「自給農法」のサイト
自然農を応用して、自給用に特化してアドバンスした分かりやすい農法。
自分で食べるためと出荷するためでは全く別モノ。
そこが農業と農の違い。
家庭菜園で化学肥料や耕運機がないといけないというのは、絶対にオカシイ。
ところが、自然農の本読んで「耕してはいけないのか!」とまた初心者は変に縛られてしまう。
いけないのでなくって、基本的にその方がよく出来るから。
もちろん種を蒔く時に表面を削ったり、草を削ったり、土寄せしたり、芋を収穫する時に掘り起こしたり、鍬で土を起こす作業は当たり前。
そういう柔軟にやっていくためにも「自給農法」は分かりやすいよ。
あっこちゃんがナンを作った。
カレーの残り、キュウリ、じゃがいもの豆腐マヨネーズ和え。
カレーの残りがあったからこうなった。
じゃがいもの和えものも、玉ねぎとミョウガの酢漬けなどと残りものの合わせ技。
タグ :農
2012年09月03日
畑の拡張
廃材天国の敷地内に植えたイチジクがジャンジャン実ってきてる。

今年は雨が少ないからか、甘みが強い。
野遊も傷みや腫れはなくなって、元気になってきた。

次々と実っていくのを毎日見に行くのが楽しい。
自分で植えた果物は年に一度の本当に一瞬の旬。
その、年に一回か二回食べる感動で十分満足する。
これこそがマクロビオティック(身土不二)の基本。
「マクロビでは果物を食べない。」とか、まことしやかに言われたりする。
でも桜沢如一師の本に肉、魚や果物を食べてはいけないと一言も書いてない。
自分の身体の状態と食べるもの、その陰陽の性質を見極める研究がマクロビオティック。
〇〇がいい、△△が悪いという絶対的な判断などできない。
人工的に作りだした不自然なものは大抵悪いけど。
放射能や砂糖は極陰性。
その季節に露地で採れないものや熱帯じゃないと栽培できないものを日本で常食することにも大きな問題がある。
それと、時期的に冬野菜の準備に入らないといけない。
今のキッチンの前の菜園はそこまで広くなく、拡張したいとあっこちゃんが前から言ってる。
僕は管理する場所が増えるので、そこまで拡張に前向きではなかった。
どうしても菜園をやりたい人はと言うとあっこちゃん。
一軒目の廃材ハウスの時は全部僕がやってた。
今現在は彼女の方が菜園に前向き。
こういう嗜好性もお互いに変化する。
その都度話し合って、やるやらないを決めた方がいい。
常々僕は「自分のやりたい事だけしかしない。」と言ってる。
それはこの権力&お金社会の常識という狂った生き方から脱するため。
決してその「やりたい事」の中には家族や他人に喜ばれないことや、健康や環境的に永続できない事は含まれない。

草茫々の所を菜園が出来るように開墾するのは僕が得意。
したいしたくないだけじゃなく、得意不得意というのもある。
タイヤショベルで押したり、ツルハシや鍬での労働という行為そのものがスポーツのようで楽しい。

自然に生えた雑木を切ったり、根を掘り起こしたりするのもあっこちゃんには大変。
僕がやると一瞬で終わる。
僕は切らなくてええんちゃうと言うけど、彼女は「成らない木は要らない。」と即決。

整地して鍬で草の根を削ってると、土歩が「やらせてー!」と寄って来た。
大人のやってる労働が彼等にとっては格好の遊び。
小さいうちは「やめたくなったー。」とすぐに止めることも多いけど、次第に続くようになってきた。
そういうのも野遊と土歩ではまた、得意なことの違いがあって面白い。
この生活(仕事)はやりたい事が山ほどあるけど、いつまでにしないといけないという期限がない。
一日をヒマで退屈しないように、何か労働して楽しみたい。
という超余裕の境地。
さあ、今日は何しよっかなー?
今年は雨が少ないからか、甘みが強い。
野遊も傷みや腫れはなくなって、元気になってきた。
次々と実っていくのを毎日見に行くのが楽しい。
自分で植えた果物は年に一度の本当に一瞬の旬。
その、年に一回か二回食べる感動で十分満足する。
これこそがマクロビオティック(身土不二)の基本。
「マクロビでは果物を食べない。」とか、まことしやかに言われたりする。
でも桜沢如一師の本に肉、魚や果物を食べてはいけないと一言も書いてない。
自分の身体の状態と食べるもの、その陰陽の性質を見極める研究がマクロビオティック。
〇〇がいい、△△が悪いという絶対的な判断などできない。
人工的に作りだした不自然なものは大抵悪いけど。
放射能や砂糖は極陰性。
その季節に露地で採れないものや熱帯じゃないと栽培できないものを日本で常食することにも大きな問題がある。
それと、時期的に冬野菜の準備に入らないといけない。
今のキッチンの前の菜園はそこまで広くなく、拡張したいとあっこちゃんが前から言ってる。
僕は管理する場所が増えるので、そこまで拡張に前向きではなかった。
どうしても菜園をやりたい人はと言うとあっこちゃん。
一軒目の廃材ハウスの時は全部僕がやってた。
今現在は彼女の方が菜園に前向き。
こういう嗜好性もお互いに変化する。
その都度話し合って、やるやらないを決めた方がいい。
常々僕は「自分のやりたい事だけしかしない。」と言ってる。
それはこの権力&お金社会の常識という狂った生き方から脱するため。
決してその「やりたい事」の中には家族や他人に喜ばれないことや、健康や環境的に永続できない事は含まれない。
草茫々の所を菜園が出来るように開墾するのは僕が得意。
したいしたくないだけじゃなく、得意不得意というのもある。
タイヤショベルで押したり、ツルハシや鍬での労働という行為そのものがスポーツのようで楽しい。
自然に生えた雑木を切ったり、根を掘り起こしたりするのもあっこちゃんには大変。
僕がやると一瞬で終わる。
僕は切らなくてええんちゃうと言うけど、彼女は「成らない木は要らない。」と即決。
整地して鍬で草の根を削ってると、土歩が「やらせてー!」と寄って来た。
大人のやってる労働が彼等にとっては格好の遊び。
小さいうちは「やめたくなったー。」とすぐに止めることも多いけど、次第に続くようになってきた。
そういうのも野遊と土歩ではまた、得意なことの違いがあって面白い。
この生活(仕事)はやりたい事が山ほどあるけど、いつまでにしないといけないという期限がない。
一日をヒマで退屈しないように、何か労働して楽しみたい。
という超余裕の境地。
さあ、今日は何しよっかなー?
タグ :菜園
2012年07月25日
このぐらいのカオスぶりがまたいいね
インドの大学に行ってるタッキーが帰ってきてる。
帰省の度にウチに寄ってくれてる。

ビワエキス作りのためのビワの葉を洗ってもらう。
この葉は近所のビワ畑から採らせてもらう。

僕はサッシの枠の周りの隙間を埋める作業。
出番の多い、畳屋でもらえるゴザ。
もらいに行って、「一束もらって行きますよ。」と顔なじみの職人さんに言うと、「一つと言わずに!」と2、3束軽トラの荷台に積み込んでくれる。

こういう斜めの複雑な形状の所が難しい。

柔軟性があるんで、ガンタッカーで強引に留めまくる。
冬に寒くないようにという目的もあるし、今は蚊が入らないためなので、小さな隙間も徹底的に埋める。

ガラスも入れて、外観はこんな感じ。
網戸はボロくなってるので、張り替えないといけない。

妹の雅も京都から帰って来てる。
「金時人参は7月中が蒔きどきやで!」と言われて、丁度今まで人参を植えてた場所に植えることにした。
不耕起と言っても耕運機で耕さないだけで、平鍬で表面を削って、備中鍬で軽く混ぜる。
雅は京都の糸川さんという師匠の元で畑をやってる。
「糸川式自給農法」と言う長年のノウハウを教えてもらいながらも、自分で実践して何年も経験を積んでるんで、「へー!」と僕も教わることが多い。
その畑の野菜を使って、手作りのフードを出店したり、ケータリングを受けたりするのを生業にしてる。
兄妹で似たような事やってる。
ま、弟の所も同類。

少し溝を作って、たっぷりと水をやって人参を蒔く場所を作る。
これは後で水を遣ったりしないようにするため。
それと溝は、大雨が降った時に流れてしまうの防ぐ。
人参って発芽させるのが難しい。
大根や葉物などは超簡単やけどね。
人参の種は軽くて小さい。
発芽のためには覆土も最小限にしておかないといけないし。
で、編み出されたのが糸川式のノウハウ。
凄い!
理にかなってる!

種に灰をまぶす。
人参やホウレン草などは酸性土壌を嫌うから。

種を蒔いた後はうっすらと覆土して、パンパン叩いてしっかり鎮圧する。
これも種が流れないため。
種を蒔いた溝の上には草を置いて、乾燥を防ぐ。
この草が湿る程度にサラッと水やりすると一週間で発芽するそうな。
ナータンとネオンくんも夕方来てて、手伝ってくれた。
というか、彼らも雅のノウハウを勉強したくて一生懸命。

ご飯もみんなで作る。
インド帰りのタッキーがスパイスを色々持って来てくれてて、カレーパーティー。
一番上のはウチの鶏さんの茹で卵を揚げたのが入ったカレー。
次がナスとキュウリのカレー。
サラダは定番の豆乳と梅酢のサッパリ系。
一番下のちっこいのはシソとミントのアチャール。
カレーにはチリは入れてなくて子どもでも十分に食べられる。
アチャール(インドの漬けもの)はかなりホットで、大人はそれをつけながら食べると丁度いい。

これは雅の焼いてきた重いパン。
薄くスライスしてカリカリに焼くとつけ合わせにいい。
上から、ナスペースト、豆腐のディップ、砂糖ナシの米飴マーマレード。

トミーも合流して、大勢でのディナーになった。
トミーは10月のテント劇「どくんご」と同時開催の「手作り市」の事で来てくれてた。
そろそろ出店者さん募集していかななー。
今年は10/20(土)、21(日)でっせー!
オリジナルで一から手作りのフードや雑貨の作家さんも来たり、マッサージやヒーリング系の人も!
みんなで宣伝して盛り上げて行こう!!

初対面と思いきや、クロマニョンズのライブの最前列で一緒だったそう。
「あー、あの時ぶつかってきた!」と。
どっちもロック好き石屋ということで、超盛り上がってた!
帰省の度にウチに寄ってくれてる。
ビワエキス作りのためのビワの葉を洗ってもらう。
この葉は近所のビワ畑から採らせてもらう。
僕はサッシの枠の周りの隙間を埋める作業。
出番の多い、畳屋でもらえるゴザ。
もらいに行って、「一束もらって行きますよ。」と顔なじみの職人さんに言うと、「一つと言わずに!」と2、3束軽トラの荷台に積み込んでくれる。
こういう斜めの複雑な形状の所が難しい。
柔軟性があるんで、ガンタッカーで強引に留めまくる。
冬に寒くないようにという目的もあるし、今は蚊が入らないためなので、小さな隙間も徹底的に埋める。
ガラスも入れて、外観はこんな感じ。
網戸はボロくなってるので、張り替えないといけない。
妹の雅も京都から帰って来てる。
「金時人参は7月中が蒔きどきやで!」と言われて、丁度今まで人参を植えてた場所に植えることにした。
不耕起と言っても耕運機で耕さないだけで、平鍬で表面を削って、備中鍬で軽く混ぜる。
雅は京都の糸川さんという師匠の元で畑をやってる。
「糸川式自給農法」と言う長年のノウハウを教えてもらいながらも、自分で実践して何年も経験を積んでるんで、「へー!」と僕も教わることが多い。
その畑の野菜を使って、手作りのフードを出店したり、ケータリングを受けたりするのを生業にしてる。
兄妹で似たような事やってる。
ま、弟の所も同類。
少し溝を作って、たっぷりと水をやって人参を蒔く場所を作る。
これは後で水を遣ったりしないようにするため。
それと溝は、大雨が降った時に流れてしまうの防ぐ。
人参って発芽させるのが難しい。
大根や葉物などは超簡単やけどね。
人参の種は軽くて小さい。
発芽のためには覆土も最小限にしておかないといけないし。
で、編み出されたのが糸川式のノウハウ。
凄い!
理にかなってる!
種に灰をまぶす。
人参やホウレン草などは酸性土壌を嫌うから。
種を蒔いた後はうっすらと覆土して、パンパン叩いてしっかり鎮圧する。
これも種が流れないため。
種を蒔いた溝の上には草を置いて、乾燥を防ぐ。
この草が湿る程度にサラッと水やりすると一週間で発芽するそうな。
ナータンとネオンくんも夕方来てて、手伝ってくれた。
というか、彼らも雅のノウハウを勉強したくて一生懸命。
ご飯もみんなで作る。
インド帰りのタッキーがスパイスを色々持って来てくれてて、カレーパーティー。
一番上のはウチの鶏さんの茹で卵を揚げたのが入ったカレー。
次がナスとキュウリのカレー。
サラダは定番の豆乳と梅酢のサッパリ系。
一番下のちっこいのはシソとミントのアチャール。
カレーにはチリは入れてなくて子どもでも十分に食べられる。
アチャール(インドの漬けもの)はかなりホットで、大人はそれをつけながら食べると丁度いい。
これは雅の焼いてきた重いパン。
薄くスライスしてカリカリに焼くとつけ合わせにいい。
上から、ナスペースト、豆腐のディップ、砂糖ナシの米飴マーマレード。
トミーも合流して、大勢でのディナーになった。
トミーは10月のテント劇「どくんご」と同時開催の「手作り市」の事で来てくれてた。
そろそろ出店者さん募集していかななー。
今年は10/20(土)、21(日)でっせー!
オリジナルで一から手作りのフードや雑貨の作家さんも来たり、マッサージやヒーリング系の人も!
みんなで宣伝して盛り上げて行こう!!
初対面と思いきや、クロマニョンズのライブの最前列で一緒だったそう。
「あー、あの時ぶつかってきた!」と。
どっちもロック好き石屋ということで、超盛り上がってた!
2012年06月29日
コツコツ作業はやってりゃ出来る
田植え2日目。
昨日は高松からヤンちゃんが来てくれた。

にこちゃんもやってる。

昨日は野遊も学校から帰ってきて植えた。

左が稲の苗で右は雑草。

苗取り班がある程度は仕分けしてくれてるけど、混じってる。
赤い根っこのがそう。
触るとフニャッとして柔らかいのが雑草で、稲は固くてしっかりしてる。
根は赤くなくて見分けにくいのもある。
最終判断は葉の根元にウブ毛があるかどうか。
ウブ毛があるのが稲でないのが雑草。
慣れるとすぐに分かるけど、初めて植える人にはちょっと難しい。
後で草が植えられてるのは僕らが直す。
初めて田植えに参加した人の多くが、「みんなでやるからできるんですねー。」と言う。
確かにみんなでやるのは楽しいし、速い。
一軒目の廃材ハウスの近くの棚田(5枚で一反分)を借りて一人で植えてた時は一週間以上はかかってた。
暑くてしんどい時もあったけど、植えてた。
不耕起やったし、遅々として進まない。
それでも廃材建築を一休みして植えてた。
休憩の時には側に成ってる夏みかんを食べながら。
植えてりゃ、植え終わる。
植えりゃ水入れる。
丸亀と違って石組の棚田で水が漏れだしたりして畔塗りをし直したり。
ジャンボタニシも居なかったので、田に這いつくばって草取りもした。
ソコソコは採れて、大家さんの河野さんの所で籾すりしてもらった。
農作業ってコツコツ仕事やから一人で出来ることが多い。
廃材建築にしても、一人でコツコツやってきたし。
出来たのを後で眺めれば「おおー!」と思うだけ。
コツコツ仕事は延々と毎日やってりゃ、いつかは出来る。
逆に「みんなでやらないと出来ない。」という事はない。
一人ででも毎日やってるから、段々みんなが集まって来る。
そういう順序。
まず、出来ない環境を排除する。
自分の時間を切り売りしない。
勤めに行かない、バイトをしない、それと同時に金のかからない生活の構築。
金がかからんから稼ぐ必要がないという順序。
そうして莫大な時間を自由に使える。
そうしてきたし、これからもそうする。

ガシラ(小さいメバル)のから揚げとチヌの塩焼き。

コンニャクのタン塩風。

豆腐のフワフワ焼きの餡かけ。

92歳のひいおばあちゃんとノワくん。
半寝たきりの生活から、自分で台所まで来てご飯を食べられるようにまでなった。
夜明け前から真っ暗になるまで植えてたと、ばあちゃん。
一人で一日一反植えてたと!?
親戚3家族で3軒分の田植えをしてたそうな。
男は牛使って代掻きや苗取り、女が田植えの選手だったと。
で、自分たちの田が終われば、賃植えとして他の田んぼにも植えに行ってたとか。
一体、一人何反植えてたんやーーー???
こういう話を聞くと、益々スイッチ入るよねー。

みんなでご飯。
さあ、今日も植えるぞーーー!!!
昨日は高松からヤンちゃんが来てくれた。
にこちゃんもやってる。
昨日は野遊も学校から帰ってきて植えた。
左が稲の苗で右は雑草。
苗取り班がある程度は仕分けしてくれてるけど、混じってる。
赤い根っこのがそう。
触るとフニャッとして柔らかいのが雑草で、稲は固くてしっかりしてる。
根は赤くなくて見分けにくいのもある。
最終判断は葉の根元にウブ毛があるかどうか。
ウブ毛があるのが稲でないのが雑草。
慣れるとすぐに分かるけど、初めて植える人にはちょっと難しい。
後で草が植えられてるのは僕らが直す。
初めて田植えに参加した人の多くが、「みんなでやるからできるんですねー。」と言う。
確かにみんなでやるのは楽しいし、速い。
一軒目の廃材ハウスの近くの棚田(5枚で一反分)を借りて一人で植えてた時は一週間以上はかかってた。
暑くてしんどい時もあったけど、植えてた。
不耕起やったし、遅々として進まない。
それでも廃材建築を一休みして植えてた。
休憩の時には側に成ってる夏みかんを食べながら。
植えてりゃ、植え終わる。
植えりゃ水入れる。
丸亀と違って石組の棚田で水が漏れだしたりして畔塗りをし直したり。
ジャンボタニシも居なかったので、田に這いつくばって草取りもした。
ソコソコは採れて、大家さんの河野さんの所で籾すりしてもらった。
農作業ってコツコツ仕事やから一人で出来ることが多い。
廃材建築にしても、一人でコツコツやってきたし。
出来たのを後で眺めれば「おおー!」と思うだけ。
コツコツ仕事は延々と毎日やってりゃ、いつかは出来る。
逆に「みんなでやらないと出来ない。」という事はない。
一人ででも毎日やってるから、段々みんなが集まって来る。
そういう順序。
まず、出来ない環境を排除する。
自分の時間を切り売りしない。
勤めに行かない、バイトをしない、それと同時に金のかからない生活の構築。
金がかからんから稼ぐ必要がないという順序。
そうして莫大な時間を自由に使える。
そうしてきたし、これからもそうする。
ガシラ(小さいメバル)のから揚げとチヌの塩焼き。
コンニャクのタン塩風。
豆腐のフワフワ焼きの餡かけ。
92歳のひいおばあちゃんとノワくん。
半寝たきりの生活から、自分で台所まで来てご飯を食べられるようにまでなった。
夜明け前から真っ暗になるまで植えてたと、ばあちゃん。
一人で一日一反植えてたと!?
親戚3家族で3軒分の田植えをしてたそうな。
男は牛使って代掻きや苗取り、女が田植えの選手だったと。
で、自分たちの田が終われば、賃植えとして他の田んぼにも植えに行ってたとか。
一体、一人何反植えてたんやーーー???
こういう話を聞くと、益々スイッチ入るよねー。
みんなでご飯。
さあ、今日も植えるぞーーー!!!
タグ :田植え
2012年06月28日
田植えスタート
いよいよ田植えスタート。

まず、朝は苗取りから。

ワラでくくった苗を予め田んぼに投げ込んでおく。

昔ながらの定規を使って植えていく。
野遊が学校でいなかったけど、イッサと土歩は活躍した。
ゆかりちゃんのお姉さんのユキエさん、関東から原発震災で移住してきたナオミさんも加わって大勢で植える。
二人とも初めてと言うけど、誰でも出来る。

お昼は外で。
ゆかりちゃんがノワくんのお守をしながら料理を担当してくれた。
写真では分からんけど玉ネギのステーキはびっくりする美味しさやった。
ノワくんも10ヶ月、超丸々と太ってきた。
ウチの子3人もこんなんやった。

何やかんや喋りながらの作業。
黙々と必死でノルマをこなすような仕事じゃない。

にこちゃんも田植えデビュー。

夜ごはんもゆかりちゃんが作ってくれた。
インゲン豆と金時豆のクリームコロッケ風。
生クリームや牛乳を使わないのは当たり前としても、豆乳すら使ってない。
トロトロに煮た豆と塩と玄米。
ほんとにクリーミーで美味しかった。

揚げ物に対してヒジキのマリネとキャベツのサラダもホッとするやさしさ。
田植えという作業そのものも楽しいけど、みんなで集まってワイワイ喋りながらの作業。
作業の合間の休憩はあっこスイーツを食べながら、お昼や夜のみんなでご飯も楽しみ。
立派な固い苗にしろ、この苗を田に植えて超分ケツして堂々たる稲に成長するにしても当たり前に約束されてる。
それは別に特別な事じゃない。
人間様が作ってる訳ではない。
籾を田におろす。
苗を田に植える。
確かにそういう補助的な作業は人間がやってる。
でも、育つのは籾の力。
太陽のパワー。
水の恵み。
そういう自然の力が「生きていくのに必要」な人間にとって最も大切な事。
原発再稼働を「国民の生活を守る」という時代錯誤の総理や、この政治を支えてるのが我々国民。
その茶番にあきれてテレビにツッコミ入れるよりも、田に立つんだ!
籾を蒔く。
それが大事やし、それで十分。
籾が稲になり、たわわにお米がとれる。
そのお米を毎日玄米で頂く。
農業で生活できない。
それは大型機械を買うから。
農で生活する。
当たり前に誰でもが出来るし、営々と先祖がやってきた。
食べるもん作って喰えないという倒錯は起こり得ないぞ。
こんなにも単純で当然の農に関わる生活だったり、自給自足的な生活が「退職してから」とか「将来の憧れ」になってるのはなんでだ???
稼がなくてはならない!
成功しないといけない!
社会的な地位を得て立派な人にならなければいけない!
、、、、、。
学校教育やマスコミの社会的な洗脳なくして成り立たたんよね。
最大の成功とは自分のしたい生活を日々満喫できること。
ココ大事なポイントよー。
時間泥棒と取引きした成功などクソ喰らえ。
平穏で自分たちだけの自給自足は実現可能だと一軒目の廃材ハウスの生活で確信した。
それだけじゃあつまらん。
「革命生活」と銘打った以上は罵られようとも、このブログでの発信はエンドレスだ。
原発再稼働、国家破産、、、様々な社会問題に立ち向かう生活だ。
武装や宗教とは一味違う。
何しろ毎日の生活やもん。
そしてその生活を支えるのは「自然の力」。
太陽や水から始まって、菌類、バクテリア、酵素、波動、量子からヒモ、暗黒物質まで宇宙の構成要素。
その絶対的な自然の一部に、この人間様も属してる。
そしてその人間が種を蒔くという作業をする。
この田んぼから一年分のお米が収穫できるんやからねー。
余裕シャクシャクじゃん!!!
それと同時に、6/29は官邸前、6/30は大飯原発、の直接行動も大事!!!
http://www.youtube.com/watch?v=xi3atPzXYXc&feature=player_embedded
まず、朝は苗取りから。
ワラでくくった苗を予め田んぼに投げ込んでおく。
昔ながらの定規を使って植えていく。
野遊が学校でいなかったけど、イッサと土歩は活躍した。
ゆかりちゃんのお姉さんのユキエさん、関東から原発震災で移住してきたナオミさんも加わって大勢で植える。
二人とも初めてと言うけど、誰でも出来る。
お昼は外で。
ゆかりちゃんがノワくんのお守をしながら料理を担当してくれた。
写真では分からんけど玉ネギのステーキはびっくりする美味しさやった。
ノワくんも10ヶ月、超丸々と太ってきた。
ウチの子3人もこんなんやった。
何やかんや喋りながらの作業。
黙々と必死でノルマをこなすような仕事じゃない。
にこちゃんも田植えデビュー。
夜ごはんもゆかりちゃんが作ってくれた。
インゲン豆と金時豆のクリームコロッケ風。
生クリームや牛乳を使わないのは当たり前としても、豆乳すら使ってない。
トロトロに煮た豆と塩と玄米。
ほんとにクリーミーで美味しかった。
揚げ物に対してヒジキのマリネとキャベツのサラダもホッとするやさしさ。
田植えという作業そのものも楽しいけど、みんなで集まってワイワイ喋りながらの作業。
作業の合間の休憩はあっこスイーツを食べながら、お昼や夜のみんなでご飯も楽しみ。
立派な固い苗にしろ、この苗を田に植えて超分ケツして堂々たる稲に成長するにしても当たり前に約束されてる。
それは別に特別な事じゃない。
人間様が作ってる訳ではない。
籾を田におろす。
苗を田に植える。
確かにそういう補助的な作業は人間がやってる。
でも、育つのは籾の力。
太陽のパワー。
水の恵み。
そういう自然の力が「生きていくのに必要」な人間にとって最も大切な事。
原発再稼働を「国民の生活を守る」という時代錯誤の総理や、この政治を支えてるのが我々国民。
その茶番にあきれてテレビにツッコミ入れるよりも、田に立つんだ!
籾を蒔く。
それが大事やし、それで十分。
籾が稲になり、たわわにお米がとれる。
そのお米を毎日玄米で頂く。
農業で生活できない。
それは大型機械を買うから。
農で生活する。
当たり前に誰でもが出来るし、営々と先祖がやってきた。
食べるもん作って喰えないという倒錯は起こり得ないぞ。
こんなにも単純で当然の農に関わる生活だったり、自給自足的な生活が「退職してから」とか「将来の憧れ」になってるのはなんでだ???
稼がなくてはならない!
成功しないといけない!
社会的な地位を得て立派な人にならなければいけない!
、、、、、。
学校教育やマスコミの社会的な洗脳なくして成り立たたんよね。
最大の成功とは自分のしたい生活を日々満喫できること。
ココ大事なポイントよー。
時間泥棒と取引きした成功などクソ喰らえ。
平穏で自分たちだけの自給自足は実現可能だと一軒目の廃材ハウスの生活で確信した。
それだけじゃあつまらん。
「革命生活」と銘打った以上は罵られようとも、このブログでの発信はエンドレスだ。
原発再稼働、国家破産、、、様々な社会問題に立ち向かう生活だ。
武装や宗教とは一味違う。
何しろ毎日の生活やもん。
そしてその生活を支えるのは「自然の力」。
太陽や水から始まって、菌類、バクテリア、酵素、波動、量子からヒモ、暗黒物質まで宇宙の構成要素。
その絶対的な自然の一部に、この人間様も属してる。
そしてその人間が種を蒔くという作業をする。
この田んぼから一年分のお米が収穫できるんやからねー。
余裕シャクシャクじゃん!!!
それと同時に、6/29は官邸前、6/30は大飯原発、の直接行動も大事!!!
http://www.youtube.com/watch?v=xi3atPzXYXc&feature=player_embedded
タグ :田植え
2012年06月27日
最高の苗
今日から田植え。
3~4日かけて植えていく。
もっとかかってもノープロブレム。
昨日から苗取りをしてる。
親父、親父の所の陶芸の作業に来てるまっちゃん、お袋、土歩、僕。
野遊は久しぶりの学校やった。
今日の田植えは弟夫婦やあっこちゃん、他にも県内の友人が何人か来る。

しっかりした苗で、バッチリ。
手植えの苗はこのぐらいの大きさで丁度いい。
ブチブチ抜いて、バシャバシャ洗って、束にする。
ワラでクルクル巻いて水に浸けておく。
この束を田植えの定規の進行方向に投げて置いていく。
この辺りはジャンボタニシが多く、機械植え用の箱苗のように苗が小さいと喰われる。
ウチではこういうしっかりした苗を手植えするので、大丈夫。
ジャンボタニシは下の固い部分は食べなくて、水に浸かって水面からちょこっと出てるような上の部分からかじる。
一番ジャンボタニシがありがたいのは雑草を食べてくれること。
全く草取りをしなくても、ヒエの一本も生えない。
除草剤をやらない場合、ヒエとコナギという二大雑草に悩まされる。
水口から米ぬかを入れて押さえたり、一般的には田打ち機(車)を押して取る。
それでも取りきれんから、何度も手で直接取る。
梅雨明けの草取りが大変。
大変な作業のことをワクワクというようにしてる以上はそれもまた楽しみの一つでもあるけどね。
午後は観音寺で鈴木博之さんと、ニュージーランドやオーストラリアに口座開設に行った仲間との勉強会。
向こうの日本人スタッフとのFAXのやりとりの仕方やネットバンキングのやり方。
博之さんは金融のプロなので、投資信託や株で失敗した人からの相談が激増してて忙しくなってるとか。
また今度、秋には廃材天国でセミナーをする事になった。
博之さんは20代、30代の若者を中心にやりたいと。
若い時に35年ローンで家買って、呪縛生活に陥る前に気付くと超ラッキー。
ナゼ、廃材天国で金融の話?と思われる人も居ると思うけど、大事やでー。
退職金の使い道に困ってて、という人ばかりが対象じゃない。
20代、30代から基本的な金融の仕組みが分かってれば、今のデフレだ、今後のインフレだとかに流されずに済む。
折角、嫌な仕事辞めてもまたバイトして稼がないと生活できないというんではね。
田舎暮らし、自給自足生活に入りたい若者は多い。
でも転ばぬ先の杖的な心配をしながらでは入れん。
自分の示す姿勢によって、稼がなくても生活できる。
藁しべ長者生活のような廃材生活は日本全国で可能だぞ。
もちろん、ここで言ってるのは財テク的なお金を増やす仕組みじゃない。
お金の不安から解放されるため。
ウチでは夫婦共々お金に対する不安は完璧にない。
あっこちゃんの物欲のなさににはさすがの僕も感服するけど、僕だって「お金ができたらアレが欲しいなー。」とか思わないしね。
宝くじも一回も買ったことがない。
あんな他力本願の真骨頂に何百円たりとも絶対に払えない。
もちろん、美ししくよく切れる包丁やバリバリにクールなチェーンソーは必要不可欠なモノやけど、そういうのは一通り揃ってしまったし。
家賃、借金、ローンナシ。
固定資産税は敷地内に建てさせてあげた看板の収入で相殺されてる。
家が廃材でタダなら今後のメンテナンスも廃材で自分で出来る。
光熱費は文字通りのフリー。
車も天ぷらカーになったし。
天草の松本さんの塩や国産の圧搾菜種油、小豆島の杉樽で寝かせた本醸造の醤油、久保さんの豆腐などの命の源として必要なモノを買っても出費なんかほんのわずか。
後は車検、国保やプロバイダ、電話ぐらいのもの。
陶芸や出店の仕事も自分から営業したりしない。
頼まれた仕事を生活に支障がない範囲で対応できる時だけする。
それで十分お金は余っていく。
何でも自分で出来るという自信に加え、「別にコレ要らんやん。」という「辞められるモノ」が続出してスリムな生活になってくる。
今の現代生活の常識的なものを、「何でも自分たち家族で作ってしまおう。」と意気込んでも中々難しい。
「そもそもコレは要るのか?」
という徹底的なソモソモ論を夫婦で展開させる事が必須。
子どもたちもそれを常に聞いてる。
そして、この廃材生活が当たり前になってる。
こんなチョロ書きの文読んでも???
ココは分かるけどソレってどーなん?とモヤモヤツッコミ満載やと思う。
参考にしたい人は真似すればいいし、したくない人は読むのを辞めろ。
ウチはたまたまこういう廃材生活を選んだ。
全身全霊を挙げて、呪縛からの解放を実践し続ける。
そしてこの簡単で明快なお気楽革命を喚起する。
再稼働反対も廃材集めも理屈じゃない。
したいからするだけ。
他人ごときに自分の芯の気持ちを説明なんか出来なくっても大丈夫だ!
3~4日かけて植えていく。
もっとかかってもノープロブレム。
昨日から苗取りをしてる。
親父、親父の所の陶芸の作業に来てるまっちゃん、お袋、土歩、僕。
野遊は久しぶりの学校やった。
今日の田植えは弟夫婦やあっこちゃん、他にも県内の友人が何人か来る。
しっかりした苗で、バッチリ。
手植えの苗はこのぐらいの大きさで丁度いい。
ブチブチ抜いて、バシャバシャ洗って、束にする。
ワラでクルクル巻いて水に浸けておく。
この束を田植えの定規の進行方向に投げて置いていく。
この辺りはジャンボタニシが多く、機械植え用の箱苗のように苗が小さいと喰われる。
ウチではこういうしっかりした苗を手植えするので、大丈夫。
ジャンボタニシは下の固い部分は食べなくて、水に浸かって水面からちょこっと出てるような上の部分からかじる。
一番ジャンボタニシがありがたいのは雑草を食べてくれること。
全く草取りをしなくても、ヒエの一本も生えない。
除草剤をやらない場合、ヒエとコナギという二大雑草に悩まされる。
水口から米ぬかを入れて押さえたり、一般的には田打ち機(車)を押して取る。
それでも取りきれんから、何度も手で直接取る。
梅雨明けの草取りが大変。
大変な作業のことをワクワクというようにしてる以上はそれもまた楽しみの一つでもあるけどね。
午後は観音寺で鈴木博之さんと、ニュージーランドやオーストラリアに口座開設に行った仲間との勉強会。
向こうの日本人スタッフとのFAXのやりとりの仕方やネットバンキングのやり方。
博之さんは金融のプロなので、投資信託や株で失敗した人からの相談が激増してて忙しくなってるとか。
また今度、秋には廃材天国でセミナーをする事になった。
博之さんは20代、30代の若者を中心にやりたいと。
若い時に35年ローンで家買って、呪縛生活に陥る前に気付くと超ラッキー。
ナゼ、廃材天国で金融の話?と思われる人も居ると思うけど、大事やでー。
退職金の使い道に困ってて、という人ばかりが対象じゃない。
20代、30代から基本的な金融の仕組みが分かってれば、今のデフレだ、今後のインフレだとかに流されずに済む。
折角、嫌な仕事辞めてもまたバイトして稼がないと生活できないというんではね。
田舎暮らし、自給自足生活に入りたい若者は多い。
でも転ばぬ先の杖的な心配をしながらでは入れん。
自分の示す姿勢によって、稼がなくても生活できる。
藁しべ長者生活のような廃材生活は日本全国で可能だぞ。
もちろん、ここで言ってるのは財テク的なお金を増やす仕組みじゃない。
お金の不安から解放されるため。
ウチでは夫婦共々お金に対する不安は完璧にない。
あっこちゃんの物欲のなさににはさすがの僕も感服するけど、僕だって「お金ができたらアレが欲しいなー。」とか思わないしね。
宝くじも一回も買ったことがない。
あんな他力本願の真骨頂に何百円たりとも絶対に払えない。
もちろん、美ししくよく切れる包丁やバリバリにクールなチェーンソーは必要不可欠なモノやけど、そういうのは一通り揃ってしまったし。
家賃、借金、ローンナシ。
固定資産税は敷地内に建てさせてあげた看板の収入で相殺されてる。
家が廃材でタダなら今後のメンテナンスも廃材で自分で出来る。
光熱費は文字通りのフリー。
車も天ぷらカーになったし。
天草の松本さんの塩や国産の圧搾菜種油、小豆島の杉樽で寝かせた本醸造の醤油、久保さんの豆腐などの命の源として必要なモノを買っても出費なんかほんのわずか。
後は車検、国保やプロバイダ、電話ぐらいのもの。
陶芸や出店の仕事も自分から営業したりしない。
頼まれた仕事を生活に支障がない範囲で対応できる時だけする。
それで十分お金は余っていく。
何でも自分で出来るという自信に加え、「別にコレ要らんやん。」という「辞められるモノ」が続出してスリムな生活になってくる。
今の現代生活の常識的なものを、「何でも自分たち家族で作ってしまおう。」と意気込んでも中々難しい。
「そもそもコレは要るのか?」
という徹底的なソモソモ論を夫婦で展開させる事が必須。
子どもたちもそれを常に聞いてる。
そして、この廃材生活が当たり前になってる。
こんなチョロ書きの文読んでも???
ココは分かるけどソレってどーなん?とモヤモヤツッコミ満載やと思う。
参考にしたい人は真似すればいいし、したくない人は読むのを辞めろ。
ウチはたまたまこういう廃材生活を選んだ。
全身全霊を挙げて、呪縛からの解放を実践し続ける。
そしてこの簡単で明快なお気楽革命を喚起する。
再稼働反対も廃材集めも理屈じゃない。
したいからするだけ。
他人ごときに自分の芯の気持ちを説明なんか出来なくっても大丈夫だ!
2012年06月26日
田んぼの代掻き
いよいよ田植えが近づいてきた。

苗代も順調。
毎年ヒノヒカリの籾を取って置いて植えてる。
最近黒米が混じって、所々に黒い株が育つようになってきた。

バラ撒きで相当大きくしてから植える。
機械植えじゃない昔はこういう苗。

3反の田んぼの代掻き。
トラクターに乗るのは親父。
僕は隅の泥を中へ投げ込む作業。
田んぼの泥は正にアースって感じで気持ちイイーー。
6年間小さい面積を不耕起自然農でやってきたけど、今のこの3反は代掻きして手植え。
無肥料、無農薬、当然除草剤もやらない。
それで、実家と廃材天国、弟家族の一年間の食べる分が採れる。
お米程効率のいい作物はない。
だからこそ、こんだけみんな作ってきた。
一軒目の廃材ハウスの時は山からの水の棚田でいい所やった。
今の実家の田んぼはコンクリートの畔にコンクリートの用水路。
一軒目の廃材ハウスの高瀬の田んぼで作ってる時、自然農の川口由一さんに会いに行った。
「実家の田んぼの回りは下水道はなく、他の家の台所の合成洗剤、他の田の除草剤や農薬も入って来るんです。」
「そういう田んぼで無農薬でやるとすればどうしたらいいでしょう?」
と質問した。
すると、彼は満面の笑みで、「そうですか!秋山くんがそういう田で草を生やし、虫たちが豊かに育つ不耕起をするなら、そこに流れ込んでくる水はどんどん浄化していきます。」
「どんどんやって下さい!。」
と!!!
僕は実家の田んぼの環境は悪く、そんな所でも自然農で無農薬栽培できるのか?という「自分たちが無農薬のものを食べたい。」といういわばエゴ的な環境意識からくるものだった。
この川口さんのマクロな視野の意見にはショックだった。
でも、このことがきっかけで丸亀という市街地郊外に廃材天国を建設したし、ここで薪の生活を実践するし、田んぼや畑もすることになった。
一軒目の家を作ってる時には、将来は徳島や高知の沢の水の飲めるようないい環境の所で自給自足したいと考えてた。
今、毎日通勤の車が通り、ゆめタウンとイオンタウンの見える廃材の家で毎日薪の生活して、家族で手植えの田んぼをしてる。
「自分たちが汚染のない、無農薬の、、、。」という感覚はない。
そやし、少々の化学物質ごとき、ものともしない自然の中の微生物は丸亀の田んぼにもある。
もちろん農薬も化学肥料もなくなった方が素晴らしい環境になるに決まってる。
そのために犠牲になるのは環境だけじゃない。
農家は1反当たり化学肥料に1万円、農薬や除草剤に1万円という大金を使わされてる。
それが住友やモンサントなどの巨体を維持するのに貢献してる。
農業は特にこのバビロンシステムの影響が強い。
減反政策の補助金でも、自治会で申し合わせて実施してみんなでもらえるという、反対する=即村八分という構図にしてた(今は変わってきてるけど)。
少数の反対派は隣近所の賛成派で潰してしまえるという論理。
これが原発をはじめとする巨大開発の常套手段。
昨日書いた「革命生活」というのは自然農の創設者、福岡正信師の「わら一本の革命」からパクッてる。
「わら一本からでも革命は起こせる。」と戦前のこれから機械化しようという時代にあって、不耕起を提唱した師の存在は大きい。
「草や虫を敵としない、そもそも害虫益虫の別はない。」という、物ごころついた頃にはトラクターとコンバイン世代の僕には超新鮮だった。
「人間のすることは全てが余計なことだ。」
「種を蒔くだけで、後は昼寝をしておけばいい。」
達観した言葉は農を哲学にまで進化させたと言われる。
川口由一さん、木村秋則さんも福岡さんの思想に基づいて実践してこられた。
僕の回りでも、徳島の沖津さん、愛媛の中谷さん、和田さん、野満さんという頼もしい自然農専業農家も活躍されてる。
自然農の捉え方はデモクラティックスクールともリンクする。
田に立てば、自然=自由=自立=自律という事がスッと理解できる。
「信じて待つ」
中々難しいけどねー。
まず、その「信じよう」「待とう」とすることにチャレンジだ!
昨日はミャンマー帰りのトミーがフラッと来た。

セルフ生春巻き。
チマサンチュがよく出来てる。
手作りのハムがアクセントにいい。

久保さんの豆腐の黒豆のおから。
キメが細かくて美味しいんよー。

つるむらさきと固もめんの炒め煮。
今年はつるむらさきの自生の勢いが半端ない。

セルフ巻きは楽しい。

トミーが洞窟で掘ってきた石のお土産を手探りで選ぶ。

オーガニックの石鹸も。
苗代も順調。
毎年ヒノヒカリの籾を取って置いて植えてる。
最近黒米が混じって、所々に黒い株が育つようになってきた。
バラ撒きで相当大きくしてから植える。
機械植えじゃない昔はこういう苗。
3反の田んぼの代掻き。
トラクターに乗るのは親父。
僕は隅の泥を中へ投げ込む作業。
田んぼの泥は正にアースって感じで気持ちイイーー。
6年間小さい面積を不耕起自然農でやってきたけど、今のこの3反は代掻きして手植え。
無肥料、無農薬、当然除草剤もやらない。
それで、実家と廃材天国、弟家族の一年間の食べる分が採れる。
お米程効率のいい作物はない。
だからこそ、こんだけみんな作ってきた。
一軒目の廃材ハウスの時は山からの水の棚田でいい所やった。
今の実家の田んぼはコンクリートの畔にコンクリートの用水路。
一軒目の廃材ハウスの高瀬の田んぼで作ってる時、自然農の川口由一さんに会いに行った。
「実家の田んぼの回りは下水道はなく、他の家の台所の合成洗剤、他の田の除草剤や農薬も入って来るんです。」
「そういう田んぼで無農薬でやるとすればどうしたらいいでしょう?」
と質問した。
すると、彼は満面の笑みで、「そうですか!秋山くんがそういう田で草を生やし、虫たちが豊かに育つ不耕起をするなら、そこに流れ込んでくる水はどんどん浄化していきます。」
「どんどんやって下さい!。」
と!!!
僕は実家の田んぼの環境は悪く、そんな所でも自然農で無農薬栽培できるのか?という「自分たちが無農薬のものを食べたい。」といういわばエゴ的な環境意識からくるものだった。
この川口さんのマクロな視野の意見にはショックだった。
でも、このことがきっかけで丸亀という市街地郊外に廃材天国を建設したし、ここで薪の生活を実践するし、田んぼや畑もすることになった。
一軒目の家を作ってる時には、将来は徳島や高知の沢の水の飲めるようないい環境の所で自給自足したいと考えてた。
今、毎日通勤の車が通り、ゆめタウンとイオンタウンの見える廃材の家で毎日薪の生活して、家族で手植えの田んぼをしてる。
「自分たちが汚染のない、無農薬の、、、。」という感覚はない。
そやし、少々の化学物質ごとき、ものともしない自然の中の微生物は丸亀の田んぼにもある。
もちろん農薬も化学肥料もなくなった方が素晴らしい環境になるに決まってる。
そのために犠牲になるのは環境だけじゃない。
農家は1反当たり化学肥料に1万円、農薬や除草剤に1万円という大金を使わされてる。
それが住友やモンサントなどの巨体を維持するのに貢献してる。
農業は特にこのバビロンシステムの影響が強い。
減反政策の補助金でも、自治会で申し合わせて実施してみんなでもらえるという、反対する=即村八分という構図にしてた(今は変わってきてるけど)。
少数の反対派は隣近所の賛成派で潰してしまえるという論理。
これが原発をはじめとする巨大開発の常套手段。
昨日書いた「革命生活」というのは自然農の創設者、福岡正信師の「わら一本の革命」からパクッてる。
「わら一本からでも革命は起こせる。」と戦前のこれから機械化しようという時代にあって、不耕起を提唱した師の存在は大きい。
「草や虫を敵としない、そもそも害虫益虫の別はない。」という、物ごころついた頃にはトラクターとコンバイン世代の僕には超新鮮だった。
「人間のすることは全てが余計なことだ。」
「種を蒔くだけで、後は昼寝をしておけばいい。」
達観した言葉は農を哲学にまで進化させたと言われる。
川口由一さん、木村秋則さんも福岡さんの思想に基づいて実践してこられた。
僕の回りでも、徳島の沖津さん、愛媛の中谷さん、和田さん、野満さんという頼もしい自然農専業農家も活躍されてる。
自然農の捉え方はデモクラティックスクールともリンクする。
田に立てば、自然=自由=自立=自律という事がスッと理解できる。
「信じて待つ」
中々難しいけどねー。
まず、その「信じよう」「待とう」とすることにチャレンジだ!
昨日はミャンマー帰りのトミーがフラッと来た。
セルフ生春巻き。
チマサンチュがよく出来てる。
手作りのハムがアクセントにいい。
久保さんの豆腐の黒豆のおから。
キメが細かくて美味しいんよー。
つるむらさきと固もめんの炒め煮。
今年はつるむらさきの自生の勢いが半端ない。
セルフ巻きは楽しい。
トミーが洞窟で掘ってきた石のお土産を手探りで選ぶ。
オーガニックの石鹸も。
2012年06月03日
しょうたくん旅立ったよ
しょうたくんが「原発なくてもええじゃないか号」で旅立った。
奥の乗用車もまだまだ調子いいけど、ウチの自作ルーフキャリア付きバンの積載性が欲しかったよう。
この後、姫路の北の市川町にあるデモクラティックスクール「まっくろくろすけ」の15周年のイベントに向かった。
彼がウチに居候する前は田植えや稲刈りの時にだけ来てた。
でも、本当のきっかけは「教育」。
ウチがホームスクーリングをするようになったのはまっくろくろすけに行ってから。
その本家はボストンにあるサドベリーバレースクール。
僕はそこまで行ってきた。
4歳から18歳までの200人の生徒がチャイムもクラス分けもカリキュラムもナシで自由に学んでる。
スクールじゃないじゃん!?
と普通は思うやろ。
とにかく子どもたちのミーティングでの自治によって運営されてる学校。
校則はないけど、子どもたちがミーティングで決めたルールは山ほど存在する。
自由だけど、責任がある。
もう、40年以上の歴史がある。
自由と自律の共存する軽やかな空気。
そこで学んで卒業する子の大半は、職人系の専門職やアーティストも多いけど、大学に進学するんだそう。
自由なだけに、もっと勉強したくなるんやろね。
サドベリーで聞いたのが「うちの子はもう1年も釣りしかしてません。何とかなりませんか。」という不安な親も居るんだとか。
創設者のダニエルさんは仮にそれが3年になっても何も言わないよ。」と。
やりたい事を辞めさせては絶対に次のステップにはいけない。
事実、何も言わなくてもその釣り好きの子はある日突然コンピューターに目ざめてそればっかり、今は数学にハマってると言ってた。
「将来困る。」のはそのやりたい事を阻害されることだ。
「学歴じゃないよねー。」と建前ではみんな言う。
でも塾がなんでこんなに流行るんだ?
優秀な大学に行って大手企業や官僚、政治家にって金のために悪事を働くのを奨めるのか。
そういう古い価値観はこれから通用しないんだってば。
子どもも大人も、人に言われたことだけをしたり、決められた事をするだけでは本領発揮できない。
本来の生きる力、生きるモチベーション、生きるポテンシャル、、、。
そういうものを眠らせておいてはいけない。
その覚醒において自由とは大前提の当たり前のようなもん。
しょうたくんと同世代のまっくろすろすけの卒業生のひかるくんはよくウチに来てた。
今は結婚して赤ちゃんも生まれ、京都の田舎の家を借り、田畑や廃材建築にも意欲を燃やしてる。
菜園の人参がイイ感じに成長してきた。
ナスやキュウリも順調に育ってる。
不耕起なのでガタガタ。
最近、雨が少ないんで超濃厚なお味。
「信じて待つ」というデモクラティックスクールの理念は自然農と非常に近いものがある。
実際、不耕起自然農を取り入れて農的な生活をしてる仲間にはホームスクーリングの家が多い。
麻婆春雨豆腐に入れた。
豆豉、ニンニク、ショウガ、を利かせると陳健一風の本格派になる。
挽肉が入らなくても干し椎茸などの干物とレンコンやゴボウを入れると旨味が出る。
にこちゃん用に玉ネギのミルフィーユご飯。
タグ :教育
2012年03月31日
栗の接ぎ木
ビニール張りの合間にあっこちゃんの親父さんが来てくれた。
「接ぎ木」の講師として。
彼は備前の実家の裏山に何十種類、100本どろこじゃない果樹を植えてる。
そこからもらってきた栗の実をあっこちゃんが廃材天国に植えてた。
9個植えて、3つ木になった。
去年、早速実をつけた木があった。
それはイガも小さければ実なんか食べる所のないようなものだった。
実生の場合はそういうもので、大きくて甘い実を得るために接ぎ木の技術がある。
大きくて甘いのが全てでもないし、野菜に関しては小さい方が美味しい場合が多いけど、栗や柿のような実物に関しては毎年小さくて甘くないのがなるよりはこういう技術を駆使したい。

もっと小さくてもいいらしいけど、このぐらい大きくなっても接げるんだと。

これも備前の親父さんにもらったブルーベリー。
接ぎ木の前に、「まだあんまし大きくならないんですよ。」と見てもらった。
「これじゃあ、おえんなあ。」
完全にほったらかし過ぎてて、色んな草の根がブルーべりーを取り囲んでて、クワで取り除いてくれた。
やっぱりそういう世話は大事なんやねー。

いよいよクリの接ぎ木。
ゆかりちゃんやハラさんも来てて、みんなに説明しながらやってくれる。

備前の実家から持ってきてくれた穂木をよく研いだナイフで削る。
「ポロタン」と「利平」という二種類持ってきてくれた。
接ぎ木をする今の芽が動く時よりも、穂木を採るのはタイミングが違う。
1月や2月の寒い時に採って、ボロ布に巻いて地中に埋めておくんだとか。

鋸で落として、切り口の形成層にナイフを入れて、手で広げる。

穂木を差し込んだ後はビニールテープをまく。
これだけ太さが違うと二本穂木を植えるんだと。
こうした方が木の修復が早いんだそう。

接ぎ目に雨水が入らないように蜜蝋をぬる。

念の為にビニールを被せて巻きつけて完成。
後は動かさないようにするだけ。
子どもたちのボールなんかが当たってもいけないんで、柵を作ろかな。
いやー。
意外と簡単。
これで、二種類のいい栗の実が採れるとはねー。
「接ぎ木」の講師として。
彼は備前の実家の裏山に何十種類、100本どろこじゃない果樹を植えてる。
そこからもらってきた栗の実をあっこちゃんが廃材天国に植えてた。
9個植えて、3つ木になった。
去年、早速実をつけた木があった。
それはイガも小さければ実なんか食べる所のないようなものだった。
実生の場合はそういうもので、大きくて甘い実を得るために接ぎ木の技術がある。
大きくて甘いのが全てでもないし、野菜に関しては小さい方が美味しい場合が多いけど、栗や柿のような実物に関しては毎年小さくて甘くないのがなるよりはこういう技術を駆使したい。
もっと小さくてもいいらしいけど、このぐらい大きくなっても接げるんだと。
これも備前の親父さんにもらったブルーベリー。
接ぎ木の前に、「まだあんまし大きくならないんですよ。」と見てもらった。
「これじゃあ、おえんなあ。」
完全にほったらかし過ぎてて、色んな草の根がブルーべりーを取り囲んでて、クワで取り除いてくれた。
やっぱりそういう世話は大事なんやねー。
いよいよクリの接ぎ木。
ゆかりちゃんやハラさんも来てて、みんなに説明しながらやってくれる。
備前の実家から持ってきてくれた穂木をよく研いだナイフで削る。
「ポロタン」と「利平」という二種類持ってきてくれた。
接ぎ木をする今の芽が動く時よりも、穂木を採るのはタイミングが違う。
1月や2月の寒い時に採って、ボロ布に巻いて地中に埋めておくんだとか。
鋸で落として、切り口の形成層にナイフを入れて、手で広げる。
穂木を差し込んだ後はビニールテープをまく。
これだけ太さが違うと二本穂木を植えるんだと。
こうした方が木の修復が早いんだそう。
接ぎ目に雨水が入らないように蜜蝋をぬる。
念の為にビニールを被せて巻きつけて完成。
後は動かさないようにするだけ。
子どもたちのボールなんかが当たってもいけないんで、柵を作ろかな。
いやー。
意外と簡単。
これで、二種類のいい栗の実が採れるとはねー。
タグ :接ぎ木
2011年11月26日
芋づくし
廃材天国のせま~い菜園とは別に、お米を作ってる田んぼの近くに親父の菜園がある。
昨日は芋掘り。
ちびっ子たちは松見歯科の定期検診だったんで、しょうたくんと僕とで。

めっちゃでっかい芋が入ってた!

ちょっと並べて干しておく。
他にも里芋も掘ったり、大根の間引き、玉ねぎの苗の植え付けもした。
芋や玉ねぎのようにたくさん作って保存しておくようなものは親父の菜園に頼ってる。
春菊や人参、葉物なんかは廃材天国の菜園で作ってる。
先日のプチ居候の「菜月自然農園」で修行してたユウジくんが植えてくれた葉物も調子よく育ってる。
松見歯科組は遅かったんで、僕としょうたくんとで料理。

ウチの芋料理の定番の大学芋。
しっかり目に素揚げした芋を醤油と味醂を煮詰めたタレに絡める。
フライパンの上のタレの煮詰まり具合がポイント。
ユルイと芋がパリッとしないし、過ぎると焦げて苦くなってしまう。
水飴を使った中華料理のソレとは別物やけど、この方がご飯のおかずになる。

子芋と自家製高野豆腐の煮物。
久保さんの豆腐を冷凍庫に入れて、高野豆腐にしたのが成功した。
スカスカ過ぎる市販の高野豆腐よりもしっかりして美味しい。
煮干しの出汁と醤油と味醂の味付け。
里芋の煮物はほっこりしてホントに美味い。
これも砂糖ナシでも本醸造の調味料を使うことで十分美味しい。

ワケギのチジミ。
ワケギはヌタ和えが代表的やし美味しいけど、コレもいける。
ポン酢で頂く。
アミエビが利いててお酒との相性も抜群。
窯焚き中の瀬戸内の魚料理もよかったけど、やっぱり玄米と野菜料理が基本。
明晰な感覚とバリバリ動ける身体には必須。
脱砂糖、脱市販がまず求められる。
手作りが当たり前になってしまえば、忙しいからとかに関係なく出来るようになる。
何が本当に美味しいのかが分かればブレなくなる。
昨日は芋掘り。
ちびっ子たちは松見歯科の定期検診だったんで、しょうたくんと僕とで。
めっちゃでっかい芋が入ってた!
ちょっと並べて干しておく。
他にも里芋も掘ったり、大根の間引き、玉ねぎの苗の植え付けもした。
芋や玉ねぎのようにたくさん作って保存しておくようなものは親父の菜園に頼ってる。
春菊や人参、葉物なんかは廃材天国の菜園で作ってる。
先日のプチ居候の「菜月自然農園」で修行してたユウジくんが植えてくれた葉物も調子よく育ってる。
松見歯科組は遅かったんで、僕としょうたくんとで料理。
ウチの芋料理の定番の大学芋。
しっかり目に素揚げした芋を醤油と味醂を煮詰めたタレに絡める。
フライパンの上のタレの煮詰まり具合がポイント。
ユルイと芋がパリッとしないし、過ぎると焦げて苦くなってしまう。
水飴を使った中華料理のソレとは別物やけど、この方がご飯のおかずになる。
子芋と自家製高野豆腐の煮物。
久保さんの豆腐を冷凍庫に入れて、高野豆腐にしたのが成功した。
スカスカ過ぎる市販の高野豆腐よりもしっかりして美味しい。
煮干しの出汁と醤油と味醂の味付け。
里芋の煮物はほっこりしてホントに美味い。
これも砂糖ナシでも本醸造の調味料を使うことで十分美味しい。
ワケギのチジミ。
ワケギはヌタ和えが代表的やし美味しいけど、コレもいける。
ポン酢で頂く。
アミエビが利いててお酒との相性も抜群。
窯焚き中の瀬戸内の魚料理もよかったけど、やっぱり玄米と野菜料理が基本。
明晰な感覚とバリバリ動ける身体には必須。
脱砂糖、脱市販がまず求められる。
手作りが当たり前になってしまえば、忙しいからとかに関係なく出来るようになる。
何が本当に美味しいのかが分かればブレなくなる。
2011年11月10日
40年選手の機械で脱穀
ハゼ掛けして天日乾燥してある稲が乾いた。
水分計で平均が14%台になればOK。
稲刈りの時で17、8%だったんで、今年は早いやろなとは思ってた。
大体コンバインで刈った籾は23、4%とか。
それを乾燥機にいれて乾燥させるのに灯油のボイラーで焚く。
機械や石油が要るだけじゃなく、天日乾燥の米とは生命力が変わる。
美味しい美味しくないは主観が強いので置いとくとして、発芽率が大きく変わるのだ。
天日乾燥のお米の籾はほぼ全て発芽する(当たり前)のに対して、乾燥機のは発芽しない米が目立つようになる。
もちろん、乾燥だけじゃなく、化学肥料の有無などにもよる。
有機肥料でも窒素過多なんかは超悪いし。
ウチは無肥料、無農薬、除草剤ナシ、天日乾燥なのでお米のスペック的には最高。

脱穀した後のワラを田んぼ中に広げるのは子どもの仕事。

近所の人が使わなくなってもらったハーベスタ(脱穀機)で脱穀。
40年級の農機具もバリバリ動く。
ディーゼルやし壊れる箇所がそもそも少ないならね。
農機具が高いというのは2、300万もする新車のトラクターにポッパー付きのコンバインの事。
10年しかもたないというのも価値観の問題。
これは農機具でも車でも家電でも一緒。
30年でも40年でも使おうと思えば使える。
ウチは現実に人が捨てるものを頂いて、いけてる訳やからねー。
ただ、しょっちゅう細かいトラブルはあるし、それで作業が中断してもOKと思わないと使えない。
今のところの農機具は、おじいちゃんが生前新車で買ったトラクター、もらいもののバインダーとこのハーベスタの3台。
田植機は手植えなので要らないし、乾燥機もハゼなので要らない。
トラクターが壊れたら不耕起でいけばええし。
バインダーなんかなくても手刈りすればええだけ。
何回も書くけど、10人分のお米を10人で作業すれば、機械なんかなくても超楽勝で一年分自給できる。
子どもと年寄りとを考えて10人分を5人で作業したって楽々。

子どもたちは同じ作業を延々と繰り返すことは出来ない。
手を変え品を変え、盛り上げと張り切ってできる。

いつもの「にこちゃんもするー。」が連発。
「あそこまで運んでみい。」と言うとホントに運んだ。
こっちが「それは無理やろー。」と思ってもこうやってほんとにやったりするから面白い。

「今年は機械のトラブルもなく、順調に終わったなー。」と親父や源と片付けてると、軽トラがハマった。
4駆のローに入れても、一旦滑りだすと押しても引いてもダメ。
ハーベスタで引っ張ると以外と出た。
「無理ならトラクター出してこなな。」と言いながらだったんでラッキー。
やっぱり、一回ぐらいはこういうトラブルがないとね。
「緊急時の工夫と閃き」
これに一番ワクワクするんやから!
水分計で平均が14%台になればOK。
稲刈りの時で17、8%だったんで、今年は早いやろなとは思ってた。
大体コンバインで刈った籾は23、4%とか。
それを乾燥機にいれて乾燥させるのに灯油のボイラーで焚く。
機械や石油が要るだけじゃなく、天日乾燥の米とは生命力が変わる。
美味しい美味しくないは主観が強いので置いとくとして、発芽率が大きく変わるのだ。
天日乾燥のお米の籾はほぼ全て発芽する(当たり前)のに対して、乾燥機のは発芽しない米が目立つようになる。
もちろん、乾燥だけじゃなく、化学肥料の有無などにもよる。
有機肥料でも窒素過多なんかは超悪いし。
ウチは無肥料、無農薬、除草剤ナシ、天日乾燥なのでお米のスペック的には最高。
脱穀した後のワラを田んぼ中に広げるのは子どもの仕事。
近所の人が使わなくなってもらったハーベスタ(脱穀機)で脱穀。
40年級の農機具もバリバリ動く。
ディーゼルやし壊れる箇所がそもそも少ないならね。
農機具が高いというのは2、300万もする新車のトラクターにポッパー付きのコンバインの事。
10年しかもたないというのも価値観の問題。
これは農機具でも車でも家電でも一緒。
30年でも40年でも使おうと思えば使える。
ウチは現実に人が捨てるものを頂いて、いけてる訳やからねー。
ただ、しょっちゅう細かいトラブルはあるし、それで作業が中断してもOKと思わないと使えない。
今のところの農機具は、おじいちゃんが生前新車で買ったトラクター、もらいもののバインダーとこのハーベスタの3台。
田植機は手植えなので要らないし、乾燥機もハゼなので要らない。
トラクターが壊れたら不耕起でいけばええし。
バインダーなんかなくても手刈りすればええだけ。
何回も書くけど、10人分のお米を10人で作業すれば、機械なんかなくても超楽勝で一年分自給できる。
子どもと年寄りとを考えて10人分を5人で作業したって楽々。
子どもたちは同じ作業を延々と繰り返すことは出来ない。
手を変え品を変え、盛り上げと張り切ってできる。
いつもの「にこちゃんもするー。」が連発。
「あそこまで運んでみい。」と言うとホントに運んだ。
こっちが「それは無理やろー。」と思ってもこうやってほんとにやったりするから面白い。
「今年は機械のトラブルもなく、順調に終わったなー。」と親父や源と片付けてると、軽トラがハマった。
4駆のローに入れても、一旦滑りだすと押しても引いてもダメ。
ハーベスタで引っ張ると以外と出た。
「無理ならトラクター出してこなな。」と言いながらだったんでラッキー。
やっぱり、一回ぐらいはこういうトラブルがないとね。
「緊急時の工夫と閃き」
これに一番ワクワクするんやから!
タグ :脱穀