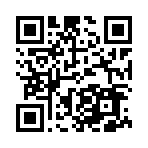2008年07月31日
鉄は儲かるよ
昨日はくず鉄をまとめて売りに行った。
以前同級生で土建屋の社長がダンプに軽く一車で5万になった、という話をしてたのを思い出し、片付けを兼ねていらない鉄製品を持っていく。
午前中軽トラに山盛り一車で18,252円。
「プレス」と言って塊状のしっかりした鉄がキロ56,4円、薄いのや錆びたのは「二級」でキロ33、5円。
要は430キロ積んで行ってこの金額。
去年の年末壊れたユンボとフォークリフトを処分して12万になった時もびっくりしたが、今回みたいにいわゆるゴミを持って行ってこんなになるとは!?
午後にもう一回、370キロで16,622円。
こりゃ側溝の鉄のフタや公園のポール持って行くのも頷ける。
ズーッと騰がってきてここへ来てピークだとか。
鉄だけじゃなく、今までなら処分代の必要だったバッテリー、壊れた農機具、バイクなどもお金になる。
アルミや銅は半端じゃなく高い。
電線などの皮膜を取ったピカ線というのが一番高いらしく、解体した家の配線をわざわざ刃物で剥がし、ピカ線にして持ってくる人もいるんだと。
がばいばあちゃんの世界になってきた。
うちみたいに古い農家など代々続いてる家なら必ず片付けるといらないもので数万円ぐらいすぐに稼げるよ。
もちろんうちもまだまだ出てきそう。
一軒目の廃材ハウスの方にも何やかんや置いてある。
片付けをしてサッパリして儲かるんやからどんどんやろう。
要は中国やインドが経済成長してるからだという。
地下資源を採掘して精製する事を考えると少々高く買っても割りに合うのだろう。
中国のバブルが崩壊すれば値崩れするという見方もある。
どっちにせよ今後は莫大なエネルギーをかけて新しい製品を作るよりもリサイクルの方が経済的にも合うという方向になっていくんだろう。
そりゃリサイクルペーパーの方が新しいペーパーより高いんじゃ買う人は環境オタクだけやもんね。
廃材もおいそれと貰えなくなる時代も来るんだろうか。
ほんとに昔の日本建築に使われてる材はよく肥えた松など今は手に入らないようなものばかり。
それが毎日ユンボで壊され燃やされてる。
古材とか言ってプレミアムな付加価値の高い材として一部には流通してるそうだが、そんなんじゃなくて普通に使うようになって欲しい。
以前同級生で土建屋の社長がダンプに軽く一車で5万になった、という話をしてたのを思い出し、片付けを兼ねていらない鉄製品を持っていく。
午前中軽トラに山盛り一車で18,252円。
「プレス」と言って塊状のしっかりした鉄がキロ56,4円、薄いのや錆びたのは「二級」でキロ33、5円。
要は430キロ積んで行ってこの金額。
去年の年末壊れたユンボとフォークリフトを処分して12万になった時もびっくりしたが、今回みたいにいわゆるゴミを持って行ってこんなになるとは!?
午後にもう一回、370キロで16,622円。
こりゃ側溝の鉄のフタや公園のポール持って行くのも頷ける。
ズーッと騰がってきてここへ来てピークだとか。
鉄だけじゃなく、今までなら処分代の必要だったバッテリー、壊れた農機具、バイクなどもお金になる。
アルミや銅は半端じゃなく高い。
電線などの皮膜を取ったピカ線というのが一番高いらしく、解体した家の配線をわざわざ刃物で剥がし、ピカ線にして持ってくる人もいるんだと。
がばいばあちゃんの世界になってきた。
うちみたいに古い農家など代々続いてる家なら必ず片付けるといらないもので数万円ぐらいすぐに稼げるよ。
もちろんうちもまだまだ出てきそう。
一軒目の廃材ハウスの方にも何やかんや置いてある。
片付けをしてサッパリして儲かるんやからどんどんやろう。
要は中国やインドが経済成長してるからだという。
地下資源を採掘して精製する事を考えると少々高く買っても割りに合うのだろう。
中国のバブルが崩壊すれば値崩れするという見方もある。
どっちにせよ今後は莫大なエネルギーをかけて新しい製品を作るよりもリサイクルの方が経済的にも合うという方向になっていくんだろう。
そりゃリサイクルペーパーの方が新しいペーパーより高いんじゃ買う人は環境オタクだけやもんね。
廃材もおいそれと貰えなくなる時代も来るんだろうか。
ほんとに昔の日本建築に使われてる材はよく肥えた松など今は手に入らないようなものばかり。
それが毎日ユンボで壊され燃やされてる。
古材とか言ってプレミアムな付加価値の高い材として一部には流通してるそうだが、そんなんじゃなくて普通に使うようになって欲しい。
2008年07月29日
あろうことか、、、ヤギが、、、
昨日の朝、ヤギさんが小屋から出ようとしない。
おとといの夕方まで普通に草食べてたのになー。
暑くてバテたんかなーと思ってた。
で、ヤギさんを連れてきた同級生のわきおさんに電話。
牧場のおじさんや獣医に聞いてくれ、多分暑さに参ったんだろうと。
手当てと言っても注射とか栄養補給ぐらいしかないやろうと。
それから容態は急変し、痙攣しはじめて口からは泡。
これは半端じゃない雰囲気。
もう命が終わろうとしてるのが刻一刻と伝わってくる。
病院に連れて行くとかいうレベルじゃない。
もう、みんなで見守ってあげよう、とあっこちゃん。
子どもたち3人と一緒に傍で見守る。
どんどんヤギさんは苦しそうになり、息も絶え絶え。
最期に大きく仰け反って昼前には死んでしまった。
何で、、、?
あっという間の出来事。
まだ小さかったから?
暑さにやられたから?
こんなに簡単に死ぬの?
実はあっこちゃんには分かっていたのかもしれない。
こうなることが。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=861769159&owner_id=2989823
この日記の後も僕が出かけて帰りが遅い時くてヤギの事を忘れてる事にダメダシを受ける。
今は暑いので、朝の7~8時ぐらいまでは何処に繋いでても問題ないが、それ以降は影で草のある所を転々と移動させていかないといけない。
一軒目の廃材ハウスでもヤギは飼った経験があるので(野犬に襲われ食べられてしまった)餌の事など多少ラフに考えていた。
ヤギは生の草と枯れた草、草の種類など自分で必要に応じて食べる。
でもまだ子ヤギだったせいもあるのか、充分に餌が足りてなかったのかもしれない。
とにかく近所で3年程前から飼い出した親戚のおじさんなど、田んぼに稲を干すように草を干したり、あちこちから生の野菜クズをもらってきたり、ソルゴ(飼料作物)を育てたりと凄く手まめに世話をしてる。
あっこちゃんの指摘する点はそこにある。
僕は他の作業を優先して、動物にそこまで愛情と時間をかけていない。
彼女も赤ちゃんがいてそこまで出来ないのは分かってる。
「まず、生き物の世話を優先しよう。」とあっこちゃんは何度も言った。
朝起きて、PCの世話をする僕も「そやな、大事やな。」返事だけは立派にしていた。
鶏の世話、ヤギの世話、子どもたちの世話、ヌカ床の世話、野菜の世話、雑木たちの水やり、、、と、一日のうちの結構なウエイトを占める。
最近僕のスケジュールが外に出る仕事が多かったのもあるが、やっぱり僕は生き物の事を軽く考えていた。
僕がちゃんと世話を出来ないのならわきおさんに相談して無理(飼う事が)ならちゃんと伝えて牧場に帰った方がヤギは幸せなんじゃないのとも言われていた。
命に関しては忙しくて余裕がなくて、、、は通用しない。
と今までも鶏、犬、猫といろいろ飼ってきて分かってるつもりだったのに。
最近一緒にキャンプに行った姫さんにも言われてた。
彼女は何より生き物たちの事を優先する。
いつも忙しくてPCを触る時間もないという彼女は鶏や畑の野菜たち、海の生き物、うちの子どもたちの事もいつも気にかけてくれてる。
「陣は子どもの頃動物飼ったことあるん?」
うちはじいちゃんとばあちゃんが動物はキライでほとんど子ども時代に動物はいなかったが、唯一猫を飼ったことがあった。
小学3,4年生だった。
黒猫でクマという名前で可愛がってた。
ある時ケンカか何かでひどく足を怪我して帰ってきた。
じいちゃんが包帯を巻いたりして手当てしてた。
でもなかなか血が止まらなく、包帯などは噛んで外すし、畳に血のシミが出来るのでじいちゃんは嫌がってた。
そして、ある日じいちゃんは子どもたちに内緒でクマを捨ててきてしまった。
もちろん「何で帰ってこんのやろ?」と知らない僕は毎日疑問に思い、母親など他の家族にしきりに聞いた。
よくは覚えていないが、誰かからじいちゃんが捨ててきたと聞かされた。
ショックだった。
でも小さい頃からじいちゃん子で、躾なども厳しかったうちの雰囲気では「何で捨てたりしたんー!」などと意思表示は出来なかった。
僕は子ども心に傷ついたが、そういうじいちゃんのドライな冷酷さをどこかで受け入れたのかもしれない。
もちろん昔は鶏、牛、羊とうちでも動物を飼ってたそうだが、あくまでも家畜だったのだろう。
今のペットのように変に可愛がったりするはずはない。
でもやっぱり生き物はパートナーとして世話をしないと、人間に飼われた以上は健全には生きられない。
僕に「いや、それは無理やわ。」という決断があればヤギさんを死なせずに済んだと思う。
それでもこのヤギさんがうちに来てくれたのはこういう一連の事を気付かせてくれる為だったのか?
うちの子どもたちがケンカしたり、ゴネたりすると僕はよく怒鳴りつけるが、もっと子どもたちにも優しくせえよというメッセージだったのか?
生き物、特に自分が世話しないと生きられない物はほんとに可愛がれるような気持ちになって飼わないといけない。
超当たり前の事なのだが、僕の中のいい加減さに気付かせてくれた。
わきおさんはじめ、みんながこの廃材天国が面白くなる事を期待してくれてる。
良かれと思って彼もヤギをプレゼントしてくれた。
でも僕の今の許容範囲を超えていた。
でも僕はスゴイ人間でもないし、言わば細かな気配りなどを無視してブルドーザーのようにがむしゃらにやってるからこそ家まで建ててしまえるのかもしれない。
「自分には出来ない!」と言う人が多いが、僕ほどのむちゃくちゃはやりたくないと言う事なのかもしれない。
自画自賛でやってきたが、今回の件は反省する所、学んだ所が多かった。
ありがとうヤギさん。
まだ子ヤギだったのにごめんね。
ヤギさんの教えてくれた事は大きかったよ。
命の世話より優先する仕事はないんやね。
とお祈りしながらみんなで埋めてあげた。
野遊も泣ききながら朝顔の花をとってきてくれた。
おとといの夕方まで普通に草食べてたのになー。
暑くてバテたんかなーと思ってた。
で、ヤギさんを連れてきた同級生のわきおさんに電話。
牧場のおじさんや獣医に聞いてくれ、多分暑さに参ったんだろうと。
手当てと言っても注射とか栄養補給ぐらいしかないやろうと。
それから容態は急変し、痙攣しはじめて口からは泡。
これは半端じゃない雰囲気。
もう命が終わろうとしてるのが刻一刻と伝わってくる。
病院に連れて行くとかいうレベルじゃない。
もう、みんなで見守ってあげよう、とあっこちゃん。
子どもたち3人と一緒に傍で見守る。
どんどんヤギさんは苦しそうになり、息も絶え絶え。
最期に大きく仰け反って昼前には死んでしまった。
何で、、、?
あっという間の出来事。
まだ小さかったから?
暑さにやられたから?
こんなに簡単に死ぬの?
実はあっこちゃんには分かっていたのかもしれない。
こうなることが。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=861769159&owner_id=2989823
この日記の後も僕が出かけて帰りが遅い時くてヤギの事を忘れてる事にダメダシを受ける。
今は暑いので、朝の7~8時ぐらいまでは何処に繋いでても問題ないが、それ以降は影で草のある所を転々と移動させていかないといけない。
一軒目の廃材ハウスでもヤギは飼った経験があるので(野犬に襲われ食べられてしまった)餌の事など多少ラフに考えていた。
ヤギは生の草と枯れた草、草の種類など自分で必要に応じて食べる。
でもまだ子ヤギだったせいもあるのか、充分に餌が足りてなかったのかもしれない。
とにかく近所で3年程前から飼い出した親戚のおじさんなど、田んぼに稲を干すように草を干したり、あちこちから生の野菜クズをもらってきたり、ソルゴ(飼料作物)を育てたりと凄く手まめに世話をしてる。
あっこちゃんの指摘する点はそこにある。
僕は他の作業を優先して、動物にそこまで愛情と時間をかけていない。
彼女も赤ちゃんがいてそこまで出来ないのは分かってる。
「まず、生き物の世話を優先しよう。」とあっこちゃんは何度も言った。
朝起きて、PCの世話をする僕も「そやな、大事やな。」返事だけは立派にしていた。
鶏の世話、ヤギの世話、子どもたちの世話、ヌカ床の世話、野菜の世話、雑木たちの水やり、、、と、一日のうちの結構なウエイトを占める。
最近僕のスケジュールが外に出る仕事が多かったのもあるが、やっぱり僕は生き物の事を軽く考えていた。
僕がちゃんと世話を出来ないのならわきおさんに相談して無理(飼う事が)ならちゃんと伝えて牧場に帰った方がヤギは幸せなんじゃないのとも言われていた。
命に関しては忙しくて余裕がなくて、、、は通用しない。
と今までも鶏、犬、猫といろいろ飼ってきて分かってるつもりだったのに。
最近一緒にキャンプに行った姫さんにも言われてた。
彼女は何より生き物たちの事を優先する。
いつも忙しくてPCを触る時間もないという彼女は鶏や畑の野菜たち、海の生き物、うちの子どもたちの事もいつも気にかけてくれてる。
「陣は子どもの頃動物飼ったことあるん?」
うちはじいちゃんとばあちゃんが動物はキライでほとんど子ども時代に動物はいなかったが、唯一猫を飼ったことがあった。
小学3,4年生だった。
黒猫でクマという名前で可愛がってた。
ある時ケンカか何かでひどく足を怪我して帰ってきた。
じいちゃんが包帯を巻いたりして手当てしてた。
でもなかなか血が止まらなく、包帯などは噛んで外すし、畳に血のシミが出来るのでじいちゃんは嫌がってた。
そして、ある日じいちゃんは子どもたちに内緒でクマを捨ててきてしまった。
もちろん「何で帰ってこんのやろ?」と知らない僕は毎日疑問に思い、母親など他の家族にしきりに聞いた。
よくは覚えていないが、誰かからじいちゃんが捨ててきたと聞かされた。
ショックだった。
でも小さい頃からじいちゃん子で、躾なども厳しかったうちの雰囲気では「何で捨てたりしたんー!」などと意思表示は出来なかった。
僕は子ども心に傷ついたが、そういうじいちゃんのドライな冷酷さをどこかで受け入れたのかもしれない。
もちろん昔は鶏、牛、羊とうちでも動物を飼ってたそうだが、あくまでも家畜だったのだろう。
今のペットのように変に可愛がったりするはずはない。
でもやっぱり生き物はパートナーとして世話をしないと、人間に飼われた以上は健全には生きられない。
僕に「いや、それは無理やわ。」という決断があればヤギさんを死なせずに済んだと思う。
それでもこのヤギさんがうちに来てくれたのはこういう一連の事を気付かせてくれる為だったのか?
うちの子どもたちがケンカしたり、ゴネたりすると僕はよく怒鳴りつけるが、もっと子どもたちにも優しくせえよというメッセージだったのか?
生き物、特に自分が世話しないと生きられない物はほんとに可愛がれるような気持ちになって飼わないといけない。
超当たり前の事なのだが、僕の中のいい加減さに気付かせてくれた。
わきおさんはじめ、みんながこの廃材天国が面白くなる事を期待してくれてる。
良かれと思って彼もヤギをプレゼントしてくれた。
でも僕の今の許容範囲を超えていた。
でも僕はスゴイ人間でもないし、言わば細かな気配りなどを無視してブルドーザーのようにがむしゃらにやってるからこそ家まで建ててしまえるのかもしれない。
「自分には出来ない!」と言う人が多いが、僕ほどのむちゃくちゃはやりたくないと言う事なのかもしれない。
自画自賛でやってきたが、今回の件は反省する所、学んだ所が多かった。
ありがとうヤギさん。
まだ子ヤギだったのにごめんね。
ヤギさんの教えてくれた事は大きかったよ。
命の世話より優先する仕事はないんやね。
とお祈りしながらみんなで埋めてあげた。
野遊も泣ききながら朝顔の花をとってきてくれた。
Posted by 陣 at
05:31
│Comments(0)
2008年07月28日
窯出しと忍者の一日弟子入り
昨日は午前中が窯出し。
今回は強還元(燻し)焼成だった為窯焚き終了から二週間もおいた。
かなり黒っぽく、渋い上がりになった。
見学の人を含め、十数人。
出した後は恒例のうどん大会。
ビール片手にぶっかけうどんに天ぷら。
最高!
午後からは「甲野善紀」先生http://www.shouseikan.com/の講習会。
古武術の研究家で、一言で言えば忍者。
昨日も真剣と手裏剣を持参。
僕らが当たり前だと思ってきた身体の使い方にいかに無駄が多いか。
身体を鍛えるとは負荷をかけるとこじゃない。
いかに楽に身体を使うかだと。
実際に先生よりも大きな男を蜘蛛のように這いつくばらせて(まず普通は返せない)横に入り、ひょいっとひっくり返す「平蜘蛛返し」。
思いっきりタックルしてくる相手の力をぐにゃっと受け流す技。
活字にすると難しいが、意図を持った直線的な動きは全て対処できるんだと。
逆に先生の動きは手とか筋力とか単純な動きじゃない為に武道経験者でもまず防ぎようがない。
先生曰く「体幹を使う」んだと。
要は腕で押す所を腕の付け根の肩、胸、背中、腰、脚と全身が腕の動きに参加してるそう。
だからどんなに大きな男であろうと先生に勝てない。
しかもその技はどんどん進化していってるんだと。
60歳を目前に今までで一番身体が動くとおっしゃる。
実際に介護の現場などで役立ちそうな力を抜いて座ってる人を簡単に起こす方法なども指導していただいた。
これらも全て身体を総動員させる使い方なので、小さな女の人が大きな男を起こしたり容易に出来る。
相手の重さが私を助けてくれるという言い方をされた。
僕は鍬や斧、田植え、稲刈りと具体的な作業について質問。
斧はテレビチャンピオンの薪割り王に勝てる自身は充分にあると。
全て身体の動きを途中で滞らせない流れるような動き。
見てて美しい。
結果、おきな力が生まれ、疲れない。
そういう動きはやればやる程鍛えられる。
負荷をかける動きはやればやる程壊れると。
先生は身体の使い方や武術という観点で独自の研究をされてきて、いかに今までの常識や囚われでみんな苦しんでるのかがバカバカしい程分かってきたと。
プロのスポーツのコーチや武道の師範の持ってる常識なんかは愚の骨頂だと。
「こうしなければいけない」という練習や修行に意味がないどころか、マイナスもいいところだと。
またスゴイ師匠に出会ってしまった。
マニアックの度を超えた研究姿勢は「好きな遊びをやってるだけなんですよ。」と修行や苦行じゃない所がすばらしい。
ほんとに好きで楽しいからいくらでも出来る。
この人間に備わった「マニア礼賛」の極意はほんとにスゴイと常々思ってはいたが、ここまでとは!
写真は手裏剣の実技指導中の先生。


今回は強還元(燻し)焼成だった為窯焚き終了から二週間もおいた。
かなり黒っぽく、渋い上がりになった。
見学の人を含め、十数人。
出した後は恒例のうどん大会。
ビール片手にぶっかけうどんに天ぷら。
最高!
午後からは「甲野善紀」先生http://www.shouseikan.com/の講習会。
古武術の研究家で、一言で言えば忍者。
昨日も真剣と手裏剣を持参。
僕らが当たり前だと思ってきた身体の使い方にいかに無駄が多いか。
身体を鍛えるとは負荷をかけるとこじゃない。
いかに楽に身体を使うかだと。
実際に先生よりも大きな男を蜘蛛のように這いつくばらせて(まず普通は返せない)横に入り、ひょいっとひっくり返す「平蜘蛛返し」。
思いっきりタックルしてくる相手の力をぐにゃっと受け流す技。
活字にすると難しいが、意図を持った直線的な動きは全て対処できるんだと。
逆に先生の動きは手とか筋力とか単純な動きじゃない為に武道経験者でもまず防ぎようがない。
先生曰く「体幹を使う」んだと。
要は腕で押す所を腕の付け根の肩、胸、背中、腰、脚と全身が腕の動きに参加してるそう。
だからどんなに大きな男であろうと先生に勝てない。
しかもその技はどんどん進化していってるんだと。
60歳を目前に今までで一番身体が動くとおっしゃる。
実際に介護の現場などで役立ちそうな力を抜いて座ってる人を簡単に起こす方法なども指導していただいた。
これらも全て身体を総動員させる使い方なので、小さな女の人が大きな男を起こしたり容易に出来る。
相手の重さが私を助けてくれるという言い方をされた。
僕は鍬や斧、田植え、稲刈りと具体的な作業について質問。
斧はテレビチャンピオンの薪割り王に勝てる自身は充分にあると。
全て身体の動きを途中で滞らせない流れるような動き。
見てて美しい。
結果、おきな力が生まれ、疲れない。
そういう動きはやればやる程鍛えられる。
負荷をかける動きはやればやる程壊れると。
先生は身体の使い方や武術という観点で独自の研究をされてきて、いかに今までの常識や囚われでみんな苦しんでるのかがバカバカしい程分かってきたと。
プロのスポーツのコーチや武道の師範の持ってる常識なんかは愚の骨頂だと。
「こうしなければいけない」という練習や修行に意味がないどころか、マイナスもいいところだと。
またスゴイ師匠に出会ってしまった。
マニアックの度を超えた研究姿勢は「好きな遊びをやってるだけなんですよ。」と修行や苦行じゃない所がすばらしい。
ほんとに好きで楽しいからいくらでも出来る。
この人間に備わった「マニア礼賛」の極意はほんとにスゴイと常々思ってはいたが、ここまでとは!
写真は手裏剣の実技指導中の先生。
2008年07月27日
田吾作村にかまど完成
昨日は高松の生島町にある「田吾作村」へかまど作りに行って来た。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=822362165&owner_id=2989823
この日記ではピザの石窯のオファーだったが、今回はかまど。
来月の23日(土)がピザの窯。
かまどはここで6つ目。
さすがになんちゃってで一日ワークショップのスタイルでやって来た僕だが、こんだけ回を重ねるとレベルアップしてくる。
特に、前回の小豆島の元気の種村と今回の田吾作村では鋳物製の焚き口も金物屋から取り寄せ、より機能性、耐久性、見た目も格段に違う。
朝、田吾作さんと大工の棟梁とで打ち合わせ。
位置と大きさなどを決める。
子どもたちや田吾作さんの娘さんの旦那などたくさん参加者が集まってくる。
まずは自然石で土台作り。
同時に若者たちには粘土、砂、藁、水とを混ぜてかまど本体の材料を準備してもらう。
僕が配合の割合とノウハウを指導。
最近は固めに練る。
もちろん練る時の労力は大変だが、この方が固くてしっかりとした粘土ブロックを作れ、堅牢な窯になる。
一同、粘土作りの大変さに「え~、これを何回もやるんすか~!?」とびびってたが、「大丈夫うちの陶芸の窯は土8tを一人、今日は軽トラに半分を何人もでやるんやから、簡単簡単!」
「俺絶対一人では無理ーーー。」と。
やった事ないとなかなかねー。
もちろんみんなで楽しくやる入り口は入りやすい。
僕の場合は一人で3ヶ月かかって本体7m、煙道を入れると全長11mの穴窯を作った経験が今では当たり前の出来事として自分の中にある。
大変だったという記憶はない。
でもそれは初めてで新鮮な体験だったし、とても楽しいと当時も今も思える。
客観的にみて大変な事でも本人がさらっと入れて、本気で楽しめたらいい。
そうすると結果(僕の場合は窯)は成功する。
みんなこの暑さの中、汗だくで「絶対明日は筋肉痛やー。」と言いながら。
子どもたちも一生懸命粘土を長靴で踏んだり、粘土ブロックを作ったりと飽きずにガンバル。
水もたくさん飲むが、こんだけ汗をかくとミネラルの補給が必須。
そこで田吾作さん手作りの梅干を出してもらう。
これが豊後梅の梅干で初めて見る巨大さ。
めっちゃ酸っぱくでおいしかったー。
何だかんだ言いながら午後に入り、かまどが形になってきたのと粘土練りの作業が終わりを迎えたのとで、みんな俄然テンションが上がる。
ブロック作りも楽しいけど、最後のディティールに凝り出すと止められない止まらないの世界。
「この俺のやったここの部分見てー。」とヒートアップ。
最後の細かい仕上げでどんどん美しくなっていく様はやっててほんとに楽しい。
田吾作さんに本業のステンレスの煙突工事をやってもらった。
これも煙突が新品で美しい~。
うちがいつも廃材利用なんで変な所に感動してしまう。
とにかく、何とか一日で完成。
みんなが集まり笑いの絶えないこの田吾作村に新たなスポットが増え、ますます楽しくなる事うけあい。
来月にはピザを焼く石窯も作る。
8/23(土)田吾作村へ来てねー。





http://mixi.jp/view_diary.pl?id=822362165&owner_id=2989823
この日記ではピザの石窯のオファーだったが、今回はかまど。
来月の23日(土)がピザの窯。
かまどはここで6つ目。
さすがになんちゃってで一日ワークショップのスタイルでやって来た僕だが、こんだけ回を重ねるとレベルアップしてくる。
特に、前回の小豆島の元気の種村と今回の田吾作村では鋳物製の焚き口も金物屋から取り寄せ、より機能性、耐久性、見た目も格段に違う。
朝、田吾作さんと大工の棟梁とで打ち合わせ。
位置と大きさなどを決める。
子どもたちや田吾作さんの娘さんの旦那などたくさん参加者が集まってくる。
まずは自然石で土台作り。
同時に若者たちには粘土、砂、藁、水とを混ぜてかまど本体の材料を準備してもらう。
僕が配合の割合とノウハウを指導。
最近は固めに練る。
もちろん練る時の労力は大変だが、この方が固くてしっかりとした粘土ブロックを作れ、堅牢な窯になる。
一同、粘土作りの大変さに「え~、これを何回もやるんすか~!?」とびびってたが、「大丈夫うちの陶芸の窯は土8tを一人、今日は軽トラに半分を何人もでやるんやから、簡単簡単!」
「俺絶対一人では無理ーーー。」と。
やった事ないとなかなかねー。
もちろんみんなで楽しくやる入り口は入りやすい。
僕の場合は一人で3ヶ月かかって本体7m、煙道を入れると全長11mの穴窯を作った経験が今では当たり前の出来事として自分の中にある。
大変だったという記憶はない。
でもそれは初めてで新鮮な体験だったし、とても楽しいと当時も今も思える。
客観的にみて大変な事でも本人がさらっと入れて、本気で楽しめたらいい。
そうすると結果(僕の場合は窯)は成功する。
みんなこの暑さの中、汗だくで「絶対明日は筋肉痛やー。」と言いながら。
子どもたちも一生懸命粘土を長靴で踏んだり、粘土ブロックを作ったりと飽きずにガンバル。
水もたくさん飲むが、こんだけ汗をかくとミネラルの補給が必須。
そこで田吾作さん手作りの梅干を出してもらう。
これが豊後梅の梅干で初めて見る巨大さ。
めっちゃ酸っぱくでおいしかったー。
何だかんだ言いながら午後に入り、かまどが形になってきたのと粘土練りの作業が終わりを迎えたのとで、みんな俄然テンションが上がる。
ブロック作りも楽しいけど、最後のディティールに凝り出すと止められない止まらないの世界。
「この俺のやったここの部分見てー。」とヒートアップ。
最後の細かい仕上げでどんどん美しくなっていく様はやっててほんとに楽しい。
田吾作さんに本業のステンレスの煙突工事をやってもらった。
これも煙突が新品で美しい~。
うちがいつも廃材利用なんで変な所に感動してしまう。
とにかく、何とか一日で完成。
みんなが集まり笑いの絶えないこの田吾作村に新たなスポットが増え、ますます楽しくなる事うけあい。
来月にはピザを焼く石窯も作る。
8/23(土)田吾作村へ来てねー。
2008年07月26日
やっと作り始めたー、ヤギさんのおうち
ヤギさんがうちに来てもう3週間。
ある日の夕方、友達が突如連れてきた。
「プレゼントや!」と。
!!!???
何の相談もなくいきなり連れてくる~?
これってありがたくないサプライズ。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=861769159&owner_id=2989823
窯焚きがあったり、わあいの床のリフォームがあったり、何やかんやでまだヤギさんの家を作れずに、超簡単仮小屋をパレットで作って夜だけはそこで寝てもらってる。
昼間はホイル付きのタイヤに繋ぎ、日陰を追って廃材ハウスの周りの草を食べたり、横になって反芻したり。
最初は特有のチョコチップ状のポロポロうんこだったのが塊状になりやがて下痢に。
何とここのすぐ近所で3年程前から親戚のおっちゃんがヤギを飼ってる。
うちは町内で2軒目。
で、慌てておっちゃんに相談に行く。
動物専用の薬をくれ、生の草ばかりじゃいかんと餌の事も教わる。
何と薬はケミカルフリーの純粋の漢方薬。
餌は干草やフスマ(麦の皮)と生の草とを両方食べられるようにしておけばヤギさんがいいように食べるんだと。
やっと最近下痢から塊状まで戻ってきた。
まだポロポロ状までは戻ってないが、もう大丈夫だろう。
昨日からやっとヤギさんの家作り。
廃材天国の中で一番最初に作った三角の道具小屋に隣接して作る。
道具小屋が4mの正三角形で、その小屋から軒を出し、囲いを作る。
3m×2.5mと割と大き目にした。
うちのトレードマークとも言うべき友達の製材所が火事で焼けた角材で雰囲気を揃える。
まだたくさんあるからねー、この丸焦げの角材。
ベースに石を置き、テキトーに角材を置き、大きさを決める。
例によって水平や垂直は一切測らない。
だって測る必要がないから。
まあ床でも張ってその上でご飯食べたり、寝たりとなれば水平ぐらいは必要だが、ヤギさんにとっては床はいらない。
もちろんいつものように設計図なしで全てが現場で寸法を合わせていく。
角材のカットは丸鋸さえ使わずにチェーンソーでテキトーにぶつ切りに。
ある程度角材を積んだ所で、いい感じに曲がった松の丸太があったので角材の柱の小口をチェーンソーで削り、ぴったりはまるようにする。
固定は徹底的にビス。
90mmと120mmのコースビス。
使うのはこのビスを打ち込むインパクトとチェーンソーだけという超荒い工事。
一応一日目はタルキを終え、パレットをバラシ野地の準備。
野地板の家をビニールシートで防水し、板葺きにしよう。
廃材天国の屋根材は板か土かやな。



ある日の夕方、友達が突如連れてきた。
「プレゼントや!」と。
!!!???
何の相談もなくいきなり連れてくる~?
これってありがたくないサプライズ。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=861769159&owner_id=2989823
窯焚きがあったり、わあいの床のリフォームがあったり、何やかんやでまだヤギさんの家を作れずに、超簡単仮小屋をパレットで作って夜だけはそこで寝てもらってる。
昼間はホイル付きのタイヤに繋ぎ、日陰を追って廃材ハウスの周りの草を食べたり、横になって反芻したり。
最初は特有のチョコチップ状のポロポロうんこだったのが塊状になりやがて下痢に。
何とここのすぐ近所で3年程前から親戚のおっちゃんがヤギを飼ってる。
うちは町内で2軒目。
で、慌てておっちゃんに相談に行く。
動物専用の薬をくれ、生の草ばかりじゃいかんと餌の事も教わる。
何と薬はケミカルフリーの純粋の漢方薬。
餌は干草やフスマ(麦の皮)と生の草とを両方食べられるようにしておけばヤギさんがいいように食べるんだと。
やっと最近下痢から塊状まで戻ってきた。
まだポロポロ状までは戻ってないが、もう大丈夫だろう。
昨日からやっとヤギさんの家作り。
廃材天国の中で一番最初に作った三角の道具小屋に隣接して作る。
道具小屋が4mの正三角形で、その小屋から軒を出し、囲いを作る。
3m×2.5mと割と大き目にした。
うちのトレードマークとも言うべき友達の製材所が火事で焼けた角材で雰囲気を揃える。
まだたくさんあるからねー、この丸焦げの角材。
ベースに石を置き、テキトーに角材を置き、大きさを決める。
例によって水平や垂直は一切測らない。
だって測る必要がないから。
まあ床でも張ってその上でご飯食べたり、寝たりとなれば水平ぐらいは必要だが、ヤギさんにとっては床はいらない。
もちろんいつものように設計図なしで全てが現場で寸法を合わせていく。
角材のカットは丸鋸さえ使わずにチェーンソーでテキトーにぶつ切りに。
ある程度角材を積んだ所で、いい感じに曲がった松の丸太があったので角材の柱の小口をチェーンソーで削り、ぴったりはまるようにする。
固定は徹底的にビス。
90mmと120mmのコースビス。
使うのはこのビスを打ち込むインパクトとチェーンソーだけという超荒い工事。
一応一日目はタルキを終え、パレットをバラシ野地の準備。
野地板の家をビニールシートで防水し、板葺きにしよう。
廃材天国の屋根材は板か土かやな。
2008年07月22日
さぬきの夢2000で手打ち
昨日はおとといキャンプから帰ってきて、そのまま姫ファミリーが滞在中。
帰って来た夜は実家で親父の精進料理をみんなで頂く。
最近腕を上げ、中々頼もしい。
昨日は朝から手打ちうどんの段取り。
もちろんいつも使ってる「さぬきの夢2000」で。
県が開発した讃岐うどん用小麦。
グルテンは弱いが、丁寧に作るとモチモチ感がたまらない。
これは丸亀にある「手打ちうどん寿美屋」の大将がいちはやく目を付け、ほとんどのさぬきうどん屋の使うオーストラリア産小麦ASWを止め100%切り替えた。
数年前にこの大将が講師で県の主催する手打ちうどん教室が近くの農協で開かれ、親父と弟の源が参加した。
それを受けた源の興奮ぶりは凄まじかった。
何せグルテンが弱いってことは打つのも繊細さが要求される上に作り置きが効かない。
業務用にはよほどのこだわりがない限り使えない。
現実7、800店もあると言われるさぬきうどん屋のうちさぬきの夢2000を含む国産小麦100%で打つ店は10軒あるなし。
その中で味の素フリーの本格派ともなれば、丸亀「明水亭」ぐらいしか僕の知る限りではまだない。
そこで、最近はうどん屋に行くのは止めて、たまに自分で打ってる。
自分で打つ麺も慣れてきたが、出汁が最高。
昆布、しいたけ、いりこ、鰹節に杉樽仕込みの本醸造醤油に三河本みりんとおいしくなる限りの事をしてる。
むしろそれが本来当たり前で、本だし(偽だし)に脱脂加工大豆などを使った醤油もどき、ましてだし醤油のような甘いのはもっての他。
そういう手抜きをしたり、材料を安く上げようと小細工してもダメ。
世の加工食品と外食産業は全部これら添加物の恩恵で大儲けをして、メタボからガンに至る病気を産み、何より手作りする日本の美しい伝統を奪った。
もちろん一口はおいしいように出来てるが、毎日食べてほんとに滋味深い感動があるかと言えばある訳がない。
作り手が効率や経済優先で作る仕事に感動しないものは受けてが感動できるばすはない。
うどん以外でもよく来る友達に言われるのが「こんなにおいしいなら店を出したら。」でもここまで素材にこだわって、手間もかけて「お金の為」には絶対にしたくない。
もちろんイベント出店やケータリング、ホームパーティーなどはその限りではない。
毎日、毎日オープンさせるのが嫌。
当然機械化したり、マニュアル化したり、グレードが落ちるだけでなく自分が楽しくなくなるのは目に見える。
えーと、作り方は蕎麦打ちをイメージして頂きたい。
大きな捏ね鉢に粉を入れ、一人が十本の指で絶え間なくグルグルとかき混ぜ、もう一人が上からチョロチョロを塩水を差してゆく(水回し)。
今は夏なので、15%の塩水を4割ちょい(粉の重量の)一応5割分作って置き、上記の工程で手の感触で加減する。
ここで弱くでもさぬきの夢2000のグルテンが引き出され、ほんのり生成りになってくる。
これをまとめ、大きいビニール袋に入れ、足で踏む。
延ばしては折りたたみ何度か繰り返す。
少し、寝かせ、ノシ棒で打っていく。
ここでも繊細な作業をしないとダメ、乱暴に打てる外麦とは大違い。
後は包丁で切り、薪でお釜をグラグラに沸かし、茹でる。
何回かに分けて茹でる為、浮いてきた泡をレードルですくうのは必須。
こうすることで塩分や粘りを捨てられる。
もちろん今は茹で上がりを冷たい井戸水で締め、ザルうどんに。
大葉、ミョウガ、ショウガ、ネギ、ゴマ、キザミノリ、夏大根のオロシ、と贅沢な薬味と最高のタレで頂く。
つくづく贅沢。
ほんとに滋味。
自分たち家族だけの昼食になかなかここまではしないが、こういうもてなしの時に自分たちも楽しめるのがいい。
写真は姫さんとこの海人くん。
一人で団子からのす作業と切る作業とこなす。
家でもやってるだけに手馴れてる。
あっこスイーツも登場。
ヒエの生地に姫さんの栗の甘露煮で作った手製モンブラン。
ブランデーが効いて上品なお味。



帰って来た夜は実家で親父の精進料理をみんなで頂く。
最近腕を上げ、中々頼もしい。
昨日は朝から手打ちうどんの段取り。
もちろんいつも使ってる「さぬきの夢2000」で。
県が開発した讃岐うどん用小麦。
グルテンは弱いが、丁寧に作るとモチモチ感がたまらない。
これは丸亀にある「手打ちうどん寿美屋」の大将がいちはやく目を付け、ほとんどのさぬきうどん屋の使うオーストラリア産小麦ASWを止め100%切り替えた。
数年前にこの大将が講師で県の主催する手打ちうどん教室が近くの農協で開かれ、親父と弟の源が参加した。
それを受けた源の興奮ぶりは凄まじかった。
何せグルテンが弱いってことは打つのも繊細さが要求される上に作り置きが効かない。
業務用にはよほどのこだわりがない限り使えない。
現実7、800店もあると言われるさぬきうどん屋のうちさぬきの夢2000を含む国産小麦100%で打つ店は10軒あるなし。
その中で味の素フリーの本格派ともなれば、丸亀「明水亭」ぐらいしか僕の知る限りではまだない。
そこで、最近はうどん屋に行くのは止めて、たまに自分で打ってる。
自分で打つ麺も慣れてきたが、出汁が最高。
昆布、しいたけ、いりこ、鰹節に杉樽仕込みの本醸造醤油に三河本みりんとおいしくなる限りの事をしてる。
むしろそれが本来当たり前で、本だし(偽だし)に脱脂加工大豆などを使った醤油もどき、ましてだし醤油のような甘いのはもっての他。
そういう手抜きをしたり、材料を安く上げようと小細工してもダメ。
世の加工食品と外食産業は全部これら添加物の恩恵で大儲けをして、メタボからガンに至る病気を産み、何より手作りする日本の美しい伝統を奪った。
もちろん一口はおいしいように出来てるが、毎日食べてほんとに滋味深い感動があるかと言えばある訳がない。
作り手が効率や経済優先で作る仕事に感動しないものは受けてが感動できるばすはない。
うどん以外でもよく来る友達に言われるのが「こんなにおいしいなら店を出したら。」でもここまで素材にこだわって、手間もかけて「お金の為」には絶対にしたくない。
もちろんイベント出店やケータリング、ホームパーティーなどはその限りではない。
毎日、毎日オープンさせるのが嫌。
当然機械化したり、マニュアル化したり、グレードが落ちるだけでなく自分が楽しくなくなるのは目に見える。
えーと、作り方は蕎麦打ちをイメージして頂きたい。
大きな捏ね鉢に粉を入れ、一人が十本の指で絶え間なくグルグルとかき混ぜ、もう一人が上からチョロチョロを塩水を差してゆく(水回し)。
今は夏なので、15%の塩水を4割ちょい(粉の重量の)一応5割分作って置き、上記の工程で手の感触で加減する。
ここで弱くでもさぬきの夢2000のグルテンが引き出され、ほんのり生成りになってくる。
これをまとめ、大きいビニール袋に入れ、足で踏む。
延ばしては折りたたみ何度か繰り返す。
少し、寝かせ、ノシ棒で打っていく。
ここでも繊細な作業をしないとダメ、乱暴に打てる外麦とは大違い。
後は包丁で切り、薪でお釜をグラグラに沸かし、茹でる。
何回かに分けて茹でる為、浮いてきた泡をレードルですくうのは必須。
こうすることで塩分や粘りを捨てられる。
もちろん今は茹で上がりを冷たい井戸水で締め、ザルうどんに。
大葉、ミョウガ、ショウガ、ネギ、ゴマ、キザミノリ、夏大根のオロシ、と贅沢な薬味と最高のタレで頂く。
つくづく贅沢。
ほんとに滋味。
自分たち家族だけの昼食になかなかここまではしないが、こういうもてなしの時に自分たちも楽しめるのがいい。
写真は姫さんとこの海人くん。
一人で団子からのす作業と切る作業とこなす。
家でもやってるだけに手馴れてる。
あっこスイーツも登場。
ヒエの生地に姫さんの栗の甘露煮で作った手製モンブラン。
ブランデーが効いて上品なお味。
2008年07月21日
無人島サバイバルキャンプ
昨日帰って来た。
無人島一泊二日のキャンプ。
アララトさんには大変お世話になり、超感謝感激。
おとといの早朝、前泊の姫ファミリーとうちの家族とでヤポネシア号に荷物を積み込み、坂出の瀬居島(埋め立てで今は島じゃない)のアララトさん宅からすぐの所の漁港に彼女は停泊している。
アララトさんもキャンプに同行してくれ、二家族にアララトさんというメンバーでのキャンプとなった。
港で土歩くんが帰りたいと言い出し(最近熱気味)あっこちゃん、土歩くん、にこちゃんはドタキャン。
カヤックも積み、沖から浜に渡る為の小船をヤポネシア号に繋ぐ。
出発と同時にスクリューにロープが絡まり、去年の12月に直径80ミリのロープが沖で絡まり、30分も海中で死闘したというアララトさんの日記が甦る。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=657096692&owner_id=704465
今回は夏だし、ロープも細く、正装のアララトさんがすぐにクリア。
いよいよ出航。
ここから無人島まで、瀬戸大橋遊覧コース。
港を出て、沖に出ると、ブオオ~~~~と法螺貝で出航のノロシ。
これはめちゃカッコいい。
島に着くと小船に荷物を移し、アララトさんが櫓を漕いで浜に渡してくれる。
道具類の多さ、水も最後には余り、荷物の多さに後で反省。
早速浜に持ち込んだ廃材でインパクトとビスでタープを立てる。
テントも設営。
あまりの暑さにここまでで一仕事を終えた感じ。
玄米おにぎりの昼食後僕と姫さんはスーツにシュノーケルで晩の酒のアテを獲りに海へ。
ここは今では底引き網漁で絶滅危惧になってるアマモの大生息地。
他の海藻類も豊かで、生態系が成り立ってる。
遠浅で入り江の鼻の磯も浅く、サザエやアワビは居そうにない。
入り江から出ると潮の流れが速く、岩から離れるとどんどん流される。
大きな岩の周りで体勢を整えつつ、ヤスで魚を狙うもアイナメとベラの小さいのぐらい。
最後に姫と二人掛かりで仕留めた大蛸が凄かった。
ヤスを眉間に打ち込んでるのに地面とヤスの両方を掴み、ヤスを抜く事さえ出来ない。
水深が浅かったから良かったものの、さすがの姫さんもうかつに蛸に手を出し、水中勝負になったら相手の方が強いと注意を促す。
底から離れても姫さんのスーツにしがみつき、なかなか網に入れさせてもらえない。
3~4㌔はあるほんとの大蛸。
必死の勝負は二人の人間が勝ち、うまく網に収めた。
子どもの為にウニも獲り、陣笠(貝)も数枚。
とにかく夜は蛸のフルコース。
みんなでテキパキ準備、料理。
蛸は生の刺身、レアにボイルしたものはマリネ、ゆっくりボイルしたものの刺身、煮付け。
ウニは今の季節が最高で卵巣が太ってる。
陣笠は上品な味でアワビにも似た味。
持っていった野菜類でイタメシ風の蛸パスタやマリネ、刺身にはミョウガ、大葉とかなりグレードの高いディナーになった。
ビール、泡盛なども持っていってて、夜は長いと酒盛りに突入。(どこがサバイバルやー)
特に姫さんとアララトさんはここのアマモ場には超感動。
僕はその貴重さが分からなくも、確かに美しかった。
夜も更け、いい気分になった頃、姫さんが「海ボタル」を獲ってくれた。
ほんとに蛍。
ブルーに光る繊細な光。
これはほんとに美しい。
翌日は子どもの遊びに付き合い、野遊も大はしゃぎで泳ぎの練習。
カヤックも姫さんとこの海人くんも野遊も一人で操舵できるようになった。
子どもはスゴイねー、頭で考えないならすんなり覚える。
この日は漁師の大きな漁船から大勢で上陸してのデイキャンプ組も島に来る。
あちらはエンジンのボートやジェットを乗り回し、キャーキャー。
こちらはカヤックに櫓漕ぎ、素潜りと原始的な遊び。
昔は僕もレーサーレプリカのバイクも好きだったが、今のエコライフになってからはそういうデカイエネルギーの乗り物を乗りまわす楽しみよりも自分の身体や感覚を使う事に喜びを感じる。
カヤックはほんとに楽しかった。
海面ギリギリをスイスイ進む快感。
海の自転車って感じ。
今回の無人島は40年前までは人が住んでたそう。
ジュセリーノさんの言う2011年の鳥インフルエンザのパンデミック(世界流行)で数億人規模が死ぬ事態になればエネルギー、流通、経済などは全部ストップするみたい。
その時なんかはこういう島で自給自足するのはもってこい。
アララトさんにカヤックや櫓漕ぎを学ばないと。
海も山も超破壊されてる自然界も、たちまち人間が経済活動を止めれば一気に回復するだろう。
姫さんの自然に接する姿勢、知識、経験もまだまだ学びたい。
2008年07月18日
「無人島キャンプ」「結婚パーティー」
明日から瀬戸内海に浮かぶ無人島で姫家族とサバイバルキャンプ。
年に一度やってる。
日本海によく行ってたが、今年はにこちゃんもいるし近くがええねと。
詫間の庄内半島の先端も候補に挙がったが、なにせキャンプ場。
アララトさんはそもそも漁師じゃなく、瀬戸内海のガイドの為に船を持ったはず、、、。
電話し、無人島でキャンプ出来る所ないすかと聞くと、知り合いにスポットを聞いてくれ、即OK。
この姫さんは野草の先生でもあるが海の先生でもある。
海洋生物学を勉強してる上に海に浮かんでる方が丘にいるより気持ちいいとおっしゃる。
僕も10年以上前に彼女に教えて貰ってシュノーケリングを覚えた。
いわゆるサザエやアワビを獲る為のそれじゃなく、海の神秘さを体感して欲しくて子どもたちにも教える。
彼女はダイビングのインストラクターの資格も持ってるが、僕はエアを噛んだ経験はまだない。
一度は数十分も海底に滞在出来る体験をしてみたい。
日本海はほんとにステキで、初期の頃行った丹後半島が忘れられない。
潜った先にトンネルがあり、向こうが見えたが、ビビッてくぐれなかった。
でっかい岩の全面を岩牡蠣が覆ってたり。
もちろん魚もたくさんヤスで突いて獲った。
夜中、ワンボックスから4,5人男が降りて来て、水中をライトで照らしながら海に入り、サザエをアワビをガッサリ持って帰った。
僕らのキャンプはサバイバルなんで、もちろん自分たちが食べるだけは海の生き物を頂く。
でもこういう密漁者のおかげで、日本海など「シュノーケル禁止」とか意味不明の事態になってる。
海は誰のものでもないが、漁師が放流したアワビの稚貝を密漁者に持っていかれたんじゃ情けない。
だからしかたない観はあるんだが、、、。
とにかく、このキャンプは自分たちの作ったお米や野菜、最小限の調味料は持っていくが、基本的に現地調達。
毎年姫さんを先頭に男たちは食糧班。
大抵サザエやアワビ以外にもタコや魚も獲れる。
飯ごうでご飯を炊き、野菜と魚介の料理。
子どもたちにもくるくる寿司には連れていきたくないし、カウンターの鮨屋は高いし、、、。
でもここではアワビにウニ、刺身にサザエの壷焼きと自然の恵みを味わわせられる。
普段は玄米菜食でもこういう時にほんとの自然の味を堪能するのは超贅沢。
要は「ウニ」という食品がおいしいのではない。
スーパーで買う、板に乗ったそれと海で拾ったそれの味の違いは言うまでもない。
もっと違うのはみんなでキャンプして、みんなで獲って、みんなで味わうという貴重な体験だ。
そこまでひっくるめて贅沢と言うのだ。
いや、マジで高級な鮨屋のウニも獲ってから何時間も経ってるからねー、この獲りたての味はスゴイよ。
ほんとに今年は楽しみ。
アララトさんに感謝。
もう一つ。
善通寺でモミの木接骨院を開業した大田さんが最近結婚された。
身体のケアのプロの大田さんの結婚パーティーを廃材天国でしようと言う話になった。
大田さん曰く、僕らの事を知らない方でも来て欲しいです、と。
8/2(土)夕方6時から。
うちにメールか電話で問い合わせてください。
年に一度やってる。
日本海によく行ってたが、今年はにこちゃんもいるし近くがええねと。
詫間の庄内半島の先端も候補に挙がったが、なにせキャンプ場。
アララトさんはそもそも漁師じゃなく、瀬戸内海のガイドの為に船を持ったはず、、、。
電話し、無人島でキャンプ出来る所ないすかと聞くと、知り合いにスポットを聞いてくれ、即OK。
この姫さんは野草の先生でもあるが海の先生でもある。
海洋生物学を勉強してる上に海に浮かんでる方が丘にいるより気持ちいいとおっしゃる。
僕も10年以上前に彼女に教えて貰ってシュノーケリングを覚えた。
いわゆるサザエやアワビを獲る為のそれじゃなく、海の神秘さを体感して欲しくて子どもたちにも教える。
彼女はダイビングのインストラクターの資格も持ってるが、僕はエアを噛んだ経験はまだない。
一度は数十分も海底に滞在出来る体験をしてみたい。
日本海はほんとにステキで、初期の頃行った丹後半島が忘れられない。
潜った先にトンネルがあり、向こうが見えたが、ビビッてくぐれなかった。
でっかい岩の全面を岩牡蠣が覆ってたり。
もちろん魚もたくさんヤスで突いて獲った。
夜中、ワンボックスから4,5人男が降りて来て、水中をライトで照らしながら海に入り、サザエをアワビをガッサリ持って帰った。
僕らのキャンプはサバイバルなんで、もちろん自分たちが食べるだけは海の生き物を頂く。
でもこういう密漁者のおかげで、日本海など「シュノーケル禁止」とか意味不明の事態になってる。
海は誰のものでもないが、漁師が放流したアワビの稚貝を密漁者に持っていかれたんじゃ情けない。
だからしかたない観はあるんだが、、、。
とにかく、このキャンプは自分たちの作ったお米や野菜、最小限の調味料は持っていくが、基本的に現地調達。
毎年姫さんを先頭に男たちは食糧班。
大抵サザエやアワビ以外にもタコや魚も獲れる。
飯ごうでご飯を炊き、野菜と魚介の料理。
子どもたちにもくるくる寿司には連れていきたくないし、カウンターの鮨屋は高いし、、、。
でもここではアワビにウニ、刺身にサザエの壷焼きと自然の恵みを味わわせられる。
普段は玄米菜食でもこういう時にほんとの自然の味を堪能するのは超贅沢。
要は「ウニ」という食品がおいしいのではない。
スーパーで買う、板に乗ったそれと海で拾ったそれの味の違いは言うまでもない。
もっと違うのはみんなでキャンプして、みんなで獲って、みんなで味わうという貴重な体験だ。
そこまでひっくるめて贅沢と言うのだ。
いや、マジで高級な鮨屋のウニも獲ってから何時間も経ってるからねー、この獲りたての味はスゴイよ。
ほんとに今年は楽しみ。
アララトさんに感謝。
もう一つ。
善通寺でモミの木接骨院を開業した大田さんが最近結婚された。
身体のケアのプロの大田さんの結婚パーティーを廃材天国でしようと言う話になった。
大田さん曰く、僕らの事を知らない方でも来て欲しいです、と。
8/2(土)夕方6時から。
うちにメールか電話で問い合わせてください。
2008年07月17日
無垢の杉板に柿渋を塗り完成
昨日で、わあいの床直しの作業は終わった。
3日間、僕とまさとかずきちさん、一日は池の側さん一家も駆けつけてくれての大助かりだった。
シロアリ発覚のハプニングもしんやさんのアイデアで面白い展開になったしね。
昨日は杉板を張る作業の続き。
もうまさやかずきちさんも要領を得てきてるんで、どんどん進む。
本ザネ加工(オスとメス)なので、最後の入れ方に困り、大工の棟梁に電話。
三角に付き合わせ、上からぐっと押し込むそう。(写真1)
あらかじめ部材をきちんと測り、丸鋸でていねいにカットしてたからだが、めっちゃうまくいった。
ゴトンッと入った時はみんなハイタッチ。
その後は柿渋塗り。
始めは少し薄めて塗って、2回目は原液に近い状態で塗る。
初めて施工したが、ペンキと違ってサラサラの水みたい。
3人で塗るとあっという間。
今回はこの週末にテリーさんというマウイからロミロミマッサージ師の方が来てのワークショップの為に作業が急がれた。
何とか間に合って良かった。
最初は仕事としてかずきちさんから依頼され、お金も払うからと言う条件だった。
でも僕の提案で、僕の大工仕事とかずきちさんのITの仕事とを物々交換しようと。
今後は月に一回か二回お互いに行き来し、あらかじめ内容と日にちを設定して、わあいでのワークショップにしようとなった。
もちろんピザの窯も作れるし、天井を取り払う工事もしたいねーと。
僕の方はもともとITのプロのかずきちさんの技術で廃材天国のHPを作ってもらったり、パソコンの技術の先生になってもらう。
大工さんに頼むと数十万の工事とプロのウェブデザイナーに頼むと数十万のHPの作成も技術と技術で交換しあう。
これは凄い合理的。
早速話は進み、HPの中で焼き物の作品を売れるねとなり、かずきちさんがイオスキッスのX2という最新の一眼レフのデジカメを取り出し、撮りかたを教えてくれる。
やっぱり一眼になると、背景をぼかしたり本格的な写真が撮れる。
なんとこのX2になると、ポートレイトのピントを合わせる時、鼻に合わせるかマツゲに合わせるか、まで出来る。
しかもこういうデジタル製品はどんどん安くなってきてる。
気合を入れて買うか?
まずはかずきちさんと打ち合わせをして、どんなサイトにしたいかなどを詰めていくのが先。
もちろん作品を売るとかいうのはほんの一部で、メインは廃材天国。
この廃材天国を利用し、たくさんの仲間を繋いで衣食住、医療、教育、アート、冠婚葬祭など生きることに必要な事を国やお金に頼らずともみんなで助け合って楽しくやっていこうとしてる。
Big Family プロジェクト!
このウェブサイトが出来るのは夢だったが、遂に実現するのかー。
かなりワクワク。
でも何にも知らない僕はかずきちさんに教わりかなり勉強しないと、、、。
2008年07月15日
橋本ちあきin廃材天国
昨日は「自然に産みたい」の著者橋本ちあきさんがうちに来てくれた。
松山でこれから一週間の半断食セミナーをされる。
その前に寄って頂いた。
天然酵母のパン屋ココペリの松本さんが10年前に坂出に呼んで講演会をして、そのご縁で今回四国に来る機会にうちで小規模にやれるといいなという運びに。
参加者は30人。
半分はちあきさんの本を読んだり、自宅出産の経験者。
僕達夫婦も野遊(6)の時にこの本に出会い、自宅出産を決意。
今回の呼びかけは僕の日記やメール、関心のありそうな人へ連絡して、口コミで広まった。
出産、教育、食と一連の切っても切り離せないジャンルのお話。
参加者からの質問に答えながらの流れとなった。
まず、助産婦さんが近くにいなくて病院か自力かしかないというケース。
これは覚悟の問題だと。
岡崎の吉村医院の先生はこの宇宙の神秘のお産に絶対に人為を加えてはいけないと言う。
ちあきさんは本人が決める問題だと。
結局、直感で「何か病院っていややな。」と思えばそれを実行した方がいいと。
特にうちのあっこちゃんみたいに一人目が病院で二人目からが自宅となるとその差があまりに大きい事に気付かざるをえない。
特に女性は直感力が鋭いように思う。
それこそ吉村先生のいうゴロゴロ、パクパク、ビクビクという不自然なライフスタイルの現代人だからこそ、その中には「何かおかしい、、、」と気付きはじめてる人も多い。
大自然に触れて気持ちいいと思わない人がいないように、不自然な事に違和感を持つのが当たり前。
で、ちあきさんは「私がどっちがいいとは言えない、本人が納得するのが一番。」と。
それには命を賭ける覚悟がいる。
人任せにしない。
何かあったら自分で責任をとる。
まあ、考えたら当たり前なんよね。
ここは何かあるとすぐ人のせいにする社会。
それこそ母親でも赤ちゃんでも死んだりすると病院などマスコミに叩かれて大変なのだろう。
でも自分が責任を持つ覚悟を決めると、じゃあそうならない為にはどうすべきかを徹底的に実行するのみだと。
彼女が実行したのは歩く事、玄米菜食に徹する事、心を平穏にする事とこの3つだけはやろうと自分に言い聞かせたそう。
ちあきさんの言い方ではチャレンジであり、実験なんだと。
凄いのは5人とも医者も助産婦もなしなだけじゃなく、そのうちの2人は自分と小さい子どもだけという事もあったそう。
この辺りは「自然に産みたい」を読むと細かく書いてある。
その極みが5人目の子の時にアフリカではオムツレスだと何かで読み、チャレンジ。
最初の一週間が特に大事で、オムツを当てていつでもしていいよーというオーラを出さないんだと。
見事に一回も失敗なく、一回もオムツをする事なくいけたそう。
子育ても、子どもの心がワクワクしない事はしないと。
学校に違和感を持った時点でホームスクーリングに切り替える。
いわゆる自然な不登校。
毎日裏山で遊び、勉強はお母さんが教える。
でも5人5様で一人目は学校に行かなかったけど、二人目は毎日楽しく行って、高校も大学も行ったそう。
高校や大学を海外で過ごした子もいるそう。
今はベジタリアンのレストランのオーナーシェフになった子、普通に広告代理店でサラリーマンをしてる子、と様々。
とにかく違いを認める。
おしつけない。
でも親の生き方、考え方ははっきりと見せ、伝える。
すると子どもは自然に判断する。
ほんと、うちでもそうありたいと願い毎日全力で生きる。
食事もこれがダメあれがダメじゃなくて小さいうちから何でうちでは買ったものを食べないかとちゃんと教えたそう。
で、頂き物やスーパーのお菓子などもどうやって作られてるかを説明すると小さいうちから覚えていく。
で、大きくなっても匂いだけでちょっと、、、と自分から食べないそう。
肉も加工品も一回は食べてみたいという好奇心は潰さずに、買ってきて焼いてみて、うわーひどい匂い、とワンちゃんの餌になったそう。
ここがおしつけじゃない凄い所。
大人になった彼らはもちろんほとんどベジタリアン、魚だけならとか鶏肉だけはと少しは食べられる子もいるそう。
とにかく15歳まで肉も魚も加工品も一口も食べてなくても男の子なんかは170後半とちゃんと成長してる。
とにかくにちあきさんと30人の参加者を包む空気がさわやかだった。
しぜーんな感じの上品な雰囲気。
質問に対しても「そうだよねー。」と同じ目線でやわらかく答える。
本を読むよりも本人に会うとこの空気ではっきり分かる。
もちろん本もすばらしいから是非読んでね。
吉村先生の鬼気迫る講演も僕は超スイッチ入るが、やっぱりお産の話は女性やねー。
女よ、あななたたちが男を動かしてる。
お産の時の子宮の収縮と弛緩は痛みを超えて、宇宙の膨張と同じ事を体験する唯一の体験だと。
自分の体と外の区別がなくなるめくるめく世界だと。
う~ん、こればっかりは男には分からない。
吉村流を借りると、女は子どもを産む為に存在し、男はそれを守る為に命を賭ける。
おお!
2008年07月14日
わあい床2日目、やっぱりねーのお約束
昨日はまたわあい(前回の日記参照)に行き、床の作業の続き。
何と京都からマイミク池の側さん一家が駆けつけてくれる。
もちろんかずきちさんとまさも一緒。
池の側さんのパートナー、しんやさんは前職を辞め、今から環境コンサルタントの事業を起業しようとする最中。
何と宮崎の松本英輝さんと親しくて、はよ会社何か辞めて起業したらとハッパをかけられてるそう。
英輝さんは肩書きがエコロジスト。
自転車で世界を旅し、日本にも世界の環境調和型の街づくりを提唱してる。
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/8894/ecocapitalmiyazaki.html
田中優さんとも知り合いで、市民バンク立ち上げの話もあったそう。
優さんはみんなが預けてるゆうちょが戦争の資金源になってると。
坂本龍一さんなどが呼びかけるAPバンクの顧問。
非電化の製品などにも詳しい。
http://www.eco-online.org/contents/people/11tanaka.html
根太の続きを終え、例の高知産の杉板を張り始めようとした時。
しんやさんが衝撃的な事実を告げる。
「あっ、そこの柄石の所にアリ道出来てるよ。」
一同「、、、、、、。」
僕が子どもの頃、うちがシロアリに食われた時、親父が大工の棟梁に聞きつつ自分で退治した時に見た記憶がある。
でもおととい柄石の周りは全部ほうきでキレイにしたばっかし。
目を疑ったが、地面から柄石を通り、柄に通じてる。
トンネル状のアリ道を壊すとシロアリさんが行ったり来たりと大忙し。
、、、、。
見たくないもを見てしまった観で一同トーンダウン。
シロアリさんはもう活動してないとタカをくくってただけにショック。
そこからしんやさんがシロアリの習性や対処法をレクチャー。
何でも本で読んで詳しいんだと。
とにかくわあいもうちと同じで殺虫剤などの化学物質は使いたくない。
特にプロの使うシロアリ駆除剤などヒ素で出来てて、シックハウスどころかヒ素の充満する家に住むハメになるそう。
害虫を殺す為に人間にも害のある毒を撒くのでは本末転倒。
大体害虫といってもシロアリさん自体は自然界として倒れた木を喰って土に戻すという大事な仕事をしてくれてる。
ただ時々人間の家も喰ってくれるのをちょっと防ぐ対策をすればいいだけ。
しんやさんによると、柄石の周りに石灰を撒き、小さなファンで床下の換気をすればまず大丈夫だと。
早速かずきちさんとしんやさんとでジョイに買い物。
僕とまさは床張りを続行。
しんやさんがいろいろアドバイスして石灰やファンなど買ってきた。
まさがマスクとゴーグルで石灰を撒き、しんやさんは床下に潜り、ファンの設置と配線。
なんでも彼は電線マニアらしく、家でも新たな配線工事などをやってると。
僕のキッチン道具マニアも珍しいかもしれないが、電線マニアは初めて聞いた。
マニア=天職やからねー。
ファンはトイレの脱臭ファン、一個2000円程、これを3つ設置。
タイマーを大元に付け、一時間おきにオン、オフさせる。
これは節電とファンの寿命を延ばす為。
このタイマー(980円)を使って夜中の冷蔵庫を開けない時間帯に一日一時間でもオフするようにするだけでもかなりの節電になるそう。
マ、マニアックやー。
悪徳業者なんかはこのファンの設置だけで10万とかぼったくるそう。
その後作業は順調に進み、床も三分の一以上、シロアリ対策もばっちり。
まさなんか石灰を撒く為に床下を這いずり回り「面白~い、昔の家ってすごーい!」と感動しまくり。
僕も解体現場には随分足を運んでるが、昔の家を修理したりバラシたりするのってめちゃ面白い。
大工さんの技術の凄さも勉強になるが、ちっちゃな石の上にきゃしゃな柄を立てて置いてるだけの基礎を見れば廃材天国などマシなもの。
ベタ基礎だ、耐震だと不安を煽って金儲けし、シロアリ駆除でもぼったくり。
そんな不安を煽る広告と洗脳に騙されるなよ。
シロアリに喰われるぐらいどうってことないって。
喰われながら140年もこの家は建ってるんやから。
○○になったらどうしよう、、、とありもしない未来の不安を考えるより今したい事をせよ。
その不安を解消する為にお金をかけ、その金を稼ぐ為にしたくもない仕事をやめられないなど、もってのほかだぞ。
しんやさんのマニアぶりに脱帽し、シロアリさんが居てくれたお陰で昨日も一日楽しめた。
結局もう一日はいるな。
杉板張りを完成させその上に柿渋を塗る。
次は16日。
なんちゃって大工を経験したい人はどうぞー。



何と京都からマイミク池の側さん一家が駆けつけてくれる。
もちろんかずきちさんとまさも一緒。
池の側さんのパートナー、しんやさんは前職を辞め、今から環境コンサルタントの事業を起業しようとする最中。
何と宮崎の松本英輝さんと親しくて、はよ会社何か辞めて起業したらとハッパをかけられてるそう。
英輝さんは肩書きがエコロジスト。
自転車で世界を旅し、日本にも世界の環境調和型の街づくりを提唱してる。
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/8894/ecocapitalmiyazaki.html
田中優さんとも知り合いで、市民バンク立ち上げの話もあったそう。
優さんはみんなが預けてるゆうちょが戦争の資金源になってると。
坂本龍一さんなどが呼びかけるAPバンクの顧問。
非電化の製品などにも詳しい。
http://www.eco-online.org/contents/people/11tanaka.html
根太の続きを終え、例の高知産の杉板を張り始めようとした時。
しんやさんが衝撃的な事実を告げる。
「あっ、そこの柄石の所にアリ道出来てるよ。」
一同「、、、、、、。」
僕が子どもの頃、うちがシロアリに食われた時、親父が大工の棟梁に聞きつつ自分で退治した時に見た記憶がある。
でもおととい柄石の周りは全部ほうきでキレイにしたばっかし。
目を疑ったが、地面から柄石を通り、柄に通じてる。
トンネル状のアリ道を壊すとシロアリさんが行ったり来たりと大忙し。
、、、、。
見たくないもを見てしまった観で一同トーンダウン。
シロアリさんはもう活動してないとタカをくくってただけにショック。
そこからしんやさんがシロアリの習性や対処法をレクチャー。
何でも本で読んで詳しいんだと。
とにかくわあいもうちと同じで殺虫剤などの化学物質は使いたくない。
特にプロの使うシロアリ駆除剤などヒ素で出来てて、シックハウスどころかヒ素の充満する家に住むハメになるそう。
害虫を殺す為に人間にも害のある毒を撒くのでは本末転倒。
大体害虫といってもシロアリさん自体は自然界として倒れた木を喰って土に戻すという大事な仕事をしてくれてる。
ただ時々人間の家も喰ってくれるのをちょっと防ぐ対策をすればいいだけ。
しんやさんによると、柄石の周りに石灰を撒き、小さなファンで床下の換気をすればまず大丈夫だと。
早速かずきちさんとしんやさんとでジョイに買い物。
僕とまさは床張りを続行。
しんやさんがいろいろアドバイスして石灰やファンなど買ってきた。
まさがマスクとゴーグルで石灰を撒き、しんやさんは床下に潜り、ファンの設置と配線。
なんでも彼は電線マニアらしく、家でも新たな配線工事などをやってると。
僕のキッチン道具マニアも珍しいかもしれないが、電線マニアは初めて聞いた。
マニア=天職やからねー。
ファンはトイレの脱臭ファン、一個2000円程、これを3つ設置。
タイマーを大元に付け、一時間おきにオン、オフさせる。
これは節電とファンの寿命を延ばす為。
このタイマー(980円)を使って夜中の冷蔵庫を開けない時間帯に一日一時間でもオフするようにするだけでもかなりの節電になるそう。
マ、マニアックやー。
悪徳業者なんかはこのファンの設置だけで10万とかぼったくるそう。
その後作業は順調に進み、床も三分の一以上、シロアリ対策もばっちり。
まさなんか石灰を撒く為に床下を這いずり回り「面白~い、昔の家ってすごーい!」と感動しまくり。
僕も解体現場には随分足を運んでるが、昔の家を修理したりバラシたりするのってめちゃ面白い。
大工さんの技術の凄さも勉強になるが、ちっちゃな石の上にきゃしゃな柄を立てて置いてるだけの基礎を見れば廃材天国などマシなもの。
ベタ基礎だ、耐震だと不安を煽って金儲けし、シロアリ駆除でもぼったくり。
そんな不安を煽る広告と洗脳に騙されるなよ。
シロアリに喰われるぐらいどうってことないって。
喰われながら140年もこの家は建ってるんやから。
○○になったらどうしよう、、、とありもしない未来の不安を考えるより今したい事をせよ。
その不安を解消する為にお金をかけ、その金を稼ぐ為にしたくもない仕事をやめられないなど、もってのほかだぞ。
しんやさんのマニアぶりに脱帽し、シロアリさんが居てくれたお陰で昨日も一日楽しめた。
結局もう一日はいるな。
杉板張りを完成させその上に柿渋を塗る。
次は16日。
なんちゃって大工を経験したい人はどうぞー。
2008年07月12日
築140年の古民家の床の張替え
昨日は高松の塩江、マイミクかずきさん主宰のわあいに行く。
築140年というとんでもない年月の小さな古民家。
茅葺にトタンを被せた、県内でも南部の山の中に行くとよく目にするタイプ。
わあいとは当初フリースクールの中でもデモクラティックスクールというボストンにあるサドベリーバレースクールをベースに子どもたちを集めて自由な学校という形で始まった。
今は大人も子どもも自由な自分になれる場として変革。
僕も兵庫のまっくろくろすけとアメリカのサドベリーバレースクールのインターンプログラムに参加して、それまでの教育観、学校、自由、人生、、、いろーんな意味でとてつもなく衝撃を受けた。
それまでも常識という囚われを外し、学校やテレビから受ける一方的な洗脳から自由にならないと、と思っていたにもかかわらず、完璧に僕の考え方を破壊し、それこそ自由な価値観をもたらしてくれた。
デモクラティックスクールとは。
チャイムなし、授業なし、先生なし、4歳から18までが同時に通い、クラス分けもなし、何をしても自由だが、自己管理は当然、学校の運営にまで責任を持つという考え方。
校則はないが、困った事が起きると子ども達が話し合って解決に向かう。
で、今まで子どもたちで決めたルールがタウンページ程もある本になってる。
常に基本がこのミーティング。
何をしたいか?したくないか?全てミーティングで自分が納得するまで話し合う。
何と、先生はいないが、ごく少人数のスタッフと呼ばれる大人たち(職員)を雇うか辞めさせるかも子どもたちが決める。
勉強は興味があれば上の子に聞いて自然とマスターしていくそう。
面白いのが、卒業生の大半は自分のやりたい事を見つけ、アーティストや職人になる子もいるが、大学に進学する率が高い事。
ほんとうに勉強したくなって行く大学はさぞ有意義なことだろう。
一番凄いのは創設者のダニエルさん始め、大人のスタッフたち。
とにかく完全に子どもたちを信じてる。
子どもが頼めば可能な限りのサポートをする。
子どもはほっといても自由。
その子どもを邪魔しないことに大人は最大の努力をしないと。
もちろん安全や躾という意味では大人が自分の生き方で手本を見せるだけ。
わあいの作業。
昨日一日、僕とかずきちさん、最近わあいに住みだしたまさの3人で、腐った床を解体して、修理する。
かつてシロアリさんに喰われた(今はいないようだった)大引きがボソボソのパスパス。
いやー、自然界ではシロアリさんのお陰で倒れた木が土に戻るというのがよく分かる。
昔の民家は通気の為に床下を掘り下げてる。
みんなその中に入り、腐った大引きに根太、座板などを全部撤去。
柄の腐ったのもジャッキでツッパリ取替え。
この辺りの作業に使う材料はわあいのお隣さんが解体した時の廃材を貰って庭に積んでたものを使う。
なんちゃって大工の僕が棟梁なんで早い、早い。
多少あわない所はノミの代わりにチェーンソーでギャーンと削る。
僕らがやってる間にかずきちくんが、超巨大ホームセンターのジョイに行き、フローリングの板を物色。
四国産の30ミリの無垢の杉板を買って来た。
イイ匂いー、美しいー。
廃材天国は一本も木を買わないというコンセプトなのでこんな新品の材料は使わないが、、、。
羨ましいほどいい材料だ。
結局、柄と大引きの入れ替え、根太の半分ぐらいまでいった。
畳じゃなくフローリングになるので、根太の下にスペーサーをカマシて高さと水平を調整。
かずきちさんもまさも初めての本格的な大工仕事にハマッてた。
プチワークショップという感じになった。
僕もなんちゃって大工でこういう民家を直すのは始めてだが、施主が何でもありのパッパッパーのかずきちさんで良かった。
昔の家を解体すると勉強になる事も多い。
まあ、敢えて僕はなんちゃってで行くけどね。
こんだけプロに頼めば何十万で済まないかも、、、。
こわーーー。
テキトーで何とかなるもんよ。
休憩の時は最近かずきちさんのハマッてる野草茶、オオバコやスギナといろいろ飲ませてくれた。
塩分とミネラル補給はアンデスのピンクの岩塩。
汗は惜しげもなくどんどん出るからね。
水分だけでは血が薄まってしまう。
スポーツドリンクは砂糖の飲みすぎになてしまうから。
続きは明日、日曜日。
柄の周りに竹酢液を塗ったり、根太の続き、いよいよフローリングの施工と柿渋塗りと一日あれば完成を見るだろう。
県内の方でまだ予定の入ってない人はどうぞ塩江まで。
わあい
087-890-2262
2008年07月11日
横焚きを終え、大くべで超燻す
昨日の朝一で横焚きに入る。
窯焚きの9割以上は正面の口から焚くのだが、最後の半日だけ窯の横に設けてある小さな口から細い薪を差込み、後ろの温度を上げてやる。
今回の設定は強還元の黒陶ねらい。
黒陶とは能登半島の先端、珠洲市に昔から伝わる伝統的な手法で、焼き締めなんだが、温度を上げた最後の仕上げに薪をアホ程くべてわざと不完全燃焼状態にし、機関車のごとくモクモク煙を出し、燻すのだ。
珠洲には備前の弟子時代にヒッチハイクで勉強に行った。
昔の黒陶の途絶えた技術を復興させた中山達磨氏を訪ねた。
思い切り手伝う気満々で行ったにも関わらず、毎日近くの行き着けの蕎麦屋、親しいランプの宿、鮨屋と呑んで喋ってばかり。
そうして一週間程経て、さすがに手伝うことを懇願し、4日間は手伝った。
やっぱりね。
見学とか遊びに行きますぐらいじゃ何にも吸収できない。
一緒に朝から晩まで仕事を共にし、飯の最中に情報交換。
お互い、非常に健全なやりとり。
今のうちのウーフ的受け入れスタイルもそれ。
うちの窯焚きのスタイルだが、今後はますます少数精鋭にしていく。
じゃんじゃん生産しない。
どんどん売れないというのも現実だが、こんだけあらゆる物が飽和してる現代にどんどん生産し、消費を促すのはピンボケどころか僕の提起する自由なライフスタイルとは丸っきり矛盾する。
今後はみんなで窯を作るワークショップ、土を精製し、作品を作るワークショップ、窯焚きのワークショップと、その貴重な体験を売る。
もちろん窯作りとかに関してはお金は取らない。
みんな作品だけ作れたら満足する。
うちはそうじゃないんよーと提案する。
このクソ暑い窯焚きも実は有難い経験。
これは陶芸だけじゃなく、薪で焼くピザ体験、おくどさんで飯焚き体験も同じ。
え~、、、と思うかもしれないが、ライオンズクラブがうちに団体で体験しに来たいと言ってくれてる。
もちろんやぶさかでない。
一見シャロー(浅い)なこういう一日体験で目からウロコをバラバラと落とさせる自信あり。
この入り口は悪くないと思ってる。
まあ、みんな喰いつく、喰いつく。
おいで、おいで、こっちのみ~ずはあ~まいぞ。
でもこのおいしい水(空気)を飲むと、いつも飲んでる不味くて不自由な水は飲めないぞ。
その覚悟は出来とるか!
覚悟して来いよ。
こっちは常に気合充分、待ったなし。
ネガティブな悩みなどけちらしてくれる!



窯焚きの9割以上は正面の口から焚くのだが、最後の半日だけ窯の横に設けてある小さな口から細い薪を差込み、後ろの温度を上げてやる。
今回の設定は強還元の黒陶ねらい。
黒陶とは能登半島の先端、珠洲市に昔から伝わる伝統的な手法で、焼き締めなんだが、温度を上げた最後の仕上げに薪をアホ程くべてわざと不完全燃焼状態にし、機関車のごとくモクモク煙を出し、燻すのだ。
珠洲には備前の弟子時代にヒッチハイクで勉強に行った。
昔の黒陶の途絶えた技術を復興させた中山達磨氏を訪ねた。
思い切り手伝う気満々で行ったにも関わらず、毎日近くの行き着けの蕎麦屋、親しいランプの宿、鮨屋と呑んで喋ってばかり。
そうして一週間程経て、さすがに手伝うことを懇願し、4日間は手伝った。
やっぱりね。
見学とか遊びに行きますぐらいじゃ何にも吸収できない。
一緒に朝から晩まで仕事を共にし、飯の最中に情報交換。
お互い、非常に健全なやりとり。
今のうちのウーフ的受け入れスタイルもそれ。
うちの窯焚きのスタイルだが、今後はますます少数精鋭にしていく。
じゃんじゃん生産しない。
どんどん売れないというのも現実だが、こんだけあらゆる物が飽和してる現代にどんどん生産し、消費を促すのはピンボケどころか僕の提起する自由なライフスタイルとは丸っきり矛盾する。
今後はみんなで窯を作るワークショップ、土を精製し、作品を作るワークショップ、窯焚きのワークショップと、その貴重な体験を売る。
もちろん窯作りとかに関してはお金は取らない。
みんな作品だけ作れたら満足する。
うちはそうじゃないんよーと提案する。
このクソ暑い窯焚きも実は有難い経験。
これは陶芸だけじゃなく、薪で焼くピザ体験、おくどさんで飯焚き体験も同じ。
え~、、、と思うかもしれないが、ライオンズクラブがうちに団体で体験しに来たいと言ってくれてる。
もちろんやぶさかでない。
一見シャロー(浅い)なこういう一日体験で目からウロコをバラバラと落とさせる自信あり。
この入り口は悪くないと思ってる。
まあ、みんな喰いつく、喰いつく。
おいで、おいで、こっちのみ~ずはあ~まいぞ。
でもこのおいしい水(空気)を飲むと、いつも飲んでる不味くて不自由な水は飲めないぞ。
その覚悟は出来とるか!
覚悟して来いよ。
こっちは常に気合充分、待ったなし。
ネガティブな悩みなどけちらしてくれる!
2008年07月09日
ありがたくない窯焚き
めちゃくちゃ早い起床。
窯焚きの当番が2時から。
昨日の朝から薪で焚いてる。
親父はおとといの晩から。
暑い暑い、汗何ℓ?
ビール何ℓ?
今回は親父のとこの小さい穴窯。
親父と僕と陶芸教室のおじさんとの3交代。
昨日はおじさんが来てくれてからは僕は薪の段取り。
窯を焚きながら薪を運ぶのはうちぐらい。
備前焼の先生なら、電話一本で薪屋が事前に薪を窯の脇へ運び込んでる。
うちは適当に庭師や土木屋の持ってきた廃材が積み込まれてるのを油圧の薪割り機で割りながら焚く。
面白いのが、備前焼の先生が一回窯を焚く薪代が40~50万円。
このアメリカ製の薪割り機が24万円。
直径1mもあるこんぴらさんの松も割れた。
木なら割れないものはない。
60㎝に切ってさえいれば。
備前は松オンリー。
うちは雑木中心。
薪の種類で上がりが全然違うのよ。
もっとも酸化炎と還元炎で根本的に変わるんやけど。
今回は強還元で黒っぽく上げる予定。
焼き締めで釉薬なしというといっつも同じ傾向かというとそうじゃない。
土は同じでも焚き方で随分変わる。
ちゃんと理屈はあるにせよ、凄いねー。
神秘やねー。
でもこの季節は窯焚きには最悪。
全然火がありがたくない。
せめて、夜だけでもぬくいなー、やっぱり火ってええなーと言える季節に焚きたいもの。
窯焚きの当番が2時から。
昨日の朝から薪で焚いてる。
親父はおとといの晩から。
暑い暑い、汗何ℓ?
ビール何ℓ?
今回は親父のとこの小さい穴窯。
親父と僕と陶芸教室のおじさんとの3交代。
昨日はおじさんが来てくれてからは僕は薪の段取り。
窯を焚きながら薪を運ぶのはうちぐらい。
備前焼の先生なら、電話一本で薪屋が事前に薪を窯の脇へ運び込んでる。
うちは適当に庭師や土木屋の持ってきた廃材が積み込まれてるのを油圧の薪割り機で割りながら焚く。
面白いのが、備前焼の先生が一回窯を焚く薪代が40~50万円。
このアメリカ製の薪割り機が24万円。
直径1mもあるこんぴらさんの松も割れた。
木なら割れないものはない。
60㎝に切ってさえいれば。
備前は松オンリー。
うちは雑木中心。
薪の種類で上がりが全然違うのよ。
もっとも酸化炎と還元炎で根本的に変わるんやけど。
今回は強還元で黒っぽく上げる予定。
焼き締めで釉薬なしというといっつも同じ傾向かというとそうじゃない。
土は同じでも焚き方で随分変わる。
ちゃんと理屈はあるにせよ、凄いねー。
神秘やねー。
でもこの季節は窯焚きには最悪。
全然火がありがたくない。
せめて、夜だけでもぬくいなー、やっぱり火ってええなーと言える季節に焚きたいもの。
2008年07月07日
プチお祝い会のプレゼントにヤギ!?
昨日は同級生で建築士のわきおさんと善通寺の建設会社の社長、いつもの仲間たちと、6人で廃材天国に遊びに来てくれた。
ほとんどの人が初めてで、えらく感激してくれた。
僕とあっこちゃんもかなり料理を楽しませてもらった。
こういう気のおけない仲間の来客はほんとに楽しい。
あっこちゃんなど何日も前から、ここぞとばかりに料理書を次々と出してはメニュー構成に余念がない。
時間のかかるものの仕込みもばっちり。
今回はイタリアン。
ウェルカムドリンクに桃100%でスムージー。
これは先日超大量にもらった出荷できない桃を冷凍してた。
自ビールで乾杯。
自家製の鶏ハムを水菜の上に並べたサラダ。
これは普通のハム(2、3週間かかる)に比べると、4日で出来るお手軽版。
胡瓜の洋風和え物。
豆の入ったラタトゥイユ。
トマトのサラダ。
定番玄米おにぎり。
一押しは手打ちパスタでラザニア。
男性陣などあっこちゃんの期待を裏切り「初めて食べるー。」と。
写真のパスタマシンは完全にプロ仕様の重くて堅牢な本物の道具。
大好きな中古厨房ショップテンポスでアホ安で買った。
パスタ(生地のこと)が手打ちなだけでなく、トマトソースも肉なしだし、ホワイトソースも豆乳ベースでバターなし、と手作りだからしつこくない。
もちろん店のは一口食べてはおいしいけど、たくさん食べると気持ち悪くなる。
うちの目指すのはいかに滋味深い感動的なおいしさ味わえるか。
その為の労力は惜しまない。
無添加ありきじゃなく、結果として市販のソースや加工品に感動的なそれはなく、使える訳がない。
自分で育てたトマトでソースを作る、うちの鶏の卵を練りこみパスタを打つ。
これこそがほんとうの贅沢。
みんなこんなにおいしいのなら店を開いたらと言ってくれるが、ここまでの手間をお金取って毎日開ける店ではまずかけられない。
週に一回一組だけとかなら可能かも。
でもお金取ってよりは仲間との物々交換(物じゃなくても)の方が楽しい。
今回はふんだんに夏野菜が採れてて、かなり食材の自給率は高かった。
廃材天国の畑はまだ狭いので、親父の方の畑からやけど。
トマト、ナス、ピーマン、ズッキーニ、じゃがいも、玉ねぎ、しし唐、水菜、小松菜、人参、夏野菜の果菜はもちろん嬉しいが、葉ものや人参の間引きの小さいのがおしゃれでいい。
で、タイトルのヤギ。
わきおさんが全くお知らせなしで連れてきて、みんなからのプレゼント!?
うちが飼うつもりかどうか、全く聞きもせずに連れて来るか!
僕はここへ来てどんどん育つ草に悩みつつあったので純粋に嬉しかった。
あっこちゃんは朝になっても「、、、私は反対。」と。
なぜなら彼女は一軒目の時にオーナーの河野さんが連れてきたヤギの世話を野遊をおぶって繋いだり、嫌々でも世話しないといけない感で嫌な思い出がある。
まあ、今回は僕も前みたいに陶芸の仕事を優先させたりせずにじっくり世話しよう。
まず小屋がいるな。
何処に作ろうかー???
計画してゆっくり考えた訳でないから、今から急いで考えんとー!
もちろん材料は山程あるからええけど。
とにかく廃材の山が片付くまでは新たな建物には着工しないでおこうと思ってたが、ヤギさんの小屋は急がれる。
おもしろくなってきたー。
ヤギの後ろは最近作ったポスト。
雑木の丸太で組み、屋根は麦わら。
2008年07月06日
陶芸とかアートのオルタナティブスタイル
昨日の陶芸日記に続き。
弟子から帰って来た当初は「売るために作るんじゃない。」「理解されないものでもいいんだ。」「より、滅茶苦茶やってやろう。」というような変に捻じ曲がった感情が強かった。
岡本太郎の「現代の芸術とは、きれいであってはいけない、うまくあってはいけない、心地よくあってはいけない。」とかにもハマッてたし、何か抽象芸術とは理解されなくて当然みたいなのがあった。
自分の内面を外に表現する訳やから絵でも写真でも書でも陶芸でもそういう要素は強い。
保守的な今までどおり、こうやってれば安心みたいなものに対するアンチテーゼ。
昨日も書いたが今はもう陶芸家という形態ではなくなってきたし、たまに作って楽しいし、多少は換金作物にもなるしって感じ。
力が抜けたというのもあるが、わざと変なものを提起しようとは思わない。
考えるに、20世紀のぐちゃぐちゃ芸術みたいなのは社会がおかしくなってきた事への心の叫びであり、不自然な所へ追い込まれた人間の発する負のエネルギーやったんちゃうか。
もちろん太郎さんの言う富士山さえ描いときゃまちがいないと言う奴は最低だというのは当たり前。
そういうのは表現以前やね。
これからは素直に美しいものを表現していく時代やと思う。
特に陶芸なんかは工芸という「用」あっての分野やから、やっぱし使いやすい、洗いやすい、軽い、というのも大切。
ほんと今までは使いにくくても重くても「これ」が俺の作品じゃーみたいな所が強かった。
いわゆる現代美術にはもう興味はない。
権威主義にのっとった師匠の言う事に従って売れる為の物を作る訳でもなく、それに反抗してわざとぐちゃぐちゃのものを提起するのでもない。
よく「私は芸術とか分からないんですよー。」という人が多いが、分かる訳がないよ。
作った本人も素直じゃない上にそんな負のエネルギーに共感できるのはずーっと現代美術を勉強してきたオタクだけだ。
ほんとに美しいものとはなんぞや?
今の僕が美しいと感じるものは田んぼの稲であり、茅葺の民家であり、たくさんの子どもがアホみたいに遊ぶ姿、それこそ日本人の原風景。
そういう生き方を目指す。
自分だけというエゴじゃなく、みんなでそういう美しい生き方を助け合って実現する。
僕の家族だけが、山奥で自給自足するんじゃない。
たくさんの人に「やってしまえば簡単やでー。」と提起できるのが今の僕のスタイル。
もちろん今は過渡期やからすぐにみんなが田園のなかでつつましく生きるという訳じゃない。
でも現実にうちは借金なしで家も建て、月に数万の必要経費は少しの作品や自給自足体験の講師料とかで自然になんとかなってる。
どうやってお金を稼ごうとかほとんど考えなくても自分たちの家族にとって必要なこと、好きなこと、ワクワクすることをするのみ。
僕なら畑の拡張とか、あっこちゃんならマニアック菓子作りとか。
まだ僕たちにも出来てない事は山ほどある。
というかやりたい事がたくさんある。
自分の育てた小麦で手打ちうどん打って、出汁の醤油も自家製、もちろんその材料の豆も自家製とか。
考えただけでもワクワクするやん。
もちろん考えるだけというではしょうもない。
実際に麦を播く、その行動に移すのが大切。
もっと大事なことは行動に移せるように自由にならないと。
出来ない要素、例えば忙しくて時間がないとかをクリアしていかないと。
例えたくさんの作品の注文が来ても超忙しくなって畑も出来ないというのは僕からしたら本末転倒でしかない。
好きなことを毎日やって生活する。
これを実現するためには不自然な自分の囚われを外していくしかない。
そうするとだんだん本来の自分のエネルギーが発揮されるぞ。
ああ、気が付いたら夢が叶ってたわ。
みたいなー。
軽くいこう。
全開で!!!
弟子から帰って来た当初は「売るために作るんじゃない。」「理解されないものでもいいんだ。」「より、滅茶苦茶やってやろう。」というような変に捻じ曲がった感情が強かった。
岡本太郎の「現代の芸術とは、きれいであってはいけない、うまくあってはいけない、心地よくあってはいけない。」とかにもハマッてたし、何か抽象芸術とは理解されなくて当然みたいなのがあった。
自分の内面を外に表現する訳やから絵でも写真でも書でも陶芸でもそういう要素は強い。
保守的な今までどおり、こうやってれば安心みたいなものに対するアンチテーゼ。
昨日も書いたが今はもう陶芸家という形態ではなくなってきたし、たまに作って楽しいし、多少は換金作物にもなるしって感じ。
力が抜けたというのもあるが、わざと変なものを提起しようとは思わない。
考えるに、20世紀のぐちゃぐちゃ芸術みたいなのは社会がおかしくなってきた事への心の叫びであり、不自然な所へ追い込まれた人間の発する負のエネルギーやったんちゃうか。
もちろん太郎さんの言う富士山さえ描いときゃまちがいないと言う奴は最低だというのは当たり前。
そういうのは表現以前やね。
これからは素直に美しいものを表現していく時代やと思う。
特に陶芸なんかは工芸という「用」あっての分野やから、やっぱし使いやすい、洗いやすい、軽い、というのも大切。
ほんと今までは使いにくくても重くても「これ」が俺の作品じゃーみたいな所が強かった。
いわゆる現代美術にはもう興味はない。
権威主義にのっとった師匠の言う事に従って売れる為の物を作る訳でもなく、それに反抗してわざとぐちゃぐちゃのものを提起するのでもない。
よく「私は芸術とか分からないんですよー。」という人が多いが、分かる訳がないよ。
作った本人も素直じゃない上にそんな負のエネルギーに共感できるのはずーっと現代美術を勉強してきたオタクだけだ。
ほんとに美しいものとはなんぞや?
今の僕が美しいと感じるものは田んぼの稲であり、茅葺の民家であり、たくさんの子どもがアホみたいに遊ぶ姿、それこそ日本人の原風景。
そういう生き方を目指す。
自分だけというエゴじゃなく、みんなでそういう美しい生き方を助け合って実現する。
僕の家族だけが、山奥で自給自足するんじゃない。
たくさんの人に「やってしまえば簡単やでー。」と提起できるのが今の僕のスタイル。
もちろん今は過渡期やからすぐにみんなが田園のなかでつつましく生きるという訳じゃない。
でも現実にうちは借金なしで家も建て、月に数万の必要経費は少しの作品や自給自足体験の講師料とかで自然になんとかなってる。
どうやってお金を稼ごうとかほとんど考えなくても自分たちの家族にとって必要なこと、好きなこと、ワクワクすることをするのみ。
僕なら畑の拡張とか、あっこちゃんならマニアック菓子作りとか。
まだ僕たちにも出来てない事は山ほどある。
というかやりたい事がたくさんある。
自分の育てた小麦で手打ちうどん打って、出汁の醤油も自家製、もちろんその材料の豆も自家製とか。
考えただけでもワクワクするやん。
もちろん考えるだけというではしょうもない。
実際に麦を播く、その行動に移すのが大切。
もっと大事なことは行動に移せるように自由にならないと。
出来ない要素、例えば忙しくて時間がないとかをクリアしていかないと。
例えたくさんの作品の注文が来ても超忙しくなって畑も出来ないというのは僕からしたら本末転倒でしかない。
好きなことを毎日やって生活する。
これを実現するためには不自然な自分の囚われを外していくしかない。
そうするとだんだん本来の自分のエネルギーが発揮されるぞ。
ああ、気が付いたら夢が叶ってたわ。
みたいなー。
軽くいこう。
全開で!!!
2008年07月05日
数ヶ月ぶりにロクロに座る
3月に親父が窯焚きをしたんで、ほんの少し(200個未満)だけコップや茶碗、皿なんかを作った。
それ以来陶芸の仕事はしていない。
今度7月の頭にまた親父の窯焚きがある。
前回は大きい窯だったが、今回は小さい穴窯。
折角焚くんならという事でまた2,3日だけ作る。
電動ロクロなら一日ぶっ通しでひくと200個ぐらいは作れる。
プロの職人は500個とかひく。
で、翌日削り。
僕の場合は削りの方に時間をかける。
ロクロで成形するのは少しならおもしろくない事はないが、毎日毎日やってるとほんとにつまらない。
あれは能率よく、形や大きさを揃えて作るには最適の機械なので、自分もその機械の一部になってしまう。
もちろん僕の場合は全く同じ規格を決めて量産するというスタイルじゃないのでまだまし。
プロの職人など、ぴったり高さも直径も同じ美しい仕事をする。
ここらへんは良い悪いじゃないのだが、作り手が自由な感覚になってくればいろいろ変化して当然。
6日、一日だけバーナーで焙りという湿気を抜くために低温で焼く。
7,8,9日と薪で焚く。
窯が小さいので日にちも短い。
大きい方の窯になると10日間ほど焚く。
この窯焚きが楽しい。
毎日お祭り騒ぎ、夜は宴会。
銘々にお酒やビールなんかを持ち寄り、僕は毎日料理担当。
こういうスタイルはまず備前焼の先生方はやってない。
牛窓の小向氏の窯焚きがいっつもこれ。
窯と料理とどっちがメインやねん、みたいな。
もちろん窯もちゃんと焚いてるが、スタッフが充実してるし、この窯の火を囲んで喋るのは楽しい上においしいお酒と料理は格別。
というか毎日の料理に手を抜かないのは焼き物以上に僕が小向さんから勉強した大切な事。
今回日程は少ないが、ちゃんとお酒のアテは充実させるんでお近くの方は遊びに来てねー。
窯の火の前で呑むのがとにかくいい。
ちょっと今回は暑いか。
それ以来陶芸の仕事はしていない。
今度7月の頭にまた親父の窯焚きがある。
前回は大きい窯だったが、今回は小さい穴窯。
折角焚くんならという事でまた2,3日だけ作る。
電動ロクロなら一日ぶっ通しでひくと200個ぐらいは作れる。
プロの職人は500個とかひく。
で、翌日削り。
僕の場合は削りの方に時間をかける。
ロクロで成形するのは少しならおもしろくない事はないが、毎日毎日やってるとほんとにつまらない。
あれは能率よく、形や大きさを揃えて作るには最適の機械なので、自分もその機械の一部になってしまう。
もちろん僕の場合は全く同じ規格を決めて量産するというスタイルじゃないのでまだまし。
プロの職人など、ぴったり高さも直径も同じ美しい仕事をする。
ここらへんは良い悪いじゃないのだが、作り手が自由な感覚になってくればいろいろ変化して当然。
6日、一日だけバーナーで焙りという湿気を抜くために低温で焼く。
7,8,9日と薪で焚く。
窯が小さいので日にちも短い。
大きい方の窯になると10日間ほど焚く。
この窯焚きが楽しい。
毎日お祭り騒ぎ、夜は宴会。
銘々にお酒やビールなんかを持ち寄り、僕は毎日料理担当。
こういうスタイルはまず備前焼の先生方はやってない。
牛窓の小向氏の窯焚きがいっつもこれ。
窯と料理とどっちがメインやねん、みたいな。
もちろん窯もちゃんと焚いてるが、スタッフが充実してるし、この窯の火を囲んで喋るのは楽しい上においしいお酒と料理は格別。
というか毎日の料理に手を抜かないのは焼き物以上に僕が小向さんから勉強した大切な事。
今回日程は少ないが、ちゃんとお酒のアテは充実させるんでお近くの方は遊びに来てねー。
窯の火の前で呑むのがとにかくいい。
ちょっと今回は暑いか。