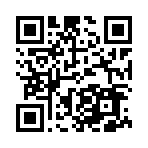2009年12月02日
新型薪ストーブ、初火入れ
今さっき、新作の薪ストーブに初の火入れしたよ。
もう、ストーブの上で、3年番茶と味噌汁用の昆布出汁が沸いてる。
玄米ご飯も蒸し器で蒸されてるし。
燃え具合最高!
エアの口の大きさなんかも適当やったけど、丁度ええみたい。
デッカイ薪がじゃんっじゃんくべられるのがいい。
当初心配してた、大口を開けた時の、室内への煙の漏れもそんなに多くない。
煙突6本もストレートに着けとるから、「引き」がええんやね。
家庭用の鍋やったら、4つも5つも乗る所もええしね。
朝の味噌汁と、お茶沸かすのはこれだけでいけそう。
もちろん、中華なべや圧力鍋を強火にかけるのは、今ままでのキッチンストーブでの直火じゃないとダメなんで、冬場は併用になるね。
この燃焼スペースの大きさも凄いね。
バーモントキャスティングスもダッチウエストもお呼びじゃないねー。
それにしても、僕みたいな素人鉄工職人は別として、厚めの鉄板で、大型の薪ストーブ作ったら、鉄工所の職人さんなら売れるんちゃう?
だって、今回のにしても、大きさ的には高級ストーブで言う所の5、60万の奴以上に大きいんやもん。
大体、ネットの5万前後の中国製の奴なんかは小さい、小さい。
一軒目の廃材ハウスの時はそれで十分やったし、今は実家のダイニングに置いてて、やっぱり、暑くなりすぎるぐらい。
天井の低い普通の家ではそれでええんかもね。
前にも書いたけど、そういうアメリカやヨーロッパの高級薪ストーブは、鋳物で堅牢な上に、燃焼効率を徹底的に考えて作ってる。
友人のカナダ製のなんか、金属の触媒(2年ごとに交換)の作用で、ある程度燃やした後は、完全に空気を遮断して、煙をも再燃焼させるというスゴ技で、一升瓶ぐらいの薪が2、3本で3時間ぐらい暖房できてたもん。
でもねー。
ここは廃材天国じゃー。
燃焼効率!?
関係ないね。
陶芸、建築、料理、風呂、暖房といくら使っても、なんぼでも持って来てくれるがなーーー。
しかも、サイズ別に各種いろんな業者がもてきてくれるんで、薪作りの手間もほとんど、ない。
この新作薪ストーブを作る最大の動機は、シルバー人材センターや造園屋のおっちゃんが持って来てくれる、50~60㎝の雑木を伐採した薪を使う為。
これは廃材天国の塀よろしく、道路沿いにズラーッと積み込んである。
これを焚けば、チェーンソーでカットする手間も全くなし。
乾いてしまった雑木なんかはソーチェーンにかなり負担をかけるからね。
ビンビンに研いでたらまだええけど、無理して長時間かけて切ると、ガイドバーが焼けて、最悪交換って事態にもなりかねんからねー。
小型のチェーンソーでもガイドバーは1万ぐらいするからね。
道具は命やぞ。
とにかく、とにかくやな。
薪ストーブを導入するにあたっては。
ちょこっとの手間で、毎日ストレスなく、薪に遠慮もぜずにじゃんじゃん焚けるような環境を作る事が一番大事。
薪を作る手間だとか、運ぶ労力が大変では、快適な薪生活は送れないぞ。
廃材天国でも、超頑張って、料理や風呂焚きや薪ストーブをやってる訳じゃない。
ここがポイント。
タダで各種いろんなサイズの薪が揃って、ガスも灯油も買わなくてええ、左ウチワライフ。
う~ん、この快適ライフを自画自賛と言わずに何と言おうか。
もっと、廃材天国が寒い所やったらよかったんかも、、、。




もう、ストーブの上で、3年番茶と味噌汁用の昆布出汁が沸いてる。
玄米ご飯も蒸し器で蒸されてるし。
燃え具合最高!
エアの口の大きさなんかも適当やったけど、丁度ええみたい。
デッカイ薪がじゃんっじゃんくべられるのがいい。
当初心配してた、大口を開けた時の、室内への煙の漏れもそんなに多くない。
煙突6本もストレートに着けとるから、「引き」がええんやね。
家庭用の鍋やったら、4つも5つも乗る所もええしね。
朝の味噌汁と、お茶沸かすのはこれだけでいけそう。
もちろん、中華なべや圧力鍋を強火にかけるのは、今ままでのキッチンストーブでの直火じゃないとダメなんで、冬場は併用になるね。
この燃焼スペースの大きさも凄いね。
バーモントキャスティングスもダッチウエストもお呼びじゃないねー。
それにしても、僕みたいな素人鉄工職人は別として、厚めの鉄板で、大型の薪ストーブ作ったら、鉄工所の職人さんなら売れるんちゃう?
だって、今回のにしても、大きさ的には高級ストーブで言う所の5、60万の奴以上に大きいんやもん。
大体、ネットの5万前後の中国製の奴なんかは小さい、小さい。
一軒目の廃材ハウスの時はそれで十分やったし、今は実家のダイニングに置いてて、やっぱり、暑くなりすぎるぐらい。
天井の低い普通の家ではそれでええんかもね。
前にも書いたけど、そういうアメリカやヨーロッパの高級薪ストーブは、鋳物で堅牢な上に、燃焼効率を徹底的に考えて作ってる。
友人のカナダ製のなんか、金属の触媒(2年ごとに交換)の作用で、ある程度燃やした後は、完全に空気を遮断して、煙をも再燃焼させるというスゴ技で、一升瓶ぐらいの薪が2、3本で3時間ぐらい暖房できてたもん。
でもねー。
ここは廃材天国じゃー。
燃焼効率!?
関係ないね。
陶芸、建築、料理、風呂、暖房といくら使っても、なんぼでも持って来てくれるがなーーー。
しかも、サイズ別に各種いろんな業者がもてきてくれるんで、薪作りの手間もほとんど、ない。
この新作薪ストーブを作る最大の動機は、シルバー人材センターや造園屋のおっちゃんが持って来てくれる、50~60㎝の雑木を伐採した薪を使う為。
これは廃材天国の塀よろしく、道路沿いにズラーッと積み込んである。
これを焚けば、チェーンソーでカットする手間も全くなし。
乾いてしまった雑木なんかはソーチェーンにかなり負担をかけるからね。
ビンビンに研いでたらまだええけど、無理して長時間かけて切ると、ガイドバーが焼けて、最悪交換って事態にもなりかねんからねー。
小型のチェーンソーでもガイドバーは1万ぐらいするからね。
道具は命やぞ。
とにかく、とにかくやな。
薪ストーブを導入するにあたっては。
ちょこっとの手間で、毎日ストレスなく、薪に遠慮もぜずにじゃんじゃん焚けるような環境を作る事が一番大事。
薪を作る手間だとか、運ぶ労力が大変では、快適な薪生活は送れないぞ。
廃材天国でも、超頑張って、料理や風呂焚きや薪ストーブをやってる訳じゃない。
ここがポイント。
タダで各種いろんなサイズの薪が揃って、ガスも灯油も買わなくてええ、左ウチワライフ。
う~ん、この快適ライフを自画自賛と言わずに何と言おうか。
もっと、廃材天国が寒い所やったらよかったんかも、、、。
2009年12月02日
屋根上に煙突つけるはチェーンソー
いよいよ、新作薪ストーブの煙突の施工。
一番元口の一本だけはステンレス製のを新調した。
元が一番火力が強くて、傷みが激しいからね。
後はブリキに塗装した奴で、行き着けの金物屋から大量にもらってストックしてる煙突。
廃材天国は天井が高いのと、今回の薪ストーブが大きいのとで、煙突は直径12cm、長さ90cmのを6本と上のH型の傘。
まずは室内にハシゴをかけて、薪ストーブの口に向けて「下げ振り」(垂直を計る道具)を降ろして天井に煙突の中心のマーキングをする。
そこへインパクトに下穴用のキリを付けて天井から屋根に向かってブスッと穴を貫通させる。
そのキリだけを残して、屋根へ登る。
廃材天国の構造は、30㎜の厚い野地板の上にブルーシートで防水して、その上に10㎜ぐらいの薄い板でシートを覆ってる。
更に、その板が飛ばないように、大量の石で重しをかけてる。
そして、屋根の上から突き抜けてるキリを確認する。
そのキリの周囲の板をチェーンソーで、ビニールを破らないように丁寧にカット。
今度はビニールをカッターでカット。
最後にそのビニールの際にチェーンソーを突っ込み、野地板をカット。
家の中は削りカスだらけ、、、。
次はいわゆる「メガネ石」という耐火性の薄い石の板に煙突の太さの穴の開いた部材なんかをはめ込む所。
もちろんメガネ石なんか買う訳ないので、これまた金物屋のペケ品の0、35㎜のカラートタンを金切り鋏で切って作る。
今回は防水性を高める為に二枚作ってビニールの下と上からとトタンで挟み込むように施工した。
ビニールとトタンの接着はセメダイン社の「スーパーX」というボンド。
コーキングに比べると、かなり高いけど、塩化ビニールのブルーシートと鉄板の接着に対してはこれしかない。
トタンの穴と煙突の接点には、アメリカ製、ルトランド社の「耐火コーキング」。
耐火コーキングなるものが存在すること自体、最近知ったばかりなので、うちではこれが初の施工。
耐火と防水の両方をクリアしないといけない、こういう部分の工事は非常に難しい。
だから、既存の家に薪ストーブを導入する際には、どうしても煙突を曲げて壁から室外に出してしまいがち。
それは煙突の施工は簡単やけど、後々の煤掃除の煩わしさが付いて回る。
毎日焚けば1シーズン2回は最低でも煤掃除せんといかんからね。
一軒目の廃材ハウスの時は、何も知らずに「室内を横に這わせた方が放熱してよく温もるんじゃないか。」とか考えたおかげで煤掃除の頻度が凄かった。
絶対、煙突はストレートやで!
とにかく、メンテナンスがめんどくさくって使う頻度が落ちるなんざ超ダサい。
後は、煙突が風でグラつかないように、3方からステンレスの針金でヒカエをとって完成。
最後、薪ストーブと煙突の接点。
鉄板に穴を開けた後、細い鉄の帯でワッカを作って、煙突を差し込むようにしたけど、少しは遊びがあって、隙間が見えてる。
ここにはセメダイン社の「耐火パテ」。
何しろ、このパテは耐火温度1200℃!?
先ほどのアメリカ性の耐火コーキングは260℃。
ただ、耐火パテは水にはそんない強くない。
それで、耐火コーキングの防水&耐火の能力に期待する所が大きい訳。
煙突の上の方ならおそらく260℃で十分という気もするし。
これでいよいよ完成やーーー!!!

小さいのは旧の煙突穴

煙突と鉄板の接点の黒いのが耐火コーキング

旧の穴にも鉄板を被せて仕上げる

手前はキッチンストーブの煙突、直径15cmと太い
一番元口の一本だけはステンレス製のを新調した。
元が一番火力が強くて、傷みが激しいからね。
後はブリキに塗装した奴で、行き着けの金物屋から大量にもらってストックしてる煙突。
廃材天国は天井が高いのと、今回の薪ストーブが大きいのとで、煙突は直径12cm、長さ90cmのを6本と上のH型の傘。
まずは室内にハシゴをかけて、薪ストーブの口に向けて「下げ振り」(垂直を計る道具)を降ろして天井に煙突の中心のマーキングをする。
そこへインパクトに下穴用のキリを付けて天井から屋根に向かってブスッと穴を貫通させる。
そのキリだけを残して、屋根へ登る。
廃材天国の構造は、30㎜の厚い野地板の上にブルーシートで防水して、その上に10㎜ぐらいの薄い板でシートを覆ってる。
更に、その板が飛ばないように、大量の石で重しをかけてる。
そして、屋根の上から突き抜けてるキリを確認する。
そのキリの周囲の板をチェーンソーで、ビニールを破らないように丁寧にカット。
今度はビニールをカッターでカット。
最後にそのビニールの際にチェーンソーを突っ込み、野地板をカット。
家の中は削りカスだらけ、、、。
次はいわゆる「メガネ石」という耐火性の薄い石の板に煙突の太さの穴の開いた部材なんかをはめ込む所。
もちろんメガネ石なんか買う訳ないので、これまた金物屋のペケ品の0、35㎜のカラートタンを金切り鋏で切って作る。
今回は防水性を高める為に二枚作ってビニールの下と上からとトタンで挟み込むように施工した。
ビニールとトタンの接着はセメダイン社の「スーパーX」というボンド。
コーキングに比べると、かなり高いけど、塩化ビニールのブルーシートと鉄板の接着に対してはこれしかない。
トタンの穴と煙突の接点には、アメリカ製、ルトランド社の「耐火コーキング」。
耐火コーキングなるものが存在すること自体、最近知ったばかりなので、うちではこれが初の施工。
耐火と防水の両方をクリアしないといけない、こういう部分の工事は非常に難しい。
だから、既存の家に薪ストーブを導入する際には、どうしても煙突を曲げて壁から室外に出してしまいがち。
それは煙突の施工は簡単やけど、後々の煤掃除の煩わしさが付いて回る。
毎日焚けば1シーズン2回は最低でも煤掃除せんといかんからね。
一軒目の廃材ハウスの時は、何も知らずに「室内を横に這わせた方が放熱してよく温もるんじゃないか。」とか考えたおかげで煤掃除の頻度が凄かった。
絶対、煙突はストレートやで!
とにかく、メンテナンスがめんどくさくって使う頻度が落ちるなんざ超ダサい。
後は、煙突が風でグラつかないように、3方からステンレスの針金でヒカエをとって完成。
最後、薪ストーブと煙突の接点。
鉄板に穴を開けた後、細い鉄の帯でワッカを作って、煙突を差し込むようにしたけど、少しは遊びがあって、隙間が見えてる。
ここにはセメダイン社の「耐火パテ」。
何しろ、このパテは耐火温度1200℃!?
先ほどのアメリカ性の耐火コーキングは260℃。
ただ、耐火パテは水にはそんない強くない。
それで、耐火コーキングの防水&耐火の能力に期待する所が大きい訳。
煙突の上の方ならおそらく260℃で十分という気もするし。
これでいよいよ完成やーーー!!!
小さいのは旧の煙突穴
煙突と鉄板の接点の黒いのが耐火コーキング
旧の穴にも鉄板を被せて仕上げる
手前はキッチンストーブの煙突、直径15cmと太い